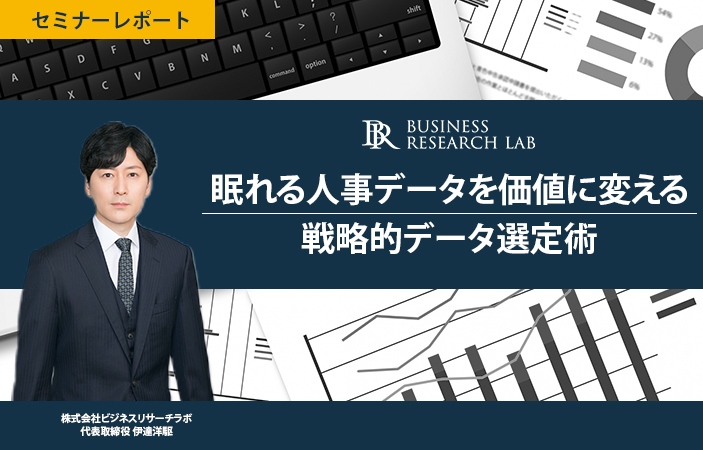2025年7月29日
眠れる人事データを価値に変える:戦略的データ選定術(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年7月にセミナー「眠れる人事データを価値に変える:戦略的データ選定術」を開催しました。
会社の中に眠るデータ。その中から本当に価値のある情報を見極め、人事施策につなげることができていますか。様々な人事データが蓄積されているにもかかわらず、どのデータを分析すべきか、またそれらをどのように意思決定に活かすべきかという課題を抱えている企業もあります。
本セミナーでは、限られたリソースの中で効果を生み出すための「人事データの選び方」に焦点を当てました。データ準備には工数がかかるからこそ、初めに何を分析すべきかを見極めることが成功への近道となります。
講師は、ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆が務めています。伊達は数多くの人事データ分析プロジェクトに携わり、独自の知見を蓄積。人と組織に関する研究背景をもとに、分析手法だけでなく、組織の本質的な課題解決につながるデータ活用法を紹介しました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
近年、多くの企業で人事領域におけるデータ分析の重要性が認識され、実際に取り組むケースも増えてきました。しかし、「分析のためのデータ準備に延々と時間がかかってしまう」「多大な労力をかけて分析したものの、アクションに結びつかない」といった悩みの声が後を絶ちません。過去に私がご相談を受けた案件でも、同様の壁に突き当たっている例が少なくありませんでした。
この問題の根底には、分析に用いるデータを適切に選べていない、という共通の原因が潜んでいます。分析手法に関する情報は数多くあれど、その前段階である「データの選び方」に焦点を当てた解説は少ないのが実情です。そこで本講演では、これまで数多くの人事データ分析プロジェクトを主導してきた経験に基づいて、分析の成否を分けるデータの選定プロセスについてお話しします。
成果指標と影響指標
人事データ分析に着手する上で、土台となるのが「成果指標」と「影響指標」という2つの概念です[1]。これらを最初に設定することが、分析という航海の羅針盤と海図を手に入れることになります。
「成果指標」とは、人や組織の目指すべき状態です。例えば、「従業員の定着率向上」という課題があるなら「離職行動(の少なさ)」が、「イノベーションの活性化」を志向しているなら「革新行動(の多さ)」などが成果指標となり得ます。これは、「どこを目指すのか」というゴールの方向性を示します。
他方で「影響指標」は、その成果指標に対してプラスやマイナスの影響を及ぼす要因を指します。先ほどの「離職行動」という成果指標に対しては、「上司からのフィードバック頻度」「能力開発機会の満足度」「時間外労働時間」といった項目が影響指標の候補として考えられるかもしれません。言ってみれば、影響指標は成果指標というゴールに向けて「どうやってたどり着くか」という道のりや手段を示唆してくれます。
この両者を定めることは、人事データ分析を意味のあるものにする上で重要です。もし成果指標がなければ、分析の目的がぼやけてしまい、どのようなデータを集め、何を明らかにしたいのかが定まりません。結果、多数のデータを前に「結局どうすればいいのか」と途方に暮れてしまいます。
逆に影響指標がなければ、たとえ成果指標が低いと分かっても、その原因を特定できません。「離職率が高い」という事実だけでは、「人間関係が問題なのか、それとも業務負荷が原因なのか」という打ち手につながる洞察は得られません。適切な指標設定を欠いたまま集められたデータに基づく意思決定は、組織を誤った方向に導く危険性があり、施策の効果検証もできないため、貴重な経営資源の浪費につながります。
成果指標の定め方
分析の根幹となる成果指標は、どのように定めれば良いのでしょうか。やみくもに流行りの指標を選ぶのではなく、自社にとって価値のある指標を見つけ出すための手順と、良い成果指標が持つ特徴について紹介します[2]。
成果指標を策定するプロセスは、組織が抱える現状を「問題」「課題」「目標」の3つに分けて整理することから始まります。最初は「最近、若手の活気がない気がする」といった、漠然とした「問題」意識からスタートすることが多いでしょう。ここから「その問題意識は、職場でどのような現象として現れているか」と問いを深めていきます。すると、「期待していた若手社員が、新規プロジェクトへの挑戦を避ける傾向がある」といったエピソードを伴う「課題」として輪郭がはっきりしてきます。
その課題が解決された後の組織の姿をイメージし、言語化します。「若手社員が自律的に学び、積極的に新しい仕事に手を挙げるようになる」といった、個人や組織のあるべき「目標」の姿を検討します。その目標の中から測定可能な要素、例えば「社内公募制度への応募」や「新規スキル習得」などを、成果指標の候補として選定できます。多くの場合、目標は多岐にわたるため、課題の深刻度や達成時のインパクトを考慮し、重要なものを2、3個に絞り込むことが現実的でしょう。
「良い」成果指標には、いくつかの共通点があります。第一に、その指標が向上することが、先ほど特定した組織課題の解決に直結していることです。第二に、会社の理念や経営者が大切にしている価値観と結びついている必要があります。例えば、チームワークを重んじる文化の会社で、個人の成果のみを追いかける指標を掲げても、現場の納得は得られにくいでしょう。
第三に、経営層、現場のマネジャー、人事部といった関係者の間で、その成果指標を追いかけることへの合意が形成されていることが重要です。関係者を巻き込まずに進めると、後から「なぜこの分析が必要なのか」という根本的な問いに直面しかねません。そして第四に、指標の定義が具体的で、誰が聞いても同じ解釈ができるようにシンプルに定められていることです。「エンゲージメント」という言葉一つをとっても、人によって「仕事への熱意」と捉えるか「組織への愛着」と捉えるかで、その後のデータ選定は違うものになってしまいます[3]。
影響指標の定め方
成果指標という目的地が決まったら、次はその目的地に至るまでのルート、すなわち影響指標の候補を幅広く洗い出していきます。精度の高い仮説を立てるためには、多様な知識ソースを活用することが必要です[4]。
一つ目は「学術知」の活用です。学術研究によって蓄積されてきた知見をヒントにするアプローチです。自社で設定した成果指標と類似する学術的な概念を探します。例えば成果指標が「働きがい」であれば、「ワーク・エンゲイジメント」や「職務満足」といった概念が参考になるでしょう。
そして、それらの概念を促進したり阻害したりする「先行要因」を調べます。職務満足の先行要因として知られる「フィードバックの質」[5]や「役割の明確さ」[6]は、自社の働きがい向上における影響指標の有力な候補となり得ます。先行要因を効率的に探すには、多くの研究を統合したメタ分析などを参照するのが近道ですが、時には個別研究のユニークな視点が新たな発見につながることもあります。
二つ目は、現場の経験則である「実践知」からのアプローチです。例えば、皆さんの職場にいる「際立って働きがいを持って仕事をしている人」と「そうでない人」を思い浮かべ、両者の行動や環境の違いを比較してみます。「仕事の裁量権が大きい」「周囲への感謝をよく口にする」といった違いが見つかれば、それが影響指標のヒントになります。また、自分が経験した「最高の職場」と「最低の職場」を比較し、コミュニケーションの質や量、物理的な環境の違いを吟味するのも有効です。さらに、同僚や上司へのヒアリング、他社の優良事例、ビジネス書などから着想を得ることもできます。
三つ目は、社内に眠る「調査知」の活用です。過去に実施した組織サーベイの報告書は、知見の宝庫です。過去の調査で、今回設定した成果指標と似た指標を扱っていなかったかを確認します。もし類似の調査があれば、そこで「成果指標と強い関連が見られた要因」は、今回の分析でも精度の高い影響指標の候補となるでしょう。
ただし、組織の状況は変化するため、過去の結果を鵜呑みにするのは危険です。むしろ、当時は関連が見られなかった要因や、分析の結果、最終的に報告書から削られた要因の中にも、現在の状況では重要な意味を持つものがあるかもしれません。分析前の候補リストまで遡って探索することが、新たな視点をもたらします。
こうして挙げた影響指標の候補について、最後にその「質」を確認します。特定の種類の要因に偏っていないか、具体的な改善策をイメージできるか、そして、なぜそれが成果指標に結びつくのかというメカニズムを自分の言葉で説明できるか、といった観点で見直し、優先順位をつけていきます。
モデルで捉える
影響指標の候補を洗い出したら、次にそれらの関係性を構造的に捉える「モデル化」のステップに進みます。各影響指標が単独で成果指標に作用するだけでなく、指標同士が相互に影響し合っていると考えます。この関係性を、変数間を矢印で結んだパス図のような形で可視化することが有効です。
指標間の関係性を構想する際、主に3つのパターンを想定することができます[7]。最もシンプルなのは、ある影響指標が直接的に成果指標を高める、あるいは低めるという「直接的な関係」です。例えば、「上司からの支援が手厚いほど、従業員エンゲージメントが高まる」という仮説がこれにあたります。
次に、ある影響指標が別の影響指標を介して、間接的に成果に影響を及ぼす「間接的な関係(媒介関係)」があります[8]。間の指標は「媒介変数」と呼ばれます。例えば、「上司からの支援」がまず「心理的安全性」を高め、その結果として「従業員エンゲージメント」が向上するという場合です。ここでは心理的安全性が媒介変数となり、「なぜ上司の支援がエンゲージメントにつながるのか」というメカニズムを説明してくれます。
ある影響指標と成果指標との関係性が、別の条件によって強まったり弱まったりする「条件的な関係(調整関係)」も考えられます[9]。この条件となる指標は「調整変数」と呼ばれます。例えば、「1on1ミーティングの頻度」と「従業員エンゲージメント」の関係を考えてみましょう。このプラスの関係は、「上司の傾聴力」が高いという条件下で、より一層強まるのではないか、という仮説が立てられます。この場合、上司の傾聴力が調整変数として機能します。
これらの関係性をモデルとして事前に構想することで、単に「何が効くか」という要因のリストアップに留まらず、「何が、どのような仕組みで作用し、どのような条件下で効果を最大化できるのか」という、より深く具体的な仮説を持つことができます。
データを選ぶ前に、こうした精度の高い関係性モデルを描くには、まず学術知や実践知に基づき「組織の中では、きっとこうなっているはずだ」という仮説のストーリーを立てることが出発点となります。いきなり複雑なモデルを描くのではなく、重要だと思われる変数間の関係性から始め、そこに「なぜそうなるのか?(媒介)」や「その効果は誰でも同じか?(調整)」と自問自答を繰り返すことで、徐々にモデルを肉付けしていくのが良いでしょう。そして、描き出したモデルが現場の感覚とズレていないか、具体的なエピソードと照らし合わせながら議論することが、モデルの納得度を高めます。
データを探す
成果指標と影響指標、そしてそれらの関係性モデルという「分析の設計図」が完成したら、次はいよいよ、その設計図を検証するための「材料」、すなわちデータを探すフェーズに入ります。
最初のステップとして、定義した全ての成果指標と影響指標をリストアップし、それぞれの指標を測定できそうなデータ項目を洗い出す対応表を作成します。この作業が、データ探索の地図となります。例えば、「上司からの支援」という影響指標に対しては、「1on1の実施頻度」「目標設定面談の記録」「サーベイにおける上司支援のスコア」などがデータ項目の候補として考えられます。
次に、この対応表を片手に、社内に存在するデータを網羅的に探索していきます。まず当たってみるべきは、人事システムに格納されている従業員の情報です。これらは他のデータと掛け合わせて分析する際の軸となります。次に、勤怠管理システムに記録されているデータも使えるかもしれません。
過去に実施した組織サーベイの回答は、従業員の意識や認識を捉える上で欠かせません。採用管理システムには候補者の経歴や面接評価が、学習管理システムには研修の受講履歴やeラーニングの修了状況が蓄積されているはずです。さらに、目標管理制度(MBO)の評価結果やコンピテンシー評価のデータも、個人のパフォーマンスや能力に関する情報源となります。
一方で、探索を進める中で、「心理的安全性」や「キャリア自律意識」といった、既存のデータでは測定が難しい指標も出てくるでしょう。これらの多くは従業員の心理的な状態に関するものであるため、新たに組織サーベイを設計・実施して測定する必要があります。
データ項目を効率的に洗い出すには、いくつかのコツがあります。一つは、指標の定義に立ち返り、「この指標が高い状態とは、誰が何をしている状態か」を考えることです。そうすることで、その行動を記録しているデータが何かを想像しやすくなります。
また、社員が入社してから退職するまでの一連の業務プロセスを思い浮かべ、各段階でどのようなデータが発生しているかをリストアップするのも有効な方法です。そして効果的なのは、各システムの管理担当者に直接「どのようなデータが取得可能か」をヒアリングすることです。思わぬデータが見つかることも少なくありません。
データの品質
社内に存在するデータを発見し、集めることができても、それらがすぐに分析に使えるわけではありません。データ分析の世界には「Garbage In, Garbage Out」、つまり「ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない」という有名な言葉があります。質の低いデータを使って分析しても、得られる示唆は無価値であるか、あるいは誤った結論を導き出す危険性があります。そのため、集めたデータの「品質」をチェックする工程が求められます。
確認すべきは、データの基本構造が分析に適した形になっているかという点です。統計分析を行う上での原則は、「1行が1人の従業員や1回の面談といった観測対象」を表し、「1列が年齢や評価スコアといった1つの変数」を表す、「整然データ」と呼ばれる形式です[10]。
しかし、実務で、この原則から外れたデータを目にします。例えば、Excelの一つのセルに「営業部・主任」のように複数の情報が結合されているケースです。これでは、部署別や役職別の集計が困難になります。分析に向けては、「部署」と「役職」をそれぞれ別の列に分けた方が、多くの分析ツールで扱いやすくなります。
次に、データの欠損値、つまり「空欄」の存在を確認します。なぜそのデータが欠けているのか(入力漏れなのか、退職者のように非該当なのか)という背景を探ります。もし特定の部署や役職のデータだけが系統的に欠損している場合、そのデータを除外して分析すると、結果が実態とは異なる偏ったものになってしまいます。
最後に、データ型と表記の統一性をチェックします。数値であるべき給与が「文字列」として入力されていたり、入社日が「2024/04/01」や「令和6年4月1日」など様々な形式で記録されていたりすると、正しく計算や集計ができません。同じ「営業部」を指すのに「営業」や「Sales」といった表記揺れがあると、別の部署としてカウントされてしまい、分析結果の正確性を損ないます。地道な作業ですが、こうしたデータのクリーニングが分析の質を左右します。
代理指標の考え方
データ探索を進める中で、本来測定したい指標、特に「心理的安全性」や「貢献意欲」といった従業員の心理状態を直接測定したデータが存在しない、という壁に突き当たることがあります。このような状況で有力な選択肢となるのが、「代理指標」を用いて代替するという考え方です。
代理指標とは、直接測定していない指標の代わりに、その指標と論理的に強い関連性があると推測される、測定可能なデータを代理として用いるものです。しかし、この代理指標の選定は慎重に行う必要があります。もし、本来の指標との論理的なつながりが希薄な代理指標を用いてしまうと、分析モデル全体の意味が根底から崩れ、全く見当違いの結論を導き出しかねません。このリスクを十分に理解した上で、その有効性と注意点を解説します。
代理指標は、新たにデータを作る時間やコストがない場合に既存のデータから速報的に状況を推定したい時や、過去のデータを分析したいが当時は本来の指標を測定していなかった、といった場合に有益でしょう。
ただし、代理指標を用いる際には、いくつかの注意点があります。重要なのは、本来の指標との論理的な整合性を重視することです。「なぜ、この行動データが、あの心理状態の代理と言えるのか」というメカニズムを説明できなければ、その代理指標を分析モデルに組み込むべきではありません。代理指標はあくまで「本来の指標を反映している『はずだ』」という仮説に過ぎず、指標そのものではないという限界を認識しておく必要があります。
単一の代理指標に依存するのは危険です。例えば、「会社への貢献意欲」の代理指標を「残業時間」だけに設定すると、家庭の事情などで残業はできないものの意欲は非常に高い、という社員の貢献意欲を不当に低く評価してしまいます。複数の異なる角度からの代理指標(例えば、「社内勉強会の開催回数」や「業務改善提案数」など)を組み合わせることで、より多角的に本来の指標を捉えることが可能になります。
代理指標をモニタリングすることは、組織に対して「この行動を重視します」という強力なメッセージを発信することになります。「残業時間」を重視すれば、不健全な長時間労働を助長するリスクも考慮しなければなりません。
具体的にどのように代理指標の候補を挙げればよいのでしょうか。一つの方法は、本来の指標の「原因となる行動」や「もたらされる結果」から探すことです。例えば、「学習意欲」という心理状態の代理指標を、その原因・行動である「研修への参加回数」や「資格取得支援制度の利用数」で代替するアプローチです。あるいは、「従業員エンゲージメント」という心理状態の結果として現れる「リファラル採用での紹介人数」などを代理指標とする考え方もあります。
測りたい指標が「著しく低い」状態を想像し、その際に観察されるであろう行動から探す方法もあり得ます。例えば、「心理的安全性」が低い職場では「会議での発言者が固定化する」「反対意見が出ない」といった状況が想定されるため、「会議における発言部署の多様性」や「チャットツールでの部署を横断したリアクション数」などが代理指標の候補になるかもしれません。
現場でエンゲージメントが高いと評判の社員に「具体的にどんな行動をしているか」をヒアリングし、その特徴的な行動をデータ化できないか検討することも、精度の高い代理指標を見つけるためのアプローチと言えるでしょう。
おわりに
本講演では、人事データ分析における「データの選び方」をテーマに、一連のプロセスを解説してきました。
まず大事なのは、分析という手段に飛びつく前に、「どこを目指すのか」という成果指標を定めることです。続いて、その成果に影響を与える要因の仮説、すなわち影響指標を、学術・実践・調査といった多角的な視点から幅広く洗い出します。そして、それら指標間の関係性をモデルとして構造的に捉え、必要なデータを探索し、その品質を確認する。この一連のステップが、分析に適したデータを見つけることにつながります。
忘れてはならないのは、データ分析はそれ自体が目的ではないということです。分析を通じて得られた示唆に基づき、より効果的な人事施策を実行し、従業員一人ひとりがその能力を発揮できる、より良い組織を作り上げていくことが本当のゴールです。
完璧なデータが全てそろうのを待つ必要はありません。まずは、今日お話ししたステップに沿って、皆さんの組織が抱える身近な課題を一つ取り上げ、「この課題における成果指標は何だろうか」「その影響指標にはどんな仮説が考えられるだろうか」と、チームで議論することから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、データに基づいた人事戦略を実現するための推進力となるはずです。
Q&A
Q:私の所属する部署には、人事データの分析を専門とする担当者がいません。本日ご講演いただいたような分析モデルを、専門知識がない状態で構築するのは難しいと感じています。どこから手をつければ第一歩を踏み出せそうですか。
専門家がいない中でデータ分析を始める際は、最初から完璧なモデルを目指さないことが重要です。シンプルで本質的なステップから始めると良いでしょう。
第一歩として、「成果指標」と「影響指標」を定義することをお勧めします。繰り返しになりますが、「成果指標」とはひとや組織の目指すべき状態、「影響指標」とは成果指標に影響を与えると考えられる要因です。
まずは組織が最も改善したい「成果指標」を一つ定め、次に関連しそうな「影響指標」の仮説を立てます。表計算ソフトで簡便に集計してみても良いと思います。「若手の離職率が高い(成果指標)のは、上司とのコミュニケーション不足(影響指標)が原因かもしれない」という仮説に基づき、クロス集計をすることから始めてみましょう。
Q:社内に存在する人事関連のデータが、複数の異なるシステムに点在している状況です。それぞれのフォーマットも統一されておらず、これらを統合して分析できる状態にするには、膨大な手間と時間がかかってしまいます。どのデータから優先的に手をつけるべきか、優先順位の付け方についてアドバイスをいただきたいです。
データが複数のシステムに散在しているという課題は、多くの企業が直面する問題です。このような状況で最も避けるべきなのは、「まずは全てのデータを完璧に整理・統合しよう」という発想です。このアプローチは膨大な工数と費用がかかる上、プロジェクトが途中で頓挫するリスクを伴います。
ここでも重要になるのが、「成果指標」、つまり分析の目的を明確にすることです。データが散在しているからこそ、目的意識を持って「どのデータが必要か」を取捨選択する必要があります。
全データの統合という考えを一旦脇に置き、「自社にとって成果指標は何か」を定義します。次に関連しそうな「影響指標」の仮説を立てることで、膨大なデータの中から優先的に集めるべきデータが見えてきます。全てのデータを統合せずとも、最小限の組み合わせから分析を始めることで、十分に有益な知見を得ることは可能です。
Q:データ分析を進めるにあたり、成果指標に影響を与えそうな要因、つまり「影響指標」の候補がたくさん挙がりすぎてしまい、どの指標を優先してモデルに組み込むべきか、優先順位付けに苦労しています。
影響指標の候補がたくさん挙がるのは、多角的な視点から仮説を立てられている証拠であり、良いことです。その上で優先順位を判断するには、二つの軸で整理してみましょう。一つ目の軸は「関連性の確信度」、二つ目の軸は「対策可能性」です。
「関連性の確信度」とは、「その影響指標が成果指標に関連していると、どれだけ確信を持てるか」という度合いです。もう一つの「対策可能性」とは、「その影響指標に対して具体的なアクションを起こせるか」という度合いを指します。
優先すべきは、この二つの軸で総合的に評価し、「関連性の確信度」と「対策可能性」の双方が高い指標です。これらは分析から有益な結果を得やすく、かつ改善アクションにつながりやすいため、有望な候補と言えます。
Q:多くの企業が陥りがちな典型的な失敗のパターンがあれば、それを反面教師として学びたいと考えています。よくある失敗例について教えていただけますか。
私たちがこれまで見てきた中で、よくある失敗は、「成果指標を定めないまま分析を始めてしまう」というケースです。これは「目的地を決めずに航海に出る」ようなもので、何を達成するのかという目的が曖昧なまま、「とりあえず手元のデータで何か分析してみよう」とプロジェクトが進んでしまいます。
このような「分析のための分析」は、たとえ興味深い結果が出たとしても、それが何の課題の解決につながるのかを説明できません。経営層からも「それで?」と問われ、プロジェクトは立ち消えとなってしまいます。
データ分析は、それ自体が目的ではなく、あくまで人や組織をより良い状態へ導くための「手段」です。分析に着手する前に、「自分たちはデータを使って何を成し遂げたいのか」を議論し、その目的を関係者間で共有すること。これが、失敗を避けるための鍵となります。
脚注
[1] 成果指標と影響指標の詳細は当社コラムが参考になります。
[2] 成果指標の定め方について詳しく知りたい人は当社コラムをご一読ください。
[3] 前者はワーク・エンゲイジメント、後者は組織コミットメントと呼ばれ、実は別の概念です。
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., and Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701–716.
Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18.
[4] 影響指標の候補を挙げる際の方法についてより詳しくは当社コラムを参考にしてください。
[5] Anseel, F., and Lievens, F. (2007). The long-term impact of the feedback environment on job satisfaction: A field study in a Belgian context. Applied Psychology, 56(2), 254-266.
[6] Fisher, C. D., and Gitelson, R. (1983). A meta-analysis of the correlates of role conflict and ambiguity. Journal of Applied Psychology, 68(2), 320–333.
[7] Baron, R. M., and Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.
[8] 媒介効果については当社コラムの内容も参考になります。
[9] 調整効果については当社コラムも読んでいただければと思います。
[10] Wickham, H. (2014). Tidy data. Journal of Statistical Software, 59(10), 1–23.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。