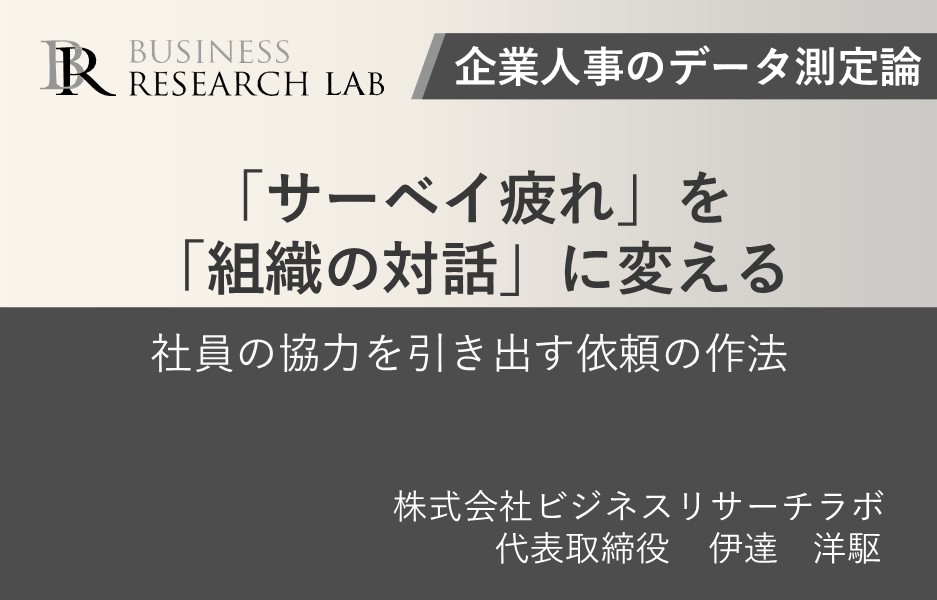2025年10月20日
「サーベイ疲れ」を「組織の対話」に変える:社員の協力を引き出す依頼の作法
組織サーベイの実施を前に、多くの人事担当者が頭を悩ませる問題、それが社員の「サーベイ疲れ」と、それに伴うマネージャー層からの反発ではないでしょうか。「またこの季節が来たか」「どうせ回答しても何も変わらない」。そんな無力感や諦めが組織に蔓延し、依頼の段階で既に協力的な姿勢を得られないという現実は、サーベイ本来の目的である「組織の健全な発展」を阻む壁となります。
この問題の本質は、調査の頻度が多いことや、設問が長いことだけに起因するものではありません。それは、過去の経験から学習された「期待の喪失」であり、サーベイが「一方的な情報収集」と化してしまったことへの、組織からの抵抗です。
本コラムでは、この根深い「サーベイ疲れ」の正体を多角的に解き明かすと共に、サーベイの設計といった課題だけでなく、依頼の瞬間にこそ凝らすべきコミュニケーションの技術に焦点を当てます。社員やマネージャーの心を動かし、「やらされ仕事」から「自分たちのための対話」へと、サーベイの位置づけを転換させるためのアプローチを考えていきたいと思います。
諦めと不信の堆積としてのサーベイ疲れ
組織に蔓延する「サーベイ疲れ」という現象は、倦怠感や多忙さからくる一時的な感情ではありません。それは、過去から現在に至るまでの組織と従業員のコミュニケーションの歴史がもたらした、「諦め」と「不信」の堆積物です。
社員がサーベイへの協力をためらう理由の一つは、「回答しても何も変わらない」という無力感を、過去の経験から学習してしまっていることにあります。かつて、期待を込めて率直な意見を投じたにもかかわらず、その声が組織の意思決定や職場環境の改善に反映されなかったという経験は、「どうせ無駄だ」という刷り込みとなります。
人事部門が多大な労力をかけてサーベイを実施し、分厚い報告書を作成したとしても、その結果が社員の目に触れる形で共有されず、具体的なアクションにつながらなければ、それは「やりっぱなし」の認識を免れません。社員から見れば、自分の時間と意見が、どこかに吸い込まれて消えていくだけのブラックボックスです。このような状況が生まれれば、次回のサーベイ依頼がいかに丁寧な言葉で綴られていようとも、その協力依頼は空虚に響いてしまいます。
サーベイの目的が不明確であることも、社員の意欲を削ぐ要因となります。なぜ今、この調査が必要なのか。その結果は何を明らかにし、会社のどのような未来につながるのか。この問いに対する納得感のある説明がなければ、社員にとってサーベイは「理由のわからない、ただの作業」になります。目的意識を共有されないまま、ただ回答を求められる行為は、社員の主体性を尊重しない、一方的な指示に他なりません。
物理的な負担も見過ごせません。業務がひっ迫する中で、高い頻度で、あるいは多くの時間を要するサーベイへの回答を求められれば、純粋な業務負荷としてのしかかります。とりわけ、前回と代わり映えのしない設問が繰り返されるタイプの調査は、回答の質を低下させるだけでなく、サーベイという取り組みそのものへの関心を低下させます。
そして、匿名性への懸念という心理的な障壁が存在します。組織や上司に対して批判的な意見を持つ場合、「正直に回答すれば、誰が書いたか特定され、不利益を被るのではないか」という不安は、決して杞憂とは言えません。この不安が払拭されないと、得られる回答は当たり障りのない建前に終始し、組織の課題を浮き彫りにすることは困難になります。
これらの要因が複雑に絡み合い、サーベイは「組織との対話の機会」ではなく、「信頼関係を試す踏み絵」のような存在へと変質してしまうのです[1]。
現場の最前線から見える景色
社員全体のサーベイ疲れとは別に、多くの人事担当者が直面するのが、マネージャー層からの抵抗です。マネージャーはサーベイの成否を左右するキーパーソンでありながら、時にその推進を阻む壁ともなり得ます。この抵抗の背景には、マネージャー特有の立場と、日々直面する現場のプレッシャーが存在します。
サーベイの結果、特に自チームのスコアが、自身のマネジメント能力を評価する成績表のように扱われることへの警戒心があります。スコアが低ければ、その原因を問われ、具体的な支援策もないまま改善を求められるのではないか。こうした不安は、サーベイを「自身の能力開発を支援するツール」ではなく、「管理・評価のためのツール」と認識させ、防衛的な姿勢を取らせるのに十分な理由となります。
マネージャー自身がサーベイの企画・設計プロセスから疎外されていることも、抵抗感を生む要因です。多くの場合、サーベイは経営層や人事部門が主導で決定し、その実施が現場に下ろされます。マネージャーは、その目的や背景について十分な説明を受ける機会もなく、「部下に回答させる」という実行役を担わされます。
これでは「会社が決めたことだから」という意識しか生まれず、「自分たちのチームをより良くするための取り組み」という当事者意識は醸成されにくいでしょう。「やらされ感」を抱えたままでは、部下に対して心からの協力を呼びかけることなどできません。
また、サーベイ実施後のプロセスが、マネージャーにとって業務負担となる現実も見逃せません。結果のフィードバックを受け、それを読み解き、チームで対話の場を持ち、改善アクションを策定し、その進捗を管理する。これら一連の活動は、本来重要であるにもかかわらず、日常業務に追われるマネージャーにとっては、通常業務に上乗せされる重いタスクとなります。特に、人事からの十分なサポート体制がなければ、その負担感はさらに増大し、「できれば関わりたくない」というのが本音になることも少なくありません。
そして、マネージャー自身も一人の社員として、過去の「やりっぱなしサーベイ」を経験しています。自らが部下に協力を要請するサーベイが、結局は組織の具体的な変革につながらないのではないかという不信感。こうした懐疑的な視点を持つマネージャーが、積極的にサーベイの推進役となることを期待するのは酷な話です。マネージャーの抵抗は、現場の最前線で組織の矛盾や課題を肌で感じているからこその、現実的な反応です。
依頼の前に信頼を醸成する
サーベイへの協力を得るための技術を語る前に確立すべきは、その土台となる組織と社員の信頼関係です。小手先の依頼テクニックは、この土台が脆弱であれば何の効果ももたらしません。信頼の醸成とは、サーベイを「一回限りのイベント」として捉えるのではなく、「組織と社員の継続的な対話のプロセス」として位置づけることに他なりません。
その対話の主役は、人事部門だけではありません。経営トップが自らの言葉で、サーベイの重要性と組織変革への強い意志を表明することが求められます。「社員の声に真摯に耳を傾け、より良い会社を皆で創り上げていきたい」というメッセージが、経営層から一貫して発信されることで、組織サーベイはただの人事施策ではなく、全社的な重要事項としての意味を持ちます。このトップの姿勢が、社員の「どうせ変わらない」という諦めに風穴を開ける最初の力となります。
続いて重要なのが、組織と社員の間で「信頼に基づく約束」を交わすという意識です。これは、サーベイを依頼する際に、組織が社員に対して約束をすることを意味します。その約束とは、例えば、「いただいた声は真摯に受け止め、結果の概要はフィードバックします。そして、明らかになった課題に対しては、何らかのアクションを起こします」というものです。
この約束を事前に、公に宣言することで、サーベイは「投げっぱなしの意見募集」ではなく、「返事のある対話」へと変わります。もちろん、この約束は必ず守られなければなりません。一度でも反故にされれば、失われた信頼を取り戻すのは困難になります。
過去のサーベイ結果がどのような改善につながったのかを、次のサーベイを依頼する前に報告することも、この「信頼に基づく約束」をより強固なものにする上で効果的です。「前回の声が、今回の変化になった」という実績が、信頼を醸成する証拠となります。
このような地道な信頼醸成を通じて、サーベイは社員にとって「監視されるもの」から「参加するもの」へと、その意味合いを変えていきます。
サーベイ依頼の作法
信頼の土台を築いた上で、いよいよサーベイの依頼というコミュニケーションの段階に入ります。特に、大企業においては、その「伝え方」に細心の注意を払う必要があります。ここでは、依頼の持つ意味を最大化する三つの作法を提案します。
第一の作法は、依頼の意義を高め、公式な重要事としての認識を醸成することです。人事部からの一斉配信メールという形式では、他の多くの業務連絡の中に埋もれてしまうかもしれません。これを避けるため、依頼のメッセージは、経営者や担当役員、あるいは事業部長といった、組織のトップが自らの「実名」で発信します。リーダー自身の言葉で、サーベイの戦略的な重要性や、社員の声に対する期待が語られることで、依頼は事務連絡ではなく、経営からのメッセージとしての重みを持ちます。
さらに、全社朝礼や部門の定例会議といった公式な場で、リーダーが直接、その目的を説明し協力を呼びかけることも有効です。これによって、サーベイは「業務時間外の任意協力」ではなく、「全社で取り組むべき公式な業務の一環」として位置づけられます。
第二の作法は、多忙な業務への「配慮」を示し、心理的負担を軽減することです。「忙しいのに、また仕事を増やすのか」という社員のネガティブな感情を先回りして和らげる工夫が求められます。依頼文には、「想定所要時間は約〇分です」と時間を明記します。これによって、回答者は漠然とした時間の拘束への不安から解放され、「その程度の時間なら協力しよう」という気持ちになりやすいものです。
回答期間を十分に確保し、繁忙期を避けるといった基本的な配慮に加え、リマインドの仕方も重要です。締め切り間際に追い立てるように催促するのではなく、期間の始め、中盤、終盤と、計画的かつ丁寧な言葉で複数回にわたり通知します。
そして、自席のPCからだけでなく、スマートフォンからも手軽に回答できるようなマルチデバイス対応も有効です。こうした一つひとつの配慮が、会社が社員の時間を尊重しているという姿勢の表明となり、信頼関係を深めることにつながります。
第三の作法は、現場のキーパーソンであるマネージャーを「やらされ役」から「推進役」へと変えることです。そのためには、マネージャーを味方につけるための仕掛けが求められます。例えば、全社への依頼に先立ち、マネージャーだけを対象とした事前説明会を実施します。その場で、サーベイの目的や背景、そして何よりも「この結果はマネージャーの皆さんを支援するためのツールであり、決して評価や詰問のために使うものではない」というメッセージを伝えます。
マネージャーが自身のチームメンバーへ協力を依頼する際に使えるメールのテンプレートや、チームミーティングで説明するための簡易な資料を提供することも有効です。これによって、マネージャーは迷いや負担を感じることなく、自信を持って部下にサーベイの重要性を語ることができます。
そして重要なのは、結果が出た後の手厚いサポート体制を事前に約束することです。例えば、「結果のフィードバック後には、人事部が各チームを巡回し、結果の読み解きやアクションプラン策定のワークショップを一緒に実施します」と伝えることで、マネージャーは「結果を渡されて終わり」という孤独な状況に陥る不安から解放され、前向きな気持ちでサーベイに臨むことができるようになります[2]。
脚注
[1] このような「サーベイに回答する従業員が、回答に際してどういったことを感じ、それによって回答がどう歪むのか」について、当社が調査・検証したレポートがあります。
組織サーベイ実態調査 結果報告会:従業員意識調査をもっと有効なものにするには(セミナーレポート)
組織サーベイで良質なデータを集める方法:組織サーベイ実態調査からの示唆
[2] ここで挙げた依頼の作法に加えて、サーベイ成功に向けた実施前の事前準備に関しては、下記の当社セミナーレポートにて解説しています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。