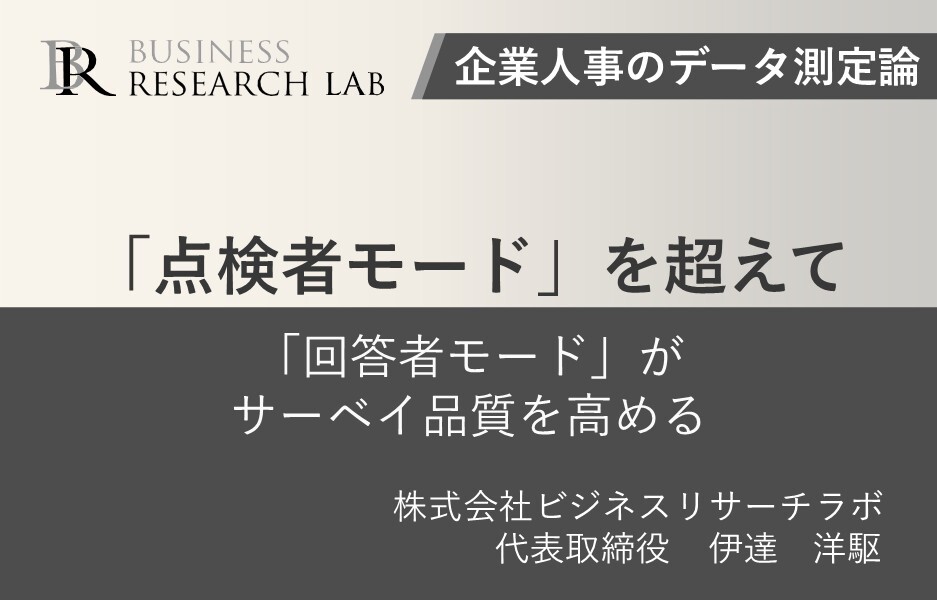2025年12月22日
「点検者モード」を超えて:「回答者モード」がサーベイ品質を高める
組織サーベイや適性検査の項目を開発する際、心理測定や尺度開発の専門家は、サービス提供先であるクライアント企業の担当者に、作成した項目案を確認してもらうプロセスを設けることが一般的です。その際、クライアント担当者からは「調査の質を可能な限り高めたい」という純粋な善意に基づき、非常に熱心なフィードバックが寄せられることがあります。
しかし、このプロセスには構造的なジレンマが潜んでいます。この「確認」という行為が、人の思考モードを、無意識のうちに切り替えてしまうのです。人間の思考には、迅速で直感的な働き(システム1)と、遅く分析的な働き(システム2)が存在すると言われています。サーベイに実際に回答する従業員は、多くの場合、前者、すなわち「回答者モード」で項目に接します。日々の経験や感情を瞬時に統合し、深く考え込むことなく直感的に回答を選択します。
ところが、「項目を『確認』してください」と依頼された瞬間、担当者の思考は後者、すなわち「点検者モード」へと移行しやすくなります。もはや「一人の回答者」としてではなく、「評価者」「批評家」として項目を客観的な分析対象と見なし、言葉の厳密な定義(例えば「『やりがい』の定義が曖昧だ」)や、極端な例外ケース(「終始一人で業務を完結させる社員はこの項目にどう答えるのか」)に固執してしまうことがあります。
専門家がこの「点検者モード」の指摘を無批判に受け入れると、項目は次第に長く、説明的で、不自然な表現になっていきます。その結果、本来測定したかった「従業員の素朴で実感的な意識」から焦点がずれ、サーベイの測定品質が低下するリスクがあります。
この善意の指摘に対応する専門家は、二重の困難に直面します。第一に、なぜその指摘(例えば、定義の厳密化)が、あえて「実感」を捉えようとする専門的な設計意図に反し、品質を損なうのかを、専門用語を使わずに平易に説明する「専門知識の翻訳」という知的コストです。第二に、クライアントの貴重な時間と善意の結晶である提案を、実質的に「否定」しなければならないという「善意の否定」という心理的負荷です。
問題は、クライアントのフィードバックの「有無」にあるのではありません。その「モード」にあります。本コラムの目的は、「点検者モード」の問題を乗り越え、なぜクライアント(非専門家)の「回答者モード」でのチェックが、専門家の論理だけでは到達できないサーベイ品質を実現するために有効なのか、その積極的な価値と具体的な実践方法を解説することにあります。
「回答者モード」の価値とは何か
「点検者モード」が引き起こす問題は、先に述べた通りです。ここからは、非専門家による「回答者モード」でのチェックが持つ積極的な価値を、二つの側面に分けて詳述します。専門家の論理だけでは担保できない品質領域が、この「回答者モード」によって支えられています。
専門家の論理と現場の実感のズレを埋める
専門家が作成するサーベイ項目は、学術的な知見や心理測定論に基づき、「測定したい概念を正しく測れる」よう設計されています。しかし、その表現はあくまで「一般的・学術的」なものであるため、特定のクライアント企業固有の「現場感覚」や「生きた言葉遣い」と乖離してしまうリスクを伴っています。
サーベイの品質を担保するために、回答者が項目を読んだ瞬間に「これは自分たちのことを問うている」と直感的に受容できるか、という点が大事です。この当事者性が感じられなければ、回答者は「他人事」としてサーベイに臨み、回答の質は低下してしまいます。
ここで、「点検者モード」の指摘と「回答者モード」の違和感を比較してみましょう。例えば、「この会社で働くことに誇りを持っている」という項目に対し、「点検者モード」は「『誇り』の定義が曖昧だ。『愛着』なのか『満足』なのか定義すべきだ」と論理的な厳密性を追求します。これは、あえて「誇り」という日常的な言葉で「素朴な実感」を丸ごと捉えようとする専門家の設計意図と衝突してしまいます。
一方、「回答者モード」でこの項目を読んだクライアントからは、「『誇り』という言葉は、うちの会社では大げさすぎて誰も使わない。ピンとこない」というフィードバックが得られるかもしれません。
後者の「ピンとこない」という直感は、専門家の論理だけでは見落としていた「現場の実感」とのズレを教えてくれます。この直感的な違和感の報告が、多くの従業員に「自分たちのためのサーベイだ」と受け入れられる表現を見つけるための手がかりとなります。
他にも、「エンゲージメント」という言葉が、専門家の間では一般的でも、その企業では浸透しておらず「他人事」のように聞こえてしまうかもしれません。「上司」という言葉が、日常的に「さん付け」文化が根付いている企業では、冷たく、心理的な距離を感じさせる表現として受け取られるかもしれません。現場で「連携」という言葉が主流なのに、項目で「協働」という言葉が使われると、回答者は一瞬思考を停止させてしまいます。
これらのズレは、点検者モードの土俵では発見しにくいものです。「回答者モード」でその企業の文化や言葉遣いを内面化した非専門家が感じる、直感的な「違和感」や「馴染みのなさ」が、サーベイの品質を高めるための情報源なのです[1]。
論理的な欠陥ではなく、感情的な障壁を検知する
サーベイの回答は、論理的な判断だけで行われるのではありません。回答者が一瞬感じる「こんなことを答えたらどう思われるか」「この質問は不快だ」といった感情的な反応が、回答意欲を減退させ、回答の歪みを生む原因となります。
「点検者モード」は、前述の通り「論理的な欠陥」や「例外ケース」の探索には優れていますが、回答者が一瞬感じる「心理的な抵抗」や「感情的な障壁」は見落としてしまいがちです。論理的に回答可能であっても、感情的に回答したくない項目は、サーベイの品質にとって脅威となります。
クライアント(非専門家)が「一従業員」としてシミュレーションする「回答者モード」は、この「感情的な障壁」を検知する上で有用な役割を果たします。
例えば、上司の評価に関する項目群を読んだとき、「論理的には回答できるが、正直に答えたら誰が回答したか特定されそうで怖いと感じるかもしれない」という直感です。「怖い」という感情が優先されれば、回答は当たり障りのないものに歪んでしまいます。
あるいは、「『挑戦』という言葉は、自社の過去の失敗プロジェクトを想起させ、ネガティブな気分になる」といった連想です。専門家がポジティブな文脈で意図した言葉が、その企業の文脈ではネガティブな感情を引き起こし、回答をためらわせるかもしれません。
また、「プライベートに関するこの質問は、会社にどこまで踏み込まれるのかと不快感を覚える」といったプライバシーへの懸念も同様です。専門家が論理的に必要だと判断した項目でも、従業員が「不快だ」と感じれば、その後の項目への回答態度にも悪影響を及ぼしかねません。
これらはすべて、論理の問題ではなく、実感の問題です。「点検者モード」で「論理的に正しいか」を検証していては、これらの障壁は発見できません。クライアントが「回答者モード」で感じる直感的な「答えにくさ」の検知は、サーベイの心理的安全性を担保し、従業員の真摯な回答態度を引き出す上で有用な情報であり、結果として測定の正確性を守ります。
批評家から共創パートナーへ
「回答者モード」の価値を理解した上で、具体的にどう行動すればよいか。良いサーベイは、専門家の「測定の知見」と、クライアントの「現場の知見」が融合した共作から生まれます。そのための技術を、専門家側(依頼側)・クライアント側(点検側)双方の立場から解説します。
専門家(依頼側)の教示の技術
この問題の多くは、専門家側の依頼の仕方に起因しています。「教示」は、クライアントの思考モードを決定づける重要なステップです。
なぜなら、「項目を『点検』してください」「『確認』をお願いします」「『レビュー』してください」といった依頼の言葉自体が、相手の点検者モードを起動させてしまうからです。「点検」や「レビュー」という言葉は、「間違いを探す」「論理的な穴を塞ぐ」という任務を相手に与えてしまいます。
したがって、専門家は依頼の言葉を意図的に設計し直す必要があります。例えば、不適切な依頼は、「項目を『点検』してください」「『間違い』や『論理的な穴』がないか見てください」といったものであるのに対して、適切な依頼は、例えば「皆さんには『批評家』ではなく、このサーベイを受ける『最初の回答者』として『体験』していただきたく思います」といった形になるでしょう。
より具体的には、「専門家が気づかない『現場の違和感』を教えてほしいです。論理的な正しさや例外ケースは専門家側でフォロー・担保していますので、ご心配いただかなくて大丈夫です。皆さんには、一従業員として10分で一気に回答するとして、『直感的に』意味が分かり、円滑に答えられるかという視点でご確認ください」と伝えます。
「良いフィードバック」の具体例を事前に示すことも有効です。例えば、「この項目を読んだとき、一瞬どういう意味か『迷いました』」「この言葉は、うちの会社では『ピンときません』」「この質問は、なんだか『答えにくい』と感じました」といった、「直感」や「感情」の報告であることを明示します。
これらの「教示」によって、クライアントを「批評家」の役割から解放し、「一人の回答者」の立場に戻すことが期待できます。
クライアント(点検側)のモード転換の技術
専門家から上記のような適切な「教示」があるのが理想ですが、そうでない場合でも、クライアント側が自らの思考モードを意識的に転換することが、プロジェクトの品質向上に貢献します。
必要なのは、自らの役割の再認識です。サーベイ項目を確認する際の役割は「論理的な穴を塞ぐ批評家」ではありません。専門家が持ち得ない「現場の直感」を報告する「シミュレーター」が価値ある役割であると認識することがスタートラインです。
項目を読んでいて、「論理的におかしい」「定義が曖昧だ」という思考が作動した瞬間に、一歩立ち止まることも有効です。そして、「これは本当に『論理的な欠陥』か。それとも、一回答者として『直感的に分かりにくい』だけか」と自問します。
後者(直感的に分かりにくい)であるならば、その「分かりにくさ」という「体験」そのものを報告することが、専門家にとって価値のある情報となります。
重要なのは、「結論(Should)」ではなく「体験(Feel)」を伝えることです。例えば、「誇り」という項目に対して、点検者モードのフィードバック(結論)は、「『誇り』の定義を脚注に『〜と定義する』と補足すべきだ」という提言になるかもしれません。他方で、回答者モードなら、「『誇り』という言葉を読んで、一瞬『愛着』のことか『満足』のことか『世間体』のことか迷った」という体験を報告するでしょう。
「〜すべきだ」という提言(点検者)ではなく、「〜と感じた」「〜で迷った」「〜を連想した」という認知プロセス(回答者)を共有するのです。
二重の困難を超え、共創へ
本コラムでは、組織サーベイの項目開発における「善意のジレンマ」の構造を検討しました。善意に基づく「点検者モード」のフィードバックが、皮肉にもサーベイの品質を損なうリスクとなり、専門家を「二重の困難」に追い込むことを示しました。
しかし、問題は「善意」にあるのではなく、その発揮される「モード」にあります。本コラムの核心として、非専門家であるクライアントの「回答者モード」でのチェックが、専門家の「論理」だけでは到達できない「現場の実感」とのズレ(価値1)、回答を歪ませる「感情的な障壁」(価値2)を発見させ、品質を高める鍵であることを論じました。
「回答者モード」を基盤としたプロセスは、専門家を「二重の困難」から解放します。クライアントからのフィードバックが「〜すべきだ(意見)」ではなく、「〜と感じた(体験)」の報告であるならば、専門家はそれを「否定」する必要がなくなります。感謝と共に「貴重な情報をありがとうございます」と、その「事実」をそのまま受容できるからです。「善意の否定」という心理的負荷は、ここで見事に解消されます。
そして、専門家は「なぜあなたの論理的な指摘が妥当性を損なうのか」を説明する防衛的な「翻訳コスト」から解放されます。そのリソースを、「直感的な違和感を解消するために、専門家として最適な表現は何か」を考える「共創」の作業に集中できるのです[2]。
この健全な関係性を築くために、双方の努力が求められます。専門家は、クライアントを「批評家」にせず「最初の回答者」として導く教示の技術と、その直感を傾聴する姿勢を磨き続ける必要があります。
クライアントは、自らのプロジェクトへの貢献意欲を、「論理的な批評」ではなく、「直感的な体験」の報告という形で発揮することが、専門家に対する貢献であると認識することが求められます。「最初の回答者」として、その貴重な「直感」を専門家にぶつけること。それが、専門家の論理を補完し、サーベイの品質を高めるための方法です。
脚注
[1] もちろん、「現場の実感」を過度に優先し、専門家が意図した測定概念そのものを歪めてしまっては本末転倒です。例えば、「エンゲージメント」という言葉が浸透していないからといって、その概念を安易に「やる気」や「満足」といった似て非なる現場の言葉に置き換えてしまうと、本来測定すべき概念の重要な側面が欠落し、測定品質はかえって低下してしまいます。「回答者モード」の直感はあくまで情報源であり、専門家はそれを受け止めた上で、「現場の実感」と「測定の論理」を両立させる着地点を探るという舵取りが求められます。
[2] ただし、共創は決して容易な作業ではありません。「〜と感じた」という「体験」の報告は、あくまで問題発見のスタートラインです。専門家は次に、なぜクライアントがそのように「感じた」のか(言葉の定義か、文化的背景か、質問の順序か等)を解釈し、その「直感的な違和感」を解消しつつ、専門的な測定意図も担保できる「代替表現」を考案・提案しなければなりません。例えば「『誇り』はピンとこない」というフィードバックに対し、専門家は「では『この会社で働くことを誇らしく思う』ではどうか?」「『この会社の一員であることを嬉しく思う』の方が実感に近いか?」といった複数の選択肢を、測定の意図を説明しながら提示し、再びクライアントの「回答者モード」で検証してもらう、といった双方向のキャッチボールが必要となります。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。