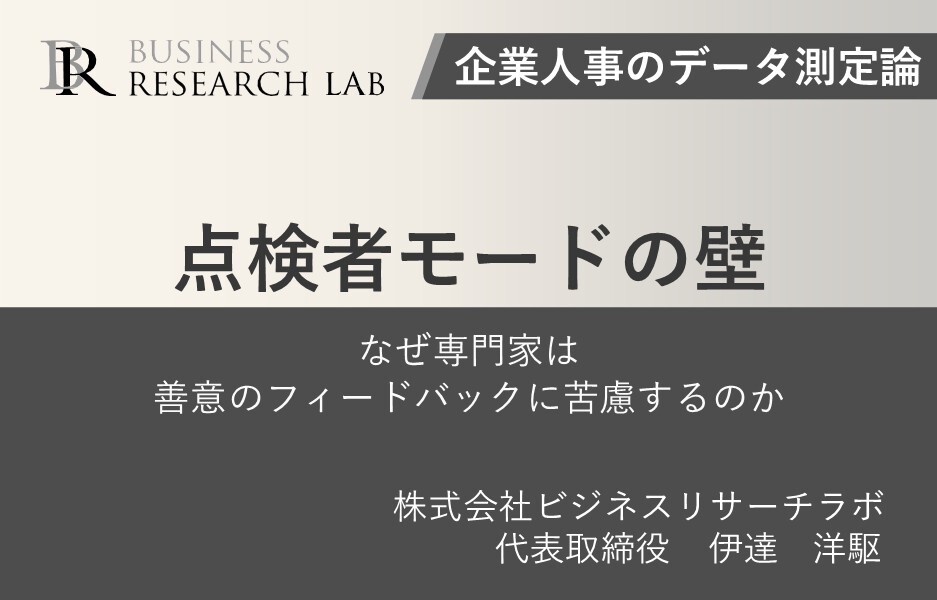2025年12月19日
点検者モードの壁:なぜ専門家は善意のフィードバックに苦慮するのか
専門家が尺度開発、例えば組織サーベイの項目作成を支援する際、開発の途中でサービスを受ける企業側に項目案を確認してもらうプロセスがあります。その際、非常に熱心にフィードバックが寄せられることがあります。「この言葉の定義が曖昧ではないか。もっと具体的な行動に落とし込むべきだ」「この項目だと、主に一人で業務を完結させる社員はどう回答すればよいのか。例外ケースが考慮されていない」といった指摘です。
これらの指摘は、調査の質を可能な限り高めたいという、企業担当者の真摯な「善意」の表れです。プロジェクトへの当事者意識と貢献意欲の高さを示すものであり、専門家にとって、ありがたいことはないでしょう。専門家は、その姿勢と貴重な時間を割いてもらったことに感謝を抱きます。
しかし、その感謝と同時に、専門家は内心で強いジレンマを抱えています。なぜなら、善意に基づいて寄せられたフィードバックが、意図せずサーベイの品質、すなわち「測定したい概念を正しく測る」という妥当性を損なってしまう可能性を伴っているからです。さらに、そのフィードバックに対応する専門家側の作業的な負荷、特に心理的な負荷が高いという側面もあります。
なぜ、調査を良くしたいという純粋な「善意」に基づくはずのフィードバックへの対応が、専門家にとって「大変」な作業となってしまうのでしょうか。それは「点検者モード」と呼ばれる状態に起因する、ある厄介な構造が関係しています。本コラムでは、この問題の背景にある人間の思考様式を解き明かしながら、専門家が直面する「二重の困難」と、そのジレンマの構造について解説します。
「回答者モード」と「点検者モード」とは
同じ人間が、同じサーベイの項目を見たとしても、その人が置かれた状況や役割によって、項目への評価や反応が異なることがあります。この現象を理解するためには、人間の思考に備わっている二つの異なる働きについて知る必要があります。一つは迅速で直感的な思考、もう一つは遅く分析的な思考です。サーベイ項目との向き合い方に応じて、この二つのモードを「回答者モード」と「点検者モード」と呼んで区別してみましょう。
初めに「回答者モード」について説明します。これは、従業員がサーベイに回答する際の、ごく自然な心理状態です。例えば、「現在の仕事にやりがいを感じている」という項目に対し、多くの人は日々の業務経験やそこで得た感情を瞬時に、かつ無意識的に統合し、深く考え込むことなく「そう思う」「どちらかといえばそう思う」といった選択肢を選びます。
このとき、思考は「直感的」かつ「迅速」に機能しています。「やりがい」という言葉の厳密な定義を自問したり、辞書的な意味を調べたりすることは、まずありません。自身の経験に照らして「おそらくこういう意味だろう」と全体的な文脈から判断し、回答を完了させます。これは、非常に効率的な情報処理の仕組みであり、私たちが日常生活を送る上で不可欠な能力です。
ところが、「このサーベイ項目を確認してください」と依頼された瞬間、この思考モードが切り替わる可能性があります。分析的で批判的な思考が起動し、「点検者モード」へと移行するのです。このモードでは、先ほどの直感的な情報処理は抑制されます。もはや一人の回答者としてではなく、「評価者」や「批評家」として、項目を客観的な分析対象と見なします。そして、言葉の厳密な定義、論理的な整合性、想定しうる例外的な状況を検証し始めます。
例えば、先ほどは直感的に受け入れていた「やりがい」という言葉が、急に多義的で曖昧なものに感じられ、「成長実感なのか、貢献実感なのか、具体的に定義すべきだ」という指摘が生まれます。これは、調査に貢献したいという誠実な動機から生じる、ごく自然な心理的変化です。
問題は、この二つのモードの間に存在する「ズレ」です。専門家は、多くの従業員が「回答者モード」で円滑に、直感的に回答できる項目を作成したいと考えています。サーベイの回答場面において、従業員は「点検者モード」にはなっていないからです。しかし、そのために協力を仰いだ企業担当者が「点検者モード」でフィードバックを提供すると、二つのモードの間で認識のすれ違いが生じます。
この「点検者モード」に基づくフィードバックには、いくつかのパターンがあります。例えば、「些細な表現への固執」です。「私の上司は私にフィードバックを与える」という項目に対し、「『フィードバック』の定義が曖昧だ」と指摘するかもしれません。しかし、多くの回答者は「フィードバック」という言葉から自身の経験を直感的に評価できます。むしろ定義を厳密にしすぎると、かえって回答が困難になる場合があります[1]。
また、「極端な例外ケースの追求」もその一つです。「私の職場は効果的に協働している」という項目に対し、「主に一人で業務を完結させる職種の社員はどう答えるのか」という指摘が入ることがあります。しかし、サーベイは多くの場合、組織の最大公約数的な状況を測定するために作られます。ごく少数の例外に項目を合わせようとすると、項目は冗長で煩雑になり、大多数の回答者にとって分かりにくいものになってしまいます。
無論、「一人で業務を完結させる社員が大多数である」場合、この指摘はまっとうですが、そのような社員がほんのわずかしかいないならば、そういった例外すべてをケアすべく項目内容を調整するのは別の問題を生むわけです。
専門家が、これらの「点検者モード」のフィードバックを無批判に受け入れ、項目を修正していくと、サーベイの品質はどうなるでしょうか。項目は徐々に長く、説明的で、不自然な表現になっていくかもしれません。それは回答者の認知的な負担を増やし、回答意欲を減退させます。
さらに深刻なのは、本来測定したかった概念、例えば「従業員の素朴で実感的な意識」といったものから、焦点がずれてしまうことです。個々の項目が細部にこだわりすぎるあまり、測定概念の全体像を捉えきれなくなるのです。これは、専門的には「妥当性の低下」と呼ばれる現象であり、サーベイの測定精度を損なうことにつながります。
専門家が直面する「二重の困難」
「点検者モード」でのフィードバックは、サーベイの品質を意図せず低下させてしまうリスクを伴っています。では、専門家は、そのようなフィードバックに対し、「品質が低下する恐れがあるので、その修正は受け入れられません」と単純に伝えれば良いのでしょうか。話はそう簡単ではありません。この「点検者モード」への対応が専門家にとって「大変」な作業となる理由は、ここに対応の難しさが潜んでいるからです。
専門家は、この対応において、性質の異なる二つの困難に同時に直面することになります。これは「二重の困難」と呼べるかもしれません。
第一の困難は、「専門知識の『翻訳』という困難」です。専門家が作成するサーベイ項目は、多くの場合、学術的背景や、長年の知見に基づく専門的な設計意図に基づいています。その設計意図は、非専門家の視点とすべてが重なっているわけではありません。
例えば、「この会社で働くことに誇りを持っている」という項目について考えます。「点検者モード」では、「『誇り』の定義が曖昧だ。『愛着』なのか『満足』なのか、脚注的に言葉を定義したほうが良いのでは」という指摘がなされるかもしれません。しかし、専門家としての設計意図は、あえて「誇り」というごく日常的な言葉で問うことによって、定義によって切り捨てられてしまうような、従業員の主観的で複雑な実感そのものを丸ごと捉えようとすることにあるかもしれません。
「点検者モード」からの指摘は、この「あえてそうしている」という専門的な設計意図に関わってくることが多々あります。「なぜ定義を曖昧にするのか」「なぜ例外を考慮しないのか」「なぜもっと具体的にしないのか」などといった問いに対し、専門家はその背景にある尺度開発の専門的な理論や意図を説明し、納得してもらう必要があります。
これが「困難」である理由は、その説明の相手が、必ずしも尺度開発の専門家ではない企業担当者であるという点です。専門家は、統計学や心理測定論の専門用語を使うことなく、なぜその表現が最適であるのか、なぜその指摘を受け入れると測定精度が落ちるのかを、平易な言葉で「翻訳」して伝えなければなりません。
しかも、一つひとつを丁寧に説明するだけの時間的な余裕がある場合は少なく、極めて端的に伝えなければならないのです。これは、非常に高度なコミュニケーションスキルと、相手の理解度を慎重に測りながら対話を進める多大なコストを要する作業です。この「専門性の翻訳」のプロセスが、第一の困難の正体です。
この第一の困難に輪をかけて対応を難しくするのが、第二の困難、すなわち「善意の『否定』という困難」です。
冒頭で強調したように、企業担当者からのフィードバックは、プロジェクトを成功させたい、より良い調査にしたいという純粋な「善意」と貢献意欲の表れです。担当者は、忙しい業務の合間を縫って、時間を割き、真剣に項目を検討してくれています。その貴重な「善意」に対し、専門家はどのような応答を迫られるのでしょうか。
仮に、第一の困難である「専門知識の翻訳」に成功し、なぜそのフィードバックを採用できないのかを説明できそうだとします。その結果として専門家が伝えなければならないメッセージは、「詳細な指摘、ありがとうございます。しかし、その指摘は採用することができません」というものになります。これは、言葉こそ丁寧であれ、実質的に相手の意見を「否定」するコミュニケーションです。
これが「困難」である理由は、その行為がもたらす心理的な負荷の高さにあります。専門家は、その専門的見地によってフィードバックを否定するにしても、フィードバックを下さった企業担当者の方の熱意や善意はよく理解しています。相手の善意を受け止め、感謝を伝えながらも、その善意の結晶である提案は退けなければならない。たくさんの指摘をもらったとして、そのほぼすべてを否定しなければならないこともあるでしょう。
この行為は、相手の貢献意欲を削ぎ、気分を害させてしまうのではないか、あるいは、専門家としての立場を笠に着て、意見に耳を貸さない傲慢な態度だと受け取られはしないか、という不安を専門家に抱かせます。良好な協力関係を維持したいという思いと、専門家としてサーベイの品質を守らなければならないという責務との間で、専門家は板挟み状態に陥ります。相手の善意を無下にしなければならないかもしれないという心理的な重圧が、第二の困難の正体です。
このように、「点検者モード」への対応は、専門知識を分かりやすく「翻訳」する論理的な困難と、相手の「善意」を実質的に「否定」しなければならない心理的な困難という、二重の困難を同時に乗り越えることを専門家に強いるのです。これが、専門家が「大変だ」と感じる理由です。
問題が厄介であり続ける「満足度の罠」
点検者モードへの対応が「二重の困難」を伴うものであることは、前述の通りです。しかし、もし話がそれだけで終わるのであれば、それは「専門家として乗り越えるべき高度な課題」に過ぎないかもしれません。この問題がより根深く、厄介な構造を持っているのは、専門家がこの「二重の困難」に対してどちらの道を選んだとしても、結果的に短期的には「顧客満足」につながってしまう可能性があるからです。これは「満足度の罠」と呼べるかもしれません。この「罠」にも、二つの側面があります。
第一の道筋は、専門家が「二重の困難」のプレッシャー、特に「善意の否定という困難」から逃れる(あるいは企業側との関係性を優先する)ために、指摘をそのまま受け入れるケースです。「確かに、定義があった方が親切ですね」と同意し、項目に補足説明を追記する修正を行うのです。
この場合、何が起きるでしょうか。サーベイ項目は企業側の意向通りに修正されます。しかし、この修正によって、回答者は直感的に回答することが妨げられ、本来測定したかったはずの「従業員の素朴な実感」から焦点がずれ、サーベイの測定品質は(専門家の目から見て)低下する可能性が高まります。
それにもかかわらず、企業側の視点からは、自らの意見が専門家によって真摯に受け止められ、サーベイ項目に「反映された」という事実が残ります。「私たちの現場感覚をよく理解してくれた」と、専門家の対応に対する満足度は高まりやすくなります。これは、「品質」を犠牲にして「満足」を得るという、本末転倒な罠です。
第二の道筋は、専門家が「二重の困難」に真正面から立ち向かい、品質を守るために指摘を丁寧に「棄却」するケースです。これは、膨大な工数と高い心理的負担を引き受けることを意味します。専門家は、多大な時間をかけて「なぜその修正が品質を損なうのか」を、専門用語を使わずに「翻訳」し、同時に、企業側の「善意」を無下にしないよう、細心の注意を払って対話を行います。
その結果、企業担当者は、たとえ自分の意見が最終的に採用されなかったとしても、「専門家が真摯に自分たちの意見に向き合い、時間をかけて丁寧に説明してくれた」というプロセスに、強く満足することがあります。「ここまで真剣に考えてくれるなら、専門家の判断に任せよう」と、納得感や信頼感を抱くのです。これは、「品質」は守られますが、専門家が「高コスト」を引き受けることによって「満足」が得られるという構図です。
これが「満足度の罠」の二面性です。第一の道(安易な受諾)を選べば、専門家の負荷は一時的に下がりますが、プロジェクトの核心である「サーベイの品質」が犠牲になります。第二の道(丁寧な棄却)を選べば、「サーベイの品質」は守られますが、専門家が「二重の困難」のコスト(膨大な工数と心理的負担)を一方的に引き受けることになります。
厄介なのは、その「高コストな対応」自体が企業側の満足度を高めてしまうため、企業側からは、その対応が専門家にとってどれほど困難で過大な負担であったかが認識されにくいという点です。むしろ、それが「当然のサービス」として期待されてしまうことすらあり得ます。どちらの道を選んでも「企業側は満足する」という結果に着地しやすいため、問題の構造(品質低下のリスク、または専門家の過大な負担)が見えづらくなってしまいます。
この構造が、専門家の葛藤を深いものにします。専門家の責務は、短期的な満足度を高めることではなく、長期的に組織の役に立つ、すなわち測定精度の高い信頼できるサーベイを提供することです。しかし、その専門家としての責務を全うしようとすればするほど、「点検者モード」の企業担当者の善意と真っ向から衝突し、「二重の困難」に立ち向かわなければならなくなります。企業の満足と、サーベイの品質、そして専門家が支払うコストが、複雑なトレードオフの関係になってしまうこの状況は、この問題が単なるコミュニケーションの失敗ではなく、厄介な構造的問題であるゆえんです。
良いサーベイは「共作」から生まれる
本コラムでは、「点検者モード」でのフィードバック対応がなぜ専門家にとって「大変」なのか、その構造について解説してきました。その困難さは、専門知識を平易な言葉で説明しなければならないという「翻訳」の責任と、相手の「善意」を心理的な配慮をもって受け止めなければならないという「対人関係」の責任という、「二重の困難」を同時に引き受けることにあります。
専門家が目指しているのは、決して専門家の意見を一方的に通すことではないでしょう。サービスを受ける企業側が持つ、現場の具体的な状況や従業員の感覚といった貴重な知見と、専門家が持つ、測定の妥当性や信頼性に関する専門的な知見が、高いレベルで融合したとき、その組織にとって真に価値のあるサーベイが生まれます。
そのためには、この「点検者モードの壁」という、プロジェクトの過程で生じやすい構造的なすれ違いを、企業と専門家の双方の共通課題として認識することが求められます。
脚注
[1] もしも、その項目が捉えようとしている概念や事柄が「多様なフィードバックの実行を細かく捉える」ためにピックアップされたものならば、この指摘は妥当となります。問題は、各項目が作問された概念や事柄に関連する目的や、その項目作問に至った理論的背景や実証研究の背景を考慮せず、個人的に納得できる内容や粒度を求めて指摘を加えることです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。