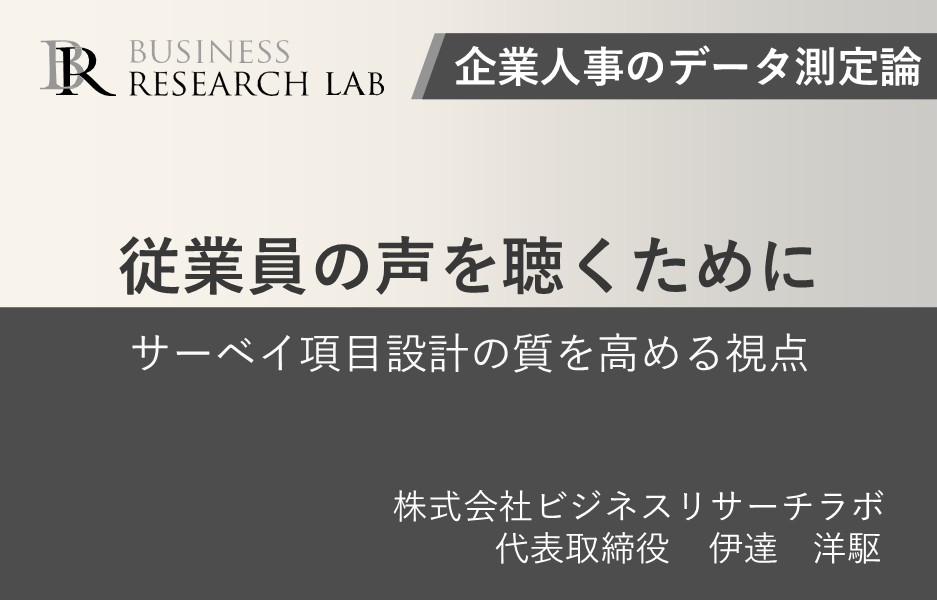2025年11月19日
従業員の声を聴くために:サーベイ項目設計の質を高める視点
仕事柄、多くの企業の組織サーベイ項目を確認する機会をいただきます。各社が従業員の声を真摯に聴き、組織をより良くしようと努めている様子がうかがえ、サーベイが組織的な対話の機会として重要視されていることを実感します。
しかし、その一方で、企業の規模や業種を問わず、項目設計の段階で共通の課題が見られることも事実です。特に、良かれと思って練られた項目が、意図せずして回答者を混乱させ、分析が困難なデータをもたらしてしまうという事態は珍しいことではありません。
本コラムでは、そうした多くの企業に共通して見られる、特に発生しやすい二つの課題―「ダブルバーレル質問」と「括弧書きによる過剰な定義」―に焦点を当てます。なぜこれらの課題が生じてしまうのか、その背景にある組織の構造や心理を考察し、より精度の高いサーベイ項目設計に向けた視点を提供することを目的とします。
一つの質問に二つの問いが混在する構造
過去に実施された、あるいは現在検討中のサーベイ項目案を思い返してみてください。次のような形式の項目が含まれていないでしょうか。
「私の上司は公正で、評価に透明性がある」
「私たちの部署では、十分な情報共有が行われ、円滑に連携がとれている」
「会社の福利厚生は魅力的で、利用しやすい制度になっている」
これらは「ダブルバーレル質問」と呼ばれるものです。一つの項目の中に、二つの問いが含まれている状態を指します。一見すると、関連性の高い事柄をまとめて聞いており、項目数を抑える上で効率的に見えるかもしれません。しかし、この形式は、サーベイデータの信頼性と有用性を低下させる可能性があります。
例えば、最初の「私の上司は公正で、評価に透明性がある」という項目を考えてみましょう。ある従業員は、「評価の基準は明確に示されており透明性は高いが、上司の個人的な感情が評価に反映されており公正ではない」と感じているかもしれません。この場合、その従業員は肯定的に答えるべきか否定的に答えるべきか、判断に迷うことになります。どちらを選んでも、その人の認識を正確に表現することはできません。結果、回答者は回答をためらうか、あるいはどちらか一方の印象のみで答えてしまうことが考えられます。
集計されたデータもまた、解釈に注意を要します。もし、この項目への肯定的な回答が10点満点で5点だったとしても、それが「公正さ」と「透明性」の両方に満足している人が5点ということか、あるいは「公正さには満足だが透明性には不満」という人と「透明性には満足だが公正さには不満」という人が混在した結果なのかを区別することができません。これでは、改善策を立案するための示唆を得ることは難しくなります。課題の核心を特定できず、「評価制度全体の見直しを検討する」といった、解像度の粗い結論に留まってしまうかもしれません。
なぜ分析を困難にするダブルバーレル質問が、多くの組織サーベイで散見されるのでしょうか。特定の誰かの意図や知識不足というよりは、組織的な配慮や合理性が複雑に絡み合った結果として生じることが多いと考えられます。
その背景の一つとして、サーベイ作成のプロセスが挙げられます。多くの組織では、サーベイの項目を作成するにあたり、経営層、各事業部門、管理職、人事部内の関連部署など、様々な関係者から意見を聴取します。組織全体の関心事を網羅し、各方面の納得感を得るために重要なプロセスです。しかし、この合意形成の過程が、ダブルバーレル質問を生む一因となることがあります。
例えば、経営層は組織統治の観点から「評価プロセスの透明性」を重視しているとします。一方で人事部としては、従業員の納得感に直結する「評価結果の公正さ」を測定したいと考えています。サーベイ全体の項目数は限られており、すべての要望を個別の項目として盛り込むことは現実的ではありません。その結果、関係部署の意向を汲み取り、それぞれの重要な要素を尊重するための調整案として、それらの要素が一つにまとめられた項目が作られることがあります。
「私の上司は公正で、評価に透明性がある」という一文は、そうした組織内の調整が反映されたものと見ることができます。このプロセスに関わる人々は、それぞれが組織をより良くしたいという意図を持っています。しかし、その意図の集積が、誰の認識も正確に反映することが難しい項目を生み出してしまう場合があるのです。
もちろん、原因は組織のプロセスだけではありません。項目を作成する担当者の思考も影響します。一つには、サーベイ項目設計における「一つの項目では一つの事柄を問う」という原則の重要性が、必ずしも常に意識されているわけではない可能性があります。むしろ、関連する概念をまとめて問うことの方が、包括的で優れた項目だと感じられていることもあるでしょう。
「効率性」への配慮も、ダブルバーレル質問を後押しする要因です。サーベイは回答する従業員にとって一定の時間を要するものです。「できるだけ項目数を少なくし、回答者の負担を軽減したい」という配慮は、人事担当者として自然なものです。その配慮が、二つの問いを一つに統合するという選択につながることがあります。ところが、その選択は、項目数を減らす代わりに、得られるデータの精度を下げてしまうことを考慮する必要があります。
さらには、私たちが測定しようとする概念そのものの複雑さも、この問題に関係しています。「組織風土」や「チームワーク」といった組織サーベイで扱われるテーマは、本質的に多面的であり、単一の項目で測ることが難しいものです。
例えば、「チームワーク」という概念を一つの項目で捉えようとして、「私たちのチームは互いに協力し、高い成果を上げている」という項目を作ってしまうかもしれません。しかし、チームの状態として「協力体制は整っているが、成果には結びついているとは言い切れない」ということもあり得ます。この場合、回答者はどちらを基準に答えれば良いか迷うことになります。
このように、ダブルバーレル質問は、文章作成上の課題というよりも、組織内の合意形成、効率性への配慮、測定対象の複雑さといった、様々な要因が絡み合って生じる構造的な現象と捉えることができます。
括弧書きによる定義が測定を歪める可能性
サーベイ項目設計におけるもう一つの注意点が、括弧書きを多用して項目の定義を厳密にしようとする試みです。これもまたダブルバーレル質問と同様に、良かれと思って行われることが多いものです。
次のような項目を目にしたことはないでしょうか。
「私の職場では、従業員エンゲージメント(仕事そのものへの熱意、組織の目標達成への貢献意欲、会社に対する愛着や信頼のすべてを指します)が高いと感じる」
この項目の作成者は、おそらく非常に真摯に項目設計に取り組んでいることでしょう。「従業員エンゲージメント」という言葉が多義的であることを理解し、回答者による解釈の差異をなくしたい、という意志が感じられます。全員に同じ定義を共有した上で回答してもらえれば、より正確なデータが得られるはずだ。そうした考えから、丁寧に補足説明を加えているのです。
しかし、この「親切な補足」は、意図とは異なる結果をもたらす可能性があります。それは、回答者の認知的な負担を増大させてしまいます。私たちの脳が一度に処理できる情報量には限りがあります。回答者はまず「従業員エンゲージメントが高いと感じる」という中心的な問いを理解し、それに対する自身の状況を評価しようとします。
しかし、そこに「(仕事への熱意、貢献意欲、愛着や信頼…)」という、長く複雑な定義が割り込んできます。回答者は、このリストのすべてを読み、記憶し、それら一つひとつについて自分の状態を評価し、最終的にそれらを統合して一つの回答を選択するという、複雑な思考プロセスを求められることになります。
これは、回答者にとって簡単な作業ではありません。多くの回答者は、この複雑なプロセスに対して、意識的・無意識的に何らかの簡略化を行います。例えば、深く考えることをやめてしまったり、正直に答えようとする意欲が減退し、当たり障りのない回答や、リストの中で最も印象に残った一部分だけで判断した回答を選んでしまう可能性が考えられます。
定義を厳密にしようとすればするほど、かえって回答の焦点が分散し、解釈が難しくなるという現象も起こり得ます。作成者は、全員に同じ基準で評価してほしいと願っています。しかし、長い定義リストを提示されると、回答者はその中から、自分にとって最も関心が高い、あるいは最も強く感じている要素を基準に回答を形成する傾向があります。
先の例で言えば、ある回答者は現在の「仕事への熱意」は低いと感じているものの、「会社への愛着」は強いかもしれません。別の回答者は、「貢献意欲」は高いものの、「仕事への熱意」はそれほどでもないかもしれません。彼らはそれぞれ、同じ項目に対して、全く異なる側面に焦点を当てて回答する可能性があります。
全員が「従業員エンゲージメント」という同じ言葉について答えているように見えて、その実、Aさんは「愛着」を、Bさんは「意欲」を主たる判断基準にしている、という事態が生じかねません。これでは、集計されたデータが一体「何に対する評価」なのかを特定することが難しくなります。定義を統一しようという試みが、結果としてデータの比較可能性を損なう場合があります。
加えて、このような項目は、従業員の「直感的な感覚」を捉えるというサーベイの目的からずれてしまう可能性も指摘できます。組織サーベイで把握したいことの一つは、従業員が理屈を超えて「普段どのように感じているか」という、組織の全体的な雰囲気や個人の実感です。それは、日々の経験の中で蓄積された総合的な認識と言えます。
しかし、分析的で詳細な定義を提示されると、回答者は自身の素な感覚よりも、「この定義に照らし合わせると、どう答えるのが論理的に適切か」という思考モードに切り替わりやすくなります。「全体としては、この会社で働くことに満足している」という直感が、「待てよ、定義には『仕事への熱意』も含まれるのか。最近の担当業務にはあまり熱意を持てていないな。となると、エンゲージメントが高いとは言えないか・・・」という分析的な思考によって修正されてしまうかもしれません。これでは組織のありのままの状態や、従業員の率直な認識を把握することが難しくなる場合があります。
それにしても、なぜこのような括弧書きによる定義づけが行われるのでしょうか。その背景には、ダブルバーレル質問とも共通する、作成者の心理や組織の事情が存在します。
一つは、やはり「解釈の差異」に対する懸念です。多様な従業員が回答するサーベイにおいて、言葉の解釈が人によって異なってしまうと、データの信頼性が揺らぐのではないか、という合理的な懸念が根底にあります。また、サーベイ結果の報告時に、経営層などから「この言葉の定義は何か」と問われた際に、明確に答えられるようにしておきたい、という自己防衛的な意識が働くことも考えられます。
過剰とも言える「誠実さ」や「完璧主義」も要因となり得ます。担当者は、自身が学んだ専門的な定義を、可能な限り正確に回答者へ伝えなければならない、という責任感を感じているかもしれません。定義の要素に抜け漏れがあってはならないという思考が、情報を削ぎ落すのではなく、付け加えていくという方向に向かわせます。
ここでも組織的な力学が影響を及ぼすことがあります。括弧内の長いリストが、関係部署からの「この要素も定義に含めてほしい」という要望をすべて反映した結果であるケースです。人事、経営企画、現場の各部門が、それぞれ重視するエンゲージメントの側面を盛り込もうとした結果、包括的ではあるものの、回答するには複雑すぎる定義が完成してしまうのです。
このように、括弧書きによる過剰な定義は、作成者の懸念や誠実さ、組織の事情が絡み合って生じるものです。その意図が合理的で善意に基づくものであっても、結果的に回答者の負担を増やし、データの価値に影響を与える可能性があるという点を認識しておきましょう[1]。
組織サーベイの項目設計は、従業員という回答者の存在を想像し、その認識や感情をいかに正確に、負担なく引き出すかを追求するプロセスです。本コラムで考察した二つの課題は、その難しさを示唆しています。自社のサーベイを振り返り、その項目が従業員の声を聴くためのものとして機能しているか、改めて検証してみる機会となれば幸いです。
脚注
[1] 語句の意味が難しく理解しがたい場合は、カッコ書きや注釈などによる補足をせざるを得ないこともあります。ここで問題となるのは、カッコ書きなどの例示や補足により、内容が無意味に多義的になり回答の意味も多様になることやそれに引っ張られて本来の率直な回答から歪むことなど、回答者の直感的な回答・評定・報告が阻害されることです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。