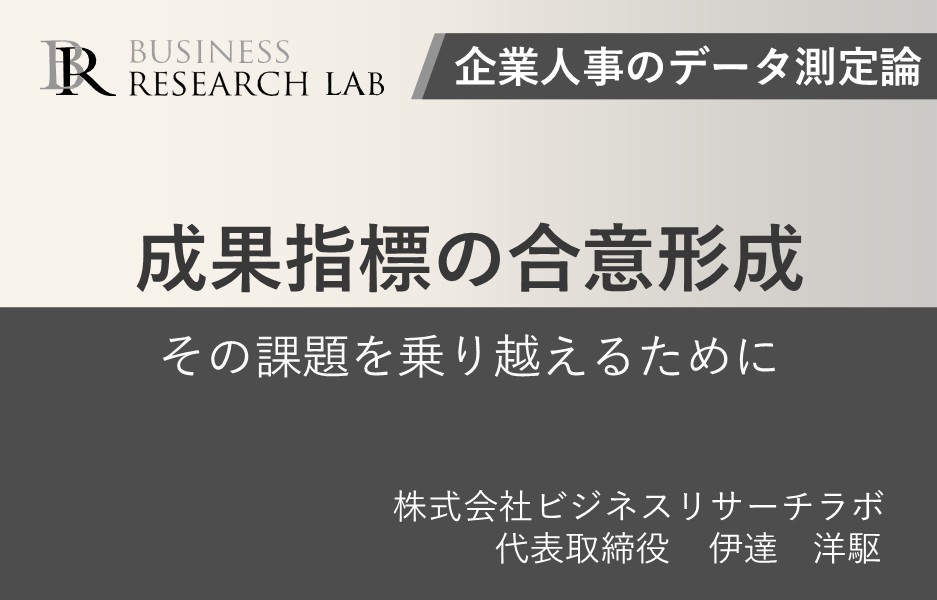2025年11月12日
成果指標の合意形成:その課題を乗り越えるために
人事領域におけるデータ活用、いわゆる「ピープルアナリティクス」や「HRアナリティクス」への関心が高まっています。人材の重要性が増す現代において、企業の持続的成長は、従業員一人ひとりのパフォーマンスやエンゲージメントといった人的資本の状況にも影響されるようになりました。こうした背景から、人事は経営戦略と連携するパートナーとしての役割を期待されつつあります。勘や経験といった主観的な判断に加え、客観的なデータに基づいて人事戦略を立案し、その効果を検証しようという動きが広がるのは、自然な流れと言えるでしょう。
しかし、その取り組みが必ずしも期待された成果につながらないケースも見られます。最新の分析ツールを導入し、専門知識を持つ人材を配置したにもかかわらず、分析結果がアクションに結びつかない。あるいは、分析レポートが経営層や事業部門の関心を得られず、取り組みが継続しなくなる。こうした状況は少なくありません。
なぜ、このような事態が起こるのでしょうか。その原因の一つは、統計モデルの精度やデータの量といった技術的な問題以前に、より根本的な部分に存在しています。それが、本コラムで論じるテーマ、すなわち「分析の目的設定」です。具体的に言えば、「何を明らかにするために分析を行うのか」という「問い」を定義し、関係者間でその「問い」に対する共通認識を築くプロセス、「成果指標の定義と合意形成」に、人事データ分析の成否に影響を与える要因が潜んでいます。
本コラムでは、人事データ分析の出発点として、なぜ成果指標の定義が重要なのかを説明します。続いて、その定義を巡る合意形成がなぜ難しいのか、その構造的な要因を深掘りします。その課題を乗り越えるための思考法やコミュニケーションのアプローチを提示します。最後に、複数の指標を扱う際に、それらをいかにして統合し、組織にとって有益な解釈を導き出していくべきか、その方法について論じていきます。
なぜ成果指標が重要なのか
人事データ分析に取り組む際、私たちの前には従業員の属性、勤怠、評価、異動履歴、サーベイの回答結果など、多岐にわたるデータが存在します。これらのデータを前にして、「何か興味深い傾向が見つからないか」という漠然とした関心から分析を始めてしまうことがあります。しかし、このアプローチでは、分析の方向性が定まりません。優れた分析は、明確な「問い」から始まります。その「問い」の起点となるのが「成果指標」です。
成果指標とは、分析によって説明、あるいは予測したいと考える「目的となる変数」を指します。例えば、「どのような要因が、若手社員の定着に影響を与えているのか」という問いを立てた場合、成果指標は「若手社員の定着率」や「離職の有無」となります。成果指標は、いわば分析プロジェクト全体の「目的地」となります。目的地が明確に定まっていて初めて、私たちはそこに到達するための最適なルート(分析手法)や、必要な装備(収集すべきデータ)を考えることができます。
出発点である成果指標の定義が曖昧なままプロジェクトを進めると、どのようなリスクが生じるのでしょうか。ここで、より複雑で代表的な例として「エンゲージメント」を考えてみましょう。
エンゲージメントは、現代の組織において重要な概念ですが、その定義は多義的です。ある経営者は、エンゲージメントを「業績への直接的な貢献意欲」や「イノベーション創出につながる行動」と捉えているかもしれません。一方で、人事担当者は「組織への愛着」や「定着意思」として使っている可能性があります。現場のマネージャーにとっては、「日々の仕事に対する熱意や活力」「チーム内の円滑な協業」こそがエンゲージメントかもしれません。
このように、関係者がそれぞれ異なるイメージを抱いたまま、「エンゲージメントを高める要因を分析する」というプロジェクトがスタートしたと想像してみてください。分析チームは、学術的にも一般的な定義である「仕事への熱意」を成果指標として設定し、分析を進めます。その結果、「上司からのフィードバックの頻度が、仕事への熱意に影響を与える」という示唆が得られました。この結果自体は間違っていないかもしれません。
しかし、経営者が本当に解決したかった課題が「貢献意欲の向上」であり、人事担当者が最も懸念していたのが「キャリア不安による若手の離職」だった場合、この示唆は的を射ていません。フィードバックを増やす施策に投資しても、キャリアパスが不透明なままでは若手は定着せず、経営者が期待した業績向上にも直結しないかもしれません。この場合、各関係者の関心事と分析結果の間にずれが生じ、アクションへとつなげていく力が弱まってしまいます。
この例が示すように、成果指標の定義は、分析上の技術的な設定ではありません。それは、「組織として、今、何を重要な課題として捉えているのか」という、組織全体の意思を明確にする行為です。この定義が明確で、かつ関係者間で共有されていて初めて、分析は価値創造のプロセスへと進むことができます。
分析の目的は、レポートを作成することでも、統計的な関連性を見つけることでもなく、組織が抱える課題を解決し、より良い状態に向けた一歩を踏み出すことにあります。その意味で、成果指標を定義し、合意形成を図ることは、人事データ分析の成否に影響を与えるステップであると言えるでしょう。
なぜ意見は一致しにくいのか
成果指標の定義が重要であると理解した上で、次なる課題は、その定義について関係者間の合意をいかにして形成するかという点に移ります。なぜ、そもそも合意形成が必要なのでしょうか。それは分析という行為が、分析担当者だけで完結する作業ではないからです。
第一に、合意形成のプロセスを経ることで、分析結果の品質が向上します。様々な視点から定義が吟味されることで、特定の意図に偏った解釈や、現実から乖離した設定に陥るリスクを減らすことができます。
第二に、分析結果から導き出される施策を実行するのは、多くの場合、人事部門だけでなく、事業部門をはじめとする現場の従業員です。従業員が分析の前提となる「問い」に納得していなければ、施策への協力や積極的な参加は期待しにくくなります。
第三に、合意形成のプロセスは、組織内でデータ分析活動の正当性を確保するためにも有用です。関係者を巻き込むことで、分析プロジェクトが一部の人間の関心事ではなく、組織全体の課題解決に貢献する公式な取り組みであることを示すことができます。
しかし、この合意形成のプロセスは、容易ではありません。多くの場合、成果指標の定義をめぐって、関係者の意見は簡単には一致しません。なぜ意見の対立が起こるのでしょうか。その原因を理解するためには、まず「誰と合意すべきか」という問いに答える必要があります。全社員と合意を得ることは現実的ではありません。重要なのは、分析の目的と結果に利害関係を持つキーパーソン、すなわちステークホルダーを見極めることです。
人事データ分析における主要なステークホルダーは、概ね、経営層、事業部門の責任者、人事部門の責任者に大別されます。それぞれ組織内で異なる役割を担っており、物事を見る視点や重視する事柄が異なります。
経営層は、企業の持続的な成長や市場における競争優位性の確保といった、マクロな視点から物事を判断します。経営層にとっての関心事は、人事施策が最終的に企業全体の生産性や収益性にどう貢献するのかという点にあります。したがって、「優秀人材」という言葉を使う時、その頭の中にあるのは、事業へのインパクトが大きい人材像であることが多いでしょう。
一方、事業部門の責任者は、自身が管轄する部署の目標達成や日々のオペレーションの円滑な遂行に責任を負っています。彼ら彼女らの視点は、より現場に根差したミクロなものです。そこにおいて「優秀人材」とは、日々の業務を確実にこなし、チームに安定をもたらす人材かもしれません。また、事業部門が直面しているのは、「中心メンバーが退職してしまった」「新人の育成が計画通りに進まない」といった、具体的で身近な課題です。短期的な業績へのプレッシャーも、その判断に影響します。
人事部門の責任者は、全社的な視点から人事戦略を考え、制度の公平性や一貫性を担保する役割を担います。個別の事象だけでなく、組織全体の健全性や、従業員体験の向上といった、中長期的な視点を持っています。彼ら彼女らが「エンゲージメント」を重視するのは、例えば、それが従業員の定着や組織文化の醸成につながると考えているからです。
このように、それぞれの立場が異なれば、一つの言葉に対する解釈も問題の捉え方も自ずと異なってきます。経営層が求める「貢献意欲」と、事業部門が求める「現場での安定性」、そして人事部門が求める「組織への愛着」。これらは全て「良い従業員の条件」として妥当なものですが、その中身は異なります。この構造的な違いが、成果指標の定義をめぐる意見の相違の根源です。
これは単純な誤解ではなく、それぞれの立場におけるミッションに基づいた、妥当な視点が必ずしも一致しない状況が生まれているということです。いずれか一方の意見を絶対的な正解とするのではなく、それぞれの主張の背景にある文脈を理解し、対話を始めることが、合意形成の第一歩となります。
合意形成を進めるためのアプローチ
成果指標の定義をめぐる合意形成が、構造的に難しい課題であることを理解した上で、私たちは次に、その課題を乗り越えるためのアプローチについて考える必要があります。このプロセスは会議の運営術ではなく、分析プロジェクトを成功に導くためのファシリテーションです。
考えなければならないのは、「いつ」合意形成を行うべきか、そのタイミングです。結論から言えば、タイミングは、本格的なデータ収集や分析モデルの構築に着手する前、プロジェクトの企画・設計段階にあります。これは家づくりに例えるならば、基礎工事を始める前に、関係者全員で「設計図」の承認を得るプロセスに相当します。
設計図が固まらないまま工事を始めれば、後から仕様変更が相次ぎ、手戻りやコスト増を招くことになります。データ分析も同様で、分析の目的地である成果指標が定まらないままデータ収集を始めれば、不要なデータを集めてしまったり、逆に必要なデータが足りなかったりといった事態に陥る可能性があります。
このタイミングで、円滑な合意形成を促すためには、いくつかの工夫が求められます。
第一に、準備段階での姿勢が重要です。人事や分析の担当者は、自身をビジネス課題の「翻訳家」として位置づけましょう。経営層が使うビジネス言語と、事業部門が使う現場言語、人事部門が使う専門用語。これらの間に立ち、それぞれの言葉の背景にある意図を汲み取り、共通の理解へとつなげていく役割です。
最初から完璧な定義を目指さないことも一策です。議論を前に進めるためには、「たたき台」となるシンプルで分かりやすい定義案を提示し、それを元に関係者の意見を引き出していきます。その際、人事部門が持つ「こうあるべきだ」という考えは一旦脇に置き、あくまで組織が直面している現実の課題を起点に考える姿勢が求められます。
第二に、関係者を巻き込むコミュニケーションの工夫です。いきなり全てのステークホルダーが一堂に会する会議を開くのではなく、プロジェクトに協力的で、影響力のあるキーパーソンに個別に相談し、「壁打ち相手」になってもらうことから始めると良いでしょう。非公式な対話を通じて提案を磨き、理解者を増やしておくことで、公式な場での議論が進めやすくなります。
議論の場では、言葉だけで定義を説明するのではなく、簡単なグラフや図を用いて「もしこのように定義すれば、データ上はこのように見えます」と可視化して示すことが有効です。抽象的な概念が具体的な形を持つことで、関係者は自分事として捉えやすくなり、建設的な意見が出やすくなります。
しかし、こうした工夫を凝らしてもなお、意見が完全に一致しない場面は訪れます。対立は避けられないものと捉え、その際の対応策を複数持っておきましょう。第一の策は、議論の視座を上げ、プロジェクトのより上位の目的に立ち返ることです。それぞれの主張に共通する目的を見出し、そこから両者の意見を包含するような、一段洗練された定義を再構築できないか模索します。
こうした統合が難しい場合は、第二の策として、スコープを分割したり、優先順位をつけたりするアプローチが考えられます。例えば、それぞれの主張がどちらも重要であると判断されるなら、「今回は二つの成果指標を設定し、両方の側面から分析しましょう」と提案することができます。
これは対立を解消し、両者の関心に応える方法です。あるいは、分析に使えるリソースが限られているのであれば、「どちらの課題がより緊急度や重要度が高いか」を客観的なデータに基づいて議論し、優先順位をつけることもあるでしょう。「採用しない」という否定ではなく、「今回はこちらを先に取り組み、もう一方の課題は次のフェーズで扱いましょう」という時間軸での合意形成です。
あらゆる手を尽くしても議論が平行線を辿る場合には、最終手段として、プロジェクトスポンサーに判断を委ねるという選択肢もあります。ただし、その場合も決定を丸投げするのではなく、それぞれの意見の要点、各案を採用した場合のメリット・デメリットを整理して提示し、スポンサーが的確な判断を下せるよう支援することが、ファシリテーターの役割となります。
複数の指標の統合
合意形成のプロセスにおいて、意見の対立を解消するための一つの手段として「複数の成果指標を設定する」アプローチを挙げました。しかし、このアプローチの価値は、対立解消の方法に留まりません。むしろ、複雑な人事課題をより深く多角的に理解するための手法として捉えるべきでしょう。人や組織というものは、そもそも多面的な存在です。それを単一の指標で測ろうとすること自体に、限界があるのは自然なことです。複数の視点、すなわち複数の成果指標を持つことで、私たちは事象の解像度を高め、より本質に迫ることが可能になります。
ただし、ここで注意すべき点があります。複数の成果指標を設定したとしても、それらを単に個別の指標として並べるだけでは、課題の全体像を捉えることはできません。「定着意思」と「仕事への熱意」、そして「パフォーマンス評価」という三つの指標を追いかけると決めたとしても、それらが互いにどう影響し合い、全体として何を意味するのかが説明されなければ、情報は断片的なままです。ステークホルダーからは「指標は分かったが、結局、我が社の課題の核心はどこにあるのか」という問いが返ってくることになるでしょう。
真価が問われるのは、ここからです。複数の成果指標という点と点を、いかにして一本の線、そして一つの意味のある「組織の状態を示すモデル」として統合していくか。そのプロセスに、人事データ分析が組織に与える価値の源泉があります。このプロセスは、大きく分けて「構造化」「可視化」「物語化」という三つのステップで考えることができます。
第一のステップは「構造化」です。複数の成果指標を、意味のある共通項でグループ分けし、全体像を整理する作業です。例えば、「定着に関連する指標群」と「活躍に関連する指標群」といったビジネス課題で分類したり、「入社初期の課題」と「中堅期の課題」といった従業員のライフサイクルで分類したりします。構造化によって、バラバラに見えていた指標群に秩序が与えられ、どこに問題が集中しているのか、全体像を俯瞰的に捉えることが可能になります。
第二のステップは「可視化」です。構造化して整理した変数間の関係性を、視覚的に表現することで、直感的な理解を促します。例えば、重要な二つの成果指標、仮に「仕事への熱意」と「定着意思」をそれぞれ縦軸と横軸に取った、2×2のマトリクスを作成してみましょう。すると、従業員は四つの象限に分類されます。「熱意も定着意思も高い」社員群、「熱意は高いが定着意思は低い」社員群、「定着意思は高いが熱意は低い」社員群、「両方とも低い」社員群。このように可視化することで、平均値だけを見ていては分からない、組織内に存在する従業員の類型が浮かび上がってきます。
第三のステップが「物語化」、すなわち統合的な解釈の構築です。構造化・可視化した結果を基に、それらが全体として何を意味しているのか、説得力のある一つのストーリーとして説明します。
先の2×2マトリクスの例で言えば、「当社のエンゲージメントにおける課題は、単にスコアが低いことではありません。『若手層は仕事への熱意が高いものの、キャリア不安から定着意思が低く、一方で中堅層は会社に残るものの、仕事への熱意が低下傾向にある』という、世代間で異なる課題を抱えていることが示唆されます」といったように、全体を貫く核心的なテーマを抽出します。この解釈はデータの要約ではなく、組織が直面している現実に対する洞察です。
こうした解釈があれば、提案されるアクションもまた、一貫性と説得力を持つことができます。「したがって、我々は二つの異なるアプローチが必要です。若手に対してはキャリアの展望を示すための施策を、中堅に対しては挑戦意欲を再活性化させるための施策を、それぞれ検討すべきです」と。このように、複数の成果指標間の関係性が解き明かされ、一つの解釈として語られる時、データは組織を動かす有益な情報へと変わるのです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。