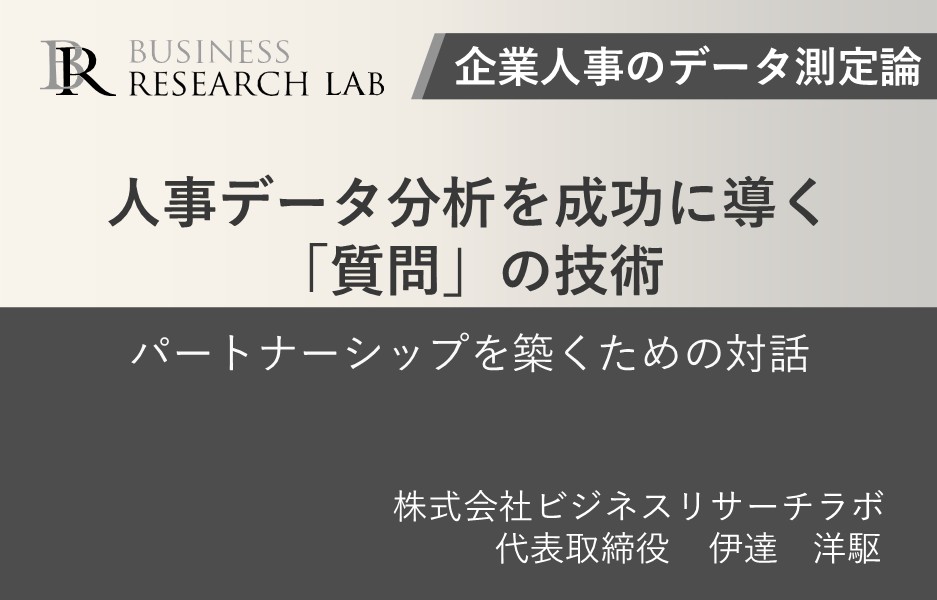2025年11月7日
人事データ分析を成功に導く「質問」の技術:パートナーシップを築くための対話
人事領域におけるデータ活用の重要性が認識され、その一歩を踏み出す企業が増えています。従業員という組織の資産に関するデータを分析し、そこから得られる洞察を人材戦略に活かすことは、持続的な成長を目指す企業にとって重要な課題です。この潮流の中で、高度な分析技術や専門知識を持つ外部パートナー、すなわちベンダーとの協働は有効かつ現実的な選択肢となります。
しかし、外部の専門家を迎え入れれば、すべての問題が自動的に解決するわけではありません。むしろ、委託という選択をしたからこそ直面する、特有の難しさがあることもまた事実です。期待したほどの成果が得られなかったり、分析結果が実務に結びつかなかったりするケースは後を絶ちません。こうしたミスマッチの原因を探ると、委託先の能力や資質だけでなく、依頼する側である企業の「関与の質」が、プロジェクトの成否に影響を与えていることが見えてきます。
本コラムでは、この「関与の質」の中核をなす要素、すなわち依頼側が「賢い質問者」になることの重要性に焦点を当てて考察していきます。ここで言う「賢い質問」とは、単にベンダーの能力を評価したり、知識を試したりするための詰問ではありません。それは、専門性の異なる両者が相互理解を深め、共通のゴールを築き上げるための「対話の設計図」であり、信頼に基づくパートナーシップを構築するためのコミュニケーションの手段です。
質問という能動的な行為を通じて、依頼側はどのようにしてプロジェクトの主導権を握り、価値創造へとつなげていくことができるのか。その道筋を、問いかけの技術と共に検討していきたいと思います。
なぜ「質問」が重要なのか
人事データ分析という専門性の高い領域を外部に委託する際、依頼側が陥る可能性があるのが、「専門家にお任せします」という姿勢です。自社にない知見を外部に求める以上、ある種の期待を込めて相手に委ねるのは自然なことかもしれません。しかし、それが「丸投げ」とも言える姿勢になってしまうと、プロジェクトを停滞させ、期待外れの結果を招く要因となります。
専門家に任せきりにしてしまうと、プロジェクトの目的が徐々に曖昧になっていきます。当初は「離職率を下げたい」という目的があったとしても、分析プロセスがブラックボックス化してしまうと、いつの間にか目的が「ベンダーが提案する高度な分析手法を試すこと」や「見栄えの良いダッシュボードを作ること」にすり替わってしまうことがあります。現場の実態や本当に解決すべき課題から乖離した分析が進み、最終的に得られたアウトプットが、誰も活用できないものとなるのです。
こうした事態を防ぎ、プロジェクトを成功へと導くためのシンプルで強力な武器が「質問」です。質問は、依頼側が受け身の姿勢から脱却し、プロジェクトの当事者として積極的に関与するための第一歩です。依頼側(人事の専門家)と受注側(データ分析の専門家)の間に存在する専門性のギャップは、放置すれば壁となりますが、質問という行為は、この壁を乗り越えて双方の知識をつなぐための役割を果たします。質問を介した対話のキャッチボールは、両者の間に共通言語を築き、同じ目線で課題を議論することを可能にします。
何をどのように問うべきか
「賢い質問者」になることの重要性を理解した上で、次に問われるのは「具体的に、何を、どのように問うべきか」という技術です。ここではプロジェクトのフェーズに応じて、ベンダーの能力や姿勢の様々な側面を明らかにするための問いかけについて、その背景にある意図と共に解説していきます。
プロジェクトの「始点」で問う
委託先との最初の接点は、プロジェクトの方向性を決定づける局面です。ここでの質問の目的は、ベンダーが指示待ちのオペレーターや自社製品の販売員ではなく、共に課題の本質を探求してくれる「思考のパートナー」となり得るかを見極めることにあります。
そのために、あえて少し抽象的な課題を投げかけてみるのが一策です。例えば、「漠然としていて恐縮ですが、当社の若手従業員の定着率を高めたいと考えています。もしご支援いただけるとしたら、何から始めると良いでしょうか」という問いです。
この問いに対する「良い」応答は、即座に解決策を提示するものではありません。こちらの投げかけた言葉を受け止め、その解像度を上げるための「逆質問」をしてくるはずです。
「ありがとうございます。非常に重要なテーマですね。より深く理解するために、いくつか確認させていただけますか。例えば、『若手』とは、入社何年目くらいまでの方々を指していますか。また、『定着率の低下』は、特定の部署や職種で特に顕著に見られる傾向はありますか。これまで社内で、この課題についてどのような議論や取り組みがなされてきたか、お聞かせいただくことは可能でしょうか」といった具合です。
こうした逆質問は、ベンダーが課題の背景や文脈を理解しようとする姿勢の表れです。安易な一般論に飛びつくのではなく、まず定義を共有し、問題の所在を特定しようと努めています。これは、顧客の個別具体的な状況に寄り添い、解決策を模索する能力を持っていることの証です。
一方で、注意すべき応答は、こちらの漠然とした問いに対して、間髪入れずに「お任せください。弊社の最新AIを使えば、離職予備軍を特定できます」「多くの企業様で実績のある、この分析パッケージが最適です」といった形で、性急に自社のソリューションを提示してくるケースです。これは、顧客の課題を理解するプロセスを省略し、自社の既存の型に当てはめようとしている可能性があります。このような応答は、「思考のパートナー」ではなく、「プロダクトの売り手」である可能性を示唆しています。
最初の対話で、相手が「答え」を急ぐのか、それとも「問い」を深めるのか。その姿勢の違いに注意深く耳を傾けることが、長期的なパートナーシップの第一歩となります。
プロセスの「透明性」を問う
プロジェクトの計画が提示された段階では、その分析プロセスがブラックボックス化しないよう、透明性を確保するための質問が重要になります。ここにおける目的は、技術的な選択の妥当性と、分析の品質を左右する仕事の丁寧さを確かめることです。
提案された分析手法について、その選択理由を掘り下げてみましょう。「今回ご提案いただいたこの分析手法について、なぜこれを選択されたのか、その理由を教えていただけますか」と尋ねることは基本ですが、さらに踏み込みます。「比較検討された他の分析手法はありますか。もしあれば、それらと比較した場合に、今回の手法が持つ利点はありますか」と問いかけます。優れたパートナーは、この質問を歓迎するはずです。そして、専門家でない相手にも理解できるよう説明を試みます。
例えば、「今回は、将来の離職率を高い精度で『予測する』ことよりも、離職に繋がりやすい『要因を特定し、理解する』ことを重視しました。そのため、結果の解釈がしやすいこちらの手法を選択しました。もし予測精度を優先するなら別の手法も考えられますが、その場合、なぜそのような予測になったのかという理由が分かりにくくなるというトレードオフがあります」といったように、課題の目的に応じた手法選択のロジックと、その判断に伴う長所・短所を正直に語ってくれるでしょう。
このような説明ができるということは、ベンダーが複数の選択肢を理解し、状況に応じて道具を選ぶことのできる専門家であることの証です。
分析の「限界」を問う
いかなる分析手法も万能ではなく、限界や弱点が存在します。その事実に対して、ベンダーがどれだけ誠実に向き合えるかを見極めることは、信頼関係を築く上で重要です。ここでの質問の目的は、ベンダーの知的謙虚さとリスク管理能力を確かめることにあります。
そのために、あえて分析のネガティブな側面に光を当てる質問を投げかけます。「今回提案いただく分析がうまく機能しないとしたら、それはどのようなケースでしょうか。この分析アプローチが内包している弱点や限界について教えてください」という問いです。
この問いに対して、「弊社のAIは高精度ですので、そのような心配はありません」といった自信過剰な応答や[1]、「それはやってみないと分かりません」といった思考停止の応答が返ってきた場合、そのベンダーはリスクに対して楽観的すぎるか、あるいは不誠実である可能性があります。
信頼できるパートナーは、この問いを、プロジェクトのリスクを共有し、共に対策を考えるための良い機会と捉えるでしょう。そして、自らの手法の限界を認め、具体的な言葉で説明します。
「重要なご指摘です。このモデルは過去のデータから予測をするため、例えば、これまでになかったような大規模な組織改編や、新しい人事制度の導入といった、前例のない出来事が起きた場合、予測精度が低下する可能性があります。また、従業員数が少ない部署の分析結果の解釈には細心の注意が必要です」といったように、具体的なシナリオを挙げて、その限界を説明してくれるはずです。さらに、「そのため、分析は一度実行して終わりではなく、定期的に精度を検証し、状況の変化に合わせて見直していくプロセスが必要です」と、運用面での対策まで言及できれば、なお良いでしょう。
結果の「出口」を見据えた思考を問う
分析は、それ自体が目的ではありません。そこから得られた洞察を、いかにして人事の意思決定や具体的なアクションにつなげるかが重要です。契約前の段階で、ベンダーがこの「出口」をどれだけ意識しているか、その思考の深さを見極めるための質問が有効です。
そのために、過去の事例や架空のシナリオを用いて、その思考プロセスを尋ねてみましょう。例えば、「過去に支援されたプロジェクトで、分析結果から人事施策の提案につながった事例があれば、差し支えない範囲で教えていただけますか。その際、どのような分析結果から、どのような検討を経て、施策の提案に至ったのでしょうか」と尋ねます。
この質問に対して、プロセスを具体的に説明できるかが重要です。「Aという分析結果から、Bという課題仮説が導き出されました。そこで、CとDという二つの施策オプションを、それぞれのメリット・デメリット、想定される現場の反応などを踏まえて提案し、最終的にC施策の実行をサポートしました」といったように、思考の道筋を語れるベンダーは、分析をアクションにつなげる能力が高いと考えられます。
次のような仮説的な質問も有効です。「仮に、今回の私たちの課題分析で『特定のスキルを持つ中堅社員のエンゲージメントが低い』という結果が出たとします。その場合、どのようなアクションの選択肢が考えられるでしょうか」と問いかけます。もちろん、この段階で完璧な答えを求めるものではありません。重要なのは、その思考プロセスです。
「まずは、なぜ中堅社員のエンゲージメントが低いのか、追加分析で深掘りする必要があります。その原因が『キャリアパスの不透明さ』なのか『業務内容のミスマッチ』なのかによって、打つべき手は異なります。前者であれば上司との対話強化やキャリア面談の仕組み作り、後者であれば異動や職務の再設計といった選択肢が考えられます」というように、多角的に可能性を検討し、慎重に次のステップを考えられるか。この「分析からアクションへの翻訳能力」が、プロジェクトの投資対効果を最大化する上で重要な能力です。
質問から対話へ
ここまで、ベンダーの能力や姿勢を見極めるための質問の技術について述べてきました。しかし、「賢い質問者」の役割は、相手を評価し、選別することに留まりません。その真価は、プロジェクトが開始されてからのパートナーシップを深化させるプロセスにおいても発揮されます。質問は、「評価」のための手段から、「協働」のための触媒へとその役割を変えていきます。
プロジェクトの初期段階において、質問は主にベンダーの能力を見極め、期待値のズレを修正するための手段として機能します。しかし、信頼できるパートナーを選定し、プロジェクトが軌道に乗り始めると、質問の性質は変化していきます。一方的な問いかけから、双方向の「壁打ち」や「議論のきっかけ」へと進化するのです。
例えば、ベンダーから提示された中間報告に対して、「この結果は興味深いですが、なぜAという部署だけ異なる傾向が出ているのでしょうか。現場の感覚としてはBという要因が考えられますが、データからは何か示唆はありますか」といった問いを投げかける。これは、相手を試すのではなく、ベンダーが持つデータ分析の視点と、依頼側が持つ現場の知見を融合させ、より深い洞察を得るための共同作業です。このような建設的な対話が、プロジェクトの価値を高めていきます。
パートナーシップを築くために
人事データ分析の外部委託を成功へと導く道は、「高い分析能力を持つパートナーを探す旅」であると同時に、「自分たちが賢い依頼者になるための旅」でもあります。どれほど優れた技術や知見を持つベンダーと契約したとしても、依頼側が受け身の姿勢で、すべてを任せきりにしてしまうと、その能力が最大限に発揮されることはありません。真の価値は、両者の専門性が化学反応を起こすような、協働のプロセスの中に生まれます。
本コラムで探求してきた「賢い質問」とは、その化学反応を促すための誠実で効果的なコミュニケーションの形です。それは、相手の能力を一方的に測るためのものではなく、専門性の違いという壁を乗り越え、相互理解を深め、信頼を醸成し、共通のゴールに向かって共に歩むための対話の出発点となります。
「なぜ?」と問うことで、私たちは思考の深さを知ります。「限界は?」と問うことで、私たちは誠実さに触れます。「だから、どうする?」と問うことで、私たちは未来へのビジョンを共有します。この一連の問いかけを通じて、依頼側とベンダーの関係は、ただの発注者と受注者という関係から、課題解決に挑む対等なパートナーへと昇華していくことでしょう。その対話の先に、データが人の可能性を解き放つ未来が待っているでしょう。
脚注
[1] 本コラム執筆時点において、AI技術の急速な発展により、高精度な分析を実現できるツールも登場しています。しかし、ここで問題としているのは技術の精度そのものではなく、顧客の個別の課題や文脈を理解せずに、一律のソリューションを性急に提示する姿勢です。どれほど優れた技術であっても、それが解決すべき課題の本質を見誤れば、期待した成果は得られません。重要なのは、技術の能力と限界を正しく理解し、顧客の状況に応じて活用する判断力と、そのプロセスを透明化して共有する姿勢です。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。