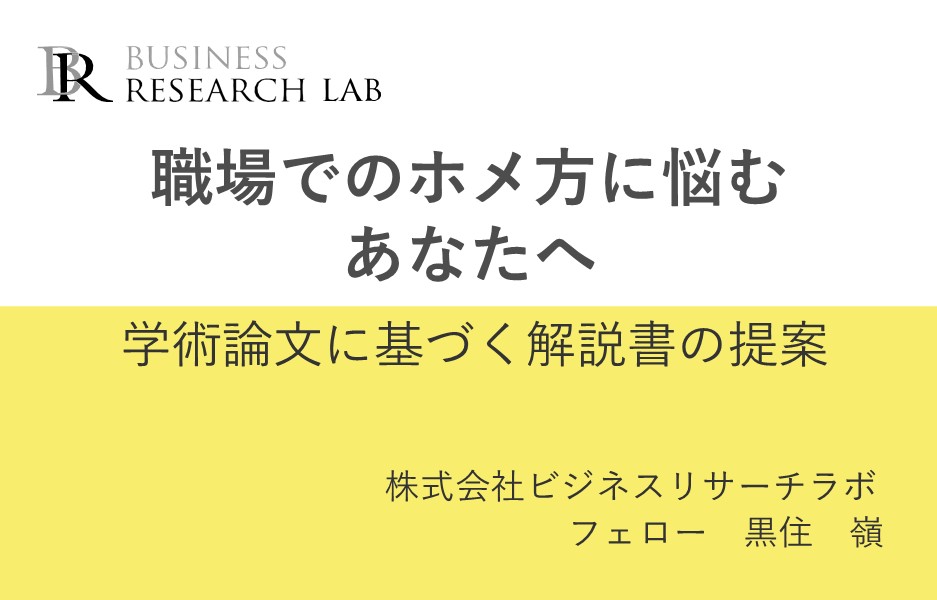2025年10月14日
職場でのホメ方に悩むあなたへ:学術論文に基づく解説書の提案
仕事や職場で関わる相手を「ホメる」という行動に、どのようなイメージを持つでしょうか。様々なメディアでホメることの有効性が取り上げられるようになってきました。その一方で、いざ「ホメるべきだ」と言われても、「どう実践していいかわからない」あるいは「ホメてばかりもいられない」といった感想を持つ方も少なくないでしょう。
こうしたビジネスの現場でのニーズを念頭に、この度、『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』を共著で上梓しました。様々な実践方法も提案される中、納得感をもってホメるために、当事者に起きるメカニズムを解説し、具体的な実践方法を提案しています。
本コラムでは、出版までの経緯や、現場での実践を見据えた拙著の特徴を紹介します。また、書籍内で扱っている解説のうち、そのエッセンスを感じてもらえる一部の内容を選別して紹介します。本コラムを通じ、「職場でホメる」という実践の意義と、「明日から試してみよう」という挑戦の意欲を持ってもらえれば幸いです。
執筆の背景
拙著では、「ホメる」という、一見すると日常的な行為を掘り下げています。「一見すると」と表現したのは、2つの理由があります。
1つには、ホメるという行動には、実は多くの要因が絡み合い、日常ではあまり意識しないような、複雑なメカニズムが存在しているという意味を込めました。この点は後述することにし、もう1つの理由として、普段の生活と仕事や職場といったビジネスシーンで、その捉え方が異なるという認識に基づいています。
たとえば、育児や教育の現場では、比較的古くから重要視されているといえます。「子どもは、ホメてのびのびと育てよう」「𠮟ってばかりでは遠慮がちに育ってしまう」など、ホメることを重視する教育方針には、納得できる方も多いのではないでしょうか。
一方、ビジネスシーンにおいて、とくに日本の職場では、「叱る」ことが長らく人材育成の中心だったといえます。たとえば、「我慢する」ことが美徳とされる文化を踏まえると[1]、仕事のミスを指摘し、指摘された側も悔しさを我慢して次の機会に活かす、といった指導方針が、一定以上の成果を上げられてきたと考えられます。
確かに現在でも、仕事で改善を求めることは不可欠です。ただ、過剰なプレッシャーやストレスとの向き合い方に対する社会的な変化、そして、多様性の尊重や人材の流動性の高まりが相まって、「ホメて育てる」ことを重視する風潮も高まっているといえます。
この背景を踏まえて、社内で行われたディスカッションでは、「納得感をもってホメる」ことに悩むビジネスパーソンは多いはず、という仮説が立ちました。叱ることによる改善を重視してきた経験からの大きな方針転換に、戸惑いを感じるのも当然です。そうしたビジネスの現場で起きる悩みに、学術研究の知見を橋渡しすることは、当社のミッションの一つでもあるのです。
こうした経緯のもと、拙著の共著である伊達と私が開催したウェブセミナー[2]は、外部のウェブメディアにも取り上げていただく[3]ほどの反響がありました。その反響は、職場でのホメ方について大きなニーズがある、という仮説を裏付け、書籍の執筆機会を提供いただくことへとつながっていきました。
拙著の特徴
研究に基づく解説と提案
ここからは、ビジネスパーソンが抱える「ホメ方」の悩みに、拙著ではどのように応えることを目指したのか、その特徴を紹介していきます。まず一つ目の特徴は、褒め方に関する多くの学術知見を踏まえて提案している点です。
学術研究では「ホメる」という行為は、ポジティブ・フィードバックと捉えます。対象となる行為を今後も続けてもらうことを意図し、行為者へポジティブな評価を返す、という意味合いです。このポジティブ・フィードバックというキーワードを中心に、様々な研究を確認していきました。
今回、書籍で取り上げた文献の数は、のべ66本に及びます[4]。これは、読者の悩みに答えるうえで必要なものを選別し、最終的に採用された結果です。また、学術研究というのは、1本の論文を成立させるために少なくとも10本以上の論文が参照されて、それぞれが「巨人の肩に乗る」という言葉を体現しています。
こうした文献に基づく拙著の解説や提案は、経験則による対応で戸惑う方にとって、大きな後ろ盾となるはずです。「学術研究ではこのように考えることができるのか」「研究結果に基づく関わり方を実践してみよう」と、納得しやすいものから取り入れてみると良いでしょう。
「限界」への言及
拙著の二つ目の特徴は、ホメ方の「限界」にも触れている点です。日常での実感を裏付けるように、学術研究でも、上手くいかないホメ方があることが実証されています。こうした限界に触れることで、なぜうまくいかないのかを理解し、そうしたホメ方を避けるといった改善を加えていくことが可能になるためです。
また、冒頭で触れたように、ホメる(あるいは叱る)といったフィードバックは、日常にありふれた行為であるものの、その心理的なメカニズムには多くの要因が関連する、複雑な現象でもあります。この背景から、「伝家の宝刀」とでもいうべき万能のホメ方というのは存在しない、という限界もうかがい知ることができます。
たとえば、褒めれば必ず効果が出るわけではなく、内容によってはむしろ相手に疑義を生じたり、パフォーマンスを下げるリスクがあります。また、伝える内容が同じであっても、状況や相手との関係性によって、効果が変わることもあります。こうした点も併せて紹介することで、自分の状況にあった方法を模索するということのヒントを提供したいと考えています。
「使い分け」の提案
三つ目は、ホメ方の使い分けを提案している点です。上述のように、「伝家の宝刀が無い」という言及はせざるを得ないものの、それだけではあまりに無責任といえます。自分の状況に合わせた方法を模索するうえでは、拙著が提案する「使い分け」の視点が役立つはずです。
拙著では第7章「相手と状況で変わるホメ方の方程式」と題した一章分をかけて、ホメ方をどう使い分けるのがよいのか、その方法を提案しています。その中でも、ホメるときの内容に注目する使い分け(7-1節)、相手の特徴(7-2節)や立場(7-3節)に応じた使い分けとして、基準もできる限り細かく設定しました。
たとえば、実務領域でも認知が広がりつつある「能力」と「努力」のホメ分け方の詳細や、防衛的な態度を示す人のホメ方、あるいは上司のホメ方といった個別のケースについても提案しています。ホメ方のバリエーションを増やすと共に、自分と相手の双方にとってよいフィードバックの機会となるよう、最適なホメ方を見つけてもらうことに活用してもらいたいです。
具体的な内容紹介
フィードバックの「比率」
本コラムの最後の話題として、拙著で実際に取り上げている内容を要約しつつ紹介していきます。それぞれ、上述した拙著の特徴を表すトピックとなっています。
まず取り上げたいのは、フィードバックの「比率」に関する研究です。これは、「ホメてばかりはいられない」というビジネスの現場で避けて通れない悩みに答えるとともに、今からすぐに取り入れることのできるアドバイスの1つでもあります。
フィードバックの「比率」というのは、研究を通して明らかになった、「ホメること対叱ること」の適切な割合を示すものです。心理学や組織論の研究から、人間関係が安定しているチームや夫婦に共通する傾向として、ポジティブな言葉とネガティブな言葉の比率が「5対1」であることが示されているのです[5]。
この結果は、例えば、日常的に褒めや感謝を5回積み重ねておくことで、1回の厳しい指摘があっても相手は建設的に受け止められる、というわけです。これは、銀行口座に預金を貯めるのに似ています。普段から心理的な「貯金」をしておけば、いざネガティブなフィードバックを伝えるときにも、残高があるので関係は揺らがないといった具合です。
例えば、ある課長が部下に対して「報告の仕方がわかりやすくて助かっている」「資料の表現が整理されていて読みやすい」と、日常的に声をかけていたとします。そのうえで、「今後は、締め切りをもう少し前倒しできるとさらに良いね」と伝えると、部下は「自分の努力を認めてもらったうえでの助言だ」と感じ、素直に改善しようと思えるのです。もしこれが、褒めが全くなく注意だけを受け続けていたら、同じ言葉でも「また怒られた」と受け止められてしまうでしょう。
拙著では、この「5対1」という割合が様々な良い効果をもたらすことだけでなく、無理にこの割合を実現しようとする場合のリスクも紹介しています。とはいえ、まずは自分が、職場の関係者との間で「叱ることの5倍ホメているだろうか」と確認してみることが、自分のホメ方を客観的に理解し、改善していくための大きな一歩につながっていくでしょう。
「信頼関係」による効果の変化
次に紹介するのは、拙著の特徴の2つ目に紹介した、ホメ方の限界に関わる内容です。具体的には、相手との信頼関係が、ホメ言葉の効果に大きな影響を及ぼすという点です。
ある研究では、上司と部下の間に信頼関係を築けている場合には、部下の責任感や上司への信頼を高める効果が確認されました。一方で、信頼関係を築けていない場合には、この効果が得られなかったのです。その理由は、「信頼関係がないのに褒められた」という状況から、相手のホメ言葉の裏を探ってしまうという心理的なメカニズムが働いていると考えられています。
これは実験によって検証された結果ではあるものの、実際のビジネスの現場でも同様のことが想定できます。例えば、普段は業務報告を受けるだけだった上司から、ある日突然「君の頑張りには感心している」と声をかけられたとします。おそらく「急にどうしたんだろう」と身構えてしまい、言葉の真意を探ろうとするのではないでしょうか。
逆に、普段から相談に乗ってくれたり、困ったときにフォローしてくれる上司であれば、同じ一言が大きな安心感や励みにつながります。こうした結果は、ホメることを表面的に導入しても意味がなく、一朝一夕にうまくいくわけでもない、という現実を映していると捉えることもできます。日ごろからの継続的な関わりの中で、信頼という土台を形成してこそ、ホメの効果は最大化されるのです。
「感謝」の効果
最後に紹介するのは、「感謝」の効果です。実は、職場で相手に感謝することは、ホメるのと同様の効果があることが報告されているのです。これは、「どのようにホメるのが良いのか」あるいは「ホメ方をどう使い分ければよいのか」を紹介する研究知見でもあります。
ポジティブ・フィードバックという点で共通する「ホメる」と「感謝」ですが、その細部は異なります。ホメる場合は、相手の行為が「良かった」と直接評価を伝えることになりますが、感謝する場合は、相手の行為によって「助かった」という貢献度を伝えることになります。この特徴から、感謝は、ホメるよりも自然な形で、相手の行動へポジティブな評価を返すことができるのです。
こうした特徴は、具体的なホメ方の悩みに答えることができます。「どうホメて良いかわからない」場合は、まず相手に頼んだタスクや日常での所作に対して、感謝を示せばよいのです。「事前の相談通りに資料を仕上げてもらい、ありがとうございます」「先ほどの会議でフォローしてくれて嬉しかったです」など、相手の貢献に感謝できれば、両者の関係性や今後のパフォーマンスを大きく好転させていくでしょう。
また、ホメの使い分けという点についても、感謝は有効な選択肢です。特に、同僚や上司といった相手を「ホメる」のは気が引けるかもしれませんが、感謝を示すことには、そのハードルは大きく下がるでしょう。「資料の作成を手伝ってもらい、助かりました」「相談の時間を作っていただき感謝しております」など、より自然な流れで相手にポジティブな評価を返すことができるのです。
さらに、上記の内容を踏まえると、先ほどの「いきなりホメても効果が得られない」という限界にも答えることができます。つまり、信頼関係がまだ構築できていない相手に対しては、より自然だと感じられる「感謝」によって、ポジティブ・フィードバックを提供する選択肢があり得ます。日常的な関わりの中で関係性を良好なものにしていく、という漸次的な対応を念頭に、積極的に実践してみるのがよいでしょう。
おわりに
本コラムでは、「どうホメてよいのか」というホメ方の悩みについて、拙著が貢献しうるという点を紹介してきました。いわゆる人間関係に関する施策について、近道や伝家の宝刀が存在しないというのは、よくある話です。しかし、「ホメる」という行為について社会的な変化が大きく生じる今、その実践に悩むことも、いたって自然な反応です。できるホメ方が少しずつ実践され、その改善を通じて職場が段々と良好な雰囲気になっていけるように、拙著が微力ながらお役に立てれば嬉しく思います。
脚注
[1] 海外では「GAMAN」と表現して、日本固有の対処法と考えられています。職場での失敗を「相手のせいにしすぎる」リスクと合わせて、下記の当社レポートで紹介していますので、適宜ご参照ください;
なぜ「人のせい」と思い込むのか :ビジネスに潜む「基本的な帰属のエラー」を読み解く(セミナーレポート)
[2] 詳細は下記レポートをご参照ください;
「ほめること」の科学:心理学的アプローチから検討する(セミナーレポート)
[3] 詳細は下記リリースにて報告しております;
「『ほめること』の科学:心理学的アプローチから検討する」セミナーの内容がログミーで3回にわたり掲載されました
[4] 編集者の方に集計いただきました。この場を借りて、お礼申し上げます。
[5] 拙著で取り上げている文献については、書籍内の引用情報をご確認ください。
執筆者

黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了、筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程満期退学。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。