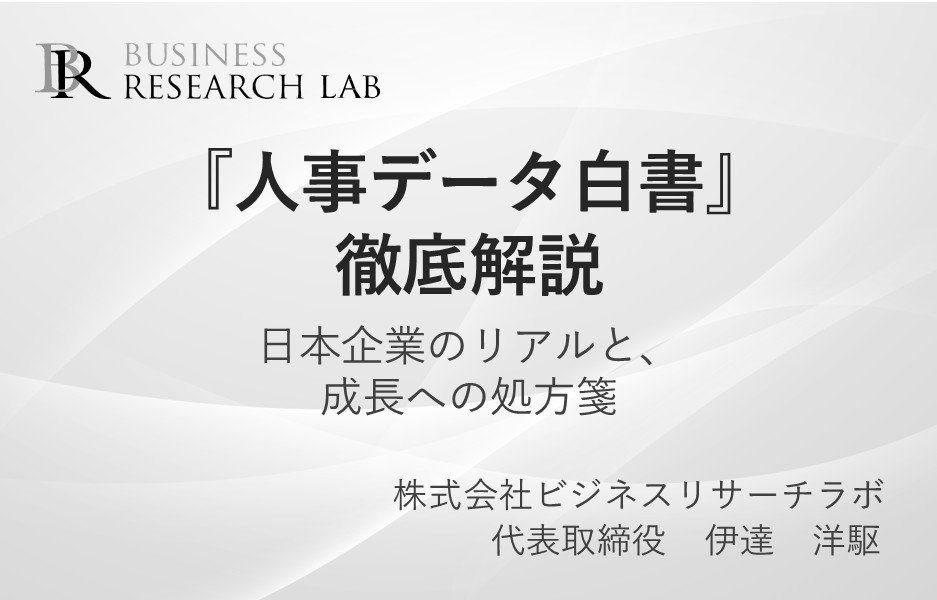2025年10月6日
『人事データ白書』徹底解説:日本企業のリアルと、成長への処方箋
私たちビジネスリサーチラボは2025年8月に『人事データ白書』を公開しました。本調査は、現代の企業経営において重要性を増す人事データの活用について、全国の人事担当者から寄せられた回答に基づいて、その実態を分析したものです。
少なからぬ企業が、経験や勘に依存した従来の人事から脱却し、客観的なデータに基づいた意思決定へと舵を切ろうと試みています。しかし、その意欲とは裏腹に、共通の課題に直面し、その歩みは必ずしも平坦なものではありません。私たちが白書を通じて描き出した日本企業の全体像は、一言で言えば「過渡期」という言葉に集約されます。
具体的には、給与計算や勤怠管理といった、いわば「守り」のデータ活用は多くの企業で定着し、業務効率化に貢献しています。しかし、そのデータを分析し、人材育成や組織開発、採用強化といった未来の競争力につなげる「攻め」の活用へと転換する段階で、壁に直面しているのです。データという新たな資源を前に、その価値を十分に引き出せずにいる。それが現在の姿と言えるでしょう。
本コラムの目的は、広大で多角的な分析が詰まった『人事データ白書』という地図を読み解くための、一つの手引きとなることです。皆さんが自社の現在地を把握し、未来に向けた一歩を構想するための情報として、白書のハイライトを紹介していきます。
データが映す、日本企業の現在地
調査対象となった企業全体の平均的な姿、すなわち多くの日本企業が共有する「現在地」から見ていきましょう。白書の第I部では、人事データ活用の全体的な傾向を明らかにしています。
データから見える風景は、活用の目的によって濃淡があることを示しています。基盤となるシステムの導入状況を見ると、「給与計算システム」の導入率は90.1%、「勤怠管理システム」は82.5%に達しており、労務管理を中心とした「守り」の業務基盤は、ほとんどの企業で確立されていると言えます。これは、正確性が求められる定型業務の効率化という目的においては、データ活用が浸透し、その価値が認められていることの証拠です。
一方で、収集したデータを多角的に分析し、戦略的な意思決定に活かす「攻め」の活用を支える「BI/分析ツール」の導入率は30.7%に留まります。この「守り」と「攻め」の間に存在するギャップが、「過渡期」という現状を象徴しています。データという原材料は手元にありながら、それを価値ある知見へと加工するための道具が、まだ多くの組織に行き渡っていません。
なぜ「攻め」への転換が十分に進まないのでしょうか。その根底にある障壁を、白書は示しています。データ活用を阻む最大の課題として、実に74.6%もの企業が「分析に必要な人材・スキルの不足」を挙げました。これは、ツールを導入するだけでは越えられない、より本質的な問題を提起しています。データを扱える人材がいない、あるいは育成できていないという現実が、多くの企業の挑戦を阻んでいるのです。
組織内部の力学もこの状況に影響を与えています。経営層の54.1%、人事部門の54.4%がデータ活用に高い意欲を示しており、トップと人事の方向性は一致しているように見えます。しかし、その一方で、人事担当者の約3割は、自社の人事以外の管理職が「データよりも経験や勘を重視する傾向が強い」と認識しています。推進しようとする力と、従来の手法を重視する文化との間に存在する温度差が、組織全体としての歩みを遅らせる一因となっているのかもしれません。
この「過渡期」の風景は、皆さんの組織の状況とどの程度重なるでしょうか。白書の第1章では、本コラムで触れた項目の他にも、データガバナンスの整備状況から担当者が持つべきスキルレベル、結果の共有体制に至るまで、自社の立ち位置を多角的に見渡すための詳細なデータを提供しています。
多様な取り組みの発見
データ活用への道のりは、一本道ではありません。企業が置かれた状況や事業環境によって、その進め方や注力する領域は異なります。白書では、企業の属性別にデータをクロス集計することで、その多様なアプローチを明らかにしました。画一的な正解を求めるのではなく、他社の取り組みから自社の戦略を相対化する視点を提供します。
企業の「規模」は、データ活用の進展を示す一つの指標となります。従業員規模が大きくなるにつれて、人事機能そのものが専門化していく様子が見て取れます。例えば、「専任の人事部門がある」企業の割合は、従業員500人以上の規模で76.5%に達します。この専門化と並行して、データ活用の重心も「守り」から「攻め」へと移行していきます。5,000人以上の企業では、「組織サーベイ・エンゲージメント調査」の結果を分析までしている割合が60.6%にのぼり、組織全体の健全性をデータで把握しようとする動きが活発化します。
「業種」による違いも顕著です。それぞれの業界が直面する固有の課題が、データ活用の方向性を定めています。例えば、変化の速い「情報通信業」では、戦略的な人材配置や育成を企図した「タレントマネジメントシステム」の導入率が74.3%と他をリードしており、人材という経営資源の価値を最大化しようとする意志が見えます。一方で、人材確保に強い課題感を抱える「運送・輸送業」では、今後の強化領域として「離職予測と離職防止」(62.5%)や「採用の高度化」(62.5%)へのニーズが突出して高く、事業継続の根幹をなす課題にデータで対処しようとする切実な姿がうかがえます。
「人事体制」もまた、データ活用の進展度を左右する要因です。「専任の人事部門がある」企業は、「タレントマネジメントシステム」の導入率が50.4%にのぼるのに対し、「総務などが人事を兼務している」企業では27.2%に留まります。人事機能の専門性が、戦略的なツールへの投資判断や、それを使いこなすための組織能力につながることが、データから示されました。
皆さんの企業と同じ規模、同じ業種の企業は、どのような課題を持ち、どこへ向かおうとしているのでしょうか。白書の第2章から第6章にかけては、多様な他社の取り組みから、自社の戦略を構想するためのヒントが得られるはずです。
活用の成否を分ける「構造」とは
データ活用を成功に導くためには、何が必要なのでしょうか。白書の第II部では、相関分析や重回帰分析といった、より高度な統計分析を用いることで、その背景にあるメカニズムの解明を試みました。分析結果が示すのは、成功の鍵が単一の要素ではなく、複数の要因が相互に連携することで成り立つということです。
重回帰分析の結果、データ活用の成果と特に強く関連する3つの要因が特定されました。それは、「人事の分析スキル・知識」(β=.41)、「データ分析結果の共有・レポーティング」(β=.28)、「人事データ分析活用の目的の広さ」(β=.23)です。
この結果は、データ活用の成否を分けるのが、高価なシステムの有無といった技術的な問題以上に、「人」の能力、「仕組み」の設計、「目的」の明確さにあることを示唆しています。優れた分析スキルがデータを価値ある知見に変え、共有と対話の仕組みがその知見を組織の行動へとつなげ、明確な目的意識が全ての活動に一貫した方向性を与えるのです。
これらの活動を支える土台として、「組織文化」の重要性も浮かび上がってきました。分析の結果、「従業員参加型のマネジメントスタイル」はデータ活用の成果と正の関連(β=.12)を、逆に「経営層の一方的な意思決定」は負の関連(β=-.09)を持つことが明らかになりました。これは、トップダウンで一方的に物事が決まる組織よりも、従業員の声を尊重し、データに基づいた「対話」を許容する文化を持つ企業の方が、データ活用が成功しやすいことを意味しています。
データ活用の推進を阻む「見えざる壁」の正体も見えてきました。探索的構造方程式モデリング(ESEM)という手法を用いた分析では、データ活用への懐疑的な見方や変化への抵抗を統合した「抵抗感」という因子が抽出されました。そして、この「抵抗感」は、「一方的なトップダウン文化」と強く関連していることが分かったのです。技術導入以前の、組織の風通しやコミュニケーションのあり方といった組織風土が、大きな障壁となっている可能性が示唆されます。
皆さんの組織には、データを価値あるものに変えるためのスキル、仕組み、文化が備わっているでしょうか。白書の第7章から第9章では、これらの成功のメカニズムを深く多角的に解き明かしています。
自社のタイプを知り、次の一歩を踏み出す
本白書の分析の集大成として、潜在プロフィール分析という手法を用い、人事データ活用への企業の取り組み方を4つの特徴的なタイプに分類しました。これは、読者の皆さんが自社を客観的に位置づけ、次に取るべき行動を構想するための実践的なフレームワークとなります。
皆さんの会社はどのタイプに当てはまるでしょうか。それぞれの特徴を簡潔に紹介します。
第一に、最も多くの企業が属するのが「未活用タイプ」(42.1%)です。データ活用への関心も取り組みも低調で、まさに「黎明期」にあります。第二は「抵抗模索タイプ」(19.3%)で、意欲はあるものの組織内の抵抗やスキル不足に直面している「葛藤期」の状態です。第三は「積極活用タイプ」(21.1%)で、組織的な抵抗が少なく、安定的にデータ活用を実践している「実践期」の企業群です。第四は、少数派ながら注目すべき「抵抗積極タイプ」(8.5%)です。強い推進力と、それに対する組織からの強い抵抗が激しく衝突する中で、高い成果を上げている「変革期」の企業群と言えます。
これらのタイプは、それぞれが直面する課題や、次に目指すべき方向性が異なります。白書では、各タイプに向けた「処方箋」を提示しています。
例えば、「未活用タイプ」に属する企業にとっては、大規模なシステム投資の前に、経営層を巻き込んで「何のためにデータ活用を行うのか」という目的を共有し、成果が見えやすい身近な課題から「スモールスタート」を切ることが有効です。一方、意欲と抵抗の板挟みにあう「抵抗模索タイプ」は、内部の力だけで壁を越えるのが難しい場合があります。他社の成功事例や客観的なROIのロジックを「外部の知見」を借りて構築し、抵抗勢力を説得するための材料とすることが求められます。
安定的に実践を進める「積極活用タイプ」は、現状に満足せず、データ活用を事業戦略と結びつけて、「事業貢献」を可視化することで、さらなる飛躍を目指すことができます。そして、大きな軋轢の中で変革を進める「抵抗積極タイプ」は、そのエネルギーを一方的な推進力としてだけでなく、抵抗勢力をも巻き込んだ「対話による文化醸成」へと転換していくことが、持続的な成長の鍵となります。
皆さんの企業は4つのタイプのうち、どこに当てはまるでしょうか。白書の第10章では、各タイプが直面する課題や持つべきスキル、今後の展望を検討しており、自社の状況に応じた行動計画を描くための情報が満載です。
白書を手に、自社の実践へ
本コラムでは、『人事データ白書』の主要な分析結果を概観してきました。白書が示すのは、データ活用に唯一の正解はなく、各企業が自らの置かれた状況を理解し、試行錯誤を重ねながら自社ならではのやり方を見出していく必要があるという事実です。その意味で、本白書は完成された「答えの書」ではなく、皆さんが自社の課題と向き合い、未来を構想するための「思考の素材」を提供することを目的としています。
人事データ活用は、技術導入のプロジェクトではありません。それは、組織の文化や意思決定のあり方を問い直し、従業員一人ひとりと向き合う、経営の活動です。データは、時に厳しい現実を突きつけますが、それは同時に、これまで見過ごされてきた課題に光を当て、組織をより良い方向へと導くための機会でもあります。
ぜひ『人事データ白書』を手に取り、皆さんの組織ならではのデータ活用の物語を紡ぎ始めてください。この白書が、その実践の助けとなることを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。