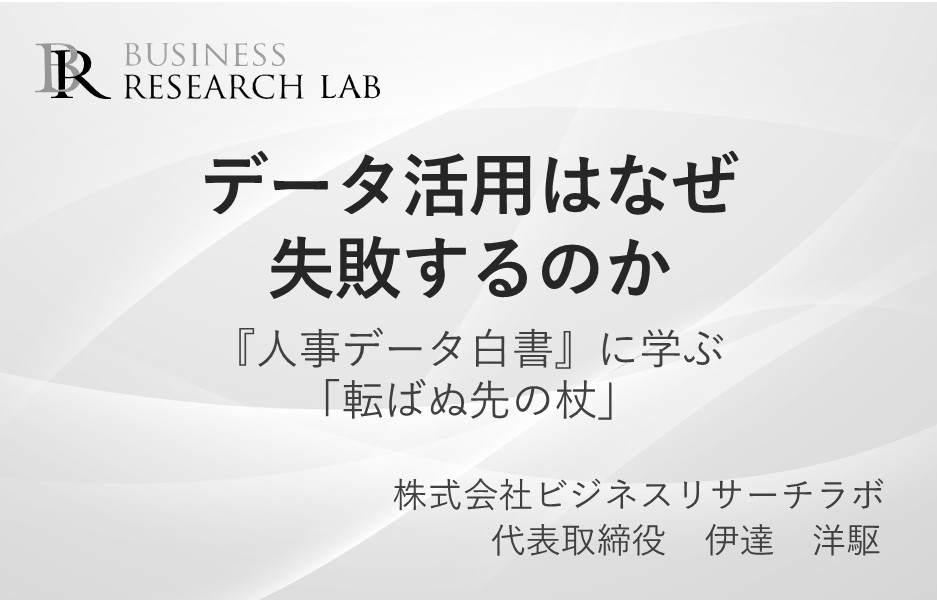2025年10月3日
データ活用はなぜ失敗するのか:『人事データ白書』に学ぶ「転ばぬ先の杖」
私たちビジネスリサーチラボは『人事データ白書』を公開しました。本調査は、全国の人事担当者の皆様から寄せられた回答データに基づき、現代の日本企業における人事データ活用の実態と構造を多角的に分析したものです。
近年、人事領域におけるデータ活用の重要性は広く認識され、多くの企業がその導入と実践にエネルギーを投じています。しかし、その理想とは裏腹に、現場からは「高価なシステムを導入したが、結局使われずに形骸化してしまった」「丹念に作成した分析レポートが、誰にも読まれることなく共有フォルダに眠っている」「良かれと思って導入した施策が、かえって現場の反発を招いてしまった」といった声が少なくない頻度で聞こえてきます。データ活用への期待が高まる一方で、なぜその実践は「失敗」に終わってしまうのでしょうか。
本コラムでは、あえてデータ活用の「成功」事例ではなく、その裏側にある「失敗」の側面に光を当てたいと思います。失敗の構造を深く理解することは、成功へと至る道筋を示すからです。幸いにも、今回の白書では、多くの人事担当者から、その経験に基づく失敗談が寄せられました。
白書の付録2に収録されたこれらの生々しい「失敗の物語」を道しるべとして、その背景に潜む構造的な問題を、白書本編の統計データと共に解き明かしていきます。本コラムが目指すのは、他社の経験から学び、自社の取り組みにおける「転ばぬ先の杖」を提供することにあります。
「良かれ」が「仇」となる
データ活用は、多くの場合、組織をより良くしたいという善意から始まります。しかし、その善意が、意図せざる結果を招き、組織に新たな問題を生み出してしまうことがあります。白書に寄せられた失敗事例を分析すると、その悲劇は主に3つに分類することができます。
第一の悲劇は、「透明性」が「監視」へと変質してしまうケースです。データを活用して組織の状況を可視化することは、問題発見や公正な意思決定の第一歩です。しかし、その運用を誤れば、データは従業員を管理し、統制するための道具となり得ます。ある企業では、「残業時間を可視化したところ、残業が少ない従業員に対して『もっと働かせるべきだ』という圧力が生まれ、結果的に労働強化につながってしまった」という本末転倒な事態が報告されました。また、別の企業からは、「健康状態に懸念があるとシステムに入力すると、上司から修正を迫られる」という、従業員の心理的安全性を脅かす事例も寄せられました。
このような失敗の根底には、組織の文化的な問題が存在します。白書の分析によれば、従業員の声を軽視する「トップダウン文化」は、データ活用の成果と負の相関関係(r=-.34)にあります。対話の文化が未成熟な組織では、データという客観的な情報が、従業員を理解するためではなく、一方的に管理するための根拠として利用されかねません。白書では71%以上の企業が「プライバシーやセキュリティへの懸念」をデータ活用の課題として認識しており、この問題が多くの組織にとって構造的な課題であることが示唆されます。
第二の悲劇は、「客観性」が「非人間性」に変わるときです。データが示す事実は、経験や勘に頼った意思決定の偏りを是正する力を持っています。しかし、その客観性を過信するあまり、数字に表れない文脈や人間的な要素を無視してしまうと、組織に混乱をもたらします。「データだけを根拠にした異動が実行され、現場の業務実態や人間関係を考慮しなかったために、かえって生産性が低下した」「数字で測定できる成果ばかりが評価され、チームへの貢献といった目に見えない働きが軽視された結果、従業員のエンゲージメントが低下した」といった声は、その典型です。
この問題は、データと現場の知見との断絶から生まれます。白書の調査では、約3割の経営層や管理職が「データよりも経験や勘を重視する傾向が強い」と人事担当者から認識されていることがわかっています。これを単なる変化への抵抗と片付けるべきではありません。むしろ、複雑な現場の状況を理解し、個別性の高い事象に対応してきた彼ら彼女らの専門的な知見が、データ活用プロセスから排除されていることへの警鐘と捉えるべきでしょう。文脈を無視した数字は、時に現実を歪めてしまいます。
第三の悲劇は、「投資」が「浪費」に終わるケースです。データ活用を推進するために、多くの企業がシステム導入やデータ収集に多額の投資を行います。しかし、その投資が成果に結びつかないまま、コストだけが積み重なっていく事例も後を絶ちません。ある企業では、「数千人の従業員を対象に何年もアンケートを実施したが、集まったデータをどう扱えば良いかわからず、当たり障りのないレポートをまとめるだけに終わり、成果が出ないままプロジェクトが廃止に至った」と言います。また、「高機能なタレントマネジメントシステムを導入したにもかかわらず、現場は従来のアナログな業務フローを変えられず、宝の持ち腐れになっている」という声も聞かれました。
これらの失敗は、白書で最大の課題として挙げられた「分析に必要な人材・スキルの不足」(74.6%)や、「具体的な活用イメージの欠如」(70.5%)が招く帰結と言えます。何を達成したいのかという目的が明確でないまま、「データを活用すること」自体が目的化し、手段の導入が先行してしまう。その結果、活用されないデータとシステムだけが残るという、避けるべき状況に陥ってしまうのです。
なぜ悲劇は繰り返されるのか
先ほど紹介した個別の失敗事例は、それぞれ異なる表情を見せながらも、その根底には共通する問題を抱えています。なぜ、これらの悲劇は多くの組織で繰り返されてしまうのでしょうか。そのメカニズムを、白書の統計分析(相関分析、重回帰分析、ESEM)の結果を用いて掘り下げていきます。
第一の構造的問題は、組織内における信頼関係の不足です。データ活用が成功するためには、従業員が安心してデータを提供し、経営層や管理職がそのデータに基づいて建設的な対話を行うという、信頼に基づいた関係性が求められます。
白書の重回帰分析は、その事実を示しています。「従業員参加型のマネジメントスタイル」がデータ活用の成果と統計的に有意な正の関連(β=.12)を持つのに対し、「経営層の一方的な意思決定」は負の関連(β=-.09)を示しました。従業員の声を尊重し、対話を通じて意思決定を行う文化が、データ活用の成否を分けるのです。先ほど見た失敗事例の多くは、この信頼という土壌が十分に耕されていない土地で、無理にデータ活用という作物を育てようとした結果、枯れてしまったものと解釈することができます。
第二に、目的の不在という問題が挙げられます。何のためにデータ活用を行うのかという目的意識がなければ、どのような取り組みも迷走します。
重回帰分析の結果、「人事データ分析活用の目的の広さ」が成果実感と統計的に有意な正の関連(β=.23)を持っていたことは、この点を裏付けています。「離職率を改善したい」「次世代リーダーを育成したい」といった経営課題に紐づいていないデータ活用は、情報の収集に終わり、具体的なアクションにつながりません。目的がなければ、どのようなデータを集めるべきか、どのように分析すべきか、そして何をもって成功と見なすのかという一連のプロセスに一貫性が生まれず、先ほど見たように、多大な投資が浪費に終わるリスクを高めます。
第三に、能力の断絶という問題です。データ活用を成果に結びつけるには、二つの異なる能力が必要です。一つは、データの中から意味のある知見を抽出する「分析能力」。もう一つは、その知見を組織の行動へとつなげる「展開能力」です。
重回帰分析は、データ活用の成果実感と強く関連する要因として、「人事の分析スキル・知識」(β=.41)と「データ分析結果の共有・レポーティング」(β=.28)の二つを特定しました。この結果が示すのは、分析能力と展開能力、その両輪が揃うことでデータ活用は推進力を得るというものです。多くの失敗は、高度な分析を行っても、その結果が組織内で共有されず、対話の材料とならない、あるいは、対話の場はあっても、そこに提示される分析の質が低いといったように、この二つの能力が断絶してしまっていることに起因します。
これらの構造的な問題を抱えたままでは、たとえ最新のシステムを導入したとしても、失敗は繰り返されます。データ活用の推進とは、技術の導入である以上に、組織の文化や能力を変革していく営みです。
抵抗積極タイプに学ぶ失敗との向き合い方
ここまで、データ活用の「失敗」とその構造について論じてきました。しかし、失敗は単に避けるべきネガティブな事象なのでしょうか。ここでは、視点を変え、失敗を組織の学習と成長の糧へと転換するための考え方を提示します。そのヒントは、白書の分析で浮かび上がってきた、ある特異な企業群の姿に隠されています。
白書の潜在プロフィール分析では、企業をデータ活用への姿勢に基づき4つのタイプに分類しました。その中で、全体の8.5%を占める少数派でありながら、注目すべき存在が「抵抗積極タイプ」です。このタイプは、データ活用を強力に推進しようとする「積極性」と、組織からの「抵抗感」が、共に突出して高いという、矛盾した特徴を持っています。通常、これほど強い逆風に晒されれば、取り組みは頓挫してしまうと考えるのが自然です。
しかし、データが示した現実は、その直感を裏切ります。「抵抗積極タイプ」は、調査した10項目の成果すべてにおいて、「非常に良くなった」と回答した割合が他のどのタイプをも圧倒していました。例えば、「離職率」の改善については65.5%が、「人材育成の効果」については72.4%が「非常に良くなった」と回答しています。
なぜ、最も困難な状況に置かれながら、最も高い成果を手にすることができるのでしょうか。その逆説的な関係を解く鍵は、「失敗の質」にあります。彼ら彼女らが直面する強い「抵抗」は、見方を変えれば、質の高い「失敗」や「困難」の連続であると捉えることができます。このタイプの企業は、既存業務の効率化といったテーマに留まらず、評価制度の見直しや組織風土の改革といった、より組織の根幹に関わる領域、いわば「聖域」にまで踏み込んでいる可能性があります。だからこそ、既存の価値観や権力関係を揺るがすことになり、強い抵抗が生まれるのです。
そして、その高い壁を乗り越える過程が、組織と担当者を鍛え上げます。強い抵抗勢力を前にして、生半可な分析やロジックは通用しません。「なぜ、そのデータが必要なのか」「その施策にどれほどの投資対効果が見込めるのか」といった厳しい問いに、客観的なデータをもって粘り強く答え続ける必要があります。そのプロセス自体が、推進担当者の分析スキルや論理構築能力を磨き上げるのでしょう。
事実、白書のデータによれば、「抵抗積極タイプ」は「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合が69.0%にのぼり、他タイプを大きく引き離しています。逆境が、彼ら彼女らを優れた実践者へと育て上げているのです。
この「抵抗積極タイプ」の姿が私たちに示すのは、失敗を敗北として終わらせるのではなく、組織の現状を映し出す客観的なデータ、すなわち「エビデンス」として捉え、次なる一手への学習機会へと転換することの重要性です。彼ら彼女らが経験する「抵抗」や「失敗」は、組織がこれまで目を向けてこなかった課題や、思考の偏りを明らかにするフィードバックです。その意味で、彼ら彼女らが経験しているのは「創造的失敗」と呼べるものかもしれません。
「失敗」を「学び」に変えるために
本コラムを通じて、人事データ活用の失敗の背景にある構造と、その失敗を乗り越えるための視点について論じてきました。白書が描き出した日本企業の「過渡期」という姿は、多くの企業がデータ活用という未知の領域で試行錯誤と失敗を繰り返している「学習期間」に他なりません。
であるならば、私たちは失敗を過剰に恐れる必要はありません。重要なのは、失敗から学び、それを次のアクションへとつなげるサイクルを、組織としていかに回していくかです。一度の失敗で取り組みを止めてしまうのではなく、なぜ失敗したのかをデータに基づいて検討し、仮説を修正し、再び挑戦する。その粘り強いプロセスの中に、組織が成長する機会が宿っています。
その観点から、この度、私たちが公開した『人事データ白書』は、他社の成功事例を学ぶためのベンチマーク資料としてだけではなく、新たな価値を提供できると確信しています。白書には、成功の光だけでなく、多くの企業が経験した試行錯誤の影もまた、データとして記録されています。他社の多様な「失敗」とその「構造」を学ぶことで、自社が陥りがちな過ちを未然に防ぎ、あるいは既に経験した失敗の意味を再解釈し、次への教訓として活かすことができるはずです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。