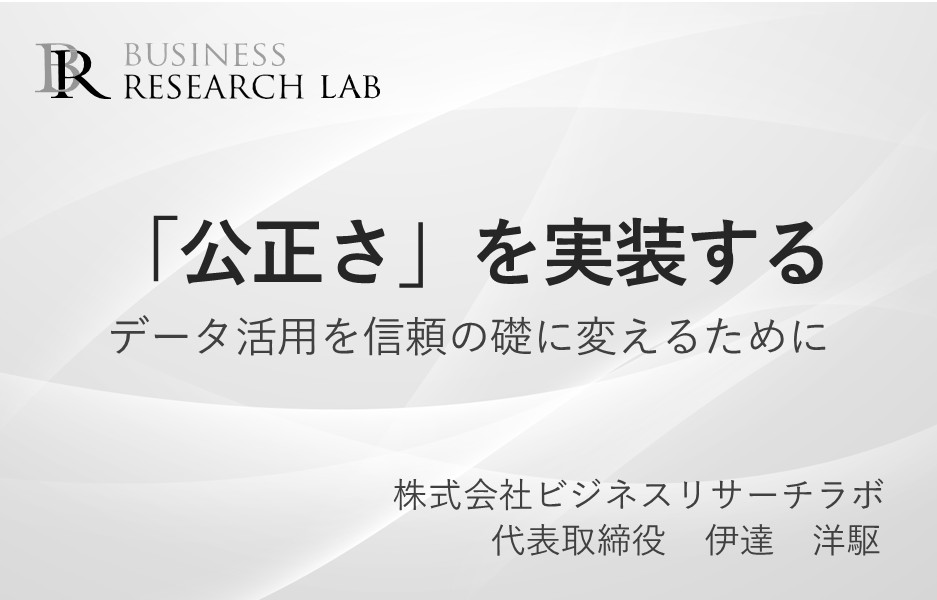2025年10月1日
「公正さ」を実装する:データ活用を信頼の礎に変えるために
データが人事課題を解決する。その輝かしい言葉とは裏腹に、人事データ活用の現場では、時折静かな断絶が生まれています。高機能なシステムが導入され、専門家が分析にあたっても、なぜか現場からは「数字だけでは実態は分からない」という反発が生まれ、従業員の間に漠然とした不信感が広がってしまうことがあります。実際に、アルゴリズムによる意思決定は、人間による決定と比較して公正さが低いと認識される場合があることが研究で示唆されています[1]。
このたび私たちビジネスリサーチラボが公開した『人事データ白書』は、全国の人事担当者の皆様から寄せられた声を通じて、この断絶の正体を検討する材料を提供してくれます。少なからぬ企業が直面するこの「見えざる壁」の正体は、技術的な問題以上に、より人間的な側面にあるのかもしれません。それは、データ活用の「使われ方」に対する従業員の認識、すなわち「データは、私たちを公正に扱ってくれるのか」という問いです。
本コラムでは、この壁の正体を考える鍵として、「組織的公正(Organizational Justice)」という概念に光を当てたいと思います。データ活用が従業員から「公正である」と認識されているかどうかが、その成否を分ける分岐点であるという仮説のもと、『人事データ白書』のデータを読み解きながら、そのメカニズムを探っていきます。
組織的公正とは何か
「組織的公正」とは、従業員が「自分は組織から公正に扱われている」と感じる主観的な認識を指します。この公正さへの信頼は、従業員のエンゲージメントや組織へのコミットメント、ひいては協力的な行動を引き出すことにつながります。この組織的公正は、性質の異なる三つの側面から構成されていることが知られています[2]。人事データ活用の文脈において、これら三つの「公正さ」が何を意味するのかを考えてみましょう。
第一に、「分配的公正」があります。これは、評価、昇進、報酬といった資源配分の「結果」が公平であるか、という認識に関わる公正さです。データ活用においては、アルゴリズムによって導き出された評価や処遇の決定が、従業員の貢献度や実績に照らして妥当なものか、あるいは特定の属性を持つ従業員に不利益な結果をもたらしていないか、といった点が問われるでしょう。たとえ客観的なデータに基づいていたとしても、その結果が従業員の納得感から乖離していれば、分配的な不公正感が生まれることになります。
第二に、「手続き的公正」です。これは、意思決定の「プロセス」が公正であるかという認識です。データの収集方法や分析基準は透明性が高く、一貫して適用されているか。従業員は、自らに関するデータの扱いや、それに基づく意思決定のプロセスに対して、意見を表明する機会を与えられているか。結果に不満があったとしても、その決定に至るプロセスが公正であると認識されれば、従業員はその決定を受け入れやすくなることが多くの研究で示されています[3]。データ活用において、この手続き的公正は重要な意味を持ちます。
第三に、「相互作用的公正」です。これは、意思決定のプロセスにおいて、権威を持つ人物(上司や人事担当者など)から、従業員がどのように扱われたかという、コミュニケーションの質に関する公正さです。具体的には、敬意のこもった丁寧な扱いを受ける「対人的公正」と、意思決定の理由について十分な説明を受ける「情報的公正」の二つに分けられます[4]。データ分析の結果を従業員に伝える際、一方的に事実を突きつけるのではなく、その背景や意味合いを真摯に説明し、個人の尊厳を尊重する姿勢が示されているか。この相互作用的公正が損なわれると、従業員は組織から軽んじられていると感じ、不信感を抱くことになります。
これら三つの公正さは、互いに独立しているわけではなく、関連し合っています。データ活用という新しい取り組みが組織に根付くためには、この三つの「公正さ」がバランスよく担保され、従業員からの信頼を勝ち得ることが求められます。逆に、一つでも欠けてしまえば、データは客観性を装った「管理・監視のための道具」へと姿を変え、組織内に新たな不信の種を蒔くことになるでしょう。
組織的公正をめぐる現在地
現実の組織において、これら三つの公正さはどのように認識されているのでしょうか。『人事データ白書』のデータは、多くの企業が組織的公正を確保する上で、様々な課題に直面している可能性を示唆しています。
初めに、「分配的公正」に関する認識から見ていきましょう。データ活用によって、公正な結果配分が実現しているという確信は、すべての企業で共有されているわけではないようです。
白書の類型分析によれば、データ活用が停滞している「未活用タイプ」の企業では、データ活用による「評価制度の精度や公正性」が「良くなった」と感じている割合は25.7%に留まり、「どちらとも言えない」が40.3%を占めています。データが必ずしも公正な結果に結びついていない、あるいはそう実感できていない従業員が多数存在することを示唆しています。
また、良かれと思って導入したデータの可視化が、意図せず公平さを欠いた結果を招く可能性も指摘されています。白書の自由記述に寄せられた事例には、「残業時間を可視化したところ、残業が少ない従業員に対して『もっと働かせるべきだ』という圧力が生まれ、労働強化につながってしまった」というエピソードがありました。これは、データという一面的な情報が文脈を無視して解釈され、一部の従業員に不利益をもたらすという、分配的公正における課題の一例と言えます。
続いて、「手続き的公正」については、より構造的な課題がデータから見えてきます。白書の重回帰分析は、示唆に富む一つの事実を明らかにしました。企業の「正社員確保の苦戦」という経営課題と最も強く関連していた要因は、採用手法や広報戦略の問題ではなく、「会社の意思決定では、経営層が一方的に決定し、従業員の声は反映されない」というトップダウン型の組織文化(β=.25)だったのです。
従業員の声を軽視し、意思決定のプロセスへの参加機会が限られている組織文化は、データ活用の成果が出にくいだけでなく、採用市場においても課題を抱えやすいという、厳しい現実を示唆しています。このトップダウン文化は、データ活用の「成果実感」とも負の相関(r=-.34)を示しており、従業員の参加を欠いたプロセスでは、データ活用の成功が遠のくことを裏付けています。
「相互作用的公正」の側面では、コミュニケーションのあり方が従業員の信頼に関わっている様子がうかがえます。白書の自由記述には、「健康状態に懸念があると入力すると上司から修正を迫られる」という、憂慮すべき事例が寄せられました。これは、データという客観的な事実の報告がためらわれるようなコミュニケーションであり、従業員の尊厳や対人的公正が軽視されかねない状況と言えます。このような環境で、従業員が正直なデータを提供し、組織を信頼することは難しいでしょう。
また、白書の類型分析からは、変革への意欲と組織の抵抗の狭間で揺れる「抵抗模索タイプ」において、人事担当者が自社の管理職を「データよりも経験や勘を重視する傾向が強い」と認識している割合が高いことも分かっています。データという客観的な事実を基にした対話が機能不全に陥り、上司から十分な説明(情報的公正)がなされないまま、一方的な判断が下されている状況を反映しているのかもしれません。
これらのデータが示す組織的公正をめぐる課題は、多くの企業が直面する「抵抗感」の一因となり、エンゲージメントや離職といった問題の背景にある可能性が考えられます。
信頼を築き、成果を出すには
データ活用が「不信の種」ではなく「公正な判断の礎」となるためには、組織は「公正さ」を理念として掲げるだけでなく、具体的な制度や行動へと実装していく必要があります。どうすれば組織的公正を確保できるのでしょうか。その処方箋のヒントもまた、『人事データ白書』のデータの中に隠されています。成功している企業群の取り組みは、公正さを実装するための方法を私たちに教えてくれます。
第一に重要なのが「手続き的公正」の確保、すなわち「透明性」と「参加」の設計です。その土台となるのが、厳格なデータガバナンスの構築です。
白書の分析によれば、データ活用で高い成果を上げている「積極活用タイプ」と「抵抗積極タイプ」では、「個人情報保護ポリシーの運用が徹底されている」割合が、それぞれ69.4%、72.4%と突出して高いことが明らかになりました。誰が、何の目的で、どのデータにアクセスできるのか。そのルールを明確化し、徹底して運用すること。このプロセスの透明性が、従業員の「自分のデータは公正に扱われる」という信頼の第一歩となります。
さらに、白書の重回帰分析は、データ活用の成果と「従業員参加型のマネジメントスタイル」(β=.12)との間に、統計的に有意な正の関連があることを示しました。分析の目的設定や施策立案のプロセスに、現場の従業員や管理職を積極的に巻き込むこと。当事者としての参加の機会が、プロセスの公正さへの納得感を高め、施策の実行力を向上させます。
第二に、「相互作用的公正」を確保するための「対話」と「説明責任」です。分析から得られた知見は、組織を動かす力を持つと同時に、使い方を誤れば人を傷つける刃にもなります。その力を建設的な方向へ導くのが、対話の文化です。
白書の相関分析によれば、「結果の共有レポーティング」という活動は、データ活用の成果と強い正の相関(r=.77)を示しました。さらにこの活動は、「経営層との意思疎通・協力関係の構築」(r=.66)といった、組織内の関係性の質を高めることにもつながっています。これは、レポーティングが一方的な情報伝達ではなく、異なる立場の人々が同じデータを見て議論するための「対話の場」として機能していることを意味します。
データは「管理の道具」ではなく、組織の課題を共に考えるための「対話の共通言語」である。この思想を組織に根付かせることが、相互作用的公正を育む上で必要です。そのためには、人事や経営層が、分析結果の意味や背景、それに基づく判断の理由を、従業員に対して丁寧に説明する責任を負わなければなりません。
第三に、これらのプロセスを通じて「分配的公正」を確保し、それを成果として証明することです。「人事データ分析活用の目的の広さ」が成果実感と正の関連(β=.23)を持つという分析結果は、データ活用の目的が「公正な評価制度の実現」や「個人の成長支援」といった、従業員にとっても有益なものであることを共有する必要性を示唆しています。
そして、その目的が絵に描いた餅で終わっていないことを、具体的な成果で示す必要があります。事実、「積極活用タイプ」や「抵抗積極タイプ」は、「評価制度の精度や公正性」や「報酬・給与設計の適正化」といった項目で、他のタイプを圧倒して成果を実感しているというデータが出ています。公正さを追求する真摯な取り組みが、実際に公正な結果として従業員に認識され、分配的公正への信頼を高めるという好循環が生まれる可能性があります。
白書で特に注目される少数派の「抵抗積極タイプ」は、これらの公正さを実装するプロセスを、ダイナミックに経験しているのかもしれません。組織内の強い抵抗に直面する中で、このタイプはデータ活用の正当性を証明するために、手続きの透明性を高め、粘り強い対話を重ねることを余儀なくされたはずです。その厳しいプロセスが、結果的に対話の質を磨き上げ、組織全体の公正さへの意識を高めて、他の追随を許さない高い成果へと結びついたのではないでしょうか。
データ活用は「組織の公正さ」を映す
本コラムを通じて、『人事データ白書』の結果を「組織的公正」という視点から読み解いてきました。その考察から導き出される結論は明快です。人事データ活用の成否を分けるのは、分析スキルの高度さやツールの性能もさることながら、その組織が「公正さ」という価値観をいかに大切にし、日々の活動の中に実装しているかでしょう。データ活用は、その組織が持つ「公正さ」のレベルを映し出す鏡であると言えます。
データは、客観性という力を持っています。その力は、使い方次第で、組織を豊かにする薬にも、人を傷つける毒にもなり得ます。客観性という名のもとに、これまで見過ごされてきた不公正を正し、組織内の対話を促し、信頼を醸成して、公正な組織を実現するための武器となる。その一方で、文脈を無視し、人間性への配慮を欠いたまま運用されれば、客観性は刃と化し、不公正を正当化し、従業員の心を傷つける凶器にもなります。
そのどちらの道を選ぶかは、データと向き合うリーダーや人事担当者一人ひとりの哲学と倫理観にかかっています。『人事データ白書』は、他社の動向を知るためのベンチマーク資料に留まりません。自社の「組織的公正」の現在地を問い直すための材料が詰まっています。『人事データ白書』をもとに、皆さんの組織がデータ活用を「信頼」と「成果」につなげるための、公正な組織へと変化するためのヒントとしてご活用いただければと思います。
脚注
[1] Newman, D. T., Fast, N. J., and Harmon, D. J. (2020). When algorithms think like managers: Perceptions of fairness in algorithmic and human-delegated decision-making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 160, 48-64.
[2] Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
[3] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. L. Erlbaum Associates.
[4] Bies, R. J., and Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, and M. H. Bazerman (Eds.), Research on Negotiation in Organizations. JAI Press.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。