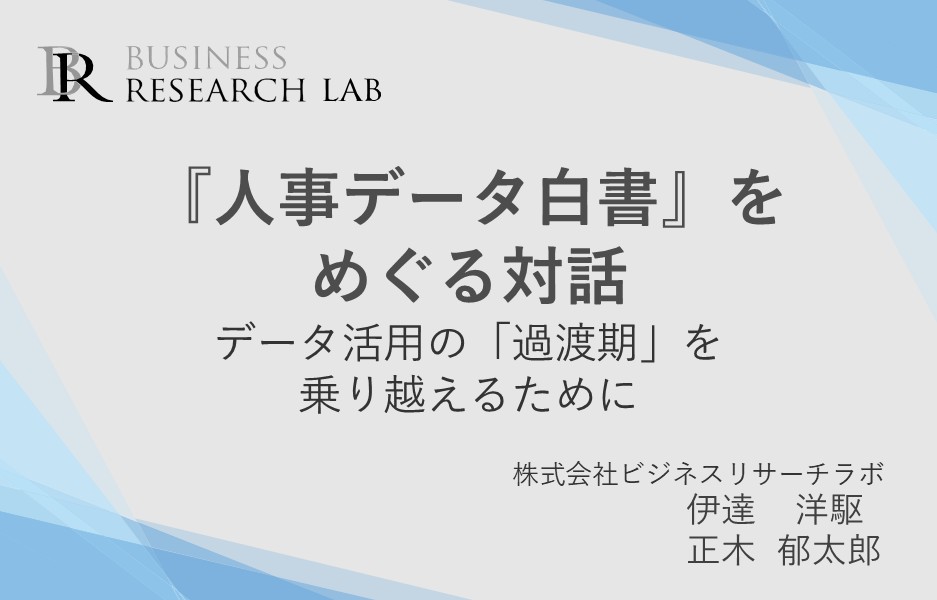2025年9月26日
『人事データ白書』をめぐる対話:データ活用の「過渡期」を乗り越えるために
近年、多くの企業経営において「人的資本経営」がテーマとなり、経験や勘に頼る従来の人事から、客観的なデータに基づいて意思決定を行う「ピープルアナリティクス」への移行が求められています。しかし、その重要性が認識される一方で、「何から手をつければ良いのか」「他社はどのレベルまで進んでいるのか」といった課題を抱える人事担当者は少なくありません。
こうした状況を踏まえ、株式会社ビジネスリサーチラボは全国の人事担当者を対象とした調査を実施し、その結果を『人事データ白書』として公開しました。本白書は、日本企業における人事データ活用の現在地を多角的に分析し、今後の指針となる示唆を提供することを目的としています。
今回、白書の公開を記念し、当社代表取締役の伊達洋駆と、当社テクニカルフェローの正木郁太郎が対談を行いました。対談では、白書が示す日本企業のデータ活用の「過渡期」という現状認識を起点に、データ活用を阻む組織内の壁や抵抗感の正体、それを乗り越えるために本当に必要なスキルや人材像、そして専門家たちがチームを組む際の難しさなど、様々なテーマへと議論を広げています。
「過渡期」をどう見るか
伊達:
今回の対談テーマは、当社が2025年8月に公開した『人事データ白書』です。この白書は、全国の人事担当者への調査に基づき、日本企業における人事データ活用の現在地を明らかにすることを目的としたものです。全体を通して見えてきたのは、多くの企業がデータ活用に乗り出しているものの、本格的な戦略活用には至っていない「過渡期」にある、という実態でした。
具体的には、給与計算や勤怠管理といった「守り」のデータ活用は9割以上の企業で定着している一方で、人材育成や組織開発といった「攻め」の領域での活用は、まだそこまで進んでいません。データという原石は集まりつつあるものの、それを磨く術が見つかっていない。そんな現状を「過渡期」と表現しています。
正木さんは様々な企業の人事データ分析に携わる中で、この全体感や現状をどのように見ていますか。
正木:
今回の白書を読んで、個人的には「かなりデータの利活用が進んだな」という印象を受けました。「過渡期」という表現も事実ではあると思いますが、同時に、この10年ほどで一気にデータ活用が進んだような感覚があります。
10年ほど前、ある企業の採用データを分析した際は、データがほとんど紙の状態で、まずは手作業で入力するところから始まりました。そもそもデータの整備が進んでおらず、さらには明確な仮説もない中で、何とか示唆を得ようと苦心したことを思い出します。そうした時から比べると、多様なデータがシステム上で揃っているだけでも、この10年で飛躍的に進歩したと感じます。
もちろん、すべての企業ではありませんが、人材育成やエンゲージメントといったテーマでデータを活用しようと試みる企業が現れていることも、大きな変化だと思います。
伊達:
確かに、私がこの仕事を始めた20年弱前を考えると、データは揃っていないのが当たり前でした。社内のどこかにあるかもしれないけれど、どこにあるか分からない。さらに、分析を前提に保管されていないため、単純な集計すら難しい状態でした。そこから考えると、タレントマネジメントシステムや採用管理システムといったHRテックの普及が、この10年における変化の要因かもしれません。
正木:
システムが急速に普及した一方で、それに人間がまだ追いついていないのが実態なのでしょう。様々なデータが集まったからこそ、「これをどう組み合わせれば何かに使えるのか」という新たな問いが生まれています。もともとデータがなければ、組み合わせるという発想もありませんでしたから、これは大いなる進歩です。
しかし、その一方でツールに振り回されてしまっている側面もあるように感じます。例えば、組織サーベイを導入したものの、自社の実態に合わない質問項目で構成されており、結果を見てもどう活用すれば良いか分からない、というケースです。これは、とりあえずツールを入れてみたものの、データの「質」が自社にフィットしていないという問題と言えます。急激に進歩した分、様々なものが追いついていないのが現状ではないでしょうか。
伊達:
20年ほど前は、特に大企業では人事管理システムや従業員意識調査を内製するケースがありました。独自のシステムを少しずつ修正しながら「秘伝のタレ」のように使っている企業があったように思います。
それに対して、ここ10年ほどでクラウド技術が進展し、セキュリティも確保できるようになったことで、大企業も外部のシステムやツールを積極的に活用するようになりました。人事業務そのものが、外部の知見に対して開かれるようになってきたことが、データが揃ってきた背景にあるのかもしれません。
一方でデータは溜まっても、それをどう活用すればいいか分からない。高性能なタレントマネジメントシステムを導入したものの、結局はこれまで通りの使い方しかできていない。技術的には様々なことが可能になっているにもかかわらず、人間側の活用能力が追いついていない。それが、この「過渡期」という状況の本質なのかもしれませんね。
抵抗感の正体とは
正木:
まさにその点が、データ活用に対する「抵抗感」にもつながっていると感じます。外部のベンダーが提供するツールは、いわば最大公約数的なものです。そのため、「うちの会社のカルチャーとはフィットしない」「自分たちの感覚と合わない」と感じる場面は少なくないはずです。結果として、「このデータは使い道がない」という認識につながり、抵抗感の一因となっているのではないでしょうか。
伊達:
多くのツール提供企業は、データ活用のモデルケースを提示していますが、それがすべての企業に当てはまるわけではありません。人と組織の課題は、一見すると似ているようで、各社で微妙に異なります。例えば「エンゲージメントの不足」という一つの現象を取っても、その意味するところや要因は企業ごとに違うはずです。
そうした自社固有の「ローカルな文脈」を無視して汎用的なツールを使おうとすると、「このシステムは使えない」「データを入力しても何もプラスになった気がしない」という不満が生まれ、社内的な抵抗感につながっていく、という構図はありそうです。
正木:
その壁を越えるのは、なかなか難しい問題です。ありもののツールを自社の文脈に翻訳して落とし込む、あるいは自社で起きている現象を一般的な概念や理論と結びつけて理解する。こうした作業を行うには、社内に推進力を持つ人物が必要ですし、社外の専門的な知見を借りる必要もあるでしょう。様々な知識と経験の組み合わせが求められる分、難易度が高い領域なのだと思います。
伊達:
データ活用は、まさに総合格闘技のようなものです。システムに保管されている定量データだけでなく、担当者が長年培ってきた経験則や、現場で語られるアイデアといった定性的な情報も、すべて重要な「データ」です。これらの多様なデータを総動員して仮説を立て、検証し、目の前の問題解決につなげていく。この一連のプロセスを回す必要があります。打撃だけ、あるいは寝技だけできても勝てないように、チームとして総合的な能力がなければ、どこかで壁にぶつかってしまうのでしょう。
正木:
ただ、過去と比べると明確に改善が進んだ側面もあります。それは、データ活用に取り組むことへの「大義名分」ができたことです。例えば「人的資本経営」というキーワードがあることで、「なぜそんなことをやるのか」という問いに対する説明が立ちやすくなりました。もちろん、それだけですべてが進むわけではありませんが、10年前、20年前に比べれば、経営者や人事担当者など、様々な人がこのテーマで動きやすい状況になっているのは間違いありません。
伊達:
大義名分、専門的に言えば「正統性」が確保されると、予算や人材も確保しやすくなります。活動を進めるための基盤は整いつつあるわけですね。その反面、いかんせん、やろうとしていること自体の難易度が高い。
そして、もう一つ興味深いのは、ニーズがあり、データも一部あり、分析できる人材も少しいる、というように、いくつかの要件が不完全に揃った状態で「とりあえず進めてしまう」ことのリスクです。もちろん、やらないよりはやった方が良いのですが、中途半端な状態で全社的に大きな取り組みをして失敗すると、「データ活用をやっても意味がなかった」という記憶が組織に刻み込まれてしまう可能性があります。
白書の自由記述にも、何千人ものデータを取ったものの、結局何も分からず、活用できなかったという失敗例が寄せられていました。こうした経験は、データ活用に対する後ろ向きな雰囲気を組織内に醸成してしまいます。
正木:
試行錯誤するにしても、最後までやり切ることが重要になりますね。例えば、大規模なサーベイを実施したのであれば、その結果を何らかの形でフィードバックし、次に何ができそうかを議論する。たとえ満点の解決策は出なかったとしても、やりっぱなしにしないことが求められます。
究極的には、心理学や社会学などで求められる調査倫理の話と同じに思えます。たとえば、調査は回答者や参加者に時間や心理的負担などの負荷をかける行為です。その負荷に見合うだけのものを返す責任がある、あるいは少なくともその負荷を認識しながら研究を行う必要がある、という基本的なリテラシーが、今後はより重要になってくるでしょう。
伊達:
もう一つ、抵抗感の背景には、既存の「人事と従業員の関係性」が反映されているように思います。従来から人事が従業員を管理・統制する姿勢で施策を進めてきた企業であれば、従業員はデータ活用を「また新たな監視や管理強化ではないか」と警戒するはずです。PCのログデータやアンケートの一つひとつが、自分たちを縛る道具になるのではないか、と。抵抗感の正体には、データ活用以前の、組織と従業員の信頼関係の問題が横たわっているのではないでしょうか。
正木:
その意味では、むしろ、データの活用目的やアクセス権限のルールなどを積極的に発信した方が、信頼関係を築きやすいかもしれません。ある企業では、データの活用目的や理念をまとめたHRポリシーを社外に公開したところ、結果的にその後のデータ活用が加速した、という事例もあります。自分たちが何を目指し、何を大切にしているのかという理念を示すことが、従業員の警戒感を和らげ、協力を得る上で有効なのだと思います。
データ活用に必要な「総合力」
伊達:
最近、AIの利活用方針を掲げる企業が増えてきています。AIの活用は、事実上、データ活用の話と深く関連する文脈ですから、今後は人事データの利活用に関する指針を策定する企業も増えていくと良いですね。
しかし、そこで問題になるのが「誰がデータ分析を担当するのか」です。大きな企業がデータ活用を始めるとき、純粋な解析の専門家が担当することがありますが、人事データをうまく分析できるかというと、必ずしもそうではありません。データの量が少なすぎると感じたり、そもそも何を分析すれば良いか分からなかったりと、苦労されているケースをよく見かけますし、相談を受けることもあります。
正木:
まさにその通りで、二極化する傾向がありますね。不安になって何もできなくなるか、逆に専門外であることに無自覚で、人事や組織の現場からすると的外れな分析に突き進んでしまうか。もし、どのような人材に任せれば良いかと問われれば、少し極端な言い方ですが、「理系出身だけれども、大学時代はそこそこ遊んでいた人」も良いかもしれません。
数字やPC操作は嫌いではないけれど、高度な分析技術に固執するより、手探りで色々と試してみる。自分に確固たる専門性がないからこそ、多様な人の意見に耳を傾け、情報を集めながら進めていける。そうしたタイプの方が、自分なりの信念や専門性を無理に違う領域にあてはめようとする、あるいはあてはめることを外部から求められる立場の方よりも、うまくいくし、ご本人の苦労も少ない可能性があるように思います。
伊達:
データ分析の専門性は、統計ソフトやプログラミング言語を使うため、分かりやすいものです。しかし、データ活用は分析スキルだけではどうにもなりません。もう一つ、重要でありながら見過ごされがちなスキルがあります。それが「測定」の知識です。
人と組織に関するデータは、自然に存在するわけではありません。何らかの方法で「測定」されて初めてデータになります。しかし、この測定、例えばアンケートの質問項目を作成するといった行為は、多変量解析のような分析作業と比べると、専門的な行為だと認識されにくい。その結果、きちんと測定されていないデータ、すなわち信頼性や妥当性の低いデータが分析対象となってしまい、多くの企業がそこでつまずいているように感じます。
正木:
測定というのは、「こういう現象を捉えるために、こういうデータを使おう」と紐づけるスキルとも言えますね。自分たちが知りたい抽象的な事柄を、アンケートの質問項目や、人の異動データといった具体的な指標に落とし込む。この、抽象と具体を往復する能力が求められるからこそ、難しいのでしょう。
伊達:
「構成概念」を測定する能力ですね。例えば、「エンゲージメント」や「コミュニケーション活性化」といった構成概念を、どのように数値化するか。この思考プロセスは、日常生活の感覚とは少し異なります。ここを疎かにすると、そもそも捉えたい現象を正しく捉えられていないデータで分析することになり、その結果から得られた示唆も、介入すべき対象も、すべてが的外れになってしまう危険性があります。
正木:
抽象的な概念と具体的な事象を行き来しながら理解できる人は、かなり限られているように感じます。キャリアの高い方でも、エンゲージメントやコミュニケーションといった言葉は使うものの、それが具体的に何を指しているのかが曖昧なケースはあります。そうした場合、私はまず「具体的に、どういう人やエピソードが思い浮かびますか」と問いかけ、そこから共通の理解を形成していくことから始めます。
中途半端に抽象的な用語を使うよりも、むしろ経験と勘をまっすぐ言葉にして「あの人は情に厚い」「自分が思ったことを素直に話し合っても怒られない、受け止められる人間関係を作りたい」といったように語る人の方が、よほど分かりやすく、人事データ分析の推進につながることさえあります。
伊達:
複数の類似した構成概念を知ることも、理解を深める上で有効かもしれません。「ワークエンゲージメント」しか知らない状態ではなく、「組織コミットメント」や「ジョブエンベデッドネス」といった類似概念を知ることで、それらの違いは何か、と区別する必要に迫られます。その違いを考えるとき、抽象的なレベルだけでは難しく、「具体的にどういう状態を指すのか」と考えざるを得なくなるはずです。周辺知識を広げることで、一つの概念への理解も深まっていくのではないでしょうか。
多様な知見をどう活かすか
伊達:
データ活用に必要なスキルが多岐にわたることを考えると、すべてを一人で担うのは困難です。そこで、様々な専門家を集めたチームで取り組むというアプローチも考えられます。実際に、機械学習の専門家、労務問題の専門家、現場をよく知る担当者などを集めた分析チームを組成している企業もあります。しかし、見聞きする範囲では、そうしたチームが必ずしもうまくいっているわけではないようです。これは、極度にダイバーシティが高いチームのマネジメントという、また別の難しさがあるからでしょうか。
正木:
そうしたチームが機能するために必要なことが、いくつかあると思います。一つは、メンバー一人ひとりが、自分の専門領域における利害をある程度は脇に置けること、つまり「健全な妥協」ができるかどうかです。例えば、研究者であれば「論文に書けるやり方でなければ絶対に嫌だ」と固執してしまうかもしれませんが、共同研究先の企業にはリソースの限界や独自にやりたいことがあるので、チームとして前に進めません。折衷案を作った方が、むしろ自分だけでは気づけなかった新しい発見もあるかもしれない、くらいの考え方がよいと思います。
二つ目は、チーム全員が、対象としているフィールド、つまり「生々しい現実」を共有することです。専門性が異なると、同じものを見ていても、見えているものが全く違います。まずは全員で現場を見学に行くなどして、自分たちが向き合っている現象について共通の認識を持つことが、対話の基盤となります。
三つ目は、チームとしてまとまるための経験を共にすることです。例えば、チームでまとめた分析結果を、上長や経営層に報告し、そこで様々なフィードバックを受ける。この人を説得するためには、どう伝えれば良いか。チームとして成功するためには何が必要か。そうした共通の目標に向かって共に戦う経験、あるいは共に叩かれる経験を通じて、専門家の集団が、一つの「チーム」になっていくのだと思います。
過渡期を乗り越えるために
伊達:
ここまで、データ活用の難しさについて議論してきましたが、最後に、今まさにこの過渡期で奮闘している人事担当者の方々へ、何かメッセージはありますか。
正木:
まずお伝えしたいのは、「確実に前に進んでいる」ということに自信を持っていただきたい、ということです。私の知る限りでも、10年前の状況から比べれば、はるかに進歩しています。様々な課題はあるにせよ、ここまで進めてこられたこと自体を、肯定的に捉えて良いのではないでしょうか。
伊達:
試行錯誤している人の数も、以前より格段に増えてきています。もはや、一人で悩む必要はないステージに来ていると感じます。社内だけでなく、社外の担当者同士で情報交換をしたり、つながりを持ったりすることが、そろそろ可能になってきているのではないでしょうか。悪戦苦闘している人は、孤立しない方が良いと思います。
正木:
自分が抱え込んでいる問題が、実は他の人から見れば、非常によくできているポイントだったりすることもあります。様々な立場の人と交流することで、自分の取り組みの価値や、少しの工夫で改善できる点に気づけるはずです。
伊達:
実際のところ、悩んでいる人ほど、きちんとできているケースが多いですよね。「この測定で本当に大丈夫だろうか」「この分析で良いのだろうか」と問題意識を持てている時点で、すでにある程度は調べているはずですから、致命的なミスはおかしていないことが多いものです。
正木:
もう一つは、経営層や人事の側が、「自分たちは何をしたいのか」「どういう組織を目指しているのか」というゴールを、分かりやすく示すことでしょうか。その目的がはっきりすれば、データ分析もそれに沿って進めやすくなりますし、従業員の協力も得やすくなるはずです。
伊達:
その目的を、途中で忘れないことも重要ですね。何年もデータ活用を進めているうちに、当初の目的が忘れられ、手段が目的化してしまうケースもあります。定期的に原点に立ち返り、再確認し続けることが大切だと感じます。
私からも一つ付け加えるならば、「任せすぎない」ということです。データ分析は専門性が高いのですが、それを理由に専門家に完全に任せてしまい、理解しようとすることを放棄してしまうと、どこかで大きな落とし穴にはまります。必ずしもすべてを深く理解する必要はありませんが、測定やデータの構造といった専門的な事柄についても、一定程度は理解しようとし続ける姿勢が、中長期的に見れば大きな差を生むのではないかと思います。
正木:
それは教える側の課題でもありますね。分析手法をどう現場で使えるか、どう伝えれば理解してもらえるか。我々のような専門家も、サイエンスコミュニケーションの観点から、伝え方を工夫し続けなければなりません。
簡単な分析手法を様々に組み合わせて多角的に見せるのか、あるいは高度な分析の本質を噛み砕いて説明するのか。いずれにせよ、究極的にはコミュニケーションの問題です。そして、その対話を通じて、データ活用に関わるすべての人々が少しずつ学び、成長していく。そうした地道なプロセスの先に、この「過渡期」を乗り越えた未来があるのだと思います。
対談者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。

正木郁太郎 株式会社ビジネスリサーチラボ テクニカルフェロー
東京女子大学現代教養学部心理・コミュニケーション学科心理学専攻専任講師。株式会社ビジネスリサーチラボ テクニカルフェロー。東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程修了。博士(社会心理学:東京大学)。組織のダイバーシティに関する研究を中心に、社会心理学や産業・組織心理学を主たる研究領域としており、企業や学校現場の問題関心と学術研究の橋渡しとなることを目指している。著書に『職場における性別ダイバーシティの心理的影響』(東京大学出版会)がある。