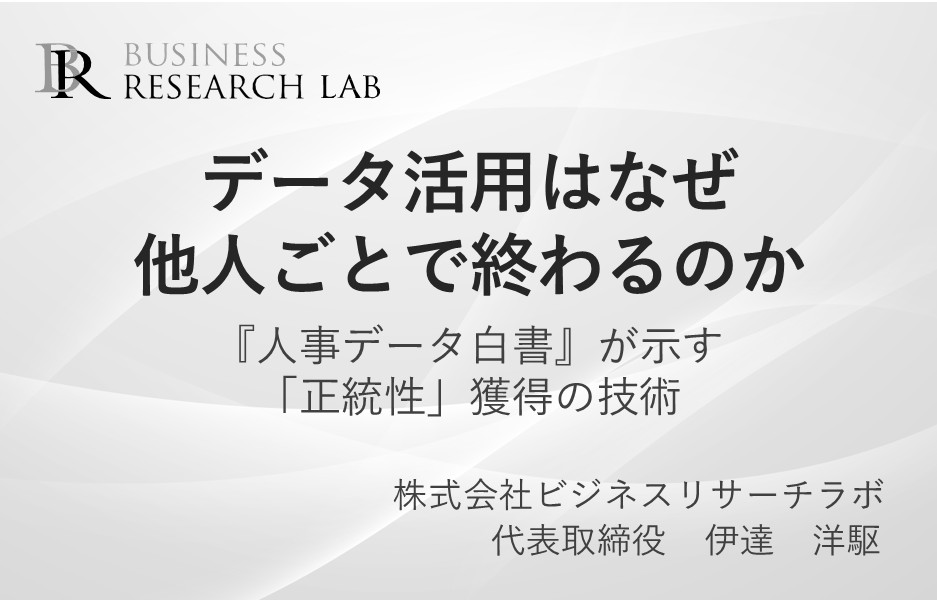2025年9月24日
データ活用はなぜ他人ごとで終わるのか:『人事データ白書』が示す「正統性」獲得の技術
私たちビジネスリサーチラボは、このたび『人事データ白書』を公開しました。本調査の実現にあたり、貴重な時間と知見をご提供くださった全国の人事担当者の皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。
白書が描き出した風景、それは一言で言えば「過渡期」です。多くの企業が高機能なシステムを導入し、専門人材を配置しようと試みながらも、その取り組みが一部の部署に留まり、組織全体へと広がらない。現場からは「自分たちの仕事とは関係ない」「数字だけでは実態は分からない」といった声が聞こえ、データ活用が「他人ごと化」してしまう。こうした壁に直面している企業は少なくないと考えられます。
白書が示すデータはこの状況を裏付けています。人事データ活用を阻む最大の課題として74.6%の企業が挙げたのは、「分析に必要な人材・スキルの不足」でした。それに次いで、「具体的な活用イメージの欠如」も70.5%の企業が課題として認識しています。これは、HRアナリティクスの導入・普及における主要な障壁として広く認識されているものです[1]。これはツールを使いこなせる人材がいないという問題に留まりません。たとえ専門家がいたとしても、その活動が組織の中で孤立し、現場の業務や意思決定と結びついていない。そうした断絶が、多くの組織で見られる状況です。
この問題の本質はどこにあるのでしょうか。技術やスキルの有無だけが原因なのでしょうか。私は、別の視点も必要だと考えています。検討すべき論点は、人事データ活用という新しい活動が、組織の中で「正しく、適切で、望ましいもの」として広く受け入れられているか、すなわち「組織の正統性(Organizational Legitimacy)」を獲得できているかという点にあると解釈できます。
本コラムでは、この「正統性」という概念を鍵として、データ活用が「他人ごと」で終わらず、組織の活動として定着するためのプロセスと条件を、『人事データ白書』のデータから探っていきます。
人事データ活用がまとうべき正統性
組織論において「正統性」とは、ある活動が、組織や社会を構成する人々の間で「当たり前で、正しく、良いこと」と見なされていることを指します。正統性を獲得した活動は、周囲からの支持や協力を得やすくなり、組織内に根付いていきます。逆に、どれだけ論理的に正しくても、正統性を得られなければ、その活動は「異物」として扱われ、やがて形骸化する可能性があります。
人事データ活用が組織に受け入れられるためには、次の3つの異なる正統性を、バランスよく獲得していくことが求められます[2]。
一つ目は、「実利的正統性(Pragmatic Legitimacy)」です。これは、「そのデータ活用は、私たち(現場や経営層)にとって、具体的で目に見える利益があるか」という問いに答えることで得られます。ROI(投資対効果)の高さや、業務効率化への貢献、コスト削減といった実利的な価値が、この正統性の源泉です。
白書のデータを見ると、多くの企業がこの実利的正統性を意識していることがわかります。データ活用の目的として「労務管理・人件費管理(コスト最適化など)」を挙げた企業が73.9%と最も高かった事実は、その一端を示しているでしょう。しかし、その一方で7割以上の企業が「ROIの不透明さ」を課題として挙げており、データ活用の「実利」を証明することに多くの企業が苦戦しているという現実も示唆されています。
二つ目は、「規範的正統性(Moral Legitimacy)」です。これは、「そのデータ活用は、倫理的・道徳的に見て『正しい』行いか」という問いに答えることで得られます。従業員のプライバシーは守られているか、評価や処遇は公正に行われているか、その活動は自社の理念や社会の価値観と整合しているか。こうした規範的な正しさが、従業員や社会からの信頼を得る上で求められます。
白書では、71%以上の企業が「プライバシーやセキュリティへの懸念」を課題として認識していることが示されました。さらに、自由記述の失敗事例に目を向けると、「健康状態に懸念があると入力すると上司から修正を迫られる」「残業時間の可視化が、逆に労働強化の圧力になった」といった記述が見られます。これらは、規範的正統性が一度損なわれると、データ活用が従業員の心理的安全性を脅かし、不信感を生む可能性を示唆しています。
三つ目は、「認知的正統性(Cognitive Legitimacy)」です。これは、「そのデータ活用は、もはや組織にとって『当たり前』で、疑う余地のないものか」という問いに答えることで獲得されます。業界の標準的な慣行として定着していたり、日常業務のプロセスに組み込まれていたりすることで、「なぜやるのか」を問うまでもなく、その活動が自然なものとして受け入れられている状態です。
白書のデータは、この認知的正統性の獲得が道半ばであることを示しています。「給与計算システム」の導入率が90.1%に達しているように、従来型の「守り」の業務は高い認知的正統性を獲得しつつあります。しかし、より戦略的な「攻め」の活用を支える「BI/分析ツール」の導入率は30.7%に留まります。また、本調査で特定された4つの企業タイプのうち、最も多くの割合を占めたのが、データ活用に低調な「未活用タイプ」(42.1%)であったという事実は、多くの企業にとって、人事データ活用がまだ「当たり前」の存在にはなっていない状況を示しています。
なぜ正統性が得られにくいのか
少なからぬ企業が、これら3つの正統性を獲得する道のりでつまずいています。推進者が直面する「抵抗」とは、突き詰めれば、データ活用が組織の中で正統性を得られていないことの現れに他なりません。白書のデータは、正統性が獲得されにくい典型的なパターンを明らかにしています。
第一に、「実利的正統性」の喪失です。これは、分析が現場や経営の具体的な利益に結びつかない、「分析のための分析」に陥ってしまうケースです。
白書の類型分析で特定された「抵抗模索タイプ」は、データ活用への意欲はあるものの、組織内の抵抗に直面している企業群ですが、このタイプがデータ活用によって得られた成果をどう感じているかを見ると、その一因が推察できます。「離職率」や「従業員エンゲージメント」といった多くの成果項目で、「どちらとも言えない」という回答が半数近くを占めているのです。これは、具体的な成功体験、すなわち「実利」を組織に示すことができていない実態を示唆しています。
自由記述にあった「数千人の従業員に何年もアンケートを実施したが、当たり障りのないレポートをまとめるだけに終わり、成果が出ないまま廃止に至った」というエピソードは、実利的正統性を証明できなかった一例と言えるでしょう。
第二に、「規範的正統性」の崩壊です。これは、データが従業員を公正に処遇するためのものではなく、一方的に管理・監視するためのツールとして使われ、組織の信頼を損なうケースです。この問題には、組織の意思決定の文化が関連していると考えられます。
白書の重回帰分析は、「会社の意思決定では、経営層が一方的に決定し、従業員の声は反映されない」というトップダウン文化が、データ活用の成果と統計的に有意な負の相関(β=-.09)を持つことを明らかにしました。相関分析においても、この文化は成果と負の相関(r=-.34)を示しています。
プロセスの公正さ、すなわち規範性が確保されない環境では、データ活用が成功しにくい可能性が示唆されます。意思決定のプロセスが公正であると従業員に認識されなければ、たとえその結果が客観的なデータに基づいていたとしても、受け入れられにくいことが知られています[3]。従業員の声を軽視する文化の下では、データは経営層の決定を後付けで正当化する道具となり、従業員の間に不信と諦めが広がる。その結果、協力が得られなくなり、活動全体が停滞する一因となり得ます。
第三に、「認知的正統性」の不在です。これは、データ活用が「一部の専門家がやる特殊なこと」という認識に留まり、組織全体の「当たり前」の活動へと浸透しないケースです。
この背景の一つには、白書で最大の課題として挙げられた「分析に必要な人材・スキルの不足」があります。人事担当者自身のスキル評価を見ても、「統計学に基づく統計解析の知識」が「ないと思う」と回答した割合は18.7%にのぼります。専門知識を持つ人材が限られている状況が、データ活用を一部の専門家の活動に留め、組織的な文化として根付くことを妨げている可能性があります。
また、組織構造もこの問題に影響します。「未活用タイプ」では、「専任の人事部門がある」割合が51.4%に留まり、「総務や経営企画などの部門が人事を兼務している」が37.5%を占めていました。人事機能の専門化の遅れが、データ活用を「当たり前」の業務として位置づける上での障壁となっている構造が見て取れます。
「正統性」を組織に根付かせる技術
どうすればデータ活用は「他人ごと」の壁を越え、組織に根付く「正統性」を獲得できるのでしょうか。そのヒントは、困難な状況にありながら、高い成果を上げている企業群の姿に見出すことができます。白書で特定された、全体の8.5%を占める少数派、「抵抗積極タイプ」です。このタイプの行動からは、3つの正統性を獲得するための技術が示唆されます。
第一の技術は、「小さな成功」で実利的正統性を証明することです。全社的な改革を最初から目指すのではなく、特定の部門や課題に的を絞り、そこで具体的かつ目に見える成果を出す。この成功体験が、データ活用の「実利」を組織に示す手段となり得ます。
白書のデータはこの点の重要性を示唆しています。「抵抗積極タイプ」は、データ活用による「離職率の改善」について、65.5%が「非常に良くなった」と回答しています。これは、組織的な抵抗が少なく、円滑に活用が進んでいるはずの「積極活用タイプ」の10.0%という数値を大きく上回ります。大きな抵抗に直面する中で、経営インパクトの大きい課題で明確な成果を出すことが、データ活用の価値を組織に認めさせる一つの方法だったと考えられます。
第二の技術は、「対話」と「ガバナンス」で規範的正統性を構築することです。データは、一方的に用いるのではなく、組織の対話を促す共通言語として活用する必要があります。
分析の目的やプロセスを透明化し、現場や従業員と共に結果を解釈し、次のアクションを考える。白書の相関分析の結果、「結果の共有レポーティング」という対話の仕組みが、「経営層との意思疎通・協力関係の構築」(r=.66)や「部門間・従業員間のコミュニケーションの活性化」(r=.66)といった成果と強い正の相関を持つことは、この対話のプロセスが信頼の醸成に関連することを示しています。
重回帰分析においても、「従業員参加型のマネジメントスタイル」が成果と正の関連(β=.12)を示したことは、ボトムアップの対話を尊重する文化の重要性を裏付けています。そして、この対話の基盤となるのが、厳格なデータガバナンスです。「抵抗積極タイプ」と「積極活用タイプ」では、「個人情報保護ポリシー」の運用が徹底されている割合が、それぞれ72.4%、69.4%と高い水準にありました。「データは公正に扱われる」という安心感を組織に示すことが、規範的正統性を築く上での第一歩です。
第三の技術は、「翻訳」と「教育」で認知的正統性を浸透させることです。専門的な分析結果をそのまま提示しても、多くの人には「他人ごと」の数字に見えるかもしれません。その数字が持つ意味を、現場の日常業務や組織の言葉に根差した物語へと「翻訳」し、誰もが理解し、自分ごととして捉えられる形に変換する能力が求められます。
この高度な翻訳を可能にするのが、専門知識です。「抵抗積極タイプ」は、「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合が69.0%と突出していました。この知識が、複雑な分析結果の本質を捉え、平易な言葉で語り直すことを可能にしていると考えられます。
そして、「翻訳」の営みを組織全体に広げ、データに基づいた意思決定を組織の「当たり前」の文化、すなわち認知的正統性へと昇華させるのが教育の役割です。白書において、40.6%もの企業が外部支援として「社内研修・リテラシー教育の提供」を求めている事実は、教育による文化醸成の重要性への認識が、多くの企業で高まっていることを表しています。
自社の「正統性」を問い直すために
人事データ活用を成功へと導く鍵は、技術の導入そのものにあるのではありません。その活動が、組織の中で「正統」なものとして受け入れられるかどうか、という社会的なプロセスが関わっています。データ活用は、一部の専門家がトップダウンで推し進めるものではなく、実利・規範・認知という3つの側面から、組織との丁寧な対話を通じてその正統性を築き上げていく営みです。
皆さんの組織では、データ活用は「実利」を証明できているでしょうか。そのプロセスは「規範」に照らして正しいものでしょうか。そして、それは組織にとって「当たり前」のものになっているでしょうか。私たちが公開した『人事データ白書』は、こうした問いに対し、自社の現在地を検討するためのデータと枠組みを提供してくれるはずです。ぜひ本白書を手に取り、皆さんの組織におけるデータ活用の「正統性」を、今一度問い直すきっかけとしていただければ幸いです。
脚注
[1] Marler, J. H., and Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3-19.
[2] Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.
[3] Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.), Social Exchange: Advances in Theory and Research. Plenum Press.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。