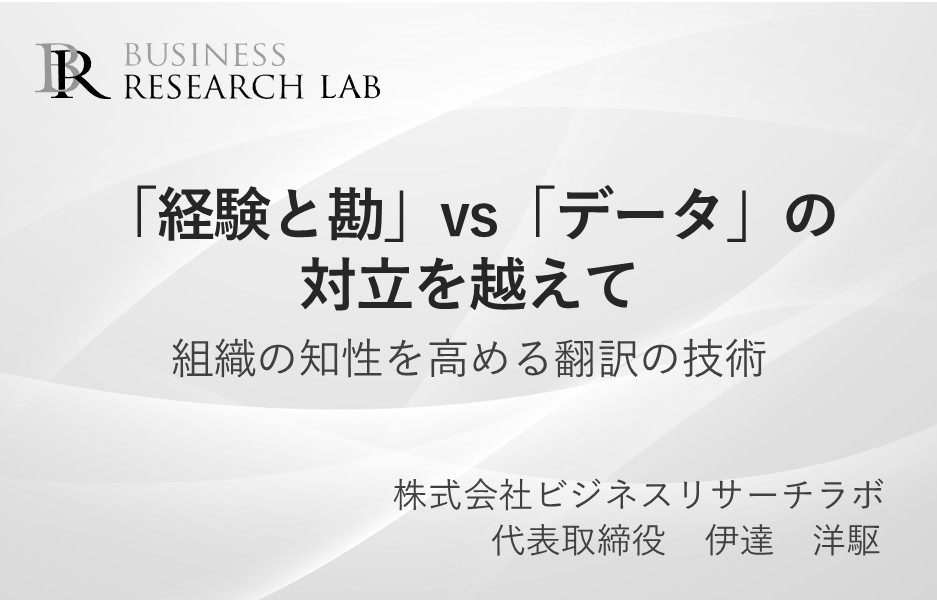2025年9月19日
「経験と勘」vs「データ」の対立を越えて:組織の知性を高める翻訳の技術
ビジネスリサーチラボは『人事データ白書』を公開しました。調査にご協力いただいた多くの人事担当者の皆様から寄せられたデータは、日本企業が置かれた状況を映し出してくれています。
データ活用の現場に目を向けると、私たちは時折、ある対立構造に直面します。それは、「データは客観的だが、現場の実態を反映していない」という現場からの声と、「経験や勘は属人的で、再現性がない」というデータ推進派の声との間の断絶です。少なからぬ組織でデータ活用が思うように進まない、あるいは導入したはいいものの形骸化してしまう原因の一つが、この対立にあるのではないでしょうか。
本コラムの目的は、「経験と勘 vs データ」という対立の構図を乗り越え、両者を統合する道筋を探ることにあります。経験知という、人間が紡ぎ出す豊かで文脈的な「言葉」や「物語」の世界。そして、データという客観的で構造的な「数字」の世界。この二つの世界を絶えず往復し、循環させることによって、個人の暗黙知を組織の「知の資産」へと昇華させることができるはずです。そのためのヒントとして、今回公開した『人事データ白書』を読み解いてみたいと思います。
分断された「数字」と「言葉」の世界
データ活用を推進しようとする時、組織は二つの孤独に直面します。一つは、数字を信奉するあまり、人間的な文脈を見失ってしまう「数字」の世界の孤独。もう一つは、個人の経験に固執するあまり、組織的な知へと昇華できずにいる「言葉」の世界の孤独です。
「数字の世界」の孤独について考えてみましょう。データは客観的な事実を提示し、私たちの思い込みやバイアスを補正してくれる可能性のある武器です。しかし、その力を過信するあまり、数字が「正解」であるかのように扱われる時、それは人間性を無視した管理ツールへと姿を変えます。
今回の白書に寄せられた自由記述の中には、その危険性を物語る生々しい声が記録されていました。例えば、「健康状態に懸念があると入力すると上司から修正を迫られる」といったエピソードや、「残業時間を可視化したところ、残業が少ない従業員に対して『もっと働かせるべきだ』という圧力が生まれ、労働強化につながってしまった」という本末転倒な事例。これらは、データが従業員の心理的安全性を脅かし、信頼関係を破壊する凶器になり得ることを示しています。
こうしたデータ信奉の罠は、組織の文化とも関わっています。白書の重回帰分析によれば、「会社の意思決定では、経営層が一方的に決定し、従業員の声は反映されない」というトップダウン型の組織文化は、データ活用の成果と負の相関関係にあることが明らかになりました。
対話が不在の組織では、データは健全な議論の材料ではなく、トップの決定を後付けで正当化するための道具として使われるかもしれません。数字の裏にある現場の複雑な事情や、従業員一人ひとりの感情は切り捨てられ、組織は客観性を装った、より硬直的な意思決定へと陥っていくのです。
一方で、私たちは「言葉」の世界の孤独にも目を向けなければなりません。長年の経験によって培われた専門家の「勘」や、現場の機微を捉える「肌感覚」は、間違いなく組織の財産です。しかし、その知見が客観的な検証を経ないまま「聖域化」され、個人の中に閉ざされてしまう時、それは組織の成長を妨げる足枷となり得ます。
白書の調査では、人事担当者から見て、自社の経営層や管理職が「データよりも経験や勘を重視する傾向が強い」と認識している割合が、それぞれ約3割存在することが示されています。
もちろん、経験知そのものが問題なのではありません。問題なのは、それが客観的な言葉で語られず、組織の中で共有・検証・継承されるプロセスを欠いていることです。特定の個人の成功体験に依存した意思決定は、その個人がいなくなれば再現できず、環境が変化した際には通用しなくなるかもしれません。それは個人の成功体験に閉じた「孤独な知」であり、組織全体として学習し、変化に対応していく能力を削いでしまいます。次世代へのスキル継承は断絶し、組織は同じ失敗を繰り返すことになるのです。
このように、分断された「数字」と「言葉」の世界は、それぞれが持つ価値を十分に発揮できないだけでなく、互いに不信感を募らせ、組織を停滞へと導いてしまう危険性を含んでいます。
「翻訳」という架け橋
この二つの世界の断絶を乗り越える鍵は、双方の言語を相互に翻訳し、対話を生み出す技術にあります。すなわち、「数字」を、現場が自分ごととして捉えられる「言葉(物語)」に翻訳すること。そして、現場の経験知や課題感という「言葉」を、客観的に検証可能な「数字(データや仮説)」へと翻訳すること。この双方向の往復運動、いわば「翻訳」という架け橋を架けることが、組織の知性を高めます。
この「翻訳」という営みを高いレベルで実践している企業群が、今回の白書の分析から浮かび上がってきました。全体の9.3%という少数派ながら、特筆すべき存在である「抵抗積極タイプ」です。このタイプは、データ活用への「積極性」と、組織からの「抵抗感」が共に突出して高いという、一見すると矛盾した特徴を持っています。
通常であれば、これほど強い逆風の中では成果を出すことは困難だと考えられます。しかし、データが示した現実は、私たちの直感を裏切るものでした。抵抗積極タイプは、データ活用によって「離職率の改善」を実感した割合が65.5%に達するなど、他のどのタイプをも圧倒する成果を手にしていました。
なぜ、最も困難な状況に置かれた、抵抗積極タイプが最も高い成果を上げることができるのでしょうか。それは、このタイプが卓越した「翻訳家」だからに他なりません。初めに、このタイプは「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合が69.0%にのぼります。これは、現場で語られる曖昧で定性的な「言葉」を、信頼性の高い「数字」へと翻訳するための、文法と語彙を習得していることの証拠です。
生半可な分析では、強い抵抗勢力を納得させることはできません。「なぜそのデータが必要なのか」「その分析は本当に正しいのか」といった問いに対し、統計的な作法に則って客観的な根拠を示し続ける。そのプロセスが、このタイプの「言葉を数字に翻訳する力」を鍛え上げたのかもしれません。
そして同時に、抵抗積極タイプは分析から得られた「数字」を、組織を動かす説得力のある「物語(言葉)」へと翻訳する能力にも長けているはずです。ただ分析結果の数値を羅列するだけでは、データに懐疑的な人々を動かすことはできません。その数字が組織のどのような課題を指し、どのような未来の可能性を示唆しているのか。抵抗の背景にある懸念や不安に寄り添いながら、データという事実を共通言語として、粘り強く対話を重ねていく。その真摯な翻訳のプロセスが、抵抗を乗り越え、組織的な行動変容を生み出す力となっています。
この翻訳のプロセスは、どのように行われるのでしょうか。「言葉」から「問い(数字)」への翻訳を考えてみましょう。現場の管理職が「最近、若手の活気がない気がする」という漠然とした経験知(言葉)を口にしたとします。これに対し、優れた翻訳家は「なるほど。それは具体的にどういうことでしょうか」と対話を始め、その言葉の背景にある文脈を探ります。
そして、その定性的な問題意識を、「組織サーベイにおけるキャリア展望の項目と、上司との個人面談の頻度や満足度のデータには、負の相関関係があるのではないか」といった、データで検証可能な「問い(仮説)」へと翻訳します。このプロセスは、現場の暗黙知に光を当て、組織の共有知へと変える一歩となります。
「数字」から「物語(言葉)」への翻訳もあります。上記の問いを検証した結果、統計的に有意な相関関係が見られたとします。しかし、その値(数字)をそのまま提示しても、多くの人の心には響きません。翻訳家は、その数字に意味と文脈を与え、次のアクションを喚起する「物語」として語り直します。
「分析の結果、A部長のチームでは、対話の機会が少ないことが若手のキャリア不安につながっている可能性が見えてきました。一方で、B部長のチームでは、定期的な面談を通じて若手の定着に成功しているようです。この成功事例を参考に、A部長のチームで新たな対話の仕組みを試験的に導入してみませんか」
このように語られることで、データは単なる評価の道具ではなく、具体的な改善策を共に考えるための、希望の物語へと変わります。抵抗積極タイプが直面する大きな抵抗は、この翻訳能力を磨き上げるための砥石となっている可能性があります。
対話する組織への移行
「言葉」と「数字」の往復運動が組織の知性を高めるのであれば、その循環を設計し、促進するリーダーの役割は重要になります。これからのリーダーに求められるのは、「経験と勘」の権威として君臨することでも、「データ」の正解を振りかざすことでもありません。二つの世界をつなぐ「対話の場の設計者」であり、組織全体の知性を引き出す「翻訳家」としての役割です。
このようなリーダーシップの有効性は、何も理想論ではありません。白書の重回帰分析は、「従業員参加型のマネジメントスタイル」がデータ活用の成果と統計的に有意な正の相関関係にあることを明らかにしました。これは、経営層がビジョンを示しつつも、管理職や従業員との協議を経て結論を出すという、ボトムアップの意見を尊重する組織文化を持つ企業ほど、データ活用が成功しやすいことを意味しています。この事実は、データ活用の本質が、トップダウンの指示とボトムアップの現実を、データという共通言語でつなぎ合わせ、組織的な対話と学習を生み出すプロセスにあることを物語っています。
「翻訳家」としてのリーダーが取り組むべきは、組織内に心理的安全性を確保することです。心理的安全性とは、簡単に言えば、組織の中で自分の意見や懸念、あるいは失敗を気兼ねなく表明できると信じられている状態を指します。
データによって、これまで目を背けてきた「不都合な真実」が明らかになることもあるでしょう。あるいは、現場の経験則が、データが示す傾向と真っ向から対立することもあるかもしれません。このような場面で、「データを疑うとは何事だ」「経験則に固執するな」と一方的に断罪するのではなく、なぜそのような違いが生まれるのかを共に探求する姿勢をリーダー自らが示すことが求められます。
データへの異論や、仮説検証の失敗は、組織の思い込みや思考の偏りを正すためのフィードバックであり、「学習」の機会に他なりません。この学習のプロセスを称賛し、挑戦したことを評価する文化を醸成すること。それが、組織の「言葉」と「数字」が健全に衝突し、より高次の知見を生み出すための土台となります。
リーダーは、完璧な正解を示す者ではなく、組織が共に学ぶプロセスを導くファシリテーターとなるのです。その時、意思決定の重圧というリーダーの孤独は、組織全体で未来を創り出す「共創」の喜びに変わっていくのではないでしょうか。データとテクノロジーが進歩し続ける時代だからこそ、私たちは、人間が紡ぎ出す言葉の豊かさと、それらが交差する対話の価値を、改めて見つめ直す必要があります。
組織の「言葉」と「数字」をめぐる旅路
人事データ活用をめぐる議論の中で、多くの企業が直面している「過渡期」の本質とは何でしょうか。それは、これまでの経験と勘に頼った「言葉の世界」と、新たに出現した客観的な「数字の世界」のどちらか一方を選ぶという、二者択一の時代を終え、両者を統合する新しい知のあり方を組織が模索している、産みの苦しみの期間であると考えられます。
本コラムでは、その苦しみを乗り越えるための鍵として、「言葉と数字の往復運動」という視点を提示してきました。この視点に立つ時、私たちが公開した『人事データ白書』は、単なる調査レポートではなく、皆さんの組織が自らの「知の資産」を最大化するための実践的なツールキットとなり得ます。
白書に記された全国の企業の平均値や傾向という「数字」は、皆様の組織で日々語られている「言葉」、すなわち現場の肌感覚や経験知を映し出す鏡となります。「我々の感覚は、全国的に見ても一般的なのか、それとも特殊なのか」「他社が成果を上げている領域で、なぜ我々は苦戦しているのか」。白書は、そうした新たな「問い」を発見するための出発点となるでしょう。
個人の経験知は、他者との対話の中で語られ、データによって検証されることで、組織の誰もが活用できる共有資産へと変わります。無機質に見えたデータは、現場の物語と結びつくことで、血の通った生きた知見へと昇華されます。言葉と数字の往復運動の先に、データドリブンでありながらも人間的な温かみを失わない、強くしなやかな組織の姿が見えてくるはずです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。