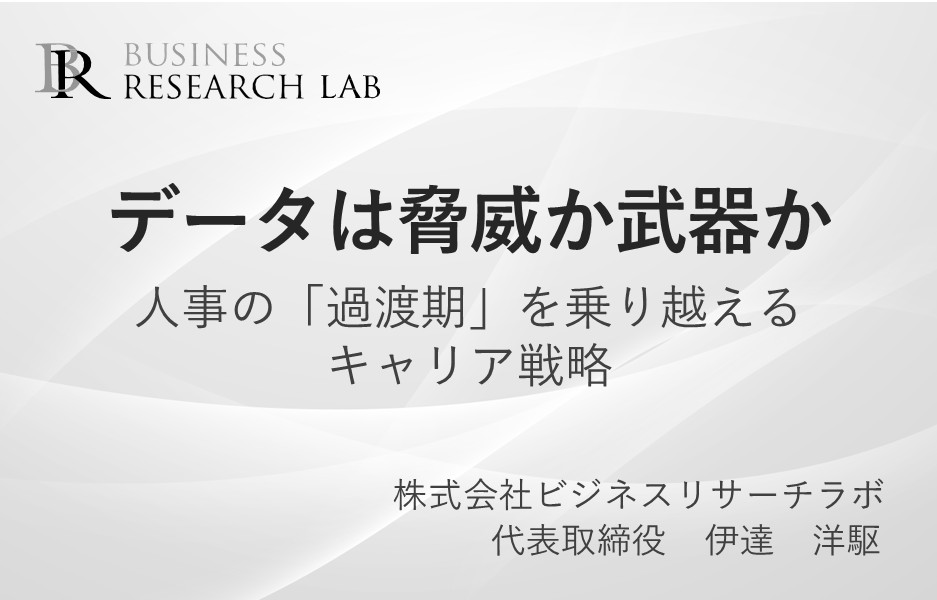2025年9月12日
データは脅威か武器か:人事の「過渡期」を乗り越えるキャリア戦略
ビジネスリサーチラボは『人事データ白書』を公開しました。白書が描き出した風景を一言で表すならば、それは「過渡期」という言葉に集約されます。給与計算や勤怠管理といった、いわば「守り」のデータ活用は多くの企業で定着し、業務効率化に貢献しています。しかし、そのデータを分析し、人材育成や組織開発、採用強化といった未来への競争力につなげる「攻め」の活用へと転換する段階で、多くの企業が壁に直面しています。その壁を象徴するかのように、調査対象となった企業の7割以上が「分析に必要な人材・スキルの不足」を最大の課題として挙げています。
この結果を前にして、「うちの会社も同じだ」と感じた人も少なくないかもしれません。データ活用は重要だと分かっているが、どこから手をつければ良いのか分からない。専門人材の育成や採用は思うように進まない。現場からは「数字だけでは分からない」という声が聞こえ、経営層からは投資対効果を問われる。こうしたジレンマは、一部の先進企業だけの悩みではなく、多くの組織が共有する課題と言えるでしょう。
しかし、本コラムで私が光を当てたいのは、この課題を、人事担当者一人ひとりの専門性、役割、市場価値の問題として問い直すことです。人事データ活用の「過渡期」とは、人事という職能の「過渡期」であり、そこに身を置く皆さん自身の「キャリアの変曲点」に他なりません。これまで当たり前とされてきた業務の価値が相対化され、新たなスキルセットが求められる時代。この変化が足元で起きています。
そこで、皆さんにあえて問いかけたいと思います。5年後、皆さんは人事としてどのような価値を組織に提供していたいでしょうか。その時、皆さんの専門性を支える武器は何になっているでしょうか。そして、今皆さんの目の前にある「データ」という存在は、いずれ仕事を奪うかもしれない脅威に見えますか。それとも、自らの可能性を解き放ち、新たなキャリアを切り拓くための武器に見えますか。本コラムは、その答えを探すためのものです。『人事データ白書』の結果をもとに、人事担当者自身のキャリアについて考えてみたいと思います。
白書が映し出す、3つの人事パーソン像
キャリア形成について考えるにあたって、まずは自らの現在地を把握することから始めましょう。『人事データ白書』に記されたデータは、現代を生きる人事担当者の姿を、いくつかの典型像として浮かび上がらせます。ここでは、その中でも象徴的な「3つの人事パーソン像」を描き出します。これらはキャリアの優劣や固定的な段階を示すものではなく、それぞれが独自の専門性で組織に貢献する役割の類型です。それぞれの価値の源泉とキャリアの可能性について考察していきます。
第一の像は、「オペレーター」です。これは、正確な業務執行の専門家であり、従来の人事機能の核を担ってきた存在です。給与計算、勤怠管理、社会保険手続き、入退社管理といった業務を、ミスなく、遅滞なく、安定的に遂行すること。その正確性と安定性が、オペレーターとしての価値の源泉です。彼ら彼女らの実直な仕事がなければ、組織は円滑に機能しません。
白書のデータを見ても、その重要性と現状がよく分かります。「給与計算システム」の導入率は90.1%、「勤怠管理システム」は82.5%に達し、多くの企業でこれらの業務がシステム化されています。また、データ活用の目的として「労務管理・人件費管理」を挙げた企業が73.9%と最も高かったことからも、オペレーションの最適化が人事データ活用の主要な動機であり続けていることがうかがえます。
しかし、オペレーターとしてのキャリアは転換点を迎えています。価値の源泉であった定型業務の一部が、AIやRPAといったテクノロジーによって自動化・代替されつつあるからです。
これは、オペレーターの専門性が不要になることを意味しません。むしろ、正確なデータなくして高度な分析はあり得ず、その基盤を支えるオペレーションの専門家の重要性は増しています。業務の自動化によって生まれた時間を、より高度なオペレーション設計やデータガバナンスの担い手として活用するなど、専門性を深化・拡大させることで、キャリアの可能性はさらに広がります。
第二の像は、「アナリスト」です。これは、「攻め」の人事への転換を担うべく登場した、データ分析の専門家です。統計学の知識を駆使し、分析ツールを自在に操り、膨大なデータの中から組織の課題や未来の兆候を読み解くこと。その高度な分析能力が、アナリストの価値の源泉です。彼ら彼女らの登場は、経験と勘に頼りがちだった人事業務に、客観性と根拠という新たな光をもたらしました。
白書が示すように、「分析に必要な人材・スキルの不足」が7割以上の企業で最大の課題となっている現状は、裏を返せば、アナリストという存在がいかに渇望されているかの証拠でもあります。そして、そのポテンシャルは計り知れません。白書の潜在プロフィール分析で特定された、全体の約9%という少数派ながら驚異的な成果を上げる「抵抗積極タイプ」は、その典型です。このタイプは、「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合が69.0%にのぼり、その高い専門スキルを武器に、「離職率の改善」で65.5%が「非常に良くなった」と回答するなど、他を圧倒する成果を叩き出しています。
しかし、アナリストのキャリアパスもまた、平坦なものではありません。高度な分析スキルを持つがゆえに、現場や経営層から「数字しか見ていない」「現場の複雑さが分かっていない」と孤立してしまう危険性があります。導き出したインサイトがどれほど鋭くても、それが組織の行動に結びつかなければ、価値にはなりません。統計的に有意な結論と、ビジネスとして有効な施策との間には溝が存在します。アナリストは、その溝を乗り越えられない「翻訳の壁」に突き当たり、宝の持ち腐れとなってしまうリスクを抱えています。
第三の像は、「チェンジエージェント」です。これは、変革の仕掛け人であり、これからの人事に求められる役割の一つと言えるかもしれません。チェンジエージェントは、オペレーターが持つ現場感覚や実務知見と、アナリストが持つ高度な分析能力を橋渡しし、データから得られた知見を組織の「行動」へと「翻訳」する役割を担います。その価値の源泉は、データという事実を共通言語として、組織内の異なる立場の人々をつなぎ、対話を生み出して、変革の渦を巻き起こしていく触媒としての機能にあります。
白書の分析結果は、このチェンジエージェントの重要性を示唆しています。例えば、「データ活用の成果実感」と最も強く相関していた要因の一つに、「結果の共有レポーティング」(r=.77)がありました。分析結果をただ報告するだけでなく、経営層や現場と共有し、対話するプロセスこそが成果に直結することを意味します。また、重回帰分析の結果、「従業員参加型のマネジメントスタイル」(β=.12)が成果と正の関連を示したことも重要です。
チェンジエージェントは、トップダウンで答えを示すのではなく、データを通じて組織全体の知性を引き出し、ボトムアップの学習と改善を促進するファシリテーターとして活躍します。この役割は、AIには代替できない、人間ならではの専門性であり、経営のパートナーとして組織を牽引していくキャリアパスと言えるでしょう。
オペレーター、アナリスト、チェンジエージェント。皆さんは今、どこに立っているでしょうか。あるいは、どこを目指したいと感じたでしょうか。『人事データ白書』を手に、少し立ち止まって考えてみていただければと思います。
キャリア形成のロードマップ
特定の役割を目指すかどうかにかかわらず、これからの人事担当者にとって、自身の専門性を高め、キャリアの幅を広げていく視点は不可欠です。ここでは、そのためのステップを、一つのロードマップとして提示します。特に、アナリストが導き出したインサイトを現場の行動につなげるような「翻訳能力」は、今後どの役割においても重要性が増していくでしょう。
キャリア形成の第一歩は、現在地を把握することから始まります。私たちはしばしば、自身の能力や置かれた状況を主観的に評価しますが、それでは進むべき方向を見誤りかねません。ここで白書は、極めて有効な自己分析のフレームワークを提供してくれます。
初めに、組織としての現在地を把握するためには、第10章で詳述されている「4つの企業タイプ」の分析がヒントとなります。自社が、データ活用への関心も取り組みも低い「未活用タイプ」なのか、意欲と抵抗の狭間で揺れる「抵抗模索タイプ」なのか、安定的に実践を進める「積極活用タイプ」なのか、それとも変革の痛みを伴いながら急進する「抵抗積極タイプ」なのか。この類型に自社を当てはめてみることで、組織が直面しているマクロな課題と、その中で自身がどのような役割を期待されているのかが明確になります。
続いて、個人としてのスキルレベルを可視化するためには、第1章に掲載されている人事担当者向けの「8つの分析スキル・知識」に関する自己評価項目が、そのままパーソナルな診断ツールとして機能します。「データベースの操作」や「データの可視化」といった基礎的なスキルから、「統計学に基づく統計解析の知識」「結果を実務に活かすノウハウ」といった応用的なスキルまで、自身の強みと弱みを棚卸しすることができるでしょう。
現在地が明確になれば、取り組むべきは、目的地までの学習計画を手に入れることです。「スキル不足」という漠然とした不安を、学習目標へと落とし込んでいく必要があります。ここでも白書は、何を、どの順番で、なぜ学ぶべきかという問いに対して、データに基づいた答えを示してくれます。多くの人が「スキル」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、「統計解析の知識」や「分析ツールを使うスキル」といったハードスキルかもしれません。もちろん、これらはアナリストとして不可欠な能力です。
しかし、白書の相関分析や重回帰分析(第7, 8章)に分け入ってみると、成果との関連性において、それらと同等、あるいはそれ以上に重要な能力が浮かび上がってきます。それは、「分析結果を参照・解釈し、実務に活かすノウハウ」や「経営層や現場に向けて分析結果をわかりやすくまとめるスキル」といった、いわば「翻訳能力」です。これらの能力が、アナリストからチェンジエージェントへの飛躍を可能にする鍵となります。場合によっては、白書に網羅された多様な分析項目や考察を読むこと自体が、目指すべきスキルセットの全体像を理解するプロセスとなるでしょう。
知識は、実践を通じてスキルへと昇華されます。ロードマップの第三のステップは、学習したことを活かすための実践の第一歩を踏み出すことです。しかし、いきなり全社を巻き込むようなプロジェクトを立ち上げる必要はありません。チェンジエージェントへの道は、小さな成功体験を一つひとつ着実に積み重ねることから始まります。
その「最初のテーマ」を見つけるためのヒントも、白書の中に隠されています。例えば、第1章にまとめられた「データ活用による成果」の各項目は、他社がどのような領域で成果を実感しているかを示す事例集です。また、「今後の強化したい領域」のデータは、人事界全体の関心がどこに向かっているかのトレンドを表しています。
これらのデータを参考に、「まずは自社の採用コストの媒体別効果を分析してみよう」「次は、先日実施した研修の効果をアンケートデータで可視化してみよう」といったように、自社の状況に合わせて始めやすく、かつ成果が見えやすいテーマを設定してみましょう。白書が示すように、いきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部門や課題で「パイロットプロジェクト」を実施し、そこで得られた学びと成功体験を組織に共有していく。アジャイルなアプローチが、リスクを抑えながら経験値を高め、変革への機運を醸成していく上で賢明な戦略です。
キャリア形成のプロセスは、孤独な戦いである必要はありません。その成否は、いかに多くの仲間を巻き込み、変革のエネルギーを組織的なうねりへと高めていけるかにかかっています。ロードマップの最終ステップは、変革を共に推進する仲間を見つけ、社内外にネットワークを構築することです。チェンジエージェントは、卓越したネットワーカーでなければなりません。
白書のデータは、そのための戦略を示唆しています。「社内にデータ分析専門部署(経営企画/IT部門など)があり、人事部門と連携している」企業は37.4%にのぼり、部門の垣根を越えた協力体制が有効であることを示しています。また、データ活用の成果は、「経営層」や「人事以外の管理職」の関与度と相関していることも明らかになっており、彼ら彼女らをいかに巻き込むかが重要です。
アナリストとして導き出したデータを、多くの関係者が理解できる言葉や物語に「翻訳」し、その課題解決に貢献するという姿勢が、信頼を勝ち取り、味方を得るための王道です。そして、『人事データ白書』が、社外の仲間とつながるためのツールとなり得ます。同じ課題を抱え、同じ白書を手に取った全国の人事担当者と、データという「共通言語」を通じて議論し、学び合う。そのようなコミュニティは、困難な変革の道のりを支える財産となるはずです。
人事の未来を形成する
ここまで、『人事データ白書』を道標として、人事担当者自身のキャリア形成について辿ってきました。その検討を通じて見えてきたのは、データ活用という大きな波が、人事という仕事の価値を再定義しようとしている、という未来の姿です。これまで人事の主な役割は、組織というシステムを安定的に「管理」することにあると考えられてきました。しかし、データとテクノロジーが定型業務を代替していく時代において、人事の価値は、組織と人の未来を構想し、その実現を主体的にデザインしていく「価値創造」へとシフトしていくでしょう。
その時、人事担当者は制度の運用者にとどまりません。データという武器を手にすることで、組織の健康状態を診断し、未来のリスクを予測し、人の可能性を引き出すための戦略を立案するという、より創造的で戦略的な役割を担うことができるのです。それは、知的で、刺激的で、そして組織の未来に直接貢献できる仕事です。
『人事データ白書』に記されたデータは事実であると同時に、多くの企業が悩み、試行錯誤を重ねているプロセスの記録でもあります。データという共通言語を手にすることで、皆さんは経営層と同じ視座で議論し、現場の管理職が抱える課題に寄り添い、組織全体の知性を結集させることができます。それが、経営のパートナーとして、組織変革の主導者へと進む道でしょう。
もちろん、キャリア形成のプロセスは平坦なものではありません。白書の分析で「抵抗積極タイプ」という存在が明らかになったように、変革にはしばしば抵抗が伴います。新しいスキルの習得には時間がかかり、試行錯誤の過程では失敗も経験するかもしれません。それは、いわば組織と個人が共に経験する「成長痛」です。しかし、白書は同時に、その痛みの先に待つ「高い成果」という風景もまた描き出してくれています。大切なのは、抵抗や失敗を恐れないことです。試行錯誤のプロセスに、組織と皆さん自身を成長させる価値が宿っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。