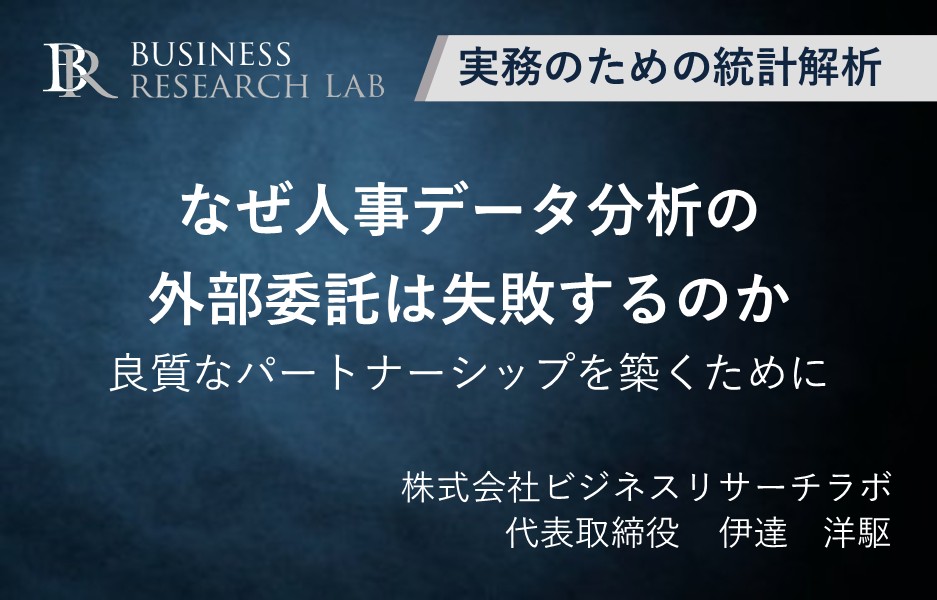2025年9月10日
なぜ人事データ分析の外部委託は失敗するのか:良質なパートナーシップを築くために
「人的資本経営」が企業価値を左右するアジェンダの一つとなる中、経験や勘といった従来の手法に加え、データに基づいた客観的な意思決定によって人事戦略の精度を高めようとする「ピープルアナリティクス(人事データ分析)」に対する期待が高まっています。
離職率の改善、ハイパフォーマーの育成、多様性のある組織の実現。こうした複雑な課題に対し、多くの企業が外部の専門家や専門企業に分析を依頼するのは、リソースや専門性を補う上で合理的な選択と言えるでしょう。
しかしその一方で、「多額の費用をかけたにもかかわらず、得られたのは既知の事実の再確認に過ぎなかった」「報告書は納品されたが、具体的な次の一手にはつながらなかった」といった声が聞かれるのもまた事実です。
なぜ、期待されているにもかかわらず、一定のプロジェクトが「残念な結果」に終わってしまうのでしょうか。本コラムでは、この問題を個別の失敗事例としてではなく、その背景にある構造的な要因から検討していきます。依頼する企業側と、依頼を受ける専門家側の双方の視点から課題を俯瞰し、いかにして両者が建設的なパートナーシップを築き、データ分析という手段を組織の力に変えていけるのか、その道筋を考察します。
なぜ「すれ違い」は生まれるのか
人事データ分析の外部委託が期待通りに進まない。その原因の根は深く、そして多くの場合、プロジェクトが始まる前の「パートナー選定」の段階にすでに埋め込まれています。これは、どちらか一方の能力や誠実さが欠けているという単純な話ではなく、依頼側と受注側の間に存在する専門性の非対称性や、ビジネス上の制約が、意図せぬ「すれ違い」を生み出してしまうという構造的な問題です。
依頼する側の挑戦と葛藤
依頼する側の事情を考えてみましょう。人事部門は、採用、労務、育成、制度設計といった「人事」領域のプロフェッショナルです。しかし、必ずしも統計学や心理測定といった「データ」の専門家ではないのは当然のことです。
この専門性のギャップが、パートナー選定におけるいくつかの困難を生み出します。例えば、専門企業から「AIが離職の予兆を精緻に予測します」「最新のビッグデータ解析で、社員のエンゲージメントを左右する隠れた要因を特定します」といった魅力的な提案を受けた時、技術的な妥当性や分析ロジックの是非を厳密に判断することは困難です。
複雑で答えのない人事課題に日々向き合う担当者にとって、データ分析という未知の力が、まるで万能の解決策、いわば「魔法の杖」のように映るのは、自然な心理と言えます。課題解決への思いが切実であるほど、その技術的なブラックボックスの中身を問うことよりも、聞こえの良い言葉に望みを託したくなる可能性があります。
多くの企業が持つ購買プロセスも、この問題を助長する一因となり得ます。「分析能力」という目に見えない価値を評価するのは難しい一方で、「価格」は明確な比較指標となります。そのため、複数の事業者から見積もりを取る際には、価格が重要な判断基準となりやすいでしょう。結果、分析の品質や担当者のスキルといった本質的な価値が十分に評価されず、安価であることを理由にパートナーが選定されてしまうという事態が起こり得ます。
依頼側が明確な目的や仮説を持たないまま、「とにかく何か意義のある発見をしてほしい」といった形で分析を「丸投げ」してしまうケースも散見されます。これは分析という行為への期待の裏返しでもありますが、目的が曖昧なままでは、どんなに優秀な分析者でも価値あるアウトプットを生み出すことは難しいでしょう。
受注する側のビジネスと現実
一方で、依頼を受ける専門家側にも、ビジネスとしての現実があります。
例えば、高度に専門的な分析手法の数理的背景を詳細に説明することは、必ずしも顧客の理解を促すとは限りません。そのため、多くのサービス提供会社は専門性を噛み砕き、サービスを分かりやすく「パッケージ化」して提供しようと試みます。この「パッケージ化」は、見せ方の工夫に留まりません。分析ロジックを標準化されたシステムに落とし込むところまで含まれることが少なくないのです。例えば、標準化されたサーベイシステムを導入し、エンゲージメントスコアを自動で集計・可視化するといったものが、その一例です。
こうしたアプローチは、効率的でスケーラブルなサービス提供を可能にし、比較的安価な価格設定を実現しますが、その一方で、本来は一社一社の固有の文脈や課題に寄り添うべき分析が、商品として消費されていく、という側面も持ち合わせます。
自社の能力を示す「実績」の見せ方にもジレンマがつきまといます。守秘義務契約の下では、過去のプロジェクトの成功体験を具体的に語ることは難しいのが実情です。その結果、「大手企業との取引実績多数」といった抽象的な表現に頼らざるを得ず、専門企業としての真の実力が伝わりにくくなります。依頼側は、その実績が単なるデータの「集計・可視化」作業なのか、それとも深い示唆を導き出した「分析」なのかを見極める必要があります。
加えて、依頼側が認識すべき点として、専門家には大きく分けて二つのタイプが存在するという事実があります。一つは、高度な統計学や機械学習のスキルに特化した「データサイエンス特化型」の専門家です。もう一つは、データ分析スキルに加えて、人事領域の「ドメイン知識」を深く理解している「人事領域融合型」の専門家です。
しかし、さらに問題を複雑にしているのが、そもそも高度な分析スキルを有しているとは言えないにもかかわらず、「専門家」としてサービスを提供しているケースが存在するという現実です。例えば、BIツールを操作して見栄えの良いグラフを作成するスキルや、基本的な集計作業を「データ分析」と称している場合です。これらはそれ自体が価値あるスキルではありますが、統計的な妥当性に基づいた深い洞察や、人事課題の根本原因に迫るための仮説検証プロセスとは異なります。
そして厄介なのは、データ分析の非専門家が、この「本質的な分析能力」の有無を見極めるのが困難であるという点です。専門用語を巧みに使い、体裁の整った提案書を作成するため、一見すると信頼できるように見えてしまいます。依頼側が、純粋な技術力を求めているのか、人事施策に直結する洞察を求めているのかによって、必要とされるパートナーのタイプは異なりますが、それ以前に「そもそも本物の専門的スキルがあるのか」という、見極めが求められるのです。これが、パートナー選定における最も見えにくい、しかし重大なリスクの一つとなっています。
失敗がもたらす負の連鎖
こうした「すれ違い」を内包したままプロジェクトがスタートしてしまった場合、どのような「残念な結果」が待ち受けているのでしょうか。その問題は、レポートの質の低さに留まらず、時間と共に形を変えながら、組織にダメージを与えていきます。
アウトプットへの失望
プロジェクトの成果物である分析レポートが納品された時、最初の失望が訪れます。
まず直面するのが、「当たり前」の再確認です。色鮮やかなグラフと共に「残業時間が長い社員ほど、離職率が高い傾向にある」といった結論が、さも重大な発見であるかのように記されています。現場の誰もが肌感覚で知っていることを、データで「裏付けた」だけでは、次の一手にはつながりません。「それは知っている。私たちが知りたいのは、なぜ残業が減らないのか、その原因だ」という虚しさが募ります。
次に訪れるのが、「だから何?」の壁です。例えば、「社内イベントへの参加回数と、社員の定着率に正の相関が見られる」という報告。これは、分析が表層的な「相関関係」の指摘に留まっています。この報告だけを見て「イベントを増やそう」と判断するのは早計です。もともと会社への帰属意識が高い人がイベントに参加しているだけで、イベント自体が定着率を上げている原因ではないかもしれません。この見極めができないままでは、的外れな施策につながるリスクがあります。
深刻なのが、「数字の罠」です。例えば、離職予測モデルを構築し、高い精度という華々しい報告がなされたとします。しかし、その中身をよく見ると、もともと離職率が5%の会社で、モデルが「全員、離職しない」と予測しているだけだった、ということがあるかもしれません。これでは、本当に注意すべき離職予備軍を一人も見つけられておらず、分析としては役に立っていません。
プロジェクト進行の疲弊
質の低いアウトプットが生まれる背景には、プロジェクト進行そのものの迷走があります。そのしわ寄せは、依頼側である人事担当者に重くのしかかります。
気がつけば役割が逆転している、という現象が起こり得ます。専門家として招いたはずのパートナー企業から的を射た提案がないため、しびれを切らした担当者の方が「こういう切り口で分析できませんか」「このデータとこのデータを掛け合わせてみては?」と、具体的な分析方針を指示しているようなケースです。これでは高い費用を払って、自らの業務負荷を増やしているようなものです。
また、依頼先の理解が浅いために、本質的でない質問が繰り返されたり、次から次へと追加のデータ提供を求められたりします。その一つひとつに対応するだけで、担当者の時間はどんどん奪われていきます。そして、ようやく出てきた中間報告は期待外れで、大幅な手戻りを指示する。こうした非効率なやり取りが重なることで、プロジェクトは遅々として進まず、関係者は心身ともに疲弊していきます。
組織に残る「負の遺産」
プロジェクトが終わり、多大な労力を費やした担当者が疲弊する。しかし、問題はそれだけでは終わりません。一度の失敗体験が、その組織におけるデータ活用の未来の可能性まで閉ざしてしまうことが、深刻な問題です。
「高いお金を払って分析を頼んだのに、結局何も役に立たなかった」という経験は、「やはりデータ分析など意味がない」「人事の仕事は『勘と経験』が一番だ」というアレルギーを組織内に植え付ける可能性があります。次に本当に価値のある挑戦をしようとしても、経営層や他部署から「また無駄な投資をするつもりか」と、協力や予算を得ることが難しくなってしまうのです。
そして、挑戦をリードした担当者の心に残る徒労感や「トラウマ」。これは個人の問題ではなく、組織から挑戦する意欲を奪ってしまったという点で、計り知れない損失です。さらに、納品された分析ツールが、ロジック不明な「ブラックボックス」と化し、誰も維持・更新できずに陳腐化していく。安易なパートナー選びは、組織の時間、資金、未来への信頼と意欲さえも蝕んでいくリスクの高い行為なのです。
良質なパートナーシップを築くために
これまで考察してきた困難な状況は、乗り越えられない壁ではありません。適切な準備と、見極めるための仕組み、丁寧な関係構築によって、このすれ違いを乗り越え、良質なパートナーシップを築くことは十分に可能です。ここでは、そのための処方箋を3つのステップで提案します。
ステップ1:依頼前の「自己分析」
プロジェクトの成否は、パートナー候補に会う前の「準備」でその大半が決まると言っても過言ではありません。プロジェクトの主体はあくまで自社である、という意識を持つことから始まります。
まず取り組むべきは、分析の「目的の解像度」を上げることです。「離職率を下げたい」というテーマを、「なぜ下げたいのか」「特にどの層の離職が組織にとって痛手なのか」「最終的に、どのような人事施策の実行につなげたいのか」と、WHYとWHATを自問自答し、掘り下げます。このプロセスを経ることで、目的は具体的でシャープなものになり、分析の成功確率を高めます。
次に重要なのが、「仮説を持つ勇気」です。「若手の離職には、キャリアパスの不透明さが関係しているのではないか」といった仮説は、間違っていても構いません。この仮説を専門家にぶつけることで、具体的で深い対話が生まれます。仮説は、専門家とのコミュニケーションの質を高めるための、最高の「たたき台」となります。この仮説構築のプロセス自体が、自社の課題を理解する上で有効です。
ステップ2:選定プロセスの再設計
入念な準備ができたら、パートナー選びです。感覚的な「印象」ではなく、「見極める力」をプロセスの中に仕組みとして組み込むことが求められます。
そのための手段が、RFP(提案依頼書)に工夫を凝らすことです。ステップ1で明確化した目的と仮説を記載し、提案企業には具体的な分析アプローチと期待されるアウトプットのイメージを求めます。可能であれば小規模なデータセットで有償のトライアル分析を依頼することも、ミスマッチを防ぐ上で有効です。
提案の場には、実際に手を動かす分析担当者の同席を求めるべきでしょう。その担当者に対し、思考の深さを問う質問を投げかけましょう。「なぜ、その分析手法を選択したのですか。他の手法でダメな理由は何ですか」「もし仮説がデータによって否定された場合、次にどのような手を打ちますか」。
こうした問いへの回答の中に、その人の思考の深さ、柔軟性、課題解決への誠実さが表れます。論理的で誠実な回答ができる人物が、信頼に値するパートナー候補です。パートナー候補がアピールする「実績」についても、「その事例で、どのような人事課題があり、分析結果が最終的にどのような人事施策につながったのか、そのストーリーを教えてください」と一歩踏み込んで尋ねることで、その企業の貢献への意識を測ることができます。
ステップ3:プロジェクト開始後の「協働」
最適なパートナーを選定できても、そこで終わりではありません。そこからが本当のスタートです。分析結果という「地図」を手に、組織が次の一歩を踏み出すまで伴走する関係を築くことが重要です。
そのためには、依頼先を「下請け」として扱うのではなく、同じゴールを目指す「パートナー」として迎え入れ、共にプロジェクトを育てていく「協働」の姿勢が欠かせません。定期的な対話の場で、進捗だけでなく、懸念事項もオープンに共有します。分析の途中経過に対して、現場の感覚と照らし合わせたフィードバックを返す。このキャッチボールの積み重ねが、信頼関係を醸成し、分析をより現実に即した、血の通ったものへと進化させていきます。分析とは、一度の作業で答えが出る魔法ではなく、対話を通じて真実を探求していく共同作業です。
データを、組織の力へ
人事データ分析の外部委託は、面倒な作業をアウトソーシングする行為ではありません。それは自社の大切な資産である「人」に関する重要な意思決定の「思考プロセス」を、外部の専門家と共有し、共に磨き上げていく高度な知的協働です。
この取り組みにおける失敗の多くは、本質的な対話の不足に起因しています。だからこそ、成功の鍵は、依頼する側がプロジェクトの主体としての自覚を持ち、自分たちが何を成し遂げたいのかを深く見つめ直すことにあります。その熱意と課題意識を共有できる相手を、慎重に、しかし能動的に見つけ出すこと。見つけ出した相手を、敬意を持ったパートナーとして迎え入れ、粘り強く対話を続けていくこと。
この姿勢を持つことができた時、外部の専門家は、分析の請負人から、組織の未来を共に創造する、かけがえのないパートナーへと変わるはずです。データ分析は、その先にある一人ひとりの社員の成長と、組織全体の発展を見据えた時、未来を切り拓くための手段となるでしょう。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。