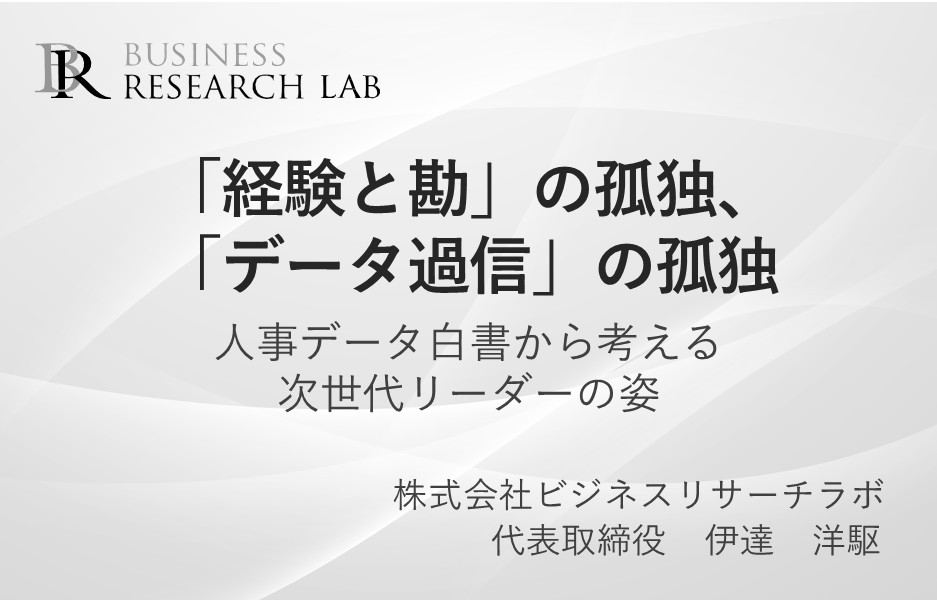2025年9月8日
「経験と勘」の孤独、「データ過信」の孤独:人事データ白書から考える次世代リーダーの姿
2025年8月、私たちビジネスリサーチラボは『人事データ白書』を公開しました。調査の実現にあたり、貴重な知見をご提供くださった全国の人事担当者の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。白書が示すのは、多くの日本企業がデータ活用の「過渡期」にあるという実態です。「守り」の活用は定着したものの、人材育成や組織開発といった「攻め」への転換には壁が存在します。
本コラムでは、組織の舵取りという重責を担う「経営者・リーダー」の立場から人事データを読み解きます。最終決断の場でリーダーが直面する「孤独」。その重圧に対し、データはどのような意味を持つのでしょうか。それは孤独な戦いを支える「参謀」となり得るのか、それとも新たな重圧となるのか。白書のデータを道標に、次世代のリーダーシップ像を探ります。
白書が映し出す、リーダーの現在地
白書が示すデータから、リーダー自身の現在地を確認することから始めましょう。そこに見えてくるのは、データ活用に対する「期待」の大きさと、その実践という「現実」との間に横たわる、決して小さくない乖離です。
白書の調査結果によれば、経営層のデータ活用に対する意識は高いレベルにあります。人事担当者から見た自社の経営層の姿として、「データ活用を推進しようと努めている」という項目に対し、肯定的な回答(「非常にあてはまる」「あてはまる」の合計)が54.1%に達しました。これは、人事部門自身の推進意欲(54.4%)とほぼ同水準であり、経営トップがデータ活用の重要性を強く認識し、全社的な旗振り役を担おうとしている様子が見て取れます。多くのリーダーが、データドリブンな経営への移行が必要であるという時代の要請を感じ取り、その変革の先頭に立とうという意志を持っていることの表れと言えるでしょう。
しかし、その高い意欲は、必ずしもリーダー自身の具体的な行動に結びついているわけではないようです。「データの集計・分析ツールを積極的に使っている」という項目になると、経営層に対する肯定的な回答は40.1%に留まります。また、「データの利活用に関する新しい知識を、日々収集している」という項目でも40.7%と、意欲の高さに比べるとやや低い水準に落ち着いています。多くのリーダーがデータ活用を「推進すべきもの」とは捉えているものの、自らが直接手を動かし、その中身を深く理解し、使いこなす「自らの武器」とまでは捉えきれていない、という現実を示唆しているのではないでしょうか。
なぜ、このような「期待と現実のギャップ」が生まれるのでしょうか。一つの可能性として、リーダーがデータ活用を、人事部門や専門部署に任せるべき「飛び道具」のように捉えているのかもしれません。経営の舵取りという本来の業務に忙殺される中で、専門的で難解に見えるデータ分析の世界にまで自ら足を踏み入れる必要はない、と。あるいは、その重要性は認識しつつも、日々進化するテクノロジーや分析手法を前に「どこから学び、どう使えば良いのか分からない」という戸惑いや壁に直面している可能性も考えられます。
いずれにせよ、このリーダー自身の「期待」と「現実」の間に存在するギャップが、多くの組織でデータ活用が「経営マター」にならず、人事部門の取り組みに留まってしまう、あるいは部分的な業務改善の域を出ないという要因となっているのかもしれません。リーダーが自らの言葉でデータの価値を語り、自らの意思決定の軸に据えることができれば、データは組織の血肉となります。その一歩手前で、多くのリーダーと組織が足踏みをしている。それが、白書から見えてくるリーダーの現在地です。
データなき意思決定、データ過信の意思決定
リーダーの孤独は、いつの時代も変わらないものです。しかし、データという新たな要素が経営に加わったことで、その孤独の質は変化し、二つの新たな様相を呈し始めているように捉えることもできます。「データなき意思決定」の孤独と、「データ過信の意思決定」の孤独です。
第一の孤独は、従来からリーダーが抱えてきたものでしょう。客観的な拠り所がないまま、自らの経験と勘を頼りに重大な決断を下しなければならないという孤独です。市場環境が複雑化し、過去の成功体験が必ずしも未来を保証しない現代において、この孤独はその重みを増しています。
白書のデータを見ても、人事担当者から見て経営層が「データよりも経験や勘を重視する傾向が強い」と認識する割合は30.4%にのぼり、否定的な回答(31.3%)と拮抗しています。これは、少なからぬリーダーが、長年の経験で培われた直感や洞察力に強い自負を持っていることの表れです。その経験知は、決して軽視されるべきものではなく、幾多の困難を乗り越えてきた組織の資産です。しかし同時に、その経験則が通用しない局面を迎えたとき、他に頼るべきものがないという不安と孤独は、リーダーの肩に重くのしかかります。
一方で、データ活用が普及するにつれて、第二の、より現代的な孤独が生まれつつあります。データを正解であるかのように過信し、数字の裏にある現場の知見や従業員の感情、組織の文脈といった情報から目を背けてしまう「データ過信の意思決定」の孤独です。データという「神託」に判断を委ねることで、リーダーは意思決定の責任から解放されるように感じるかもしれません。しかし、それは自らの思考を放棄することで生まれる、新たな孤独に他なりません。
この危険性は、白書の分析結果にも示されています。重回帰分析の結果、「会社の意思決定では、経営層が一方的に決定し、従業員の声は反映されない」というトップダウン型の組織文化は、データ活用の成果と負の相関関係にあることが明らかになりました。このような組織では、データは事実を探求するためのものではなく、リーダーが下した結論を後付けで正当化するための道具として使われるかもしれません。リーダーにとって不都合なデータは無視され、都合の良いデータだけが取り上げられる。これでは、組織が持つ多様な知見は押し殺され、健全な意思決定は望めません。
リーダーはどちらの孤独を選ぶべきなのでしょうか。答えは、そのどちらでもありません。データがリーダーにもたらす価値は、意思決定の「正解」を教えることにあるのではなく、意思決定の「質」を高めるための対話の素材を提供することにあります。経験や勘という主観と、データという客観を、組織の中で健全に衝突させる。そのプロセスを通じて、より立体的で、納得感のある結論を導き出す。データは、リーダーをどちらの孤独からも解放し、組織をより高い次元の意思決定へと導く可能性を秘めています。
データは「参謀」である
データは、リーダーにとって、何を意味するのか。私は、それを「参謀」という言葉で表現したいと考えています。かつての名将が優れた軍師を傍らに置いたように、現代のリーダーは、データという、時に耳の痛い進言も厭わない、優秀な参謀を手にすることができます。この参謀は、リーダーに三つの価値を提供し、その意思決定を新たな次元へと引き上げます。
第一の価値は、組織の解像度を高める「眼鏡」としての役割です。リーダーの地位が高くなるほど、現場の実態は見えにくくなるものです。報告はきれいに整えられ、生々しい問題はオブラートに包まれる。しかし、データはそのような忖度をしにくいものです。
白書のデータを見ると、従業員規模が大きくなるほど「組織サーベイ・エンゲージメント調査」の結果を分析までしている企業の割合が増加し、5,000名以上の企業では60.6%に達します。大企業のリーダーほど、個々の報告だけでは捉えきれない組織全体の健全性や、部門間の連携状況、あるいは離職の予兆といった、これまで目に見えなかったものをデータという眼鏡を通して見ていることの表れです。この眼鏡は、リーダーが陥りがちな現状認識のバイアスを補正し、より的確な問題発見を可能にします。
第二の価値は、不確実な未来への航路を描くための「羅針盤」としての役割です。ビジネスの世界に正解はありません。しかし、過去のデータを分析することで、未来の傾向を予測し、より確度の高い「仮説」を立てることは可能です。
白書の調査では、データ活用によって成果を実感している企業は、「スキルアップやリスキリングなど人材育成の効果」といった項目でポジティブな変化を感じています。これは、どのような研修が、どのような人材の、どのような能力向上につながったのかということをデータで検証し、人材育成という未来への投資効果を最大化しようとする仮説検証サイクルが機能している証拠と言えます。データは、行き先を指し示すだけでなく、どのルートが目的地への最短距離である可能性が高いかを示唆し、リーダーの意思決定を支えます。
第三の価値は、変革への合意を形成するための「共通言語」としての役割です。いかに優れた戦略を描いたとしても、それが組織のメンバーに理解され、共感されなければ、変革のエネルギーは生まれません。特に、既存のやり方を変えようとすれば、必ず抵抗が生まれます。その際、データは強力な武器となります。
白書の相関分析によれば、「結果の共有レポーティング」という活動は、「経営層との意思疎通・協力関係の構築」と強い正の相関(r=.66)があることが示されました。これは、データがただの報告資料ではなく、感情的な対立や立場の違いを超えて、客観的な事実に基づいた建設的な議論を促す「共通言語」として機能していることを意味します。リーダーが自らのビジョンを、データという誰もが理解できる言葉で語るとき、それはトップダウンの指示ではなく、組織全体を巻き込む説得力のある物語へと昇華されます。
眼鏡として組織の今を正しく見つめ、羅針盤として未来への仮説を立て、共通言語として変革への道のりを共に歩む仲間を増やす。データという参謀は、リーダーの孤独な決断を、組織全体の知性が結集した、より確かなものへと変えていきます。
「孤独」から「共創」へ
データという参謀を得たとき、リーダーシップのあり方が変容を迫られます。もはや求められるのは、唯一の正解を指し示す者としてのリーダーではありません。自らも完璧ではないことを認め、組織が直面する複雑な問いに対して、データを通じて組織全体の知性を引き出し、共に答えを探求していく「ファシリテーター」としての役割が重要性を増してきます。ここにおいてリーダーの役割は、答えを与えることから、「良質な問い」を立てることにシフトします。
このリーダー像は、理想論ではありません。白書の分析結果が、その有効性を裏付けています。今回の重回帰分析において、データ活用の成果と最も強く関連する組織文化は何かを探ったところ、示唆に富む結果が示されました。「従業員参加型のマネジメントスタイル」が、データ活用の成果と統計的に有意な正の相関関係にあったのです。これは、経営層がビジョンを示しつつも、管理職や従業員との協議を経て結論を出すという、ボトムアップの意見を尊重する組織文化を持つ企業ほど、データ活用が成功しやすいことを意味しています。
この結果が物語るのは、データ活用の本質が、トップダウンの指示とボトムアップの現実を、データという共通言語でつなぎ合わせ、組織的な対話と学習を生み出すプロセスにあるということです。リーダーが「我々の組織のエンゲージメントを高めるには、何が鍵となるだろうか」という問いを立てる。現場は、データ分析を通じて「若手層のキャリア展望の欠如がエンゲージメント低下の要因ではないか」という仮説を提示する。そのデータをもとに、リーダーと現場が対話し、共にキャリア支援の施策を考え、実行し、その効果を再びデータで検証する。
このような対話のサイクルが、組織を「学習する組織」へと変化させていきます。リーダーは、この学習サイクルを設計し、促進する触媒となります。そのとき、意思決定の重圧という「孤独」は、組織全体で未来を創り出す「共創」の喜びに変わっていくのではないでしょうか。
人や組織に関するデータは、時にリーダーに厳しい現実を突きつけます。しかしそれは、リーダーを追い詰めるためのものではありません。むしろ、その事実は、リーダーを経験と勘に頼る意思決定の孤独から解放し、組織をより良い未来へと導くための武器となります。データを「管理の道具」ではなく「対話の共通言語」と捉えるとき、それは組織内の信頼を醸成し、これまで見えなかった可能性の扉を開くでしょう。
リーダーの孤独は、組織の孤独でもあります。リーダーが一人で悩み、決断する組織では、従業員もまた、自らの声が届かないという孤独を感じています。人事データ活用には、その二つの孤独をつなぎ、組織を「共創」の舞台へと変えるポテンシャルがあります。本白書が、多くのリーダーにとって、その挑戦を始めるための一助となることを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。