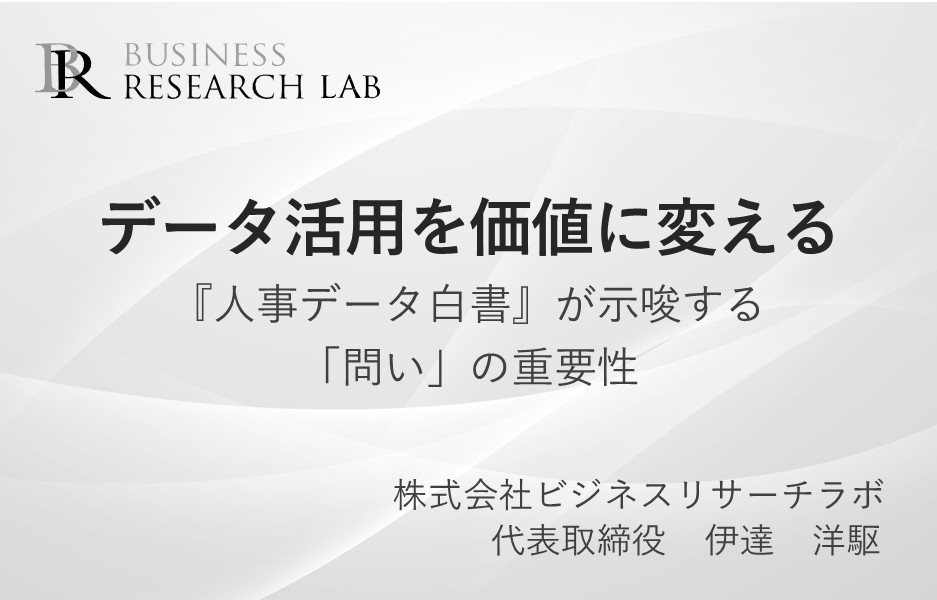2025年9月5日
データ活用を価値に変える:『人事データ白書』が示唆する「問い」の重要性
私たちビジネスリサーチラボは『2025年版 人事データ白書』を公開しました。本調査の実現にあたり、貴重な時間と知見をご提供くださった人事担当者の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。皆様から寄せられたデータは、現代の日本企業における人事データ活用の「現在地」を、解像度高く映し出してくれました。
白書が描き出した日本企業の平均的な姿は、一言で言えば「過渡期」です。給与計算や勤怠管理といった、いわば「守り」のデータ活用は多くの企業で定着し、業務効率化に貢献しています。しかし、そのデータを分析し、人材育成や組織開発といった未来への競争力につなげる「攻め」の活用へと転換する段階で、多くの企業が共通の壁に直面している実態も明らかになりました。高機能なシステムを導入し、膨大なデータを収集したものの、その先の一歩が踏み出せない。データという広大な海を前に、どこへ向かえば良いのか分からずにいる。そんな感覚が、多くの組織を覆っているのかもしれません。
この停滞から抜け出し、データ活用を組織の力へと変える鍵は、どこにあるのでしょうか。本コラムでは、分析の精度を上げることに加えて、データを通じて「組織の対話の質」を高めることに注目したいと思います。データは、組織が自らを客観的に見つめ、未来について語り合うための共通言語となり得ます。白書の分析結果を紐解きながら、データ活用を価値へと昇華させる、組織的な対話のプロセスについて考察していきます。
データが活用しきれない情報になる理由
データは、それ自体が直ちに価値を持つわけではありません。どのような光を当てるかによって、それは輝く宝石にもなれば、意味を見出せない石の集まりにもなり得ます。データ活用の成否を分ける要因の一つは、データをどう扱うかという「問い」の存在です。良質な問いがなければ、データは意味をなしません。
データ活用の道のりにおいては、時にそのポテンシャルを十分に引き出せないアプローチが見受けられます。白書の自由記述に寄せられた声の中にも、多大な労力をかけた取り組みが、期待した成果に結びつかなかったという経験談が散見されました。それらの経験から学ぶことで、私たちはデータとのより良い向き合い方を見出すことができます。
例えば、データ活用の出発点として、「目的不在型」のアプローチがあります。これは、「とりあえずデータを集めたので、何か面白い分析をしてほしい」というように、探求の目的が明確でないまま分析を始めようとするケースです。データ活用への期待感はありながらも、それを組織のどの課題解決に結びつけるのかという議論がなされないままでは、分析担当者はどこに向かうべきかを見失ってしまいます。
白書には、数千人の従業員を対象に何年もアンケートを実施したものの、集まったデータをどう扱えば良いかわからず、定型的なレポート作成に終始し、やがて活用されなくなったという声が寄せられました。これでは、データは数字の羅列に留まり、価値ある知見が生まれることは難しいでしょう。分析チームのモチベーションを維持することも困難になります。
「手段先行型」のアプローチも、同様の課題につながることがあります。「高機能なタレントマネジメントシステムを導入したのだから、とにかくこれを使いたい」というように、手段の活用が目的化してしまう状況です。優れた道具も、何のために使うのかという目的、すなわち「解くべき問い」がなければ、その真価を発揮することはできません。目的と合わない道具を無理に使うことは、現場に新たな混乱と負担を生じさせる可能性もあります。
白書に寄せられた声の中には、最新システムを導入したにもかかわらず、現場の業務フローは旧態依然のままで、結局は個人の経験や勘に頼った意思決定が行われている、というものもありました。これは、投資の正当性を後付けで証明しようとするあまり、本来の目的を見失ってしまうという本末転倒な状況と言えるかもしれません。
「他社事例参照型」のアプローチも挙げられます。「他社がやっているピープルアナリティクスを、うちでも導入してほしい」といったケースです。他社の成功事例に学ぶことは重要ですが、その背景にある経営課題や組織文化といった、その企業ならではの文脈を考慮せずに模倣するだけでは、多くの場合うまくいきません。
自社の状況から切り離された問いは、現場の共感を得ることが難しく、「なぜ、それを我々がやる必要があるのか」という素朴な疑問を生みます。結果的に、データ活用は「自分ごと」として捉えられにくくなり、組織に変革をもたらすことなく形骸化してしまう可能性があります。これは、自社の課題と向き合うという本質的なプロセスを省略し、手軽に見える解決策に頼ろうとする姿勢の表れとも言えます。
これらのアプローチに共通するのは、データ活用に対する考え方、すなわち「我々は何のためにデータと向き合うのか」という問いかけが、組織の中で十分に共有されていない点です。データは万能の解決策ではなく、組織が自らの課題と向き合い、より良い未来を構想するための鏡です。その鏡に何を映し出すのかを定めることから価値創造は始まります。
価値創造の起点となる「良質な問い」の構造
組織を動かし、成果へと導く「良質な問い」とは、どのようなものでしょうか。それは、分析のきっかけとなるだけでなく、組織のエネルギーを結集させ、価値創造のプロセスを駆動させる力を持っています。白書の分析結果は、その構造を三つの側面から示唆しています。
第一に、良い問いは「経営課題」に接続されています。白書の重回帰分析では、「人事データ分析活用の目的の広さ」が「データ活用の成果実感」と統計的に有意な正の関連を持つことが明らかになりました(β=.23)。データ活用を何のために行うのかという目的意識が明確であるほど、成果に結びつきやすいという事実を示しています。
良質な問いは、「なぜ、今それが重要なのか」という問いに、経営の言葉で答えることができます。例えば、「3年後の事業拡大を見据え、次世代リーダー層の育成が急務である。そのために、現行の育成プログラムが、将来リーダーに求められるコンピテンシーの獲得に本当に貢献しているのかをデータで検証したい」といった問いは、人事部門の課題であると同時に、経営全体の課題でもあります。
このように、人事の取り組みを経営アジェンダの中に位置づける問いは、経営層からの理解と支持を得やすく、必要なリソースの確保にもつながります。人事施策の価値を、コストではなく「未来への投資」として語ることを可能にするのです。
第二に、良質な問いは「検証可能な仮説」へと変換されます。白書の調査では、多くの企業が「データは収集しているが、分析はしていない」という状態にあることが示されました。この背景には、「問うべきことが具体的でないため、分析のしようがない」という現実があるのかもしれません。
良質な問いは、漠然とした問題意識から一歩踏み込み、具体的な分析計画に落とし込める解像度を持っています。例えば、「若手の離職が増えている気がする」という問題意識を、「入社3年目までの社員の離職理由は、配属部署の上司のマネジメントスタイル(例:1on1の頻度、フィードバックの質)と関連があるのではないか」という検証可能な仮説の形に変換するのです。この仮説があれば、「上司のマネジメントスタイルを測定するサーベイデータと、人事基本情報を紐づけて分析する」といったアクションへとつながります。
このように、問いを仮説へとシャープにすることで初めて、データは意味のある分析対象となり、根拠に基づく議論が可能になります。このプロセスは、問題の本質を思考する訓練でもあり、組織の分析能力を高めることにも貢献するでしょう。
第三に、良質な問いは「組織の物語」へと昇華します。白書の相関分析によれば、「結果の共有レポーティング」という活動は、「経営層との意思疎通・協力関係の構築」(r=.66)や「部門間・従業員間のコミュニケーションの活性化」(r=.66)といった成果と強く結びついていました。これは、データが組織の対話を促す「触媒」として機能していることを示唆しています。
良質な問いは、その答えを探求するプロセスが、組織内に新たなコミュニケーションを生み出す「物語」の力を持っています。例えば、「どうすれば、我々の組織はもっと部門の壁を越えた協業を促進できるか」という問いを立て、社内コミュニケーションツールの利用ログを分析したとします。その分析結果は、ただの数字の報告書として共有されるだけではありません。
「A事業部とB事業部の間では、このプロジェクトをきっかけにコミュニケーションが活発化し、新たなアイデアが生まれている。この成功の背景には何があるのだろうか」といった、人々の心を動かし、次のアクションを喚起するストーリーとして語られるべきです。データに文脈と意味を与え、共感を呼ぶ物語として語ること。問いが魅力的であればあるほど、多くの人々が「自分ごと」としてその探求の物語に参加し、組織全体を巻き込むうねりを生み出すことができます。
「問い」を組織の力に変える対話の技術
価値ある問いを立てることは、変革の始まりに過ぎません。その問いを組織全体の力へと変えていくためには、多様な視点や意見を尊重し、建設的な議論を育む「対話」が求められます。データは、対話を豊かにするための共通言語となります。
良質な問いを立てて分析を進めても、組織には様々な反応が生まれます。白書では、データ活用への「積極性」と「抵抗感」が必ずしも相反するものではなく、両方が同時に高く存在する「抵抗積極タイプ」という企業群の存在が明らかになりました。この事実は、変革を目指す際には、異なる意見や視点が生じるのが自然な状態であることを示唆しています。大切なのは、それを乗り越えるべき障害としてのみ捉えるのではなく、組織が持つ多様な視点を含む資源として受け止め、対話のエネルギーに変えていくことです。
例えば、データに基づいた新しい人事施策に対して現場から懸念の声が上がった場合、その背景にある「これまでのやり方で大切にしてきた価値観」や「新しいプロセスへの具体的な不安」に真摯に耳を傾ける。そして、その懸念を解消するために、どのような追加データが必要か、あるいはどのような移行プロセスが考えられるかを共に議論する。このような対話の場を設計することが、組織全体の納得感を醸成する上で重要になります。抵抗感は、見方を変えれば、変革をより良いものにするためのフィードバックであり、対話の出発点です。
対話のプロセスにおいては、データという「事実」と、現場で長年培われてきた「経験知」が交差します。この二つは、時に異なる結論を示唆することがあるかもしれません。しかし、その違いを不毛な対立で終わらせるのではなく、より高次の解決策を生み出す「健全な衝突」へと導くことが可能です。
例えば、データ分析の結果が「Aという施策が有効である」と示唆したとしても、現場の管理職は「自分の経験上、Bという施策の方が効果的だ」と感じるかもしれません。ここで重要なのは、どちらが正しいかを決めることではありません。「データが示す傾向と、あなたの経験が示す洞察には、どのような背景の違いがあるのでしょうか」「この二つの知見を統合し、我々の組織にとって最適なアプローチを導き出すことはできないだろうか」と問いかけるのです。
このような対話を通じて、データだけでは見えなかった文脈的な要因が明らかになったり、経験知だけでは気づけなかった新たな可能性が発見されたりします。データと経験知を相互に尊重し、対話を通じてぶつけ合うことで、組織の意思決定はより立体的で強靭なものになります。
こうした対話の積み重ねが、組織を「学習する組織」へと進化させていきます。白書の分析結果から「従業員参加型のマネジメントスタイル」が成果と関連している(β=.12)ことが示されたのは、示唆に富んでいます。データ活用の最終的なゴールは、特定の問いに答えを出すことだけではありません。
データに基づいた対話を通じて、組織自身が環境の変化を察知し、自らの課題を発見し、集合的な知性で解決策を模索し、行動し、その結果から学ぶ。この自己変革のサイクルを回し続ける能力を身につけることが、本来の目的と言えるでしょう。データ活用は、学習プロセスを加速させるための原動力となります。データを通じて対話する文化が根付いた組織は、変化に対してしなやかに適応し続けることができるはずです。
白書は組織の対話を生む「問いの手引き」
本コラムでは、人事データ活用の本質が、問いを立て、データに基づいた対話を通じて、組織の集合知を高めていくプロセスであることを論じてきました。データは、分析の対象であると同時に、組織のコミュニケーションを活性化させ、これまで見えなかった課題や可能性を照らし出すものでもあります。その可能性を最大限に活用するためには、技術的なスキルだけでなく、多様な人々を巻き込み、建設的な対話を育むという能力が求められます。
その意味で、私たちが刊行した『2025年版 人事データ白書』は、唯一の正解が書かれた「答えの書」ではありません。皆様の会社が自らの「問い」を発見し、組織の対話の質を高めるためのヒントが詰まった「手引き」として活用していただきたいと願っています。白書には、多くの日本企業がどのような道のりを歩み、どのような成果や課題に直面しているのかが、客観的なデータとして記されています。他社の経験から学ぶことは、自社の状況を相対化し、次の一手を構想するための材料となるでしょう。
皆様の組織は今、どのような対話を必要としているでしょうか。その対話を生み出すために、どのような問いを立てるべきでしょうか。ぜひ白書を手に取り、皆様の組織の対話を、より豊かなものにするきっかけとしてご活用いただければ幸いです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。