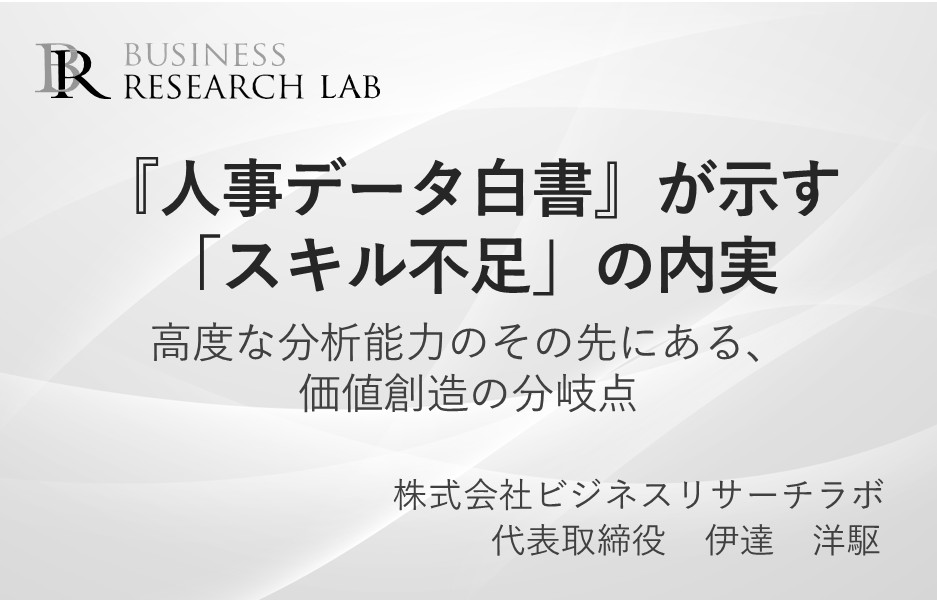2025年9月1日
『人事データ白書』が示す「スキル不足」の内実:高度な分析能力のその先にある、価値創造の分岐点
2025年8月に、私たちビジネスリサーチラボは『2025年版 人事データ白書』を公開しました。全国の人事担当者の皆様から寄せられた貴重なデータは、日本企業における人事データ活用の「現在地」を映し出しています。多くの企業で給与計算や勤怠管理といった「守り」のデータ活用は定着しつつあるものの、人材育成や組織開発といった未来を創る「攻め」の活用へと転換する段階で共通の壁に直面しています。その中でも大きな課題の一つとして、7割以上の企業が挙げたのが「分析に必要な人材・スキルの不足」でした。
しかし、この「スキル」とは何を指すのでしょうか。統計ツールを使いこなす能力のことでしょうか。もしそうであれば、なぜ専門家を配置してもプロジェクトが停滞し、現場からは「数字だけでは分からない」という声が上がるのでしょうか。実は、この「スキル不足」という言葉の裏には、より本質的な能力に関する論点が含まれています。
本コラムでは、白書のデータを紐解き、特に注目すべき少数派の企業群が示す分析結果を手がかりに、「スキル不足」の内実について考察します。そして、これからの人事に求められる「高度な分析能力」と、その先にある「もう一つの能力」について論じ、データ活用の課題を乗り越えて、組織を新たなステージへと導くための視点を提示したいと思います。
なぜ「スキル」をめぐる議論はすれ違うのか
人事データ活用の現場を訪れると、必ずと言っていいほど話題にのぼるのが「スキル」の問題です。今回の『人事データ白書』でも、その実態は数字として表れました。「74.6%の人事担当者が何らかの形で人材やスキルの不足を課題として認識している」という事実は、この問題がいかに多くの企業にとって深刻かつ共通の課題であることを示しています。
議論の前提として、明確にしておきたい点があります。それは、経営を動かし、組織を変えるような示唆を得るためには、統計解析などの高度な専門スキルが必要であるということです。中途半端な分析は、結果の意味を取り違えたり、見せかけの関連性に飛びついたりすることで、誤った結論を導き、組織をミスリードする危険があります。
そのことを裏付けるデータが、白書の分析の中に存在します。今回の調査では、潜在プロフィール分析という手法を用いて、企業をデータ活用への姿勢に基づき四つのタイプに分類しました。その中で、全体の約9%という少数派ながら、最も注目すべき存在が「抵抗積極タイプ」です。このタイプは、データ活用への「積極性」と組織からの「抵抗感」が共に突出して高いという、一見すると矛盾した特徴を持っています。通常であれば、これほど強い逆風の中では成果を出すことは困難だと思われます。
しかし、現実は異なる様相を呈しています。「抵抗積極タイプ」は、データ活用による成果の実感度が他のどのタイプをも上回っていたのです。例えば、データ活用による離職率の改善について、「非常に良くなった」と回答した割合は、このタイプでは65.5%に達します。これは、円滑にデータ活用が進んでいるはずの「積極活用タイプ」の10.0%という数値を大きく超える結果です。
この傾向は離職率に留まりません。「人材育成の効果」が「非常に良くなった」と回答した割合は72.4%、「コミュニケーションの活性化」では69.0%と、多岐にわたる項目で他のタイプを圧倒する成果を実感していることが明らかになりました。
なぜ、「抵抗積極タイプ」はこれほどの成果を手にすることができるのでしょうか。その背景に、高い専門スキルがあることがわかりました。抵抗積極タイプは、「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合が69.0%にのぼり、他タイプを大きく引き離していました。
さらに、「集計や分析の結果を参照・解釈し、実務に活かすノウハウ」が「豊富にある」と回答した割合も65.5%に達しており、高度な知識とそれを応用する実践力を兼ね備えていることがうかがえます。卓越した成果を上げるためには、高度な分析スキルが基礎となることを、この結果は表しています。
しかし、ここで一つの問いが生まれます。もし高度な分析スキルこそが成功の鍵なのであれば、なぜ多くの企業では、分析スキルを持つ人材を育成・採用しても、必ずしもこれほどの成果には結びつかないのでしょうか。高いスキルを持つ専門家が、現場から「数字しか見ていない」と敬遠されたり、経営層に「結局どうすればいいのか」と問われて言葉に詰まったりする光景は、決して珍しいものではありません。
白書では「スキル不足」以外にも、「具体的な活用イメージの欠如」(70.5%)や「ROIの不透明さ」(71.8%)といった課題が上位に挙がっています。これらの課題は、分析スキルそのものというより、分析から得られた知見をいかに組織の価値に結びつけるか、というプロセスに困難が存在することを示唆しています。卓越した分析スキルに加えて、もう一段階別の能力が求められるのではないでしょうか。それこそが、価値を創造する上で分岐点となるのかもしれません。
分析スキルを「組織の価値」に転換する翻訳能力
高度な分析スキルは、価値ある知見を得るための手段です。しかし、分析から得られた知見を、組織の誰もが価値を認める施策へと展開し、実行に移さなければ、ビジネスとしての成功には至りません。この展開・実行のプロセスが、私たちが「翻訳スキル」と呼ぶものです。高度な分析スキルを前提とした上で、そのアウトプットを十分に活用し、組織のエネルギーに変える能力。その重要性は、白書の分析結果にも表れています。
白書の相関分析によれば、「データ活用による成果」と最も強い正の相関を示したのは、やはり「人事の分析スキル知識」(r=.78)でした。しかし、注目すべきは、それに僅差で続いたのが「結果の共有レポーティング」(r=.77)であったという事実です。これは、高度な分析能力(スキル)と、それを組織に展開し、対話を生み出す活動(翻訳)が、成功のために重要な二つの要素であることを意味しています。この両輪を回すために必要な三つの翻訳能力について考えていきましょう。
一つ目は、「経営課題」を「分析計画」に翻訳する力です。経営層が語る「最近、若手のモチベーションが低いようだ」という漠然とした問題認識を、そのまま受け取るだけでは不十分です。それを、「どの部門で、どのような業務に従事する、入社何年目の社員の、エンゲージメントサーベイのどの項目が、どのような要因と関連して低下しているのか」といった、データで検証可能な「分析の問い」へと変換しなくてはなりません。
さらに、その問いに答えるためには、どのようなデータを収集し、どのような高度な分析手法(例えば、白書でも用いている重回帰分析やESEM、潜在プロフィール分析など)を用いるべきかという、具体的で実行可能な「分析計画」にまで落とし込む能力が求められます。高度な分析手法を知っているからこそ、どの課題にどの手法が最適かを見極めることができるのです。
白書では、今後強化したい領域として「評価・タレントマネジメントの高度化」(54.1%)や「採用の高度化」(51.8%)が上位に挙がりました。多くの企業がこうした人事課題を認識していますが、それを具体的な分析計画にまで落とし込む「翻訳」の段階でつまずいているケースは少なくないでしょう。白書の重回帰分析においても、「人事データ分析活用の目的の広さ」(β=.23)が成果実感と統計的に有意な関連を示していました。これは、分析の目的を設定するという翻訳能力が、成果に直結することを示唆しています。
二つ目は、「統計的事実」を「組織の物語」に翻訳する力です。高度な分析から得られたアウトプットは、しばしば専門的で難解なものになります。例えば、「ESEMの結果、データ活用への姿勢は『積極性』『抵抗感』『模索』の3因子で説明され、成果実感には『積極性』因子が強く影響していました」という統計的事実をそのまま伝えても、多くの人の心には響きません。
この事実を、経営層や現場の管理職が直感的に理解し、自分たちの課題として受け止められるような、組織の文脈に沿った「物語」として再構築する能力が必要です。分析が高度になればなるほど、専門家と非専門家の間の知識の断絶は広がります。だからこそ、翻訳の価値は増すのです。
白書の付録2「現場の声にみるデータ活用の光と影」には、「当たり障りのないレポートをまとめるだけに終わり、成果が出ないまま廃止に至った」という失敗事例が寄せられています。これはまさに、統計的な事実を組織の物語へと翻訳できなかった結果と言えるでしょう。白書の相関分析で、「結果の共有」が「経営層との意思疎通・協力関係の構築」(r=.66)や「部門間・従業員間のコミュニケーションの活性化」(r=.66)といった成果と強く結びついているのは、データを通じて語られる物語が、組織の対話を促す「触媒」として機能していることを示唆しています。
三つ目は、「分析的インサイト」を「組織の行動」に翻訳する力です。分析からどれほど鋭い洞察(インサイト)が得られても、それが具体的なアクションに結びつかなければ意味がありません。「分析の結果、上司との1on1の頻度が定着率と相関していました」という発見で終わらせず、「そこで、来月から各部署でこのような目的とアジェンダで1on1を実施しませんか。まずはA事業部で試験導入し、3ヶ月後に効果検証しましょう」と、現場が実行可能なプランに落とし込む。さらには、その施策に必要な投資の妥当性を、予測される効果(ROI)と共に経営陣に説明し、組織的な合意を形成して変革を推進していく。この一連のプロセスを主導する能力が求められます。
白書のデータを見ると、「経営層・管理職に向けた、定期的(半期/年次ペース)の分析レポートの提出」を実践している企業は7割以上にのぼる一方、「部署や現場レベルで分析結果を共有し、意見交換する仕組みや機会の設計」を精力的に実施している企業は14.0%に留まります。このギャップは、分析的インサイトが現場の行動にまで十分に翻訳されていない実態を示唆しているのかもしれません。
白書によれば、データ活用が進んでいる企業ほど、「ROIの不透明さ」や「予算の制限」を「大きな課題」として強く認識する傾向が見られました。分析が高度化し、投資額が増えるに伴い、その価値を経営陣に説明し、組織を動かすという「翻訳」の難易度と重要性が増していることを指しています。
「分析の専門家」と「変革の翻訳家」
ここまで論じてきたように、これからの人事に求められるのは、高度な分析スキルを持つ「専門家」としての顔と、その知見を組織の力に変える「翻訳家」としての顔、その両方を兼ね備えることです。分析に終始し、専門的なレポートを作成するだけでは、組織を変えることは難しいでしょう。一方で、客観的な根拠を欠いたままでは、現場の協力を得て施策を推進することは困難です。
この二つの役割の重要性は、白書の重回帰分析の結果からも裏付けられます。分析の結果、「データ活用の成果実感」に対して、「人事の分析スキル・知識」(β=.41)と「データ分析結果の共有・レポーティング」(β=.28)の両方が、それぞれ独立して統計的に有意な正の影響を与えていることが明らかになりました。専門家としての能力と、翻訳家としての活動が、両方揃って成果が最大化されることを示唆しています。
この二つの役割を高いレベルで実践している理想像が、再び白書に登場する「抵抗積極タイプ」なのかもしれません。このタイプでは、高い専門スキルを武器に、強い「抵抗」という厳しい現実と向き合い、データという客観的根拠をもって粘り強く対話を重ね、組織を動かしてきたはずです。そのプロセスが分析能力と翻訳能力を同時に鍛え上げたのではないでしょうか。このタイプが直面する「抵抗感」の大きさと、それを乗り越えて得られる「高い成果」のコントラストが、二つの能力を兼ね備えることの価値を表しています。
データ活用は、ただの業務改善ツールではありません。組織の文化を変革する営みです。白書の重回帰分析の結果、「従業員参加型のマネジメントスタイル」(β=.12)が成果にプラスに働き、「経営層の一方的な意思決定」(β=-.09)がマイナスに働くことが示された事実は、示唆に富んでいます。データ活用は、トップダウンの指示とボトムアップの現実をデータという共通言語でつなぎ、協調的な組織文化を育む中で、その真価を発揮するのです。
また、白書の分析では、「専任の人事部門がある」企業ほど、データガバナンスの整備や戦略的システムの導入が進んでいることも明らかになっています。人事部が専門性を高め、組織の変革を担うハブとなることの重要性は、データの上からも明らかです。そのプロセスにおいて、人事部は経営と現場の間に立つ「変革のハブ」としての新たなアイデンティティを確立するための機会を手にしていると言えるでしょう。
二つのスキルを磨くための教科書に
「スキル不足」という、多くの企業が直面する課題。その本質は、分析能力の欠如に留まりません。第一に、統計的に意味のあるインサイトを導き出すための「高度な分析能力」を習得し、第二に、それを組織の価値へと転換させる「翻訳能力」をも身につけるという、人事部に課せられた二重の、そしてやりがいのある挑戦です。
二つのスキルをいかにして獲得し、組織の中で実践していくか。そのヒントとなるデータが、この『2025年版 人事データ白書』にはたくさん含まれています。他社がどのようなスキルを課題とし(第1章)、どのような組織体制で(第3, 4, 5章)、どのような成果と課題に直面しているのか(第1, 10章)。成果の裏にある構造的なメカニズムはどのようなものか。本コラムでも触れた相関分析や重回帰分析(第7, 8章)、統合的なESEM(第9章)は、データ活用の成功構造を理解する上で多くの示唆を与えてくれます。また、自社がどの成長段階にあるのかを客観視するためには、第10章のタイプ別分析が有効なフレームワークとなるでしょう。
ぜひ『2025年版 人事データ白書』を手に取り、皆様の会社が「分析の専門家」と「変革の翻訳家」という二つの顔を併せ持つ、人事機能を発展させるための参考として、ご活用いただければ幸いです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。