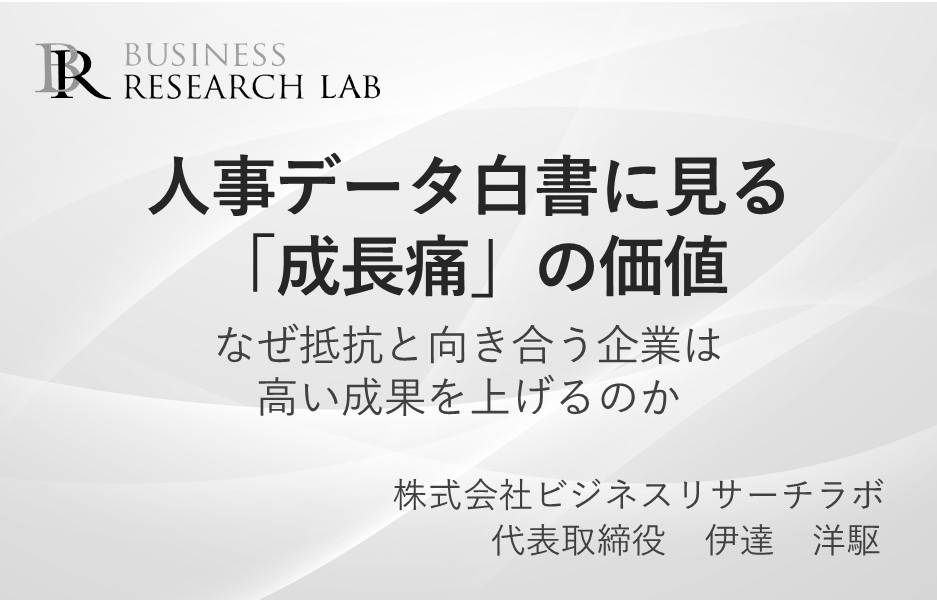2025年8月29日
人事データ白書に見る「成長痛」の価値:なぜ抵抗と向き合う企業は高い成果を上げるのか
このたび、私たちビジネスリサーチラボは『2025年版 人事データ白書』を公開しました。本調査は、現代の企業経営において重要性を増す人事データの活用について、その実態と構造を多角的に分析したものです。調査にご協力いただいた多くの人事担当者の皆様から寄せられた貴重なデータは、日本企業が置かれた状況を映し出してくれました。
調査結果を概観すると、多くの企業がデータ活用の「過渡期」にあるという共通の姿が浮かび上がります。給与計算や勤怠管理といった、いわば「守り」のデータ活用は多くの企業で定着し、業務効率化に貢献しています。しかし、そのデータを分析し、人材育成や組織開発、採用強化といった未来への競争力につなげる「攻め」の活用へと転換する段階で、多くの企業が共通の壁に直面している実態も明らかになりました。事実、「分析に必要な人材・スキルの不足」は、7割以上の企業が認識する最大の課題となっています。
全体の傾向を把握し、自社の立ち位置を客観的に知ることは、次の一手を考える上で不可欠です。しかし、平均的な姿を眺めるだけでは、この過渡期という霧を抜けるための示唆を得ることは難しいかもしれません。私たちが分析を深める中で見えてきたのは、平均像からはこぼれ落ちてしまう、示唆に富んだ少数派の企業群の存在でした。本コラムでは、特に注目すべきその一群の姿を深掘りすることで、データ活用をめぐる課題と、それを乗り越えるためのヒントを探っていきたいと思います。
理想とされる「円滑な推進」が意味するもの
人事データ白書の分析では、人事データ活用への企業の取り組み方を、その背後にある姿勢やマインドセットに基づいて、四つの異なるタイプに分類しました。一つ目は、データ活用への関心・取り組み共に低調な「未活用タイプ」。二つ目は、意欲はあるものの組織内の抵抗やスキル不足に直面する「抵抗模索タイプ」。三つ目は、組織的な抵抗が少なく、安定的にデータ活用を実践する「積極活用タイプ」。四つ目は、強い推進力と組織からの強い抵抗が激しく衝突する「抵抗積極タイプ」です。
この中で、多くの企業が理想的な状態として目指すのは、おそらく「積極活用タイプ」でしょう。このタイプに属する企業は、組織的な抵抗が少なく、経営層から現場までが一体となってデータ活用を推進している、いわば円滑な運用が実現できている状態です。実際に、積極活用タイプは安定的に成果を創出しており、データ活用が組織に定着した一つの形にあることは間違いありません。予測可能性が高く、安定した組織運営を志向する上で、この状態が魅力的に映るのは当然のことと言えます。
しかし、組織変革という少し異なる視点からこの状態を眺めてみると、一つの論点が浮かび上がります。抵抗が少ないという事実は、裏を返せば、既存の価値観や力関係を揺るがすような、本質的な課題への挑戦を保留にしている可能性を示唆していないでしょうか。もちろん、無用な摩擦は避けるべきです。しかし、変革はしばしば心地よい現状維持の姿勢を打ち破ることから始まります。組織がこれまで目を向けてこなかった領域に光を当てようとすれば、そこには何らかの抵抗が生まれるのが自然とも言えます。
ここで言う「改善」と「変革」は似て非なるものです。改善が既存のプロセスの延長線上にある連続的な進歩であるとすれば、変革は既存の枠組みそのものを問い直す非連続的な飛躍を意味します。「改善」は望ましいものですが、時にそれは痛みを伴う「変革」の機会と引き換えになることがあります。円滑な推進という安定が、より大きな飛躍の可能性を無意識のうちに手放すことにつながってはいないか。この点を念頭に、本コラムでは、最も困難な道を歩んでいるように見える、もう一つの興味深いタイプに光を当ててみたいと思います。
「抵抗積極タイプ」の掘り下げ
人事データ白書の中で、全体の8.5%を占める少数派でありながら、私が注目したいのが「抵抗積極タイプ」です。この企業群の姿は、一見すると矛盾に満ちています。その特徴を示す因子得点を見ると、データ活用への前向きな意欲やスキル、行動を統合した「積極性」が全タイプの中で突出して高い一方で、データ活用への懐疑的な見方やトップダウン文化といった障壁を示す「抵抗感」もまた高い数値を示しています。組織内には強い推進力と、それに反発する力が同時に存在し、せめぎ合っている状態にあるのです。
通常、これほど強い逆風に晒されれば、取り組みは頓挫してしまうか、少なくともその成果は限定的なものになると考えるのが普通です。しかし、データが示した現実は、私たちの直感を裏切るものです。抵抗積極タイプの企業がデータ活用によって実感している成果の度合いは、他のどのタイプをも圧倒していました。
例えば、データ活用による離職率の改善について、「非常に良くなった」と回答した割合は、このタイプでは65.5%に達します。これは、円滑に進んでいるはずの「積極活用タイプ」の10.0%という数値を凌駕するものです。人材育成の効果(72.4%)やコミュニケーションの活性化(69.0%)といった項目でも、同様に他を圧倒する成果を上げていました。
なぜ、最も困難な状況に置かれた抵抗積極タイプが、最も高い成果を手にすることができるのでしょうか。この逆説的な関係性の背景には、いくつかのメカニズムが働いていると推察されます。
一つ目の可能性は、抵抗積極タイプが取り組んでいる「課題の質」が異なるという点です。抵抗が少ない「積極活用タイプ」が主に取り組むのが、既存業務の効率化といったテーマであるのに対し、「抵抗積極タイプ」は、評価制度の見直しや組織風土の改革といった、より組織の根幹に関わる領域に踏み込んでいるのかもしれません。
人事データ白書のデータを見ても、抵抗積極タイプは「離職防止」や「組織風土改革」といった目的へのコミットメントが強いことがわかります。こうした組織の「聖域」とも言える領域に踏み込むからこそ、既存のやり方や価値観を持つ人々からの抵抗が生まれる。要するに、抵抗の大きさは、彼ら彼女らが挑んでいる変革の大きさの裏返しであると考えることができます。
二つ目に、その厳しい環境が、結果的に「推進プロセスの質」を高めているという可能性です。強い抵抗に打ち勝つためには、生半可な分析やロジックでは通用しません。「なぜ、そのデータが必要なのか」「その施策にどれほどの投資対効果が見込めるのか」といった厳しい問いに、客観的なデータをもって答え続ける必要があります。そのプロセス自体が、推進担当者の分析スキルや論理構築能力を鍛え上げ、施策の質を磨き上げることにつながります。
実際に、彼ら彼女らの自己評価による分析スキルは高く、例えば「統計学に基づく統計解析の知識」が「豊富にある」と回答した割合は69.0%にのぼり、他タイプを引き離しています。逆境が、優れた実践者に育て上げているのかもしれません。
三つ目に、推進側と抵抗側の衝突が、長期的には「組織学習を促進するエンジン」として機能しているという視点です。短期的に見れば、意見の対立は組織に軋轢を生みます。しかし、その議論の過程で、これまで暗黙のうちに共有されてきた前提が問い直され、「我々にとって本当に大切なものは何か」「どのような組織でありたいのか」といった、より深い対話が組織に生まれるきっかけとなり得ます。
データという客観的な事実と、現場で培われた経験知が健全にぶつかり合うことで、組織はより高い次元での意思決定能力を学習していく。このプロセスが、持続的な競争優位性の源泉となる可能性があります。
組織内に存在する「抵抗」の多面的な理解
データ活用を推進する上で避けて通れない「抵抗」という現象も、その内実を冷静に検討すれば、より解像度高く理解することができます。私は、組織内で見られる抵抗を、その背景にある要因から、いくつかの性質に分けて捉えることができると考えています。
一つは、新しいプロセスへの移行に伴う、心理的な負荷や学習コストへの反応です。これは、現状維持を望む自然な感情から生まれるもので、「やり方を変えるのは面倒だ」「新しいツールを覚える時間がない」といった声として現れます。変化そのものへの適応に関する課題と言えるでしょう。日々の業務に追われる中で、新たな負担が増えることへの純粋な反発であり、丁寧な説明やトレーニングによって緩和できる可能性があります。
二つ目は、現場で長年培われてきた専門性や経験知、いわば職人的な勘が、データによって軽視されることへの懸念やプライドに根差したものです。「現場の複雑な状況は、単純な数字だけでは分からない」「私たちの経験を無視するのか」といった意見は、この性質の抵抗の典型です。これは、データという形式知と、現場の暗黙知との間に生じる衝突と捉えることができます。この種の抵抗は、データ活用が現場の知見を否定するものではなく、その価値を補強し、より確かなものにするためのツールであることを示さなければ、解消は難しいでしょう。
三つ目は、データによる透明性の向上が、既存の意思決定プロセスや組織内の力関係に変化を及ぼすことへの警戒感です。これまで特定の人物や部門が持っていた情報や権限が、データによって相対化されることへの不安が、抵抗の背景にあるケースです。組織内の政治的な力学に関わる、根深い問題と言えます。この抵抗と向き合うことは、データ活用がただの業務改善ではなく、組織のガバナンス改革であることを意味します。
これらの抵抗は、単に乗り越えるべき障害なのではなく、変革を進める上で配慮すべき論点を示唆しています。例えば、二つ目の「経験知とのプライド」は、データ分析の初期段階である仮説構築のプロセスに、現場のキーパーソンを積極的に巻き込むことの重要性を示唆しています。彼ら彼女らの知見は、分析の質を高める上で資源となり得ます。
大切なのは、自社で起きている抵抗がどの性質のものかを見極めることです。その背景にある懸念や不安を理解することが、一方的な説得ではなく、建設的な対話に向けたコミュニケーション戦略を立てるための第一歩となるはずです。
過渡期を乗り越えるための次の一手
「抵抗積極タイプ」の検討から見えてくるのは、変革を志すリーダーの役割の重要性です。彼ら彼女らが見せるリーダーシップは、単にトップダウンで指示を出すスタイルとは一線を画します。むしろ、組織内に存在する抵抗と真摯に向き合い、対話を重ね、変革のエネルギーを組織全体で生み出していく、触媒のような役割を果たしているのではないでしょうか。この過渡期を乗り越えるために、リーダーにはどのような姿勢が求められるのでしょう。
第一に、変革の「目的の明確化と共有」が挙げられます。なぜ今、データ活用に取り組む必要があるのか。それによって、従業員や組織にとってどのような未来が拓けるのか。そのビジョンを、抽象的なスローガンではなく、自社の文脈に沿った具体的な言葉で、粘り強く語り続けることが求められます。目的への共感が、困難なプロセスを乗り越えるための求心力となります。
第二に、「心理的安全性の確保」です。データが、従業員を管理したり、誰かの責任を追及したりするための「監視の道具」ではなく、組織全体で課題を共有し、共に学ぶための「共通言語」であることを、リーダー自らの言動で示す必要があります。データが示した不都合な真実からも目を背けず、失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを称賛する文化を醸成することが、挑戦を促します。イノベーションが試行錯誤から生まれることを考えれば、この文化の重要性は計り知れません。
第三に、「対話の場の設計」が重要になります。抵抗する意見を持つ人々を排除するのではなく、彼ら彼女らを含めた多様なステークホルダーが、同じデータを前にして議論できる場を意図的に設けるのです。データは、感情的な対立を、事実に基づいた議論へと導く力を持っています。リーダーは、その対話を促進するファシリテーターとしての役割を担うことが期待されます。
こうした姿勢を基盤としつつ、より実践的な戦略として、例えば全社展開の前に特定の部門や課題で「パイロットプロジェクト」を実施し、具体的な成功体験と学びを組織で共有することが有効でしょう。また、現場を知り尽くしたキーパーソンを、分析プロジェクトのアドバイザーとして迎え入れ、その知見をプロセスに組み込むことも、抵抗を協力へと転換させる上で一手となり得ます。そして、人事データ白書で最大の課題として挙げられた「分析人材・スキルの不足」に対処するため、計画的な人材育成への投資が不可欠であることは言うまでもありません。
成長痛を伴う推進プロセス
本コラムで深掘りしてきた「抵抗積極タイプ」の検討は、人事データ活用の推進が、不可避的に組織の「成長痛」を伴うプロセスであることを示しています。しかし、その困難と真摯に向き合い、乗り越えようとする試みの中に、より高い成果と組織の成熟につながる道筋が隠されているのではないでしょうか。
その意味で、私たちが刊行した「人事データ白書」は、他社の動向を知るためのベンチマーク資料というだけではありません。ましてや、唯一の正解を示す解答集でもありません。各企業が自社の成長段階と直面する課題を認識し、これから始まる自社の変革の物語をいかに紡いでいくかを構想するために活用していただきたいと願っています。データ活用は人事部門だけのものではなく、組織の未来を左右する経営の課題です。
人事データ白書に記されたデータは、客観的な事実であると同時に、多くの企業が悩み、試行錯誤を重ねているプロセスの記録でもあります。ぜひ白書を手に取り、自社の現在地を確認し、未来への戦略を構想するための一助としていただければ幸いです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。