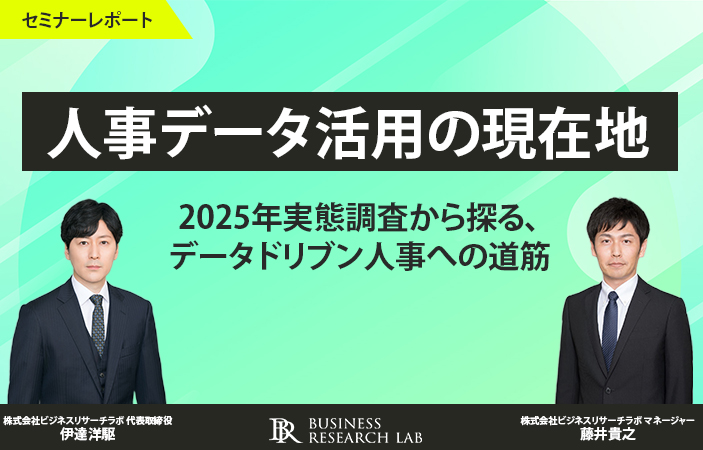2025年8月26日
人事データ活用の現在地:2025年実態調査から探る、データドリブン人事への道筋(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年8月にセミナー「人事データ活用の現在地:2025年実態調査から探る、データドリブン人事への道筋」を開催しました。
人事領域におけるデータ活用への関心が高まっています。多くの企業が取り組みを始める中で、他社の状況や自社の現在地を把握したいというニーズも増しているのではないでしょうか。こうした背景から、株式会社ビジネスリサーチラボでは、企業の人事データ活用に関する調査を実施しました[1]。
調査からは、多くの企業が直面する共通の課題が見えてきます。例えば、データ分析のスキルセットについて尋ねたところ、「データベースの操作」や「結果の可視化」はある程度できるものの、「統計学に基づく解析」のような、より専門的なスキルには課題を感じるという回答が多く見られました。
本セミナーでは、このような分析スキルや体制の実態に加え、データの収集・統合プロセス、レポートの共有範囲、そしてデータ活用によってどのような成果や課題が生まれているのか、調査結果を基に多角的に報告しました。また、情報通信業や製造業といった業種によるアプローチの違いにも光を当て、それぞれの特徴を比較検討しました。
他社の取り組みや課題を客観的なデータで知ることは、自社の戦略を冷静に見つめ直し、次の一歩を具体化するための機会となります。データとどう向き合い、組織の力へと変えていくのか。そのヒントを探りました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
人事データ白書2025:調査の概要とデータ活用の現状
はじめに
藤井:
「人事データ白書2025」は、全国の人事担当者への調査を通じて、日本企業が人事データをどう活用しているか、その成果や課題を分析したものです。少子高齢化による労働力人口の減少、働き方の多様化、激化する人材獲得競争といった環境変化の中で、経験や勘に頼る人事からデータに基づく意思決定(ピープルアナリティクス)への移行は、持続的成長のために欠かせない課題となっています。
実際、国際的な研究でもデータドリブン経営を積極導入している企業はそうでない企業に比べ生産性が高いという結果が報告されており、人事領域でもデータ活用が企業パフォーマンスに直結し得ることが示唆されています。このセミナーでは、こうした背景を踏まえつつ、日本企業の現状をデータで俯瞰し、皆さんの現場でのヒントになる知見を共有したいと思います。
人事データ白書の調査概要
本白書の目的は、日本の企業における人事データ活用の実態を明らかにし、各社が今後取り組みを進める上での指針や示唆を提供することにあります。人事領域でデータ活用の重要性は認識されつつも、「何から手を付ければいいのか」「他社はどの程度進んでいるのか」「投資対効果をどう測るか」など悩みを抱える担当者は少なくありません。
そこで本調査では、データガバナンス体制の構築状況、採用・育成・評価といった各領域での分析活用の実態、担当者に求められるスキル、組織としての課題、データ活用がもたらす成果に至るまで、幅広いテーマを網羅しました。こうした包括的な調査によって、自社の現在地を客観的に把握するベンチマークを提供し、成功企業の共通点や多くの企業が直面する壁を明らかにすることで、今後の戦略立案や課題解決に役立つ情報発信を目指しています。
次に、調査の方法と対象についてご説明します。本調査は2025年6月3日~4日にかけてインターネット調査で実施され、最終的に342名の人事担当者から有効回答を得ました。回答者は従業員100名以上の企業に勤務する人事部門所属の正社員(経営層は除く)で、業種は製造業(33.8%)が最も多く、次いでサービス業(17.4%)、情報通信業(10.3%)、建設業(7.1%)、商社・卸売・小売(6.5%)と続き、特定業種に偏らず幅広くカバーしています。
企業規模も1,000~4,999人が25.7%、5,000人以上が20.8%と大企業が半数を占めつつ、100~199人も18.1%含まれるなど、中堅企業からも広く回答を得ています。また、回答者の役職内訳は一般職担当者が38.6%、管理職が33.3%、部長級が28.1%とバランス良く含まれており、現場レベルの課題感と経営層寄りの視点の両方が反映されたデータと言えます。
このように調査は幅広い企業規模・業種・職位を網羅しており、日本企業全体の傾向を捉えることを意図しています。
人事データ活用の現在地 – 「守り」から「攻め」への移行状況
それでは調査結果に基づき、現状の概要からお話しします。多くの企業では、給与計算や勤怠管理といった従来型の労務管理目的でのデータ収集やシステム導入、いわゆる「守り」のデータ活用はすでに定着しています。
しかし、こうして蓄積したデータをさらに分析し、人材育成や組織開発、採用力強化など将来の競争力につなげる「攻め」の活用へ転じる段階で、多くの企業が壁に突き当たっていることが明らかになりました。そして、この移行を阻む最大の障壁こそが「分析に必要な人材・スキルの不足」であり、実に7割以上の企業がこの課題を認識しています。データという原石は手元にあるものの、それを磨いて価値を引き出す術を持つ人材がいない――まさに多くの企業に共通するジレンマと言えるでしょう。
要するに、人事データ活用の現在地は「守り」はできているが、「攻め」に踏み出す途上にある過渡期だということです。
組織内に共存する「推進力」と「抵抗感」
ここからは、人事データ活用に対する組織の姿勢について注目ポイントをお話しします。データ活用を巡る前向きな推進力と慎重・否定的な抵抗感が社内にどう存在しているかを分析したところ、興味深い結果が得られました。企業のデータ活用への姿勢は「積極性(推進力)」と「抵抗感」という2つの独立した因子に整理できることが示されたのです。
当初は「積極性が高ければ抵抗感は低い」つまり一つの軸上の裏表の関係か、あるいは強い負の相関で別個の2要素になるかと想定していました。しかし蓋を開けてみると、両者の相関はほとんどゼロで、これはデータ活用に積極的な企業が必ずしも抵抗感が低いわけではないことを意味します。言い換えれば、「データ活用を前向きに推進しようとしているが、同時に社内に強い抵抗にも直面している」企業が少なからず存在するということです。
実際、調査では強い推進力と強い抵抗が同居する企業も観測されており、現代の日本企業がデータ活用を巡る過渡期ならではの混乱と、それを乗り越えようとする熱意を内包しているように感じられます。社内には推進派と慎重派のせめぎ合いがあるというのは多くの皆さんも実感があるかもしれませんが、その構図がデータから裏付けられた形です。
ポイントは、抵抗勢力をゼロにするのは難しいにせよ、経営層・現場管理職・人事部門の三位一体で推進力を高め、組織的な対話を促すことが成果につながるという示唆です。これは、「人」と「組織」の成熟度こそがデータ活用成功のカギだという言い方ができるかもしれません。
企業のデータ活用タイプ(4類型)
人事データ活用への取り組み方は企業ごとに様々ですが、本調査では分析の結果、特徴的な4つのタイプに分類できることが分かりました。自社がどのタイプに属するかを知ることが、次の一手を考える出発点になります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 未活用タイプ(46.3%):最も多くの企業が属する「黎明期」で、人事データ活用への関心も取り組みも低調な段階です。何から手を付けてよいか分からず停滞している状態です。
- 抵抗模索タイプ(21.2%):意欲はあるものの、組織内の抵抗やスキル不足という壁に直面する「葛藤期」です。データ活用を推進したい思いと現実とのギャップに苦しんでいる状況にあります。
- 積極活用タイプ(23.2%):組織的な抵抗が少なく、経営層から現場まで一体となって安定的にデータ活用を実践する「実践期」に当たります。既に着実に成果を生み出している段階です。
- 抵抗積極タイプ(9.3%):強い推進力と強い抵抗が激しく衝突する「変革期」です。社内の軋轢を乗り越えながら高い成果を手にしている少数精鋭タイプと言えます。
この分類を見ると、自社がどのポジションかによって抱える課題も異なることが想像できるでしょう。
例えば「未活用」の会社はまず関心喚起や小さな成功体験作りから始める必要があるでしょうし、「抵抗模索」の会社は抵抗勢力との対話やスキル不足解消が急務です。「積極活用」の会社は引き続き成果を伸ばしつつ他社の模範となるケースが増えるでしょう。「抵抗積極」の会社は大きな成果を出す半面、内部対立で組織が疲弊しないよう対話による文化醸成へエネルギーを向けることが持続成長の鍵となります。
人事データ活用で直面する課題
実際に人事データを活用することでどんな成果が出ているのか、そしてどんな課題があると感じられているのかを見てみましょう。
提示した10項目すべてで過半数の人事担当者が何らかの課題を感じているという結果でした。中でも「分析に必要な人材・スキルの不足」が最も強い課題感を持たれており、「少し課題」「まあまあ課題」「大きな課題」を合わせると74.6%もの担当者がスキル不足を問題視しています。
次いで「ROI(投資対効果)の不透明さ」、「データ集計・分析にかかる作業コストの多さ」、「プライバシー・セキュリティへの懸念」といった項目も各合計で7割を超え、費用対効果の不明確さや実務負担、情報管理上の不安が大きな懸念となっていることが分かりました。
さらに「具体的な活用イメージの欠如」(どう施策につなげるか分からない)も70.5%が課題と感じ、「データ品質の問題」も69.0%が課題と回答しています。
組織内の理解不足・抵抗感では、「経営層の理解不足・抵抗」を課題とする声が65.8%なのに対し、「人事以外の現場管理職の理解不足・抵抗」は69.3%とわずかに上回りました。現場管理職との連携不足がデータ活用推進上のより大きなハードルになっている可能性があります。
また「データ活用にかかる予算制限」も67.5%、「成功事例の少なさ」も64.4%が課題と感じており、リソース確保やロールモデル不足も壁になっているようです。
どの項目も「課題を感じていない」と答えた割合は1割未満で、人事データ活用がほぼ共通の課題として広く認識されている状況です。特に人材・スキル不足は突出して深刻な課題として捉えられており、多くの企業が「少し課題」と感じ始めている段階であることもうかがえます。課題は人的資源、コスト、データ品質、組織理解など多岐にわたり、一筋縄ではいかない複雑な状況が示されています
「過渡期」が示す日本企業の現実
以上、見てきたように、多くの日本企業は人事データ活用の重要性を認識し第一歩を踏み出しつつあるものの、本格的な戦略活用には至っていない過渡期にあることがお分かりいただけたかと思います。
従来型の労務管理領域(給与・勤怠など)ではデータ収集やシステム化がほぼ完了し「守り」の活用は定着していますが、収集データを分析して将来の意思決定に活かす「攻め」の活用には領域によって濃淡があり、多くの企業が移行の壁に直面しています。その根底にある最大の壁がやはり「分析人材・スキルの不足」です。
人事担当者はデータベース操作や可視化などの基本スキルはあるものの、統計解析など高度な知識が乏しく、多くが分析業務を他業務と兼任しているのが実情です。経営層や人事部門はデータ活用に高い意欲を示す一方、経営層は旗振り役に徹し実務を担う人事部門のスキルが追いついていないという構造的ギャップもあります。結果として、データ収集・統合プロセスの多くが未だ手作業に頼っていたり、分析結果の共有も経営層への報告止まりで現場管理職を巻き込んだ全社的な活用文化の醸成には至っていないという声も聞かれました。
企業自身もこうした現状を認識しているからこそ、今後の展望として「評価・タレントマネジメント」や「採用」の高度化に注力し、外部の専門支援も積極的に求める声が多数上がったのかもしれません。
最後に、企業がデータ活用を競争力へ昇華させていくために不可欠なのは、トップの方針のもと、専門人材の育成・確保、分析体制の整備、現場を巻き込むリテラシー向上へ本格的に投資し、「意欲」と「実践」の溝を埋めていくことだと考えられます。日本企業の人事データ活用はまさに今、過渡期を乗り越えようとする重要な局面にあり、本日の内容が皆さんの組織で次の一歩を踏み出す一助になれば幸いです。
人事データ活用の専門性と向き合う:社内外の専門家との効果的な協働方法
はじめに
伊達:
人事データの戦略的な活用は競争力の源泉となりつつあります。しかし、その重要性を認識しながらも、多くの企業がデータ分析に必要な専門性の壁に直面しているのが実情です。本講演では、株式会社ビジネスリサーチラボの『人事データ白書』で示した調査結果を基に、人事部門がデータ分析の専門性とどのように向き合い、それを組織の力に変えていくべきか、その方法を探ります。
人事データ活用の実態調査:課題、先進事例、成果を生む要因
人事データ活用を推進する上で、多くの企業が直面する課題や、先進的な企業の取り組み、成果を生み出すための要因は何でしょうか。『人事データ白書』の調査結果は、その実態を浮き彫りにしています。
データ活用を阻む最大の障壁として、多くの人事担当者が「分析に必要な人材・スキルの不足」を挙げています。実に74.6%もの担当者がこれを課題と感じており、データという原石を手にしながらも、それを磨き価値を引き出す術を知る専門家がいないというジレンマが、多くの企業に共通する姿として浮かび上がります。
人事部門が持つスキルを自己評価してもらうと、データベースの操作やデータの可視化といった基礎的なスキルはある程度保有しているものの、特に「統計学に基づく統計解析」のような、より高度で専門的な知識については苦手意識を持つ割合が相対的に高く、いずれのスキル項目においても「豊富にある」という回答は1割程度です。この結果は、多くの企業において、人事データ活用が高度な専門性を要するレベルには至っていない現状を示唆しています。
その一方で、業種によってはデータ活用を戦略的に推進し、競争力へと転換しようとする先進的なアプローチが見られます。とりわけ「情報通信業」「製造業」「金融・証券・保険業」の3業種では、経営層自身がデータ活用の重要性を強く認識し、その推進にリーダーシップを発揮している様子がうかがえます。
経営層が「データ活用を推進しようと努めている」と認識している割合は、情報通信業で54.3%、製造業で63.5%、金融・証券・保険業では66.7%に達します。このトップの強い意志は、体制整備へと結びついています。高度な分析スキルを持つ「専任のデータサイエンティスト」が人事部門に在籍している割合は、情報通信業で42.9%、製造業で40.0%、金融・証券・保険業で38.9%と、いずれも高い水準にあります。
さらに、人材の価値を最大化するための「タレントマネジメントシステム」の導入も進んでおり、特に情報通信業では74.3%もの企業が導入済みです。こうした先進的な業種では、短期的な分析レポートの提出も活発に行われており、情報通信業で60.0%、製造業で55.7%が実践しています。データに基づいた知見が経営の意思決定に活かされるという、価値創造のサイクルが機能し始めています。
興味深いことに、外部の専門家に対するニーズは、データ活用が遅れている企業よりも、むしろ活用が進んでいる大企業においてより高まる傾向が見られます。「分析レポート作成支援・高度な統計解析の代行」といった専門的な支援を求める声は、従業員規模が1,000人から4,999人の企業で56.8%、5,000人以上の企業では69.0%に達し、中小企業を大きく上回ります。
この背景には、データ活用が深化するにつれて、社内の人材だけでは対応しきれない、より高度で複雑な分析への要求が高まっている可能性が考えられます。また、これはスキル不足の裏返しというだけではありません。自社の分析結果を客観的な視点で評価し、新たな知見を得るために、第三者の専門性を積極的に取り入れようとする、組織としての成熟した姿勢の表れと解釈することもできるでしょう。
では、データ活用の成果を左右する要因は何なのでしょうか。重回帰分析という統計手法で探ると、3つの要因が浮かび上がりました。成果と最も強く関連していたのは「人事の分析スキル・知識」(β=.41)でした。データを価値ある情報へと変換する専門的な能力が、成果創出の源泉です。次に強く関連していたのは「データ分析結果の共有・レポーティング」(β=.28)です。分析で得た知見を組織内で共有し、対話を生むプロセスが、データを組織全体の行動変容へとつなげる「共通言語」として機能します。そして、「人事データ分析活用の目的」(β=.23)も重要です。活動全体の方向性を定める指針が、リソースを効果的に集中させることを可能にします。
これらの結果が示すのは、データ活用の成功の鍵が、高機能なシステム以上に、それを扱う「人」の能力と、データに基づいた協調的な対話を許容する「組織」のあり方にあるという、シンプルかつ本質的な事実です。
データ活用の成果を引き出す専門家との協働方法
『人事データ白書』の調査結果が示すように、データ活用の成果は、専門的なスキルや知識、それを組織で共有し対話する文化と強く結びついています。企業の成果を最大化するためには、社内外に存在するデータ分析の専門家と、いかに効果的に連携し、協働していくかが鍵となります。単純な業務の委託や支援要請を超えた、戦略的なパートナーシップの構築に他なりません。
初めに、社内に在籍するデータサイエンティストや分析専門部署といった専門家との関わり方についてです。彼ら彼女らは、高度な分析技術と自社の事業や組織文化という固有の文脈とをつなぐ役割を担います。その能力を引き出すためには、人事担当者の側からの働きかけが不可欠です。
第一に、依頼の仕方を工夫することが求められます。『人事データ白書』の分析において、データ活用の成果は、「何のために分析するのか」という目的の明確さと強く関連していました。専門家に対して、「このデータを分析してほしい」と作業を依頼するのではなく、「私たちはこのような人事課題を解決したい。そのために、データから何が分かるだろうか」というように、課題の背景や目的、すなわち「なぜ」の部分を深く共有することが重要です。目的意識の共有が、分析の質を高め、活動全体を成果へと導きます。
第二に、専門家をただの分析の「実行者」としてではなく、対話の「パートナー」として尊重し、積極的に巻き込む姿勢が求められます。今回の調査によれば、分析結果の共有や対話は、成果に結びつく2番目に強い要因でした。専門家を経営会議や現場のミーティングといった対話の場に招き、彼ら彼女らの口から直接、データが示す事実の背景や解釈における注意点を説明してもらうのです。これによって、データは数字の羅列から、組織を動かす説得力のある「共通言語」へと変わり、組織全体の行動変容を促します。
第三に、人事担当者が持つ専門知識を専門家と共有することの重要性です。本調査の中で、成果と最も強く関連していたのは、統計知識と実務ノウハウを合わせた「人事の分析スキル・知識」でした。これは、単純な統計スキルだけでなく、それを人事という専門領域(ドメイン)で活かせる能力が重要であることを意味します。専門家が人事特有の課題や社内の実情を深く理解して初めて、データは価値ある「知見」へと昇華されます。
続いて、社外のコンサルタントやベンダーといった専門家との協働方法です。彼ら彼女らは、社内にはない高度な知見や客観的な視点をもたらし、特にデータ活用が深化している大企業ほど、そのニーズは高まる傾向にあります。外部専門家との関係においても、戦略的な視点が求められます。
第一に、その関係性を「スキル不足の穴埋め」から「戦略的パートナーシップ」へと転換することです。今回の調査によると、データ活用が進んだ企業は、より複雑な分析や、自社の分析結果を客観的に評価してもらうために外部専門家を起用しています。多くの企業で基礎的なスキルが不足しているからこそ、外部の専門家には不足分を補ってもらうだけでなく、社内の常識を問い直し、新たな視点をもたらす「壁打ち相手」としての役割を期待することが、より高い成果につながります。
第二に、将来のニーズを見越して、平時から高度な専門家との関係を構築しておくことです。データ活用が深化するにつれて、社内だけでは対応できない、より高度で複雑な分析への要求は高まります。「統計学に基づく統計解析」のような高度なスキルは、保有している人材が限られているのが実情です。いざという時に迅速に依頼できるよう、高い専門性を持つ専門家が誰なのかを見極め、関係を築いておくことが人事の競争力となります。
第三に、外部への依頼を「丸投げ」にせず、自社の能力向上につなげる仕組みを組み込むことです。『人事データ白書』の調査に見られたように、7割以上の企業が「分析人材・スキルの不足」を最大の課題として認識しているという問題を解決するためには、外部委託を単発のレポート納品で終わらせてはもったいないでしょう。ワークショップの開催やトレーニングといった「知識の移転」も含め、組織全体のスキルを底上げする視点を持つのが良いでしょう。これによって、組織内部に持続可能なデータ活用能力を蓄積していくことができます。
おわりに
本講演では、『人事データ白書』の調査結果を基に、データ分析の専門性との向き合い方について考察しました。明らかになったのは、データ活用の成否が技術やシステムの問題以上に、専門性を持つ「人」とどう向き合い、協働していくかという「組織」の課題であるという事実です。社内外の専門家をパートナーとし、対話を通じてその知見を組織の力に変えていく。その先に、データが組織の未来を拓く風景が広がっているはずです。
Q&A
Q:高度なデータ分析・統計解析とは、具体的にどのレベルを指すのでしょうか。どのあたりからが「高度」と言えるのか、線引きがあれば教えてください。
藤井:
「ここからが高度な分析です」と明確に線を引くのは難しいのですが、分析の「深さ」や「複雑さ」に段階があると捉えていただくと分かりやすいかと思います。
例えば、「各部署の平均値を比較する」といった単純な集計も分析の第一歩です。一方で私たちが「高度な分析」と呼ぶものは、そこから一歩踏み込み、統計学の理論を用いてデータに隠された意味を探るプロセスを指します。
単に部署ごとの平均値を比較するだけでなく、「部署による違い」と同時に「部署内に存在する個人個人の違い」や「勤続年数などの他の要因が与える影響」といった、複数の視点を考慮に入れて分析を進めていくようなケースです。このように、考慮すべき点が増え、扱うデータの範囲が広がるにつれて、分析の難易度は上がっていきます。
伊達:
二つの観点を提供できるかなと思います。一つ目は、「推測統計」を用いるかどうかです。統計学には、手元のデータの特徴を要約する「記述統計」と、一部のデータ(標本)から全体の集団(母集団)の性質を推測する「推測統計」があります。後者を扱うようになると、専門知識が必要となり、分析の難易度は上がります。これが「高度な分析」の一つの特徴です。
二つ目は、分析手法そのものの「数学的な複雑さ」です。分析手法が数学的に難解になるほど、それを正しく理解し、使いこなすためには、ある程度の「数学的リテラシー」が求められます。使い方を誤るリスクを避けるためにも、こうした知識が要求される分析は「高度」と言えるでしょう。
Q:人事の専門知識を分析担当者と共有することが重要だというお話でしたが、具体的にはどのような知識を共有すると良いのでしょうか。成功事例などがあれば教えてください。
藤井:
私が特に重要だと考えているのは、人事施策の背景にある「文脈」や、過去の「意思決定の経緯」を共有することです。データ分析担当者は数字のプロですが、社内の人間関係や組織文化といった、数字に表れない「行間」を読むことまでは難しいものです。こうした背景情報が共有されることで、分析担当者は「人事のパートナー」として、より的確な分析を行うことができます。
伊達:
人事と分析担当者がうまく協働できている企業では、人事側から「課題感」と「仮説」が積極的に共有されているという共通点があります。すなわち、重要なのは「今、現場で何が問題だと感じているのか(課題感)」、そして「その問題の原因は何だと考えているのか(仮説)」という情報を伝えることです。
例えば、人事担当者が「最近、若手社員の離職が多い(課題感)。もしかすると、上司とのコミュニケーションが原因かもしれない(仮説)」と伝えるとします。この情報があることで、分析担当者は「では、その仮説を検証するために、面談頻度と離職意思を分析しましょう」と、具体的な計画を立てられます。
人事担当者が持つ現場感覚や問題意識を、分析の基礎情報として提供すること。これが、データ分析を成功に導く重要な「専門知識の共有」と言えるでしょう。
Q:伊達さんのお話の中で、人事の分析スキルが「成果」と関連していたと伺いました。ここで言う「成果」とは何を指していますか。
伊達:
調査における「成果」の定義ですね。結論から申し上げますと、私たちの調査で測定した「成果」とは、売上や利益率といった客観的な経営指標ではなく、「人事データ活用が、組織にとって良い影響をもたらしているか」という、人事担当者自身の主観的な評価を指します。調査では、具体的な質問を複数用意し、データ活用がもたらす価値を多角的に尋ねています。詳細は『人事データ白書』をご覧ください。
脚注
[1] 調査結果の詳細は『人事データ白書:日本企業におけるデータ活用の現在地と未来』をご覧ください。
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。

藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ マネージャー
関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。