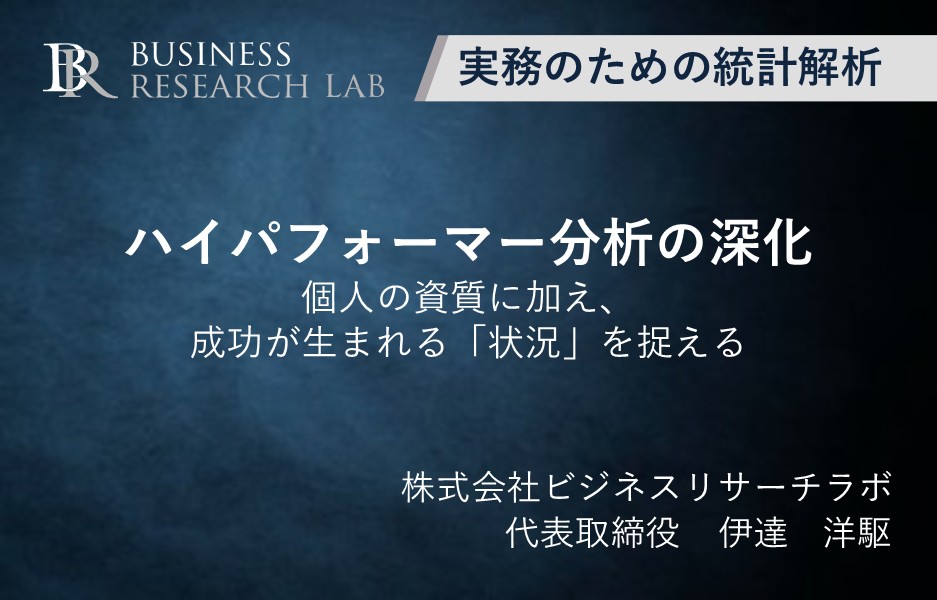2025年8月25日
ハイパフォーマー分析の深化:個人の資質に加え、成功が生まれる「状況」を捉える
ハイパフォーマー分析は、人材戦略を策定する上で有用です。事業環境の複雑化や人材獲得競争の激化を背景に、自社で継続的に高い成果を出す人材の特性をデータに基づいて解明し、その知見を採用、育成、配置といった人事施策に活かすことへの期待は高まっています。
一般的なハイパフォーマー分析では、優れた成果を出す従業員に共通するコンピテンシーや行動特性、価値観といった「個人の資質」を特定することに主眼が置かれます。その結果、「当社のハイパフォーマーは主体性が高い」「戦略的思考力に優れている」といったモデルが構築され、採用面接の評価項目や研修プログラムの内容に反映されていきます。
しかし、こうしたアプローチに真摯に取り組んできた人事担当者ほど、ある種の壁に直面しているのではないでしょうか。それは、分析から導き出された「理想の人物像」に合致する人材を採用・育成しても、必ずしも期待通りのパフォーマンスを発揮するわけではないという現実です。
あるプロジェクトではエースとして輝いていた人材が、別のチームに異動した途端に精彩を欠いてしまう。特定のリーダーのもとで急成長を遂げた若手が、上司の交代と共に伸び悩んでしまう。こうした現象は、個人の資質だけでは説明がつきません。
個人の能力と実際の発揮パフォーマンスとの間に生じるギャップを理解する鍵は、本コラムの主題である「状況」です。個人の資質が「種」であるとすれば、状況はその種が根を張り、芽を出し、花を咲かせるための「土壌」です。どれだけ優れた種であっても、土壌が合わなければ十分に育つことはできません。
本コラムでは、この見過ごされがちな「状況」という要因に光を当て、それをいかに分析し、ハイパフォーマー分析をより立体的で実用的なものへと深化させるか、そのアプローチについて詳述していきます。
なぜ「個人の資質」だけでは不十分なのか
人の行動や成果を理解する上で、クルト・レヴィンが出した有名な考え方があります。彼は、人の行動(Behavior)は、その人個人(Person)と、その人が置かれた環境(Environment)の関数である、と述べ、それを「B=f(P, E)」という式で表現しました[1]。
この式をパフォーマンスに置き換えるならば、高い成果とは、個人の資質や能力と、その人が働く環境との相互作用によって生まれるものと捉えることができます。この観点に立つと、個人の資質のみに注目した分析がなぜ不十分であるかが明確になります。
第一に、「再現性の欠如」という問題があります。これは分析で見出された特性が、あくまで「特定の環境下で成功した要因」に過ぎないことを示唆しています。個人の資質は、それ単体で常に価値を発揮するわけではなく、特定の環境という触媒があって輝く「ポテンシャル」のようなものです。
例えば、分析によって「主体性」がハイパフォーマーの資質だと判明したとします。しかし、その主体性を持つ人材が、上司が事細かに指示を出し、逸脱を許さないマイクロマネジメントを行うチームに配属されたらどうなるでしょうか。その人材の主体性は発揮されるどころか、むしろ「指示に従わない」「和を乱す」と評価され、本人にとってはフラストレーションの源泉となりかねません。この場合、「主体性」という資質そのものに問題があるのではなく、その資質を活かす「状況」が欠けているのです。
その環境要因を無視して資質だけを模倣しようとしても、期待した成果は得られず、貴重な人材のポテンシャルを損なう結果に終わる可能性があります。成功は、資質と環境が適切に組み合わさった時に生まれます。
第二に、「施策の限界」という壁に突き当たります。分析の結果、成功要因が個人の性格や価値観ばかりに帰結した場合、組織として打てる手は限られます。個人のパーソナリティを外部から変えることは容易ではなく、時間がかかりますし、そもそも倫理的な観点からも慎重な検討が必要です。結果、施策としては「そのような特性を持つ人材を新たに採用する」という採用中心の考え方に偏ってしまいます。
このアプローチは、組織内に「持っている人」と「持っていない人」という固定的な二項対立を生み出します。これでは、現在組織に在籍している大多数の従業員のパフォーマンスをいかにして向上させるか、という育成や組織開発の観点からの有効な答えを提示することができません。「持っていない」と見なされた従業員は成長の機会から遠ざけられ、モチベーションを失うかもしれません。組織の関心は「今いる人材をどう育てるか」から「どこかから完成品の人材を見つけてくるか」へと移り、それは持続的な組織力の向上にはつながりにくいのです。
「状況的要因」を捉えるアプローチ
これまで感覚的に語られてきた「状況的要因」を、どのように分析の対象とすれば良いのでしょうか。その核は、統計的な分析アプローチ、例えば、重回帰分析の考え方を応用すると良いでしょう[2]。このアプローチではまず、解明したい対象である「パフォーマンス」を「従属変数」として設定します。分析のゴールが「パフォーマンスが何によって決まるのかを説明すること」であることを意味します。
次に、このパフォーマンスを説明するための要因、すなわち「独立変数」として、二つの異なる種類のデータを投入します。一つは、これまでも分析対象とされてきた「個人要因」です。これには、従業員の経験年数やスキルレベル、あるいは適性検査から得られる個人の特性などが含まれます。
もう一つが、本コラムで重要視する「状況的要因」です。上司のマネジメントの質、仕事の自律性、チーム内の協力体制といった、個人を取り巻く外部環境に関するデータです。これらのデータは、組織サーベイなどを通じて数値化することが可能です。
この枠組みを用いることで、パフォーマンスという一つの結果に対して、様々な個人要因と状況的要因がそれぞれどの程度影響を与えているのか、それらの組み合わせによってさらなる影響が生まれるのかを、統計的に評価することができます。このアプローチの利点は、これまで「良い上司」「良い職場風土」といった曖昧で主観的な言葉でしか語れなかった事柄を、客観的なデータに基づいた議論の対象へと変える点にあります。
三つの目的と「状況的要因」の貢献
状況的要因を分析に組み込むことの価値は、ハイパフォーマー分析が持つ複数の目的に対して、それぞれ異なる形で貢献することにあります。ここでは、分析の目的を「予測」「育成」「スコアリング」という三つの側面に分け、それらがどのように連携し、状況的要因がどう貢献するのかを見ていきます。
これら三つの目的は独立しているのではなく、密接に連携しています。まず「予測」というプロセスを通じてパフォーマンスのメカニズムをモデル化し、そのモデルから得られる知見を組織全体の「育成」施策に展開し、同時にそのモデルを個々の従業員に適用して「スコアリング」を行い、個別最適な配置や育成につなげる、という一連の流れとして捉えることができます。
特に「予測」は後続の二つの目的の基礎となるモデルを構築する根幹の活動であり、「スコアリング」はそのモデルの具体的な個人への適用例と言えます。この関係性を念頭に置きながら、それぞれの目的における状況的要因の貢献を見ていきましょう。
目的1:将来の活躍を「予測」するモデルの構築
第一の目的は、将来の活躍を「予測」するためのモデルを構築することです。これは、どのような要因がパフォーマンスに影響を与えるのか、その法則性や関係性を統計的に明らかにしようとする試みであり、他の目的の土台となります。予測モデルを構築する際、状況的要因はモデルの精度と現実味を高めます。
状況的要因の影響の仕方には、大きく分けて二つのパターンがあります。一つは「主効果」です。これは、個人の特性にかかわらず、従業員に影響を与える要因を指します。例えば、心理的安全性が極端に低い、あるいは過度な長時間労働が常態化している職場環境は、多くの人にとってパフォーマンスの阻害要因となるでしょう。
重回帰分析においては、この要因が単独でパフォーマンスに大きな負の影響を与える変数として特定されます。このような要因を特定することは、組織全体のパフォーマンスの土台となる環境条件、つまり誰もが安心して能力を発揮するための基準を明らかにすることにつながります。
もう一つは「交互作用」です。これは、ある人の持つ特性による影響が、その人が置かれる状況や環境によって異なる場合を指します。例えば、「高い裁量」という状況は、「主体的に行動したい」という特性を持つ人材にとってはパフォーマンスを加速させる要因となり得ますが、一方で「明確な指示を好む」人材にとっては混乱を招きかねません。分析モデル上では、個人要因と状況的要因の掛け算の項(交互作用項)が、パフォーマンスに対して意味のある影響を持つ形で現れます。
このような交互作用を分析することで、「誰にとって、どのような環境が良いのか」という、個人と環境の最適なマッチング条件を見つけ出すことができ、単に「良い人材」を探すのではなく、「この人材が最も輝く環境はどこか」という、より解像度の高い人材配置の指針を得ることが可能になります。実際、個人と環境の適合度が高いほど、パフォーマンスが向上することが多くの研究で示されています[3]。
目的2:組織的な「育成」と再現性の向上
第二の目的は、ハイパフォーマーを組織的に「増やし、育てる」ことです。これは、先の予測プロセスで構築したモデルから得られた知見を、組織改善のアクションにつなげるフェーズです。この目的において、状況的要因の分析は有効です。なぜなら、個人の性格を変えることは難しい一方で、上司のマネジメントスタイルや仕事の与え方、組織の制度や風土といった状況的要因は、組織が意思を持って介入し、改善することが可能だからです。
分析によって「ハイパフォーマーは、挑戦的な目標を与えられ、それに対する上司からの適切な支援を受けている」という事実が明らかになったとします。これは、ハイパフォーマーを育成するための「設計図」のようなものです。この設計図に基づき、組織は管理職に対して目標設定やコーチングに関する研修を実施したり、挑戦を促すような評価制度を導入したり、あるいは1on1の質を高めるためのガイドラインを整備したりと、多面的な施策を展開できます。
重要なのは、これらの施策が場当たり的なものではなく、データという根拠に基づいている点です。これによって施策の説得力が増し、関係者の協力を得やすくなります。
施策実行後には、再びサーベイなどを通じて状況的要因の変化を測定し、パフォーマンスへの影響を検証することで、PDCAサイクルを回して、施策を継続的に改善していくことができます。分析結果が、組織として取り組むべき人事施策に直結し、その効果を測定して改善していくという一連のプロセスを可能にするのです。
これは、一部のスター人材の成功体験を再現性のない逸話として語るのではなく、その成功を支えた環境要因を特定し、組織全体でその環境を再現していくという、持続可能なアプローチを可能にします。
目的3:個別最適化のための「スコアリング」
第三の目的は、個人の潜在的な可能性を「スコアリング」し、選抜や育成計画に活かすことです。このスコアリングは、第一の目的で構築した予測モデルがなければ成立しません。予測モデルというパフォーマンスを算出する方程式に、個々の従業員の個人要因や状況要因の値を代入することで、一人ひとりのポテンシャルを数値化します。予測とスコアリングはモデル構築とモデル活用という表裏一体の関係にあります。
このアプローチにおいて状況的要因は、スコアを静的な「格付け」から、動的で文脈依存の「ポテンシャル予測」へと転換させる上で重要な役割を果たします。例えば、ある従業員のスコアが低い場合、その原因が本人の資質にあるのか、それとも良好でない状況的要因によってポテンシャルが抑制されているだけなのかを考えることができます。
この動的なスコアは、戦略的な配置のための「シミュレーション」を可能にします。ある人材を、特性の異なる複数の部署に配置した場合のポテンシャルスコアをそれぞれ試算し、その人材が最も能力を発揮できる場所はどこかをデータに基づいて検討することができます。
個別の育成計画を立てるための「診断ツール」としても機能します。スコアが低い原因となっている状況的要因を特定し、それを改善するためのアクション、例えば上司による関わり方の変更や、本人の役割の再定義などを、育成計画の中心に据えることができます。
マネージャーとメンバーとの対話も、「あなたのスコアは低い」という一方的な通告ではなく、「この環境要因を一緒に改善することで、あなたのポテンシャルはもっと発揮されるはずだ」という建設的なものに変わります。スコアは対話の出発点となり、個人と組織が協力して成長を目指すための共通言語として機能するのです。このように状況的要因は、スコアリングが安易なラベリングになることを防ぎ、対話を促すための要素となります。
個人の可能性を解き放つ視点
ハイパフォーマー分析において、個人の資質だけでなく、その個人が置かれた「状況」を捉えることの重要性を見てきました。それは、分析から得られる示唆をより深く、より実用的なものにするための視点です。ハイパフォーマー分析の目的は、単に「誰が優秀か」という問いに答えることだけではありません。その本質は、「どのような資質を持つ人が、どのような状況に置かれたときに、なぜ高いパフォーマンスを発揮するのか」という、成功の背後にあるメカニズムを解明することにあります。
そのメカニズムを理解した上で、組織全体でその成功を再現できる環境を意図的に設計していくことが、目指すべき方向性と言えるでしょう。これからの時代に求められる人材戦略は、優れた原石を見つけ出す能力だけに依存するものではありません。それに加えて、様々な人材がその内なる輝きを放つことができるような「土壌」を育み、維持していくための思考が求められます。
個人の努力や才能だけに成功の要因を求めるのではなく、そのポテンシャルを解き放つのは組織全体のシステムであり、環境であるという認識に立つことが重要です。データに基づいた客観的な分析と、それによって促される一人ひとりへの理解と対話。その両輪を回していくことによって、組織は持続的に成長し、変化の激しい時代を乗り越えていくことができます。
ハイパフォーマー分析を、個人を評価するツールから、組織と個人が共に成長するための学習の機会へと転換させていくこと。そのためのヒントは、私たち一人ひとりが働く「状況」の中に眠っています。
脚注
[1] Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers.
[3] Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., and Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals’ fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. Personnel Psychology, 58(2), 281–342.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。