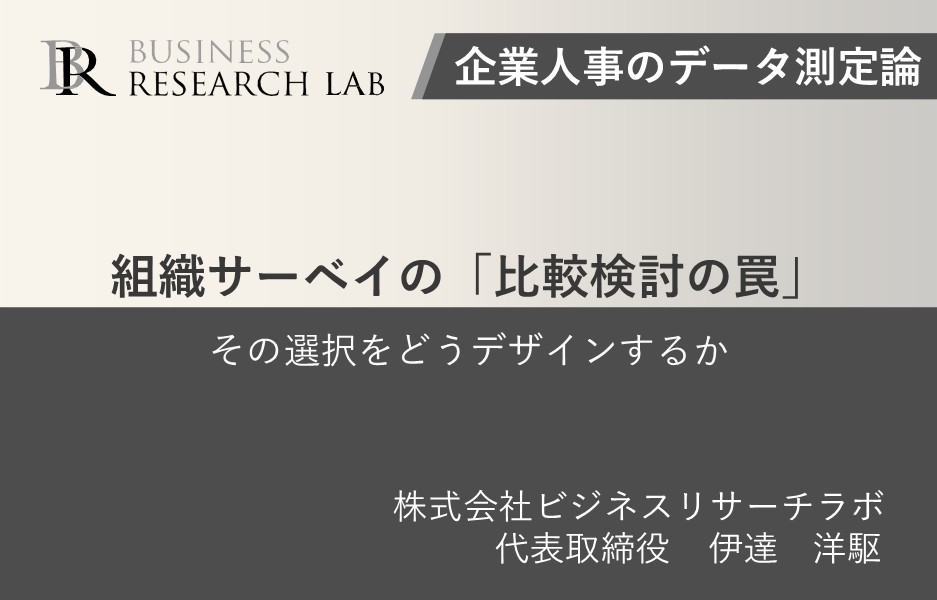2025年8月21日
組織サーベイの「比較検討の罠」:その選択をどうデザインするか
私たちビジネスリサーチラボは少し変わった立場で、組織と人事の世界に関わっています。一つは、企業一社一社の固有の課題に向き合い、調査をゼロから設計するオーダーメイド型の組織サーベイを提供する立場。そしてもう一つは、多くの企業が利用できる標準化された仕組み、すなわちパッケージ型サーベイを開発するHR事業者様を支援する立場です。すなわち、個別性の高い課題解決に深く関わることもあれば、汎用性の高い仕組み作りに携わることもあります。
この二つの現場に身を置いていると、組織サーベイの選択というテーマが、単なる「AかBか」という話ではないことがよく分かります。誠実に選ぼうとするほど、ある種の「ジレンマ」に陥りやすい光景も目の当たりにしてきました。その現象とは、「パッケージ型」と「オーダーメイド型」を同じテーブルで比較検討し始めた途端、その議論が構造的にパッケージ型に有利な形で進むというものです。
本コラムでは、どちらか一方を推奨したり、その価値を貶めたりする意図はありません。目的は、この「比較検討の罠」とも呼べる現象の構造を、双方の現場を知る立場から解き明かし、人事の皆さんが自社の状況と目的に照らして、確信の持てる選択をするための思考の枠組みを提供することにあります。
パッケージ型サーベイが築く「共通の評価基準」
パッケージ型サーベイの開発支援という立場から、その設計思想の根幹にあるものについてお伝えします。それは「標準化」という、強力で社会的な意義も大きい思想です。
私たちがパッケージ型サーベイを設計する際に重視することの一つが「アクセシビリティ」、すなわち、できるだけ多くの企業が、組織の声を聴くという活動を始められるように、その導入障壁を下げることです。誰もが一定水準のサービスを妥当なコストで享受できる。この基盤があるからこそ、より多くの企業が組織の状態を把握し、改善に向けた一歩を踏み出すことができます。組織サーベイも同様に、まずは自社の状態を把握するという活動を、広く普及させることが重要だと考えています。これは組織診断の「民主化」とも言えるでしょう。
そのために必要なのが、標準化された設問と指標です。エンゲージメントや満足度といった、目に見えない複雑な概念に、検証済みの共通の評価基準を適用する。これは、組織の状態をデータで定量的に表現し、比較可能にするための枠組みを社会に提供する試みです。この共通の枠組みがあれば、二つの重要な価値を手にすることができます。一つは「他社比較(ベンチマーク)」、そしてもう一つは「時系列比較(定点観測)」です。
ベンチマークは、自社の立ち位置をデータの中で示してくれます。経営層は、データが示す数値の中で自社がどこに位置しているのかを知りたいと考えるでしょう。データで示された座標軸によって、的確な目標設定と、資源配分の意思決定が可能になるからです。パッケージ型サーベイが提供するベンチマークは、人事部門が経営と対話するための有効なコミュニケーションツールです。
同様に重要なのが、時系列での比較です。同じ基準で毎年調査を続けることで、「昨年実施した施策は、本当にスコアの向上につながったのか」「この事業部で起きている変化は、ポジティブなものかネガティブなものか」といった、自社内での変化を捉えることができます。定点観測の価値は、時に他社比較以上に重要です。組織改善は一朝一夕には成し遂げられません。長期的な視点で自社の変化を追い続ける上で、標準化されたサーベイは一つの基盤となります。
パッケージ型サーベイは、管理職層に対する「育成ツール」としての機能も果たします。サーベイで問われる項目(例えば、上司の支援、成長機会、承認など)は、それ自体が「良いマネジメントとは何か」というメッセージを含んでいます。サーベイ結果を通じて、管理職は自身のマネジメントの強みと弱みを認識し、改善に向けたアクションを考えるきっかけを得ることができます。
したがって、「まずは組織の健康状態を網羅的に、かつ効率的に把握したい」「世の中の標準的な基準で、自社の現在地を確認したい」「長期的な視点で組織の変化を追跡できる体制を整えたい」といった判断に基づいて、パッケージ型サーベイを選択するのは合理的です。組織開発という長い道のりを歩むにあたり、信頼できる基準と方向性を得るための、堅実な第一歩と言えます。
オーダーメイド型サーベイが拓く「深い対話」
一社一社の課題解決を支援する立場から、オーダーメイドというアプローチの本質について掘り下げて解説します。パッケージ型が広範なデータを提供するものであるとすれば、オーダーメイド型は、特定の課題を解決するために、その原因を掘り下げ、解決策を導き出すためのアプローチです。
このアプローチの核心は、完成した調査票そのものよりも、むしろ「問いを作るプロセス」にあります。皆さんが人事担当者として、「我が社にとって、今、本当に問うべきことは何か」という問いと向き合う。このプロセスは、それ自体が価値の高い組織開発の活動です。
例えば、M&A後の組織文化の融合という、難易度の高い課題に直面しているとします。この場合、問うべきは一般的なエンゲージメントだけではありません。「旧A社の社員は、新しい評価制度をどう受け止めているか」「旧B社の社員は、意思決定のスピード感にどう適応しようとしているか」「両社の社員が協働する上で、どのようなコミュニケーション上の障壁を感じているか」など、その状況で生まれ得る具体的な問いが必要になります。
この問いを作るために、私たちは対話を重ねます。時には、「我々が目指す新しい文化とは、具体的にどのような行動で示されるのか」といった定義そのものから議論することもあります。対話のプロセスを通じて、関係者の間で課題認識が深まり、これまで漠然としていた問題の輪郭が浮かび上がってきます。サーベイを実施する前に、すでに関係者の当事者意識が醸成され、変革への機運が高まっていく。これが、オーダーメイド型がもたらす、見えにくい価値です。
分析の深度も異なります。オーダーメイドでは、課題の仮説に基づき、変数間の関係を統計的に検証するための分析モデルをあらかじめ設計に組み込むことが可能です。例えば、「特定のリーダーシップ開発プログラムが、本当に管理職の行動変容を通じて、部下のエンゲージメント向上に寄与しているのか」といった、施策の効果測定を精緻に行うことができます。
したがって、オーダーメイド型を選択すると良いのは、重要かつ個別性の高い人事課題に直面している場合です。一般的な調査では解明が難しい、複雑な問題の原因を探るための、的を絞ったアプローチと言えます。その選択は、課題解決に向けたアクションプランの策定に直結する活動の始まりを意味します。
「比較検討の罠」の構造
二つのアプローチが、それぞれ異なる思想と目的を持つ、別のソリューションであることを理解いただけたかと思います。ここで、本題である「比較検討の罠」に話を戻しましょう。なぜ、性質の異なるものを同じテーブルで比較すると、構造的に特定の結論が導かれやすいのでしょうか。双方の現場を知る立場から、その構造を分析します。
第一に、「比較表というフォーマットの限界」があります。稟議を通すため、あるいは合理的な意思決定のために、私たちはしばしば比較表を用います。その項目は、「価格」「機能数」「導入期間」「ベンチマークの有無」といった、定量化しやすく、誰の目にも明らかな「見える価値」が中心となります。企業の購買プロセスは、多くの場合、こうした有形物の比較を前提に設計されています。この土俵の上では、製品として完成されているパッケージ型が優位に映るのは、ある意味で当然のことです。
一方で、オーダーメイド型の価値の核心である「設問設計プロセスを通じた組織内対話の促進」や「自社課題に特化した深い洞察」「組織の課題解決能力の向上への寄与」といった「見えにくい価値」は、比較表の一行に落とし込むことができません。結果、比較検討という行為そのものが、一方に有利なバイアスを生んでしまいます。
第二に、「『製品購入』と『プロジェクト組成』の混同」です。私たちは無意識のうちに、二つを同じカテゴリーの「サービス」として捉えますが、その本質は異なります。パッケージ型サーベイの選択は、仕様と価格が明確な「製品」を、その費用対効果を吟味して「購入」する行為です。ここにおけるリスク管理は、主に「製品が仕様通りに機能するか」という点に集約されます。
一方、オーダーメイド型サーベイの選択は、まだ形のないゴールに向かって、専門家というパートナーと共に、時間と知恵を投資して課題解決を目指す「プロジェクト」を「組成」する行為です。ここにおけるリスク管理は、「協働プロセスが円滑に進み、期待した成果(課題解決)につながるか」という、より複雑で不確実性の高いものになります。
「製品」と「プロジェクト」の違いは、「事前にアウトプットを明示できるか」という点にも表れます。パッケージ型サーベイの提供事業者は、具体的なサンプルレポートやデモ画面を提示できます。購入する側は、「最終的にどのような形の納品物が手に入るか」を正確に把握した上で、意思決定ができます。これは、物品購入のプロセスと似ており、安心感があります。
一方、オーダーメイド型は、そのプロセス自体が価値であり、最終的なアウトプットは調査と分析の結果によって形作られます。どのような洞察が得られるか、どのような報告書が最適かは、プロジェクトが完了するまで確定しません。「アウトプットの不確定性」はプロジェクトの本質ではありますが、購買担当者や具体的な成果物を重視する意思決定者から見れば、リスクとして捉えられるかもしれません。納品物を約束できる「製品」と、プロセス重視の「プロジェクト」では、比較の前提が大きく異なります。
第三に、人事担当者の皆さんが置かれている「組織内の現実」があります。皆さんには、自身の選択に対する説明責任があります。その際、「多くの企業が導入している標準的な製品です」という説明は理解されやすいのに対して、「我々の特殊な課題を解決するため、この専門家とプロジェクトを立ち上げます」という説明は、より高度な課題認識の共有と、関係者の深い理解を必要とします。特に、短期的なROIを求められる風潮の中では、価格が明確で効果が分かりやすく見えるパッケージ型の方が、組織的な承認を得やすい傾向があります。これは、多くの組織が抱える意思決定の力学なのです。
「どのツールか」から「どの戦略か」へ
「比較検討の罠」は、誰かが悪意を持って仕掛けたものではありません。合理的な判断をしようとすればするほど、陥りやすい構造的な課題です。どうすれば、この罠から抜け出し、より本質的な選択ができるのでしょうか。
そのための鍵は、議論の出発点を変えることです。「どのツールが良いか」という問いから始めるのではなく、「私たちの組織は、今回のサーベイを通じて、何を達成しようとしているのか」という、目的(Why)の明確化から始めるのです。「Why」の解像度を高めるために、さらにいくつかの問いを立ててみましょう。
「このサーベイの結果は、具体的に誰の、どのような意思決定に活用されるのか」「もし、この調査をしなかった場合、組織はどのような機会損失を被るのか」「サーベイ後のアクションに、我々はどれくらいの時間と予算を投じる覚悟があるのか」。こうした問いを社内で議論し突き詰めていくと、大きく分けて二つの、あるいはその中間に位置する「戦略パス」が浮かび上がってきます。
戦略パスA:広域モニタリング戦略
「まずは組織全体の健康状態を、定量的な指標で網羅的に把握したい。世の中の標準と比較することで、自社の現在地を正確に知り、優先的に対処すべき課題領域を見極めたい。この活動を継続することで、データに基づいた組織運営の文化を醸成したい」。もし、皆さんの組織がこの戦略を選択するのであれば、その最適な戦術はパッケージ型サーベイです。その上で、「どのパッケージが、自社の規模や業種、長期的なデータ活用の思想にフィットするか」という、より具体的なツール選定の議論に進むのが合理的でしょう。
戦略パスB:特定課題解決戦略
「我々は今、事業の根幹に関わる、重要かつ個別性の高い課題に直面している。この課題の真因を深掘りし、的を射た解決策を導き出すために、ピンポイントで洞察を得る必要がある。このプロジェクトの成功が、人事の成果につながる」。もし、この戦略を選択するのであれば、議論の焦点は、もはやツール比較ではありません。この難易度の高いプロジェクトを成功に導くために、「どの専門知識と経験を持つパートナーと協働すべきか」という、パートナー選定の議論に進むべきでしょう。
戦略パスC:ハイブリッド戦略
もちろん、現実にはこの二つを組み合わせるアプローチも有効です。例えば、全社的にはパッケージ型サーベイ(パスA)で定点観測を行いつつ、そこで特定された特定の課題部署やテーマに対してのみ、オーダーメイドの調査(パスB)を実施する、というものです。これによって、網羅性と深度を両立させることが可能になります。
このように、思考のフレームを「ツールの比較検討」から「戦略パスの選択」へと転換する。そのことを通じて「比較検討の罠」から解放され、より俯瞰的な意思決定を下すことができるようになります。
選択をデザインする役割
組織サーベイの選択は、単なるツール選びではありません。それは自社が今、どのような発展段階にあり、どのような課題認識を持っているのかを示すものです。
パッケージ型サーベイがもたらす「標準化」の力と、オーダーメイド型サーベイが拓く「個別性」の深み。この二つは対立するものではなく、組織の成長を支える、相互に補完し合う二つのアプローチです。どちらのアプローチを、どのタイミングで、どの程度活用するのか。その判断が、これからの人事担当者の皆さんに求められる役割なのかもしれません。
その役割は、選択肢を評価することではありません。組織内の対話を促し、戦略目的を明確にし、目的に最適な「選択のプロセス」をデザインすること。比較表を作る前に、まず「我々の戦略はAか、Bか、それともCか」という対話の場を設ける。それが、人事部門が発揮すべき専門性でしょう。戦略的な思考と実践の先に、人事という仕事の価値が生まれるはずです。.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。