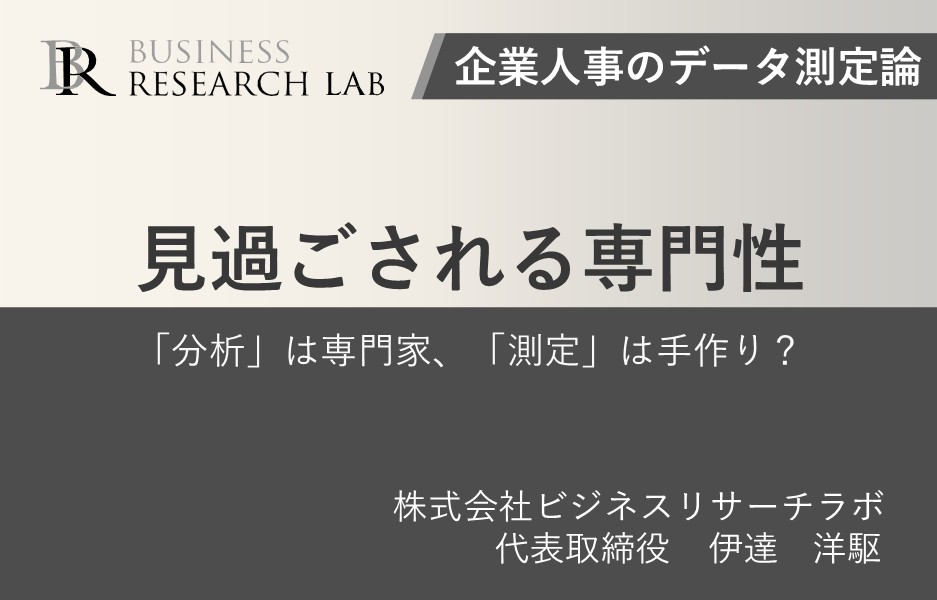2025年8月19日
見過ごされる専門性:「分析」は専門家、「測定」は手作り?
現代の企業経営において、「データに基づいた意思決定」は、もはや一部の先進的な企業だけが掲げるスローガンではなくなりました。組織の重要な資産である「人」を扱う人事の領域では、HRテクノロジーの隆盛とともにデータの活用が叫ばれています。従業員のエンゲージメントを可視化し、離職の兆候を予測し、ハイパフォーマーの特性を分析することで、より科学的でより公正な人事を目指そうとしています。
こうした潮流の中で、一躍注目を浴びたのが「データ分析」の専門性です。統計学や機械学習を駆使して膨大なデータから意味のある知見を掘り起こす「データサイエンティスト」という職種は、多くの企業が求める存在となりました。高度な分析モデルを構築し、未来を予測するその技術は、明確で分かりやすく、その専門性には多くの人が敬意を払うところでしょう。経営層も人事担当者も、「高度な分析は専門家に任せるべきだ」というコンセンサスを形成しつつあります。
しかし、その一方で、非常に重要でありながら見過ごされがちな一つの領域に目を向ける必要があります。それはデータ活用のまさに「入り口」となるプロセス、すなわち「測定」の領域です。具体的には、従業員サーベイのアンケート項目を作成したり、採用や昇進で用いるアセスメントを設計したりする技術、学術的には「心理測定(サイコメトリクス)」と呼ばれる分野の専門性です。
アンケートの作成など、誰にでもできるのではないか。そう考える人は少なくないかもしれません。質問をいくつか考え、選択肢を並べれば、それらしい形にはなります。しかし、その「問い」が、本当に私たちが知りたいことを、歪みなく、正確に捉えられているかという点にまで思いを馳せる機会は少ないのが実情でしょう。
結果的に、多くの組織では、心理測定の専門家が不在のまま、いわば「手作り」のアンケートが重要な意思決定の根拠として使われています。これは、精密な航海計器を持たずに、手作りの羅針盤で大海原に乗り出すようなものです。針がどちらを指していても、それが本当に正しい北を示している保証はどこにもありません。
本コラムでは、なぜ「分析」の専門性は認識されやすい一方で、「測定」の専門性は見過ごされやすいのか、その構造的な問題を考察します。そして、その専門性の軽視がもたらす弊害を明らかにし、最後に、この問題に対して専門家と人事担当者がそれぞれどのように向き合い協働していくべきか、未来志向のアプローチを検討していきます。
「分析」と「測定」で認識の差が生まれる理由
データ活用という一つの大きなテーマの中で、なぜ「分析」と「測定」の専門性は、異なる受け止められ方をするのでしょうか[1]。その背景には、両者の専門性が持つ性質の違い、結果の現れ方、人事という職務の特性が複雑に絡み合っていると考えられます。
専門性の「可視性」
第一に、両者の専門性は「目に見えやすさ」において違いがあります。
データ分析の専門性は「可視的」です。例えば、統計解析ソフトであるRやPythonのコードを書き分析モデルを構築するスキルは、専門家でなければ持ち得ないことが一目瞭然です。アウトプットも、将来の離職率を予測するモデルなど、具体的で形あるものとして現れます。その作成プロセスと成果物を見れば、誰もが「これは素人には無理だ」と納得し、専門家への依頼が必要だと判断できます。
他方で、心理測定の専門性は、その多くが「不可視」です。質の高いアンケートを作成するプロセスには、測定したい概念(例えば、エンゲージメント)を定義し、それを具体的な質問項目に落とし込み、尺度の「信頼性」や「妥当性」を統計的に検証するという、目に見えにくい地道な作業が含まれます[2]。
「信頼性」とは、その測定がどれだけ安定的か、結果がブレないか、という指標です。信頼性の低いアンケートは、いわば「伸び縮みするゴム製の定規」で物の長さを測るようなもので、測るたびに結果が変わり、信用できません。
「妥当性」とは、その測定が「本当に測りたいものを測れているか」という指標です。例えば、「リーダーシップ」を測るつもりのアセスメントが、実は「社交性」や「自己主張の強さ」を測っているだけだとしたら、それは妥当性が低いと言えます。
こうした信頼性や妥当性を担保するための専門的な手続きは、最終的に完成したアンケート用紙の見た目からは、(非専門家から見ると)ほとんど窺い知ることができません。良い質問と悪い質問の違いも、一見しただけでは判別がつきにくいものです。専門性が成果物の裏側に隠れて見えにくいことが、その価値を過小評価させる要因となっているのでしょう。
「もっともらしい結果」が出てしまう
第二に、プロセスに問題があった場合の結果の現れ方が異なります。
データ分析の世界では、手法やロジックを誤ると、プログラムがエラーで停止したり、全く意味をなさない結果が出力されたりすることがあり、問題が比較的表面化しやすいと言えます[3]。
ところが、心理測定の場合、たとえ尺度の設計が不適切であったとしても、何らかの「もっともらしい結果」が算出されてしまう、という特徴があります。例えば、不適切な組織サーベイであっても、「満足と答えた人は65%」「A部署の平均点は3.2点」といった集計値を出すこと自体は可能です。その数値だけを見れば、何かを把握できたような気になってしまいます。
この「何となくの結果が出てしまう」という事象が、かえって問題の根深さを見えにくくしています。分析のエラーのように失敗として現れないため、「この結果は本当に信頼できるのか」「この問いは正しかったのか」という品質への問いかけがなされにくいのです。
正しい羅針盤も、壊れた羅針盤も、針がどこかを指し示すこと自体は同じです。しかし、その針が指す方角が信頼できるかどうかが違うのと同じように、表面的な結果が得られることと、その結果が事実を反映していることとは、別の問題なのです。
人事業務の特性と経験の非対称性
第三に、人事担当者の持つ経験やスキルセットとの親和性も関係しています。
人事という職務は、給与計算、勤怠管理、人員構成の把握など、日々、定量的なデータを扱う場面があります。そのため、既存のデータをより高度に活用する「データ分析」に対しては、その重要性を理解しやすく、自身の業務の延長線上にあるものとして捉えやすい側面があります。
しかし、心理測定の背景にある学問領域は、多くの人事担当者がキャリアを通じて体系的に学ぶ機会が少ないのが現状です。これは人事担当者の能力の問題ではなく、一般的なキャリアパスの構造的な問題です。結果的に、心理測定の専門性を具体的にイメージしたり、その必要性を肌で感じたりする機会が乏しくなります。
従業員サーベイなどを内製する際に、過去のフォーマットを参考にしたり、メンバーで話し合って項目を作成したりすることで、「何となく」形にできてしまうという経験が、かえって専門性の必要性を感じる機会を奪っている側面もあるかもしれません。こうした経験の非対称性が、分析と測定に対する認識の差を生み出しています。
これらの要因が複合的に絡み合うことで、「分析は専門家へ、測定は自前で」という、非対称な認識が組織の中に形成されていくのです。
専門性の軽視がもたらす弊害
手作りの羅針盤が指し示す方角を信じて航海を続けると、どのような結末が待っているのでしょうか。心理測定の専門性を軽視することは、単に「少し精度の低い調査」で終わる問題ではありません。組織の健全性を静かに蝕み、気づいたときには取り返しのつかない事態を招きかねない、深刻な弊害の種を蒔く行為に他なりません。その根源にあるのは、コンピュータサイエンスの有名な格言「Garbage In, Garbage Out」でしょう。
不正確で歪んだデータという「ゴミ」を組織のシステムに入力すれば、そこから導き出される意思決定や施策もまた「ゴミ」となってしまいます。具体的な弊害は、大きく三つの側面に現れます。
誤った意思決定という経営リスク
組織にとって致命的なのは、誤ったデータに基づいて、経営や人事の意思決定を行ってしまうことです。これは企業の持続的な成長を阻害する、直接的な経営リスクとなります。
例えば、人材マネジメントの各領域で、次のような歪みが生じます。採用の場面を考えてみましょう。妥当性の低い自作のアセスメントを使い、「協調性」を測るつもりが、単に「同調圧力に弱い人材」を選んでしまうかもしれません。その結果、イノベーションを生み出すために必要な、健全な意見対立を恐れる同質的な組織が出来上がってしまう可能性があります。本来であれば組織の未来を担うはずだった、鋭い視点を持つ優秀な候補者を、不適切な物差しで不合格にしてしまうという機会損失も計り知れません。
配置や育成においても同様です。不正確なサーベイによって、従業員の強みやキャリア志向を正しく把握できなければ、せっかくの才能を活かせないミスマッチな配置が生まれます。また、組織開発の文脈では、組織サーベイの結果は、しばしば組織の「健康診断」に喩えられます。しかし、その診断が誤っていたらどうなるでしょうか。
例えば、サーベイ結果が「福利厚生への不満」を声高に示していたとします。経営陣や人事は、それに応えようと多額の費用を投じて新たな福利厚生制度を導入するかもしれません。しかし、もしそのサーベイの質問項目が従業員の本質的な不満を捉えきれておらず、真の原因が「上司とのコミュニケーション不全」や「評価制度への不信感」にあったとしたら、その投資は的外れに終わります。真の病巣は放置されたまま、組織の体力が失われていくのです。
従業員の心への悪影響
専門性を欠いた測定は、数値上のリスクだけでなく、従業員一人ひとりの心にも悪影響を及ぼします。
アンケートやアセスメントは、組織が従業員に向き合うための大切なコミュニケーションツールです。しかし、その問いが稚拙であったり、特定の回答へ誘導するような意図が透けて見えたりすると、従業員はそれを見抜きます。「この会社は、私たちの本音を知りたいわけではないのか」「どうせ結論は決まっているのだろう」。そうした不信感は、組織に対するコミットメントを低下させます。
何度も意味を感じられない調査に付き合わされるうちに、従業員の間には「サーベイ疲れ」や、どうせ何も変わらないという「シニシズム」が蔓延します。回答は次第に形式的になり、当たり障りのないものになるか、あるいは深く考えずに回答されるようになります。こうなると、アンケートはもはや組織の実態を映す鏡ではなく、ただ形骸化した儀式をなぞるだけの無価値なものと化します。
さらに、納得感のないアセスメントの結果が、自身の評価や昇進・昇格に影響を及ぼすと知ったとき、従業員の心には不公平感が生まれます。自身のキャリアが、信頼できない物差しで測られることへの不満と無力感は、仕事へのモチベーションを奪いかねません。公正であるべき人事制度への信頼が揺らぐことは、組織の土台である心理的安全性を損なうことにつながるのです。
見えないコストの増大
専門家への依頼費用を惜しむことが、長期的には大きなコストを生むという、皮肉な現実もあります。
まず、質の低い調査の設計、実施、分析、報告にかかる従業員や人事担当者の時間と労力は無駄になります。これは目に見える直接的なコストです。
しかし恐ろしいのは、その背後にある「見えないコスト」です。誤った採用判断によって生じる再採用のコストや、早期離職に伴う損失。効果のない研修や的外れな制度改定に投じられた多額の投資。これらは全て、適切な測定がなされていれば防げたかもしれないコストです。
最大のコストは「機会損失」です。本来であれば、質の高い測定を通じて組織の課題を特定し、的確な手を打つことで、生産性を向上させ、イノベーションを促進して、従業員のウェルビーイングを高めることができたかもしれません。その「得られたはずの未来」を逃してしまうことが、専門性の軽視がもたらす大きな代償と言えるでしょう。
このように、心理測定の専門性を軽視することは、些細な手抜きではなく、組織の羅針盤を狂わせ、進むべき道を見誤らせ、共に航海する乗組員の心を離反させ、船体に静かな浸水を引き起こす、リスクの高い行為なのです。
未来へ向けた協働のアプローチ
これまで見てきたように、心理測定の専門性が軽視される問題は、根深く、多岐にわたる弊害をもたらします。しかし、この課題を乗り越える道は、決して閉ざされているわけではありません。専門家サイドと人事サイドが、それぞれの立場でできることに向き合い、互いに歩み寄る「協働」のアプローチが解決の鍵を握ります。
専門家サイドに求められること
まず、心理測定の専門家サイドには、自らの知識や技術をビジネスの現場へと橋渡しする努力が求められます。その役割は知の「翻訳者」であり、ビジネスパートナーであるべきです。
第一に、専門知識を「ビジネス言語」に翻訳する能力が必要です。「この尺度はα係数が0.8で、高い信頼性があります」と語るだけでは、多忙な人事担当者や経営層に、その価値は届きません。そうではなく、ビジネス上のメリットやリスク回避に直結する言葉で語る必要があります。「妥当性」という言葉も、「これを使えば、『将来活躍する人材』と『そうでない人材』を的確に見抜くことができ、採用のミスマッチを減らせます」と翻訳することで、その重要性が実感を持って伝わるでしょう。
第二に、価値を可視化し、リスクを具体的に提示する努力も重要です。抽象的な理論の説明に終始するのではなく、「専門性を軽視したA社では、組織サーベイで誤った課題を特定し、多くの費用を投じた施策が無駄になりました。一方、専門家と協働したB社では、真の課題であるマネジメント層の育成に集中投資し、離職率を改善できました」といった、具体的な成功・失敗事例を提示することで、専門性への投資が、リターンを生む戦略的投資であることを示すことができます[4]。
第三に、提供する価値の柔軟性も求められます。全ての企業が、常にフルスペックのコンサルティングを必要としているわけではありません。人事のニーズや予算、そしてリテラシーのレベルに応じて、「まずは既存アンケートの課題を洗い出す簡易診断から始めませんか」「項目作成の部分だけ、専門家として監修します」「分析とレポート作成の部分でお手伝いします」といった、多様な関与の選択肢を提示することが、人事担当者が「最初の一歩」を踏み出すためのハードルを下げます。
教育者として、人事担当者向けの勉強会を開催し、測定の基礎を啓蒙することも、長期的なパートナーシップを築く上で有効なアプローチでしょう。専門家は、知識を独占するのではなく、共有し、相手をエンパワーする存在となるべきです。
人事サイドに求められること
一方、人事サイドにも、これまでの慣習を見つめ直し、新たな一歩を踏み出す勇気が求められます。それは、専門家に全てを丸投げすることではなく、自らがより賢明な「問い手」となり、戦略的なパートナーとなるための変革です。
第一に重要なのは、「測る」ことに対する意識改革です。「アンケートは、毎年恒例の意見集約イベント」という認識から、「組織の意思決定の品質を左右する、重要なデータを取得するプロセス」へと、その位置づけを格上げする必要があります。「何を尋ねるか」だけでなく、「その問いは、いかにして尋ねられるべきか」という「問いの品質」に、もっと注意を払うべきだという意識の転換が出発点となります。
第二に、健全な懐疑心と知的好奇心を持つことが大切です。「毎年、このアンケートを使っているから」という惰性を断ち切り、「この質問項目は、本当に今の組織課題を捉えられているのだろうか」「このアセスメントの結果は、何を根拠に信頼できると言えるのだろうか」と、自組織の「当たり前」を疑う視点を持ちましょう。
専門家になる必要はありませんが、例えば、バイアスの種類(社会的望ましさなど)や、信頼性・妥当性といった概念の基礎を学ぶだけで、世の中の調査やアセスメントを見る目は変わります。その知的好奇心が、外部の専門家と対等に議論し、より良いものを共創していくための基盤となります。
第三に、スモールスタートを恐れないことです。組織の全ての測定を一度に変えることは現実的ではありません。まずは、経営へのインパクトが大きい一つのプロジェクトから、専門家の知見を取り入れてみるのが賢明でしょう。例えば、次世代リーダーの選抜アセスメントや、全社的な組織サーベイのリニューアルなど、失敗が許されない重要な領域で、専門家と協働してみるのです。
そこで「これまで見えなかった課題が、こんなにもクリアになった」「施策に対する現場の納得感が高まった」といった成功体験が生まれれば、それが組織内に専門性の価値を伝播させ、文化を変えていくための原動力となります。人事担当者は、専門家を「調査の外注先」としてではなく、自社の組織・人事戦略を成功に導くための「戦略的パートナー」として位置づけ、積極的に活用していく姿勢が求められます。
協働が生み出す価値
専門家がビジネスの現場に歩み寄り、人事が測定の専門性に敬意を払う。この両者の歩み寄りが実現したとき、組織にはこれまでにない価値が生まれます。人事が抱える生々しいビジネス課題と、専門家が持つ測定の科学的知見が掛け合わさることで、「データ」は、組織を動かす力を持つ「インサイト」へと昇華します。組織の隠れた強みや、誰も気づかなかった課題の原因を照らし出し、より的確で、より効果的な打ち手を可能にするでしょう。この協働は、データ活用という言葉が本来目指すべき価値創造の姿です。
脚注
[1] 本コラムでは議論を単純化するため、分析と測定を分けていますが、実際には不可分です。例えば、信頼性・妥当性の高い尺度を開発するプロセスには、因子分析といった統計「分析」が必要となります。良い測定は、良い分析によって品質が担保されるということです。
[2] 信頼性と妥当性に関する詳細は当社コラムを参考にしてください。
[3] データ分析のエラーは表面化しやすいと述べましたが、これはあくまで測定と比較した際の相対的な特徴です。分析においても、プログラムがエラーで停止することなく、一見「もっともらしい」結果が算出される「サイレントエラー」は起こり得ます。例えば、分析の前提となるデータに選択バイアスが含まれていたり、不適切な変数を用いていたり、目的に合わない分析手法を用いていたりする場合です。測定の不備と同様に、誤った結果は組織の意思決定を誤った方向へ導くリスクをはらみます。
[4] 専門家だからこそ、測定や分析の限界をよく知っており「そういった情報発信や助言は、簡単にはできない」と感じる方がいるかもしれません。しかし、そこで止まってしまっては、市場の知識・実践レベルはいつまでも高まらず問題は解消されないままで、専門家の多様なキャリアや活躍の場の広がりを失ってしまうことにもつながりかねません。加えて、学術的な限界の中で言えること・やれることを見定められるのも専門家のスキルであり、責任であると言えます。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。