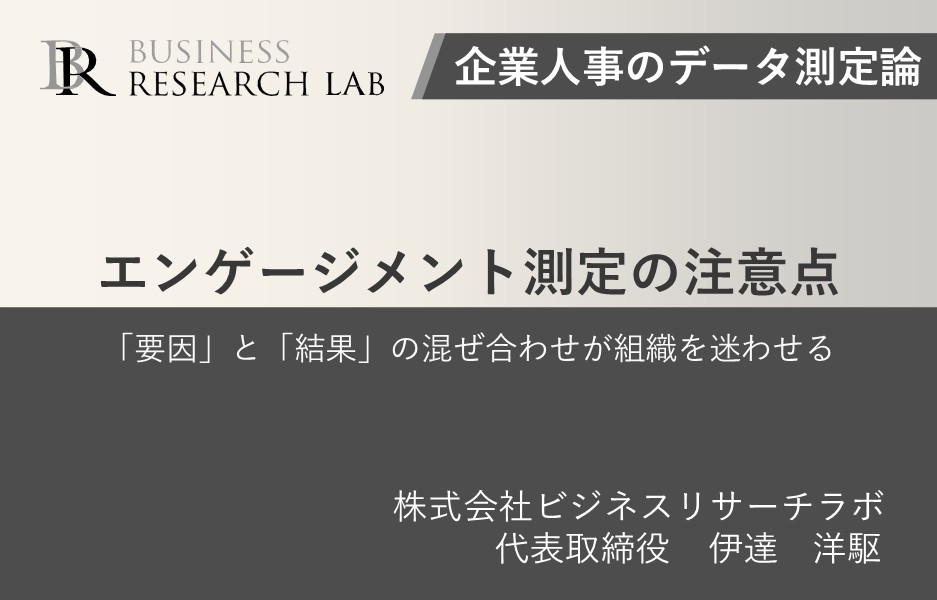2025年8月18日
エンゲージメント測定の注意点:「要因」と「結果」の混ぜ合わせが組織を迷わせる
企業の持続的成長における人的資本の重要性が高まる中、「従業員エンゲージメント」は組織運営における中心的な概念の一つとして定着しました。従業員のエンゲージメントが高い状態は、生産性の向上や離職率の低下、さらには組織全体の革新性につながると期待されており、多くの企業がその測定と向上に取り組んでいます。その主要な手段として、従業員を対象としたサーベイが広く活用されています。
サーベイは、組織の状態を可視化し、改善に向けた課題を特定するための診断ツールです。しかし、その有効性はサーベイの設計、特に測定項目の構成に依存します。もし、その設計に問題が含まれていた場合、サーベイから得られるデータは組織の実態を正確に反映せず、かえって意思決定を誤った方向へ導く可能性があります。
本コラムの目的は、エンゲージメント測定において時折見られる特定の設計上の課題を検討することにあります。それは、エンゲージメントという中核的な概念と、その「要因」や「結果」にあたる周辺的な概念とを区別せずに測定してしまうという問題です。これがなぜ分析の信頼性を損なうのか、そして、その不確かなデータに基づいてさらなる分析を進めることがいかにリスクを伴うのかを論じます。最終的に、より信頼性の高い知見を得るための、構造的に整理された測定と分析のアプローチを提案します。
測定における概念の混同とその影響
エンゲージメントサーベイの設計における課題は、測定対象となる概念の定義と範囲設定にあります。学術的な研究の蓄積により、エンゲージメントに関連する概念は、大きく三つの異なる領域に分類して捉えるのが一般的です[1]。
第一に、エンゲージメントを構成する「中核概念」です。これは、従業員が仕事に対して示す、持続的で肯定的な心理状態そのものを指します[2]。具体的には、仕事から活力を得て精力的に取り組む状態(活力)、仕事に誇りとやりがいを感じる状態(熱意)、そして仕事に集中し没頭する状態(没頭)といった要素で構成されます[3]。これが、私たちが最も知りたいエンゲージメントの本体です。
第二に、エンゲージメントの「要因」です。エンゲージメントという心理状態に影響を与える、職場環境や仕事の特性、組織の制度などを指します。例えば、上司からの支援、同僚との良好な関係、仕事の自律性、成長の機会、適切な評価などがこれにあたります。これらはエンゲージメントを醸成するためのインプットであり、エンゲージメントそのものではありません。
第三に、エンゲージメントの「結果」です。エンゲージメントが高いことによってもたらされる、個人や組織にとって望ましい行動や成果を指します。個人のレベルでは職務満足の向上や組織への定着意向、組織のレベルでは生産性の向上や顧客満足度の改善などが挙げられます。これらはエンゲージメントから生まれるアウトプットであり、エンゲージメントとは区別されるべき概念です。
問題となるのは、これら三つの異なる概念(中核概念、要因、結果)を区別せず、それらを測定する項目を合算して、単一の「エンゲージメントスコア」として算出することです。このような設計は、一見すると包括的に見えるかもしれませんが、測定の妥当性を損なう二つの問題点を内包しています。
一つ目の問題は、測定している対象が曖昧になり、スコアの解釈が困難になることです。例えば、ある従業員のスコアが高い場合、その背景には複数の可能性が考えられます。仕事そのものへの熱意(中核概念)が高いのかもしれません。あるいは、仕事への熱意は低いものの、職場環境(要因)が快適であるためスコアが高くなっているのかもしれません。また、会社に長く勤め続けたいという意向(結果)が強いだけで、同様に高いスコアが算出される可能性もあります。
このように、全く異なる状態にある従業員が、同じ「高エンゲージメント」というラベルで括られてしまいます。これでは、スコアが高い、あるいは低いという結果が得られても、その意味内容を特定することができません。組織や個人がどのような状態にあるのかを正確に把握できなければ、適切な対策を講じることは困難です。
二つ目の問題は、関連性の分析が困難になることです。サーベイを実施する目的の一つは、「何が要因でエンゲージメントが変動し、その結果としてどのような影響が出ているのか」という関連を理解し、改善策の立案につなげることです。例えば、「上司からの支援(要因)が、仕事への熱意(中核概念)を高め、離職意向の低下(結果)につながる」といった関連性を明らかにすることが求められます。
しかし、要因、中核概念、結果をすべて合算した指標では、これらの関係性を分析する前提が崩れてしまいます。原因と結果が指標の内部で混ざり合っているため、何が原因で何が結果なのかを検証する道が閉ざされてしまうのです。これでは、組織が抱える問題の根本原因を特定することができず、施策の立案は経験や勘に頼らざるを得なくなります。測定の段階で概念を混同することは、データに基づく合理的な組織改善の機会を失うことに直結します。
不確かなデータに基づく分析のリスク
測定の初期段階で概念を混同するという問題を抱えたまま、さらにその不確かなデータを用いて分析を進めようとすると、事態はより深刻になります。例えば、前述の「エンゲージメントスコア」と、それとは別に測定した特定の「要因」との関係性を分析し、施策の優先順位を決定しようとするケースです。このアプローチは、信頼性の低い土台の上にさらに分析を重ねる行為であり、導き出される結論の妥当性を損ないます。
この種の分析が抱える第一のリスクは、トートロジー(同義反復)に陥る可能性です。例えば、エンゲージメントスコアの算出項目に「上司は適切な支援を提供してくれる」という項目(要因A)が含まれているとします。その上で、追加の分析として「上司との関係性の質」(要因B)とエンゲージメントスコアとの相関を調べたとします。要因Aと要因Bは概念的に近いため、この分析は実質的に「上司との関係性」と「上司との関係性を含む指標」の関係を調べていることになります。
当然、両者の間には高い相関が見出される可能性が高いのですが、それは「ある概念は、それ自身と強く関連する」という自明の事実を再確認しているに過ぎません。この結果から「我が社では上司との関係性がエンゲージメントの最重要課題である」と結論づけることには、論理的な飛躍があります。それは新たな知見ではなく、測定設計の重複が生み出した人工的な結果である可能性が高いのです。
第二のリスクは、たとえ分析対象の要因がスコアに含まれる要素と重複していなかったとしても、得られる相関関係の解釈が困難になる点です。ここで言うエンゲージメントスコアは、前述の通り「中核概念」「要因」「結果」が混ざり合った指標です。この指標と、新たに追加した特定の要因との間に統計的な関連が見られたとしても、その関連が何を意味するのかを特定することはできません。
例えば、「成長機会」という要因とエンゲージメントスコアの間に正の相関が見られたとします。この相関は、いくつかの異なる関係性を反映している可能性があります。一つは、「成長機会」が「仕事への熱意」(中核概念)を直接的に高めているという、本来明らかにしたい関係性です。
しかし、同時に、「成長機会」が豊富な職場は、もともとスコアに含まれている「上司の支援」(別の要因)も手厚い傾向がある、という要因間の関係性を反映しているだけかもしれません。あるいは、「成長機会」を感じている従業員は、結果として「組織への貢献意欲」(結果)も高まるという、要因が直接結果に影響する関係性を示している可能性も否定できません。
そして第三のリスクは、こうした不確かな分析に基づいて組織の資源が投下されてしまうことです。信頼性の低い分析から導かれた「見せかけの相関」を根拠に、特定の要因を改善するための施策が全社的に展開される可能性があります。
しかし、その要因がエンゲージメントの中核概念に対する本当の要因でなかった場合、多大な時間とコストを費やしたにもかかわらず、従業員の心理状態は改善されず、施策は空振りに終わります。このような経験は、データに基づく組織改善への取り組みに対する不信感を組織内に生み、将来のより妥当なアプローチの導入を阻害することになり得ます。
信頼できる知見を得るためのアプローチ
サーベイを組織改善につながるツールとするためには、測定と分析のプロセス全体を見直す必要があります。その核は、これまで述べてきた問題の逆、すなわち、測定の段階で各概念を明確に分離し、それらの関係性を体系的に分析するという、基本的な原則に立ち返ることにあります。
そのための第一歩は、サーベイの設問設計において、エンゲージメントの「中核概念」「要因」「結果」を、それぞれ独立した測定カテゴリとして区別することです。各カテゴリに属する設問群を明確に分け、それぞれが個別のスコアとして算出できるように設計します。これによって、各概念を純粋な形で捉えることが可能となり、以降の分析の信頼性が担保されやすくなります。
第二歩は、この分離されたデータを用いた段階的な分析の実施です。まず、エンゲージメントの「中核概念」のスコアを用いて、組織全体の現状や部門ごとの状態を正確に把握します。組織の健康状態を示す基本的な指標となります。
続いて、要因分析を行います。エンゲージメントの「中核概念」のスコアを従属変数とし、様々な「要因」のスコアを独立変数として、両者の統計的な関連の強さを分析します。この分析を通じて、「数ある要因の中で、自社の従業員のエンゲージメントに最も強く影響を与えているのはどの要因か」をデータに基づいて特定することができます。これによって、組織は改善努力を集中すべき効果的な領域、すなわち「キードライバー」を特定できます。
例えば、ある組織では「上司の支援」が、別の組織では「成長の機会」がキードライバーとして特定されるかもしれません。このように、自組織に固有の課題を特定できることこそが、このアプローチの利点です。
第三歩として、エンゲージメント向上の取り組みがもたらす価値を検証します。エンゲージメントの「中核概念」のスコアと、「結果」として測定した業績評価、生産性指標、離職行動などとの関係性を分析します。これによって、「エンゲージメントの向上が、組織のパフォーマンス向上にどの程度貢献するのか」を示し、取り組みの正当性や投資対効果を経営層に説明するための根拠を得ることができます。
このような構造化されたアプローチは、分析の精度を高めるだけではありません。組織内での対話の質を向上させます。信頼性の高いデータに基づいて特定された課題は、現場の管理職や従業員にとって納得感が高く、「私たちの部署では、なぜ『成長の機会』のスコアが低いのか」「それを改善するために何ができるか」といった議論を促進します。
脚注
[1] Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
[2] Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., and Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
[3] 従業員エンゲージメントの概念は、学術的には多様な定義が存在します。本コラムで述べるワーク・エンゲージメント(仕事への心理的な関与状態)に加え、組織コミットメント(組織への愛着や一体感)も従業員エンゲージメントとして扱われることがあります。実務においては、これらが区別されずに測定される場合も見られますが、両概念は理論的には異なる構造を持つため、測定設計時には注意が必要です。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。