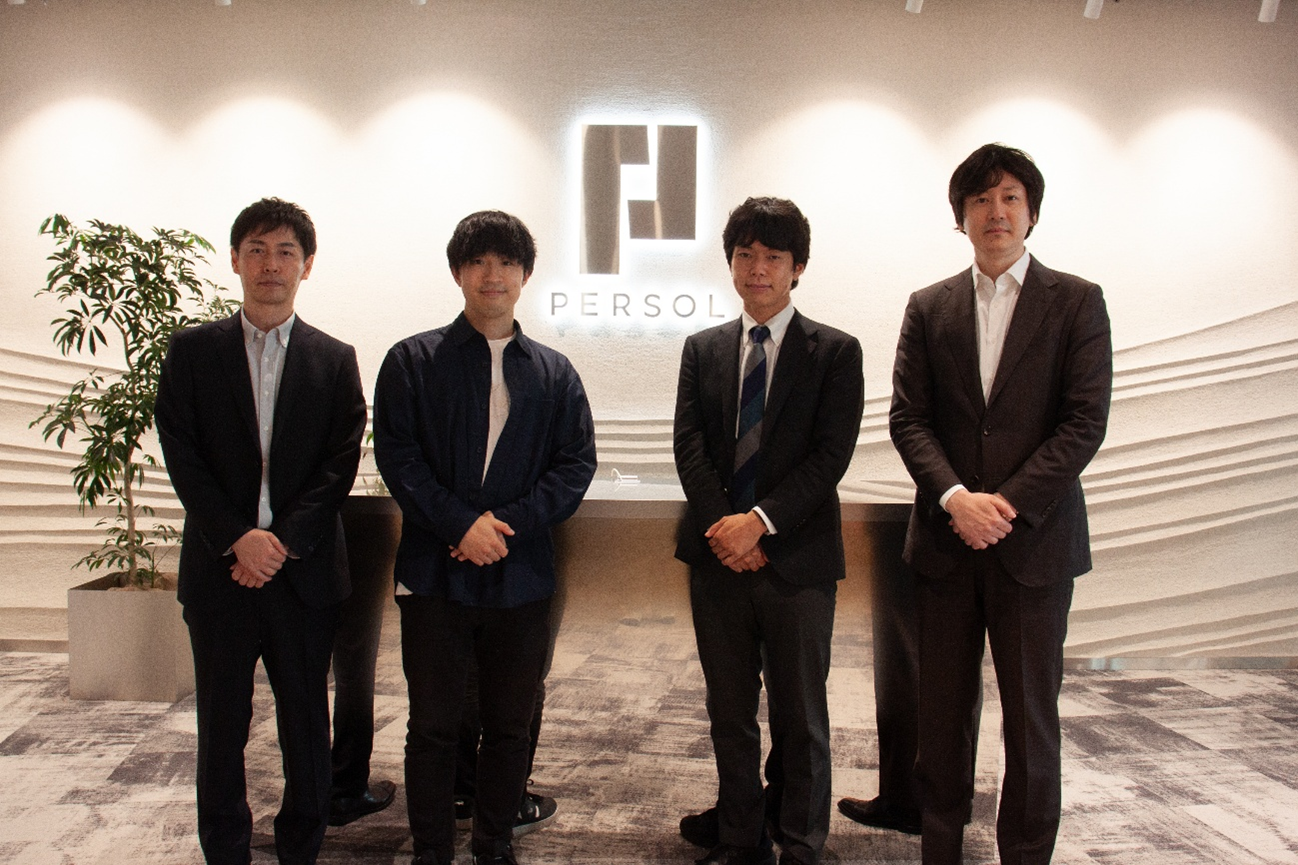2025年7月8日
パーソルキャリア株式会社|心理検査の尺度開発に関するコンサルティング
(左から)株式会社ビジネスリサーチラボ 藤井貴之、パーソルキャリア株式会社 テクノロジー本部 デジタルテクノロジー統括部 デジタルソリューション部 人事エンジニアグループ 倉持裕太様、株式会社ビジネスリサーチラボ 能渡真澄、同 伊達洋駆
大手人材サービス企業であるパーソルキャリア株式会社様。同社は、新卒採用向け心理検査の設問設計において、測定したいものを的確に測るための「構成概念妥当性」の担保や、客観的な根拠に基づいた設問作成に課題を感じていました。既存の適性検査がブラックボックスであり、本質的な改善につなげられないという危機感から、透明性の高い心理検査の内製化を目指していました。
これらの背景をもとに、ビジネスリサーチラボでは心理検査の尺度開発に関するコンサルティングを行いました。プロジェクトを推進された倉持様、およびビジネスリサーチラボの伊達、藤井、能渡が、プロジェクトの経緯や成果について語り合いました。
心理検査開発におけるプロの視点の必要性
藤井:
早速ですが、弊社にご相談いただく前、社内でどのような課題感をお持ちだったか、特に新卒採用向けの心理検査の設問設計について、当時のお悩みをお聞かせいただけますか。
倉持様:
心理検査の開発に着手した当初、一言で申しますと、「心を測る」ことの難しさを痛感し、専門家の力が必要だと強く感じていました。
藤井:
「心を測る」ことの難しさ、ですか。
倉持:
はい。もともと弊社では既存の適性検査を導入していましたが、各要素がどのような設問に基づき、どのように算出されているかを十分に把握・解釈するのが難しく、活用面で課題を感じていました。たとえば、データ分析から「この要素が重要だ」と見えても、それをどう評価・判断すればよいか明確にしきれず、改善につなげにくいと感じる場面もありました。そうした背景から、より透明性と柔軟性のある心理検査の内製化に踏み切りました。
藤井:
内製化をご決断されたのですね。
倉持様:
当時、社内に専門的な知見を持つメンバーがいなかったこともあり、私自身が学生時代に少し近い分野を学んでいた経験を活かし、新卒2年目ながらも手探りで取り組みを進めました。ただ、文献を参考に項目を作成しても、「構成概念妥当性」、つまり「作成した項目群が本当に測りたいものを測れているのか」という壁に突き当たりました。特に専門家から見て内容的な側面で妥当性を担保するのが難しかったのです。
能渡:
ご自身で作成された項目の客観的な根拠を示す点でもご苦労があったのではないでしょうか。
倉持様:
おっしゃる通りです。「この設問で本当に意図した能力を測定できるのか」と問われても、自信を持って答えられませんでした。統計手法の解釈については、自分たちだけで進めるのではなく、専門家の方に確認していただきたいと考えていました。不確かなままリリースし、後になって「使えないデータだった」という状況になることは避けたいという思いが強くありました。そこで、できるだけ早い段階で専門的なレビューを受けるべきだと判断し、御社にご相談させていただきました。
藤井:
構成概念妥当性が課題だったのですね。
倉持様:
そうですね。修士課程で学習科学や教育工学を専攻し、質問紙調査も経験していたため、構成概念妥当性の検討には慎重になったと思います。人事領域のデータサイエンティストとなって、奇遇にも、大学院時代の専攻に近い心理検査開発に関わることになり、改めて専門書や論文を読み漁りました。
伊達:
倉持さんのように人事領域で心理測定やデータ分析に精通されている方は稀有ですね。独学で知識を深めたとは驚きです。
倉持様:
ありがとうございます。とはいえ手探りが多く、レビューしてくださる方が身近にいなかったので、御社とのプロジェクト経験そのものが大きな学びになっています。
信頼できる専門性への期待
藤井:
専門家を探される中で、弊社にご依頼いただけた理由をお聞かせいただけますか。
倉持様:
直接のきっかけは、項目反応理論について調べていた際に、能渡さんが執筆されたコラムを拝見したことです。
能渡:
私のコラムがきっかけでしたか。大変光栄です。
倉持様:
項目反応理論の段階反応モデルについて、初心者向けで実践的な日本語の文献が少なく困っていました。能渡さんのコラムは専門性が高く、かつ非常に分かりやすく、まさに光明が見えた感覚でした。特に「一次元性」と「局所独立性」という前提条件の解説部分に感銘を受け、設問設計にも深い知見をお持ちだと確信しました。
それまでは、例えば、因子分析の結果を見て「この設問は因子負荷量が低いから削除しよう」といった表面的な判断しかできていませんでした。専門家の方々はここまで深く考察されるのかと自身の未熟さを痛感し、自分たちの設問に潜む問題点への不安を感じました。御社から様々な角度から評価いただければ、自信を持てる状態にできると思い、連絡しました。
能渡:
私が統計コラムを書く際に裏側で力を入れているポイントを深く読み込んでいただけて、とても嬉しい限りです。
倉持様:
もう一つ理由がありまして。他のコンサルティング会社にもお声がけし、その一社に「ビジネスリサーチラボさんにもお声がけしている」と相談したところ、「それなら間違いなくビジネスリサーチラボさんに依頼した方が良い。自信を持って推薦します」とおっしゃったのです。業界の方がそこまで言うなら間違いないだろうと。
伊達:
それは初耳です。嬉しいですね。
能渡:
弊社へのご相談には、測定したい概念をサーベイで捉えられている前提を持って「このデータで何か分析してほしい」というものが多いですが、倉持さんは「そもそもこの測定は上手くできているのか」という根幹の問いからスタートされています。その着眼点と探求心が素晴らしいです。
専門家との協働による成長
藤井:
プロジェクトを振り返ると、一つ目は新卒採用向け心理検査の開発支援でした。企業理念や求める人物像に合致し、活躍・定着する人材の心理特性を測定したいというご要望でしたね。二つ目は、社内アンケートにおける回答バイアス評価と対処のご相談でした。これらのプロジェクトで特に印象に残っていることはありますか。
倉持様:
どちらも私が作成した資料をベースにレビューいただく形でした。新卒向け検査のプロジェクトで鮮烈だったのは、私が作った設問リストに、御社から、全面真っ赤になるほどの修正コメントを添えてご返送いただき、その内容の充実度に驚くとともに、プロの視点からのご指摘に大きな気づきを得ました。
一同:
(笑)
倉持様:
社内でも「これはすごいのが来たぞ」と衝撃と共に話題になりました(笑)。プロの目で見るとこれほど改善点が見つかるのかと痛感しました。しかしネガティブではなく、これらをクリアすれば質の高いものが作れるという確信につながりました。何より、高い専門性を持つ皆様と一緒に課題に取り組めることが嬉しく、心強かったです。
伊達:
倉持さんが我々の指摘を真摯に前向きに受け止めてくださる信頼感があったからこそ、踏み込んだレビューができました。
倉持様:
社内アンケートの回答バイアスに関するプロジェクトでは、御社からご提供いただいた資料の網羅性と質の高さに驚きました。様々な学術論文から情報を収集・精査し、非常に分かりやすく体系的にまとめてくださっていました。曖昧だった知識がくっきりと整理され、明確な全体像として捉えられました。
能渡:
かなり難易度の高い資料をお送りした自覚はありましたが、お役に立てて何よりです。
伊達:
1回目と2回目のプロジェクト間で、倉持さんからご提示いただく資料のレベルやご質問の専門性が飛躍的に上がっていると感じました。短期間にどれほど勉強されたのだろうと驚きました。
倉持様:
本当ですか。大変励みになります。1回目のプロジェクトで設問設計の基本や回答バイアスへの対処法を実践的に教えていただいたことが大きかったですね。そこから視野が広がり、自分で論文を調べたり専門書を読み込んだりするようになりました。御社との最初のプロジェクトが私の知的好奇心に火をつけてくれたのは間違いありません。この経験を通じて、数年後にはもっと成長できるだろうという手応えを感じています。勝手ながら、皆様をメンターのような存在として捉えています(笑)。
能渡:
倉持さんご自身が成長を実感し、次につなげていらっしゃると伺えるのは喜ばしいことです。弊社のフィードバックを糧とし、積極的に学びを深められ、次のご相談ではより高度なレベルで課題を捉えていらっしゃる。好循環ですね。
倉持様:
はい、御社との出会いがなければ今の自分はなかったと実感しています。このような専門領域においては社内に気軽に相談できる相手がほとんどおらず、孤軍奮闘している感覚でしたので、高い専門性を持つプロ集団と協働させていただけることは、アウトプットの質向上だけでなく、自身の知識やスキル向上にもつながりました。
専門性と経験値:ビジネスリサーチラボの強み
能渡:
市場に向けて心理測定やアセスメント開発の高い専門性を発揮する専門家は、日本全体で見ても多くはありません。弊社の強みは、年間を通じて多くの心理測定プロジェクトに多様な業界のクライアント様と関わらせていただく機会がある点です。弊社では日常業務として数多くの尺度開発や改善を行っており、その豊富な経験が専門性を支えています。
伊達:
我々が手掛ける尺度の数や分析するデータの種類、直面する課題の多様性はなかなかのものです。実践の場で取り組むことで、理論だけでは得られない経験値やノウハウが蓄積されます。
倉持様:
実は御社に声をかける前に、大学の研究室や業務系のコンサルティングファームなど様々な相談先を検討しました。ただ、採用活動という特殊なシチュエーションで用いる心理検査の内製開発という観点からは、学術的な正しさだけでなく、ビジネス現場特有のニーズや制約への対応力も求められます。その点、御社は学術と実務のバランスが非常に優れており、安心して依頼できると感じました。結果的に、御社にお願いして本当によかったと改めて感じています。
藤井:
確かに実務では予算や納期など様々な制約があります。理想通りにはいかない中で、いかに創意工夫し最善を追求するか。そこには経験に裏打ちされた「勘所」が必要ですね。
伊達:
人事データ分析の領域では、倉持さんのように社内で専門家が不足し、一人で高度な業務を担っている方は少なくないと感じます。
倉持様:
たくさんいらっしゃると思います。弊社は分析については恵まれた環境ですが、他社ではIT部門の協力を得ながら手探りで進めていたり、外部ツールを導入しても使いこなせていなかったりするケースも聞きます。「この大量のデータをどう扱えばいいのか」というご相談は御社にも多いのではないでしょうか。
能渡:
多いですね。「分析手法までは理解できても、実際のデータをどう処理し分析すれば良いか、分析結果をどう解釈すればいいかが分からない」といった実践的なご相談はよくいただきます。
プロジェクトの楽しさと学びの環境
藤井:
倉持さんとのミーティングは、クライアントとベンダーを超え、まるで大学の研究室で研究者同士がディスカッションしているような知的な刺激に満ちていました。私自身、研究者時代を思い出すような高度で本質的な議論ができ、大変楽しくやりがいを感じました。
倉持様:
そのように言っていただけると光栄です。私も御社の皆さんとのディスカッションは毎回刺激的で、多くの学びがありました。
伊達:
弊社クライアントの人事ご担当者は人事労務の専門知識が豊富ですが、一方で、必ずしも統計解析や心理測定の専門家ではありません。倉持さんのように、その領域における専門知識や深い洞察をお持ちの方は少数派です。
能渡:
特に「測定」の分野は学習機会が限られています。データ分析手法の解説は増えていますが、その前段階の「何を」「どのように」測るかという尺度開発や測定に関する理論の情報は、依然少ないのが実情です。
倉持様:
本当にそう思います。心理検査の尺度開発に関する専門書は日本語では限られています。教科書も一般的・抽象的な記述が多く、具体的なノウハウはなかなか得られませんでした。
プロジェクト後の展開とデータオーナーシップの理念
藤井:
プロジェクトの成果を踏まえ、社内でどのようなアクションを取られたか、また今後の計画についてお聞かせいただけますか。
倉持様:
新卒採用向け心理検査では、項目反応理論に基づく分析手法など多岐にわたるサポートをいただいたおかげで、現在、弊社の新卒採用では、検査を通じて応募者の理解を深めながら、採用プロセスの心臓部として機能しています。
藤井:
実際に開発したものが実運用に乗っているのは喜ばしいことです。
倉持様:
さらに、弊社独自の取り組みとして、検査結果に基づき、学生一人ひとりに対して個別のフィードバックレポートをお渡しする仕組みも開発しました。私が所属する人事のIT部門では、数年前から「データオーナーシップ」という考え方を大切にしており、この取り組みもその方針に基づくものです。
伊達:
データオーナーシップ、ですか。興味深いですね。データを提供してくれた方に有益な形で還元する思想は、倫理的観点からも信頼関係構築からも今後ますます重要になります。
倉持様:
応募者から一方的に情報をいただくだけでなく、弊社に応募してくださるすべての学生に対し、今後のキャリア形成や自己理解に有益なものをお返ししたいという想いです。検査データから潜在的な強みや課題を分析し、アドバイスと共にフィードバックする仕組みは、応募者の満足度向上や採用ブランドイメージ向上に貢献できていると感じています。
藤井:
応募者にとってもメリットのある取り組みですね。
倉持様:
今後の展開としては、大規模な応募者データを詳細に分析し、尺度の精度向上や新たな活躍人材の傾向発見につなげたいと考えています。サンプルサイズが増えることで、より信頼性の高い結果が期待できます。
能渡:
学術研究としても貴重なデータセットですね。
倉持様:
また、回答バイアスの問題についても、検査結果の補正方法の改善や高度な統計モデリング導入にチャレンジしたいです。これまでは内容的妥当性や構造的妥当性の検証が中心でしたが、今後は検査スコアと実際の職務行動との関連を示す「基準関連妥当性」の検証にも本格的に力を入れます。
現在の心理検査で測定している各要素は自己回答形式なので「自己認識レベル」を測定しています。現場のマネジャーからすると、実際の行動特性と一致している方が実用的です。入社数年後の社員にも同じ検査を受けてもらい、人事評価などと照らし合わせ、尺度の実用性を検証・改善につなげていきたいです。
長期的には、社員への価値還元がなければ人事のデータ収集・分析は支持を得られず形骸化する危機感があります。「人事がよく分からないデータを集めて社員を評価しているらしい」という不信感を生んではいけません。幸い、弊社の人事には明確なビジョンがあり、施策提案時も「その施策はビジョンにどのように結びつくのか」「データの取得、分析を通じて社員にどんな価値を提供するのか」を問われるため、意思決定もスムーズで、社員からの信頼も得やすい環境です。
伊達:
ビジョンがあるおかげで、施策の目的と効果検証のための分析が戦略的に連動しているのは、人事データ分析が成功するポイントですね。まず目的があり、そのためにどんなデータが必要でどう分析・解釈するかが重要です。「とりあえずデータがあるから何か分析してほしい」では、実用性の低いアウトプットに終始しがちです。
倉持様:
目的が曖昧なままでは分析担当者も困りますよね。
ビジネスリサーチラボへの今後の期待
藤井:
最後に、弊社の今後の支援や情報発信について、ご要望や期待があればお聞かせください。
倉持様:
手厚いサポートに感謝しかありませんが、あえて期待を申し上げるなら、項目反応理論に関する、より専門的で詳細な解説記事やセミナーがあると嬉しいです。ターゲット読者層は限られるかもしれませんが(笑)。
伊達:
(笑)。確かにニッチですが、倉持さんのように情報を真剣に必要とされる方は必ずいらっしゃいます。価値ある情報提供が我々の使命です。実際、専門性の高い分析系コラムがきっかけでご相談いただくことも少なくありません。「等化」に関する記事も準備中です。
倉持様:
それは非常に楽しみです。伊達さんがシェアされるコラムはいつもチェックしています。高度な内容は独学では難しく、ありがたい情報源です。項目反応理論を用いて検査開発・運用していると、まさに等化の知識が必要になる場面が出てきます。最新の学術動向や実践的ノウハウを日本語でキャッチアップしたいニーズは常にあります。
能渡:
倉持さんのような実務家のニーズは貴重です。より深い分析内容に踏み込んだコンテンツも積極的に検討します。
倉持様:
もう一点、プロジェクトの進め方について。今回は全てオンラインでしたが、本日初めて皆さんと直接お会いし、対面コミュニケーションの良さを改めて感じました。皆さんの熱意や専門家としての自信が画面越し以上に伝わってきました。
藤井:
我々も本日、倉持さんと直接お会いできて有意義な時間を過ごさせていただいています。
倉持様:
オンラインは効率的ですが、微妙なニュアンスや「熱量」が伝わりにくい面もあると感じます。もしキックオフミーティングだけでも対面でお話しできていれば、目的や背景にある想いの共有が深まり、その後のコミュニケーションもより一体感のあるものになったかもしれません。
伊達:
コミュニケーションの質という観点ですね。
倉持様:
はい。御社のフィードバックは常に論理的で的確ですが、そこにもう少し「このプロジェクトを成功させるためにこうすべきです。一緒に頑張りましょう」といった、共に汗をかく仲間のような熱のこもったコミュニケーションや共感が加わることで、プロジェクト全体の推進力が増したかもしれません。これは個人的な願望に近いですが。
伊達:
貴重なご意見ありがとうございます。倉持さんのように専門性の高い方とは、対等なパートナーとしてオープンで踏み込んだ議論をする方が、アウトプットの質も満足度も向上するかもしれないと感じました。本音で意見を言い合える信頼関係の中でこそ、革新的なアイデアが生まれる可能性も高まりますね。
倉持様:
私自身、無意識のうちに「共に課題解決に取り組める仲間」を御社に求めていたのかもしれません。今回のプロジェクトは大きな学びと成長の機会となりました。
伊達:
もしかすると倉持さんのように、奮闘されている担当者の方が多くいらっしゃるかもしれません。そうした方々がつながり、学び合えるコミュニティがあっても面白いですね。
倉持様:
素晴らしいアイデアですね。御社主催でクライアント企業の担当者を集めた勉強会などがあれば、ぜひ参加したいです。新しい協業や業界全体のレベルアップにつながると思いました。
藤井:
本日は貴重なお話をありがとうございました。いただいたご意見を真摯に受け止め、今後のサービス改善や情報発信に活かしてまいります。