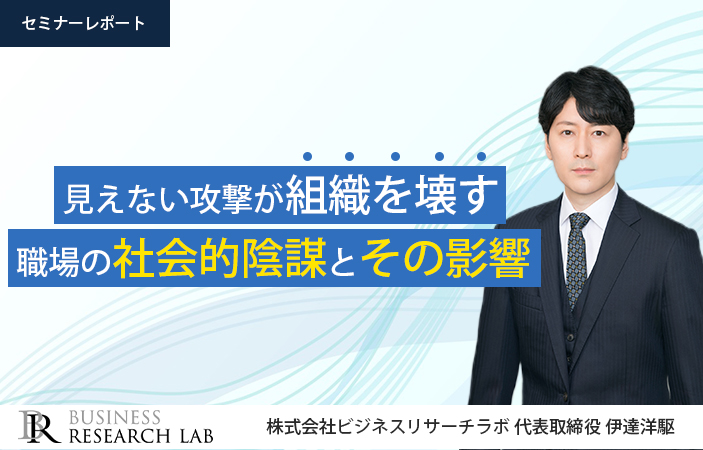2025年5月21日
見えない攻撃が組織を壊す:職場の社会的陰謀とその影響(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年5月にセミナー「見えない攻撃が組織を壊す:職場の社会的陰謀とその影響」を開催しました。
企業の成長と発展を支えるのは、何よりも「人」です。しかし、一見すると円滑に見える職場の人間関係の裏で、組織の活力を密かに奪う現象が存在しているかもしれません。
「社会的陰謀」と呼ばれるこの現象は、直接的な暴言やいじめとは異なり、陰口や意図的な情報操作、仲間外れなど、表面化しにくい形で進行します。こうした行為は単なる人間関係のトラブルだけではなく、組織の生産性低下や優秀な人材の流出につながる深刻な問題として、近年の学術研究で注目を集めています。
本セミナーでは、組織内で起こる「社会的陰謀」について、その本質と組織への影響を理解し、人事として何ができるのかを考えました。これまで「なんとなく感じていた」職場の息苦しさや生産性低下の背景に、新たな視点で光を当てました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
私たちが日々過ごす職場という小さな社会には、様々な力学が働いています。笑顔の裏に隠された駆け引きや情報操作、さりげない排除の仕組み。このような水面下の行為は「社会的陰謀」と呼ばれ、組織の中で静かに、しかし確実に影を落としています。
社会的陰謀の巧妙さは、その見えにくさにあります。被害者は自分の感覚を疑い、「私の思い過ぎかもしれない」と自問自答を繰り返すうちに、精神的な消耗へと導かれていきます。また、こうした目に見えない攻撃は個人の心の健康を蝕むだけでなく、組織全体の創造性や生産性を低下させる原因ともなっています。
本講演では、社会的陰謀の実態とその影響、そして予防策について、研究知見をもとに考えていきます。
社会的陰謀とは
社会的陰謀とは、職場や組織において他者の成功や評判を故意に妨げる行為を指します。具体的には、同僚について悪い噂を広める、重要な情報をわざと伝えない、仕事の進行を巧妙に妨害する、会議で特定の人の意見を無視するなどの行動が含まれます。
社会的陰謀が研究対象として注目されるようになったのは比較的最近のことです。ある体系的な文献調査によれば、2000年代初期には社会的陰謀に関する研究はわずかでしたが、その後、急速に増加し、現在では組織行動論や社会心理学のテーマの一つとなっています[1]。
社会的陰謀の特徴的な点は、相手の評判を落とし、仕事上の信頼を失わせることを目的としている点です。暴言や身体的な攻撃といった顕在的な攻撃とは異なり、社会的陰謀は巧妙かつ潜在的に行われるため、第三者からは見えにくいという厄介さがあります。
社会的陰謀と類似した概念として、職場でのいじめやパワーハラスメント、無礼な言動などがありますが、社会的陰謀の場合は特に「陰で」行われる情報操作や人間関係の歪曲に焦点が当てられています。
社会的陰謀がもたらすもの
社会的陰謀は被害者だけでなく、組織全体にも様々な悪影響をもたらします。多くの研究によって、その否定的な帰結が明らかになっています。
第一に、社会的陰謀を受けると、精神的な負担により感情的に疲弊します。韓国のホテルで働くフロントライン従業員を対象とした調査では、社会的陰謀を経験した従業員ほど感情的消耗が強まることが確認されました[2]。「周囲が意図的に邪魔をしていると感じたことがある」「同僚から冷たい扱いを受けたと自覚することがある」というのが、この研究における社会的陰謀になります。
分析の結果、社会的陰謀の経験と感情的消耗の間には関連性が見られ、さらにその感情的消耗が仕事の先延ばし行動を助長することも明らかになりました。感情的に疲れ切った状態では、日常的な業務に対する集中力が低下し、「後でやろう」という先延ばし行動が増加します。これは短期的には個人の仕事パフォーマンスの低下をもたらし、長期的には組織全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
第二に、社会的陰謀は周囲との信頼関係を崩壊させます。マレーシアの従業員を対象にした研究では、同僚からの社会的陰謀が信頼感の低下を通じて、職場での協力行動の減少につながることが実証されました[3]。分析の結果、同僚から社会的陰謀を受けると、その人たちへの信頼が大きく揺らぎ、結果として周囲を自主的に助ける行動(組織市民行動)が減少することが明らかになりました。
信頼の喪失は建設的な行動を弱めるだけでなく、組織に害をもたらす行動(反組織的行動)を増加させる傾向も確認されています。これは「自分が攻撃されたのだから仕返しをしても構わない」という互恵性の原理が働いているためと考えられます。
第三に、社会的陰謀は組織に対する愛着のあり方を歪めます。ある研究では、組織コミットメントの三つの次元(情緒的コミットメント、規範的コミットメント、継続的コミットメント)と社会的陰謀の関係が調査されました[4]。分析の結果、社会的陰謀を受けると情緒的コミットメント(組織への愛着や帰属意識)と規範的コミットメント(組織に対する義務感)は低下する一方、継続的コミットメント(組織を離れることによる損失を避けるための帰属意識)は逆に高まりました。
社会的陰謀に晒された従業員は、組織に対する愛着や義務感は失われるものの、「ここを辞めると収入面などで困るから」という計算に基づいて組織に留まる可能性が高まるということです。これは、いわゆる「会社に愛着を持たないぶら下がり社員」を生み出す危険性を示唆しています。
第四に、社会的陰謀は従業員の創造性を低下させます。広告代理店の従業員を対象にした調査では、社会的陰謀を強く感じるほど、従業員が新しいアイデアを生み出す力が阻害されることが明らかになりました[5]。このメカニズムとして、周囲への不信感と知識隠蔽行動が媒介要因となっていることが示されています。
社会的陰謀に晒されると、「自分のアイデアを共有すると利用されるだけかもしれない」という恐れから、知識やノウハウを隠すようになります。そうなると、組織内での知識共有や相互刺激が減少し、結果として創造的な発想が生まれにくくなります。イノベーションが重視される現代企業において、この影響は看過できません。
さらなる深刻な悪影響
社会的陰謀の悪影響はさらに複雑かつ深刻な形で現れることが明らかになっています。特に注目したほうが良いのは、社会的陰謀が有能な人材に深刻なダメージを与える可能性があることと、被害者が新たな加害者になるという負の連鎖を引き起こす危険性です。
初めに、高い能力を持ち、自信を持って仕事に取り組む人ほど、社会的陰謀による悪影響が大きいという事実があります。アメリカやイギリスの医療関係者などを対象とした調査では、自己評価が高く、マネジメントシステムへの信頼が強い従業員ほど、上司からの社会的陰謀に深く傷つくことが示されています[6]。
この調査では、上司からの社会的陰謀の経験度、自己評価、組織のマネジメント全般への信頼感などを測定し、それらと従業員のストレスや離職意向との関連性を分析しました。その結果、自己評価が高い従業員ほど、上司からの社会的陰謀による精神的負荷を強く感じ、その後に離職を考えたり、仕事場面でのストレスを抱え込んだりすることが分かりました。
このメカニズムについて研究者たちは、自己認知理論に基づく説明を提示しています。自分を有能だと認識している人ほど、「なぜ自分がこのような不当な扱いを受けるのか」と強く感じ、それがさらなる心理的苦痛を生むというのです。
さらに、マネジメントへの信頼が高いほど、その落差による失望感も大きくなります。組織全体を信頼していたにもかかわらず、直属の上司から陰謀を受けるという矛盾した状況に直面すると、「組織を信じていたのに裏切られた」という感覚が増幅されます。
この結果は組織にとって憂慮すべきものです。組織が保持したい人材、すなわち有能で自信にあふれ、組織を信頼している従業員が、社会的陰謀によって大きな打撃を受け、離職リスクが高まるからです。
もう一つの深刻な問題は、社会的陰謀の連鎖的な広がりです。ある銀行の従業員を対象とした縦断的研究では、社会的陰謀の被害者が後日、自らも加害者になるという現象が確認されています[7]。この研究では、複数の時点でデータを収集し、初期の被害経験がその後の加害行動にどのように影響するかを追跡しました。
分析の結果、他者から社会的陰謀を受けて精神的に消耗した従業員が、後日、同僚に対して同様の陰謀行為に及ぶ可能性が有意に高くなることが明らかになりました。研究者たちはこのプロセスを、対人関係における不公正感の知覚と自己統制資源の枯渇という二つの要因で説明しています。
社会的陰謀の被害を受けると、まず「自分は不当な扱いを受けている」という不公正感が生まれます。この不公正感は、「自分も同じように他者を扱っても構わない」という道徳的正当化につながりやすくなります。さらに、社会的陰謀による継続的なストレスは自己統制資源を消耗させ、衝動的な行動や攻撃的な反応を抑制する能力を低下させます。
社会的陰謀を予防するには
これまで見てきたように、社会的陰謀は個人の心理的健康だけでなく、組織全体の機能にも深刻な悪影響を及ぼします。社会的陰謀を予防するために、どのような取り組みが可能でしょうか。研究知見から、いくつかのアプローチを探ってみましょう。
社会的陰謀の原因の一つとして、同僚に対する嫉妬感情があります。通信関連の職場に勤める従業員を対象とした調査では、同僚に嫉妬を感じる人ほど、社会的陰謀の加害者になる可能性が高いことが明らかになっています[8]。この研究では、嫉妬のタイプを「模倣的嫉妬」「無力感を伴う嫉妬」「悪意を伴う嫉妬」などに分類し、それぞれが社会的陰謀とどのように関連するかを分析しました。
結果、嫉妬を抱く従業員は、そうでない従業員に比べて周囲の評価や地位を落とそうとする行為に走りやすいことが確認されました。興味深いことに、一見向上心のように見える模倣的嫉妬(相手のように成功したいという感情)でさえ、時に他者を貶める行動につながります。
嫉妬が強い場合は、同僚の評判を意図的に傷つける言動に及ぶ確率が高まります。こうした知見は、嫉妬感情が必ずしも自己向上の動機づけとして機能するとは限らず、むしろ周囲への敵意や破壊的行動を引き起こす危険性があることを表しています。
次に目を向けるべき要因は、政治的スキルとライバル意識の関係です。政治的スキルとは、職場内で情報収集や人脈形成に長けた能力を指しますが、そのようなスキルを持つ人が周囲にいると、自分の地位への脅威を感じて社会的陰謀を仕掛ける可能性があることが研究で提示されています[9]。
この研究では、政治的スキルの高い従業員が成功している場面に遭遇すると、周囲の人々が「自分の立場が脅かされる」と感じ、直接的な衝突を避けつつも、陰で相手の評判を傷つけようとすることが確認されました。とりわけ、ライバル意識の強い環境や競争的な評価制度がある場合、このような行動が起こりやすくなります。
さらに、「将来の脅威」の認識が社会的陰謀を誘発する可能性もあります。ある長期追跡調査では、「近い将来、自分を追い抜くかもしれない」と感じる同僚に対して、現時点で既に妨害行為を仕掛けることが確認されました[10]。この研究では、参加者に同じ組織で働く他者の成長度合いを評価してもらい、その人物が今後どの程度台頭してくるかをイメージしてもらっています。
分析の結果、将来の脅威を強く感じるほど、嫉妬や不安が高まり、その後の社会的陰謀行動につながることが明らかになりました。組織内の競争が激しい環境では、この傾向がより顕著になります。現時点ではそれほど目立っていなくても、潜在的に有能だと認識される人物に対して、早い段階から妨害行為が始まる可能性があります。
これらの知見を踏まえると、社会的陰謀を予防するためには、他者との相対的な比較を意識しやすい環境は可能な限り避けるべきでしょう。周囲と自分を比べることを促されると、嫉妬や不安、さらには敵意を生み出しやすくなります。そのような感情が高まると、社会的陰謀行動へと発展するリスクが高まります。
比較対象としては、他者ではなく、むしろ自分自身の過去の状態や将来の目標を基準にすることが望ましいと言えます。「昨年の自分と比べてどれだけ成長したか」「半年後の目標に向けてどのように進歩しているか」といった視点から評価を行うことで、個人の成長や目標達成に集中できます。他者に対する敵意や嫉妬を生み出す比較ではなく、自分自身に意識が健全な形で向くような設計が、社会的陰謀の予防において重要となります。
とはいえ、実際の職場環境においては、他者との比較が必要な場合や、完全に避けることが困難な状況もあります。業績評価や昇進選考、プロジェクトチームの編成など、ある程度の比較は組織運営上、不可避です。このような場合に重要なのは、他者比較によってネガティブな事態や結果に陥ることを想像させないような工夫です。「あの人が評価されると自分の立場が危うくなる」「彼・彼女が昇進すれば自分のチャンスが減る」といったゼロサム的な想像が、社会的陰謀行動のリスクを高めます。
そうではなく、他者比較を通じて自分の良い面や独自の強みを明確化するように促すことが大切です。「彼・彼女のプレゼン能力は素晴らしいが、自分は細部への配慮に優れている」「あの人は創造性に長けているが、自分は実行力がある」といったように、比較を通じて互いの補完関係や多様な強みの価値を認識できるようにしましょう。
仮に比較によって自分の弱みや改善点が見つかったとしても、それは将来的に向上させていける成長の機会として捉える視点を共有しましょう。「現時点での不足は、明日への成長のチャンスでもある」という成長志向の姿勢を醸成することで、他者への敵意ではなく自己改善への動機づけが強まります。
それでも、人間である以上、他者の成功や卓越した能力に対して嫉妬や不安、時には羨望といった感情を抱くことは自然なことです。これらの感情は基本的な人間の心理として現れるものであり、過剰に否定したり抑圧したりするべきものではありません。こうした感情を職場で認識し、必要に応じて共有できる心理的安全性の確保が求められます。
「嫉妬を感じるなんて未熟だ」「不安になるのは弱さの表れだ」といった価値判断を職場に持ち込むのではなく、こうした感情も含めて人間らしさの一部として受け入れるということです。嫉妬や不安、不満といった感情を健全に表現できる環境がなければ、それらは陰湿で破壊的な形で表出してしまう恐れがあるからです。
この種の感情の開示や共有を組織内で進めるためには、まずはリーダーが率先して自らの弱みや過去の失敗、現在感じている不安や葛藤などを適切な形で開示しましょう。リーダーがあえて脆弱性を見せることで、「完璧である必要はない」「困っていることや感じていることは正直に伝えても大丈夫」という信念がチーム内に根付いていきます。
例えば、会議の冒頭で「先週の私の判断にはこういう誤りがあった」と率直に認めたり、「このプロジェクトについて私もこんな不安を感じている」と共有したりすることが、チーム全体の心理的安全性を高める一歩となります。リーダーの率直さと誠実さが、組織全体の透明性と信頼関係を強化し、結果的に、社会的陰謀のような間接的で破壊的な対処法に頼る必要性を減少させます。
おわりに
社会的陰謀は、その巧妙さと潜在性ゆえに見過ごされがちですが、個人の心理的健康と組織全体の活力を蝕む深刻な問題です。本講演で見てきたように、その影響は感情的消耗から創造性の低下、さらには負の連鎖的拡大にまで及びます。
しかし、希望はあります。嫉妬や比較がもたらす危険性を理解し、成長志向の文化を育み、心理的安全性を確保することで、社会的陰謀の連鎖を断ち切ることができます。それには、問題を個人間の軋轢と矮小化せず、組織全体の課題として認識し、透明性と相互尊重に基づいた対策を講じることが必要です。
職場の人間関係の質が、私たちの仕事の質と幸福感を左右する現代において、社会的陰謀のない組織づくりは、持続可能な成功のための条件の一つだと考えられます。
Q&A
Q:「社会的陰謀」という訳は誤解を招くのではないでしょうか。例えば、「転覆行為」や「静かな追い落とし行為」という呼び方はどうでしょうか。
「ソーシャル・アンダーマイニング」の訳は確かに難しい部分があります。「アンダーマイニング」には弱体化や弱めるという意味合いがあり、「ソーシャル・アンダーマイニング」は相手の信頼を失墜させたり、評判を下げたりする行為を指します。
「社会的陰謀」と訳されるケースがあるため、今回はそのように訳しました。ご提案いただいた「転覆行為」や「静かな追い落とし行為」も、相手を弱体化させるという意味では近いと思います。特に「追い落とし」という表現は、相手を弱めたり、追いやったりする力という部分が伝わっていると思います。
また「社会的」という言葉もやや分かりにくいかもしれません。これは「人間関係に関する」という意味ですが、社会全体を連想させてしまう部分があるかもしれません。
Q:講演の中で嫉妬が社会的陰謀につながると説明がありましたが、評価制度が嫉妬を生みやすい設計になっていないか見直したいと考えています。どのような制度設計がおすすめでしょうか。
相対評価と絶対評価について触れたことがきっかけになったのかもしれません。組織を運営していく上で相対評価をまったく行わないことは難しいため、相対評価と絶対評価のバランスが重要になってきます。
また、個人の成果だけでなく、チームへの貢献や他者支援といった要素を評価に取り入れることも一つです。これは社会的陰謀の「逆バージョン」とも言えるでしょう。協力的な行動を積極的に評価する形が考えられます。
講演でも触れましたが、「誰かが評価されると自分の取り分が減る」というゼロサム的な思考を避けることも肝要です。そのためには、評価制度を設計・運用する際に、様々な役割や強みが評価される複線型の評価を取り入れる方法があります。多様な評価軸を設けることで、一元的に「あの人と私が競争する」という状態を避けられるのではないでしょうか。
Q:中途入社の社員が社会的陰謀の標的になりやすいと感じています。特に経験豊富な専門職が既存のやり方に疑問を投げかけると、抵抗や排除の動きが見られます。新しい視点を生かしたいのですが、どうすれば良いでしょうか。
キャリア採用で入ってきた社員が「既存のやり方に疑問を投げかける」ことで社会的陰謀の標的になりやすいというご指摘ですね。新しい人材の意見は既存の社員にとって脅威に感じられる場合があります。
例えば、この問題に対しては、「翻訳者」の役割を担う人材がいると効果的です。5年前にキャリア採用で入社した社員など、社内の人間関係と規範を理解しつつ、新しく入ってくる人の気持ちも分かる立場の人が橋渡し役となると良いでしょう。メンターなど、公式に橋渡し役を任命することで、抵抗や排除の動きが薄まる可能性があります。
また、中途入社の社員に対しても、組織へ知見を提供することの重要性と同時に、既存の関係性や仕事の進め方に敬意を払うことの大切さを伝えることも有効です。オンボーディングのプロセスの中でこうした点を伝えることで、中途社員に対する社会的陰謀が減少する可能性があります。
Q:社会的陰謀の問題を人事部が把握しても、「余計なことに介入するな」と現場マネージャーから反発されることがあります。階層や権限の壁を越えてこの問題に関与するためにはどうすれば良いでしょうか。
なぜマネージャーが反発するのかを考えてみると良いかもしれません。自分の自律性や権限が脅かされると感じ、防衛的な反応を示している可能性があります。
対応として考えられるのは、社会的陰謀の問題を「誰が」解決するのかというスタンスを明確にすることです。人事部が「問題解決者」として主導的に介入すると反発を招きやすいので、あくまで「支援者」としてのポジションで関わるのが良いでしょう。
具体的には、似たような問題を抱えている、あるいは既に解決した経験のあるマネージャー同士のつながりを作り、人事部がそのファシリテーターとなる方法が考えられます。このように、問題解決を押し付けるのではなく、マネージャー自身が解決するのをサポートする立場から関わることで、状況が緩和される可能性があります。
Q:社会的陰謀が原因で退職した元社員から、後日、口コミサイトで会社の評判を下げるような投稿をされるケースがあります。このようなレピュテーション・リスクにどう対応すれば良いか困っています。
大前提として考えるべきなのは、退職した社員が口コミサイトで不満を表明しているということは、組織内でその声が聞かれなかった可能性があるということです。その意味では、心理的安全性の高い職場づくりが重要です。
すでに退職が決まった状況での対応としては、第三者による退職面談を退職プロセスに組み込むことが考えられます。中立的な立場の人が「組織を改善するためのフィードバックが欲しい」という姿勢で聞き取りを行うことで、様々な経験や問題点を把握し、組織改善につなげることができるでしょう。
また、退職後も良好な関係を継続しましょう。例えば、アルムナイ・ネットワークを構築し、ポジティブな関係を維持できるようにすることも対策として考えられます。
すでに否定的な投稿が出てしまっている場合は、その内容を真摯に受け止め、組織改善に活かす姿勢を示します。口コミは現在の社員や入社を検討している人も見ている可能性があるため、見て見ぬふりをするのではなく、学びの姿勢を組織内外に示していきましょう。少しでも改善できるところがあれば、それを改善のチャンスととらえ、前向きな姿勢で対応することが有効です。
脚注
[1] Haider, B., Khizar, H. M. U., Kallmuenzer, A., and Hilal, O. A. (2024). Unraveling social undermining at the workplace: A systematic review of past achievements and future promises. Strategic Change, 33(1), 45-67.
[2] Jung, H. S., and Yoon, H. H. (2022). The Effect of Social undermining on employees’ emotional exhaustion and procrastination behavior in deluxe hotels: Moderating role of positive psychological capital. Sustainability, 14(2), 931.
[3] Lin, D. O., and Angeline, T. (2019). The Effects of co-workers’ social undermining behaviour on employees’ work behaviours, Istanbul International Academic Conference Proceedings.
[4] Jing, E. L., Gellatly, I. R., Feeney, J. R., and Inness, M. (2023). Social undermining and three forms of organizational commitment: The moderating role of employees’ attachment style. Journal of Personnel Psychology, 22(1), 31-42.
[5] Khan, M. A., Malik, O. F., and Shahzad, A. (2022). Social undermining and employee creativity: The mediating role of interpersonal distrust and knowledge hiding. Behavioral Sciences, 12(2), 25.
[6] Booth, J. E., Shantz, A., Glomb, T. M., Duffy, M. K., and Stillwell, E. E. (2020). Bad bosses and self-verification: The moderating role of core self-evaluations with trust in workplace management. Human Resource Management, 59(2), 135-152.
[7] Lee, K. Y., Kim, E., Bhave, D. P., and Duffy, M. K. (2016). Why victims of undermining at work become perpetrators of undermining: An integrative model. Journal of Applied Psychology, 101(6), 915-924.
[8] Yarivand, M. (2024). How envy drives social undermining: An analysis of employee behavior. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 9(7), 2005-2011.
[9] Sun, S. (2022). Is political skill always beneficial? Why and when politically skilled employees become targets of coworker social undermining. Organization Science, 33(3), 1142-1162.
[10] Reh, S., Troster, C., and Van Quaquebeke, N. (2018). Keeping (future) rivals down: Temporal social comparison predicts coworker social undermining via future status threat and envy. Journal of Applied Psychology, 103(4), 399-415.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。