2026年2月20日
なぜ新しいシステムは使われないのか:技術受容モデルで読み解く導入の壁
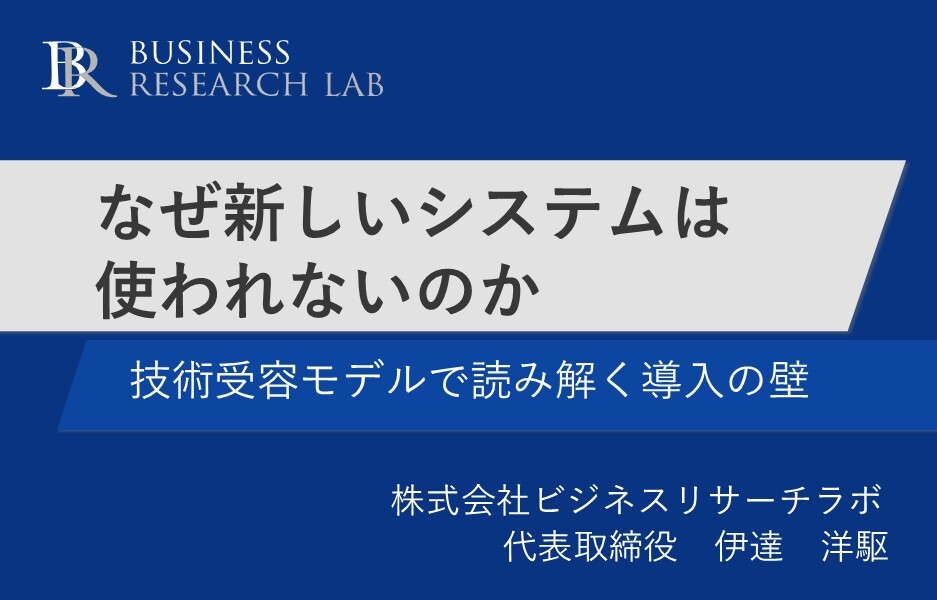
新しい技術が私たちの職場や生活に導入されることは、日常的な風景となりました。しかし、組織が多大なコストを投じて導入したシステムが、思うように使われないという現実は、多くの現場で共通する悩みではないでしょうか。最新の機能を備えたツールであっても、それが人々に受け入れられ、活用されなければ、期待された成果を生むことはありません。
人はどのようなときに新しい技術を「使おう」と決意するのでしょうか。この問いに光を当てたのが、「技術受容モデル(TAM)」と呼ばれる考え方です。これは、特定の技術が人々に受け入れられる過程を説明しようとする、この分野の議論の出発点とも言える枠組みです。
しかし、このモデルも万能ではありません。発表以来、他の様々な理論と比較され、時には弱点を補う形で拡張され、より大きな枠組みへと統合されていくことになります。本コラムでは、「技術受容モデル」が、他の主要な理論とどのように比較され、発展していったのか、その学術的な探求の道のりをたどります。
技術の利用意図は、TRAよりTAMが強く予測した
新しい技術を人々が受け入れる過程を解明しようとする試みの中で、基本となる二つの理論モデルを直接比較した研究があります[1]。一つは「合理的行動理論(Theory of Reasoned Action: TRA)」、もう一つは「技術受容モデル(Technology Acceptance Model: TAM)」です。
どちらのモデルも、「信念が態度を形成し、その態度が意図を、意図が実際の行動を引き起こす」という共通の骨格を持っています。しかし、その「信念」の扱いに違いがありました。
合理的行動理論は、汎用的な枠組みです。その状況ごとに関連する信念を新たに見つけ出し、それらの信念と、その結果をどう評価するかの組み合わせで、態度が決まると考えます。一方、技術受容モデルは、情報技術の利用に特化しています。あらかじめ「知覚された有用性(その技術が仕事の成果向上に役立つか)」と「知覚された使いやすさ(その技術を努力なく使えるか)」という二つの信念が根幹にあると特定し、これらが態度や意図にどう作用するかを分析します。
この研究は、二つのモデルのどちらが「技術を使おう」という意図をより強く説明できるのかを、実際の現場で検証しました。対象となったのは、あるビジネススクールのMBA課程に在籍する107名の学生です。彼ら彼女らが学期中に任意で使用できるワープロソフト「WriteOne」が、分析対象の技術となりました。ワープロは必須ではなく、自発的な利用が想定されるため、受容の過程を調べるのに適していました。
調査は二回に分けて行われました。一回目は、学期開始時に1時間の導入講習を受けた直後(Time 1)、二回目は14週間後の学期末(Time 2)です。Time 2では、実際にどの程度ソフトを使用したか、自己申告による使用頻度も尋ねられました。
分析の結果、いくつかの事実が浮かび上がりました。「使用する意図」は、その後の「実際の使用」をある程度予測できることがわかりました。導入直後の意図と14週間後の使用頻度には相関(r=.35)が、学期末の同時点での測定では相関(r=.63)が確認されました。意図を考慮に入れると、他の変数(態度、有用性、使いやすさなど)は実際の使用に直接的な結びつきを持たず、意図がそれらの考えを代表している様子がうかがえました。
二つのモデルの意図に対する説明力を比較しました。合理的行動理論は、意図のばらつきの約3割(Time 1で32%, Time 2で26%)を説明しました。このモデルでは、「態度」は意図と強く関連していましたが、「主観的規範(周囲の人が自分に使ってほしいと思っているか)」は、二つの時点ともに明確な関連が見られませんでした。
対照的に、技術受容モデルは、意図のばらつきの約5割(Time 1で47%, Time 2で51%)を説明しました。両方の時点で「有用性」は意図に対して強い正の関連を持っていました。「使いやすさ」は、導入直後(Time 1)では意図に直接的・間接的なかかわりを持ちましたが、14週間後(Time 2)では、主に「有用性」を高めることを通じて、意図に結びついていることがわかりました。
この結果から、技術受容モデル、特に「有用性」「使いやすさ」「意図」という三つの要素だけでも、人々の受容を力強く説明できることが示唆されます。
このことは、「使いやすさ」が「有用性」を高めることを通じて、間接的に意図や使用に結びつくという技術受容モデルの理論的な仕組みと一致します。「使いやすさ」と「使用」の間に関連が見られても、「有用性」を考慮に入れると「使いやすさ」の直接的な結びつきが消え、「有用性」の関連が強く残るというパターンが観察されました。
技術受容の予測精度はTAM、原因特定はTPBが優れていた
先ほどの研究では、技術受容モデルが、その前身である合理的行動理論よりも、技術の利用意図をうまく説明できることが示されました。しかし、人間の行動を説明する理論は他にも存在します。その代表格が「計画的行動理論(Theory of Planned Behavior: TPB)」です。
計画的行動理論は、合理的行動理論を拡張したもので、人の「意図」は三つの要素によって決まるとされます。一つ目は「態度」(その行動を良いか悪いか評価する)、二つ目は「主観的規範」(周囲がその行動をどう思うか)、三つ目は「知覚された行動統制」(その行動を自分がうまく実行できると思うか)です。
技術受容モデルと計画的行動理論は、いくつかの点で異なります。技術受容モデルは、技術利用に特化し、「有用性」と「使いやすさ」を二大信念として仮定します。
一方、計画的行動理論は汎用的であり、状況に応じて関連する信念(例:時間、コスト、他者の意見)が変わると考えます。また、計画的行動理論は「主観的規範」という社会的圧力を明確に含みます。さらに、行動の制御可能性について、技術受容モデルは「使いやすさ」というシステム内部の要因に焦点を当てますが、計画的行動理論の「知覚された行動統制」は、スキルといった内部要因だけでなく、時間や機会、リソースといった外部の状況要因も含む、より広い概念です。
これら二つのモデルを、三つの基準(1. 意図の予測精度、2. 提供される情報の価値、3. 適用の容易さ)で比較する研究が行われました[2]。
研究は、経営学入門コースの学生262名を対象に実施されました。課題は、売上やコストを予測する会計関連のもので、学生は「スプレッドシート」か「電卓」のどちらを使ってもよいとされました。どちらを使っても成績に変わりはなく、利用は完全に任意でした。
学生はランダムに二つのグループに分けられ、一方は技術受容モデルに関する質問群に、もう一方は計画的行動理論に関する質問群に回答しました。計画的行動理論を適用するためには、その状況固有の信念を特定する必要があります。事前のパイロットスタディにより、この課題では「所要時間」「正確性」(態度の基盤)や、「スプレッドシートの知識」「アクセス環境」(行動統制の基盤)が関連する信念として特定され、質問項目に組み込まれました。
分析の結果、予測精度について、両モデルともスプレッドシートを使うかどうかの意図を非常によく予測できることがわかりました。技術受容モデルは、意図のばらつきの約69%を説明しました。意図に対しては、「知覚された有用性」が「態度」よりも強い結びつきを持っていました。
一方、計画的行動理論は、意図のばらつきの約60%を説明しました。意図に対しては、「態度」と「知覚された行動統制」が結びついていましたが、「主観的規範」は明確な関連が見られませんでした。予測精度という点では、技術受容モデルが計画的行動理論をわずかに上回る結果となりました。
続いて、適用の容易さ(コスト)です。技術受容モデルは「有用性」と「使いやすさ」という標準化された項目を使えるため、迅速かつ安価に調査が可能です。対照的に、計画的行動理論は、状況ごとの信念を特定するための事前調査が必要であり、より多くの手間がかかります。
最後の基準は、提供される情報の価値、すなわち「診断力」です。技術受容モデルが提供する情報は、「有用だと感じられていない」「使いにくいと思われている」という一般的なレベルにとどまります。一方、計画的行動理論は、「なぜ」有用でないと感じるのか(例:「時間がかかるから」)、あるいは「何が」利用を妨げているのか(例:「知識が不足しているから」)といった、具体的な原因を突き止めるための情報を提供します。
この研究は、両モデルがどちらも強力であるとしたうえで、目的に応じた使い分けを提案しています。多様なユーザーの全般的な認識を迅速に把握したい場合は、技術受容モデルが適しています。しかし、特定のグループがなぜシステムに不満を持っているのか、その具体的な原因を深く掘り下げたい場合は、計画的行動理論が優れた情報をもたらします。
技術受容の説明力は、TAMとTTFの統合で向上した
これまでの比較は、技術受容モデル(TAM)と、人間の一般的な行動理論(TRAやTPB)との間で行われてきました。しかし、TAMの内部にも、見落とされている視点があるのではないかという議論が起こります。TAMは「有用性」や「使いやすさ」といった個人の「知覚」に焦点を当てますが、そもそもその技術が、ユーザーの行うべき「業務(タスク)」に適しているのかという視点が欠けている、という指摘です。
情報技術は本来、組織的なタスクを達成するためのツールです。「有用性」という言葉には、暗黙のうちに「何かのタスクにとって有用」という意味が含まれていますが、タスクの特性を組み込むべきだという考え方があります。これが「タスク・テクノロジー・フィット(Task-Technology Fit: TTF)モデル」です。
TTFモデルは、TAMとは異なる視点を取ります。このモデルの基本的な考え方は、技術がユーザーの活動(タスクの要求)を適切にサポートする場合、すなわち「フィット」する場合にのみ、その技術は利用されるというものです。合理的なユーザーは、仕事のパフォーマンス向上という便益を最大化できるツールを選択すると仮定します。
TAMが「態度」(そのITが好きか)という側面を捉えるのに対し、TTFは「合理性」(そのITがタスク達成に役立つか)という側面を捉えます。ユーザーは、たとえそのITが好きでなくても、仕事のパフォーマンスが向上するならばそれを利用することもあるため、両方の側面を考慮することが有益だと考えられます。
そこで、TAMとTTFという二つの異なる視点を持つモデルを統合し、より高い説明力を持つ新しいモデルを構築しようとする研究が行われました[3]。
この研究では、TTFモデルの構成要素(タスク特性、ツール機能、ツール経験、TTF)が、TAMモデルの構成要素(知覚された有用性、知覚された使いやすさ)の「先行要因」として位置づけられました。
この統合モデルを検証するため、大手企業3社に勤務するプログラマー・アナリストが対象とされました。彼ら彼女らが実際に行った60のソフトウェア保守プロジェクトに関するデータが収集されました。
TAMに関する変数(意図、態度、有用性、使いやすさなど)は、プロジェクトの「開始前」に測定されました。一方、「実際のツール利用」や「タスク特性」はプロジェクトの「完了後」に測定されました。
この研究の特徴は、「タスク・テクノロジー・フィット(TTF)」を、ユーザーの主観的な知覚(「フィットしていると思うか」)としてではなく、客観的に算出した点です。プログラマーが報告した保守タスクの活動と、利用可能なツールの機能とを突き合わせることでTTFスコアが算出されました。
分析の結果、まず各モデルを単独で検証しました。TAM単独モデルは、「実際のツール利用」のばらつきの36%を説明しました。一方、TTF単独モデルは、41%を説明し、TAM単独を上回りました。
その後、提案された統合TAM/TTFモデルを検証したところ、「実際のツール利用」のばらつきの51%を説明しました。これは、TAM単独(36%)やTTF単独(41%)のいずれよりも高い説明力でした。
TTFからTAMへの経路については、予想通りの結果と予想外の結果が混在していました。
予想通りだったのは、「ツールの機能性(複雑さ)」が「使いやすさ」に負の関連を、「ツール経験」が「使いやすさ」と「有用性」の両方に正の関連を持っていた点です。
予想外だったのは、理論的に強い関連が予想されていた「TTF(適合性)」から「有用性」への直接的なパスが、有意ではなかった点です。タスクに適合しているからといって、即座に「有用だ」とは認識されていませんでした。
しかし、分析を深めると、「TTF」は「使いやすさ」に正の関連を持っており、その「使いやすさ」を介して「有用性」に間接的な関連を持っていることがわかりました。この発見は興味深く、ツールがタスクにどれほど客観的にフィットしていても、それが「使いやすい」と知覚されなければ、最終的に「有用」だとは認識されない可能性を示しています。
技術受容理論を統合したUTAUTは、説明力が向上した
これまでの道のりで、「技術受容モデル(TAM)」が、合理的行動理論(TRA)と比較され、計画的行動理論(TPB)と診断力の違いが検討され、タスク・テクノロジー・フィット(TTF)モデルと統合されることで、その説明力を高めてきた過程を見てきました。
この過程で明らかになったのは、TAMが中核的ながらも、それだけでは捉えきれない要因(社会的圧力、行動の制御可能性、タスクとの適合性など)が存在するということです。その結果、情報システムの研究分野では、TAM、TPB、TTF、イノベーション普及理論(IDT)など、個人の技術受容を説明するための多様なモデルが乱立する状況が生まれていました。
これらの乱立するモデルをレビューし、経験的に比較して、一つの統一的な枠組みへと統合しようとする研究プロジェクトが実施されました[4]。その成果が、「技術受容と利用の統一理論(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT)」です。
この研究は、まず8つの著名なモデルを特定し、それらを同一のデータセットで比較することから始まりました。
データは、4つの異なる組織(エンターテイメント、通信、銀行、行政)で、新しい技術が導入されるタイミングから縦断的に収集されました。技術導入後の複数の時点(トレーニング直後、1ヶ月後、3ヶ月後など)で調査が行われ、実際の利用行動は6ヶ月間にわたって追跡されました。また、4組織のうち2組織は利用が任意(自発的)な環境、他の2組織は利用が強制的(義務的)な環境であり、状況の違いも考慮されました。
この比較分析の結果、8つのモデルの利用意図に対する説明力は、17%から53%の範囲であることがわかりました。この比較結果と、各モデルの構成要素間の概念的な類似性に基づき、UTAUTモデルが定式化されました。
UTAUTは、個人の「行動意図」と「利用行動」を予測するために、4つの核となる決定要因と、4つの調整変数を統合したモデルです。4つの核となる要因は以下の通りです。
- 「パフォーマンス期待(Performance Expectancy)」:システムが仕事の成果向上に役立つかという信念。TAMの「有用性」など、各モデルで最も強力だった成果関連の概念を統合したものです。
- 「努力期待(Effort Expectancy)」:システムの利用がどれだけ容易か。TAMの「使いやすさ」など、努力関連の概念を統合したものです。
- 「社会的影響(Social Influence)」:重要な他者が自分にシステムを使うべきだと信じているか。TPBの「主観的規範」など、社会的圧力の概念を統合したものです。
- 「促進条件(Facilitating Conditions)」:利用をサポートする組織的・技術的インフラが存在するか。TPBの「知覚された行動統制」など、障壁除去の概念を統合したものです。
UTAUTの最大の貢献は、これらの4要因が「いつ」「誰にとって」強まるのかを規定する「調整変数」を導入した点です。調整変数として、「性別」「年齢」「経験」「自発性(任意か強制か)」の4つが設定されました。例えば、以下のような関連が想定されました。
- 「パフォーマンス期待」は、特に男性、そして若年の従業員において意図への結びつきが強い。
- 「努力期待」は、特に女性、高齢の従業員、利用経験の浅い初期段階で結びつきが強い。
- 「社会的影響」は、利用が「強制的」な状況で、特に高齢の女性、かつ経験の浅い場合にのみ意図と結びつく。
- 「促進条件」は「意図」には直接関連せず、「実際の利用行動」に直接関連する。この結びつきは、特に高齢の従業員が経験を積むにつれて強まる。
このUTAUTモデルの有効性を、元の4組織のデータと、新たに追加した2組織(金融サービス、小売)のデータを用いて、2段階で検証しました。その結果、UTAUTモデルは、行動意図のばらつきの約69%から70%を説明しました。これは、元の8モデルのどの拡張版よりも(最大53%)高い説明力でした。
脚注
[1] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
[2] Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior. Information Systems Research, 2(3), 173-191.
[3] Dishaw, M. T., and Strong, D. M. (1999). Extending the technology acceptance model with task-technology fit constructs. Information & Management, 36(1), 9-21.
[4] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., and Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






