2026年2月20日
翻訳されるアイデア:技術と制度が社会に定着するまで
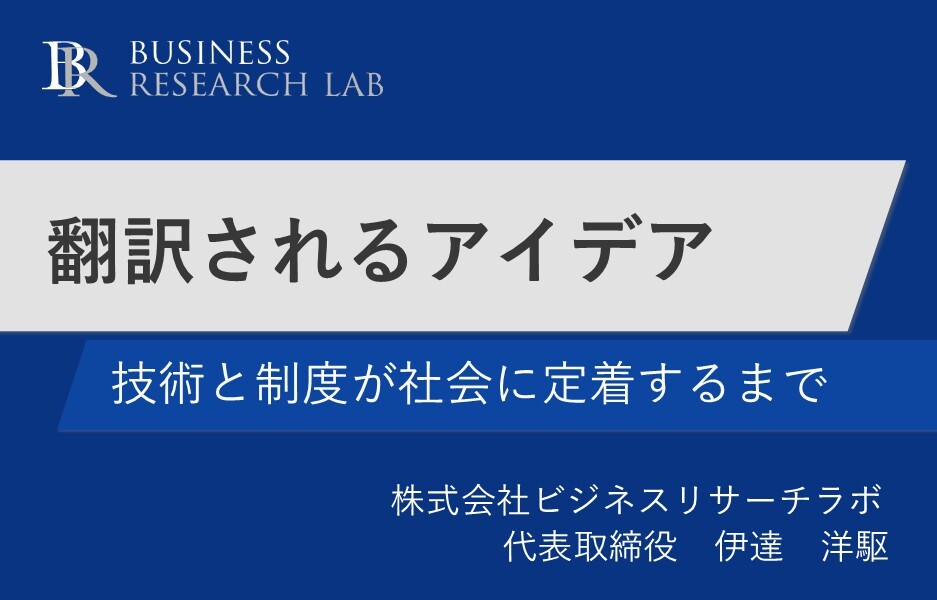
画期的なアイデアや優れた技術が、必ずしも世の中に受け入れられるとは限りません。歴史を振り返れば、性能は確かだったにもかかわらず忘れ去られていった無数の仕組みが存在します。一方で、当初は期待されていなかったものが、思いがけない形で社会の必需品となることもあります。この違いはどこから生まれるのでしょうか。
新しいものが社会や組織に広まる過程は、その性能や合理性で語られやすいものです。しかし、その裏側では、もっと複雑で人間味あふれる物語が繰り広げられています。あるアイデアを推し進めようとする人々の情熱、それに抵抗する人々の思惑、それらを取り巻く人々や、ときにはモノや制度までもが絡み合い、一つのうねりを生み出していきます。
本コラムでは、新しいものが社会に導入され、普及していくプロセス、その力学に光を当てます。フランスで明暗を分けた二つの会計手法、ブラジルの奥地で想定外の使われ方をした製氷機、イタリアの公共組織で三者三様の運命をたどった管理制度、ある企業で当初の目的を見失った人事システム。これらの物語を読み解き、アイデアや技術が、人々や組織の思惑によってその意味を翻訳され、姿を変えながら根付いていく過程を探ります。
会計手法の普及は、技術の優劣よりネットワーク構築力で決まる
新しい仕組みが世に広まるかどうかは、その仕組み自体の性能だけで決まるわけではありません。それを支持する人やモノの「つながり」がいかに広く、強固であるかが運命を分けます。このことを、第二次世界大戦後のフランスで対照的な結末を迎えた二つの原価計算手法の物語から探ってみましょう[1]。
最初に登場するのは、ジョルジュ・ペランが開発した「ジョルジュ・ペラン法(GPM)」です。これは、工場の多様な製品の生産量を独自の共通単位に置き換えることで、間接費をより正確に計算できるとされた画期的な手法でした。ペランは、この技術的な合理性さえあれば、戦後の生産性向上という時代の波に乗り、自然と受け入れられるはずだと信じていました。
しかし、彼の試みは限定的な成功に終わります。その背景には、「つながり」の構築を軽んじていたことがあります。彼は自身の発明の「純粋性」にこだわり、手法の秘密が漏れることを恐れて保護しました。この行動は、他者がGPMを自らの組織の状況に合わせて修正したり応用したりする機会を閉ざしてしまいました。使う人々がそれを自分たちのものとして解釈し、形を変えていく過程が、普及には欠かせませんが、ペランはその可能性を自ら断ち切ってしまったのです。
ペランは会計事務所と提携しましたが、そこでも壁にぶつかります。GPMは技術者の視点で生み出されたものであり、会計の専門家たちの関心を引けませんでした。会計士が使う言葉や問題意識に合わせて手法を説明し直す、いわば「翻訳」する努力が不足していたため、現場の会計士たちは導入に抵抗を示しました。ペランが築こうとしたつながりは商業的なものに限られ、学術界や専門職団体といった、より広い世界からの支持を得られませんでした。
当時のフランスには、強力な支持基盤を持つ二つの競合手法がありました。一つは国の公式会計基準に採用されていた「部門別計算」。もう一つはアメリカから導入され広まっていた「直接原価計算」です。ペランはこれらのライバルと積極的に議論を交わすことをせず、結果としてGPMは歴史の中に埋もれていきました。
一方で、1980年代後半にアメリカからフランスへ導入された「活動基準原価計算(ABC)」は、異なる道を歩みます。ABCをフランスに紹介したのは複数の大学教授や実務家たちで、彼ら彼女らは最初から学会などを通じて緩やかな「つながり」を形成しながら活動しました。
ABCの推進者たちは、GPMとは対照的に、巧みな戦略を展開します。国際競争の激化という、当時のフランス産業界が直面していた大きな課題を取り上げ、ABCがその解決策であると位置づけました。これは、単なる新しい計算手法の紹介ではなく、時代の要請に応える物語としてABCを提示する「問題提起」でした。この物語は多くの経営者や専門家の心をつかみました。
彼ら彼女らは初期段階から、学者、コンサルタント、導入企業、政府省庁までを巻き込んだ、多様なネットワークを築き上げました。会計専門職団体を味方につけ、専門誌で特集を組むなど、GPMが失敗した会計士たちとの連携にも成功します。
もちろん、ABCの道のりも平坦ではありませんでした。伝統的な「部門別計算」の支持者たちから、「ABCは部門別計算の焼き直しに過ぎない」という厳しい批判を受けます。しかし、ABCのネットワークはこの試練を乗り越えました。批判を無視するのではなく、それを逆手にとったのです。
彼ら彼女らは、ABCを単なる「優れた原価計算手法」として紹介するのは不十分だったと認め、それを「プロセス管理」や「組織横断的な視点」といった、より広範な経営哲学、すなわち「活動基準マネジメント(ABM)」として説明し直しました。この戦略的な「再翻訳」は、最も手ごわい批判者であった学者の評価を変えさせるほどでした。批判者は、ネットワークを破壊する者から、補強する同盟者へと変わったのです。
この論争が沈静化すると、ABCのネットワークは一気に拡大します。コンサルティング会社や専門のソフトウェア会社が市場に参入し、ソフトウェアという人間以外の仲間が加わりました。最終的に、ABCはフランスの多くの経営管理の教科書で標準的な手法として紹介されるようになり、当たり前の存在となりました。この二つの物語は、新しい仕組みの普及が、中身の優劣以上に、それを支える「つながり」の質と量に左右されることを物語っています。
導入技術は、開発者の想定を超え、住民の利用で価値を変えた
先ほどは、専門家たちの世界で繰り広げられた、意図的なネットワーク構築の物語を見ました。しかし、技術の導入は、常に計画通りに進むとは限りません。とりわけ、異なる文化や環境に技術が持ち込まれたとき、それは開発者の想定を大きく超え、利用者たちの手によって新たな価値を持つものへと生まれ変わることがあります。ブラジル・アマゾンの奥地に導入された太陽光発電製氷機(SIM)の事例は、その複雑なプロセスを浮き彫りにします[2]。
この研究の舞台となったコミュニティでは、電力へのアクセスが非常に不安定で、多くの住民は魚や肉を塩漬けにして保存していました。このような状況を改善するため、ある研究所が中心となり、バッテリーを必要としない太陽光発電の製氷技術を導入するプロジェクトが開始されました。食料保存を改善し、住民の生活の質を向上させることが大きな目的でした。
この製氷機には、開発者の様々な意図が込められていました。例えば、バッテリーを使わない設計は、環境への配慮に加え、「コミュニティにはバッテリー交換を管理する組織能力はないだろう」という、過去の経験に基づく開発者側の想定が反映されていました。開発者たちは、この機械が主に商業用の魚や果物の保存を改善し、住民の収入向上につながることを期待していました。
しかし、実際に運用が始まると、現実は想定とは異なる様相を呈します。機械の生産性は期待を下回り、技術的な問題が頻発しました。メンテナンス作業は、それ自体が複雑な営みでした。現地のチームが、遠く離れた専門家とインターネットで連絡を取り、部品をブラジル各地から取り寄せ、地域の修理業者を雇う。この一連の流れは、人間だけでなく、インターネットや飛行機といった人間以外の要素が相互に依存し合う、脆弱な「つながり」の上に成り立っていました。
最も大きな想定外は、氷の使われ方でした。開発者が期待した商業用の食料保存ではなく、住民が氷を使用した主な目的は、飲み水を冷やすことだったのです。調査期間中、コミュニティの共有発電機が故障し、各家庭の冷凍庫が使えなくなったという偶然も、この使い方を後押ししました。利用者にとっては、たとえ氷が完全に固まっていなくても、冷たい水が手に入るだけで十分に価値があり、それはプロジェクトの「成功」と見なされました。これは、導入者が期待した価値基準とは異なる、現場ならではの価値基準が存在することを示しています。
技術の導入は、コミュニティのあり方にも変化を促しました。住民たちは交代制のチームを組織し、日常業務を管理する体制を築こうとしました。このプロセスを通じて、製氷機はただの道具ではなく、住民に新たな社会的組織化を促す存在として機能しました。しかし、この共同管理も簡単ではありませんでした。住民の都合や天候への認識の違いから機械が稼働しない日があるなど、利用者の行動が機械の効率に影響を及ぼしました。当初の管理体制は次第に形骸化し、最終的には特定の住民が中心となって作業を担うようになります。
このような期待外れの性能や予期せぬ利用は、プロジェクトの「失敗」ではありません。むしろ、技術と利用者が互いに作用し合う、学びのプロセスと捉えることができます。利用者は、製氷機を自分たちの生活様式やニーズに合わせて「家畜化」することで、技術を現地の文脈に適応させる上で決定的な役割を果たしました。
この現場からのフィードバックは、技術開発チームへと伝えられ、機械の改善に活かされました。冷却室の断熱性を向上させたり、電気回路を簡素化したり、氷が主に飲み水に使われている実態を踏まえ、より衛生的な容器に変更したりといった対応が迅速に行われました。このことは、技術開発が研究室で完結するものではなく、現場での使用という現実との対話を通じて、継続的に行われるプロセスであることを物語っています。
新制度の導入は、現地の文脈に合わせて翻訳される過程
物理的な「技術」が現場でその意味を変えていく様を見てきましたが、より抽象的な「制度」や「アイデア」が組織に導入される際には、さらに複雑な変容が起こります。同じ制度であっても、導入される組織の文化や力関係といった固有の文脈によって、異なる解釈をされ、多様な姿で根付いていくことがあります。イタリアの公共部門における管理会計の導入プロセスは、この「翻訳」という現象の恰好の事例です[3]。
第一の事例であるイタリア財務省は、巨大な官僚組織でした。ここでの改革は、法律を背景に、事務次官という推進者の下で始まり、彼はコンサルティング会社という外部の専門家を味方につけました。当初、管理会計は「インプットとアウトプットに関する測定の抽象的スキーム」として定義されました。しかし、現場の管理者はこの新しい制度を、自分たちの仕事ぶりを監視するための「検査手段」と見なし、強い抵抗感を示しました。労働組合もこの革新に反対します。
この対立と交渉の過程で、管理会計は新たな「翻訳」を遂げます。それは、測定ツールではなく、「戦略的統制」と「管理会計」を分けるという、より洗練された考え方でした。この分化によって、管理会計には、政治的な意思決定と現場の行政責任を切り分けるという新たな意味が与えられました。不安定な道のりではありましたが、強力な推進者と外部の専門家が「頭脳」として機能し、巨大組織の中で管理会計という制度を形作っていったのです。
第二の事例、ジェノヴァでは、異なる物語が展開します。財務サービス部門の長が改革の旗手となり、彼は法律をそのまま適用するのではなく、それを自分たちの市の状況に合わせて「翻訳」することが自らの義務だと考えました。彼の周りには様々な人々が集まり、ネットワークが形成されます。後に、ある民間研究所が「頭脳」として機能することを申し出て、重要な同盟者となりました。
ジェノヴァの特徴は、現場の管理者たちの抵抗がほとんどなかったことです。彼ら彼女らはこの新しいアイデアを明確なものと捉え、自分たちの局に導入することを自らの役割として受け入れました。ここでは、現場の主体的な関与が、スムーズな「翻訳」を可能にしたといえるでしょう。
第三の事例であるペルージャは、さらに複雑な様相を呈します。ここでの管理会計導入の試みは、何度も中断と再開を繰り返す、不安定なプロセスをたどりました。推進者たちには専門知識が不足し、ネットワークは特定の一人の会計士に依存するという脆弱な構造を持っていました。政治家も行政官も、管理会計が一体何なのかをほとんど理解していませんでした。そのため、それぞれの立場から都合の良い解釈がなされました。
結果、ペルージャでは、管理会計は一つのまとまった制度として定着しませんでした。そうではなく、既存の経済情報システムの一部に組み込まれたり、市民とのコミュニケーション手段へと姿を変えたりと、複数の異なる人工物へと分解されていきました。ここでは、アイデアを一つの形にまとめ上げる中心が存在しなかったために、それぞれの部分がばらばらに「翻訳」され、本来の姿を失ってしまったように見えます。
これら三つの事例は、新しい制度の導入が、導入先の組織が持つ固有の文脈の中で、そこにいる人々が意味を再定義し、交渉し、全く新しいものを共同で作り上げていくプロセスであることを明らかにしています。
人事システムの目的は、導入過程で他部門の利害に翻訳された
これまで見てきたように、新しい技術や制度の意味は、導入の過程で「翻訳」され、変容していきます。このプロセスは、ときに導入を主導するはずの人々の当初の意図さえも裏切り、予想もしなかった結末を迎えることがあります。良かれと思って導入したものが、なぜか逆の結果を招いてしまう。この現象の裏側には、どのような力学が働いているのでしょうか。ある製造業の会社における人事情報システム(HRIS)の導入プロジェクトは、その事例となります[4]。
オーストラリアの大手製造業MFC社では、20年以上にわたり、「WebCHRIS」という人事情報システムが使われていました。このシステムは、人事部門内の専門チームによって、現場のユーザーのニーズに合わせて長年かけて細かくカスタマイズされ、従業員からの満足度は非常に高いものでした。この時点では、人事部門がシステムの主導権を握り、人事の視点から従業員サービスを向上させるという目的の下、安定した関係性が築かれていました。
しかし、この安定は、新しいグループ人事ディレクターの就任と、会社全体の経営戦略の転換をきっかけに崩れ去ります。ここから、システムの目的が「翻訳」されていくプロセスが始まりました。
変革の口火を切ったのは、新しい人事ディレクターでした。彼は、旧システムの高い機能性ではなく、「システムの運用が特定の個人に過度に依存していること」や「サポートが脆弱であること」を「問題」として定義し直したのです。彼はこれを、人事部門の課題としてではなく、会社全体の「ビジネス上のリスク」として提起しました。この問題提起は、物語の焦点を「現場の使いやすさ」から「全社的なリスク管理」へと鮮やかに転換させました。
この新しい物語は、これまで人事システムに関心のなかった、強力な人々を引きつけました。経営トップ、情報システム部門、財務部門、外部のコンサルタントといった面々です。彼ら彼女らにとって、旧システムを廃止し、全社的な統合システムであるSAPのHRモジュールを導入するという解決策は、それぞれの利害と完全に一致していました。情報システム部門にとってはシステムの標準化、経営層にとっては事業部門を売却する際に魅力的であるといった計算がありました。
こうして、「リスク管理」と「企業戦略」という、より大きな物語の下に、人事部門の外のアクターたちによる新しいネットワークが形成されていきました。この新しいネットワークの前では、旧来のネットワークに属していた人事の専門チームや現場ユーザーの声はかき消されていきます。彼ら彼女らが訴えるSAPへの移行による機能低下の懸念は、より大きな「会社のため」という言説の前では、些細な問題と見なされました。
最終的に、この権力闘争は、新しいネットワークの勝利に終わります。人事システムの管理権限は、人事部門から情報システム部門へと移管されました。長年システムを支えてきた給与計算チームは解雇され、本社にSAPのスキルを持つ新しいチームが作られました。
その結果、導入された新しいシステムは、現場が必要とする基本的な人事機能において旧システムに劣り、ユーザーの不満は増大しました。人事部門は、自部門の名前がついたシステムに対するコントロールを完全に失い、何か変更を加えるには情報システム部門の許可と費用が必要になりました。
人事部門の戦略的パートナーとなることを期待されていたはずの人事情報システムは、その目的を翻訳の過程で失いました。それはもはや人事のためのツールではなく、「全社的なIT基盤の一部」であり、「売却可能な企業資産」へと、その意味を変えられてしまったのです。この事例は、「翻訳」が言葉の解釈の違いではなく、組織内の利害がぶつかり合う政治的な闘争であることを教えてくれます。
脚注
[1] Alcouffe, S., Berland, N., and Levant, Y. (2008). The role of actor-networks in the diffusion of management accounting innovations: A comparative study of budgetary control, GP method and Activity-Based Costing in France. Management Accounting Research, 19, 1-17.
[2] Penteado, I. M., do Nascimento, A. C. S., Correa, D., Moura, E. A. F., Zilles, R., Gomes, M. C. R. L., Pires, F. J., Brito, O. S., da Silva, J. F., Reis, A. V., Souza, A., and Pacifico, A. C. N. (2019). Among people and artifacts: Actor-Network Theory and the adoption of solar ice machines in the Brazilian Amazon. Energy Research & Social Science, 53, 1-9.
[3] Pipan, T., and Czarniawska, B. (2010). How to construct an actor-network: Management accounting from idea to practice. Critical Perspectives on Accounting, 21(3), 243-251.
[4] Dery, K., Hall, R., Wailes, N., and Wiblen, S. (2013). Lost in translation? An actor-network approach to HRIS implementation. Journal of Strategic Information Systems, 22(3), 199-217.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






