2026年2月19日
組織の「注意」は設計できるか:戦略人事への新たな視座(セミナーレポート)
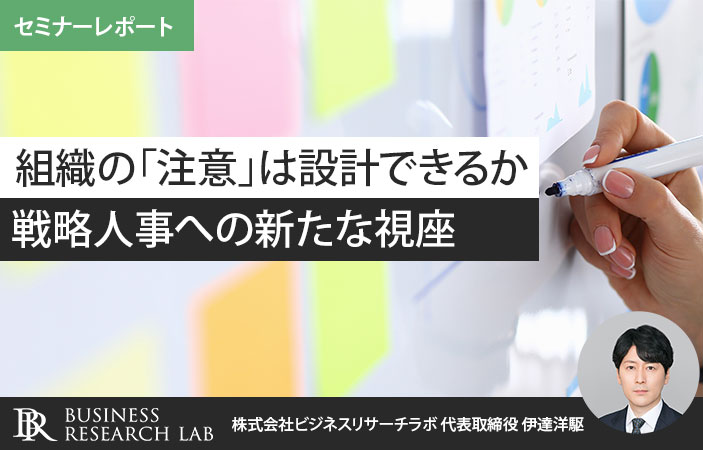
ビジネスリサーチラボは、2026年1月にセミナー「組織の『注意』は設計できるか:戦略人事への新たな視座」を開催しました。
なぜ、優れた戦略が実行されないのか。なぜ、現場からの重要な提案が上層部に届かないことがあるのか。なぜ、組織は有望な機会や致命的なリスクの兆候を見過ごしてしまうのか。
同じ環境下にあっても、変化へしなやかに適応できる組織と、そうでない組織が存在します。その分岐点の一つが、組織の「注意(アテンション)」がどこに向けられているかにあります。
企業が持つ資源は有限ですが、経営トップから現場の従業員まで、人々の「注意」もまた、組織にとって希少な資源の一つです。この限られた「注意」が、組織全体として何に、どのように配分されるかが、企業の優先順位、資源配分、最終的な行動を決定づけます。
本セミナーでは、「アテンション・ベースド・ビュー」というアプローチに基づき、組織行動のメカニズムを解説しました。このアプローチの核心は、組織の「注意」の配分が、個々人の意識や能力の問題だけでなく、組織内の「仕組み」によって方向づけられていると捉える点にあります。
会議の設計や運営方法、報告のフォーマット、業績評価の基準、組織内で日常的に使われる「言葉」。これら組織に埋め込まれた構造や日々の実践が、従業員が「何に注目し、何を無視するか」を規定するルールとして機能しているのです。
組織の「注意」という見えざる資源の働きを理解することは、戦略の実行力を高め、イノベーションを促進し、変化に対応できる組織を構築する上で、新たな示唆を提供するはずです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
なぜ、精緻に練られたはずの戦略が、実行段階で頓挫してしまうのでしょうか。なぜ、現場で発生しているはずの重要な変化の兆候、例えば、顧客の不満、技術革新の芽、中核人材の離職の予兆が、意思決定層に届くことなく握り潰されてしまうのでしょうか。
多くの企業が直面するこの種の問題の根源は、個々の従業員の能力不足にあるのではなく、組織全体としての「認知リソース」の配分ミスにあると考えられます。それが「注意(アテンション)」です。組織が持つ「注意」という有限な資源が、どこに向けられているか。その総和が、組織の行動を決定づけます。
そして、その配分を方向づけているのは、個人の意識以上に、組織内に張り巡らされた「仕組み」、例えば、会議体、報告プロセス、使われる言葉に他なりません。本講演では、「アテンション・ベースド・ビュー」というアプローチをもとに、組織の「注意」が機能するメカニズムを解剖するとともに、人事がその「設計主体」としていかなる役割を果たし得るのか、その可能性を考えます。
なぜ組織は「わかっているはず」を見過ごすのか
組織が直面する環境の変化に対し、適切な対応が遅れる「組織的な見落とし」が発生する背景には、大きく分けて二つの力学が働いています。一つは経営層の認知の方向性であり、もう一つは組織内部の感情が引き起こす認知の歪みです。
第一の力学は、経営層の関心が組織の行動を規定するという点です。組織の航路を定めるトップマネジメントが、その限られた「注意」を何に振り向けているかは、企業の戦略的な選択に直結します。
この関係性を実証した研究の一つに、光ファイバー技術の黎明期における通信機器メーカーの動向を分析したものがあります[1]。1976年から2001年にかけ、26社の企業が調査されました。各社のCEOの「注意」の方向性を客観化するため、年次報告書の「株主への手紙」がテキスト分析され、CEOが「新技術」「既存技術」「関連産業」といった語彙をどの程度使用しているかが計測されました。
分析の結果、CEOが「新技術」や「関連産業」といった未来志向の言葉を多用する企業ほど、新市場への参入が迅速でした。逆に、「既存技術」への言及が多ければ多いほど、参入は遅延しました。ここで注目すべきは、企業が保有する既存技術の特許(=組織能力)自体は、参入の障害になっていなかったという点です。組織の適応力を決定づけたのは、能力の有無ではなく、トップの「注意」が未来と外部環境に開かれていたか、それとも過去の成功体験である内部に閉じられていたかという認知の方向性の問題だったのです。
また、イノベーションの実現プロセスにおいても、CEOの「注意」の向きが成果を左右することが示されています[2]。1990年代半ばのインターネットバンキングの台頭期を対象に、米国の小売銀行176行の対応が調査されました。この研究では、CEOの株主向け書簡から「未来志向」「外部志向」「内部志向」という三つの「注意」の方向性が測定され、イノベーションプロセスを「検知(新技術の発見)」「開発(製品化)」「展開(機能拡充)」の三段階に分解し、それぞれの段階への影響が分析されました。
その結果、求められる「注意」の配分が、イノベーションの段階ごとに異なることが判明しました。新技術の兆候を捉える「検知」段階では、「未来志向」と「外部志向」が強いCEOほど、迅速に行動していました。
技術を製品化する「開発」段階では、同様に「未来志向」と「外部志向」がプロセスを加速させた一方で、この段階に限っては「内部志向」も開発速度を高める方向に作用しました。これは、プロジェクトが具体化すると、社内の資源配分や調整といった内部課題へのCEOの「注意」が推進力となるためと解釈されます。
そして、サービスを市場に展開し、機能を拡充していく「展開」段階では、「未来志向」のみが正の影響を与えていました。未来と社外への視野が革新の種を発見し、内外両面への配慮がそれを具現化し、再び未来への構想力がその後の成長を牽引するというプロセスが明らかになりました。
「組織的な見落とし」を生む第二の力学は、組織内の「感情」、特に階層間で生じる感情の齟齬が「注意」の配分を歪める点です。かつて携帯電話市場で圧倒的な地位を誇ったノキア社が、スマートフォンへの適応に失敗した要因を分析した研究は、この問題を克明に描き出しています[3]。
研究者たちは、同社が競争の激化に直面した2005年から2010年にかけて、経営層や従業員へのインタビューを実施しました。その結果、トップマネジメントとミドルマネジメント(中間管理職)が、全く異質の「恐れ」を抱いていたことが判明しました。
トップ層が感じていたのは、競合の出現や投資家からの圧力といった「外部環境に対する恐れ」です。それに対し、ミドル層が抱いていたのは、上司からの叱責や解雇への不安といった「組織内部に対する恐れ」でした。この「恐れの非対称性」は、組織内の情報流通に深刻な機能不全をもたらしました。
トップ層は、「外部への恐れ」から現場に過度な圧力をかける一方で、自社の技術的な弱みといったネガティブな情報を共有することを避けました。ミドル層は、「内部への恐れ」から、トップからの非現実的な要求に対しても「実行可能です」と応じ、楽観的な進捗報告を繰り返しました。
この相互作用の結果、トップの認識と現場の実態との間に、修復不可能な「能力認識ギャップ」が拡大していきました。組織の資源と「注意」は、目前の端末開発という短期的な目標にのみ浪費され、スマートフォンの競争力の根幹であるOS開発という本質的な課題は、継続的に無視されることになったのです。この事例は、心理的安全性の欠如が、職場環境の問題ではなく、組織の重要なセンサーである現場からの正確な情報への「注意」を遮断し、組織的な失敗に直結する経営課題であることを示しています。
組織の注意を方向づける仕組みとは何か
組織の「注意」は、具体的にどのようなメカニズムによって特定の方向へと導かれてしまうのでしょうか。「アテンション・ベースド・ビュー」が提示する考え方は、「注意」の配分が個人の自由な意識や選択の結果である以上に、組織の構造的な特性、すなわち「仕組み」によってあらかじめ決定されているというものです[4]。
この理論は三つの基本原理に基づいています。第一は「注意の焦点」です。人間が一度に処理できる情報には限界があり、ある対象に意識を集中させると、それ以外の情報は認識の外に置かれやすくなります。第二は「状況化された注意」です。人の「注意」の向きは、その人が置かれた文脈や状況によって規定されます。予算審議の場にいるか、新製品のブレインストーミングの場にいるかで、同じ人物でも「注意」を向ける対象は異なります。
そして最も重要なのが、第三の「注意の構造的分配」です。組織は、規則、資源配分のプロセス、会議体、報告手続き、役職や力関係を通じて、「注意」が流れる経路を設計しています。これらの組織に埋め込まれた制度や慣行が、組織全体としての「注意の配分ルール」として機能し、最終的な組織行動を形成しているのです。ここでは、その「仕組み」を、「場」「言葉」「手続きと尺度」という三つの切り口から解き明かします。
第一の仕組みは、「場」の設計、すなわち会議体やコミュニケーション・プロセスの構造です。組織内の「誰が、いつ、どこで、何について議論するか」という「場」の設定が、組織の「注意」が何に向かうかを左右します。
この点を実証した研究として、世界的な多角化企業であるゼネラル・エレクトリック(GE)社の50年間(1951年〜2001年)の歴史分析があります[5]。この研究では、本社と事業部のコミュニケーションの「場」がいかに設計されていたかが、組織の適応力に与えた影響を追跡しました。
例えば1960年代後半、戦略立案機能が本社に集中し、本社と事業部が直接議論する「クロスレベルの場(階層横断的な場)」が失われると、コンピュータ事業は現場の実態から乖離した計画によって苦境に陥りました。この失敗の反省から、1970年代以降、戦略・財務・人材という三つの異なる機能に特化した「クロスレベルの会議体」が体系的に導入・運用されるようになります。
この仕組みのもと、メディカル・システムズ事業部は、CTやMRIといった革新的な新技術が登場した際、これらの会議体を通じて迅速に認識を共有し、集中的な資源配分を受けることに成功し、目覚ましい成長を遂げました。この事例は、異なる階層と機能を持つ人々を意図的に交差させる「場」の配置が、組織全体の「注意」を束ね、環境変化への対応力を生み出すことを示しています。
また、「場」の「形式性」も「注意」の向きに影響を与えます。184社の上場企業の取締役会議事録を分析した研究では、取締役会の構成(多様性)と運営方法(非形式性)が、「企業家的課題(新製品開発や新規市場参入など)」に関する議論の時間にどう作用するかが検証されました[6]。
その結果、勤続年数の多様性や異業種出身者の存在は、企業家的な議論を増やす方向に働きましたが、それ以上に強い影響を与えたのが「非形式性」でした。会議が社外の施設で開催される、議題の自由度が高い、開催頻度が多いといった「非形式的」な「場」であるほど、多様な取締役が持つ未来志向の視点が議論に反映されやすくなることが確認されました。どのような人々が参加するかだけでなく、その人々がどのような「場」で対話するかが、組織の未来に向けた「注意」の質を決定づけるのです。
第二の仕組みは、「言葉」の設計、すなわち組織内で公式・非公式に使われる「語彙」です。「言葉」は、私たちが世界を認識し、解釈するための枠組みを提供します。組織内でどのような「言葉」が共有されているかは、何が「重要な問題」として認識され、何が「些末な問題」として無視されるかを左右します。
ある研究では、戦略的な変革プロセスにおいて、コミュニケーションが情報伝達のパイプとしてではなく、組織の「共同の注意」を動的に再編成するプロセスとして機能すると論じられています[7]。参加者たちが対話を通じて互いの認識をすり合わせ、ある特定の事象に共同で「注意」を向けていく、そのプロセスの中核に「語彙」が位置づけられます。
例えば、ある組織が「プラットフォーム戦略」という「言葉」を採用すれば、従業員の「注意」は、個別の製品機能の開発だけでなく、外部パートナーを巻き込んだ生態系全体の構築といった、それまでとは異なる次元の課題に向けられるようになります。新しい「言葉」を導入したり、既存の「言葉」の意味を再定義したりすることは、組織が参照している認識の地図を書き換え、「注意」の配分を意図的に変容させる手段となり得ます。
第三の仕組みは、「手続きと尺度」の設計、すなわち公式な報告フォーマットやKPI(重要業績評価指標)です。人々は、組織が公式に「重要である」と定義し、測定・評価する対象に対して、自らの「注意」を優先的に集中させるという合理的な行動をとります。
この関連で、組織の中間管理職が、いかに自らの問題意識を「論点」として上層部に認識させ、具体的な行動を引き出すか、という「論点提案活動」の成否を分析した研究があります[8]。米国の地域基幹病院に勤務する中間管理職42名に対し、上層部への働きかけに関する成功事例と失敗事例(合計82)の聞き取り調査が行われました。
分析の結果、成功した提案活動には共通する働きかけのパターンが特定されました。その一つは「見せ方」の工夫であり、提案内容を個人の思いつきとして提示するのではなく、数値やデータで裏付けられた事業計画という、組織が日常的に意思決定で用いる「型」に合わせて提示することでした。もう一つは「結び付け方」の工夫であり、その提案が、組織全体で共有されている「価値目標」(例えば、収益性の向上や地域社会での評判の維持)にいかに貢献するかを明確に接続して説明することでした。
この研究が示すのは、現場からの重要な提案であっても、それが上層部の「注意」を引くためには、組織の公式な意思決定の論理、すなわち既存の「手続き(型)」や「尺度(価値基準)」に適合させる必要があるという事実です。これは裏返せば、経営企画部門が定める報告の「手続き」や、人事部門が関与する業績評価の「尺度」が、従業員が日々の業務で何に「注意」を払うべきかを規定する「仕組み」として機能していることを意味しています。
「注意」のアーキテクトとしての戦略人事
これまで見てきたように、組織の「注意」の配分は、経営層の関心、組織内の感情、そして「場」「言葉」「手続き」といった制度的な「仕組み」によって複雑に決定されています。戦略人事の役割は、これらの「仕組み」の設計と運用に関与し、組織全体の「注意」という貴重な認知リソースを、戦略実行という重要な目的に向かって導く「アーキテクト(設計者)」となることです。KPIや評価制度を直接的に変更することが(短期的には)困難であったとしても、人事が主体的に着手できる実践的なレバーはいくつも存在します。
第一のレバーは、ボトムアップの「注意」を吸い上げる「情報チャネル」の設計です。公式の報告ルート(手続き)が、その性質上、短期的な業績目標といった定義済みの尺度への「注意」を優先させるのであれば、それとは異なる種類の「注意」、すなわち、まだ定義されていない「弱い兆候」や「懸念」を拾い上げるための、非公式あるいは半公式のチャネルを意図的に構築することが有効です。
例えば、デンマークの大手製薬会社が1993年の品質管理危機を分析した研究があります[9]。この企業は、危機の予兆を見過ごした反省から、組織の「注意」のあり方を再設計しました。その設計思想の中核には、「安定性(継続的な観察)」「鮮明性(多角的な視点)」「整合性(部門横断での連携)」という三つの注意の次元を同時に高める狙いがありました。
特に独創的だったのが「ファシリテーション」という仕組みです。社内で人望の厚い管理職が「ファシリテーター」として任命され、各部門を定期的に巡回し、従業員から「公式の場では語られない懸念」を直接ヒアリングしました。これは、公式の階層フィルターを意図的に迂回し、現場の生の声を経営層に届け、「弱い兆候」に対する「注意」の「安定性」を担保する仕組みでした。
この知見に基づき、デンマークの製薬会社の事例のように、人事の中から「ファシリテーター」役を担う人を選び、部門横断で非公式な懸念(=弱い兆候)を収集・分析し、経営層に直接報告するチャネルを制度化することが考えられます。
第二のレバーは、人材配置と「異質な場」の設計です。組織の「注意」が、過去の成功体験や既存事業の論理といった内部の慣性に固定化されるのを防ぐためには、意図的に異質な視点、すなわち異なる「注意」のパターンを持つ人材を配置し、それらの「注意」が建設的に衝突し、交差する「場」を設計することが求められます。
この点に関して、61社のハイテク企業を対象とした調査では、経営チームの「情報の探し方」が新製品の導入数にどう結びつくかが検証されました[10]。その結果、多くの新製品を生み出すチームには、「馴染みのない領域」「遠い場所」「多様な情報源」から情報を得ているという共通のパターンが確認されました。自らの慣れ親しんだ世界から踏み出し、遠く広く「注意」を向けることが、革新的なアイデアとの遭遇率を高めていました。
この研究のさらに興味深い発見は、「探索の強度」に関するものです。「探索の強度」を「努力(探索活動に注ぐエネルギー量)」と「持続性(一つのテーマを粘り強く掘り下げる姿勢)」に分解して分析したところ、「持続性」は新製品導入数と正の関係にあったのに対し、「努力」は負の関係にあることが分かりました。トップチームが探索に「努力」を注ぐほど、新製品の数は減っていたのです。
この考察が示すのは、トップの「注意」は有限な資源であり、闇雲な「努力」に「注意」を振り向けると、戦略立案や実行といった他の不可欠な活動に割くべき「注意」が奪われてしまうという実態です。イノベーションとは、ただの「頑張り」の問題ではなく、限りある「注意」をいかに賢く配分するかという戦略的な問いなのです。
人事としては、「遠く多様な」視点を持つ人材を採用・配置することに加え、GEの事例で見た「クロスレベルの会議体」や、取締役会の事例で示された「非形式的」な場、あるいは部門横断のタスクフォースなど、異なる「注意」が化学反応を起こす「場」を設計し、そのファシリテーションを主導していく役割が求められるかもしれません。
例えば、「既存事業の論理」が支配的な部門に、「新規事業の論理」を持つ人材を意図的に配置する(またはその逆)といった施策が挙げられます。採用プロセスにおいても、単なるスキルフィットだけでなく、「認知的多様性(異なる問題解決のアプローチや視点を持つか)」を見極めるための問い(例えば、「当社の事業で見過ごされている機会は何だと思いますか」)を組み込むこともあり得ます。
さらに、「戦略的重要テーマ」に関する全社的なワークショップを開催し、部署や役職の垣根を超えた「注意」の交流を意図的に創出することも考えられます。
第三のレバーは、リーダーシップ開発と組織文化の醸成です。どれほど精巧な「仕組み(チャネルや場)」を設計したとしても、それを実際に運用するリーダーの意識や、組織全体に流れる文化が伴わなければ、仕組みは機能不全に陥ります。
リーダーシップ開発においては、まずリーダー自身が、自らの「注意」の向き(例えば、カレンダーの使い方や会議での発言内容)が、部下や組織全体の「注意」の方向性を決定づけるシグナルとして機能していることを自覚することから始める必要があります。CEOの「注意」が新技術導入のタイミングやイノベーションのプロセス全体を左右した研究群が示したように、リーダーが発する「言葉」と、日常的に「注意」を払う対象が、組織全体の優先順位を定義づけています。
そして、これらの仕組みを支える基盤となるのが組織文化です。ノキアの事例が示した「恐れの非対称性」は、心理的安全性の欠如が組織の「注意」のセンサー(現場からの声)をいかに破壊するかを如実に物語っています。
また、1992年から2004年にかけて日本企業2123社を対象とした研究では、業績が目標水準を「上回った」時にもR&D投資(未来への探索)を増やすという、特有の「V字型」の投資パターンが確認されました[11]。研究者たちはその背景を、直接的な評価制度以上に、日本企業社会に根差す「互酬性」の文化にあると考察しました。従業員や取引先といった多様な利害関係者との長期的な関係性を重視する文化が、短期的な業績への「注意」だけでなく、長期的な未来への「注意」(探索活動)をも支えていたのです。
リーダーシップ開発の中で、「自身のカレンダー(時間の使い方)が、部下への『注意』のシグナルとしてどう機能しているか」を振り返り、意図的に再設計する機会を組み込むことが考えられます。また、1on1ミーティングのガイドラインを整備し、業務の進捗確認ではなく、「部下が今、何に『注意』を払っているか(懸念、機会、違和感など)」を引き出すためのトレーニングを管理職層に提供することも考えられます。
加えて、日本企業の事例のように、自社が「大切にする価値観(例えば、長期志向、顧客への真の貢献)」を再定義し、それが「短期業績」以外の重要な活動(未来への探索など)への「注意」を正当化する「語彙」として機能するよう、社内広報や研修を通じて繰り返し浸透させることも、文化醸成に向けたアプローチです。
おわりに
本講演では、「アテンション・ベースド・ビュー」というレンズを通して、組織がなぜ重要な機会やリスクの兆候を見過ごしてしまうのか、その背景にある「注意」の配分メカニズムについて考察してきました。組織が環境の変化に適応できない、もしくは戦略を実行できない理由は、多くの場合、そこにいる人々の能力や意欲の欠如ではなく、組織に根ざした「仕組み」が、彼ら彼女らの貴重な「注意」を、戦略とは異なる方向、それは往々にして過去の成功体験や、短期的な内部の課題へと向けさせているという事実にあるのかもしれません。
どれほど優れた戦略が策定されたとしても、組織に属する人々の「注意」がその戦略の実行へと集中されなければ、戦略は理念のまま実行に移されることはありません。人事としては、従業員の有限で貴重な「注意」という認知リソースが、組織として最も重要な戦略的課題に向かうように「仕組み」をデザインする、「組織のアーキテクト」としての役割を担うことが重要になります。
ぜひ、皆さんの組織の「会議」は、「報告手続き」は、日常的に「使われている言葉」は、従業員の「注意」を未来と外部に向けているか、それとも過去と内部に向けているか、改めて観察してみてください。その「注意」の配分構造を戦略的な意図を持って設計し直すことが、変動の時代における戦略実行力を高める、人事の新たな役割となるはずです。
Q&A
Q:経営層が新しいスローガンや用語を作っても、現場からは「またか」と冷ややかな反応をされ、定着しないことが多々あります。新しい言葉が単なるお題目にならず、実際の行動変容につながるためには、どのような仕掛けを行うべきでしょうか。
言葉というものは、人々の「注意」を特定の方向へ向ける機能を持っています。しかし、その言葉が組織に浸透しなければ、当然ながら注意を方向づける力も発揮されません。
言葉を浸透させるためにやりがちなのが、その言葉の定義を書いた紙を配ったりすることですが、正直なところ、それだけではあまり意味がありません。重要になるのは、その言葉が自然と使われるような「状況」や「文脈」をいかに作っていけるかということです。
例えば、会議の冒頭で必ずその新しい言葉に関連する活動報告を行うというルールを設けてみるのはどうでしょうか。あるいは、人事評価のシートの項目の中にその言葉を組み込んでみるのも一つの手です。また、もし皆さんの会社に社内報があるならば、その言葉をうまく体現している社員をピックアップし、どのような思いで働いているのかというストーリーと共に紹介していくのも効果的です。
このように、日常の業務フローの中に、その言葉に触れざるを得ない機会を意図的に作り出していく必要があります。そうすることで、言葉がお題目ではなくなり、社員の行動変容につながったり、組織として向けたい方向へ注意が向くようになったりします。
Q:組織の階層間で「注意のズレ」が生じる原因について質問です。このズレは、組織の仕組みの中でも、組織構造の基本となる「ポジション(役職や立場)」による違いが大きいと考えられますか。
その要因は大きいでしょう。それぞれのポジションが負っている「責任」と、日々担っている「仕事」の種類や性質が異なるからです。
人は、自分が担当している仕事や、責任を負っている領域に対して自然と注意を向けるものです。例えば、部長であれば部長としての責任範囲がありますから、そこに対して注意を払うのは当然のことだと言えます。これを逆算して考えると、その人がどのような責任や役割を持っているかが分かれば、その人がどこに注意を向けやすいのか、ある程度予測がつくということでもあります。
ただし、ポジションや責任だけで全ての注意が決まるわけではありません。もう一つ重要な要素として考えられるのが「価値観」です。その人が働く上で何を大切にしているのか、何に重きを置いているのかという個人的な価値観も、注意の方向性を決める源泉になります。
特定の価値観を持っている人は、その価値観に関連する事柄に対して敏感になりますし、強く注目するようになります。要するに、階層間での注意のズレは、構造的な「ポジション」の違いと、個人的な「価値観」の違いの双方が組み合わさって生じていると捉えるのがよいでしょう。
Q:経営層の注意の方向性が戦略を決めるとのお話がありましたが、当社は過去の成功体験に固執しており、人事が新しいデータを提示しても関心を示してくれません。人事から経営層に対して行えるイシューセリングの方法を教えてください。
有効なアプローチの一つは、経営層が現在重視している既存の価値観や言葉とうまく紐付けることです。過去の成功体験に固執している経営層であっても、例えば「創業の精神」や「顧客第一主義」といった、彼ら彼女らが大切にしている価値観や言葉があるはずです。新しい課題を提案する際には、それら既存の重要な言葉とセットにして提示することが重要です。
なぜなら、新しい提案をする際に「過去のやり方はもう古いので変えましょう」という文脈で伝えてしまうと、経営層は自分たちの過去を否定されたと感じ、無意識に注意を向けなくなってしまうからです。そうではなく、「私たちが大切にしてきた創業の精神や顧客への思いをこれからも守り抜くためにこそ、今この変革が必要なのです」というロジックを組み立てます。過去を否定するのではなく、過去の精神を守るための手段として新しい提案を位置づけることで、経営層の注意を引きやすくなります。
また、社内の声だけでは動きにくい場合の一般的な手法ですが、切迫感を演出することも有効です。競合他社の最新の動向を伝えたり、お客様からの厳しい生の声をフィードバックしたりするなど、外部の視点や客観的なデータをセットで提示することで、「変わらなければならない」という危機感を醸成できるのではないでしょうか。
Q:自分のチームで注意の再設計を始めたいと思います。まずは身近な会議を観察してみようと思うのですが、会議の何を記録・観察すれば、現在のチームの注意の偏りが見えてくるでしょうか。
会議というのは、まさに組織の「注意」が形成される場であり、同時にそれが可視化されやすい場でもあります。会議の観察から始めるのはやりやすく、効果的な方法だと思います。
具体的に観察すべきポイントは大きく二つあります。一つ目は「時間配分」です。会議の中で、何について話している時間が長いかを記録してみてください。大きく分けると「過去の話題」と「未来の話題」があります。過去の話題とは、報告連絡や振り返り、反省などが該当します。一方、未来の話題とは、新しい提案や計画作り、目標設定などの話です。
この時間の割合を見るだけでも、チームがどこに注目しているかが分かります。「うちは過去の報告ばかりで時間が終わっているな」と気づくかもしれませんし、逆に「未来の話ばかりで足元の振り返りが疎かになっているな」と気づくかもしれません。
二つ目は「言葉(ボキャブラリー)」です。会議の中でどのような言葉が使われているかに注目してください。例えば、「できない理由」「リスク」「制約」といったネガティブな言葉ばかりが飛び交っている会議になっていないでしょうか。それとも、「どうすればできるか」「どのような可能性があるか」「機会」といった前向きな言葉が多く使われているでしょうか。
使われている言葉が違えば、当然チームが見ている世界も異なります。発せられた言葉を記録し、それがどのような意味合いを持っているかでグルーピングしてみると、自分たちのチームが何に注意を向けているのか、その偏りが透けて見えてくるはずです。
脚注
[1] Eggers, J. P., and Kaplan, S. (2009). Cognition and renewal: Comparing CEO and organizational effects on incumbent adaptation to technical change. Organization Science, 20(2), 461-477.
[2] Yadav, M. S., Prabhu, J. C., and Chandy, R. K. (2007). Managing the future: CEO attention and innovation outcomes. Journal of Marketing, 71(4), 84-101.
[3] Vuori, T. O., and Huy, Q. N. (2016). Distributed attention and shared emotions in the innovation process: How Nokia lost the smartphone battle. Administrative Science Quarterly, 61(1), 9-51.
[4] Ocasio, W. (1997). Towards an attention-based view of the firm. Strategic Management Journal, 18, 187-206.
[5] Joseph, J., and Ocasio, W. (2012). Architecture, attention, and adaptation in the multibusiness firm: General Electric from 1951 to 2001. Strategic Management Journal, 33, 633-660.
[6] Tuggle, C. S., Schnatterly, K., and Johnson, R. A. (2010). Attention patterns in the boardroom: How board composition and processes affect discussion of entrepreneurial issues. Academy of Management Journal, 53(3), 550-571.
[7] Ocasio, W., Laamanen, T., and Vaara, E. (2018). Communication and attention dynamics: An attention-based view of strategic change. Strategic Management Journal, 39(1), 155-167.
[8] Dutton, J. E., Ashford, S. J., O’Neill, R. M., and Lawrence, K. A. (2001). Moves that matter: Issue selling and organizational change. Academy of Management Journal, 44(4), 716-736.
[9] Rerup, C. (2009). Attentional triangulation: Learning from unexpected rare crises. Organization Science, 20(5), 876-893.
[10] Li, Q., Maggitti, P. G., Smith, K. G., Tesluk, P. E., and Katila, R. (2013). Top management attention to innovation: The role of search selection and intensity in new product introductions. Academy of Management Journal, 56(3), 893-916.
[11] O’Brien, J. P., and David, P. (2014). Reciprocity and R&D search: Applying the behavioral theory of the firm to a communitarian context. Strategic Management Journal, 35(4), 550-565.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






