2026年2月19日
「贈ること」から始まる社会:人間関係と権力の起源をたどる
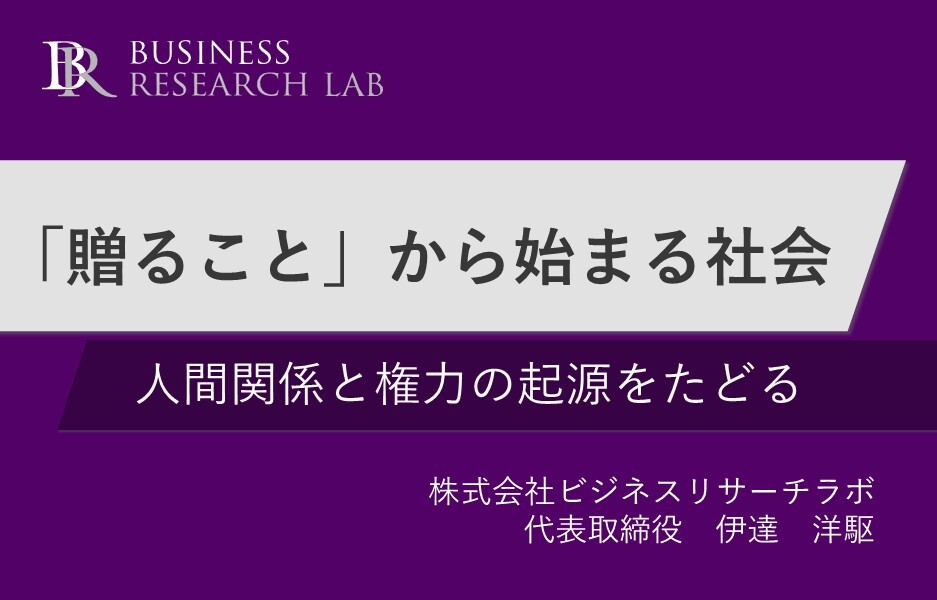
職場で旅のお土産を配る、友人の誕生日にプレゼントを贈る、困っている同僚の仕事を手伝う。私たちの日常は、こうした数えきれない「やり取り」で満ちています。その一つひとつは、ごく自然な親切心から生まれた、ささやかな行為に見えるかもしれません。
しかし、誰かから思いがけない親切を受けたとき、私たちの心に宿る「ありがとう」という感謝の気持ちの隣に、なぜ「今度はこちらが何かお返しをしなくては」という、一種の義務感や落ち着かない気持ちが芽生えるのでしょうか。それはただの礼儀作法なのでしょうか、それとももっと根源的な何かが働いているのでしょうか。
実は、その素朴な感覚が、人間社会の基本的な仕組みを解き明かします。人と人との間で交わされる無数のやり取りは、物や善意が移動するだけではありません。それらが鎖のようにつながり、積み重なっていく中で、信頼関係を生み出し、目には見えない安定した秩序を編み上げていきます。
しかし、この力は常に穏やかな顔をしているわけではありません。もし、そのやり取りが一方通行になり、お返しのバランスが崩れたとき、かつて対等だったはずの関係は変質し始めます。助ける側と助けられる側という非対称性が生まれ、やがては「権力」という、より強固な社会構造へと発展することがあります。
本コラムでは、この「交換」というシンプルでありながらも奥深い視点を通して、私たちの社会がいかに形作られているのかを考えていきます。古代社会で行われていた不思議な贈物の習慣から、現代の人間関係を支える暗黙のルール、組織の中で権力が生まれる瞬間、さらには私たちの経済活動を規定する論理まで。これらの現象が、「交換」という一本の糸でどのようにつながっているのかをたどることで、日常や職場、社会全体を新しい視点から見つめ直すきっかけを提供します。
贈与は返礼義務を伴い、物と人格が一体となって社会関係を築く営み
現代社会で私たちが慣れ親しんでいる、お金を介した「売買」とは異なり、古代社会では物を「贈る」という行為が社会を動かす力を持っていました。そこでは、贈られる物は単なる物体ではなく、贈る人の人格や魂の一部を宿した「生きている存在」として扱われていたのです[1]。
例えば、南太平洋のポリネシアでは、結婚のような人生の節目で財産が交換されました。特に儀式で使われるマットのような財産は、便利な道具というだけでなく、一族の誇りと魂が織り込まれた宝と見なされ、その家の歴史や名誉として扱われました。
ニュージーランドのマオリの社会には、この物と人格の結びつきを説明する「ハウ」という霊的な力の概念があります。贈り物には元の持ち主の「ハウ」が宿っており、それは常に故郷へ帰りたがると信じられていました。そのため、贈り物を受け取った者は返礼をしなければならず、さもなければ「ハウ」が災いをもたらすとされました。お返しは礼儀である以上に、世界のバランスを回復するための必須の行為だったのです。何かを贈ることは自分の一部を託すことであり、受け取ることは相手の一部を受け入れること。この物を通じた魂の交流が、人間関係を築く力となっていました。
この贈与の力学が、より競争的な形で現れる社会もあります。メラネシアのトロブリアンド諸島には「クラ」という儀礼的交換の制度があり、島の共同体同士が特定の宝物を交換し続けました。これは生活必需品のためではなく、より価値ある宝物を気前よく贈ることで、自らの名誉と地位を高めるための競争でした。
北米の太平洋岸北西部の先住民社会には「ポトラッチ」という、さらに激しい贈与の慣習がありました。祝宴の主催者は、蓄えた財産を招待客に惜しげもなく分け与え、時には目の前で破壊して見せました。山積みの毛布に火を放ち、貴重な銅板を打ち砕く。この行為は、自らの富と権力を誇示し、ライバルを圧倒するための究極の手段でした。招待された者は受け取った以上の返礼を将来しなければならず、できなければ地位と名誉を失いました。与える、受け取る、返礼するという三つの義務が、社会を厳格に支配していたのです。
こうした物と人格が結びついた交換のあり方は、古代の法制度にも名残が見られます。古代ゲルマンの社会では、契約時に交換される質草に差し出す人の人格が宿るとされ、それが契約を守らせる力になると考えられていました。ドイツ語で「贈り物」を意味する言葉が同時に「毒」をも意味することは、贈り物が持つ、関係を結ぶ力と義務で縛る危険な側面を象徴しています。
このように、贈与には返礼を強制する力が内蔵されています。この「お返し」の原理が、より一般化された社会のルールとして私たちの行動をどう規定しているのか、次に掘り下げましょう。
互酬性の規範は社会を安定させ、人間関係を始めるきっかけともなる
古代社会の贈与の根底にあった「何かを受け取ったら、何かを返さなければならない」という原理は、私たちの社会にも「互酬性の規範」として根付いています。このルールは、社会の安定を保ち、新しい人間関係が始まる上で重要な働きをしています[2]。
社会制度が存続するのは、それが社会に良い働きをするからだと説明されることがありますが、そこには貢献を受けた側からの「お返し」によってその存続が支えられている、という相互関係の視点が欠けていることがあります。もちろん、権力による強制など、お返しがなくても関係が続く場合はありますが、多くの場合、社会的な関係はこの相互のやり取りによって維持されています。
このバランスが崩れた「価値が不釣り合いな交換」は「搾取」につながる可能性があります。互酬性の規範は、そのような事態を防ぐ社会的な仕組みとして機能します。この規範は「自分を助けてくれた人を助けるべきだ」そして「自分を助けてくれた人を傷つけてはならない」という二つの基本的な要求から成り、社会の安定に多方面から貢献しています。
一つは、人々の利己的な動機を社会の維持へと方向付ける点です。将来助けてもらうためには、まず自分が誰かを助けておくのが賢明だと人々は考えます。自分の利益を追求する行動が、結果的に社会全体の協力関係を強化します。
この規範は権力者の権力乱用を抑制します。権力者が誰かから奉仕を受けた場合、たとえ力で優位にあっても、この規範によって道徳的な「返礼の義務」が生じます。これが搾取的な関係の出現を抑えます。
さらに、互酬性の規範は時間の中で人間関係を安定させます。贈り物を受け取ってからお返しをするまでの「借り」がある期間、借り手は貸し手との関係を断ちにくくなります。義務がまだ果たされていないという事実が、関係を維持する働きをします。
この規範のもう一つの特徴はその柔軟性です。特定の地位に課される義務と異なり、互酬性が要求する内容は状況によって変化します。この不確定性のおかげで、規範はルールが未整備な新しい人間関係にも適用でき、社会構造の隙間を埋めます。
そして、互酬性の規範は、社会を維持するだけでなく、新しい関係を「開始させるメカニズム」でもあります。見知らぬ人同士が出会うとき、そこには不信感が漂います。しかし、互酬性の規範が心にあれば、「たとえ今与えても、相手はいつか返してくれるはずだ」という信頼が生まれます。この信頼が、最初の一歩を踏み出す勇気を与え、協力関係を築くきっかけとなります。
しかし、もしこの「お返し」のバランスが崩れてしまったら、社会はどう変化するのでしょうか。この互酬性の不均衡がもたらす、権力の誕生を見ていきましょう。
返礼できない受益が、対等な交換関係を権力構造へと転化させる
「お返し」のバランスが保たれている限り、人々の関係は対等であり続けます。しかし、社会には指示する側とされる側といった非対称な関係が存在します。このような権力構造は、互酬性のバランスが崩れ、返礼が不可能になったときに始まる、交換のもう一つの物語です[3]。
社会的な交換は、金額や期日が明確な経済取引と異なり、「未特定の義務」を生みます。この曖昧さが信頼を育み、「いつかお返ししよう」という気持ちが長期的な人間関係を支えます。
しかし、この交換が一方向的になったとき、事態は一変します。ある人が、他者が必要とする希少な資源(例えば、専門知識や問題解決能力など)を独占的に提供し続けると、周りは恩恵を受け続ける一方で、見合うお返しができなくなります。感謝は、やがて返礼できない負い目と提供者への依存心に変わります。
この状況で受益者には、(1)同等の返礼をする、(2)代替源を探す、(3)力で奪う、(4)欲求を抑える、という選択肢があります。権力は、この四つの道がすべて塞がれたときに生まれます。返礼もできず、他を頼ることも、力で奪うことも、諦めることもできないとき、残された選択肢は提供者に「服従」することだけです。この「服従」が、返礼不能な恩恵に対する唯一の「お返し」となり、対等な交換関係は支配と従属という権力構造へと転化します。
このプロセスは職場でも観察できます。経験豊富なベテラン社員に若手社員が助言を求め続けると、若手は感謝と尊敬、指示に従うという「服従」でしか返礼できなくなります。こうしてベテランは、公式の役職とは無関係に、非公式のリーダーとしての地位を確立します。
ただし、権力が長期的に安定するには「正当化」が必要です。単に力で従わせる支配は反発を招きます。権力が、従う側からも「公正で、自分たちの利益になる」と認められたとき、それは「権威」へと昇華します。支配者が力を集団全体の福祉のために用いることで、部下は自発的に指示に従うようになります。このプロセスを経て、非公式な権力は安定した組織構造の基礎となります。
原始経済は潜在能力を使い切らず、世帯単位の生産様式が過少生産を生む
現代の経済は「より多く、より効率的に」という考えに基づいています。しかし人類の歴史には、潜在能力をあえて使い切らず、「ほどほど」で満足する、異なる経済の論理が存在しました。多くの原始社会で、「過少生産」とも呼べる現象が見られます[4]。これは技術の未熟さではなく、利用可能な資源や労働力を意図的に活用しきっていない状態を指します。
第一に、資源が未利用でした。焼畑農業を行う多くの社会では、土地が持つ潜在的な収容能力よりも、はるかに少ない人口しか住んでいませんでした。第二に、労働力も未利用でした。人々は一日中働き詰めるわけではなく、労働は断続的で、休息や儀式のために頻繁に中断されました。第三に、生産の基本単位である「世帯」レベルで見ても、多くが自給自足を達成できていませんでした。
なぜ、このような「過少生産」が生じるのでしょうか。その答えは、これらの社会の経済を支える「家内生産様式」という構造にあります。この生産様式では、目的は利益の最大化ではなく、家族が暮らすために必要なものを手に入れる「生計のための生産」です。そのため生産目標は有限であり、ひとたび必要量が確保されると、それ以上働く強い動機が生まれません。システム自体に、余剰を生み出して拡大していこうとする力が内蔵されていません。
この傾向は、「チャヤノフの法則」によって強められます。これは、世帯内の働き手一人当たりの扶養家族の割合が高いほど各働き手は懸命に働くが、逆に生産力に余裕のある世帯ほど各働き手はあまり働かなくなるという法則です。社会の生活水準は平均的な世帯に設定されるため、能力の高い世帯の潜在力は十分に発揮されません。
さらに、各世帯は独立した生産単位として機能し、世帯間の経済的な結びつきが弱いため、社会全体で生産力を最大化しようという協力体制は生まれにくいのです。
脚注
[1] Mauss, M. (1966). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies (I. Cunnison, Trans.). Cohen & West. (Original work published 1925)
[2] Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25, 161-178.
[3] Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. John Wiley & Sons.
[4] Sahlins, M. (1972). Stone Age Economics. Aldine-Atherton.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






