2026年2月18日
ミドルが編む戦略:言葉と文脈の力学
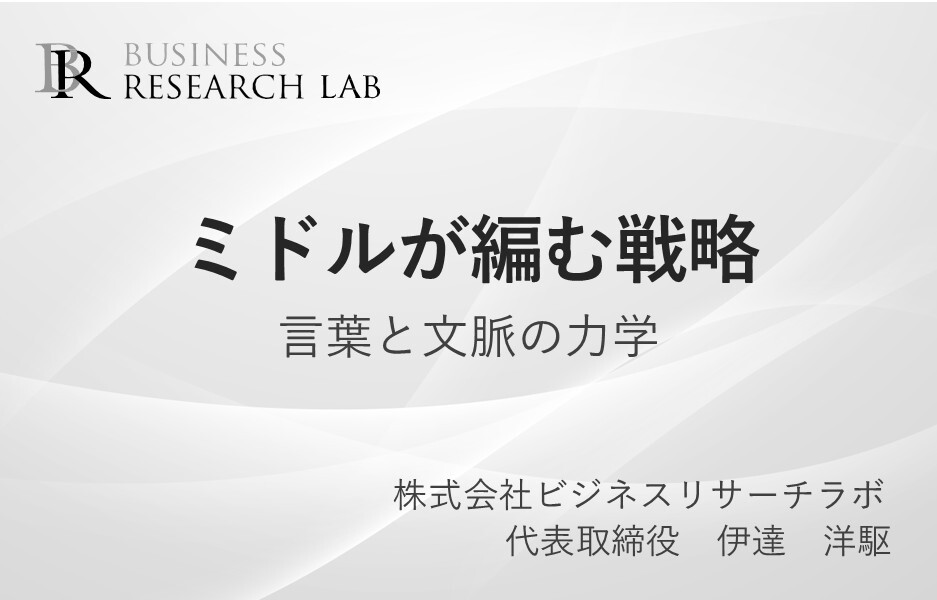
「戦略」という言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょう。優れた経営者が未来を見通し、会社の壮大な針路を描くシーンを想像するかもしれません。市場を分析し、競合を読み、大胆な打ち手を決断する。それは知的でダイナミックな営みに見えます。
しかし、戦略の姿は、そうした華やかな場面だけにあるのではないとしたらどう思いますか。私たちの職場で行われている、ごくありふれた日常業務の中に、戦略を形作る重要な手がかりが隠されています。
例えば、会議で使われる資料にどのような言葉が選ばれているか。あるいは、誰が最初に発言し、どのような雰囲気で議論が進むのか。顧客との電話でのやり取りや、他部門の同僚との短い立ち話。そうした一つひとつのささやかな営みが積み重なり、組織全体の方向性は少しずつ定まっていきます。
本コラムでは、そうした「ミクロな実践」に光を当てます。戦略が、一部のトップ層によって一方的に「作られる」ものではなく、現場の一人ひとりの日々の活動の中から「生まれてくる」プロセスであることを見ていきたいと思います。
戦略は道具の特性と人の意図の相互作用から生まれる
戦略を考えるとき、私たちは何らかの「道具」を使います。企業の強み弱みを整理するフレームワークや、事業を評価するチャートなどが代表例です。これらは合理的な判断を助ける便利な手段ですが、本当に中立で客観的なのでしょうか。使う道具が、私たちの思考を特定の方向へと導いているのかもしれません。
この問いを探求した研究は、戦略ツールを、使う人と相互に作用しあう「生きた道具」として捉え直す視点を提示しています[1]。道具には特定の使い方を促す性質があり、使う側にもそれぞれの立場や意図があります。戦略とは、この両者の相互作用から生まれるという考え方です。
ある通信機器メーカー「CommCorp」の事例を見てみましょう。ITバブル崩壊後、同社は多くのプロジェクト見直しに迫られました。その際、あるマネージャーが「バブルチャート」という図を導入しました。もともとこのチャートは「製品の変化度」と「プロセスの変化度」を軸とするものでしたが、彼は自社の危機的状況に合わせ、軸を「市場への到達度」と「製品の到達度」という独自基準に作り替えました。道具が教科書通りではなく、現場のニーズに応じて柔軟に改造されることを示す一例です。
経営会議でこの新チャートが提示されると、活発な議論が起こりました。しかし、議論の中心は個々のプロジェクト評価より、「そもそも、この軸の定義でよいのか」という点に集まりました。リスク・リターンの観点を加えるべき、投資規模を考慮すべきといった意見が出されました。
すぐに結論は出ませんでしたが、このプロセスを通じ、会社として短期的に何を優先し、長期的にどう挑戦すべきか、といった価値観が共有されていきました。誰が何を大事だと考えているのかが可視化され、ばらばらだった認識が揃っていったのです。
この事例が物語るのは、戦略ツールが単に答えを出す計算機ではないということです。むしろ、多様な意見を持つ人々が対話し、交渉するための「共通の言語」や「対話の場」を提供します。その道具の構造自体が、議論の焦点を定め、何が語られ、何が見過ごされるかを方向づけています。
道具の選択においても、合理性だけではない力学が働きます。組織内で長く使われ慣れ親しんだツールは、最適でなくても選ばれやすいという性質があります。視覚的に分かりやすいシンプルなツールも好まれます。数値を扱うツールは客観的に見えるため魅力的ですが、使いこなすには習熟が求められます。
もちろん、人の要因も選択に作用します。高い権限を持つ人ほど選択の自由は大きく、特定のツールに習熟した人はそれを選びやすくなるでしょう。
このように、戦略を立てる行為は、最適な道具を選んで正しく適用するという単純な作業ではありません。道具を選ぶ段階から組織の慣習や個人の経験、権力関係が絡み合い、使われる過程で人々は対話し、時に道具を改造しながら、進むべき方向性の合意を形成していきます。戦略とは、こうした道具と人の相互作用の中から、少しずつ姿を現してくるものだと言えます。
戦略会議は微細な実践を通じて戦略の安定と変化を生む
戦略ツールという「モノ」と人の関わりが凝縮される場所が「会議」です。形式的で退屈に見えるかもしれませんが、そこで交わされる言葉やごく細かな手続きの一つひとつが、組織の戦略を維持し、あるいは変化させる上で決定的な働きをしています。
この会議という営みを、戦略が生まれる社会的な実践の場として捉え、その内部を詳細に観察した研究があります[2]。英国の三つの大学で行われた51の戦略会議を分析したものです。大学は権限が分散し目標も多様なため、トップダウンが難しく、会議が合意形成の重要な場となります。
この研究は、会議を「開始」「遂行」「終了」の三局面に分け、各局面の微細な実践が、既存戦略を維持する「安定化」と、変化を生む「不安定化」にどう結びつくかを解き明かしています。
会議の「開始」段階。「場所」も重要な意味を持ちます。トップマネジメントの領域で会議が開かれると、参加者は普段の所属部署の利害から距離を置き、組織全体の議題に集中しやすくなります。誰が「議題」を設定し、その順番を決めるかも、議論の範囲と流れをコントロールする上で大きな力となります。トップが「議長」を務めれば、進行管理の権威が生まれます。これらは会議全体の方向性を形作る土台です。
議論の進め方である「遂行」段階。分析の結果、四つの異なるタイプが見られました。
一つ目は「自由討議」。議長が細かく管理せず、参加者が自由に意見交換する形式です。自律的な雰囲気の中、既存の枠組みを揺るがす新しいアイデアが生まれやすく、戦略を「不安定化」させる方向に働きます。
二つ目は「制約付き自由討議」。一見自由な議論ですが、議長が流れに介入し、トップの意向から外れそうになると制約します。これによって新しいアイデアの出現が妨げられ、戦略を「安定化」させます。
三つ目は「制約付き討議」。指名された人が順番に発言する形式的な議論です。自発的な応酬が起こりにくく、既存戦略を再確認する発言が多くなるため、これも「安定化」に貢献します。
四つ目が「事務的討議」。観察された議論の半数以上がこれに該当したといいます。合意済みの事項の進捗報告など、管理的・事務的な内容です。新たなアイデアは生まれず、既存戦略を着実に進めるという点で、強力な「安定化」の機能を果たしていました。
最後に「終了」段階。議論の締めくくり方が、生まれたアイデアの運命を決めます。例えば、ある提案に「ワーキンググループ」を設置し、会議の外で検討を継続させると、生まれたばかりのアイデアが時間をかけて具体化され、発展する機会を得ます。これは「不安定化」につながります。結論を出さずに議題を次回に持ち越す「再スケジューリング」も同様です。
一方で、論争的な提案に対する「投票」は、異なる結果をもたらす傾向がありました。投票に持ち込まれる時点で反対が根強く、否決されるか、可決されても実行で抵抗に遭いやすいため、結果的に戦略を「安定化」させます。
この研究は、組織の「安定」が、何もしないことの結果ではなく、変化の芽を摘み、既存の方向性を再確認する能動的な実践によって維持される「社会的な達成」であることを示しています。会議という日常の中に、戦略の安定と変化をめぐる微細で決定的な力学が働いています。
ミドルが暗黙知を使い、顧客との間で戦略を創る
戦略は組織の中だけで完結するものではなく、顧客との関わりが企業の存続を左右します。この組織の内と外の境界線に立ち、戦略を顧客に伝え、また顧客とのやり取りの中から戦略を形作っていくのが、中間管理職、すなわちミドルマネージャーです。
トップが掲げた抽象的な方針を、彼ら彼女らはどう顧客が理解できる言葉に「翻訳」し、受け入れてもらうよう働きかけているのか。その姿を、一社の高級婦人服メーカーに密着して描き出したエスノグラフィーがあります[3]。
この会社は、厳しい競争を背景に、製品ラインを拡大するという戦略転換に乗り出しました。研究者は、変革の初期段階で顧客との関係構築を担った二人のミドルマネージャーの日常業務を観察しました。
分析の結果、彼ら彼女らが戦略的変革を解釈し(センスメイキング)、外部に伝達・説得していく(センスギビング)上で、四つの微細な実践を組み合わせていることが明らかになりました。これらの実践の根底には、長年の経験で培われた、言葉にできない「暗黙知」があります。
一つ目は、新しい方向性の「翻訳」。ミドルマネージャーは、戦略転換の背景にある財務的な事情などをそのまま語りません。代わりに、顧客やメディアが聞きたいであろう物語を選び、再構成します。例えば、新しいコレクションが生まれた理由を、相手に応じて「現代女性のため」「調査の結果」「経営陣との議論の末」など、異なる角度から語り分けました。
二つ目は、戦略の「過剰符号化」。戦略に関する言動を、相手が属する社会や文化の規範(コード)に埋め込み、メッセージの意味を補強します。例えば、相手の母語で会話し、地域のファッションを応援する意義に触れることで、コレクションに特別な意味を付与しました。また、性別も資源として活用し、「女性同士」の共感や、男性として女性の美しさを語ることで、魅力を訴えかけました。
三つ目は、顧客の「規律化」。言葉だけでなく、ジェスチャーや空間演出などを通じ、顧客が新しいコレクションを受け入れるよう感情的に働きかけます。ショールームの音楽や照明を調整し、自ら服を着てみせることで、顧客が「この服を売りたい」と感じる空気感を創り出しました。
四つ目が、変革の「正当化」。なぜ会社が製品ラインを変えるのかを説明する際、一貫して「顧客の言説」を用いました。この戦略変更は「顧客が望んだことに応えるため」と繰り返し語ることで、会社の評判を維持しつつ、新しい方向性を正当化したのです。
この研究から見えてくるのは、戦略がトップダウンで伝達される静的な情報ではないということです。それはミドルマネージャーが暗黙知を総動員し、顧客との日々のコミュニケーションの中に宿らせるものです。彼ら彼女らは単なる伝達役ではなく、戦略の意味をその場で創造していく主体です。
戦略とはミドルが言葉と文脈を操り影響力を行使すること
ミドルマネージャーの活動は、顧客という「外向き」だけにとどまりません。組織の「内向き」にも、上司や部下、他部門を動かし、戦略的な変革を実現させる必要があります。公式な権限が限られる中で、彼ら彼女らはどのように周囲に働きかけ、物事を前に進めているのか。その鍵は、言葉と、その言葉が生きる「文脈」を操る能力にあります。
ミドルマネージャーの影響力の源泉を「言説的能力」という概念で捉えた研究があります[4]。これは単に話がうまいということではなく、組織の文化や人間関係といった文脈を深く理解し、他者にとって意味のある説得的なメッセージを組み立て、共有する総合的な能力を指します。
この能力は、相互に関連する二つの活動から成り立ちます。
一つは「会話を演じる」こと。他者を自分の計画に引き込むため、公式・非公式の会話を通じて行う相互作用です。情報を一方的に伝えるのでなく、相手の関心事を理解し、適切な言葉や論理でメッセージを「作り上げ」、効果的に「広める」活動です。例えば、コスト意識の強い文化の企業で改革を進めたマネージャーは、常に「利益」「コスト削減」という組織の共通言語を使い、各部門のメリットを論理的に示すことで協力を取り付けました。
もう一つは「舞台を設定する」こと。「会話」が効果的に行われるための文脈や機会を意図的に作り出す活動です。誰と誰を会わせるか、どんな形式で話すか、どのタイミングで切り出すかなどを計画し、実行します。例えば、反抗的とされるチームとの調整役を担ったマネージャーは、まず非公式な場でゲームを共にし、交渉の土台となる信頼関係という「舞台」を設定しました。
この二つの活動は切り離せません。言葉は、それが語られる「舞台」があって初めて力を発揮し、巧みな「会話」は次の「舞台」を作り出します。ミドルマネージャーは、この二つを組み合わせることで、公式な権限がなくても組織を動かしていきます。
彼ら彼女らは、組織特有の専門用語や価値観、部門間の力関係、キーパーソンといった人間関係の歴史、暗黙のルールといった目に見えない「文脈」を理解し、その知識を駆使して自身の状況を有利に変えていきます。
この研究が示唆するのは、戦略の実行が計画書通りの機械的なプロセスではないということです。それは、様々な利害を持つ人々を説得し、巻き込み、協力体制を築く、地道で政治的なプロセスです。ミドルマネージャーが持つ、言葉と文脈を操る能力は、そのプロセスを動かします。
脚注
[1] Jarzabkowski, P., and Kaplan, S. (2015). Strategy tools-in-use: A framework for understanding “technologies of rationality” in practice. Strategic Management Journal, 36(4), 537-558.
[2] Jarzabkowski, P., and Seidl, D. (2008). The role of strategy meetings in the social practice of strategy. Organization Studies, 29(11), 1391-1426.
[3] Rouleau, L. (2005). Micro-practices of strategic sensemaking and sensegiving: How middle managers interpret and sell change every day. Journal of Management Studies, 42(7), 1413-1443.
[4] Rouleau, L., and Balogun, J. (2011). Middle managers, strategic sensemaking, and discursive competence. Journal of Management Studies, 48(5), 953-983.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






