2026年2月18日
マニュアル以上、即興未満:ルーティンがもたらす学習
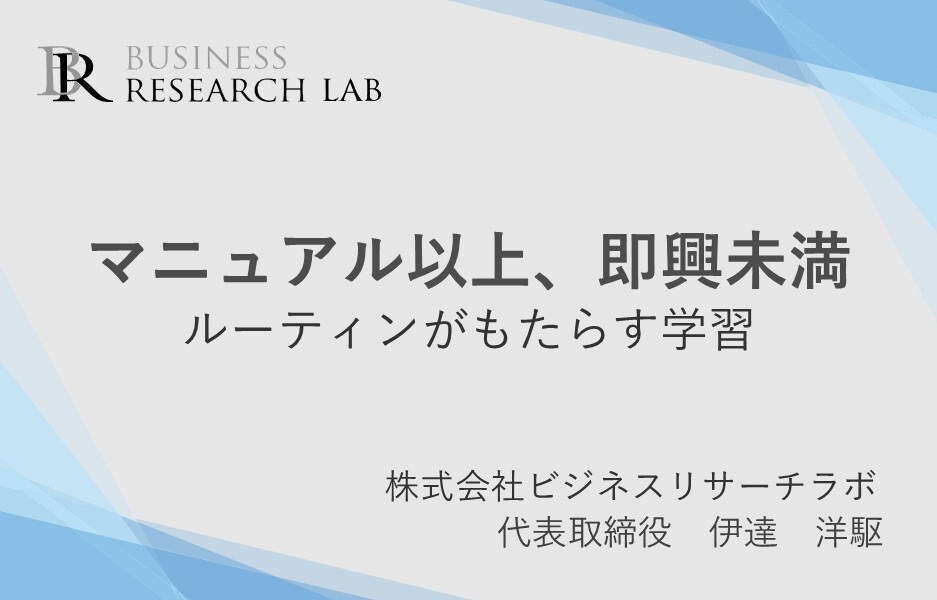
海外の小説が日本語に翻訳される際、言葉の置き換え以上の創造的な作業が行われます。魅力的な邦題がつけられ、文化背景を補う訳注が加わる。これは、異文化で生まれた物語を、日本の読者が心地よく深く理解できるように作り変える「翻訳」という営みです。
実は、このような「翻訳」は、ビジネスの世界、特に経営の手法や理念が国境を越えて広まる過程でも、より複雑でダイナミックな形で起きています。ある国で成功した生産方式や人事制度は、別の国に導入される時、設計図通りにはいきません。受け入れ先の社会の歴史、文化、政治的な思惑の中で、その意味合いを変え、新しいものとして生まれ変わることさえあります。
本コラムでは、「翻訳」というレンズを通して、経営のアイデアが世界を旅する物語を紐解きます。それは効率性の追求にとどまらず、異文化をどう理解し、受け入れるかという問いにつながります。一見、普遍的に見える経営の原理が、国境を越えることでいかに多様な姿を見せるのか。そのプロセスを追いかけてみたいと思います。
日本の経営実践は異質さを強調する形で米国へと翻訳された
「ルーティン」と聞くと、どのようなイメージが浮かぶでしょうか。毎日繰り返される退屈な作業、創造性を奪う画一的な手続き、あるいは変化を拒む組織の硬直性の象徴かもしれません。多くの人が、ルーティンワークを「こなす」ものと捉え、そこからは新しい何かが生まれるとは期待していないのではないでしょうか。しかし実は、その「決まりきった仕事」が、組織が絶えず変化し、しなやかさを保ち続けるための源泉にもなっています。
一見すると、安定と変化は正反対の概念に思えます。ところが、組織の日常に根ざしたルーティンの内部を観察すると、そこには動的な世界が広がっています。人々は決められた手順をただ機械的に繰り返しているわけではなく、日々の実践の中で微妙な工夫を加え、予期せぬ出来事に対応し、より良い方法を模索しています。
本コラムでは、固定的で動かないものと見なされやすいルーティンが、連続的な変化と柔軟性を生み出す仕組みとして機能する側面に光を当てていきます。組織の現場で、ルーティンがどのように実行され、解釈され、作り変えられていくのか。その過程を解き明かすことで、「決まりきった仕事」に秘められた、組織を活性化させる可能性を探っていきます。
組織ルーティンは固定的ではなく、連続的な変化の源
組織におけるルーティンは、しばしば「標準業務手順書」のような、一度決めたら変わらない固定的なものとして認識されます。しかし、実際の現場では、同じルーティンが毎回全く同じように実行されることは稀です。そこには、実行する人々の解釈や反応が介在し、ルーティンが絶え間ない変化のきっかけとなり得ます。
ある大学の学生寮を対象とした、約4年間にわたる長期的な観察記録は、この側面を浮き彫りにします[1]。研究者は、寮の運営に関わる人々の中に身を置き、予算編成、スタッフの採用と訓練、学生の入退去といった、毎年繰り返される複数のルーティンを追い続けました。当初は「大きくは変わらない行動パターン」という前提で観察を始めましたが、現場で目にしたのは、多くのルーティンが年々その姿を変えていく様子でした。
例えば、学生が退去する際の「損傷査定」というルーティンがありました。従来の手順は、学生が部屋を空けた後にスタッフが損傷を確認し、修理費を請求するという事務的なものでした。しかし、現場の責任者たちは、このやり方が学生の責任感を育む機会を損なっていると感じていました。
そこで、手順が変更されます。退去前に、居住する学生とスタッフが一緒に部屋の状態を確かめ、その場で責任の所在を話し合う形にしたのです。この変更は、単に手続きを修正しただけではありません。学生に当事者意識を促し、スタッフとの対話を通じて教育的な関与を深めるという、新たな価値を生み出しました。これは、既存のやり方の不都合な点を是正する「修復」であると同時に、対話という新しい機会を組み込む「拡張」でもありました。
学生が入居する際の「ムーブイン」というルーティンも、変化を遂げました。当初は各寮が個別に対応していたため、周辺は毎年ひどい交通渋滞に見舞われ、新入生や家族の不満も大きいものでした。この問題を解決するため、組織は中央で交通整理を統括する方式へ移行します。警察と連携して一方通行のルートを設定し、荷降ろしのための停車時間を制限するなど、改善策を導入しました。その結果、入居プロセスはスムーズになります。
しかし、変化はそこで終わりませんでした。一度成功を収めると、関係者の間では「もっと良くできるはずだ」という意識が芽生え、理想の水準が引き上げられました。次はロビーの混雑緩和へと課題が移り、さらには大学のフットボールの試合日程という外部からの予期せぬ出来事に対応するため、入居日を前倒しするといった再設計も行われました。この過程で、組織は大学の運動部門など、これまで関係の薄かった他部署とも連携するようになり、利害関係者を巻き込みながら問題を解決していくという新しい行動様式を学習していきました。
このように、ルーティンは固定的な規則ではなく、理念や目標を実現するための実践の連なりとして捉えることができます。ある実践の結果は、次の実践の計画に反映されるだけでなく、時には「何を目指すべきか」という理念や理想を更新します。
不都合な結果を「修復」しようとする試み。新たな可能性を活かそうとする「拡張」の動き。一度達成した水準に満足せず、より高みを目指し続ける「ストライビング」。これらの反応が日々の実践の中で繰り返されることで、ルーティンは安定した繰り返しの中から、連続的な変化を生み出す装置として機能していきます。
組織ルーティンは、硬直的でなく柔軟性と変化の源泉
先ほどは、現場の人々の実践を通じてルーティンが少しずつ変化し続ける様子を見てきました。そうであるならば、ルーティンが持つ安定性、すなわち、組織の活動を秩序立てる側面はどこから来るのでしょうか。安定と変化という、一見矛盾する二つの性質は、どのように一つのルーティンの中に共存しているのでしょうか。この問いに答えるためには、ルーティンを構成する複数の要素に分解して考えることが助けになります[2]。
ルーティンは、単一の行動手順として存在するわけではありません。それは、少なくとも三つの異なる側面が相互に絡み合ったシステムとして理解することができます。
一つ目は「オステンシブな側面」と呼ばれるものです。これは、そのルーティンが「どのようなものであるか」を示す、抽象的な理解や理念、共有されたイメージを指します。いわば、ルーティンの「台本」や「設計図」に相当する部分で、手順書に書かれたり、人々の間で語られたりする一般的なパターンです。
二つ目は「パフォーマティブな側面」です。これは、特定の場面で、特定の人々によって実際に行われる、具体的な行為の連なりを指します。オステンシブという抽象的な「台本」を、現場の状況に合わせて人々が「上演」する、一回性の実践です。ここには、個人の技能や即興的な判断、チーム内の相互作用といった現実の動きが含まれます。
三つ目は「アーティファクト」です。これは、マニュアルやチェックリスト、情報システム、あるいはオフィスのレイアウトといった、ルーティンの実行を助けたり、制約したりする物理的なモノや記号を指します。アーティファクトは、オステンシブという抽象的な理解を形あるものとして固定する媒体であり、同時にパフォーマティブという具体的な行為を方向づける道具でもあります。
これら三つの側面は、互いに影響を与え合いながら循環しています。人々の日々の具体的な実践(パフォーマティブ)は、そのルーティンとはこういうものだという共有された理解(オステンシブ)を少しずつ更新していきます。更新された理解は、次の実践が行われる際の参照点となります。実践の中で生まれた改善点がチェックリスト(アーティファクト)に書き加えられれば、それは次回以降の多くの人々の実践に波及します。
この循環構造が、ルーティンが安定性と柔軟性を両立させるメカニズムです。パフォーマティブな実践の場面では、状況に応じて小さな差異、すなわち「バリエーション」が生まれます。それは創意工夫かもしれませんし、エラーかもしれません。
これらのバリエーションのうち、良い結果をもたらしたものは、語りや記述(オステンシブ)を通じて共有されたり、テンプレート(アーティファクト)に反映されたりすることで「選択」されます。組織の仕組みとして「保持」されることで、場当たり的な成功で終わることなく、組織の能力として定着していきます。
この視点に立つと、標準化は硬直性をもたらすものではなくなります。適切に設計された標準(オステンシブやアーティファクト)は、人々が安心して試行錯誤できる「規律化された即興」の土台となります。ルーティンは、毎回全く同じことを繰り返すための仕組みではなく、実践から生まれた多様なバリエーションを選び出し、組織の学習成果として保持していくための、柔軟な生成システムとして機能することができます。
日常のルーティンでの試行錯誤が組織全体の価値観を変える
これまで、ルーティンの内部で起こる変化の仕組みを見てきました。日々の小さな実践の積み重ねが、手順や手続きといったルーティンを変容させていく。その変化は、ルーティンというミクロなレベルに留まるのでしょうか。それとも、組織全体の価値観やアイデンティティといった、よりマクロなレベルにまで及ぶことがあるのでしょうか。
新しく設立されたある研究機関の事例は、日常的なルーティンにおける試行錯誤が、組織の根幹をなす理念、すなわち「組織スキーマ」をも変え得ることを物語っています[3]。組織スキーマとは、組織の構成員が共有している、物事の捉え方や価値判断の枠組みのことです。この研究機関は設立当初、「起業家的で、非官僚的、ネットワーク的な組織」という理想を明確に掲げていました。これは、経営陣によって言語化された「表明されたスキーマ」と呼べるものです。
この理想を実現する上で、研究者を採用する「採用ルーティン」は特に大切なものと位置づけられていました。しかし、ここで問題が生じます。理想に従い、民間企業のように迅速で待遇の良い条件で人材を確保しようとしても、上位組織の公務員規定に阻まれて契約が承認されないという事態が頻発したのです。これは、ルーティンの実行を妨げる「問題」でした。
組織は当初、規定を回避できる別の契約形態を探すなど、非官僚的であろうとする理想に沿った形でこの問題の解決を試みます。しかし、それらの試みも失敗に終わりました。度重なる失敗を経て、組織はついに、規則の遵守を前面に出し、手続きを整備するという、当初の理想とは逆の官僚的な解決策へと方向転換せざるを得なくなりました。採用ルーティンは、より秩序だったものになりましたが、その代償は大きなものでした。
ルーティンのこの変化は、組織内に深刻な矛盾を生み出します。「我々の組織は、本当に起業家的と言えるのだろうか」という、組織の根幹に関わる「疑問」が生まれたのです。これは、具体的な業務上の「問題」とは質の異なる、組織のアイデンティティに関わる、より高次のエラーでした。
この「疑問」を解消するために導入されたのが、「アンバサダーモデル」という新しい仕組みでした。これは、各研究部署と事務局との間に調整役を置くことで、現場の自律性を尊重しつつ、必要な手続きを円滑に進めることを目指すものです。この試みを通じて、組織は官僚的な現実と起業家的な理想を両立させる道筋を見出します。最終的に、「官僚的か、起業家的か」という二者択一の考え方を捨て、「官僚的であり、かつ起業家的でもある」という、より成熟した新しいスキーマを表明するに至りました。
同様のプロセスは、新入社員を温かく迎えるという「歓迎ルーティン」でも観察されました。「組織は家族である」という当初のスキーマは、組織の急成長の中で機能不全に陥り、「我々は本当に家族のように運営できるのか」という「疑問」を生みます。ここでもアンバサダーモデルの導入などを通じた試行錯誤の末に、「プロフェッショナルであり、かつ(家族のように)人を大切にする」という新しいスキーマへと変化していきました。
この事例が明らかにするのは、二つの異なる学習プロセスの連鎖です。組織はルーティン実行上の「問題」に直面し、それを解決するための試行錯誤を繰り返します。その結果として生じた行動が、意図せずして当初の理想と矛盾する時に、組織のあり方に関する「疑問」が喚起されます。組織はこの「疑問」を解消するために、より大きな仕組みの変革を伴う試行錯誤に着手し、組織スキーマを変化させていきます。
安定に見えるルーティンも絶えず多様な形に変化する
新しい組織が試行錯誤を通じてその価値観を形成していく様子は、ルーティンの持つダイナミックな側面をよく表しています。しかし、このような変化は、流動的な新しい組織だからこそ起こる特別な現象なのでしょうか。規則が厳格に定められ、ITシステムによって高度に自動化された、成熟した組織のルーティンは、本当に固定的で安定しているのでしょうか。
この問いを検証するために、ノルウェーの四つの異なる組織で行われている「請求書処理」のプロセスが、大規模なデータを用いて分析されました[4]。請求書処理は、会計ルールや監査要件に縛られた、構造化された業務です。分析の対象となったのは、ワークフローシステムの監査ログに記録された、約5ヶ月間にわたる3万件以上の業務記録です。一件の請求書が処理されるまでの一連のアクション(誰が、いつ、何をしたか)を、一つのシーケンスとして捉え、そのパターンを解析しました。
ルーティンが固定的であるならば、観測されるシーケンスのパターンはごく少数に集約され、時間が経ってもその構造は変わらないはずです。しかし、分析結果は、この直観的な想定とは異なる様相を示しました。
初めに、実行されたパターンの多様性です。分析対象となったどの組織においても、数百から数千ものユニークなシーケンスが発見されました。特に、複数の担当者による承認が必要なプロセスでは、非常に多くのバリエーションが存在していました。ルーティンは、少数の決まりきった手順の繰り返しではなく、膨大な数の異なる遂行パターンの集合体でした。
続いて、時間の経過に伴う変化です。5ヶ月という比較的短い期間を前半と後半に分けて比較したところ、多くのルーティンで、アクションのつながり方、要するに遷移の構造が統計的に有意に変化していることが確認されました。特定の外部的な出来事があったわけではないにもかかわらず、ルーティンの実行パターンは、いわば「漂流」するように、その姿を変え続けていました。
この多様性と変化は、何によって生み出されているのでしょうか。分析によれば、その要因は主に組織の内部にありました。例えば、担当者の経験です。その業務に対する経験が豊富な担当者が関わるほど、実行パターンは典型的な形に近づく傾向が見られました。
一方で、自動化の効果は、より複雑でした。データ入力のような定型的な業務では、自動化率が高いほどパターンは典型的なものになりました。しかし、複数の人が関わる承認業務では、自動化は必ずしも変動を減らしませんでした。特に、経験の浅い担当者が自動化されたシステムを使う場面では、むしろ非典型的なパターンが増加するという結果が得られました。これは、システムが業務を補完する過程で、経験の浅い担当者の迷いやイレギュラーな対応を誘発した可能性を示唆します。
この実証研究から浮かび上がるのは、ルーティンの二層構造です。会計ルールのような深層の構造は安定している一方で、誰がどの順番で承認するかといった表層の実行系列は、豊かな多様性を示し、変化し続けています。その変化の仕方は、担当者の経験と、それを支える技術(自動化)がどのように組み合わさるかによって決まります。たとえ厳格で安定しているように見えるルーティンであっても、その内実を微視的に見れば、それは決して変わらない世界ではなく、人と技術の相互作用の中で「絶えず違っていく」現象なのです。
脚注
[1] Feldman, M. S. (2000). Organizational routines as a source of continuous change. Organization Science, 11(6), 611-629.
[2] Feldman, M. S., and Pentland, B. T. (2003). Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change. Administrative Science Quarterly, 48(1), 94-118.
[3] Rerup, C., and Feldman, M. S. (2011). Routines as a source of change in organizational schemata: The role of trial-and-error learning. Academy of Management Journal, 54(3), 577-610.
[4] Pentland, B. T., Harem, T., and Hillison, D. (2011). The (N)ever-changing world: Stability and change in organizational routines. Organization Science, 22(6), 1369-1383.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






