2026年2月16日
測ることは、すでに介入である:サーベイが組織を動かす
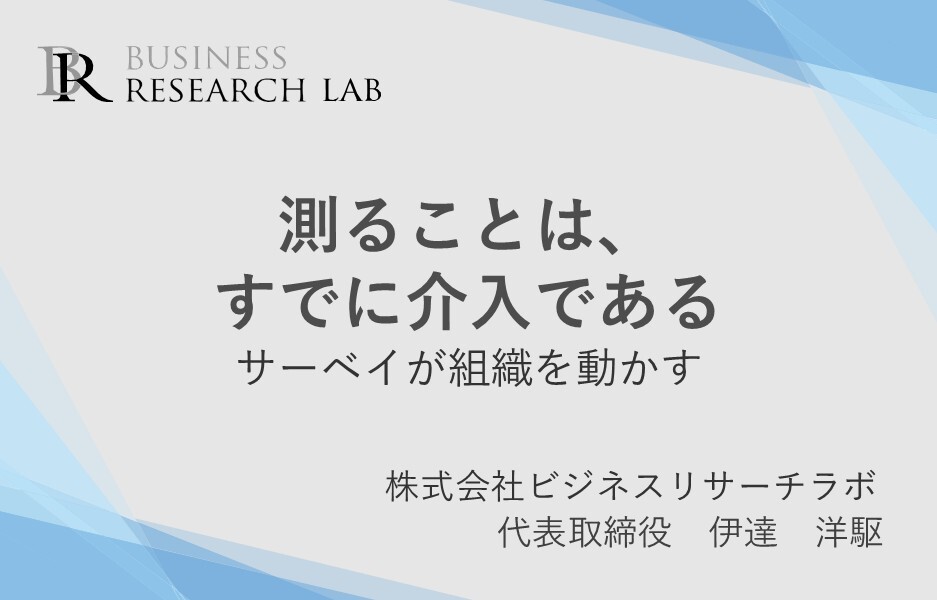
組織の健全性を測るため、多くの職場で定期的に実施される従業員サーベイ。その結果報告書に並ぶ数字、特に「回答率」のパーセンテージを見て、担当者は安堵したり、あるいは頭を悩ませたりするのではないでしょうか。高い回答率が得られれば、正確な診断ができたと考え、低い回答率であれば、その信頼性に疑問符がつく。このような考え方は、一見すると合理的であるように思えます。
しかし、その常識は、物事の一面にしか光を当てていません。サーベイという行為は、単なる測定ではなく、組織という生きたシステムに関与し、働きかけるプロセスです。質問票が従業員の手元に届いた瞬間から、組織には目に見えない変化の波が立ち始めます。それは期待かもしれないし、あるいは冷笑や無関心かもしれません。
本コラムでは、サーベイをめぐるこうした「当たり前」を一度脇に置き、その方法と測定の奥深さを探求していきます。回答率という数字の裏に隠された意味、集まったデータの偏りの問題、そして、サーベイの結果が共有された「後」に続くプロセスが、いかに組織の未来を形作っていくのか。複数の知見を頼りに、サーベイという営みを多角的に検討していきます。
回答率の高さは偏りの無さを保証しない
多くの組織において、従業員サーベイを実施する際の一つの目標として「高い回答率」が掲げられます。回答率が高ければ高いほど、集まったデータは組織全体の意見を反映していると考えられ、その結果の信頼性も増すように思われます。しかし、この直感的な理解は、必ずしも真実ではありません。回答率の数値は、得られたデータに偏りがないことを保証するものではないのです[1]。
この点を理解するために、二つの架空のシナリオを考えてみましょう。ある会社が100人の従業員を対象に、新しい人事制度への満足度を尋ねる調査を行いました。
一つ目のシナリオでは、90人から回答があり、回答率は90%に達しました。その内訳は、「満足」が45人、「不満」が45人でした。この結果だけを見ると、社内の意見はちょうど半々に分かれているように見えます。
しかし、まだ回答していない10人が存在します。もし、この10人全員が「満足」だと答えたとしたら、最終的な結果は「満足」55人、「不満」45人となり、賛成派が多数を占めます。逆に、10人全員が「不満」だったとすれば、「満足」45人、「不満」55人で、反対派が多数となります。このように、90%という非常に高い回答率であっても、未回答者の意見次第で、組織全体の多数派の結論が覆ってしまう可能性が残ります。
二つ目のシナリオでは、回答者はわずか10人で、回答率は10%でした。その内訳は、「満足」が5人、「不満」が5人でした。この低い回答率を見ると、このデータから組織全体の意向を推し量るのは無謀だと感じるかもしれません。しかし、回答しなかった残りの90人のうち、ちょうど半数の45人が「満足」で、残りの45人が「不満」だったとしたらどうでしょう。その場合、組織全体では「満足」が50人、「不満」が50人となり、10%の回答者から得られた結果と一致します。
これらのシナリオが示すのは、データの偏りを決定づけるのは、回答率の高さや低さそのものではないということです。問題は、回答した人々と回答しなかった人々の間に、調査テーマに関する意見や特性の体系的な「違い」が存在するかどうかにあります。
たとえ回答率が高くても、何らかの理由で不満を持つ人々だけが意図的に回答を避けていれば、結果は現状を過度に楽観的に映し出すでしょう。逆に回答率が低くても、回答しなかった人々が、単に多忙や失念といった理由で回答しなかっただけで、その意見分布が回答者と似ていれば、結果的に偏りは生じないこともあり得ます。
したがって、「業界標準の回答率は50%だから、それを超えれば一安心だ」といった考え方には、あまり根拠がありません。他の組織の回答率がどうであれ、自分たちの組織で得られたデータに偏りがないことの証明にはならないからです。
調査の回答率は個人と組織で異なる
先ほどは、回答率という一つの数字だけではデータの質を判断できないことを見ました。しかし、そうは言っても、自分たちのサーベイの回答率が、世間一般と比べてどの程度の水準にあるのかは、誰もが気になるところでしょう。ここでは、数多くの学術研究を横断的に分析し、サーベイの回答率の実態を明らかにした調査の結果を紐解いていきます[2]。
この調査は、経営学や心理学の分野で評価の高い17の学術雑誌に、ある二つの年に掲載された1600件以上の論文を精査するところから始まりました。その中から、質問紙調査を用いた490件の研究を特定し、詳細な分析を行いました。対象となったのは、10万を超える組織と40万人以上の個人からの回答です。
分析から浮かび上がった一つの事実は、調査の対象によって回答率に差があるということでした。具体的には、従業員一人ひとりの意識や態度、行動について尋ねる「個人レベル」の調査と、経営幹部や組織の代表者に対して、会社の方針や制度といった事柄について尋ねる「組織レベル」の調査とを比較したところ、前者の平均回答率が約53%であったのに対し、後者は約36%と、低い水準にとどまっていました。
この背景には、組織レベルの調査が、多忙を極める経営層などを対象とすることが多く、回答を得るためのハードルが高いという事情があるのかもしれません。
この調査は、回答率の長期的な推移についても興味深い知見を提供しています。過去の同様の調査では、1970年代から1990年代にかけて、学術研究におけるサーベイの回答率は低下する傾向が見られました。しかし、今回の調査で2000年代のデータを確認したところ、その低下傾向には歯止めがかかり、回答率はおおむね安定していることがわかりました。
一般的に回答率を高めると信じられている手法の効果についても検証が行われました。例えば、回答者への謝礼(インセンティブ)の提供です。分析の結果、謝礼の有無は、個人レベルの調査でも組織レベルの調査でも、回答率と明確な関連が見られませんでした。回答を促すためのリマインダーについても、同様に回答率を押し上げる決定的な要因とはなっていないことが分かりました。特に組織レベルの調査においては、督促を行ったと報告している研究の方が、そうでない研究に比べて回答率が低いという、一見すると直感に反する結果も得られています。
この逆説的な結果について、研究者は「督促をしたから回答率が下がった」と解釈すべきではないと注意を促しています。そうではなく、因果関係が逆である可能性、要するに「最初の回答の集まりが悪かった研究者が、何とかして回答率を上げようと、結果的に督促を多用することになった」と考える方が自然でしょう。
調査後のフォローが成果を左右する
サーベイを実施し、データを集計・分析して、報告書を完成させる。この段階でサーベイ・プロジェクトは一つの区切りを迎え、関係者は安堵のため息をつくかもしれません。しかし、サーベイの価値を決定づけるのは、実はここから始まるプロセスです。調査結果は、組織変革に向けた対話の「出発点」に過ぎず、その後のフォロー、つまり結果の共有、職場での議論、具体的な行動計画へとつなげていく一連の活動が、サーベイの成否を分けます。
このサーベイ後のフォローというプロセスは、どのような要素から成り立っているのでしょうか。ある研究では、この複雑なプロセスを理解するための「概念フレームワーク」が提案されています[3]。それは、プロセスを大きく「インプット(前提条件)」「プロセス(実際の活動)」「アウトプット(成果)」の三つの段階で捉えるものです。
「インプット」には、議論の材料となるサーベイのデータや、組織が置かれている外部環境などが含まれます。「アウトプット」は、フォロー活動によってもたらされる、職務満足度の向上や生産性の改善といった、個人や組織レベルでの望ましい結果を指します。
この二つをつなぐ中心的な部分が「プロセス」です。これは、単に会議を開いて結果を報告するだけの単純なものではありません。そこでは、組織の構造や利用可能なリソース(時間、予算、経営層の支援など)、組織文化といった「組織システム」と、議論に参加する従業員、その議論を主導する管理職、プロセスを支援する人事担当者や外部コンサルタントといった「人間システム」とが、相互に複雑に作用し合います。
このフォロー・プロセスについて、これまでの研究は何を明らかにしてきたのでしょうか。多くの関連研究を体系的にレビューした調査によると、研究の多くは、フォロー活動を行った結果どうなったかという「アウトプット」の測定に集中してきたことが分かりました。一方で、プロセスの質、例えば、会議がどのように運営されたか、管理職がどのような振る舞いをしたか、リソースの不足が議論にどう作用したか、といった点に光を当てた研究は、驚くほど少ないのが現状です。
成果に関する研究結果も、「まちまち」というのが正直なところです。フォローによって従業員の満足度が改善したという報告もあれば、目立った変化はなかったという報告もあり、一貫した結論は得られていません。このばらつきの背景には、研究ごとにフォローの実行の質が異なっていたり、調査期間中に組織再編のような他の出来事が起こったりと、様々な要因が考えられます。
しかし、そのような中でも、複数の研究で共通して見出されている一つの発見があります。それは、「サーベイの結果に基づいて、職場で具体的な行動が起こされた」と従業員が認識しているグループでは、そうでないグループに比べて、職務満足度などの指標が一貫して良好であるという事実です。これは、フォロー活動が行われるだけでなく、それが従業員に「変化が起きている」と実感される形で実行されることが大切であることを示唆しています。
診断データの収集やフィードバックが介入である
私たちは、従業員サーベイを「組織の健康診断」にたとえることがあります。問診票や測定機器を使って客観的なデータを集め(診断)、その結果を専門家が分析し、問題があれば処方箋を出す(介入)。この「診断してから介入する」というステップは論理的で分かりやすいモデルです。しかし、この一見すると自明な考え方の前提を、一度立ち止まって問い直してみる必要があります。データを集めるという行為は、本当に中立的な「診断」なのでしょうか[4]。
組織という人間関係の集合体において、誰かが誰かに質問を投げかけるという行為は、その瞬間に何らかの作用を及ぼさずにはいられません。質問は、受け手の思考を特定の方向へ導き、それまで意識していなかった事柄に目を向けさせます。サーベイへの回答を依頼することは、従業員に対して「あなたの意見には価値がある」というメッセージを送ると同時に、「組織はこの問題に関心を持っている」という期待を抱かせます。要するに、「データを集める」という行為が、すでに組織に対する「介入」としての性質を帯びているのです。
この視点に立つと、従来の「診断→介入」という直線的なモデルが持つ危うさが見えてきます。例えば、経営トップが自部門のチームの問題点を把握するために、コンサルタントに依頼して部下全員に調査を行うというシナリオを考えてみましょう。これは一般的な「診断」活動に見えますが、実際には、部下の立場からすれば、上司の意向で始められた調査に「答えざるを得ない」という状況に置かれます。このプロセスは、意図せずして組織内の力関係を再確認させ、従業員の受け身な姿勢を強めてしまう可能性があります。
全社サーベイの結果を、経営層から部長、課長へと、階層的に下ろしていく「カスケード」と呼ばれるフィードバック方法も同様です。このトップダウンのアプローチは、効率的に情報を伝達できるように見えますが、現場の従業員にとっては「上から問題点を指摘された」という受け止め方になりがちです。「問題は上にあるのだから、解決策も上が考えるべきだ」という依存的な空気を生み出し、本来、職場の問題を最もよく知るはずの現場の当事者意識を削いでしまうことにもなりかねません。
データ収集が介入であるという前提に立つならば、サーベイのプロセスはどのようにデザインし直されるべきでしょうか。ここで、「上向きカスケード(ボトムアップ)」という、従来とは逆の発想に基づくフィードバック設計が提案されています。
このアプローチでは、各職場のチームに、全社の平均値などと比較する前の「自分たちのチームだけの」生データを返します。そして、二つのことを問いかけます。「このデータは、私たちの実感や意見を正しく反映しているか」、そして「ここに示された課題のうち、どれが自分たちの力で解決できることで、どれが上位の組織に働きかけるべきことか」。
このプロセスを、各チームが主体的に行うのです。自分たちで解決すべき課題はその場で行動計画を立て、自分たちだけでは解決できない課題だけを、一つ上の階層に上げていきます。各階層で同じように、自分たちの責任範囲で解決できることと、さらに上に上げるべきことを仕分けていく。このプロセスを繰り返すことで、経営層に届くのは、全社的な視点でしか判断できない重要な課題だけになります。
この方法は、サーベイを「経営層が情報を吸い上げるためのツール」から、「各職場が自律的に問題を発見し、解決していくためのツール」へと、その意味合いを転換させます。問いを立て、データを返すという介入のプロセスを通じて、現場の当事者意識を育むこと。それが、サーベイが組織にもたらしうる価値ある成果の一つなのかもしれません。
脚注
[1] Rogelberg, S. G., and Stanton, J. M. (2007). Introduction: Understanding and dealing with organizational survey nonresponse. Organizational Research Methods, 10(2), 195-209.
[2] Baruch, Y., and Holtom, B. C. (2008). Survey response rate levels and trends in organizational research. Human Relations, 61(8), 1139-1160.
[3] Huebner, L.-A., and Zacher, H. (2021). Following up on employee surveys: A conceptual framework and systematic review. Frontiers in Psychology, 12, 801073.
[4] Schein, E. H. (1995). Process consultation, action research and clinical inquiry: Are they the same? Journal of Managerial Psychology, 10(6), 14-19.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






