2026年2月16日
経営モデルは輸入されず翻訳される:変容のプロセス
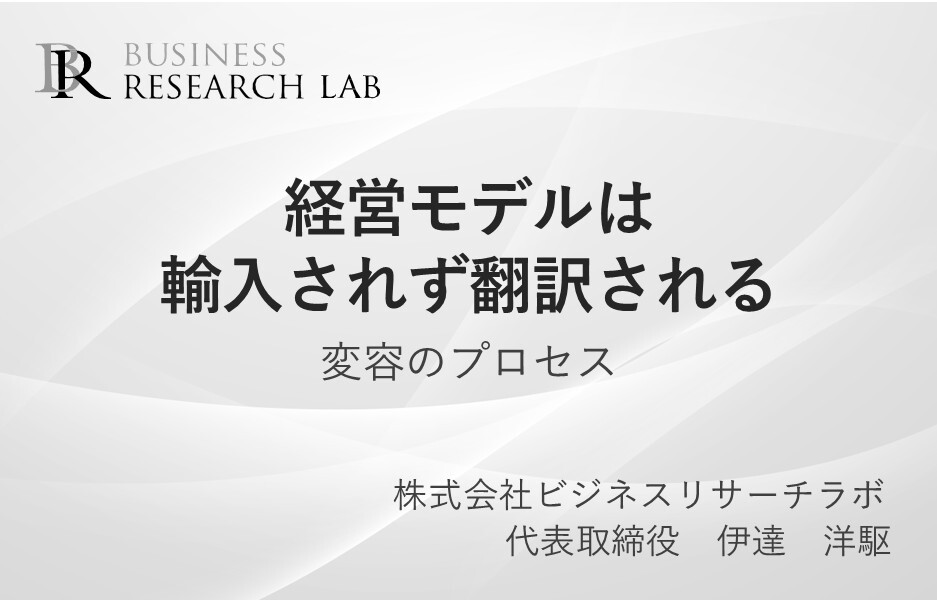
海外の小説が日本語に翻訳される際、言葉の置き換え以上の創造的な作業が行われます。魅力的な邦題がつけられ、文化背景を補う訳注が加わる。これは、異文化で生まれた物語を、日本の読者が心地よく深く理解できるように作り変える「翻訳」という営みです。
実は、このような「翻訳」は、ビジネスの世界、特に経営の手法や理念が国境を越えて広まる過程でも、より複雑でダイナミックな形で起きています。ある国で成功した生産方式や人事制度は、別の国に導入される時、設計図通りにはいきません。受け入れ先の社会の歴史、文化、政治的な思惑の中で、その意味合いを変え、新しいものとして生まれ変わることさえあります。
本コラムでは、「翻訳」というレンズを通して、経営のアイデアが世界を旅する物語を紐解きます。それは効率性の追求にとどまらず、異文化をどう理解し、受け入れるかという問いにつながります。一見、普遍的に見える経営の原理が、国境を越えることでいかに多様な姿を見せるのか。そのプロセスを追いかけてみたいと思います。
日本の経営実践は異質さを強調する形で米国へと翻訳された
1970年代から1990年代にかけ、アメリカ産業界は日本の経済成長の秘密を学ぼうと躍起になっていました。品質管理サークルやジャストインタイムといった日本の組織運営の実践が次々と紹介されましたが、その過程は単純な模倣ではありませんでした。そこには、アメリカという受け手にとって未知のアイデアを理解させるための「翻訳」のプロセスが存在していました。
この動きを分析したある調査は、「翻訳エコシステム」という枠組みを提示しています[1]。これは、翻訳者、翻訳されるアイデア、翻訳プロセス自体が、相互に結びつきながら発展していく生態系のようなシステムを指す考え方です。この生態系の中で、多様な翻訳者たちが日本の経営をアメリカの文脈に接続しようと試みました。
翻訳の初期段階では、「人」のマネジメントに焦点が当てられました。その翻訳には二つの流れがありました。一つは「直接翻訳」です。当時アメリカに進出したYKKなどの工場がその舞台となり、日本人駐在員が現場でアメリカ人従業員と共に働くことで、実践が「物質化された翻訳」として機能しました。これらの工場は、アメリカの経営者や研究者にとって生きた教材となりました。
もう一つは、書籍などを通じた「間接翻訳」です。『セオリーZ』などのベストセラーがその代表で、日本の経営をアメリカの組織行動論の言葉で語り直しました。その際、翻訳者たちは二つの対照的な手法を駆使します。
一つは「異質化」で、日本の文化や歴史的背景を強調し、その独自性を際立たせました。しかし、それだけでは「自分たちとは違う世界の話だ」と敬遠されかねません。そこで、もう一つの「同質化」が用いられました。IBMなど、日本と似た実践を行う優れたアメリカ企業を例に挙げ、「日本だけの特別な話ではない」と心理的な垣根を下げたのです。このバランス感覚が翻訳の鍵でした。
この時期の転換点となったのは、1980年に放映された『If Japan can, why can’t we?』というテレビ番組です。日本の生産性の高さの源流に、アメリカ人の品質管理専門家デミングの教えがあると指摘したのです。この事実は多くの経営者に衝撃をあたえ、関心の対象を「人」のマネジメントから、より具体的な品質管理や生産管理の手法へとシフトさせました。
1980年代以降、翻訳の対象は生産管理やイノベーションへと広がり、翻訳エコシステムは拡大・複雑化します。ホンダやトヨタが次々とアメリカに工場を建設し、親会社の生産方式を忠実に再現しようとしました。特にトヨタとGMの合弁事業NUMMIは、労働組合の強い古い工場で日本の生産方式を成功させ、懐疑論を覆す象徴となりました。工場ではカイゼンやカンバンといった日本語がそのまま使われ、日本のモデルであることが意図的に示されました。
この時期の間接翻訳で大きな役割を果たしたのが、『The Machine that Changed the World』です。この本は、トヨタ生産方式を「リーン生産方式」という新しい言葉で再定義し、包括的なモデルとして提示しました。「リーン(贅肉のない)」というアメリカの聴衆に響きやすい言葉(同質化)と、模範としてのトヨタの提示(異質化)の絶妙なバランスが、その普及を後押ししました。
このように、日本の経営実践がアメリカに渡る過程は、多様な翻訳者たちが直接的な提示と間接的な再定義を相互作用させながら、一つの大きな生態系を築き上げたプロセスでした。それは異質なものをテコにして理解を促し、自分たちの文脈に引き寄せていく、したたかで創造的な営みだったのです。
日本の仕事様式は、英国の文脈で翻訳され変容する
経営モデルの翻訳は、個々の企業の現場という、よりミクロなレベルではどのような姿で現れるのでしょうか。日本の「カイゼン」に代表される仕事の様式が、異なる文化を持つ英国の工場に持ち込まれた時、どのように受け止められ、変容していくのか。この問いを、日本の多国籍企業の英国拠点での比較調査が解き明かしています[2]。この調査は、組織が外部の慣行を単純に模倣するのではなく、自らの文脈で能動的に「翻訳」するという視点から、その複雑な実態を浮き彫りにします。
調査の前提となるのは、日本と英国の対照的なビジネスシステムです。日本は集団主義や労使協調を基盤とする「高度に協調的」な一方、英国は個人主義や歴史的な労使対立を背景に持つ「区画化された」システムとされます。この隔たりが大きい両国間で、日本のワークシステムがどのように移植され、作り変えられるかが焦点です。
比較されたのは、日系企業が買収した元英国工場、日系企業が新設した工場、英国のローバーとホンダの技術提携の三事例です。研究者たちは、長期間のインタビューや現場観察を通して、翻訳のリアルな姿を捉えました。
分析の結果、日本のワークシステムの定着度合いは三事例で異なりました。買収工場での抵抗が最も大きく、新設工場や技術提携では比較的受け入れが進んでいましたが、それでも日本のやり方がそのまま導入されたわけではなく、英国の文脈に合わせた「翻訳」が起きていました。
初めに、組織構造の改革といった「技術」の側面です。三事例とも階層削減やチーム制導入を試みました。しかし、新設工場ではチームリーダーが単なる管理職と見なされ、日本のような柔軟な役割分担には至りませんでした。買収工場では、従業員のスキル不足などもあってチームワークは形骸化しました。
品質サークル活動やチーム精神といった「哲学」の浸透は、より困難を伴いました。買収工場では研修が不十分で、改善活動は根付きませんでした。新設工場でも、経営陣への不信感から品質サークルは「冗談だ」と見なされていました。最も「哲学」の翻訳が進んだのはローバーとホンダの提携で、ローバーの技術者はホンダの徹底した問題解決会議を評価し導入しました。しかし、これも「翻訳」され、ホンダでは二日間かける会議が、ローバーではより短時間のものに変わりました。
三事例で差が生まれた原因は何だったのでしょうか。調査は三つの要因を指摘します。第一に、両者の橋渡しをする「境界連結者」の存在です。日本人駐在員などが現場に関与した新設工場や技術提携では、受容が進みました。第二に、研修予算といった利用可能なリソースの差です。第三に、送り手と受け手の間の相互作用のレベルでした。密な共同作業や、時には仕事後にパブでアイデアを練るような個人的な関係が、信頼を育み学習を促しました。
このことから見えてくるのは、ワークシステムの普及が、制度的な制約と、それを乗り越えようとする人々の能動的な営みとの相互作用によって形作られるプロセスだということです。組織は外部のアイデアに直面した時、それを一方的に受け入れたり拒絶したりするのではなく、自らの文脈を通して「編集」し、自分たちなりの形へと作り変えていきます。
経営モデルの国際的普及は、受入国の政治力学で翻訳される
経営のアイデアが国境を越える際、その「翻訳」のプロセスに、国家レベルの政治が関与することがあります。ある経営モデルが特定の国で特定の形で受け入れられる背後には、国家、労働組合、経営者といったアクターたちの政治的な力学が働いていることがあります。このダイナミズムを、1950年代のイスラエルにおける二つのアメリカ発の経営モデルの導入過程を分析した歴史的な調査が明らかにしています[3]。
調査の舞台は建国直後のイスラエルです。当時、経営や生産性といったテーマは、ただの経済問題ではなく、国家建設という大きな目標と直結した政治的な議論の対象でした。この特殊な状況が、経営モデル導入の裏にある政治的利害関係を、私たちにはっきりと見せてくれます。
分析対象は、「科学的管理法」と「人間関係論」という、思想的に対立するとされる二つの経営モデルです。前者は科学的分析による効率化を、後者は労働者の感情への配慮による生産性向上を目指します。イスラエルでは、この二つのモデルが、国家、強力な全国労働組合「ヒスタドルート」、民間経営者という三者の政治的駆け引きの中で、それぞれ独特の形に「翻訳」されていきました。
科学的管理法の導入は国家主導で行われました。その目的は、生産性向上に留まらず、国家が民間企業への監督を強め、主権を確立するという大きな政治的目標のためでした。国家は、科学的管理法を「科学的で非政治的」な手法として提示することで、自らの介入の正当性を主張しようとしました。この翻訳の過程で、モデルが結びつけられる「大きな物語」も変化します。アメリカで「近代性」の象徴とされたのに対し、イスラエルでは「ナショナリズム」と「国家建設」という物語に接続され、その実践は愛国的な行為とさえ見なされました。
実践レベルでの翻訳も起きました。個人の成果に応じた「出来高払い制」は、労働者の連帯を重んじる労働組合の力を削ぐため、そのまま導入されませんでした。代わりに、工場全体の生産性向上に基づいて全労働者に一律で支払われる集団的なボーナス制度が考案され、その決定には労働組合が関与しました。労働組合の権力は、この翻訳によって維持されたのです。
続いて、人間関係論です。このモデルの導入を主導したのが労働組合自身だったという事実は驚きかもしれません。自ら巨大企業群を経営していたヒスタドルートは、「労働組合による経営は矛盾」という外部からの批判をかわすため、人間関係論を導入。「我々は労働者の福祉に配慮する合理的な経営を行っている」と主張し、自らの正当性を高めようとしたのです。
ここでもモデルの意味は翻訳されました。アメリカで「労使間の連帯」を強調したのに対し、イスラエルでは「労働者階級内の連帯」や「国民的連帯」を促進するモデルとして解釈されました。実践レベルでは、本来、組合の力を弱めるはずの福利厚生業務などが、引き続き組合の支部によって行われ、組合の影響力は維持されました。一方で、個人を対象とする心理検査などは、集団主義的なイデオロギーにそぐわないため、ほとんど採用されませんでした。
この二つの事例が示すのは、思想的に対立するはずの二つの経営モデルが、イスラエルの政治的文脈の中で、国家と労働組合の権力を維持・強化するという類似したパターンで翻訳された事実です。経営モデルの普及は、純粋な知識の移転ではなく、高度に政治的なプロセスであり得ます。
多国籍企業の子会社では、言語間翻訳が政治的管理ツールになる
国家という大きな舞台だけでなく、翻訳をめぐる政治は、多国籍企業の子会社という場面でも起きています。本社から送られてくる企業理念の文書を現地の言葉に置き換える作業。その言葉一つひとつを選ぶプロセスが、子会社の経営陣にとって、組織を自分たちの意図する方向へ動かすための政治的管理ツールとなり得ます。このミクロな権力の実践を、ある米系製薬企業のポーランド子会社で行われた、企業バリュー文書の翻訳プロセスを追跡した分析が描き出しています[4]。
この分析は、翻訳を単なる意味の伝達ではなく、「受け手に特定の反応を引き出すことを意図した、意味の作成・移送行為」と捉えます。この視点に立つと、本社からの方針伝達は一方通行ではなくなり、子会社側で行われる翻訳が、本社の意図を子会社の利害に沿うように「編集」する場となります。
調査の舞台となったポーランドの子会社では、経営会議で企業バリュー文書の英語からポーランド語への翻訳が行われました。研究者はその会議を観察・記録し、翻訳の背後にある力学を解き明かしました。分析から浮かび上がってきたのは、翻訳が四つの連動するプロセスを通じて、ミクロな政治の場となっていく様子です。
第一は「目的づけ」です。翻訳の目的を「本社の理念を忠実に伝えること」ではなく、「子会社の業績を改善するための管理ツール」として位置づけ直しました。第二は「枠付け直し」です。原文の意味を、その目的に沿うように組み替えます。例えば、本社が掲げた「enduring(持続する)」という価値は、「長期目標の達成に向けた粘り強さ」という、より業績達成を意識した言葉へと転換されました。
第三は「受容化」です。翻訳された言葉が、従業員に伝わり響くように調整する作業です。従業員の抵抗を先回りして、誤解を招きかねない言葉を避けたり、ポーランドの歴史的・文化的な文脈で反発を招くような表現を回避したりしました。第四が「規範の書き込み」です。翻訳テキストの中に、会社が従業員に期待する具体的な行動のガイドラインを刻み込みます。抽象的な価値を具体的な行動に結びつけ、従業員を方向づける「脚本(スクリプト)」として作り上げたのです。
これら四つのプロセスを通じて、言語の翻訳という行為は、編集作業を超え、組織内の権力関係を反映し、従業員の行動を管理するための政治的な実践となります。この事例が示唆するのは、多国籍企業の本社が発信する理念は、子会社にそのまま届くとは限らないということです。子会社の経営陣による「翻訳」のプロセスが、組織の現実を形作る上で決定的な意味を持つのです。
脚注
[1] Westney, D. E., and Piekkari, R. (2020). Reversing the Translation Flow: Moving Organizational Practices from Japan to the U.S. Journal of Management Studies, 57(1), 57-86.
[2] Saka, A. (2004). The cross-national diffusion of work systems: Translation of Japanese operations in the UK. Organization Studies, 25(2), 209-228.
[3] Frenkel, M. (2005). The politics of translation: How state-level political relations affect the cross-national travel of management ideas. Organization, 12(2), 275-301.
[4] Ciuk, S., James, P., and Sliwa, M. (2019). Micropolitical dynamics of interlingual translation processes in an MNC subsidiary. British Journal of Management, 30(4), 926-942.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






