2026年2月12日
監視は協力を妨げるか:管理と信頼のジレンマ
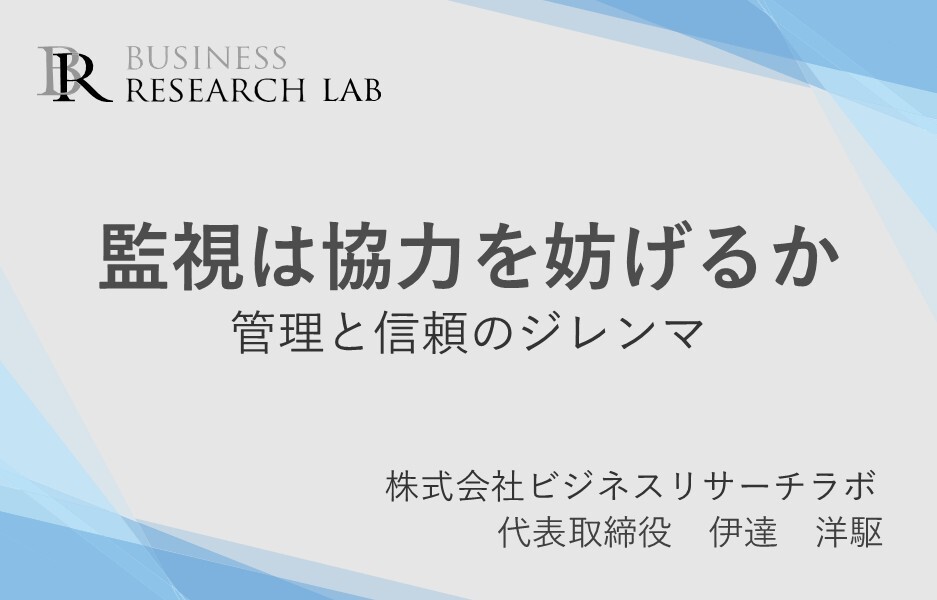
私たちの働き方は、近年その姿を変えつつあります。同じオフィスに毎日顔を合わせるというスタイルはもはや唯一の選択肢ではありません。物理的に離れた同僚とデジタルツールでプロジェクトを進めたり、社内外から多様な専門性を持つメンバーが一時的に集結したりする働き方が出てきています。
このような環境の変化の中で、以前にも増してその価値が語られるようになった概念が、チームにおける「信頼」です。メンバー同士が互いを信じ、安心して業務に取り組める状態は、円滑な協力関係を築き、チーム全体のパフォーマンスを高める上での基盤です。
しかし、この「信頼」という言葉は、私たちが素朴に思い描くほど単純なものではありません。それは、チームが置かれた状況や環境によって繊細にその性質を変容させます。例えば、チームの連携を促すための管理ルールが、意図せずしてメンバー間の疑心暗鬼を招いてしまう。あるいは、多様な知見を求めて集まった専門家チームの中で、互いの能力を認め合っているにもかかわらず、本質的な議論がかみ合わなくなってしまう。
本コラムでは、「信頼」が、チームを取り巻く様々な条件―管理の仕方、メンバーの構成、活動期間の長さ―によって、いかに複雑な様相を呈するのかを探求していきます。具体的な調査や実験の知見を紐解きながら、チームにおける信頼の光と影を浮き彫りにします。
ルールによる管理は、監視を強め信頼を損なう
チームで仕事を進める上で、何らかのルールを設けることはごく一般的です。特に、メンバーが地理的に分散した「仮想チーム」においては、その必要性が一層高まるように思われます。誰がいつまでに何をするのか、進捗はどうなっているのか。これらを明確にするための定期報告や計画の共有は、プロジェクトを円滑に進めるための合理的な管理手法だと考えられています。こうした、ルールや手順で個人の行動を方向づけようとするアプローチは「行動コントロール」と呼ばれます。しかし、この管理手法が、実はチーム内の信頼関係を蝕んでいく可能性はないでしょうか。
この問いを検証するため、ある実験が行われました[1]。対象は、複数の大学に在籍する学生で構成された51の仮想チームです。各チームは、インターネット関連の新規事業計画を策定するという共通のプロジェクトに、デジタルツールのみを用いて取り組みました。
実験では、チームが二つのグループに分けられました。一つの「行動コントロール群」は、週に一度、計画や担当者、進捗を記した詳細な報告書を提出することが義務付けられました。もう一つの「自己管理群」にはそのような義務はなく、プロジェクトを自由に進めることが許されました。実験の開始前と終了後に、各チームメンバーが互いに抱く信頼の度合いを測定し、その変化が比較されました。
プロジェクト終了後、両グループの信頼度には違いが表れました。自己管理群では信頼レベルに大きな変化はなかったのに対し、週次報告を義務付けられていた行動コントロール群では、信頼度が低下していたのです。秩序を保つはずのルールが、かえって信頼を損なうという結果になりました。
なぜ、このような事態が生じたのでしょうか。その手がかりは、各チームのコミュニケーション記録の分析から見えてきました。信頼が大きく低下したチームでは、二種類の出来事が頻繁に発生していました。一つは、メンバーが義務を認識しながら意図的に果たさない「背信」です。例えば、締め切り間際に一人のメンバーが完全に連絡を絶ってしまうといった行為がこれにあたります。
もう一つは、義務に対する認識がメンバー間で異なる「不一致」です。意図的な裏切りではないものの、他者の期待を裏切る行動となります。あるメンバーが報告書作成に協力的でないと感じ不満を表明したケースで、記録を見ると、他のメンバーはアイデアの議論に注力していた、というような認識の齟齬がこれにあたります。
これらの「背信」や「不一致」は信頼を揺るがします。行動コントロール、すなわち週次報告の義務が、これらの出来事をより深刻な問題へと発展させる触媒として機能していました。
行動コントロールは、二つのメカニズムを通じて信頼低下を助長します。第一に、メンバー間の「監視」を強めます。締め切りが設定されると、メンバーはお互いの進捗状況や貢献度を以前よりも注意深く見るようになります。第二に、義務の「顕著性」を高めます。報告書を作成する過程で、誰が何を担当するのかが文書化され、全員の共通認識となります。これにより、もし誰かが義務を果たせなかった場合、その事実が非常に際立って見えるようになります。
要するに、行動コントロールという仕組みは、チーム内に「締め切り」と「明確な責任分担」という構造を作り出します。この構造は、同時にメンバー同士が互いを評価し、監視し合う状況を生みます。その結果、「背信」や「不一致」といった、どのチームにも起こりうる小さなつまずきが、この強化された監視の網にかかりやすくなり、より重大な問題として認識されてしまいます。自己管理群のチームでも同様の出来事は起こり得たはずですが、そこでは監視の目も緩やかで、義務の輪郭も曖昧だったため、大きな問題に発展しにくかったと考えられます。
この研究から浮かび上がるのは、チームを管理しようとする合理的な試みが、意図せずして信頼というデリケートな関係性を損なう皮肉な構図です。仮想チームというコミュニケーションに困難を伴う環境において、秩序維持のためのルールが、かえってメンバー間の心理的な距離を広げ、不信感の温床となり得ます。
異分野チームでは信頼が建設的論争につながりにくい
先ほどは、チームの管理手法が意図せずして信頼関係に影を落とす様相を見てきました。視点を変え、チームの内部、すなわち「どのようなメンバーで構成されているか」という点が、信頼の働き方にどう変化をもたらすのかを考えてみましょう。特に、異なる専門分野を持つ人々が協働する「異分野チーム」では、信頼はどのように機能するのでしょうか。
この点を明らかにするため、看護教育の現場を舞台としたある調査が行われました[2]。対象は、卒業研究に相当する科目に参加した学生たちで、看護学生だけで構成された「非学際チーム」と、看護学生とデザイン専攻の学生が協働する「学際チーム」が比較されました。
このような短期間で初対面のメンバーが集まるチームでは、「スウィフト・トラスト(迅速な信頼)」と呼ばれる、相手の役割や専門性から能力を素早く信じることから始まる信頼が形成されやすいとされます。この信頼は、相手の能力や専門性への確信である「認知的信頼」と、相手への配慮や好意といった感情的な結びつきである「情緒的信頼」の二つの側面から成り立っています。
調査では、この迅速な信頼がどのようなチーム内行動に結びつくのかが調べられました。対象とされたのは、「建設的論争」(意見の違いを創造的な議論につなげること)、「援助行動」(困っているメンバーを助けること)、「自発的コミュニケーション」(必要な情報交換を積極的に行うこと)の三つです。
分析の結果、全体に共通する関係性として、「認知的信頼」、つまり相手の能力への信頼が、これら三つの協調行動すべてを促進することが見出されました。チームメンバーが互いの専門性を信頼しているほど、活発な議論が生まれ、助け合い、円滑なコミュニケーションが行われるという関係です。
しかし、チームの構成(学際か、非学際か)がこの関係性にどう作用するかを調べると、興味深いパターンが浮かび上がりました。認知的信頼が「援助行動」や「自発的コミュニケーション」につながる強さは、学際チームと非学際チームの間で大きな違いはありませんでした。専門分野が異なっていても、相手の能力を信じていれば、情報の交換や助け合いは同じように行われるのです。
ところが、「建設的論争」においてだけ違いが現れました。非学際チームでは、認知的信頼の高さが、そのまま活発な建設的論争へとスムーズに結びついていました。しかし、学際チームではその結びつきが弱まっていました。同じように高いレベルで相手の能力を信頼していても、異分野のチームではそれが健全な意見対立に発展しにくいという結果でした。
なぜ、援助や情報交換は分野の壁を越えられるのに、建設的論争は阻まれてしまうのでしょう。その背景には、異分野チームが抱える構造的な課題があります。異なる専門分野の出身者は、それぞれが依拠する知識体系、物事を評価する際の基準、日常的に使う言葉の定義までもが異なります。
根底にある「常識」が異なるため、たとえ互いの能力を尊敬し信頼していても、一つの論点を深く掘り下げて議論を戦わせることが困難になります。援助行動や自発的なコミュニケーションは、比較的表面的なやり取りでも成立しますが、建設的論争は互いの主張の前提や論理構造を深く理解し、的確な批判や代替案を提示する高度な知的作業です。そこでは、専門用語を翻訳し、異なる評価基準をすり合わせるという、追加的な「翻訳コスト」が発生します。
学際チームでは、この翻訳コストの壁が、認知的信頼が建設的論争へと転化するのを妨げていると考えられます。信頼はあっても、議論がかみ合わない。その状況が意見の対立を避けることにつながり、多様な視点がぶつかり合うことで生まれるはずの創造的な解決策に至る道を閉ざしてしまうのかもしれません。
短期の信頼は情報共有を促すが、資源支援は別
これまで、チームの管理方法やメンバー構成の側面から、信頼の複雑な性質を探ってきました。ここでは別の角度から、特に、災害支援の現場のように、初対面の多様な組織がごく短期間だけ協力し合う極限的な状況で、信頼がどのように生まれ、どこまでの機能を果たし得るのかを見ていきましょう。
突発事態に対応するために急ごしらえで形成される協力ネットワークでは、長期的な関係構築の猶予がありません。そこでは、相手の所属組織の評判や専門性などを手がかりに、素早く信頼関係を築く「スウィフト・トラスト(迅速な信頼)」が機能します。
この短期的な信頼が人道支援の現場でどう機能しているかを検証した調査があります[3]。東南アジアで人道ロジスティクスの研修に参加した、様々な組織に所属する実務家を対象に調査が行われました。調査の目的は、何が迅速な信頼を生み、それがどのような協力行動を促し、活動の有効性にどう結びつくのかを明らかにすることでした。
「信頼の源泉」については、四つの要因が信頼形成を後押しすることがわかりました。「第三者からの情報」(紹介や評判)、「手続きや規程の類似性」(共通のルール)、「組織の価値観の類似性」、「能力の知覚」(高い専門性や経験)です。災害現場という混乱した状況では、こうした客観的な手がかりが相手を信じるための足がかりとなります。一方で、「宗教の類似性」は関連が見られず、専門家としての職業的規範が優先されることがうかがえました。
「信頼がもたらすもの」に目を向けます。調査では、協力行動を二つのレベルに分けました。一つは「情報共有」という比較的負担の少ない協力、もう一つは人的・物的サポートを提供する「資源支援」という、より負担の大きい協力です。分析の結果、迅速な信頼は「情報共有」のレベルを有意に高めることが確認されました。しかし、「資源支援」に対しては、迅速な信頼からの直接的な結びつきは認められませんでした。
最後に「協力行動の成果」です。情報共有と資源支援は、いずれもネットワーク全体の「協調の有効性」、すなわち、現場が円滑に回っている度合いを有意に高めることがわかりました。協力行動が活発であるほど、支援活動全体がうまくいくということです。
これらの結果を総合すると、人道支援という短期決戦の現場における信頼の役割と限界が浮かび上がります。迅速な信頼は、初対面の組織間の協力を始動させるものであり、特に情報共有のような低コストの協力を進める上で不可欠です。しかし、その効力は万能ではありません。高コストの協力を促すには、短期的な信頼だけでは不十分です。
この調査は、信頼の「効力の範囲」を弁別して考えることの重要性を教えてくれます。緊急性の高い短期的なチームにおいて、信頼がどこまでをカバーでき、どこから先は別の支えが必要になるのか。その境界線を見極めることが、効果的な協力関係を設計する上で有用です。
脚注
[1] Piccoli, G., and Ives, B. (2003). Trust and the unintended effects of behavior control in virtual teams. MIS Quarterly, 27(3), 365-395.
[2] Liu, H.-Y. (2021). The relationship between swift trust and interaction behaviors on interdisciplinary and non-interdisciplinary teams in nursing education. Nurse Education in Practice, 51, 102977.
[3] Lu, Q., Goh, M., and De Souza, R. (2018). An empirical investigation of swift trust in humanitarian logistics operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 8(1), 70-86.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






