2026年2月10日
場所がくれる自己肯定感:消費と観光の心理を紐解く
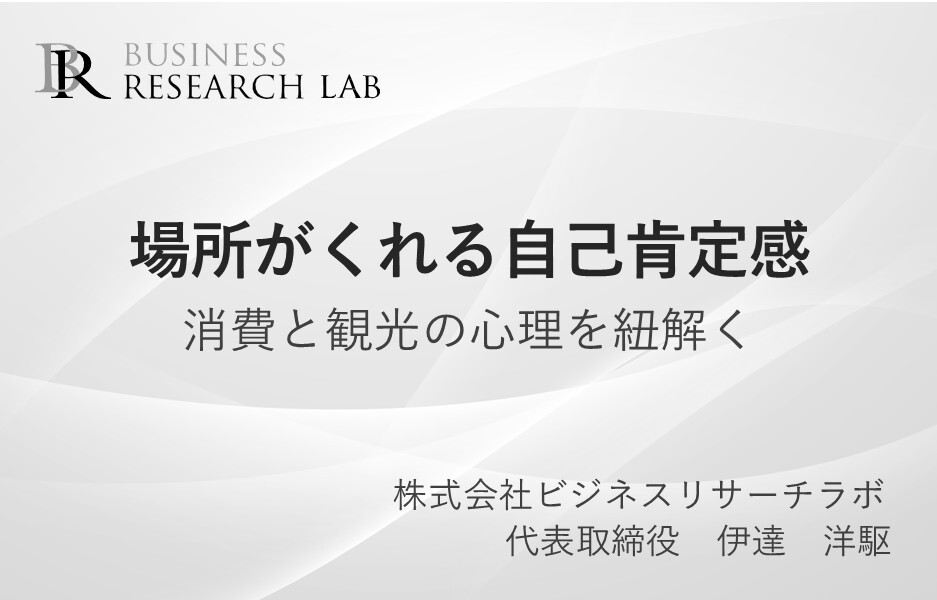
ふと立ち寄ったお店で居心地の良さを感じたり、旅先の風景に故郷のような一体感を抱いたりした経験はないでしょうか。私たちは日々、様々な「場所」と関わっています。その関わりは、物理的な移動だけでなく、私たちの心や「自分は何者か」という自己認識、すなわちアイデンティティと結びついています。
本コラムでは、「場所のアイデンティティ」という視点を通して、私たちの消費行動や観光体験を眺めていきます。ある研究によれば、私たちが店内で無意識に探しているのは、商品だけでなく「歓迎されている」という感覚かもしれません。別の研究は、観光客が再びその地を訪れたいと思う気持ちの裏には、旅の満足度が隠されていると語ります。住民が観光をどう受け入れるかも、その土地への誇りが関わっているようです。
私たちの場所への思いは固定的ではなく、状況に応じて変化するしなやかさも持っています。場所と自己との対話が私たちの行動にどう現れるのかを探っていきましょう。
店の雰囲気から、自分が歓迎される場所なのかを判断する
私たちは買い物をするとき、商品の価格や品質だけでなく、店の「雰囲気」を無意識に感じ取っています。雰囲気とは内装や照明だけでなく、店内の他の客や従業員の様子、交わされる言葉、向けられる視線といった社会的な手がかりも含まれます。それらの情報から「ここは自分がいて良い場所か」「自分は歓迎されているか」を瞬時に判断しているのかもしれません。このような、自己認識と場所との一致感は「場所のアイデンティティ」と呼ばれ、消費者の行動を理解する上でひとつの視点を提供します。
この点について、ある定性的な調査が行われました[1]。特定の民族的背景を持つ消費者20人に対して、商業施設での体験に関するインタビューが実施されたのです。この調査からは、人々が場所のアイデンティティを評価する際に用いる、三つの共通した観点が見えてきました。
一つ目は、「場所への同類化」です。店内にいる従業員や他の顧客が、自分と同じような背景を持つかを評価することです。例えば、ある同性愛者の男性は、自分と客層が異なると感じるスポーツバーなどを居心地悪く感じ、避けると言います。自分と似た人々がいる空間には安心感を覚え、そうでない空間は避けるという心の動きがうかがえます。
二つ目は、「言語的な否定性」です。従業員や他の顧客から、否定的な言葉を直接投げかけられた経験です。ある白人男性は、ワイキキの高級店で高価な腕時計を見たいと頼んだところ、「それはとても高価で、あなたには買えませんよ」と言われた経験を話してくれました。このような言葉は、購買意欲を削ぐだけでなく、その場所への拒絶感を強く生み出します。
三つ目は、「非言語的な手がかり」です。言葉にはならないものの、視線や態度で伝えられるメッセージです。あるトランスジェンダーの女性は、百貨店で保守的な身なりの男性から疑いのまなざしを向けられたと語りました。監視するような視線やあからさまな無視は、言葉以上に雄弁に「あなたはこの場所にふさわしくない」と伝え、人を深く傷つけます。
これらのテーマをより広い範囲で検証するため、ヒスパニック系と同性愛者の消費者、各100人を対象に、お気に入りのレストランについて評価を求める定量的な調査も行われました。
分析の結果、その店を再び利用したい、あるいは他人に勧めたいという「ロイヤルティ」や「口コミ」の意向に強く結びついていたのは、否定的な言語的・非言語的な手がかりが「ない」ことでした。料理やサービスの質も関連していましたが、それ以上に、不快な言葉や視線を向けられないという心理的安全性がリピート利用の鍵を握っていたのです。
また、店に不満があった場合に外部へ申し立てたり、他社へ乗り換えたりといった行動を抑制する要因は、「場所への同類化」、すなわち他の顧客や従業員に自分と同じ背景の人がいるという認識でした。この感覚は、多少の不満があってもその場所との関係を維持する動機につながります。また、店の価格が上がっても顧客として留まるかという「価格耐性」にも関わっていました。
この一連の調査は、消費者が店を選ぶ際、商品やサービスだけでなく、そこで得られる「自己の肯定感」や「所属感」を無意識に求めていることを物語っています。店という空間は、人がアイデンティティを再確認し、社会的なつながりを感じる舞台でもあるのかもしれません。
観光客の忠誠心は、場所への一体感が満足度を経て育まれる
店舗のような小さな空間で感じる所属感は、より大きなスケールである観光地においても、私たちの心に作用するのでしょうか。先ほどは、消費者がその場の人々との同類性や歓迎されている感覚をいかに見出しているかを見てきました。この感覚は、旅行者が訪れた土地に対して抱く「一体感」と通じます。その一体感が再びその場所を訪れたいという「忠誠心」にどう結びつくのかは、観光地にとって大きな関心事です。
この問いを探るため、中国特有の「レッドツーリズム」を対象とした調査が行われました[2]。レッドツーリズムとは、中国共産党の歴史に関連する史跡などを巡る旅行形態で、愛国心教育や地域振興といった目的を持っています。しかし、多くの観光地では、再訪率の低さが課題でした。
調査は、レッドツーリズムの象徴的な都市である遵義市を訪れた観光客371人を対象に、アンケート形式で実施されました。分析の焦点は、「観光の動機」「場所への一体感」「満足度」「忠誠心」という四つの要素の関わりを解明することでした。
分析から得られた結果は、忠誠心が生まれるまでの道のりが単純ではないことを示していました。「紅色文化を体験したい」という観光動機が、直接的に忠誠心を生むことはありませんでした。同様に、観光客がその場所の歴史や文化に抱く「一体感」も、それ単体では再訪意欲には結びつきませんでした。歴史的な場所を訪れ、心を動かされたとしても、それだけでは「また来たい」という気持ちには必ずしもならないことが分かってきました。
何が忠誠心を生み出すのでしょうか。分析の結果、観光客の「満足度」が、忠誠心と強い直接的な結びつきを持つことが判明しました。旅行という体験全体を「良かった」と肯定的に評価することが、再訪や推薦といった行動に直結する大きな要因だったのです。
動機や一体感は、忠誠心に間接的な形で関わっていました。一つは、「動機」が「満足度」を高め、その満足度が「忠誠心」につながる経路です。旅行の目的が満たされる質の高い体験が提供されれば、満足度が高まり、結果として忠誠心が育まれます。
もう一つの経路は、より多段階的でした。「動機」はまず「場所への一体感」を高め、その一体感が次に「満足度」を向上させ、最終的に「忠誠心」へと結実するというものです。例えば、紅色文化を学びたいという動機で訪れた観光客が、展示を通じて歴史に共感し一体感を覚える。その一体感が旅行全体の体験価値を高め、満足につながる。その高い満足感が再訪意欲を芽生えさせる、という複雑な心のプロセスが浮かび上がります。
この調査から分かるのは、たとえ特殊な目的を持つ観光であっても、人々の心を動かし、再び足を向かわせるためには、最終的に「満足のいく体験」が不可欠だということです。場所への一体感や共感は、それ自体がゴールではなく、素晴らしい体験を通じて満足へと昇華されることで、持続的な関係性、すなわち忠誠心へと発展していくのです。
観光への態度は、場所が与える誇りと自信に左右される
観光客が旅先で得る満足感は、その場所への忠誠心を育む上で欠かせません。しかし、観光は訪れる側と受け入れる側の相互作用で成り立っています。観光客が良い体験をするには、地域住民の友好的な態度が大きな意味を持ちます。受け入れる住民は、自分たちの土地が観光地となることをどう捉えているのでしょうか。住民の観光に対する態度は、何によって形作られるのでしょう。
この問題を考える上で、伝統的には、住民が経済的利益とコストを天秤にかけるという「社会交換理論」が用いられてきました。しかし、人の心は損得勘定だけで動くものではありません。そこで、住民がその土地に抱くアイデンティティ、すなわち「場所アイデンティティ」という観点から、この問題を捉え直す試みが行われました[3]。
この研究では、場所アイデンティティが四つの原則から成り立つと考えられています。すなわち、場所の「独自性」(ユニークさ)、「継続性」(自分の人生とのつながり)、「自尊心」(場所への誇り)、「自己効力感」(コミュニティへの自信)です。
調査は、アメリカ中西部の都市インディアナポリスの住民464人を対象に行われました。住民に、これら四つの原則や、観光がもたらす事柄への認識、観光を支持するかどうかを尋ねました。
分析の結果、住民の観光に対する態度と深く関連していたのは、「自尊心」と「自己効力感」の二つでした。その場所に誇りを持ち、コミュニティの能力に自信を持っている住民ほど、観光の肯定的な側面を高く評価し、否定的な側面を低く評価する傾向が見られたのです。一方で、場所の「独自性」や「継続性」は、観光への態度と直接的な結びつきを持ちませんでした。
この結果は、住民が観光を受け入れるかどうかは、土地の客観的な魅力や歴史よりも、住民が抱く主観的な誇りや自信に左右されることを物語っています。自分たちの街は素晴らしいという自尊心や、観光客が増えても対処できるという自己効力感が、観光を「脅威」ではなく「機会」として捉える心理的な基盤となるのです。
さらに分析を進めると、「自尊心」と「自己効力感」は、観光への認識(肯定的か、否定的か)を形成し、その認識を介して、最終的に観光支持の態度につながるという間接的な構造が明らかになりました。誇りや自信が、観光という現象の光と影のどちらをより強く見るかを方向づけ、その結果として賛成や反対の態度が生まれるわけです。
また、その土地での居住期間が10年以下の住民は、10年を超える住民に比べて、場所への自尊心や自己効力感が低いことも分かりました。居住期間が長くなるにつれて、場所への誇りや自信が育まれていく過程がうかがえます。この研究は、地域の観光政策を考える上で、住民の自尊心や自己効力感を育むことの重要性を示唆しています。
場所の規模を意識させると、そこへの愛着や一体感が強まる
これまで見てきたように、人は特定の場所に対して、ある程度安定した感情や認識を持っています。しかし、私たちが抱く場所へのアイデンティティや愛着は常に一定なのでしょうか。それとも、置かれた状況によって変化する、もっと流動的なものなのでしょうか。
この問いを探るため、人のアイデンティティは状況に応じて活性化するという考え方に基づいた実験が行われました[4]。特定の場所のスケール、例えば「近隣」「都市」「国」を意識させると、その場所への思いが強まるのではないかという仮説が立てられたのです。
実験には、ポルトガルのリスボンに住む178人の大学生が参加しました。参加者は、長年リスボンに住む「永住者」と、学期中だけ住む「一時的滞在者」に分けられました。アンケートの導入部分で「近隣」「都市」「国」のいずれかの単語をさりげなく強調し、特定の場所のスケールを意識させる操作を行いました。その後、参加者は三つのスケールすべてについて、場所へのアイデンティティ(自己認識の一部という感覚)と場所への愛着(感情的な絆)の強さを評価しました。
分析の結果、この操作は、「近隣」というスケールに対してのみ、はっきりとした変化をもたらしました。アンケートで「近隣」を強調された参加者は、そうでない参加者に比べて、自分たちの近隣へのより強いアイデンティティと愛着を報告したのです。
しかし、その現れ方は、永住者と一時的滞在者とで異なっていました。永住者の場合、予想通り「近隣」を意識させられると、近隣へのアイデンティティと愛着がともに強まりました。
一方、一時的滞在者には予期せぬ結果が見られました。「近隣」を意識させられたとき、彼らがより強く報告したのは、近隣への絆ではなく、なんと「国」に対するアイデンティティと愛着だったのです。研究者らは、一時的滞在者にとって近隣はつながりの薄い仮の住まいであるため、そこを意識させられたことで、かえってより安定的で意味のある「ポルトガル人である」という大きなスケールのアイデンティティに心の拠り所を求めたのではないかと考察しています。
弱いアイデンティティが刺激されると、人は無意識に、より強固な別のアイデンティティを活性化させるのかもしれません。
この研究は、私たちの場所への感覚がいかに文脈に依存し、柔軟に変化するかを描き出しています。私たちの心には、近隣の住民、都市の市民、国民といった複数の場所アイデンティティが存在し、どのアイデンティティが表に出るかは、その時々の状況によって決まるのです。場所との関係は、静的で固定されたものではなく、常に揺れ動き、再構築され続けるプロセスであると言えます。
脚注
[1] Rosenbaum, M. S., and Montoya, D. Y. (2007). Am I welcome here? Exploring how ethnic consumers assess their place identity. Journal of Business Research, 60(3), 206-214.
[2] Dai, Q., Peng, S., Guo, Z., Zhang, C., Dai, Y., Hao, W., Zheng, Y., and Xu, W. (2023). Place identity as a mediator between motivation and tourist loyalty in ‘red tourism’. PLOS ONE, 18(10), e0284574.
[3] Wang, S., and Chen, J. S. (2015). The influence of place identity on perceived tourism impacts. Annals of Tourism Research, 52, 16-28.
[4] Bernardo, F., and Palma-Oliveira, J. (2013). Place identity, place attachment and the scale of place: The impact of place salience. Psyecology, 4(2), 167-193.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






