2026年2月10日
空っぽではない場所:空間の政治性と私たちの身体
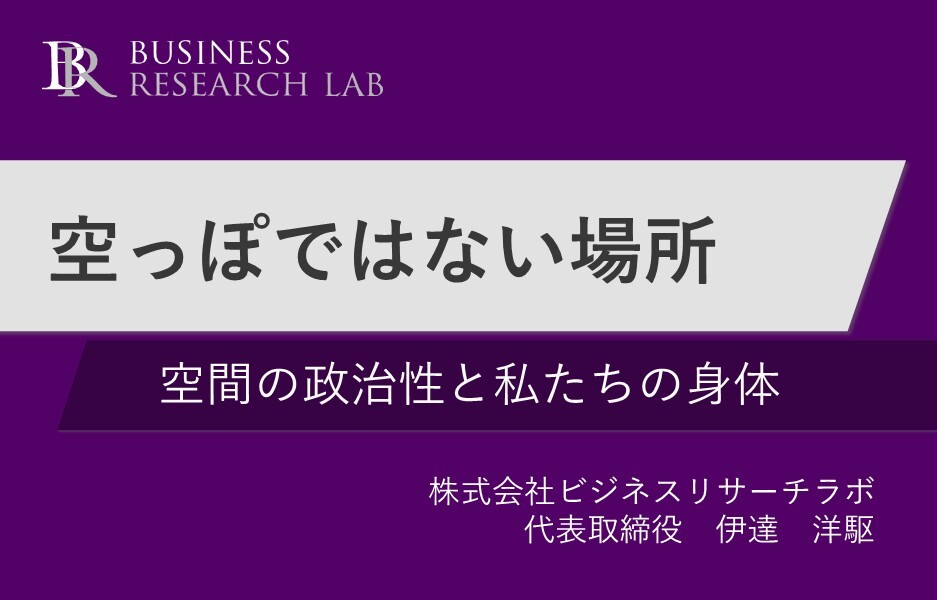
私たちが日々を過ごすオフィス、学校、公共の広場。これらの空間を、私たちは何気なく「そこにあるもの」として受け入れています。壁や窓、机の配置、廊下の幅。それらはただの機能的な設計の産物であり、私たちの行動とは無関係な背景に過ぎないのでしょうか。
しかし、その空間の作りは、私たちの人間関係や行動、さらには感情までも方向づけています。机の配置一つで、誰と誰が会話しやすくなるかが決まるかもしれません。建物のデザインが、私たちに特定の振る舞いを無意識のうちに促しているかもしれません。空間は、空っぽの容器ではありません。そこには、目には見えないルールや力関係、設計者の意図が織り込まれています。
本コラムでは、一見中立に見える「空間」が、いかに私たちの社会生活を形づくり、時には私たちを統制し、私たちがその空間といかに関わり、抵抗していくのか、その物語を紐解いていきます。
統制は空間と身体の実践で共に形づくられる
組織における人々の行動を管理する仕組みは、規則や命令といった言葉だけで成り立っているわけではありません。それは物理的な空間のあり方と、その中で人々がどのように身体を動かすかという実践とが結びついて形づくられます。社会的なルールと、建物や物といった物質的な環境は、互いに無関係に存在するのではなく、相互に作用し合いながら現実を創り上げています。
それは、川の流れと川岸の関係に似ています。川の流れが岸の形を削り取るように、社会のルールは物理的な空間を編成します。同時に、川岸の地形や地質が水の流れを規定するように、空間の作りが人々の行動や関係性を方向づけます。
ある電力会社が本社を新しい建物に移転した事例は、この関係性を描き出しています[1]。新社屋は、広大な吹き抜けを持つ開放的なオープンプランオフィスとして設計されました。設計の中心にあったのは、効率性や快適性だけではありませんでした。階段やコピー機、給湯室といった人々が必ず利用する設備を、意図的に「村の井戸」として戦略的に配置したのです。その狙いは、部署間の壁を取り払い、従業員同士が偶然出会い、言葉を交わす「計画された偶発性」を日常の中に制度として組み込むことでした。
この空間設計は、当時進められていた経営方針の転換とも密接に連携していました。会社は、従業員一人ひとりが自律的な主体として、積極的に人脈を築き、キャリアを形成していくことを期待していました。開放的で流動性の高いオフィス空間は、そうした新しい働き方を身体で体験させ、肯定的に内面化させるための装置として機能しました。実際、従業員への調査では、新しい環境への高い受容が報告されています。見通しの良い空間は、静かでプロフェッショナルな仕事の雰囲気を醸成しました。
従業員たちも、この新しい空間にただ順応しただけではありませんでした。広大な空間の中で、身振りや視線を使った独自のサインを編み出し、離れた場所にいる同僚と即座に連携を取り合いました。これは、設計者が意図した交流を、身体の実践を通じてさらに発展させたものです。また、社屋の一部が市場のリアルタイムな動きを映し出すトレーディング・フロアに改装されると、従業員は立ったまま仕事をするようになり、その身体は市場経済の速度と緊張感を直接的に体現することになりました。
しかし、この精緻に設計された秩序は、予期せぬ形で変化します。従業員数の急増によって、オフィスの収容能力が限界に達したのです。すると、各チームは書庫やキャビネットを「壁」のように使い、自発的に自分たちの領域を囲い込み始めました。当初の開放性は失われ、空間の雰囲気も変わっていきました。これは、経営への単純な抵抗ではありません。物理的な環境が変化したという条件のもとで、人々の身体と物が相互に作用し合い、新しい秩序が自ずと生まれてきた過程でした。
給湯室で順番待ちの列が長くなった際に見られた対応も象徴的でした。施設管理部門は、給湯器の電圧を上げて湯の出る速度を速めるという技術的な解決策を施しました。しかし、この小さな物質的な調整は、人々の休憩時間や会話のリズム、移動のパターンに変化をもたらし、組織全体の情報の流れや仕事のテンポにまで連鎖していきました。
この事例が示すのは、組織における統制が、設計者の意図や経営方針といった観念だけで実現するものではないという事実です。それは、設計された空間と、その中で活動する人々の身体、そこに置かれた物とが織りなす相互作用の中で、日々新たに生成され続けるプロセスです。
美的演出は統制装置だが現場が撹乱する
空間が人々の行動を方向づける力は、通路の設計や設備の配置といった機能的な側面だけにとどまりません。建物の美しさや使われている素材、空間全体が醸し出す「雰囲気」といった美的、感覚的な側面もまた、人々のアイデンティティや感情に働きかけ、見えない統制の装置として機能することがあります。しかし、人々はそのような空間のメッセージを一方的に受け取るだけの存在ではありません。ある省庁の新庁舎をめぐる出来事は、建築の美学が権力と抵抗の舞台となる様子を映し出しています[2]。
その庁舎は、世界的に高い評価を受ける美しい建築物でしたが、そこで働く職員たちからは反発を招きました。設計段階で意図されたのは、庁舎を国家の「ショーウィンドウ」として位置づけ、プロフェッショナリズムや近代性、「西洋的」な先進性を国内外に示すことでした。最新技術を駆使した透明なフェンス、ガラスや金属を多用した内外装、役職に応じて明確に区別された空間の質と広さ。これらすべてが、組織が理想とするアイデンティティを体現し、職員にもそれにふさわしい振る舞いを促すための、計算された美的演出でした。
しかし、職員たちの「生きられた」経験は、その設計思想とは異なるものでした。来客を迎えるための豪華な空間と、一般職員が働く高密度のキュービクルとの格差は、日々の業務の中で不公平感として体験されました。多くの職員は、建物の代表性には誇りを感じつつも、その西洋的な洗練さに「自分たちらしさ」からの乖離という居心地の悪さを感じていました。可視化されたヒエラルキーは、組織内の分断を深めることにもなりました。
やがて、職員たちはこの美的演出に対して、様々な形で異議申し立てを始めます。それは「カルチャー・ジャミング」とも呼べる、文化的記号の意味を読み替え、転覆させる試みでした。例えば、庁舎の美しさを紹介する公式の写真集を、子どもが工作に使う素材にしたり、窓を固定するための突っ張り棒として利用したりしました。豪華な壁材には「中華料理店のタイル」といったあだ名をつけ、その権威をからかいの対象へと変えました。
抵抗は、言葉遊びだけではありませんでした。物理的な空間への介入も行われました。「開かない窓」への抗議として、窓の絵が描かれた仮装をして庁内を歩き回ったり、電子ロックの隙間に爪楊枝を挟んで扉を常に開いた状態にしたりしました。これは、美観を優先し、働く環境を二の次にした設計思想への身体的な抗議でした。
さらに、規則で禁止されていたにもかかわらず、庁舎のモノクロームな美学とは対照的な、色彩豊かなペルシャ絨毯や個人的な装飾品を持ち込み、意図的に空間の均質性を乱しました。庁舎の透明なフェンスのそばにゴミを散らかし、「ショーウィンドウ」としての美観を汚すという行為もありました。
これらの行為は、単純な個人の逸脱ではありません。職員の組合が中心となり、建物の問題点を言語化し、個々の不満を組織的な問題として共有する場が作られました。その結果、職員たちの即興的で多様な抵抗の実践は、経営側が意図したアイデンティティ規制に対抗する、もう一つの秩序形成の力へと束ねられていったのです。
この事例は、建築の美学が、組織の公式なアイデンティティを人々に内面化させる装置として機能する一方で、その同じ美的なメディアを通じて、人々が自らのアイデンティティを主張し、公式の物語を攪乱する抵抗の拠点にもなりうることを示しています。空間の美しさは、決して中立ではなく、解釈と意味づけをめぐる政治的な闘争の場なのです。
職場空間がジェンダー規範を物質化し演技を要請する
組織の空間をめぐる政治は、時に集団的なアイデンティティの対立として現れますが、より個人的で、私たちの日常に深く根差した次元でも作動しています。その一つが、ジェンダーです。オフィスというごくありふれた空間が、実は「男らしさ」や「女らしさ」といった社会的な規範を無言のうちに強化し、私たちに特定のジェンダーに沿った振る舞いを演じるよう要請していることがあります。
ある大学で働く女性たちを対象とした調査は、この見えざる力学を解き明かしました[3]。この調査では、参加者に一枚のアート作品を見せるという手法が用いられました。その作品は、オフィスで働く女性が机の陰に隠れ、やがて自らゴミ袋に入って捨てられるまでを連続写真で表現したものです。この視覚的な刺激は、多くの女性たちが職場で抱える、言葉にしにくい身体的な感覚や経験を語るための触媒となりました。
参加者たちの語りから浮かび上がってきたのは、職場空間をめぐる三つの共通した経験でした。
第一に、「閉じ込められている」という感覚と、それに伴う「不可視であると同時に過剰に可視である」という矛盾した経験です。アート作品の女性像に自らを重ね、多くの人が職場で「そこにいるのに、いないかのように扱われる」という疎外感を口にしました。自分の存在や仕事が正当に評価されないという不可視性です。その一方で、女性は常に「明るく、話しかけやすく、いつでも対応可能」であることを期待され、他者の都合でいつでも中断させられる存在、要するに過剰に他者の視線にさらされる存在としての経験も語られました。
第二のテーマは、「侵入される」という感覚です。ある参加者は、背後から不意に人が近づいてくることに不安を感じ、自分の机の向きを変えた経験を語りました。これは、物理的なレイアウトを変更することで、自己の境界線を守ろうとする試みです。また、別の参加者は、隣の男性同僚の書類や私物が、自分のスペースへと「溢れ出してくる」状況を表現しました。いくら片付けても、そこはいつの間にか「彼の空間」になってしまう。自分の居場所が他者によって侵食されていく感覚です。
第三に、そうした制約の中での「限定的な自己表現」の実践が明らかになりました。多くの女性は、自分のオフィス空間を写真や小物で飾りますが、そこには慎重な計算がありました。例えば、子どもの写真を飾るにしても、「多すぎない適切な量」を意識し、「人間味があり、親しみやすい」という印象を演出しようとします。これは、プライベートを過度に見せることが、プロフェッショナルでないという評価につながることを避けるための自己規制です。空間の装飾は、好みの問題だけではなく、組織の中で承認される主体となるための戦略的な自己呈示の一部となっているのです。
これらの語りが示すのは、オフィス空間が単なる物理的な背景ではないということです。机の向き、飾られた写真の枚数、来客への身のこなし。こうした微細な事柄が、ジェンダー規範を物質化し、その規範に沿った「演技」を人々に求める舞台装置となっています。
宗教祭礼が兵士に共通知を与え反乱を促す
これまで、オフィスや庁舎といった、意図的に設計され、管理された空間が持つ政治性を見てきました。そのような明確な設計や管理の意図がない、一時的に生まれる人々の集いの場は、どのような力を持つのでしょうか。一見すると非政治的な宗教的な祭礼が、実は強力な権威への抵抗を生み出すための土台となることがあります。19世紀のインドで起きた軍隊の反乱を分析した歴史研究は、この問いに一つの答えを提示します[4]。
分析の対象となったのは、東インド会社のベンガル地方軍で起きた大規模な反乱です。当時、兵士たちの間では、新しく配備された銃の薬包に、ヒンドゥー教徒が禁忌とする牛の脂と、イスラム教徒が禁忌とする豚の脂が塗られているという噂が広まっていました。これは兵士たちにとって、自らの宗教的アイデンティティを揺るがす脅威でした。しかし、上官による厳しい監視体制のもとで、個々の兵士が反乱というリスクの高い行動に踏み切ることは困難でした。
ここで鍵となったのが、ヒンドゥー教やイスラム教の宗教祭礼でした。祭礼は、支配者の監視の目が届きにくい「自由な空間」として機能しました。普段は別々の兵舎で生活している兵士たちが、宗教という共通の旗印のもとに、一堂に会する機会を提供したのです。この場は、不満を共有するだけの場所ではありませんでした。より重要なのは、祭礼という熱気と一体感の中で、「自分と同じように感じ、行動しようとしている仲間が、これほど大勢いる」という事実を、誰もが互いに直接確認できたことです。
これが「共通知」の形成です。「他の皆も参加するだろう」ということを、その場にいる全員が知っている状態。この相互の確信が、個人の恐怖を乗り越え、集団で行動を起こすための心理的な閾値を下げたのです。祭礼の儀式や音楽、共有される食事といった身体的な経験が、噂によって掻き立てられた怒りや不安を、連帯感と行動への決意へと転換させる触媒となりました。
この関係を、歴史的なデータを用いて定量的に検証した分析があります。それによると、反乱が発生する確率は、宗教祭礼の当日、あるいはその直後に著しく高まり、祭礼から日数が経過するにつれて低下していくというパターンが確認されました。祭礼が、反乱のタイミングを合わせるための調整装置として機能していたのです。
祭礼の機能は、特に故郷のコミュニティから遠く離れた場所に駐屯している部隊において、顕著に見られました。日常的に頼れる支援ネットワークが乏しい彼らにとって、祭礼は大規模な動員を可能にするほぼ唯一の機会でした。また、近くにキリスト教の伝道所があるような、自らの宗教的アイデンティティが脅かされていると感じやすい環境では、祭礼の動員力はさらに増幅されました。
一方で、イギリス軍の大規模な部隊が近くに駐留している場合には、祭礼の動員効果は弱まることも分かりました。これは、兵士たちが感情の爆発で行動していたのではなく、成功の可能性を計算していたことを示しています。
この歴史的な事例が教えてくれるのは、権力への抵抗が、必ずしも周到に組織された秘密結社のような場所だけで計画されるわけではないということです。祭礼のような、一時的で、公然と開かれた人の集いが、抑圧された人々に共通の認識と連帯感をもたらし、大きな政治的変動を引き起こすための武器となりうるのです。空間は、そこに集う人々の相互作用を通じて、予期せぬ政治的な力を生み出す可能性を秘めています。
脚注
[1] Dale, K. (2005). Building a social materiality: Spatial and embodied politics in organizational control. Organization, 12(5), 649-678.
[2] Wasserman, V., and Frenkel, M. (2011). Organizational aesthetics: Caught between identity regulation and culture jamming. Organization Science, 22(2), 503-521.
[3] Tyler, M., and Cohen, L. (2010). Spaces that matter: Gender performativity and organizational space. Organization Studies, 31(2), 175-198.
[4] Rao, H., and Dutta, S. (2012). Free spaces as organizational weapons of the weak: Religious festivals and regimental mutinies in the 1857 Bengal Native Army. Administrative Science Quarterly, 57(4), 625-668.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






