2026年2月9日
コンサルタントは俳優か:舞台裏に宿る専門家の技法
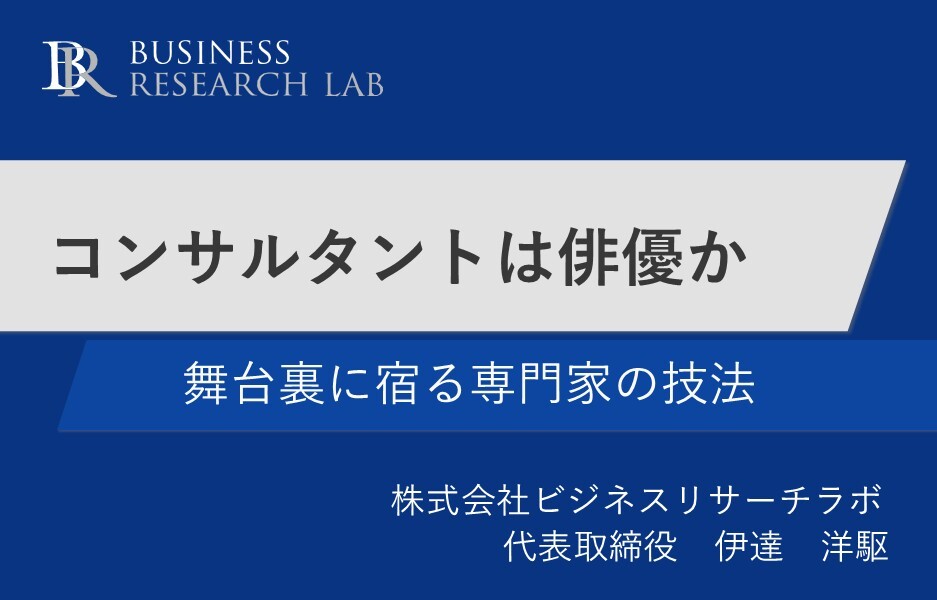
私たちの社会生活は、一つの大きな舞台にたとえられることがあります。家庭、学校、職場。私たちはそれぞれの場所で、状況に応じた顔を使い分けながら他者と関わっています。特にビジネスの世界では、この「舞台」という見方は現実味を帯びます。会議での発言、上司への報告、顧客との商談。その一つひとつが、自分という存在を他者にどう認識させるかを決める「上演」の連続と捉えることができるかもしれません。
この考え方の根底にあるのが、「印象管理」という概念です。これは、他者から見られる自分自身のイメージを、意図的あるいは無意識的にコントロールしようとする営みを指します。聞く人によっては、見栄や体裁、不誠実なごまかしといった響きを感じるかもしれませんが、印象管理は、円滑な関係を築き、社会的な目標を達成するために誰もが行う、ごく自然なコミュニケーションの一部です。
本コラムでは、この営みをただの処世術としてではなく、プロフェッショナルが自らの価値を創造するための高度な技法として捉え直します。組織で「演じる」という行為がどのような力学を生むのか、個人の評価はその巧拙にどう左右されるのか、専門家はいかに「信頼」という印象を設計しているのか。学術的な知見を紐解きながら、職場で繰り広げられる「パフォーマンス」の世界を探求していきます。
演劇研修は脚本支配の政治を暴く
組織の人材育成の手法として、「演劇研修」が存在します。参加者が演劇の技法を用いて特定の場面を演じ、コミュニケーション能力などの向上を目指すものです。一見、風変わりな取り組みに思えますが、その実践を観察すると、組織内に流れる力関係が浮かび上がってきます。
組織内で行われる演劇的な活動の実態を分析した研究が行われました[1]。その分析は、研修の裏側にある力学、すなわち「誰が物語をコントロールしているのか」という点を明らかにすることを目的としていました。そのために、二つの軸からなる分析の枠組みが用いられました。
一つ目の軸は、「役のコントロール」、要するに「誰が演じるのか」です。一方の端には、プロの俳優が演じ、従業員は受動的な観客となる形式があります。もう一方の端には、従業員自身が演者となる形式が存在します。
二つ目の軸は、「脚本のコントロール」、要するに「何が演じられるのか」です。プロが執筆した完成された台本を演じる形式もあれば、台本がなく、その場で物語を創り出していく即興の形式もあります。
この二つの軸を組み合わせることで、個々の演劇研修が、経営側の意図を強く反映したものか、従業員側の自発性を引き出すものかを整理できます。
例えば、経営側のコントロールが強い典型例として、ハラスメント防止研修が挙げられます。専門家が監修した脚本に基づき、プロの俳優が職場の場面を演じます。従業員はそれを見て、組織として許容される行動の境界線を学びます。ここでの目的は、会社の方針を明確に伝え、従業員の行動を一定の方向に導くことです。
一方で、従業員の関与が高まるにつれて、研修の様相は変わります。管理職研修で行われる「ロールプレイング」では、参加者自身が上司役や部下役を演じますが、役柄や状況設定はあらかじめ与えられていることが多く、演じる自由には限りがあります。
さらに観客の関与を促す対話型の演劇もあります。上演後、観客から出された「私ならこうする」という提案を俳優が取り入れて、場面を演じ直すのです。観客は受け手ではなく、物語の展開に直接介入します。
従業員側のコントロールが最も強くなるのは、即興で演じる形式です。ブラジルの演出家が考案した「被抑圧者の演劇」と呼ばれる手法はその代表例です。「フォーラムシアター」では、参加者が抑圧的な状況を描いた短い劇を即興で創作し、演じます。その後、もう一度演じ直すのですが、今度は観客がいつでも「ストップ」と叫んで劇を止め、舞台に上がって登場人物に代わり、別の行動を試すことができます。観客は傍観者であることをやめ、問題解決に主体的に関わる「観客兼俳優」へと変身します。
こうした分析から、演劇研修が持つ二面性が見えてきます。経営側のコントロールが強い場合、それは従業員の行動や意識を望ましい方向へ形成するための「支配の道具」として機能する可能性があります。たとえ従業員に即興が求められても、組織の暗黙のルールという「見えざる脚本」によって、その自由は制約されているかもしれません。
しかし、従業員側のコントロールが強い場合、演劇は普段は語られない本音を公の場に引き出す機能を持ちます。それは組織内に緊張をもたらすこともありますが、同時に、隠されてきた問題を表に出し、対話と変革のきっかけを生み出す可能性を秘めています。
印象操作の巧拙が職場での評価を左右する
組織という舞台から、私たち一人ひとりのパフォーマンスへと目を向けてみましょう。会議でのプレゼン、採用面接、上司との立ち話。これらすべてが、自分を他者にどう見せるかという上演の一部と考えることができます。その上演の巧拙が、職場での評価やキャリアの行方を左右することがあります。
組織における人々の振る舞いを「演劇」のメタファーで理解するアプローチがあります。それによれば、職場での相互作用は、「俳優(私たち自身)」「観客(相手)」「舞台(状況)」「脚本(暗黙のルール)」といった要素に分解できます。これらが組み合わさって日々の「上演」が成り立ち、その動機は「好かれたい」「有能に見せたい」など多岐にわたります。上演の結果は「レビュー(観客の反応)」として返ってきて、評価や昇進に結びつきます。
社会心理学の知見を基に、職場で頻繁に見られる自己呈示の戦略を分類した研究があります[2]。そこでは、五つの典型的な型が紹介されています。
一つ目は「取り入り」です。上司など地位の高い人に好かれることを目的とします。相手を褒めたり、意見に同意したりすることで評価を高めようとしますが、この戦略には「取り入りのジレンマ」が伴います。あからさますぎる態度は、お世辞として見抜かれ、かえって評価を下げる危険があるからです。
二つ目は「自己宣伝」です。自らの有能さをアピールする戦略です。採用面接などで、自分の能力をやや大げさに語り、実績を強調します。しかし、この戦略にも「自己宣伝のパラドックス」があります。昇進など報酬が大きくなるほど、人は自分を良く見せようとするため、その振る舞いが作為的であることを見破られやすくなります。
三つ目は「威嚇」です。相手に恐れを感じさせ、服従を引き出そうとします。叱責や罰則を多用するマネジメントがこれにあたりますが、従業員の萎縮や離職を招き、悪循環に陥る可能性があります。日常的な手法としては、極めて高いコストを払うことになります。
四つ目は「模範提示」です。自らの道徳性や組織への献身性をアピールします。長時間労働をいとわず、組織のために尽くす姿は周囲の尊敬を集めるかもしれません。これは、印象管理が偽りだけを意味するものではないことを示します。ただし、自己満足のために献身を演じると、偽善と見なされる危険も伴います。
五つ目は「哀願」です。自らの無力さや弱さを演出し、援助を引き出します。「コンピューターが苦手で」と訴え、仕事を肩代わりしてもらうような行動です。短期的には利益を得られても、長期的には自身の成長機会を失い、周囲からの評価を損なうことになります。
印象の設計がコンサルの価値を生む
専門知識や助言といった、形のないサービスを提供するビジネスでは、「品質」をいかに顧客に伝え、納得させるかが成功の鍵です。経営コンサルティングのような分野では、「印象の設計」がビジネスの根幹をなす活動となります。
経営コンサルティングの実践を「劇場」として分析した研究があります[3]。それによれば、コンサルティングの本質は、顧客に「信頼できるプロフェッショナルである」という印象を創造し、維持することにあるとされます。なぜなら、コンサルティングは購入前に品質を確かめられないサービスだからです。顧客は「解決策の約束」を購入するのであり、その約束が果たされるかは契約後でなければ分かりません。
そのため、顧客はサービスの具体的な中身よりも、品質を推し量る手がかり、すなわち「専門性の象徴」に頼らざるを得なくなります。高い学歴や資格、洗練された報告書、自信に満ちた態度。これらが、能力を判断するための代理指標として機能します。
このような状況では、演劇における「表舞台(フロントステージ)」と「舞台裏(バックステージ)」の管理が大切になります。顧客の目に触れるのは、完璧に演出された表舞台でなければなりません。分析に行き詰まったり、チーム内で意見が対立したりといった舞台裏の混乱は、顧客に見せてはなりません。バックステージの様子が少しでも漏れれば、プロとしての信頼という演目が崩壊してしまいます。
印象設計の巧みさは、エグゼクティブ・サーチ(ヘッドハンティング)の仕事の分析から、より明らかに見て取れます。この仕事の価値は、最終面接というクライマックスの「上演」に集約されます。サーチ・コンサルタントの真の仕事は、この晴れ舞台を成功させるための、舞台裏での緻密な演出にあります。
初めに、顧客である組織の「脚本」を読み解きます。経営陣や関係者に繰り返し聞き取りを行い、その組織が何を評価し、何を嫌うのか、といった文化の機微を把握します。続いて、その脚本に最もふさわしい「役者」を見つけ出し、徹底的な「役作り」を施します。最終面接に向け、候補者がその組織の求める人物像を自然に体現できるよう、模擬面接などを通じて周到に準備します。
このプロセス全体は、秘密主義の中で進められます。これもまた、候補者の自尊心を守り、顧客が安心して最終候補者という「完成品」だけを吟味できる状況を作るための、高度な舞台管理です。
協働の儀礼がコンサルの演劇的自覚を支える
プロフェッショナルにとって、「演じる」という技術は仕事の価値を左右する能力です。彼ら彼女ら自身は、この技術をどのように捉え、内面化しているのでしょうか。それは顧客を操作するテクニックなのでしょうか。
カナダの医療セクターで働くコンサルタントを対象とした調査研究が、この問いに答える手がかりをくれます[4]。医療という領域は、多様な専門職集団の利害が複雑に絡み合う特殊な環境です。調査では、コンサルタントが持つ「演劇的自覚」の実態が探られました。
ここで言う「演劇的自覚」とは、ただの印象操作の意識ではありません。他者に与える印象を戦略的に管理する意識と、自分自身の専門家としての信念を誠実に表現する意識という、一見矛盾する二つの側面を、状況に応じて使い分ける高度な気づきの状態を指します。
分析の結果、コンサルタントたちは、「協働」という言葉を使いながら、一連の儀礼的な相互作用を通じて、この演劇的自覚を実践していることがわかりました。彼ら彼女らのパフォーマンスは、コンサルティングのプロセス、すなわち「入場」「診断」「実施」「終結」という四つの段階に応じて、その姿を変えていきます。
第一の「入場」段階は、契約を結ぶ場面ですが、それ以上に、組織文化への理解を示す「オーディション」の性格を帯びています。ここで信頼できるパートナーとしての第一印象を確立することが、その後の活動の土台となります。
第二の「診断」段階では、組織が抱える問題点を報告します。しかし、事実をありのままに突きつけるのではなく、関係者の感情や面子に配慮し、誰もが受け入れ可能な「物語」へと編集し直します。
第三の「実施」段階では、変革の実行を組織内部の人々に引き継ぎ、自分たちは主役の座から舞台袖へと下がります。これは、外部支援から組織の自走へと、主導権をスムーズに移行させるための儀礼的なプロセスです。
最後の「終結」段階では、プロジェクト完了後も成果が定着するよう、責任の所在などを明確化する仕組みを組織内に残します。協働関係は、一度築けば終わりではなく、継続的に再演出し続ける必要があるのです。
このプロセスから浮かび上がってくるのは、熟練したコンサルタントの二つの顔です。一つは、状況を冷静に分析し、目的達成のために儀礼を操作する、戦略的な「行為者」としての顔。もう一つは、舞台裏で自らの振る舞いを振り返り、問い直す、省察的な「実践家」としての顔です。
彼ら彼女らにとって印象管理とは、顧客を欺くためのテクニックではありません。それは、複雑な人間関係の中で合意を形成し、困難な変革を前に進めるために不可欠な、高度な専門技術です。その実践は、戦略性と誠実性の間の緊張関係を、常に自覚的に引き受け続ける営みであると言えます。
脚注
[1] Nissley, N., Taylor, S. S., and Houden, L. (2004). The politics of performance in organizational theatre-based training and interventions. Organization Studies, 25(5), 817-839.
[2] Gardner, W. L., III. (1992). Lessons in organizational dramaturgy: The art of impression management. Organizational Dynamics, 21(1), 33-46.
[3] Clark, T., and Salaman, G. (1998). Creating the “right” impression: Towards a dramaturgy of management consultancy. The Service Industries Journal, 18(1), 18-38.
[4] Lalonde, C., and Gilbert, M.-H. (2016). Dramaturgical awareness of consultants through the rhetoric and rituals of cooperation. Journal of Organizational Change Management, 29(4), 630-656.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






