2026年2月9日
「当たり前」を揺さぶる力:制度が変わる瞬間を探る
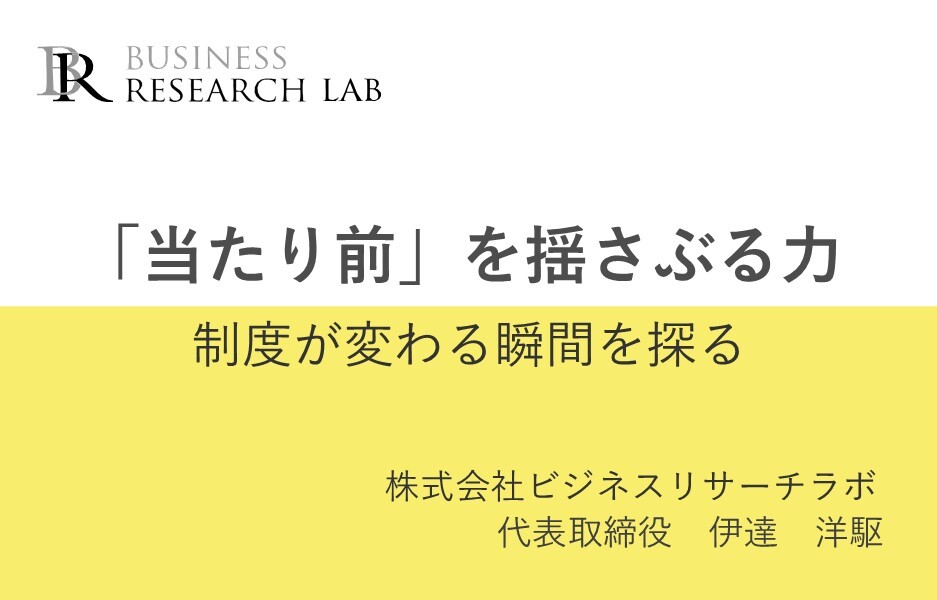
私たちの周りにある社会の「当たり前」は、どのように形作られ、変わっていくのでしょうか。働き方のルール、業界の慣習、社会の常識。これらは一度定着すると、私たちの行動を方向づけます。しかし、歴史を振り返れば、かつての常識が覆された例は無数にあります。変化は確かに起きます。
その変化は誰が、どのように起こしているのでしょうか。私たちは、社会を変えるのは強い信念を持つ英雄的な人物や、画期的なアイデアを持つ革新的な組織だと考えがちです。もちろん、そうした存在が引き金になることもあります。しかし、社会の仕組み、すなわち「制度」が変わるプロセスは、もっと多様で奥深いものです。
本コラムでは、社会の仕組みが変わる様々な形を、事例を通して探求します。社会貢献と利益追求の両立を目指す組織の葛藤。業界の「標準」を作ろうとする企業のジレンマ。特定の誰かが意図せずとも、多くの人々の行動が積み重なって生まれる変化。新しいものを生み出すだけでなく、それが何であるかを言葉で説明し、体系化することの力。これらの物語は、制度変革が一つの決まった筋書きで進むのではないことを教えてくれます。
理念より「手段」の共有でハイブリッド組織を築く
社会的な課題の解決とビジネスとしての利益を両立させる「ハイブリッド組織」が増えています。貧困層支援と銀行の収益性、環境保護と製品開発。二つの異なる目的を一つの組織で両立させることは容易ではありません。異なる価値観や仕事の進め方が組織内で衝突し、対立を生むことも少なくないからです。
ボリビアの二つのマイクロファイナンス組織は、この課題に異なる方法で向き合いました[1]。両者はともに非営利組織から商業銀行へ転換したという似た経歴を持ちながら、その後の組織運営は対照的な道を歩みます。
一つ目の組織、BancoSolは、多様な人材の結集から始めました。社会開発の経験豊かな活動家や、銀行業務に精通した専門家など、各分野で高い能力を持つ人々を積極的に採用しました。「貧困をなくす」という大きな目的を共有すれば、背景の異なるメンバーもまとまるだろう、という考えが根底にありました。入社後には手厚い研修で組織の使命を繰り返し伝えました。
しかし、現実は思惑通りには進みませんでした。能力を重視して集められた多様な人材は、やがて「社会開発」と「銀行」という二つの異なる論理の代弁者となっていきました。業務の進め方から従業員の服装といった細部に至るまで、両者の見解の相違が表面化します。理念の共有を目指したにもかかわらず、組織の中には修復困難な亀裂が入り、一時期は運営そのものが危機的な状況に陥りました。
一方、後発であったLos Andesは、BancoSolの混乱を教訓としました。採用方針で重視したのは、即戦力としての「能力」ではなく、特定の経験が浅い新卒などの若い人材を厳選することでした。特定のやり方に染まっておらず、組織文化をまっさらな状態から吸収しやすい人々を育てることにしました。
そして、Los Andesが徹底的に教え込んだのは、抽象的な理念よりも、日々の業務を高い水準で遂行するための具体的な「手段」でした。融資審査や回収を正確に行う技術など、「業務の卓越性」が、社会的目標と財務的健全性を両立させる土台であると位置づけました。昇進は筆記試験や実技で公平に判断され、報酬は個人の業績と明確に連動させました。
この一貫した方針の結果、Los Andesの内部では、出身背景による対立はほとんど見られませんでした。従業員は「質の高い金融サービスを提供するプロ集団である」という共通のアイデンティティを育んでいきました。この業務実践と固く結びついたアイデンティティは強固なものとなり、組織の安定と健全な経営につながりました。
この二つの組織の経験は、異なる価値観が共存する組織を束ねるための一つの知見を示します。崇高な「目的」を掲げるだけでは、人々の思考様式の違いを乗り越えることは難しい場合があります。それに対し、公正なルールのもとで、具体的な「手段」を共有し磨き上げるプロセスは、結果的に人々の心を一つにし、共通の誇りを生み出すことがあるのです。
技術標準化で公開と管理のジレンマに直面する
組織内部のルール作りから視点を移し、一つの企業が業界全体の「当たり前」、すなわち「標準」を作り出そうとする際の困難を見ていきましょう。パソコンのOSやスマートフォンの充電規格のように、一度標準が定着すれば社会の利便性は増しますが、そこに至るまでには激しい競争や駆け引きが繰り広げられます。
1990年代、インターネットが普及し始めた頃、「Java」というソフトウェア技術が大きな期待を集めました[2]。米国のSun Microsystems社が開発したこの技術は、「一度プログラムを書けば、どんな種類のコンピューターでも動く」という画期的な特徴を持っていました。特定のOSに縛られない自由なソフトウェアの世界。Sun社はJavaを通じて、その未来の中心に立とうと考えました。
壮大な目標を実現するため、Sun社はJavaを独占せず、「みんなの技術」として広く公開する戦略をとりました。競合他社も含め、誰でも簡単にJavaを使えるようにし、多くの企業を巻き込んでJavaを中心とした生態系を作り、ネットワーク全体の価値を高めようとしたのです。これは新しい標準を立ち上げる際の「動員」戦略でした。
しかし、この「公開」戦略は、やがてSun社自身を苦しめるジレンマを生みます。最大のライバルであったMicrosoft社は、Javaの勢いを見てライセンス契約を結びますが、自社のWindows OSに都合の良いように独自の拡張を加え始めました。「どこでも動く」はずのJavaが、分断されてしまう恐れが出てきたのです。
この事態に、Sun社はJavaの統一性を守るための「管理」を強化せざるを得なくなります。互換性のないアプリケーションを排除する厳格な認証制度を導入し、国際的な標準化団体にお墨付きをもらおうと働きかけます。
すると今度は、Java生態系に参加していた他の企業から「Javaは『みんなの技術』だと言っていたのに、結局はSun社がすべてを支配しようとしている」と不満の声が上がり始めました。多くの仲間を引き入れるために掲げた「公開」の理想と、標準の統一性を守るための「管理」の現実が対立したのです。Sun社は、Javaを広めようとすればするほど、この板挟みの状況から抜け出せなくなっていきました。
このJavaの物語は、新しい制度や標準を社会に根付かせようとする試みが、矛盾した圧力にさらされることを物語っています。変革の旗手は、多くの共感や協力を集める「社会的スキル」を発揮しなくてはなりません。しかし、人々が集まると利害がぶつかり、ルールから逸脱する動きが出てきます。そのとき、協力を維持するためにルールを強制する「政治的スキル」が必要になります。この二つのスキルは両立が難しく、新しい「当たり前」を作ることの困難さは、このジレンマに根ざしています。
行為の累積や「場作り」も制度変化を起こす
特定の組織や人物が明確な意図を持って制度を変えようとする事例を見てきました。私たちは社会の変化を考えるとき、こうした「誰が」主導したのかという物語に馴染みがあります。しかし、世の中のすべての変化が、このような形で起こるわけではありません。明確な設計者がいないまま、社会の仕組みが大きく転換することもあります。
制度が変わるプロセスは、大きく三つの異なる様式に整理できます[3]。
一つ目は、これまで見てきた「アントレプレナーシップ」です。これは変革の意図を持つ個人や組織が、周囲を説得したり、交渉したりしながら、新しい制度を創り出していく動きです。Javaの事例は、この様式の典型と言えます。
二つ目は、「パーテイキング」と名付けられた様式です。これは特定の誰かが主導するのではなく、多くの人々のバラバラに見える行動が意図せずして積み重なり、結果として制度変化を生むプロセスを指します。例えば、1920年代のアメリカにおける商業ラジオ放送の誕生がこの様式にあたります。当初アマチュアの趣味だったラジオは、部品メーカーや小売店、広告主など、多様な人々の個別の動機に基づく行動が連鎖し、新しい産業の形を創り上げました。誰かが最初から壮大な計画を描いていたわけではありません。
三つ目は、「コンヴィーニング」という様式です。これは問題が複雑で、単独の組織では解決策を見いだせない状況で、関係者が協力するための「場」や「仕組み」を作るところから変化が始まるプロセスです。例えば、かつてのパレスチナで子供たちの栄養改善という課題があった際、国際NGOや大学が連携して共同で活動する枠組みを設けました。この協働の「場」から信頼性の高いデータと知見が生まれ、国家全体の政策へと結実しました。不確実性の高い状況で、協働のための器を創り出すこと自体が、制度変化への第一歩となりました。
このように、制度の変化は多様な経路をたどります。明確なリーダーシップが発揮されることもあれば、名もなき人々の行動の集積が大きなうねりとなることもあります。あるいは、人々が知恵を出し合う「場」作りが変革の起点になることもあります。
創造するだけでなく自ら「理論化」して変革を導く
意図せざる行動の積み重ねがもたらす変化を見てきましたが、再び「アントレプレナーシップ」、すなわち明確な意図をもって社会の常識を覆そうとする人物に焦点を戻します。そのような変革者は、一体何をしているのでしょうか。新しいものを生み出しているだけなのでしょうか[4]。
スペインの料理人、フェラン・アドリア。彼のレストラン「エル・ブジ」は、世界の料理界に衝撃を与え続けました。食材を泡状にする「フォーム」など、彼の厨房から生まれた斬新な技術と料理は、それまでの高級料理の概念を覆し、料理界の制度を変えました。彼の活動を詳しく見ると、変革のプロセスにはいくつかの重要な要素が組み合わさっていることがわかります。
第一の要素は、言うまでもなく圧倒的な「創造性」です。アドリアは「創造とは、コピーしないことだ」と語り、既存の模倣を徹底的に避けました。その創造性を持続させるため、彼はレストランを年半年のみ営業し、残りの期間は専門の工房で実験と開発に没頭する仕組みを確立しました。
しかし、彼の非凡さは創造する点に留まりません。第二の要素として、「理論化」のプロセスがありました。彼は生み出した料理や技術を作りっぱなしにせず、実験過程をすべて記録・分類し、自らの料理の進化の軌跡を一つの体系としてまとめ上げたのです。「なぜこう作るのか」を常に問い、独自の料理哲学を言葉にしました。評論家が担うべき分析や意味づけを自ら行い、創造活動に客観的な文脈を与えました。
第三に、そうして生み出され理論化された新しい料理の価値を、世に認めてもらうための「評価」を獲得する努力がありました。彼はミシュランの三つ星といった専門家からの評価と同時に、有力メディアに取り上げられるなど社会的な名声も築き上げました。そのために業界の重鎮やメディア関係者と良好な関係を築くことも厭いませんでした。
最後に、価値が認められた自らの創造物を積極的に世に広める「普及」の活動です。自身の哲学と技術を盛り込んだ豪華な料理本を次々と出版し、世界各地で講演会を行いました。模倣されやすい世界で、自身の創造のオリジナリティを証明し、後進に道筋を示すためでした。
この一連の活動から浮かび上がるのは、制度を変えるほどの変革は、「創造」の一点突破では成し遂げられないという事実です。アドリアの新しい料理が世界に受け入れられ、常識を変える力を持ったのは、彼自身が、その新しさの価値を言葉で「理論化」し、正当性を担保する「評価」を築き、粘り強く「普及」させるという、一連の活動を実行したからです。
脚注
[1] Battilana, J., and Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations. Academy of Management Journal, 53(6), 1419-1440.
[2] Garud, R., Jain, S., and Kumaraswamy, A. (2002). Institutional entrepreneurship in the sponsorship of common technological standards: The case of Sun Microsystems and Java. Academy of Management Journal, 45(1), 196-214.
[3] Dorado, S. (2005). Institutional entrepreneurship, partaking, and convening. Organization Studies, 26(3), 385-414.
[4] Svejenova, S., Mazza, C., and Planellas, M. (2007). Cooking up change in haute cuisine: Ferran Adria as an institutional entrepreneur. Journal of Organizational Behavior, 28(5), 539-561.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






