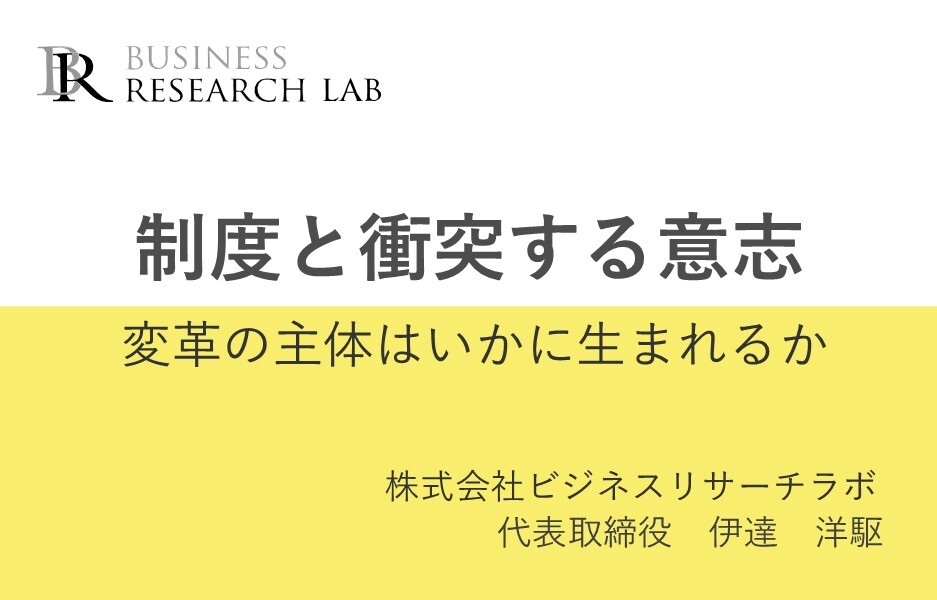2026年2月6日
制度と衝突する意志:変革の主体はいかに生まれるか
私たちの周りには、当たり前とされる慣習や、暗黙の了解として存在する「ゲームのルール」があります。多くの人々や組織は、そのルールの中でいかにうまく立ち振る舞うかを考えます。しかし、時としてそのルール自体を書き換えようとする人々や組織が現れます。自らが属する社会や業界の構造に働きかけ、新たな秩序を生み出そうとする、こうした変革の担い手を「制度的企業家」と呼ぶことがあります。彼ら彼女らの振る舞いは、私たちの社会にダイナミズムをもたらします。
しかし、ここには一つの大きな問いが横たわっています。特に、既存のルールの恩恵を最も受けているはずの、いわば「内部の人間」が、なぜ自らを形作ってきたはずの環境を変えようと思い立つのでしょうか。深く構造に根を下ろした存在が、その構造自体を動かすという現象は、一見すると矛盾しているように思えます。
本コラムでは、この「行為主体(エージェンシー)」、すなわち、構造を変える力がどこからやってくるのかという問いを探求していきます。業界の中心にいるエリートが変革者となる過程、変革を可能にする環境条件、変革者の内面的な思考様式、変革を実現するために用いられる道具。これらの分析を通じて、社会が変化していく背後にある、人間の営みに光を当てていきたいと思います。
業界エリートは制度の矛盾に直面し制度的企業家となる
社会や業界の変化は、しばしばその周縁部にいる、既存の秩序に縛られない存在によって引き起こされると考えられるかもしれません。中心部にいるエリートたちは、現状維持によって多くの利益を得ているため、変革に対しては消極的であるというのが通説でした。しかし、この見方に一石を投じる研究があります[1]。それは、1980年代から1990年代にかけて、当時「ビッグファイブ」と呼ばれた世界最大手の会計事務所が、業界のあり方を変えようとした事例を分析したものです。
当時の会計業界では、専門家の自律性を尊重する伝統的な組織モデルが主流でした。これは、会計という単一の専門分野に特化し、商業主義とは一線を画し、専門的技術を高めることを是とする価値観に支えられていました。ところが、業界の頂点に君臨していたビッグファイブは、この慣習を破り、「学際的実務」という新しい組織形態を導入しようと試みます。これは、会計だけでなく、コンサルティングや法律といった複数の専門サービスを一つの組織に統合し、大企業の顧客にあらゆるサービスを一体的に提供することを目指すものでした。
商業的な成功を第一に掲げるこの動きは、従来の価値観とは相容れないものであり、特に法律事務所の買収にまで乗り出した際には、法曹界や規制当局から抵抗を受けました。
既存の制度に最も深く埋め込まれているはずのエリートたちが、このような急進的な変革を主導したのは、彼ら彼女らがその特異な立場ゆえに、既存制度が内包する「矛盾」に直面したからでした。この変革のメカニズムは、四つの連動する力学によって説明されます。
第一に、「業績への懸念」です。ビッグファイブは他の会計事務所に比べて高い収益を上げていましたが、主力の監査業務だけでは、これまでのような高い成長率を将来にわたって維持することは難しいという危機感を抱いていました。この現状維持と将来の成長との間にある緊張関係が、既存のやり方を見直し、新たな収益源を探す動機となりました。
第二に、「境界の橋渡し」という立ち位置です。ビッグファイブは、世界中に展開する巨大グローバル企業を主な顧客としていました。これらの顧客は、国ごとに異なる会計監査だけでなく、経営戦略に関するコンサルティングなど、多様なサービスを一つの窓口で提供してくれることを望んでいました。会計業界とグローバル企業という二つの異なる世界の間に立つことで、ビッグファイブは、従来の会計業界の常識にはない新しいビジネスモデルの可能性に気づかされました。
第三に、「境界の不整合」が生じていたことです。顧客のグローバル化に対応するため、ビッグファイブ自身も国境を越える巨大な組織へと変貌していました。一方で、会計士を監督する専門職団体や規制当局の権限は、国や州といった地域レベルにとどまったままでした。ビッグファイブの事業範囲と、それを規制する側の管轄範囲との間にズレが生まれていたのです。このズレのおかげで、ビッグファイブは既存の専門職団体の細かい統制から事実上自由になり、新しい試みに対して開かれた姿勢をとることができました。
第四に、圧倒的な「資源の非対称性」です。上記のような状況の結果、ビッグファイブは規制当局をはるかにしのぐ技術的、財政的、政治的な力を持つに至りました。規制当局が作成する基準よりも高度な研修プログラムを自前で開発し、規制が不利とみれば訴訟も辞さず、政治的な働きかけによって抵抗することも可能でした。この力関係の逆転は、規制当局からの圧力を弱め、ビッグファイブが変革に向けて突き進むことを後押ししました。
これらの四つの要素が組み合わさることで、エリート組織の制度への埋め込みは弱まり、変革への「動機」「気づき」「自由」がそろいました。この事例は、制度の中心にいる存在であっても、その立場ゆえに複数の制度ロジックの交差点に立たされ、矛盾に直面することで、既存の枠組みを乗り越える力を獲得しうることを示しています。
「適度な不確実性」をテコに制度変革を駆動する
先ほどは、業界のエリートが、その置かれた特殊な環境によって変革の担い手となりうる過程を見ました。外部からの圧力や顧客からの要求といった要因が、行為主体性を引き出すきっかけとなることがうかがえます。しかし、変革が実際に起こるためには、行為者の意図や能力だけでなく、その場の「状態」も関わっています。どのような環境下で、人々は既存のルールを書き換えようという行動をとることが可能になるのでしょうか。
この問いを解き明かす鍵は、「不確実性」という概念にあります[2]。私たちの行動は、一方では社会的に確立された「制度」によって方向づけられています。制度は、次に何が起こるかを予測可能にし、日々の活動から不確実性を減らすことで、安定した社会秩序を生み出します。他方で、私たちは自らの目的を達成するために、意識的に資源を動員し、既存のルールを解釈し直したり、新たなやり方を試みたりする「戦略的行為」も行います。
この二つの力は、一見すると対立しているように見えます。制度は安定を、戦略的行為は変化を目指すからです。しかし、両者は切り離せない関係にあります。戦略的な選択というものは、ある程度安定した制度という土台があって初めて、意味のあるものとして構想できるからです。
この両者の関係を結びつけるのが、不確実性の度合いです。もし環境の不確実性が高すぎると、人々は将来を見通すことができず、リスクを避けるようになります。その結果、新しい試みは抑制され、過去から慣れ親しんだやり方や、信頼できる既存のパートナーとの関係に固執するでしょう。完全な混乱状態では、秩序を創造しようとする意図的な行動は起こりにくいのです。
逆に、不確実性が低すぎる、要するに制度が極めて強固で、あらゆる物事が決められているような環境ではどうでしょうか。そこでは、そもそも変化の余地がありません。ルールは絶対的なものと受け入れられ、それに従う以外の選択肢は考えられなくなります。このような硬直した状態も、新たな変化を生み出す力を奪います。
したがって、制度を変えるような起業家的行為が最も生まれやすいのは、不確実性が「適度」な水準にあるときです。それは、ルールが十分に共有されていて、自分の行動がどのような結果につながるかある程度予測できる一方で、完全に固定化されてはおらず、新たな解釈や試行錯誤の余地が残されている状態です。未来が計算可能でありながら、まだ開かれている。そうした環境が、戦略的な行為の可能性を開きます。
この関係性は、循環的なプロセスとして捉えることができます。まず、適度に制度化された安定した状態が、起業家的な介入の機会を提供します。その介入が成功すると、既存の秩序は一時的に揺らぎ、不確実性が高まります。しかし、やがて人々はその変化に適応し、学習を通じて新たな慣行が定着し、再び安定した状態へと収束していきます。そして、その新たに形成された秩序が、次の戦略的行為の舞台となります。このように、制度の安定と変化は、不確実性を介して、終わりなき循環を繰り返していると考えることができます。
制度的企業家とは自律的に思考し既存構造と衝突する人物
これまで、変革の力が生まれる外部的な条件、すなわち業界内での立ち位置や、環境の不確実性といった点に光を当ててきました。しかし、同じような環境に置かれていても、ある人は現状を維持しようとし、別の人はそれを変えようとします。この違いはどこから来るのでしょうか。変革を駆動する人々の内面、その思考の様式に、行為主体性の源泉があるのではないか。この問いを探求するにあたり、「内省」のあり方に着目した理論が手がかりを与えてくれます[3]。
この理論の出発点にあるのは、制度論が抱える問いです。私たちは皆、社会の構造や文化といった、自分たちを取り巻く環境から強い条件づけを受けています。では、人はどのようにしてその条件づけから自由になり、環境を変えるような行為をなしうるのでしょうか。その答えは、人が自分自身と対話する「内的対話」の様式にあるとされます。
詳細なインタビュー調査を通じて、この内的対話のあり方にはいくつかの類型が見出されました。
一つは、自分の考えをまとめるために他者との対話を必要とする「対話的内省者」です。このタイプの人々は、周囲との調和を保ち、既存の環境の継続性を維持する行動をとりやすいとされます。一方で、他者の意見から相対的に独立して、自分自身の内で思考を完結させることができる人々がいます。これが「自律的内省者」です。このタイプの人々は、自らのプロジェクトを追求する過程で、既存の構造と衝突し、それを変えようとする可能性を秘めています。
この「自律的内省者」が、制度的企業家の原型であるという考えを、歴史的な事例研究が裏付けています。分析の対象となったのは、19世紀のイギリス・リバプールでビール醸造会社を経営していたアンドリュー・バークレイ・ウォーカーという人物です。彼は、当時の業界の常識を覆す経営革新を行いました。それは、パブの運営を個人事業主である借家人に任せるのではなく、給与を支払う管理者を雇用して直営化するというものでした。詳細な会計システムと検査官による監督体制を伴うこの仕組みは、当時としては画期的なものでした。
ウォーカーの人物像や行動の記録を分析すると、「自律的内省者」を特徴づける三つの性質が浮かび上がってきます。
第一に、際立った「個人主義」です。彼は寡黙な人物として知られ、残された手紙も非常に簡潔で、ビジネスと金銭に関する価値観が人間関係に優先していたことがうかがえます。
第二に、「仕事への専念」です。彼は抽象的な理論には関心を示さず、大学への寄付に際しても、政治経済学の講座ではなく、実用的な工学実験室を選んでいます。彼の個人的な帳簿には、公私にわたる詳細な数字の計算がびっしりと書き込まれており、数字という客観的な言説を通じて世界を捉えていた様子が見て取れます。
第三に、「文脈的な不連続性」を恐れない姿勢です。彼の父親は事業が一定の規模に達したところで満足しましたが、ウォーカーは満足することなく、アイルランドの蒸留所やウェールズの炭田開発など、次々と新しい分野へと事業を拡大していきました。
興味深いのは、ウォーカー自身は、業界の制度を変革しようという意図を持っていたわけではないという点です。彼はあくまで一人の企業家として、自らの事業の成功を追求していました。しかし、その思考様式が「自律的」であったがゆえに、目的を追求する過程で、既存のやり方との間に衝突が生じ、新たな経営管理の仕組みを生み出すことになったのです。
この事例からうかがえるのは、行為主体性とは、変革を目的とする意識から生まれるというよりは、自律した思考様式が、既存の構造と相互作用する中で、副産物として発露するものである、ということです。
「測定」という道具を使い社会構造の力を引き出す
私たちはここまで、変革の力が生まれる背景として、エリートが直面する「矛盾」、環境の「適度な不確実性」、個人の内面にある「自律的な思考様式」といった要因を順に見てきました。これらは変革への動機や可能性の扉を開くものです。しかし、新しいアイデアやビジョンが、現実の社会に根付き、多くの人々に受け入れられる「制度」となるためには、それだけでは不十分です。アイデアを現実に定着させるための「道具」が必要となります。ここでは、制度的企業家が用いる道具の一つとして、「測定」という行為を取り上げます[4]。
この議論の土台となるのは、現実は複数の階層から成り立っているという考え方です。私たちの目に見える日々の実践や経験の背後には、それを生み出す出来事の層があり、さらにその奥には、物事のあり方を規定する根本的な構造や因果的な力が潜んでいると捉えます。制度で言えば、日々の行動(経験の層)は、慣習化されたルールや手順(現実化の層)によって形作られ、そのルール自体は、社会で共有されている正当性の原理や意味の枠組み、すなわち「制度ロジック」(実在の層)から導き出されています。
この枠組みにおいて、制度的企業家とは、実在の層にある制度ロジックの力を引き出し、それを具体的なルールや実践へと変換する存在として理解されます。フランスで「社会的責任投資(SRI)」という新しい市場が立ち上がった過程を分析した研究は、このプロセスを描き出しています。
1990年代後半のフランスでは、社会的責任投資はまだ黎明期にありました。企業の社会的パフォーマンスと財務的なパフォーマンスの間に明確な関係があるという証拠はなく、投資家からの強い需要もありませんでした。このような逆風の中、ARESEというソーシャル・レーティング機関が設立され、この新しい市場の形成に決定的な貢献をしました。ARESEの成功の鍵は、社会的パフォーマンスという曖昧なものを「測定」し、数値化するという戦略にありました。
「測定」という行為は、それ自体が社会的な構造として、いくつかの因果的パワーを持っています。第一に、「定義する力」です。ある事柄を測定し、数値に還元する行為は、その事柄が客観的に存在し、測定可能であるという印象を生み出します。ARESEは、企業の社会的パフォーマンスを定量的なスコアにすることで、「社会的責任とは何か」を定義してみせました。
第二に、「比較可能にする力」です。共通の指標でスコアが付けられることで、これまで比べようがなかった異なる企業の社会的パフォーマンスを、同じ土俵の上で比較し、順位付けすることが可能になります。これは、投資家が投資先を選ぶ際の意思決定を簡素化します。
第三に、「正当化する力」です。数値やスコアといった形式は、「科学的」「客観的」なものとして受け入れられやすい性質を持っています。ARESEは、社会的パフォーマンスを金融業界の人間が慣れ親しんだ「金融の言語」に翻訳することで、社会的責任投資という活動全体に、信頼性と正当性を与えることに成功したのです。
このように、ARESEは「測定」という道具を用いることで、社会的責任という、それだけでは金融市場に受け入れられにくいロジックを、金融の合理性という支配的なロジックと結びつけ、新しい市場を創造しました。行為主体性とは、新しいビジョンを掲げるだけでなく、それを社会に根付かせるための文化的な道具を戦略的に選び、使いこなす技術でもある、ということがここから理解できます。
脚注
[1] Greenwood, R., and Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields: The Big Five accounting firms. Academy of Management Journal, 49(1), 27-48.
[2] Beckert, J. (1999). Agency, entrepreneurs, and institutional change: The role of strategic choice and institutionalized practices in organizations. Organization Studies, 20(5), 777-799.
[3] Mutch, A. (2007). Reflexivity and the Institutional Entrepreneur: A Historical Exploration. Organization Studies, 28(7), 1123-1140.
[4] Leca, B., and Naccache, P. (2006). A critical realist approach to institutional entrepreneurship. Organization, 13(5), 627-651.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。