2026年2月5日
制度を守り、時に壊す:「恥」の二つの働き
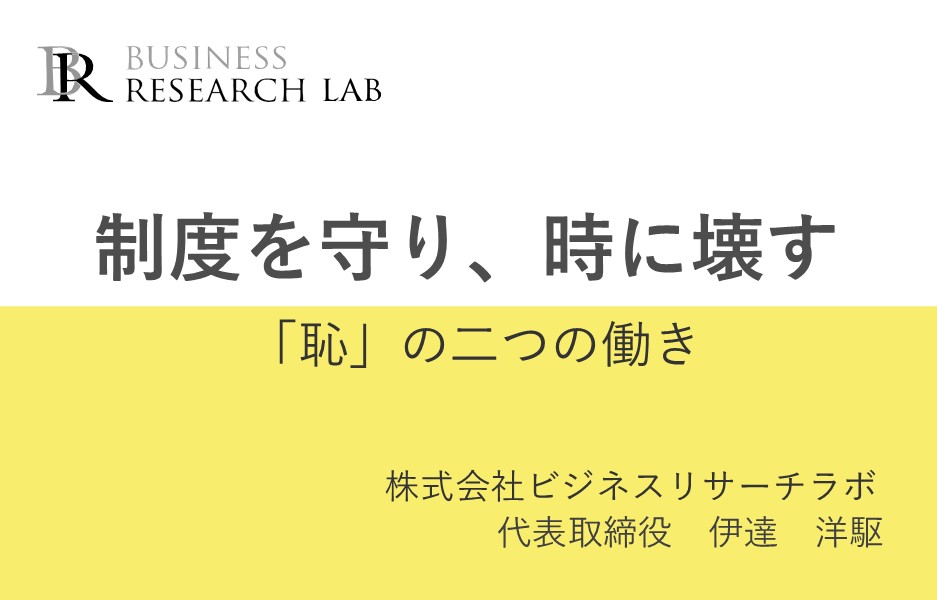
応援しているスポーツチームが、信じられないようなミスで敗れたとき。あるいは、親しい友人が公の場でマナーに反する行動をとったとき。自分自身が何かをしたわけではないのに、なぜか顔が熱くなり、その場から消えてしまいたいような気持ちになった経験はないでしょうか。この「もらい事故」のような恥ずかしさは、私たちの日常に潜む感情の一つです。
「恥」を個人の内面で完結する、個人的でネガティブな感情だと捉えるかもしれません。失敗した自分、能力のない自分を責める、痛みを伴う自己評価。しかし、この感情は、私たちの内側から湧き上がるだけでなく、人と人との関係や、社会そのものを動かす、目には見えない力として働いています。
自分一人の問題だと思っていた恥が、実は所属する集団の評判を守るための防衛反応だった。あるいは、社会のルールや秩序を維持するための、巧みな仕組みの一部だった。そして、時には、深く愛している組織や集団から、自らを遠ざける引き金にさえなってしまった。
本コラムでは、「恥」という感情の、そうした社会的側面に光を当てていきます。個人の感情の枠を超え、集団の力学や社会の制度にまで関わる「恥」の多面的な姿を、いくつかの研究を手がかりに探求していきます。自分のせいではないのに感じるあの居心地の悪さの正体を知ることは、私たちが生きる社会の仕組みと、その中で振る舞う自分自身の姿を、少し違った角度から見つめ直すきっかけになるでしょう。
身内の逸脱が生む恥は、集団の評判を守るため制止を促す
私たちの周りには、電車内では静かにする、禁煙の場所では吸わないといった、様々なルールや規範があります。もし自分の仲間がそれを破っていたら、私たちはどう感じるでしょうか。「やめてほしい」という気持ちが芽生えるとき、その感情は集団の評判を守る警報装置として働いているのかもしれません。
この心の動きを検証した調査があります[1]。フランスの大学生を対象にしたこの調査では、模擬的な状況でどのような感情が生まれ、どう行動につながるかが調べられました。
最初の実験では、参加者はヨーロッパの学生会議の場面を想像します。禁煙の表示があるにもかかわらず、一人の学生が喫煙を始めます。この喫煙者が自分と同じ「フランス人(内集団)」だと説明されたグループと、「ベルギー人(外集団)」と説明されたグループでは、反応が異なりました。
喫煙者が身内であるフランス人の場合、参加者はより強い羞恥や当惑を感じ、その感情が強いほど、喫煙をやめさせようとする意図も高まっていたのです。同じ違反でも「身内」が行うと集団全体のイメージが損なわれると懸念し、それが羞恥感情となり、評判を守るために逸脱を止めさせようという動機になります。
次の実験では、逸脱が起きる状況に変化が加えられました。逸脱者は常にフランス人ですが、それがフランス人しかいない「私的な」状況で起きるか、他の国の学生たちが見ている「公的な」状況で起きるかが比較されました。結果、他の集団の目がある公的な状況の方が、参加者ははるかに強い羞恥感情を報告し、制止しようとする意図も高まりました。外からの視線にさらされることで、一個人のルール違反が「フランス人全体の評判」を損なう問題へと意味を変え、恥を増幅させます。
最後の実験では、評判への脅威がより直接的に提示されました。参加者の一部は事前に、「フランス人は規範を無視しがちだ」といった、自国への否定的なステレオタイプに関する文章を読みます。この仕掛けの後で仲間の逸脱を目にした参加者は、最も強い羞恥を感じ、最も強くその行動をやめさせたいと望みました。「やっぱりそうだ」とステレオタイプを裏付けてしまうことへの強い懸念が、恥を最大化し、評判を守る行動へと人々を駆り立てる様子がうかがえます。
これらの実験は、身内の不始末に感じる恥が、個人の道徳観だけでなく「他者からどう評価されるか」という評判への配慮から生まれることを示しています。そしてその恥は、集団の顔に泥を塗る行為をやめさせようとする行動の原動力となります。
集団の失敗では、恥は償いを促し、防衛行動は拒絶感から生じる
自分の国や組織が、過去に道徳的に許されない過ちを犯したと知ったとき、私たちの心には複雑な感情が渦巻きます。この種の恥は、時に私たちを過去と向き合わせ償いへと向かわせる一方、時には問題から目を背けさせる力も持ちます。この一見矛盾した感情の背後には、どのような心の仕組みがあるのでしょうか。
ノルウェーのある調査は、「恥」を細かく分解してこの問いを解き明かそうとしました[2]。参加した地域住民は、自国が過去に少数民族へ組織的な差別を行っていたという文章を読み、その事実への感情や考えを問われました。
この調査は「恥」の経験を、その源泉となる二つの異なる認識(「集団の道徳的な欠陥」という内面的評価と、「他者から非難されるのでは」という外的評価への懸念)と、そこから生まれる複数の感情に分けて捉えました。分析の結果、「集団の欠陥」という認識は「恥ずかしい」と感じる純粋な「感じられる恥」と強く結びつき、一方、「他者からの非難懸念」は、孤立するように感じる「感じられる拒絶」と強く結びついていることがわかりました。
この二つの感情の分岐点が、問題の焦点を「自分たちの内側」に向けるか、「他者からの視線」に向けるかの違いにあります。「感じられる恥」は、あくまで自分たちの集団の道徳的な欠陥という内面的な問題に直面し、「私たちは間違っていた」という痛みを伴う内省です。そのため、その痛みから逃れるには、過ちを正し、道徳的な自己を回復するしかありません。これが償いという建設的な行動につながります。
一方で「感じられる拒絶」は、問題の焦点が「他者からどう見られ、どう扱われるか」という外面的な評価にあります。ここでは「社会的な孤立からどう身を守るか」が優先課題となり、問題そのものと向き合うよりも、非難の的から逃れるための隠蔽や逃避といった自己防衛的な行動が選ばれやすくなります。
そして、これらの異なる感情は、人々を全く逆の方向へと導いていました。自分たちの欠陥を認識することから生まれる純粋な「感じられる恥」は、過去の過ちを正そうとする建設的な動機と強く結びついていました。この恥を感じた人々は、自らを悔い、被害者に償いをしたいと考えていました。
対照的に、他者からの非難を懸念し、「拒絶されている」と感じることは、異なる結果につながりました。この「感じられる拒絶」は、辛い非難から身を守るため、問題から距離を置いたり隠蔽したりしようとする、自己防衛的な動機を強く予測していました。
要するに、集団の失敗への反応は、二つの経路をたどります。一つは、自らの欠陥を内省し痛みを受け入れることから始まる道です。この道で感じる純粋な「恥」は、集団が道徳的な自己を回復させ、関係を修復するための建設的なエネルギー源となります。もう一つは、他者の視線を過度に恐れ、自分を守ろうとすることから始まる道です。この道で感じる「拒絶」の感覚は、人々を内向きにし、問題と向き合うことを避けさせます。
同じ失敗という出来事でも、それを「自分たちの欠陥」と捉えるか、「他者からの非難」と捉えるかで、感情と行動は分かれるのです。
人々が恥を避けることで制度は維持され、辱めが変革を促す
私たちはなぜ、赤信号で道を渡らないのでしょうか。法律で罰せられるからだけでなく、たとえ誰も見ていなくても多くの人はルールに従います。私たちの行動は、明文化された規則以外にも、無数の見えない規範に形作られています。私たちをそれに従わせる力とは何でしょうか。その鍵を握るのが、「恥」を利用した社会の仕組みにあります。
この問いに、組織論の観点から一つの理論的枠組みが提示されました[3]。それは、「恥」という感情が社会制度を維持する力と変革する力の両方を生み出すプロセスを描き出すものです。
制度が維持されるのは、社会に浸透する「システミック・シェイム(制度的な恥)」、すなわち何が「恥ずべきこと」とされるかについて共有された理解があるからです。例えば、会社の重要な会議でカジュアルすぎる服装をしない、あるいは場の空気を読まずに的外れな発言をしない、といった行動は、明確な規則で罰せられるからというよりも、「そんなことをしたら恥ずかしい」という感覚によって自己規律されています。これがシステミック・シェイムの働きです。
この力は、私たち一人ひとりの内面にある「恥の感覚」を通じて機能します。私たちは他者の視点という内なる「鏡」で自身を評価し、価値ある社会的つながりを失う原因となる「恥」を避けようとして、無意識に行動を調整しています。罰せられるからではなく、「恥ずかしい思いをしたくない」からルールを守るのです。この絶え間ない自己規制が、社会制度を強力に維持する力だと、この理論は説明します。
しかし、この制度維持の仕組みは、時に制度を変革するエネルギーへ転化します。その引き金となるのが、「エピソード的シェイミング(具体的な辱め)」、すなわち規範からの逸脱者に対して、管理者などが意図的に恥をかかせる行為です。通常、辱めを受けた人は再び規範に従うことで制度は強化されます。
ところが、辱めを受けた人が、その経験を「不当だ」と結論づけ、拒絶することがあります。この拒絶を可能にする重要な条件が、人々が複数のコミュニティに所属していることです。ある集団では「恥」とされる行為が、別の集団では許容されるかもしれません。この代替的な価値観や社会的なつながりが、不当な辱めに抵抗する支えとなります。
辱めを拒絶した人は、制度を変革しようと行動することがあります。一つはコミュニティを離れ、外部からその制度を攻撃する「離脱」の道。もう一つは、コミュニティに留まり、内部から制度を変えようと声を上げる「発言」の道です。恥を避ける日常的な自己規制は社会を安定させますが、公然の「辱め」は既存の秩序への疑問となり、社会変革の力にも転じ得ます。
組織への愛着が強い人ほど、不祥事の恥から組織を離れたくなる
自分が長年勤め、愛着を感じている会社や母校が、社会から激しい非難を浴びる不祥事を起こしたら、私たちはどう感じるでしょうか。怒りや失望と共に、まるで自分自身の価値が傷つけられたかのような、深い恥を抱くでしょう。この恥は、時に最も組織を愛していた人々を、皮肉にも組織から遠ざけてしまうことがあります。
この現象を、台湾で実際に起きた二つの事件(ファストフード業界の廃油事件、大学の会計不正スキャンダル)を通じて検証した研究があります[4]。研究者たちは、事件の渦中にいた従業員や学生に調査を行い、組織の不祥事がメンバーの心に与える影響を調べました。
この研究が光を当てたのは、「代理の恥」という感情です。これは、事件に直接関与していなくても、所属組織が不正を犯しただけでメンバーが経験する恥を指します。この恥を感じたメンバーが組織から心理的に距離を置こうとする「心理的距離化」との関連が探られました。
調査の結果、「組織が悪い」と考えるメンバーほど強い「代理の恥」を感じ、その恥が強いほど「会社を辞めたい」「留学したい」といった、組織から離れたいという欲求が強いことが確認されました。
しかし、この研究の重要な発見は、「組織への同一化」、すなわち組織への愛着が強い人ほど、この負の連鎖が強まる点にありました。分析の結果、もともと組織への愛着が強いメンバーほど、不祥事の際により強い「代理の恥」を感じ、組織から離れたいという欲求も一層強くなっていました。
これは組織への愛着が持つ逆説的な側面です。通常、組織への強い一体感は忠誠心や貢献意欲の源泉とされます。しかし、組織が社会の信頼を裏切る危機に直面した時、その強固な結びつきは裏目に出ます。組織を「自分ごと」として深く捉えるからこそ、その失敗はメンバー自身の自己イメージを深く傷つけ、耐え難い恥を生みます。そして、その傷ついた自己イメージを守るため、恥の原因である組織とのつながりを断ち切ろうとします。
組織への愛着という、平時における最大の強みが、有事における最大のリスクにもなりうる。この皮肉な現実は、組織と個人の関係の複雑さを示しています。
脚注
[1] Chekroun, P., and Nugier, A. (2011). “I’m ashamed because of you, so please, don’t do that!”: Reactions to deviance as a protection against a threat to social image. European Journal of Social Psychology, 41, 479-488.
[2] Gausel, N., Leach, C. W., Vignoles, V. L., and Brown, R. (2012). Defend or repair? Explaining responses to in-group moral failure by disentangling feelings of shame, rejection, and inferiority. Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 941-960.
[3] Creed, W. E. D., Hudson, B. A., Okhuysen, G. A., and Smith-Crowe, K. (2014). Swimming in a sea of shame: Incorporating emotion into explanations of institutional reproduction and change. Academy of Management Review, 39(3), 275-301.
[4] Chi, S.-C. S., Friedman, R. A., and Lo, H.-H. (2015). Vicarious shame and psychological distancing following organizational misbehavior. Motivation and Emotion, 39, 795-812.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






