2026年2月5日
組織の「当たり前」を解き明かす:ルーティンがもたらす安定と変化(セミナーレポート)
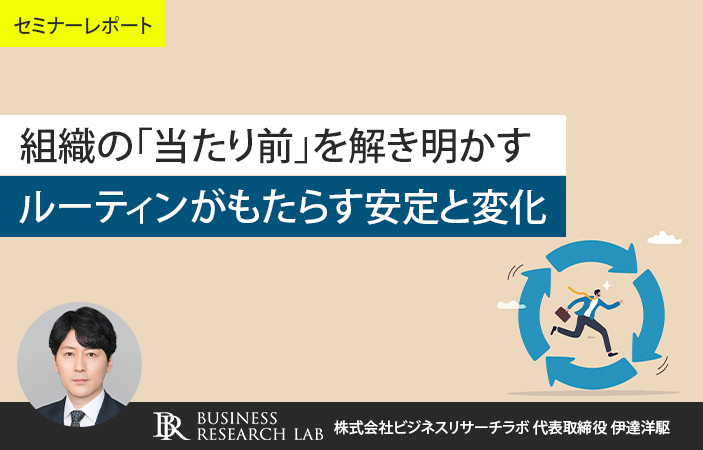
ビジネスリサーチラボは、2025年12月にセミナー「組織の『当たり前』を解き明かす:ルーティンがもたらす安定と変化」を開催しました。
組織は、日々繰り返される業務を通じてその安定性を保っています。しかし、市場環境の変化に対応するためには、新しい状況に適応し、変化し続ける能力も不可欠です。この「安定性」と「適応性」という、一見すると矛盾する二つの性質を、組織はどのように両立させているのでしょうか。その鍵を握るのが、私たちが普段意識することの少ない「組織ルーティン」です。
本セミナーでは、組織の根幹をなす「組織ルーティン」に焦点を当てました。ルーティンと聞くと、決まりきった画一的な作業を想像するかもしれません。しかし近年の研究は、ルーティンが固定的なものではなく、組織の学習や変化を生み出す源泉であることを明らかにしています。
日々の業務の中で、人々は定められた手順をただ繰り返すのではなく、状況に応じて解釈を加え、小さな工夫を重ねています。その実践の積み重ねが、組織の能力を少しずつ変容させていくのです。本セミナーを通じて、組織の日常業務に潜む力学を理解し、組織開発や変革推進の実務に応用可能な視点を提供しました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
多大な労力をかけて新しい評価制度や業務プロセスを導入したにもかかわらず、現場の行動がなかなか変わらない、あるいは経営層が掲げる理念が現場に浸透しない、といった経験はないでしょうか。一方で、詳細なマニュアルが存在するわけでもないのに、なぜか円滑に業務が遂行され、高い成果を上げている組織やチームも存在します。
これらの現象の背景には、私たちが普段あまり意識することのない、組織に根ざした「当たり前のやり方」、すなわち「組織ルーティン」が関わっています。ルーティンと聞くと、画一的で創造性のない作業を想像するかもしれませんが、近年の研究は、それが組織の安定性を支えると同時に、変化や学習を生み出す源泉でもあるという、複雑で動的な側面を明らかにしつつあります。
本講演では、この組織ルーティンという視点を通して、組織における安定と変化のメカニズムを検討し、組織開発や変革推進に応用可能な知見を提供していきます。
ルーティンの正体:「当たり前」を分解する
組織におけるルーティンを「決まりきった作業手順」と捉えるのは、その一面しか見ていません。実際のルーティンは、手順書以上の、より複雑な構造を持っています。近年の経営学の研究では、組織ルーティンを「理念」「行動」「モノ」という三つの側面が相互に作用しあう動的なシステムとして捉える視点が提示されています[1]。
第一の「理念」とは、そのルーティンがどのようなものであるかを示す、人々の頭の中にある抽象的な理解や共有されたイメージを指します。いわばルーティンの「脚本」や「設計図」に相当する部分です。
第二の「行動」は、理念とは対照的に、特定の場面で、特定の人々によって実際に行われる具体的な行為の連なりです。理念という脚本を、現場の状況に合わせて人々が「上演」する、一回性の実践と言えます。そこには個人の技能や即興的な判断、チーム内の相互作用といった現実の動きが含まれます。
第三の「モノ」は、マニュアルやチェックリスト、情報システム、あるいはオフィスのレイアウトといった、ルーティンの実行を助けたり制約したりする物理的な事物です。これら三つの側面は互いに影響を与え合っており、例えば日々の行動の積み重ねが、理念を少しずつ更新していくこともあります。
三側面でルーティンを捉えることの重要性は、理念と現実の行動との間に「乖離」が生じ得るという点を明らかにすることにあります。人々が頭で理解している「あるべき姿」と、現場で実際に行われていることの間には、しばしば隔たりが見られます。この乖離の存在を実証した研究があります。
ある研究において、旅行代理店のエージェントと大学図書館のレファレンス係、両者の業務が比較分析されました。調査手法は、双方へのインタビューを通じて、各自の仕事の多様性に関する認識を問うものです。これはルーティンの「理念」の側面を探る試みと言えます。結果、旅行代理店側は、扱う商品が三種類(航空券、ホテル、レンタカー)に限定されるため、仕事の多様性は低いと答えました。他方、図書館側は、あらゆる分野の質問に対応することから、仕事の多様性は極めて高いと考えていました。
しかしながら、続いて両者の実際の業務、つまり「行動」の側面を観察すると、インタビューでの回答とは全く逆の実態が明らかになりました。旅行代理店の仕事は、顧客の入り組んだ要望に応える多様な手続きから成り、極めて複雑でした。それとは対照的に、図書館のレファレンス係と利用者間の応対は、より単純で反復的な型で成り立っていました。
同様の乖離は、別の金融機関を対象とした研究でも観察されています。この研究では、四つの異なる部署を対象に、ルーティンの多様性について調査が行われました。この調査においても、アンケートによる理念上の多様性と、行動観察から判明した現実の多様性には、正反対の結果が見られました。多様性が低いと認識された部署の行動は実際には変化に富み、逆に多様性が高いと認識された部署の行動は、より定型的なものだったのです。
これらの事例が示唆するのは、ルーティンのある一つの側面だけを見て、その全体像を判断してしまうことの危うさです。人々が「いつも通りの仕事だ」と感じていても、要するに理念が安定していても、日々の行動レベルでは大きな変化が起きている可能性があります。逆に、組織が「新しいやり方を導入した」と宣言し、人々の意識が変わったとしても、客観的に見れば行動パターンは以前とほとんど変わっていないということも起こり得ます。
組織の実態を理解するためには、制度やマニュアルといった「モノ」を整えるだけでは不十分です。現場で何が行われているかという「行動」を観察し、社員がどのような認識を持っているかという「理念」を理解することが不可欠です。理念と行動のズレが、組織を理解するための出発点となります。
なぜ組織は変われないのか:安定性のメカニズム
組織変革を進める上で、現場がなかなか変わらないという壁に直面することがあります。変化への抵抗は、従業員の怠慢や反抗心から生じていると単純に結論づけられるかもしれませんが、実態は複雑です。ルーティンが維持される背景には、従業員による合理的な判断が存在する場合があります。
この論点を明確にしたのが、ある州立大学の住居部門を対象とした調査研究です[2]。研究対象は、寮の維持・改修予算の配分を決める「予算編成ルーティン」でした。
もともと三つの主要課の現場マネージャーは、各々が個別に予算要求リストを提出する形式でした。しかし管理職は、マネージャー間の協力を促し、建物全体で優先順位付けした「単一リスト」を提出するよう要求しました。その背景には、現場が各課の利益を超え、建物全体に連帯責任を持つべきだ、という理想がありました。しかし、この試みは何年にもわたって失敗し、現場からは相変わらず部門ごとにバラバラのリストが提出され続けました。
一見すると、これは現場が変化に抵抗した事例に見えます。ところが、研究者が参与観察を通じて明らかにしたのは、管理職が語る理想と、組織の日常で実際に行われている行動との間に、埋めがたい矛盾があったことでした。現場のマネージャーたちは、上司の言葉よりも、日々の業務で目の当たりにする組織の現実から「この組織で本当に意味のある行動は何か」を学び取り、古いやり方を続けるという合理的な判断を下していました。
この矛盾は三つの側面に現れていました。一つ目は「協調」です。管理職は現場に協力を求めながら、自分たち自身は予算会議の場で、限られた予算を奪い合う競争的な交渉を繰り広げていました。これは、結局は自分の課の利益が最優先されるというメッセージを現場に発信していました。
二つ目は「対等な権力」です。協力の前提となる現場マネージャー間の対等な関係が、現実には存在しませんでした。三つ目は「管理者意識」です。管理職は現場に当事者意識を求めましたが、実際には、建物の運営に関する重要な決定の多くが、現場の権限が及ばないところで行われていました。
これらの事実が示すのは、現場マネージャーが怠慢や反抗心によって変化を拒否したのではないという点です。彼ら彼女らは組織の現実を見つめ、「理想を謳う言葉より、競争や階層こそが現実を動かす」との理解を形成しました。この認識を元に、旧来の手法を継続することが最も合理的な行動だと結論付けました。ルーティンの安定とは、無意識の繰り返しではなく、参加者が状況を解釈し、最善の行動を意識的に選び続ける努力が生み出すものだと言えます。
新しいルールを導入しても組織が変わらないもう一つの要因として、人間の記憶の仕組みが関わっています。頭では新しいルールを理解していても、長年かけて体に染みついた仕事の進め方は、そう簡単には上書きできません。この困難さの根源を明らかにしたのが、あるフランスの食肉加工企業が国際的な品質基準を導入しようとした際の事例研究です[3]。
この企業は、大手顧客からの要求で、国際的な品質基準であるISO規格を導入することを決定しました。これは、作業手順をすべて文書化し、そのルールに従うことを求める厳格なシステムです。しかし、このトップダウンでのルール導入は、現場で様々な困難に直面しました。
第一に、政治的な側面からの抵抗がありました。経験と勘を頼りに仕事を進めてきた従業員にとって、事細かに作業方法を指示され、記録を求められることは、自分たちの自律性を奪われるように感じられました。第二に、従業員は認知的な過負荷に苦しめられました。新しい手順、膨大な記録、不慣れな検査機器など、覚えるべきこと、やるべきことが一度に押し寄せ、現場は飽和状態に陥りました。皮肉なことに、品質を高めるためのルール導入が、この混乱によってかえってミスを誘発し、一時期、製品の汚染が増加する事態まで発生しました。
三つ目の壁は、身体に深く刻まれた記憶でした。人間の記憶は、言葉で説明可能な「宣言的記憶」と、身体が記憶している「手続き的記憶」に大別されます。マニュアルの内容は「宣言的記憶」としてすぐに理解できても、「手続き的記憶」、要するに長年の繰り返しで無意識に動く体の習慣は容易に変わりません。新たな手法が自然な動作として定着するには、多くの時間と実践の繰り返しが求められたのです。
経営陣は、ルールを押し付けるだけでは変革は進まないことを痛感し、アプローチを変更します。従業員に対して集中的な訓練プログラムを実施し、新しいスキルを習得した従業員を昇進させるなど、変化への動機づけとなる仕組みを整えました。また、一人の従業員が定期的に異なる作業を担当する「タスクローテーション」も取り入れました。
この事例が示すように、組織に変革をもたらすには、ルールを提示するだけでなく、現場が直面する理想と現実の矛盾を解消する必要があります。そして、新しい行動が「文化」として根付くまで、研修やタスクローテーションなどを通じて、辛抱強く学習プロセスを支援することが重要になるのです。
これらの知見を踏まえ、人事としてはどのような行動をとることができるでしょうか。例えば、「現場で起きている矛盾の発見」を目的とした対話の機会を設けることが有効でしょう。新しい制度を導入する際には、説明会のような一方通行の情報伝達に終始するのではなく、現場の管理職や従業員を対象に「新しい制度と、普段大切にしているやり方との間で、何か矛盾を感じる点はありませんか」といった問いを投げかけます。
大学寮の事例が示したように、従業員は組織の現実を敏感に感じ取っています。彼ら彼女らが抱く違和感や懸念に耳を傾けることで、制度設計の段階では見えなかった矛盾点を特定し、変革への心理的な障壁を下げることができます。
「手続き的記憶の上書き」を意識した学習プログラムを設計することも有効かもしれません。食肉加工企業の事例が示したように、一度の研修で行動を変えることは困難です。
新ルールの全体像を理解してもらう座学を行い(宣言的記憶へのインプット)、少人数でのロールプレイングやシミュレーションを通じて、実際に体を動かしながら新しい手順を試す機会を設けます(手続き的記憶の形成)。数週間後にフォローの場を設け、実践してみて分かった疑問や課題を共有し合うことで、新しい行動の定着を支援していくといった、段階的なアプローチが求められます。
ルーティンは「変化の源泉」である
組織の安定性を支えるルーティンですが、それは決して固定的なものではありません。日々の業務の実践の中から、組織の変化や学習を生み出す源泉となり得ます。決まりきった仕事に見えるルーティンの内部で、絶えず変化が起きていることを示したのが、ある大学の学生寮を対象とした約4年間にわたる長期的な観察研究です[4]。
研究者は、寮の運営に関わる人々の中に身を置き、予算編成、スタッフの採用と訓練、学生の入退去といった、毎年繰り返される複数のルーティンを追い続けました。当初は「大きくは変わらない行動パターン」という前提で観察を始めましたが、現場で目にしたのは、多くのルーティンが年々その姿を変えていく様子でした。
一例として、学生が寮を退去する際の「損傷査定」ルーティンが挙げられます。これまでの手順では、学生の退室後に職員が部屋を点検し、修理費用を請求する、という事務的な流れでした。しかし、この方法では学生の責任感を育む好機を逃している、と現場の責任者は感じていたのです。
そのため、手順の変更が実行されました。学生が退去するより前に、本人と職員が共に部屋の状況を確認し、責任の所在をその場で協議する形へと改めました。この変更は、単なる手続きの修正に留まらず、学生の当事者意識を高め、職員との対話による教育的な関与を深めるという新しい価値を創出しました。これは、旧来の方法が持つ欠陥を直す「修復」であり、同時に話し合いという新たな機会を設ける「拡張」でもありました。
また、学生が入居する際の「ムーブイン」というルーティンも変化を遂げました。当初は各寮が個別に対応していたため、周辺は毎年ひどい交通渋滞に見舞われていました。この問題を解決するため、組織は中央で交通整理を統括する方式へ移行します。その結果、入居プロセスはスムーズになりました。
しかし、変化はそこで終わりませんでした。一度成功を収めると、関係者の間では「もっと良くできるはずだ」という意識が芽生え、理想の水準が引き上げられました。次はロビーの混雑緩和へと課題が移るなど、より高みを目指し続ける「ストライビング」という反応が見られました。
このように、ルーティンは固定的な規則ではなく、日々の実践の中で修復・拡張・ストライビングといった反応が繰り返されることで、連続的な変化を生み出す装置として機能していきます。日々の小さな工夫や問題解決の積み重ねが、ルーティンを進化させ、組織の能力を高めていくのです。
このような変化は、比較的柔軟な組織に限った話なのでしょうか。規則が厳格に定められ、ITシステムによって高度に自動化された、成熟した組織のルーティンは固定的で安定しているのでしょうか。この疑問を確かめるため、ノルウェーにある四つの別組織で実施されている「請求書処理」の工程が、大規模なデータによって分析されています[5]。請求書処理とは、会計規則や監査要件に制約される、構造化された業務です。
この研究では、調査の方法として、ワークフローシステムの監査ログに記録された、約5ヶ月間にわたる3万件以上の業務記録を分析対象としました。一件の請求書が処理されるまでの一連のアクション(誰が、いつ、何をしたか)を一つのシーケンスとして捉え、そのパターンを定量的に解析しました。もしルーティンが固定的であるならば、観測されるシーケンスのパターンは少数に集約され、時間が経ってもその構造は変わらないはずです。
しかし、分析で得られた結果は、直観的な想定とは違う様相を示しました。まず、実行されたパターンの多様性が挙げられます。分析対象の全組織において、数百から数千に及ぶ固有のシーケンスが見つかりました。とりわけ、複数の担当者による承認を要するプロセスで、極めて多くのバリエーションが確認されました。これは、ルーティンが決まった手順の反復ではなく、膨大な数の多様な遂行パターンの集合体であることの証拠です。
第二に、時間の経過に伴う変化です。5ヶ月という比較的短い期間を前半と後半に分けて比較したところ、多くのルーティンで、アクションのつながり方、すなわち遷移の構造が統計的に有意に変化していることが確認されました。特定の外部的な出来事があったわけではないにもかかわらず、ルーティンの実行パターンは、いわば「漂流」するように、その姿を変え続けていました。
この実証研究から浮かび上がるのは、たとえ厳格で安定しているように見えるルーティンであっても、その内実を細かく見れば、それは決して変わらない世界ではなく、人と技術の相互作用の中で絶えず変化している現象であるということです。
ルーティンが持つ変化の力を組織の資産に変えるために、人事として取り組めることは何でしょうか。
一つ目は、「現場の小さな工夫を収集する仕組み」の構築です。大掛かりな業務改善提案制度である必要はありません。例えば、社内のコミュニケーションツールに「ちょっと良くしたこと」を気軽に投稿できるチャンネルを開設したり、チームの定例会議の冒頭5分を「私のカイゼン共有タイム」としたりするなど、現場の従業員が日々の業務の中で見出した小さな工夫や成功体験を、手間なく共有できる場を作ります。学生寮の事例のように、価値ある変化は現場の実践から生まれます。
二つ目は、「バリエーション(逸脱)の背景を探る」ことを目的としたミーティングの開催です。請求書処理の事例が示したように、標準的な手順から外れた行動は、必ずしもエラーや怠慢の結果とは限りません。特定の業務プロセスをテーマに選び、担当者を集めて、実際の業務の進め方や判断のプロセスについて話し合ってもらいます。そこでは、「なぜマニュアルと違うやり方をしているのか」を問い詰めるのではなく、「そのやり方に至った背景には、どのような顧客の要望や現場ならではの制約があったのか」を明らかにすることに主眼を置きます。
こうした対話を通じて、マニュアルには書かれていない実践的な知恵を組織の共有知へと転換させることができます。
おわりに
本講演では、組織ルーティンという概念を「理念・行動・モノ」の三側面から分解し、それが組織の安定性と変化の両方に関わっていることを見てきました。組織が変わらない背景には、現場の合理的な判断や、体に染みついた記憶の壁といった、複雑なメカニズムが存在します。一方で、固定的に見えるルーティンが、日々の実践を通じて絶えず変化し、組織の学習や適応の源泉となっていることも確認しました。
組織ルーティンは、固定的で管理すべき対象ではなく、組織の安定を支え、同時に変化を生み出す「生きたシステム」です。それは日々の業務を通じて、人と人との「つながり」を形成し、物事の進め方に対する「共有された理解」を育む、組織の社会的な土台でもあります。
ぜひ皆さんの組織の「当たり前」を見つめ直してみてください。なぜ、そのやり方が続いているのでしょうか。現場では、どのような工夫や困難が生まれているのでしょうか。その「当たり前」の中に、組織の本来の強み、そして次なる変革を成功に導くための種が眠っているかもしれません。
Q&A
Q:コンプライアンスやガバナンス関連のルールについて質問です。会社側はマニュアルを配布したり、社員に研修を行って教育しようとしたりしますが、それでも現場での不正やうっかりミスはなくなりません。社員へのルール徹底のためには、他にどのような工夫が必要でしょうか。
セミナーでお話ししたルーティンの3要素という枠組みで考えると分かりやすいかもしれません。ルーティンには「理念」「行動」「モノ」という3つの要素がありました。ご質問のケースは、このうち「理念」と「モノ」を中心に働きかけようとしている状態です。「本来こうあるべき」と言葉で伝えるのは理念への、マニュアル配布はモノへのアプローチです。しかし、一番重要である「行動」、要するに実践の現場への働きかけが十分ではないのかもしれません。
実際に仕事の中でどう振る舞うべきか、現在の行動をどう修正すべきか。そういった具体的な行動レベルでのフィードバックが求められます。マニュアルを渡すことに比べると、一人ひとりの行動への介入は手間がかかり、手薄になりやすいでしょう。しかし、重要なルールを単なるお題目ではなく、「組織ルーティン」として定着させるには、行動のレベルまで細心の注意を払う必要があります。現場に入り込み、実践を通じてルールを浸透させていくプロセスが、不正やミスを減らす工夫だと言えます。
Q:「現場が変わらないのは、現場にとってはそれが合理的判断だからである」というお話に納得しました。しかし、その現場レベルでの合理性が、全社的な視点で見ると「部分最適」になってしまっている場合、現場のマネージャーに対してどのように対話をしていけばよいでしょうか。
現場には現場の理屈があり、それを否定して「全社視点を持て」と抽象的に伝えても、なかなか響かないのが現実です。有効なのは、時間軸を変えて考えることです。現場が信じている合理性を、中長期的な目線で捉え直してみるのです。今は良くても、そのやり方を続けることが、将来的には自分たちの首を絞めることになるかもしれない。そういった可能性を示唆していきます。
例えば、外部環境の変化を材料にします。「世の中が変わる中で、今の最適化を続けるとどうなるか」をシミュレーションします。現在のやり方に固執することが、将来的にリスクになるというシナリオを共有します。そうすることで、「自分たちが守ろうとしている利益を将来も確保したいなら、今変化することが必要だ」と気づいてもらえる可能性があります。
現場の合理性を否定するのではなく、それを守るためにも変化が必要だという文脈で語ることで、現場の理屈と全社的な方向性がうまく噛み合うようになるはずです。
Q:手続き的記憶が変化を阻むというお話がありましたが、これを逆手にとり、変革したい新しい行動を強制的に「型」として反復練習させることは有効でしょうか。
型から入るというやり方自体は有効な手段の一つです。型を反復させれば、短期的には行動変容につながります。しかし、この方法にはリスクも潜んでいます。反復を強制すれば、現場には「やらされ感」が残り、監視の目がなくなった瞬間に元のやり方に戻ってしまう可能性があります。「言われている間だけやればいい」となってしまい、定着しないのです。
手続き的記憶を利用すること自体は良いのですが、同時並行で意味付けを行いましょう。「なぜこの型が必要なのか」という背景や理由、すなわち「理念」をしっかり説明し続けることです。
行動だけを先行させても、理念だけを説いても、ルーティンは定着しません。行動を変えさせながら、同時に理念も更新していく。行動と理念を行ったり来たりさせながら、その両方を往復することで、新しいルーティンが組織に深く根付いていくのだと思います。
Q:ルーティンの変化を推奨すると、現場での勝手な変更がリスクになるのではないかと心配です。会社としての統制と、現場の自律的な変化のバランスをどう設計していけばよいですか。
そのバランスは多くの企業が悩む点です。「工夫して変えよう」と推奨した結果、コンプライアンス違反などが起きては本末転倒です。
一つの考え方として、ルーティンの中に「変えてはいけない領域」と「工夫して変えてもいい領域」を区分けすることをお勧めします。法規制や安全に関わる部分は、勝手に変えてはいけない領域として厳守してもらいます。一方で、それ以外の業務効率やサービス向上に関わる手順などは、現場の裁量で工夫できる領域として開放するのです。
避けるべきなのは、リスクを恐れて「すべての変更を禁止する」ことです。何でも禁止してがんじがらめにすると、組織は環境変化に適応できなくなります。ルーティンの変化は組織が適応するための術の一つです。守るべきところは守りつつ、それ以外では実験や試行錯誤ができる余地を残しておく設計が、組織運営において重要です。
Q:現場から生まれる様々な業務のバリエーション(変異)について、それが単なるミスやサボりなのか、それとも意味のある逸脱なのかを見分けるにはどうしたらよいでしょうか。
難しい問題ですが、見分けるための切り口を二つ提案します。一つ目は「結果」です。その逸脱した行動によって、顧客や次の工程に対して提供する価値が高まったのかどうか。品質やスピードが向上しているなら、それは「良い逸脱」と言えます。
二つ目は「意図」です。なぜその逸脱をしたのかという動機です。例えば「楽をしたかっただけ」という意図で、価値も生まれていないなら、それは「悪い逸脱」であり、是正が必要です。しかし、意図が「もっと良くしよう」という実験的な動機に基づいていた場合はどうでしょうか。試行錯誤の結果、今回は失敗したとしても、それは現状を変えようと挑戦した結果です。そこには「次はどうすればうまくいくか」という学習の種が含まれています。
無自覚な逸脱とは異なり、意図を持って挑戦した結果の失敗は、組織にとって学びのある逸脱と捉えられます。結果だけでなく、背後にどのような意図や試行錯誤があったのかまで踏み込んで見極めることが大事です。
脚注
[1] Pentland, B. T., and Feldman, M. S. (2005). Organizational routines as a unit of analysis. Industrial and Corporate Change, 14(5), 793-815.
[2] Feldman, M. S. (2003). A performative perspective on stability and change in organizational routines. Industrial and Corporate Change, 12(4), 727-752.
[3] Lazaric, N., and Denis, B. (2005). Routinization and memorization of tasks in a workshop: The case of the introduction of ISO norms. Industrial and Corporate Change, 14(5), 873-896.
[4] Feldman, M. S. (2000). Organizational routines as a source of continuous change. Organization Science, 11(6), 611-629.
[5] Pentland, B. T., Harem, T., and Hillison, D. (2011). The (N)ever-changing world: Stability and change in organizational routines. Organization Science, 22(6), 1369-1383.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






