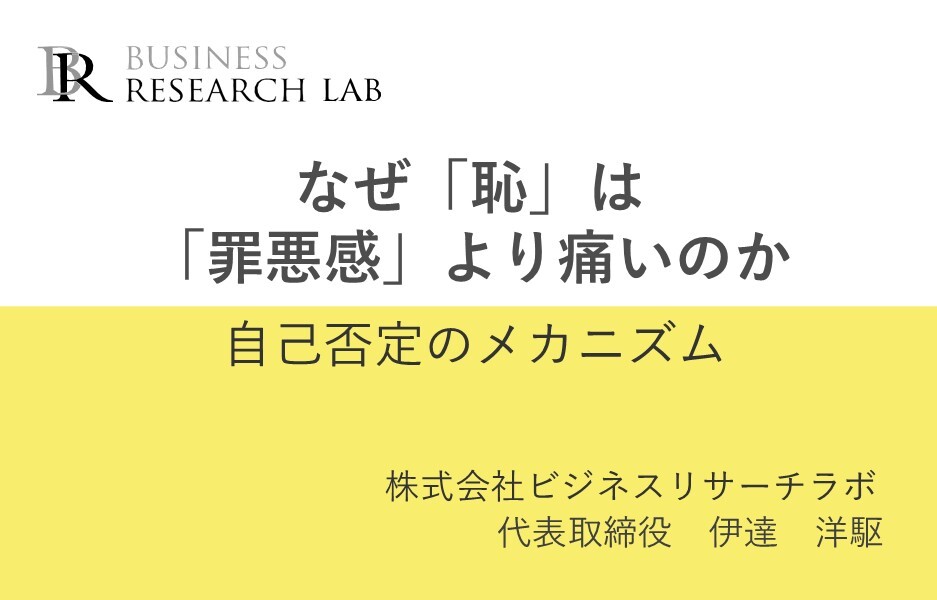2026年1月30日
なぜ「恥」は「罪悪感」より痛いのか:自己否定のメカニズム
誰しも一度は、顔から火が出るような思いをしたことがあるでしょう。人前で大きな失敗をしてしまった時、自分の未熟さを痛感した時、あるいは誰かを深く傷つけてしまったと気づいた時。私たちの胸に込み上げてくる、あの居た堪れない感覚。私たちはそれを総称して「恥ずかしい」と表現します。
この「恥」という感情は、実は非常に複雑で、多面的な顔を持っています。似たような状況で感じる「罪悪感」や、とっさの失態に対する「当惑」とは、何が違うのでしょうか。これらの感情を一緒くたにしてしまうと、私たちは自分自身や他者が経験している心の痛みの本質を見誤ってしまうかもしれません。
恥は、時に私たちを成長させるバネになる一方で、心を蝕み、他者への攻撃性へと転化することもあります。この感情が持つ力は侮れません。本コラムでは、「恥」という感情を、心理学の知見を頼りに解き明かしていきます。恥とよく似た感情である「罪悪感」や「当惑」との境界線を明らかにし、さらには「恥」そのものの中に存在する、異なる性質を持つ側面にも光を当てます。
恥は罪悪感と違い、行為でなく自己全体を否定する痛い感情
私たちは日常生活の中で、「恥」や「罪悪感」、あるいは「当惑」といった言葉を、時として同じような意味合いで使うことがあります。しかし、これらの感情は本当に同じものなのでしょうか。それとも、単に強さが違うだけなのでしょうか。この問いに答えるため、ある研究者たちは、大学生たちに協力を仰ぎ、それぞれの感情がどのような体験なのかを調べました[1]。
この調査では、参加者一人ひとりに、過去に経験した「恥」「罪悪感」「当惑」の三つの感情について、具体的な出来事を文章で記述してもらいました。あえて感情の定義は伝えず、参加者自身の解釈に委ねる形をとりました。
記述の後、それぞれの体験について、多角的な質問に答えてもらいました。例えば、その感情がどれほど強かったか、どれくらい続いたか、隠したいと思ったか、償いたいと思ったか、といった感情の質に関する質問。あるいは、その出来事が起きた時、誰が、何人くらい周りにいたのか、といった社会的な状況に関する質問です。これらの回答を分析することで、三つの感情の輪郭が浮かび上がってきました。
感情が生まれる状況について、興味深い事実が判明しました。古くから、恥は他者の目がある「公的な」場面で、罪悪感は一人の時でも感じる「私的な」場面で生じる、と考えられてきました。しかし、調査結果はこの通説を覆しました。恥も罪悪感も、他者がいる状況で経験されることが多かったものの、どちらも一人でいる時に経験されることも決して少なくなかったのです。むしろ、一人で経験される割合は、罪悪感よりも恥の方がわずかに高いという結果でした。
このことから、「恥は公的、罪悪感は私的」という単純な線引きは、実態とは異なることがわかります。
一方で、「当惑」は、その性質が際立っていました。当惑を感じた出来事のほとんどすべてが、他者の前で起きており、まさに「公的な感情」と呼べるものでした。また、当惑は、恥や罪悪感に比べて、より多くの人の前で起こるという性質も持っていました。親しい友人の前で感じやすい恥や罪悪感に対し、当惑は知人や見知らぬ人の前で起こりやすいという違いも見られました。
感情の「質」に目を向けてみましょう。参加者の評価から、三つの感情は体験として異なっていることがわかりました。特に当惑は、他の二つとは大きく異なる感情でした。当惑は、三つの中で最も不快感が低く、最も短時間で消え去る感情と評価されました。道徳的な過ちというよりは、ささいな社会的なヘマから生じることが多く、後から笑い話にできるような軽い出来事と捉えられていました。
対照的に、恥と罪悪感は、どちらも非常に不快で、深刻な状況から生じる、長く続く強い感情だと評価されました。参加者は強い責任感や後悔を感じ、償いをしたいという気持ちを報告しています。しかし、この二つの間にも違いが存在しました。恥は、罪悪感よりも「痛みを伴う強烈な」感情でした。恥を感じている時、人は自分が「小さく」「劣っている」と感じ、他者から孤立している感覚を強く抱きます。その結果、自分のしたことを隠したいという欲求が強まり、自分の非を認めたくないという気持ちが、罪悪感の時よりも顕著になります。
この違いは、評価の焦点がどこにあるかに起因すると考えられます。罪悪感が「私はひどい『こと』をしてしまった」という特定の『行為』への後悔であるのに対し、恥は「『私』はダメな人間だ」という『自己全体』への否定感なのです。行為ではなく、自己が欠陥品であるかのように感じる。この全体的な自己否定が、恥という感情の核にあり、その耐え難い痛みの源泉となっていると言えます。
従来の「恥」を分解し、自己改善につながる恥と拒絶感を区別
恥が自己全体への否定という痛みを伴う感情であることが見えてきました。この性質から、恥は人を隠れさせ、回避させる、非生産的な感情だと長らく考えられてきました。しかし、本当にそうでしょうか。「恥ずかしい」という思いが、次こそはと奮起するきっかけになった経験はないでしょうか。この矛盾を解き明かすために、一部の研究者たちは、「恥」という一つの言葉で括られてきた感情を、もっと細かく分解して考える必要があると主張しています[2]。
そのモデルの中心にあるのは、道徳的な失敗を犯した時に、私たちが何を気にしているのかという視点です。一つは、自分自身の理想像である「自己像」への関心。もう一つは、他者の目に映る自分、すなわち「社会的イメージ」への関心です。この二つの関心軸から、失敗に対する評価と、それに伴う感情、行動への動機づけを整理し直しました。
まず考えられるのは、社会的イメージが損なわれ、他者から非難されたり、仲間外れにされたりすることを恐れるケースです。この「他者からの非難」という評価は、「拒絶感」や孤立感といった感情を引き起こします。この感情がもたらす痛みは非常に強く、人は自分を守るために、その場から逃げたり、失敗を隠したり、時には他者を攻撃したりといった「自己防衛」的な行動に走りやすくなります。
ここで重要なのは、この反応の引き金になっているのが、社会から排斥されることへの恐怖であり、これまで「恥」と呼ばれてきた現象の一部は、この「拒絶感」で説明できるのではないかということです。
関心の矛先が自分自身、つまり自己像に向けられる場合を考えます。ここで評価の仕方が二つに分かれます。一つは、失敗を「自分は根本的にダメな人間だ」という、全体的で変えようのない欠陥の証拠として捉えてしまう評価です。この評価は、強い「劣等感」や無力感、抑うつ気分につながります。これもまた、自己防衛的な行動や、あるいは無気力につながりやすいものです。かつての研究では、この劣等感も「恥」と混同されて測定されてきた可能性が指摘されています。
もう一つの自己像への評価は、新しい恥の理解の鍵を握ります。それは、失敗を、自分のある「特定の側面」における、修復可能な欠陥の表れだと評価するものです。例えば、「自分の誠実さが足りなかった」「思いやりが欠けていた」といったように、人格全体ではなく、改善可能な一部分の問題として捉えるのです。この「特定の自己欠陥」という評価から生まれる感情が、本来の「恥」であると、このモデルは考えます。
この種の恥は、全人格的なダメージではなく、あくまで変えることのできる自己の一側面への厳しい自己批判です。だからこそ、ここから生まれる最も合理的な行動は、その欠点を是正しようとする「自己改善」への動機づけです。不足を補うために努力したり、規範を学び直したりする。この自己改善への動きは、自然と、他者への謝罪や償い、関係修復といった「社会的改善」へとつながっていきます。
このように、「恥」という大きな傘の下に隠れていた感情を、「拒絶感」「劣等感」「自己改善につながる恥」とに分けて考えることで、なぜ恥がある時は人を立ち直らせ、ある時は人を追い詰めるのか、その仕組みが見えてきます。自己防衛的な反応を引き起こすのは、主に他者の目を気にするあまり生まれる「拒絶感」であり、自己全体を悲観する「劣等感」です。一方で、自分の変えられる部分に目を向けた「恥」は、明日への成長の糧となりうる側面を秘めています。
恥は公的な自己評価、罪悪感は私的な償いとして区別すべき
これまで、恥を自己全体への否定として捉え、さらにその中にも自己改善につながる側面があることを見てきました。ここで、最初の問いに立ち返ってみたいと思います。それは、恥と罪悪感を区別する上で、他者の存在、要するに「公的」か「私的」かという文脈は、どれほど意味を持つのかという点です。
最初の研究では、この区別は明確ではないとされましたが、別の視点からこの問題を深く探求した研究もあります[3]。その研究は、これまでの二つの主要な区別、すなわち「自己か行動か」という焦点の違いと、「公的か私的か」という文脈の違いを、対立するものとしてではなく、組み合わせることで両感情をより深く理解できると論じました。
まず、研究者たちは、過去に開発された複数の心理尺度を分析することから始めました。これらの尺度は、それぞれ異なる理論的背景(「自己か行動か」を重視するもの、「公的か私的か」を重視するものなど)に基づいて作られていましたが、いずれも個人の「恥を感じやすい傾向」と「罪悪感を覚えやすい傾向」を測定しようとするものでした。
大学生にこれらの尺度に答えてもらい、その結果を統計的に分析したところ、明快な構造が浮かび上がりました。開発の背景が異なるにもかかわらず、各尺度の「恥」に関する項目は一つの大きな「恥」の因子に、そして「罪悪感」に関する項目はもう一つの「罪悪感」の因子に、それぞれ綺麗にまとまったのです。これは、研究者たちが異なる言葉で説明しようとしてきたものの根底には、やはり「恥」と「罪悪感」という、区別されうる二つの安定した心理的特性が存在することを示唆しています。
これらの傾向が他の性格特性とどう関連するかも調べられました。その結果、恥を感じやすい傾向は、神経質さや自尊心の低さと結びついていました。一方で、罪悪感を覚えやすい傾向は、他者への共感的な配慮や、視点を変えて物事を考える力と結びついていました。
この発見を踏まえ、研究者たちは、実験的な手法を用いて、二つの感情がどのような状況で最も典型的に現れるのかを検証しました。大学生の参加者に、様々な違反行為が書かれたシナリオを読んでもらい、その状況でどのような反応をするかを想像して評価してもらいました。シナリオは操作されており、違反行為が他者に目撃される「公的な」状況と、誰にも見られていない「私的な」状況の二種類が用意されました。
また、評価してもらう反応も、「自分はひどい人間だと感じる」(自己への否定的評価)、「その場を離れたくなる」(回避行動)、「あんなことをすべきではなかったと感じる」(行動への否定的評価)、「謝罪したり、埋め合わせをしたりする」(接近行動)といったように分類されていました。
この実験から、二つの感情を区別する上で、文脈と反応の種類の両方が大切であることが明らかになりました。「恥」という感情と最も強く結びつくのは、「公的な」場面で失敗を犯した時に、「自分はダメな人間だ」と自己全体を否定的に評価する反応でした。他者の目に晒されているという状況が、自己への評価をより痛烈なものにします。
それに対して、「罪悪感」と最も強く結びつくのは、「私的な」場面で過ちを犯した時に、「謝罪や償いをしたい」と考える接近行動でした。誰に見られていなくても、自らの行為を正そうとする内的な動機づけ、これこそが罪悪感の本質的な姿だと言えます。他者の目を気にする自己防衛的な気持ちが少ない私的な状況だからこそ、他者への配慮や道徳的な責任感が純粋な形で現れるのかもしれません。
この結果は、二つの理論的区別が互いに補い合う関係にあることを教えてくれます。恥は、他者の視線を意識する「公的な」文脈で、その評価の対象が「自己」に向けられた時に最も鋭く現れる感情です。一方で、罪悪感は、他者の視線とは独立した「私的な」文脈で、その評価の対象が「行動」とその修復に向けられた時に、最も純粋な形で現れる感情です。
恥は怒りや他者非難につながるが、罪悪感はそれを抑制する
恥という感情が、自己全体に向けられた痛烈な自己否定であることを見てきました。これほどまでに辛い感情を抱えた時、私たちの心はどのようにその痛みに対処しようとするのでしょうか。黙って耐え忍び、自分の中に閉じこもるというのが、一般的なイメージかもしれません。しかし、心の防衛メカニズムは、時として予想外の形で機能します。ある研究は、恥と罪悪感が、私たちの内に秘めた「怒り」や他者への攻撃性と、全く逆の関係にある可能性を明らかにしました[4]。
この研究の出発点には、臨床現場などからの観察がありました。それは、深く傷つけられた自尊心、すなわち恥の感情が、自分を守るために「外向きの怒り」に転化することがあるというものです。耐え難い自己否定の痛みから逃れるため、その原因を他者に求め、非難することで、一時的に心のバランスを保とうとします。この仮説を検証するため、研究者たちは大学生を対象に、彼ら彼女らがどれくらい恥や罪悪感を感じやすい傾向にあるか、そして、どれくらい怒りや敵意を抱きやすいかを、複数の質問紙を用いて測定しました。
ここでの分析の工夫は、恥と罪悪感の重なり合う部分を統計的に分離した点にあります。実際の経験では、恥と罪悪感は同時に感じられることも多いため、両者の影響が混ざり合ってしまいます。そこで、罪悪感の影響を取り除いた「純粋な恥」と、恥の影響を取り除いた「純粋な罪悪感」が、それぞれ怒りや敵意とどう結びつくかを分析しました。
結果、恥を感じやすい傾向は、怒りを感じやすい気質、敵意、他者を非難する考え方、さらには疑り深さや恨みがましさといった、怒りや敵意に関連する様々な側面と一貫して正の関連を持っていました。恥を感じやすい人ほど、他者に対して怒りや敵意を向けやすいという関係が見出されたのです。
対照的に、「純粋な罪悪感」は、これらの怒りや敵意の指標と、ことごとく負の関連を示しました。罪悪感を覚えやすい傾向を持つ人ほど、怒りを感じにくく、他者への敵意も低いという関係です。罪悪感は、怒りを抑制する方向に働くようです。
この対照的な結果は、二つの感情の焦点の違いから説明できます。恥は、自己全体が攻撃される痛みを伴います。この痛みはあまりに強烈なため、人は「自分だけがこんなに苦しむのは不公平だ」と感じ、その苦しみの原因を外に探そうとします。その結果、他者を非難し、怒りを向けるという防衛的な反応が生まれやすいのです。自分の内側に向いていた否定の矢印を、外側に向け変えることで、崩れそうな自己を守ろうとする心の働きと言えます。
一方、罪悪感は、あくまで特定の「行為」に焦点が当たります。自己全体が脅かされるわけではないため、防衛的になる必要性が低いのです。むしろ、自分の行為が他者に与えた損害に意識が向かい、共感や償いの気持ちが喚起されます。この他者への配慮は、他者を非難したり攻撃したりする怒りとは、相容れないものです。したがって、罪悪感は怒りの感情を鎮める方向に作用すると考えられます。
一つ、特筆すべき点があります。恥は怒りや敵意と強く結びついていましたが、それは必ずしも、殴ったり罵倒したりといった、直接的な攻撃行動に結びつくわけではありませんでした。関連が見られたのは、内面のイライラや恨み、間接的な形での敵意の表出でした。これは、恥が、内にこもる性質と、外に発散される怒りの、両方の側面を併せ持っていることを示唆しているのかもしれません。
脚注
[1] Tangney, J. P., Miller, R. S., Flicker, L., and Barlow, D. H. (1996). Are shame, guilt, and embarrassment distinct emotions? Journal of Personality and Social Psychology, 70(6), 1256-1269.
[2] Gausel, N., and Leach, C. W. (2011). Concern for self-image and social image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 41, 468-478.
[3] Wolf, S. T., Cohen, T. R., Panter, A. T., and Insko, C. A. (2010). Shame proneness and guilt proneness: Toward the further understanding of reactions to public and private transgressions. Self and Identity, 9, 337-362.
[4] Tangney, J. P., Wagner, P., Fletcher, C., and Gramzow, R. (1992). Shamed into anger? The relation of shame and guilt to anger and self-reported aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 62(4), 669-675.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。