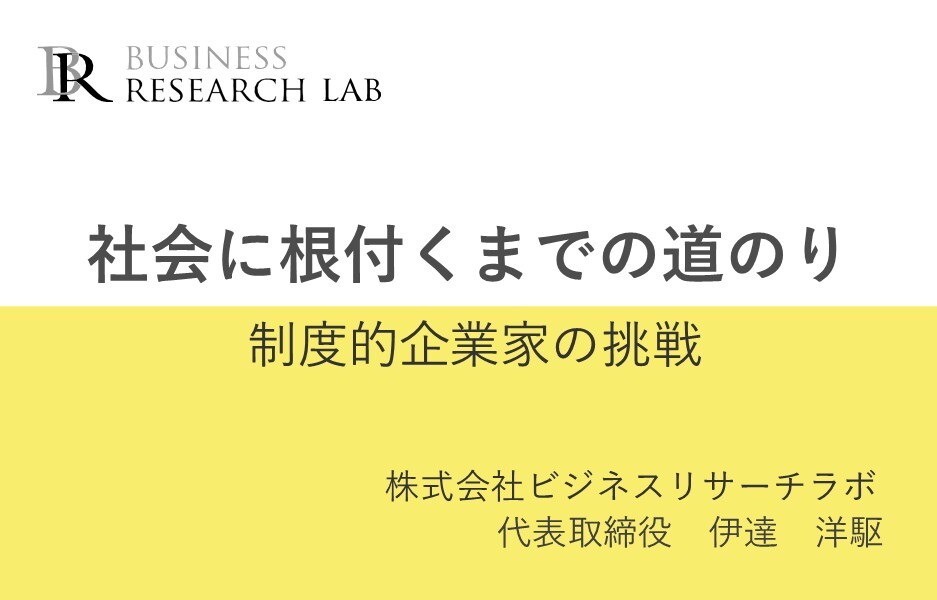2026年1月30日
社会に根付くまでの道のり:制度的企業家の挑戦
私たちの周りでは、新しいビジネスや画期的なアイデアが生まれています。しかし、そのすべてが社会に受け入れられ、定着するわけではありません。多くは「常識外れだ」「必要ない」といった抵抗に遭い、消えていきます。成功するイノベーションとそうでないものの違いは、どこにあるのでしょうか。製品やサービスの質が高いだけでは、十分ではないようです。
本コラムでは、新しい分野や組織が社会的な「正しさ」を認められ、当たり前の存在になっていくプロセス、すなわち「正統化」の道のりを探ります。鍵を握るのは、「制度的企業家」と呼ばれる人々です。彼ら彼女らは、新しい事業を立ち上げるだけではありません。社会の価値観や常識を巧みに再構築し、自らの活動のための場所を創り出していきます。
ここでは、ホームレス支援の社会事業、経営コンサルティングの黎明期、写真文化を創り上げたカメラメーカー、新興国の高級病院という、異なる事例を掘り下げていきます。これらの物語を通じて、新しいものが社会に根付くまでの知的な格闘の様子を検討していきましょう。
事業が失敗しても新しい組織の型を社会に残す
新しい事業の成功は、一般的に商業的な存続によって測られます。しかし、事業が経済的に立ち行かなくなったとしても、その挑戦が社会に何も残さないわけではありません。ある事業が失敗に終わる一方で、それが提示した新しい組織のあり方、「組織の型」が社会的な正統性を獲得し、後続の者たちに引き継がれていくことがあります。個別の企業の成否と、それが推進する社会的なプロジェクトの成否は、必ずしも一致しないのです。この複雑な関係性を、英国のある社会企業の事例から紐解いてみましょう[1]。
分析の中心は、「Aspire」という社会企業です。1990年代後半の英国で設立され、当時のホームレス支援のあり方に疑問を抱いていました。宿泊や食事の提供は一時しのぎであり、根本原因である失業問題は手付かずでした。彼ら彼女らは、ホームレスの人々に安定した有給の仕事とトレーニング、生活支援を提供することが、持続可能な解決策だと考えました。
そこで生み出されたのが、営利目的のカタログ宅配ビジネスの仕組みを活用し、ホームレスの人々を雇用するという前例のない事業モデルでした。これは、「利益の最大化」を目指す営利企業の論理と、「社会貢献」を第一とする非営利の支援の論理という、相容れない二つの価値観を橋渡しする試みでした。Aspireは寄付に頼らず、投資家に対して経済的・社会的なリターンの両方を約束する、自立したビジネスとして設計されました。
この革新的なアイデアは、当時の英国政府の政策とも合致し、全国的な支援を受けるに至ります。Aspireはフランチャイズ方式で急速に事業を拡大し、「ホームレスを雇用する社会企業」という新しい組織の型は、有望なアプローチとして広く認識されるようになりました。
しかし、商業的な道のりは平坦ではありませんでした。全国規模の事業を運営する基盤整備は難航し、多くのフランチャイズが経営難に陥りました。創業者たちは社会的なビジョンに優れていましたが、商業的な経営手腕には長けていなかったのです。最終的に、Aspireグループは事業を停止し、清算されました。
ここで見過ごせないのは、Aspireという個別の事業は失敗したものの、彼ら彼女らが創り出した「組織の型」は生き続けたという事実です。Aspireが消えた後も、同様のモデルを採用する組織が次々と生まれ、英国のホームレス支援分野で社会企業というアプローチが定着していきました。
この事例は、新しい組織の型が創造されるプロセスが、複数の階層にまたがる複雑な活動から成ることを明らかにします。個人というミクロなレベルでは、創業者たちの認知的な働きがありました。彼ら彼女らはホームレス問題を「住居の問題」から「雇用の問題」へと捉え直し、「もしビジネスが慈善活動よりも優れた支援を提供できるとしたら」という常識を覆す未来を想像しました。
組織というメソなレベルでは、アイデアを具体的な形にする設計作業が行われました。既存の営利ビジネスのモデルを「文化的な道具箱」として利用し、非営利の支援活動から得た要素(安定した固定給の保証など)を組み込み、新しい組織の設計図を構築しました。それに加えて、この新しい組織がなぜ優れているのかを説明する一貫した物語を創り上げ、多様な関係者から支持を集めました。
社会というマクロなレベルでは、この新しい型が社会全体に受け入れられるための活動が展開されました。創業者たちは、自分たちの取り組みを、当時の英国政府が推進していた「社会企業」といった、より大きな社会的・政治的な言説の中に位置づけ、活動の正当性を高めました。同時に、政府高官や有力な財界人といった社会的に信頼性の高い人々との連携を深めました。有力者からの支持は、この新しい組織の型に強力な「お墨付き」を与えました。
他分野の権威を借り、利他主義を示して信頼を得る
新しい組織の型を社会に根付かせるには、有力者との連携が有効です。この「権威を借りる」戦略は、全く新しい分野をゼロから立ち上げる際に、より決定的な意味を持ちます。まだ社会的な評価が定まらない未開拓の領域では、先駆者たちは自らの正しさをどのように証明すれば良いのでしょうか。経営コンサルティングという分野が確立されていく初期の歴史を通じて、制度的企業家が信頼を獲得していくための戦略を見ていきます[2]。
19世紀後半から20世紀初頭にかけてのアメリカでは、企業の大規模化が進み、経営は複雑化していました。会社の所有者と経営者が分離し、専門的な経営手腕が求められる時代が到来します。規制変更で従来の相談役の活動が制限され、経営アドバイスを専門に行う新しい職業が生まれる余地が生まれました。
しかし、専門的な経営コンサルティングという形態が、当初からすんなりと受け入れられたわけではありません。企業にとってはアドバイス機能を自社内に持つのが合理的だと考えられていましたし、低価格を武器にする別のタイプのコンサルティング会社も存在しました。このような状況下で、「専門的コンサルティング」の創始者たちは、いかに自らの正当性を築き上げていったのでしょうか。
彼ら彼女らの活動は、三つの戦略に整理できます。
第一は「理論化」、すなわち自分たちの活動の正しさを説明する論理の構築でした。彼ら彼女らは、当時広まっていた合理性や効率性を尊重する価値観と、大企業の非効率な経営実態との矛盾を指摘しました。その解決策として、既存の専門分野の知見を経営に応用することを提示しました。ある者は心理学を、ある者は会計学を、またある者は化学の手法を応用しました。彼ら彼女らは、自らのアドバイスを個人的な経験則ではなく、すでに社会的な権威を持つ学問に基づいた客観的なものとして位置づけました。
この理論化で特徴的だったのは、「利他主義」の表明でした。ある創業者は利益に無関心だと公言し、またある者は自社の経営を二の次にして顧客の問題解決に没頭しました。自らの利益より顧客や社会全体の利益を優先する姿勢は、道徳的な正しさを示し、新しいサービスへの懐疑的な見方を和らげました。
第二の戦略は「提携」です。彼ら彼女らは、自らが理論的な根拠とした専門分野の権威と、具体的な関係を築きました。マサチューセッツ工科大学やシカゴ大学といった一流大学と強いつながりを持ち、専門家団体のトップを務めるなど、専門分野での地位を確立しました。権威ある機関とのつながりは、実績のない新しい事業の信頼性を補強するシグナルとして機能しました。加えて、社会的なエリート層との個人的なネットワークを構築し、有力者からの支持を取り付けました。
第三の戦略は「集団行動」でした。個々の会社がばらばらに活動するのではなく、団結して業界全体の正当性を高めようとしたのです。「経営コンサルタント技術者協会(ACME)」という団体を設立し、共通の敵と見なした競合他社を攻撃することで、自分たちのアイデンティティを明確にしました。誇大な広告や成功報酬などを禁じる倫理規定を策定し、「専門性」の基準を自ら作り上げました。
この団体は、会員企業に組織構造の標準化を促すなど、業務のやり方の均質化にも取り組みました。これらの活動を通じ、「専門的経営コンサルティング」という概念が、客観的な社会規範として認識されるようになりました。この規範は、後の世代が模倣する手本となり、この組織形態が社会に定着する上で基盤となったのです。
技術を既存の習慣に結びつける物語で普及させる
新しい分野の正当性を確立するには、その活動の正しさを説明する「物語」を構築することが求められます。これが新しい「技術」の場合はどうでしょうか。技術の普及は、性能の高さだけで決まるわけではありません。その技術が人々の生活の中でどのような意味を持つのか、新しい物語を創り出し、社会に浸透させていくプロセスが必要です。コダック社がロールフィルムカメラを導入し、写真撮影を一部の専門家のものから、誰もが楽しむ日常的な文化へと変えた歴史をたどってみましょう[3]。
ロールフィルムカメラ登場以前、写真撮影は非常に複雑で専門的な技術を要しました。撮影の都度、重いガラス板の準備や、暗室での化学処理が必要でした。写真は、専門知識を持つプロフェッショナルか、芸術として探求する裕福なアマチュアのものでした。
コダックが開発したロールフィルムカメラは、技術的には画期的でしたが、当初は写真業界から相手にされませんでした。画質が従来のガラス板に比べて劣っていたからです。既存の写真家から見れば、それは「おもちゃ」のようでした。技術的な解決策はあっても、社会にその解決策を必要とする「問題」意識がありませんでした。
この逆境を乗り越えるため、コダックは技術ではなく、写真という行為の意味を社会的に再構築する戦略に乗り出します。その戦略は、四つの物語の創造から成り立っていました。
第一に、新しい技術を、すでに社会に根付いていた既存の習慣の中に埋め込む戦略です。コダックが目を付けたのは「バケーション」でした。広告は新しいカメラを冒険や旅行と結びつけ、休暇先での記録を奨励しました。「コダックなしの休暇は、無駄になった休暇」という言葉が生まれるほど、写真撮影は旅行に欠かせない要素として人々の意識に刷り込まれていきました。コダックは、既存の習慣を豊かにする道具としてカメラを位置づけました。
第二に、新しい役割を社会に創り出す戦略です。それまで「写真家」は専門家を指す言葉でしたが、コダックは子どもや女性を含む普通の人々を、新しい「写真家」として定義しました。これを可能にしたのが、「あなたはシャッターを押すだけ。あとは我々がやります」という画期的なサービスです。撮影と現像を切り離すことで、誰でも気軽に写真を撮れるという新しい役割が生まれました。
第三に、フィールドレベルでの新しい制度の創設です。コダックは、「スナップショット」と「写真アルバム」という新しい概念を社会に広めました。従来の写真は計画的なものでしたが、コダックは画質の粗さを逆手にとり、日常の何気ない瞬間を気軽に撮影する「楽しさ」を強調しました。これが「スナップショット」の誕生です。それらの写真を貼り付けて家族の思い出を保存する「写真アルバム」という習慣を普及させました。
第四に、フィールド内の既存制度の修正です。コダックは、「カメラ」という言葉が持つ意味を根本から変えました。当初は「楽しい」おもちゃとして宣伝されていましたが、やがて技術が向上すると、今度は「貴重な瞬間を捉えるための必須の装置」として、その価値を再定義していきました。複雑な科学装置であったカメラは、思い出を記録する身近な道具へと意味を変容させたのです。
四つの戦略が一体となって機能した結果、コダックはロールフィルム技術を社会に定着させることに成功しました。彼ら彼女らは単に製品を売ったのではなく、写真撮影を日常の文化として根付かせ、「コダックモーメント」という言葉に象徴される、全く新しい制度的フィールドを創り上げたのです。
新興国の「制度的空白」で対立する価値観を操る
新しい分野や技術を正当化するプロセスは、その舞台となる社会の制度や文化と関わっています。その舞台が、制度が未発達で複数の価値観が混在する「新興国」であったなら、企業家はどのような戦略を取るべきでしょうか。先進国の常識が、そのまま通用するとは限りません。そこには特有の困難と、同時に特有の好機が存在します。インドで生まれた高級産科病院の事例を通じて、新興国における正当化戦略の独特なあり方を考察します[4]。
この研究の舞台であるインドの市場には、「制度的空白」と呼ばれる特徴がありました。これは、市場を支える公的な仕組みが十分に発達していない状態を指します。この研究では、制度的空白を「欠落」ではなく、複数の、時には矛盾する価値観が共存する「機会の空間」として捉え直します。
当時のインドの病院業界には、二つの対立する価値観が存在しました。一つは、医師が絶対的な権威を持つ伝統的な「コンプライアンス・ロジック」。もう一つは、患者を「顧客」とみなし満足度を優先する新しい「カスタマーケア・ロジック」です。この二つの価値観の対立と、富裕層からの質の高い医療への需要が相まって、「高級病院」が生まれるための制度的な空間が創出されました。
加えて、事業の正当性を確立する上では、その国の文化的な特徴も障壁となりえます。インドの場合、上司と部下の間の不平等を許容する「高い権力格差」と、身内以外を信用しない「低い一般的信頼」が挙げられます。前者は従業員の自主的な行動を妨げ、後者は顧客からの信頼獲得を困難にします。
このような複雑な環境の中、2007年に「ブルームーン」(仮名)という高級産科病院が設立されました。海外経験を持つ創業者によるこの病院は、国際基準の医療を、高級ホテルのような豪華な環境と徹底した顧客中心のサービスで提供することを目指しました。
ブルームーンがこの新しい組織形態を正当化するために用いた戦略は、四つの行動に分類できます。第一は「仲介」です。制度的な不確実性を減らし、価値を提供することに焦点を当てます。ブルームーンは、当時問題だった高い妊産婦死亡率に着目し、国際基準の医療でリスクを低減できると訴えました。これは社会全体の利益に貢献する「利他的なフレーミング」であり、顧客の信頼を得る上で有効でした。高い権力格差という文化障壁に対し、看護師が医師ではなくビジネス部門に報告するという革新的な組織構造を導入しました。
第二は「制度的空白の架橋」です。制度的な問題を解決し、その解決策を新たな標準として確立することを目指します。ブルームーンは、競合病院に対する自社サービスの優位性を強調する「利己的なフレーミング」を用いました。海外の投資ファンドからの資金調達を成功させ、事業モデルの正しさを外部に証明しました。
第三は「制度的距離の橋渡し」です。先進国で成功している仕組みや実践を自国に導入します。創業者の豊富な海外経験をアピールし、「インドと国際基準の医療のギャップを埋める」と訴えました。国内に信頼できる評価機関が乏しかったため、オーストラリアの認証機関といった国外の権威ある団体との「提携」を通じて、自らの正当性を補強しました。
第四は「独自のアイデンティティの構築」です。「高級」というコンセプトの信頼性を確立することに焦点を当てます。「妊娠は病気ではなく、ウェルネス(健康的な状態)である」と宣言するなど、「顧客フレンドリーな理論化」を行いました。低い一般的信頼という文化を乗り越えるため、インドの文化には根付いていなかった笑顔での顧客対応をスタッフに徹底させ、患者を「ゲスト」と呼ぶなど、従業員の意識改革を図りました。
このように、新興国の制度的企業家は、制度的空白を機会として捉え、存在する複数の矛盾した価値観を操りながら、新しい組織形態を正当化していくことが示されます。
脚注
[1] Tracey, P., Phillips, N., and Jarvis, O. (2011). Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms: A multilevel model. Organization Science, 22(1), 60-80.
[2] David, R. J., Sine, W. D., and Haveman, H. A. (2013). Seizing opportunity in emerging fields: How institutional entrepreneurs legitimated the professional form of management consulting. Organization Science, 24(2), 356-377.
[3] Munir, K. A., and Phillips, N. (2005). The birth of the ‘Kodak moment’: Institutional entrepreneurship and the adoption of new technologies. Organization Studies, 26(11), 1665-1687.
[4] Jayanti, R. K., and Raghunath, S. (2018). Institutional entrepreneur strategies in emerging economies: Creating market exclusivity for the rising affluent. Journal of Business Research, 89, 87-98.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。