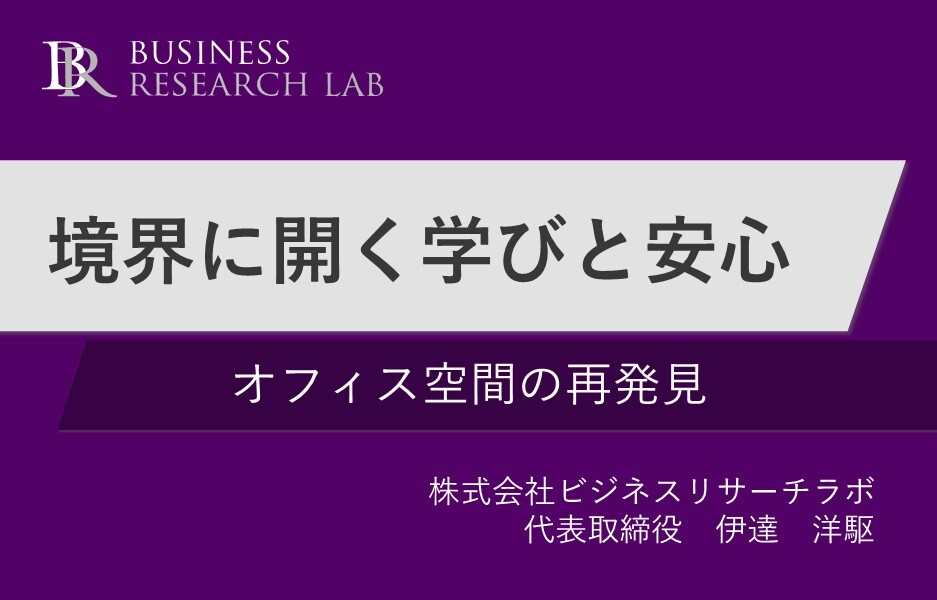2026年1月29日
境界に開く学びと安心:オフィス空間の再発見
ふと、隣の同僚の机に目をやることがあります。きれいに整頓された机、家族の写真が飾られた机、専門書が山積みになった机。私たちは、そうした光景から、持ち主の性格や仕事ぶりを無意識のうちに想像しているのではないでしょうか。オフィスという空間は、単に仕事をするための箱ではありません。そこにあるモノや、その配置、そして人々が過ごす時間の痕跡には、私たちが思う以上に豊かな情報が宿っています。
普段は気にも留めないようなオフィスの片隅、あるいはパーテーション一枚を隔てた小さな領域が、実は私たちの人間関係や心のあり方、さらには新しいアイデアの誕生にまで関わっているのかもしれません。本コラムでは、そうした「小さな空間」に秘められた大きな力に光を当てていきます。オフィス装飾の解読法から、廊下や階段の踊り場といった「隙間」の意外な機能まで、私たちの職場環境をめぐる目に見えない力学を、いくつかの研究を手がかりに探求していきます。
装飾は所有者不在で地位、反復で一貫性が強まる
私たちは、同僚の机の上にあるものを見て、その人がどんな人物かを推し量ることがあります。整然と置かれた文房具、趣味の小物が、持ち主の個性や地位について何かを語りかけてくるように感じられます。このような、オフィス内の装飾や私物が他者にどう解釈され、人物像の判断に結びつくのかを明らかにした研究があります[1]。
この研究は、二段階にわたる質的手法で進められました。
初めに、IT企業などに勤める37名に質問紙を配布し、同僚のオフィスのどのような装飾が印象に残り、そこから何を感じ取ったかを自由に記述してもらいました。これによって、人々がどのような物理的な手掛かりから人物像を読み取っているのか、その実例が豊富に集められました。続いて、その中から20名を選んで、インタビューを実施しました。インタビューでは、具体的な事例を挙げてもらいながら、装飾から同僚のアイデンティティを判断する際の思考のプロセスを掘り下げていきました。
分析の結果、人々の解釈の仕方には、大きく分けて二つの異なるパターンがあることが見出されました。
一つは「トップダウン型」と呼ばれる思考の様式です。これは、いくつかの目立つ手掛かり、例えば高価そうな家具や、飾られた学位記、あるいは全体の整頓具合といった情報を素早く拾い上げ、「この人は管理者タイプだ」「プロフェッショナル意識が高い(あるいは低い)人物だ」といった、あらかじめ持っている典型的な人物像(プロトタイプ)に当てはめて判断するやり方です。少数の情報から素早く結論を導くため、効率的ではありますが、一面的な見方やステレオタイプな判断に陥りやすい側面も持ち合わせています。
もう一つは「ボトムアップ型」の思考様式です。こちらは、一つの手掛かりだけで結論を急ぐのではなく、オフィス内の多様な情報を広く収集し、それらを丁寧に結びつけながら、多角的な人物像を構築しようとします。例えば、机の上の書類の山を見ても「だらしない」と即断するのではなく、「どのような種類の書類が、どのように積まれているのか」「仕事の動線を考えて、あえてここに置いているのかもしれない」といったように、その背景にある持ち主の意図や動機まで探ろうとします。
この方法は、時間がかかり、より注意深い観察を必要としますが、精緻で文脈に沿った、より深い理解に至る可能性があります。
この研究では、条件の違いによる解釈の変化も調べています。それは、装飾の持ち主と会う前にオフィスを見た場合と、会った後に見た場合とで、人々の見方がどう変わるかという点です。持ち主の人物像をまだ知らない、要するにオフィスだけが目の前にある状況では、人々は特にトップダウン型の思考を働かせ、家具の質や大きさといった手掛かりから、その人の「地位」を読み取ろうとするようです。重厚な机は高い地位を、質素な備品は低い地位を連想させやすいのです。
ところが、持ち主と実際に会って話した後に同じオフィスを観察すると、人々の関心は変化します。地位のような社会的な属性よりも、その人ならではの価値観や趣味といった「独自性」に焦点が移るのです。以前は地位の印としか見えなかったものが、その人の個性を示す手掛かりとして解釈され直されます。このとき、解釈の仕方もボトムアップ型へと移行しやすくなります。
オフィスの装飾が毎日同じようにそこにある、という「反復性」も、私たちの解釈に作用します。毎日散らかった机を目にしていると、「あの人は整理整頓が苦手な人だ」という印象が強化され、その人らしさとして固定化されていきます。トップダウン型の解釈では、一度形成された印象はなかなか覆りにくく、一貫性が強く認識されることになります。
一方で、ボトムアップ型の解釈をする人は、装飾のわずかな変化にも気づきやすいことがわかっています。例えば、以前まで飾られていたランニング大会のゼッケンがある日突然外されたのを見て、「あの人は、より企業人らしい自分を演じようとしているのかもしれない」と、持ち主の心境やアイデンティティの変化を読み取ることがあります。
狭間の小場所で儀礼と媒介が新たな慣行を生む
新しいアイデアや働き方は、一体どこで生まれるのでしょうか。公式な会議室での議論から生まれることもあれば、全く予期しない場所での雑談がきっかけになることもあります。異なる背景を持つ人々が偶然に出会う「狭間」のような小さな場所に、新たな慣行が生まれる可能性が秘められていることを論じた理論研究があります[2]。
この研究が光を当てるのは、「インタースティシャル・スペース」と呼ばれる場所です。これは、制度化された領域の「すき間」に存在する、小規模で非公式な相互作用の場を指します。例えば、17世紀のロンドンで新しい保険や取引の慣行を生んだコーヒーハウスや、パーソナルコンピュータ革命の火付け役となったアマチュアたちのコンピュータクラブなどがその典型例です。
こうした場所には三つの共通する特徴があります。第一に、異なる組織や専門分野など、多様な背景を持つ人々が集まること。第二に、そこでのやりとりが偶発的で、決まった形式や議題がないインフォーマルなものであること。第三に、参加者が本業の合間に、共通の趣味や勉強会といった活動のために集まっていることです。
このような「狭間の小場所」では、既存の組織のルールや常識から一時的に解放されます。参加者は、それぞれが自らの現場から持ち寄った知識や行動様式(テンプレート)を、形式ばらずに交換し合います。失敗しても大きな痛手にはならないという安心感が、自由な試行錯誤を促します。
異なるテンプレートが予期せぬ形で組み合わさり、そこから全く新しい活動のアイデアが生まれます。これを「集団的実験」と呼びます。例えば、前述のコンピュータクラブでは、技術者の実践的な知識と、社会活動家の協働的な精神が混ざり合い、自分たちの作った装置を持ち寄って即興でデモンストレーションし、知識を自由に共有するという、当時としては画期的な慣行が自然発生的に生まれました。
しかし、こうした場で生まれた新しい活動の芽は、非常に脆いものでもあります。場所自体が偶発的で一時的なものであるため、せっかく生まれた活動も一過性に終わり、定着せずに消えてしまいやすいのです。その脆さを乗り越え、新しい活動が持続的な「慣行」へと育っていくためには、何が必要なのでしょうか。
この研究は、二つの条件を提示します。一つ目は、「成功する相互作用リチュアル」の存在です。リチュアルというと儀式のようなものを想像するかもしれませんが、ここでは、参加者全員の意識が一点に集中し、強い一体感や高揚感が生まれるような相互作用の瞬間を指します。
コンピュータクラブの例で言えば、誰かが持ち込んだ手作りの装置のデモンストレーションに人々が熱狂し、歓声が上がった瞬間がそれにあたります。このような強い感情を伴う共同体験は、人々の記憶に深く刻み込まれ、「あの興奮をもう一度味わいたい」という動機づけを生み、活動の反復を促します。逆に、参加者の関心や感情的な高ぶりを生まない活動は、自然と淘汰されていきます。
二つ目の条件は、「カタリスト(媒介者)」の存在です。これは、新しい活動の定着を陰で支える人のことです。カタリストは、議論を交通整理したり、場の雰囲気を作ったりして、相互作用が盛り上がるのを助けます。また、次回の集まりを呼びかけたり、前回の議論の内容を共有したりすることで、時間的に途切れがちな活動をつなぎ合わせます。
参加者のやりとりの中から自然発生的に生まれた言葉やシンボルを拾い上げ、それをグループの共有財産として育てることで、活動に共通の意味を与えていきます。カタリストは、人々を上から支配するリーダーとは異なります。多様な参加者の意図を汲み取りながら、下から湧き上がるエネルギーをうまく方向づけ、活動が自走していくのを手助けする調整役です。
このように、異なる人々が集う非公式な「狭間の小場所」は、新しいアイデアの実験場となります。そこで生まれた活動の芽が、人々の熱狂的な相互作用と、それを支える媒介者の存在によって育まれたとき、それはやがて一つの持続的な慣行として定着し、既存の組織や社会へと広がっていく可能性を秘めています。
境界の小場所が安心と学びを育む
オフィスには、デスクや会議室といった明確な目的を持つ「主役」の空間だけでなく、廊下や階段、給湯室といった、普段あまり意識されない「脇役」の空間も存在します。こうした境界線上にある、いわば「狭間の空間」が、働く人々にとってどのような意味を持ち、どのように利用されているのかを、質的研究で描き出したものがあります[3]。
この研究は、英国の美容室で働く43名の美容師を対象に行われました。研究者は参加者一人ひとりに使い捨てカメラを渡し、「あなたにとって職場で意味のある場所」を自由に撮影してもらうよう依頼しました。その後、現像された写真を見ながら一対一でインタビューを行い、なぜその場所を撮影したのか、そこで何を感じ、どのように過ごしているのかを聞き取りました。この「フォト・インタビュー」という手法によって、言葉だけでは捉えきれない、人々の空間に対する主観的な経験や感情が、豊かに浮かび上がってきました。
分析から明らかになったのは、階段の踊り場や店の裏口、物置といった、本来は長居するはずのない「狭間の空間」が、美容師たちにとって三つの大切な機能を持つ「一時的な居場所」へと作り替えられている実態でした。
第一に、それはプライバシーを確保し、「隠れる」ための場所でした。美容室のフロアは、常にお客様や他のスタッフの視線に晒される、いわば「舞台の上」です。感情を抑え、プロとしての顔を保ち続けなければならない緊張感の中で、ほんのわずかな時間でも一人になり、気持ちをリセットする必要性を多くの美容師が感じていました。
写真に撮られたのは、薄暗い金属製の階段や、店の外のちょっとした段差といった場所です。参加者はそこで一息ついたり、気持ちを落ち着けたりすることで、「自分らしさを取り戻す」と語ります。公式な休憩室(裏方)とも、接客フロア(表舞台)とも違う、その境界線上にある小さな隙間が、心の避難所として機能していました。
第二に、そうした空間は、仲間との絆を育む「非公式のスタッフルーム」になっていました。トイレの前の小さなスペースや、タオルが積まれた物置の隅などが、気の置けない同僚との私的な会話の場として利用されていました。そこでは、仕事の悩みや個人的な相談事が、気兼ねなく語られます。
興味深いことに、多くの美容室には公式のスタッフルームが設けられているにもかかわらず、美容師たちはあえてこうした非公式な場所を選んで集まっていました。公式のスタッフルームは、上司の目があったり、休憩時間中でも電話対応を求められたりと、必ずしも心からリラックスできる場所ではなかったのです。それに対して、自分たちで「発見」し、暗黙のうちに領有した境界の小場所は、誰にも邪魔されずに本音で語り合える、社交の場となっていました。
第三に、これらの場所は、新たなひらめきや学びが生まれる触媒としての働きも担っていました。カラー剤が並ぶ棚の前や、店の裏の路地といった、管理の網の目から少し外れた場所で、同僚と偶然出会った際の立ち話から、新しい技術のヒントを得たり、仕事への見方が変わったりすることがあると、多くの美容師が語っています。公式のミーティングのような堅苦しさがなく、偶発的で対等な会話が生まれるからこそ、創造的な対話が可能になります。
この研究が示すのは、用途が定められていない曖昧な「空間(space)」が、人々の反復的な利用と、そこに込められた愛着や安らぎの感情によって、意味のある「場所(place)」へと人間化されていくプロセスです。管理された主舞台の周縁にある、見過ごされがちな境界の小場所は、働く人々の心の安定を支え、仲間との連帯感を醸成し、偶発的な学びを誘発する、「一時的な居場所」として、日々の仕事に不可欠な存在となっていたのです。
物理環境は利点と欠点を併せ持つ
これまで見てきたように、オフィスの物理的な環境は、私たちの認知や行動、人間関係に働きかけをしています。しかし、だからといって「こういう環境が絶対的に良い」という万能な答えがあるわけではありません。ある状況では利点となる特徴が、別の状況では欠点になりうる。こうした物理環境が持つ二面性と、そこに生じる緊張関係を体系的に整理した研究があります[4]。
この研究は、職場環境に関する過去の膨大な実証研究を統合し、一つの大きな見取り図を描き出そうとする試みです。その結論は明快です。壁や仕切りの有無、家具の配置、あるいは窓から見える風景といった環境のあらゆる要素は、それ自体が一方的に良い、あるいは悪いのではなく、常に利点と欠点を併せ持っているというものです。
例えば、「仕切りや囲い」について考えてみましょう。個室や高いパーテーションは、プライバシーを確保し、集中力を高めるのに役立ちます。機密性の高い会話や、深い思考を要する作業には、このような閉じた空間が適しているでしょう。しかしその一方で、囲いは人々を孤立させ、偶発的なコミュニケーションの機会を奪うかもしれません。
興味深いことに、ある研究では、壁のないオープンな空間よりも、少し高めの仕切りがある方が、非公式な会話が増えたという結果も報告されています。これは、仕切りがあることで「他人に迷惑をかけていない」という感覚が生まれ、かえって気軽に声をかけやすくなるからだと考えられます。完全に開くのでも、完全に閉じるのでもない、その中間に最適な解がある可能性を示唆しています。
机や椅子、照明などを個人が「調整できること」も、一般的には望ましいとされます。自分の好みに合わせて環境をコントロールできるという感覚は、仕事への満足感や自己効力感を高めます。しかし、これもまた裏の顔を持ちます。選択肢が多すぎると、調整作業が負担になったり、かえって集中力を削いだりすることがあります。また、適切な調整方法を知らなければ、良かれと思って行った変更が、逆に不快な環境を生み出してしまうこともあり得ます。
自分の机周りを写真や小物で飾る「パーソナライゼーション」も同様です。家族の写真や趣味の品々は、自分らしさを表現し、職場への愛着を育む助けになります。しかし、その飾り方が過度であったり、高価なものであったりすると、見る人からは「地位を誇示している」といったステレオタイプな解釈をされ、意図しないメッセージを発してしまう危険性も伴っています。
この研究は、物理環境が持つこのような二面性が、なぜ生じるのかを説明するための枠組みを提示しています。それによれば、職場環境は常に三つの異なる機能がせめぎ合う場であるとされます。第一に、仕事の効率や快適さを支える「道具的機能」。第二に、組織の文化や個人の地位を象徴する「象徴的機能」。第三に、見た目の美しさや心地よさに関わる「審美的機能」です。
これら三つの機能は、しばしば互いに衝突します。例えば、ガラス張りの壁は、開放性や透明性という「象徴的機能」は満たすかもしれませんが、プライバシーの確保という「道具的機能」を損ないます。
このように、職場をデザインするということは、ある一つの正解を見つける作業ではなく、これら三つの機能の間で発生する緊張関係、すなわちトレードオフを認識し、その時々の文脈に応じてバランスをとっていく営みであると言えるでしょう。どの要素も、それ自体に絶対的な価値があるわけではなく、その配置や運用、そこで働く人々の解釈によって、その意味合いを様々に変えていくのです。
脚注
[1] Elsbach, K. D. (2004). Interpreting workplace identities: The role of office decor. Journal of Organizational Behavior, 25, 99-128.
[2] Furnari, S. (2014). Interstitial spaces: Microinteraction settings and the genesis of new practices between institutional fields. Academy of Management Review, 39(4), 439-462.
[3] Shortt, H. (2015). Liminality, space and the importance of “transitory dwelling places” at work. Human Relations, 68(4), 633-658.
[4] Elsbach, K. D., and Pratt, M. G. (2007). The physical environment in organizations. Academy of Management Annals, 1(1), 181-224.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。