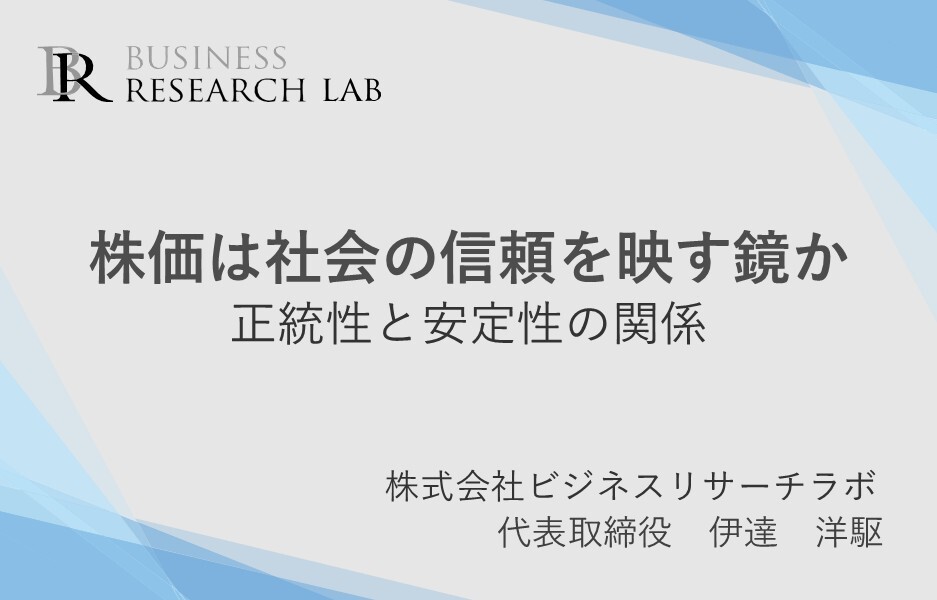2026年1月29日
株価は社会の信頼を映す鏡か:正統性と安定性の関係
私たちの周りには、数多くの「当たり前」が存在します。会社には特定のルールがあり、社会には共有された慣習があります。私たちは普段、そうした「当たり前」を意識せず受け入れ、行動しています。ある事柄が「もっともだ」「適切だ」と広く受け入れられている状態を、「正統性」と呼びます。それは、組織や社会がスムーズに機能するための、目には見えない潤滑油のようなものです。
しかし、この正統性は決して一枚岩ではありません。ある場所では賞賛される行動が、別の場所では非難の的になることもあります。新しい技術やビジネスが登場したとき、最初は社会から奇異の目で見られるかもしれません。それが時間を経て、私たちの生活に不可欠な「当たり前」へと変わるプロセスには、何が起きているのでしょうか。社会からの信頼、すなわち正統性は、企業の価値にどう結びつくのでしょうか。
本コラムでは、この捉えどころのない、しかし私たちの社会を動かす力である「正統性」をめぐる話を四つの観点から行います。
一つ目は、社会のルールを破る過激な活動が、なぜか組織の評価を高めてしまう逆説的な世界。二つ目は、国境を越えて活動する企業が直面する、文化や価値観の板挟みという複雑な現実。三つ目は、日々のニュースが、いかに特定の出来事を「もっともらしい物語」として私たちの心に届けているのかという、言葉の舞台裏。最後に、社会的な評価という無形の資産が、株価という具体的な数値にどう反映されるのかを考えます。
非合法な活動と巧みな説明が、組織に正統性を与える
社会のルールを公然と破るような、過激ともいえる行動が、その組織の社会的な評価を高めることがあります。常識的に考えれば、非合法な活動は組織の評判を貶めるはずですが、現実には、そうした直感に反する事態が起こり得ます。その背後には、組織の構造と言葉を巧みに組み合わせた、計算されたプロセスが存在します。
この現象を解き明かすため、かつてアメリカで活動した二つの社会運動団体の事例が分析されました[1]。一つはエイズ対策強化を訴えた「アクト・アップ」。もう一つは原生林保護を掲げた「アース・ファースト!」です。両団体は、その崇高な目的とは裏腹に、製薬会社の役員室占拠や、木の伐採を物理的に阻止する「ツリー・スパイキング」といった過激な直接行動で知られていました。
これらの行動は、メディアの関心を引きつけます。プロセスはここから始まります。メディアの注目は、主張を世に広める機会ですが、同時に過激な手法への批判に晒される危険も伴います。このジレンマの中で、組織は巧みな立ち回りを見せます。
メディアが取材に訪れると、組織は自らが信頼に足る存在であることを示す「舞台装置」を提示します。記者会見のための広報委員会を設けたり、メンバーに専門家がいることを紹介したりと、社会的に認められた手続きや構造を持っていることをアピールするのです。これは、組織が理性的な対話が可能な相手であるという印象を作り出します。
それと並行して、問題となった過激な行動と、組織本体との間に距離を置く作業が行われます。スポークスパーソンは、「あの行動は、組織の公式な決定ではなく、独立した一部のメンバーが独自に行ったものです」と説明します。これによって、組織が掲げる正統な「目的」を、物議を醸す「手段」から切り離し、組織本体への非難を防ぎます。
この下準備の上で、スポークスパーソンによる本格的な言葉の戦略が展開されます。最初は防御的な姿勢で、「組織に責任はない」と主張します。次に、行動そのものを正当化する段階に移ります。「エイズで多くの人々が命を落としている現状では、強い手段もやむを得なかった」といった論理で、人々の意識を問題の「手段」から、共感しやすい「目的」へと誘導していきます。
状況が落ち着くと、今度は攻勢に転じます。自分たちの行動が社会に良い変化をもたらしたと主張し始めます。「私たちの抗議活動がエイズ治療薬の価格を引き下げた」「我々の存在が他の穏健な環境団体の主張をより受け入れられやすくした」と、行動の肯定的な側面を強調します。最後に、その成果は自分たちの功績なのだと宣言します。
この一連のプロセスを経ることで、不思議な逆転現象が起こります。事件直後にメディアを賑わせた、過激な行動への批判は時間とともに薄れていきます。その一方で、繰り返し語られた共感を呼ぶ「目的」や輝かしい「成果」のイメージが心に残り、組織への支持や称賛へと変わるのです。当時の報道を分析すると、当初の批判的な論調が、次第に専門家や他の団体からの支持表明へと変化していく様子が確認できます。
ここから見えてくるのは、正統性が行動の是非だけで決まるわけではないという事実です。組織の構造的な体裁と言葉による物語が組み合わさることで、社会的な評価は作り変えられていきます。
多国籍企業は異なる正統性を同時に得る必要がある
一つの社会の中でさえ、正統性の獲得には戦略が必要とされます。活動の舞台が国境を越え、文化も法律も異なる複数の社会にまたがったとしたら、事態はどう変わるのでしょうか。そこでは、「当たり前」が一つではないという、より複雑な課題が組織に突きつけられます。この課題に日々直面しているのが、多国籍企業です[2]。
多国籍企業、特にその海外子会社は、一種の板挟み状態に置かれています。本国で効率的とされる人事制度が、進出先の国では地域の雇用慣行にそぐわないかもしれません。本社が掲げるグローバルな行動規範と、現地の商習慣との間でジレンマも生じます。このように、多国籍企業は、本国と現地の、時に相反する複数の要求に同時に応えなければならないのです。
この複雑さは、国ごとに法律、規範、価値観といった「制度」が異なるという現実から生じます。また、企業を評価する「観衆」が、本国の投資家、現地の政府、地域の住民、労働組合など多様であることも一因です。ある観衆を満足させる行動が、別の観衆の不興を買うことも珍しくありません。子会社は、現地の社会に根を下ろして活動する一方で、親会社グループの一員でもあり続けなければならない「二重の埋め込み」という状況にも置かれます。
こうした複雑な環境の中で、多国籍企業が向き合う正統性は、いくつかの異なる次元で考えられます。評価がなされる「レベル」が、国全体、業界、組織自体と異なります。同時に、正統性の「タイプ」も、法律遵守(規制的正統性)、社会倫理への適合(規範的正統性)、地域社会での自然な受容(認知的正統性)と複数あります。多国籍企業は、これら複数のレベルとタイプが複雑に絡み合ったパズルを解くように、自らの正統性を築いていく必要があります。
企業はこの難題にどう立ち向かうのでしょうか。新たな国に進出する際は、現地の社会に受け入れられるための努力をします。現地の評判の良い企業と提携したり、権威ある団体から認証を取得したりすることで、「私たちは怪しい存在ではありません」という信号を送ります。現地の人材を積極的に登用し、地域のサプライヤーから部品を調達することも、社会に溶け込む上で助けとなります。
事業が軌道に乗った後も、正統性を維持するための不断の努力が求められます。世界共通で守るべき核となる原則は維持しつつ、現地の文化や慣習に合わせて柔軟に運用できる二層構造のルールを設計したり、政府や地域社会といった評価者ごとに、対話の窓口を設け、説明責任を果たしたりすることが欠かせません。
もし問題が発生し正統性が揺らいだ場合には、その修復が試みられます。原因を調査し、説明と謝罪を行うだけでなく、現地の意見を取り入れてガバナンスの仕組みを改めるなど、構造的な改革にまで踏み込むことが、信頼を回復することにつながります。
メディアの言説が産業再編の正統性を構築する
ここまで、組織が自らの行動や構造を工夫することで、社会的な評価を築き上げていくかを見てきました。しかし、組織の評判は、組織自身の努力だけで完結しません。私たちの多くは、情報を新聞やテレビといったメディアを通じて得ています。メディアは、事実を伝える中立的な鏡なのでしょうか。あるいは、その「語り口」によって、私たちの認識を特定の方向へと導く力を持っているのでしょうか。
ここでは、メディアが用いる「言葉の戦略」が、企業の合併といった大きな経済的出来事の正統性をいかに形作っていくのか、そのプロセスに光を当てます。この問いを探る上で、かつて行われたフィンランドとスウェーデンの大手製紙会社の国境を越えた合併が、分析対象となりました[3]。この合併は、業界初の大規模な国際再編であり、長年のライバル関係にあったことなどから、両国で大きな議論を呼びました。前例のない物議を醸す出来事であったからこそ、それを社会に受け入れてもらうための「正統化」が強く必要とされたのです。
当時の新聞記事を分析した結果、メディアがこの合併を「もっともらしい」出来事として読者に提示するために用いた、五つの言説戦略が浮かび上がりました。
一つ目は「正常化」です。この合併は前例のないものでしたが、報道では、自動車業界など他の産業の国際合併を引き合いに出し、これをグローバル競争におけるごく自然な流れであるかのように位置づけました。未知の出来事を、既知のカテゴリーに当てはめることで、「普通のこと」として受け入れやすくします。
二つ目は「権威付け」です。記事の中では、「市場は合併を歓迎している」「専門家は高く評価している」といった表現が頻繁に用いられました。「市場」や「専門家」という客観的な響きを持つ言葉を権威として利用し、合併の決定が正しいという印象を作り出します。
三つ目は「合理化」です。合併の目的を説明する際に、「規模の経済」「シナジー効果」といった経済学的な用語が多用されました。「年間数十億円の経費削減が見込める」といった具体的な数字が示されると、それは客観的な事実のように響きます。
四つ目は「道徳化」です。これは、合併を正当化するだけでなく、その正当性に疑問を呈するためにも用いられました。合併に批判的な人々は、「国益に反する」といった価値観に訴えかけました。すると、今度は企業側が「国際競争を勝ち抜くことが、この国の道徳的な責務だ」と反論するなど、道徳的な綱引きがメディア上で繰り広げられました。
五つ目は「物語化」です。多くの記事は、この複雑な経済現象を、スポーツの試合かドラマのように描き出しました。両社の歴史が、今回の合併をクライマックスとする物語として語られ、企業の経営者を「ヒーロー」として描き、その成功物語を通じて合併を美化しました。
これらの分析が明らかにしたのは、ニュースが単なる事実の断片の集まりではないということです。そこには、特定の出来事を正当化するための言葉の戦略が埋め込まれています。ある出来事の正統性は、それが客観的に正しいかだけでなく、社会の中でどう「語られるか」によって左右されるのです。
正統性は株価の長期的な変動リスクを低くする
言葉の力が、社会的な出来事の正統性を構築するプロセスの一端が見えてきました。そうして築かれた「正統性」という評価は、具体的にどのような価値を生むのでしょうか。目に見えない社会的な信頼が、企業の経済的な価値、すなわち「株価」という現実的な指標にどう結びつくのか、その関係性を探ります。
企業の環境問題への取り組みは、現代の投資家にとって無視できない判断材料です。しかし、「環境に配慮している」という評判が、企業の株価にどう現れるのか、そのメカニズムは自明ではありません。この点を明らかにするため、ある分析が行われました[4]。その分析がユニークなのは、短期的な株価の上下動ではなく、より長い目で見たときの株価の「安定性」に着目した点です。
ここでいう安定性とは、専門的には「非体系的リスク」の低さとして測定されます。これは、経済全体の動向とは無関係に、その企業固有の事情によって生じる株価のブレの大きさを示す指標です。ブレが小さいほど、株価は安定的であると評価されます。
分析の対象は、アメリカの化学や石油といった環境への負荷が高い業種に属する企業群です。主要経済紙の記事の論調から、各企業の「環境正統性」を数値化しました。このスコアと、各社の株価の長期的なブレとの関係性が検証されました。その際、企業が自ら発信する良いニュースと悪いニュースの影響も考慮に入れられました。
分析の結果、環境面での正統性と株価の安定性との間に結びつきがあることが確認されました。社会から「環境問題に真摯に取り組んでいる」と評価されている企業ほど、長期的に見て株価のブレが小さいという結果が示されたのです。
これは、社会的な信頼が厚い企業は、予期せぬ環境事故や規制当局とのトラブルに見舞われる可能性が低いと投資家から見なされるためと考えられます。万が一問題が発生しても、社会からの信頼が一種の緩衝材となり、過度な株価の暴落を防ぐことにつながるのかもしれません。投資家が抱く将来への不確実性が小さいことが、株価の安定につながると解釈できます。
一方で、企業が自ら発信する情報がもたらす結びつきは、より複雑でした。環境関連の負債といったネガティブな情報を自ら開示した場合、それは新たな不確実性として受け止められ、株価のブレを大きくする方向に働きました。
他方、環境への新たなコミットメントを表明するといったポジティブな情報発信は、企業の置かれた状況によって異なる形で作用しました。もともと環境面での評価が低い企業にとっては、こうした前向きなアピールが「私たちは変わろうとしています」という有効なメッセージとなり、株価の不安定さを抑える助けとなることが分かりました。しかし、もともと評価が高い企業が同じようにアピールをしてもその効果は限定的で、場合によっては過剰な自己宣伝が投資家の疑念を招く可能性さえ示唆されました。
この一連の分析が物語っているのは、正統性という社会的な評価が、イメージの問題にとどまらないということです。それは、株価の長期的な安定性という具体的な形で、企業の経済的価値と結びついています。社会からの信頼は、企業の存続基盤を支える、現実的な経営資産の一つです。
脚注
[1] Elsbach, K. D., and Sutton, R. I. (1992). Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions: A marriage of institutional and impression management theories. The Academy of Management Journal, 35(4), 699-738.
[2] Kostova, T., and Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. Academy of Management Review, 24(1), 64-81.
[3] Vaara, E., Tienari, J., and Laurila, J. (2006). Pulp and Paper Fiction: On the discursive legitimation of global industrial restructuring. Organization Studies, 27(6), 789-810.
[4] Bansal, P., and Clelland, I. (2004). Talking trash: Legitimacy, impression management, and unsystematic risk in the context of the natural environment. Academy of Management Journal, 47(1), 93-103.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。