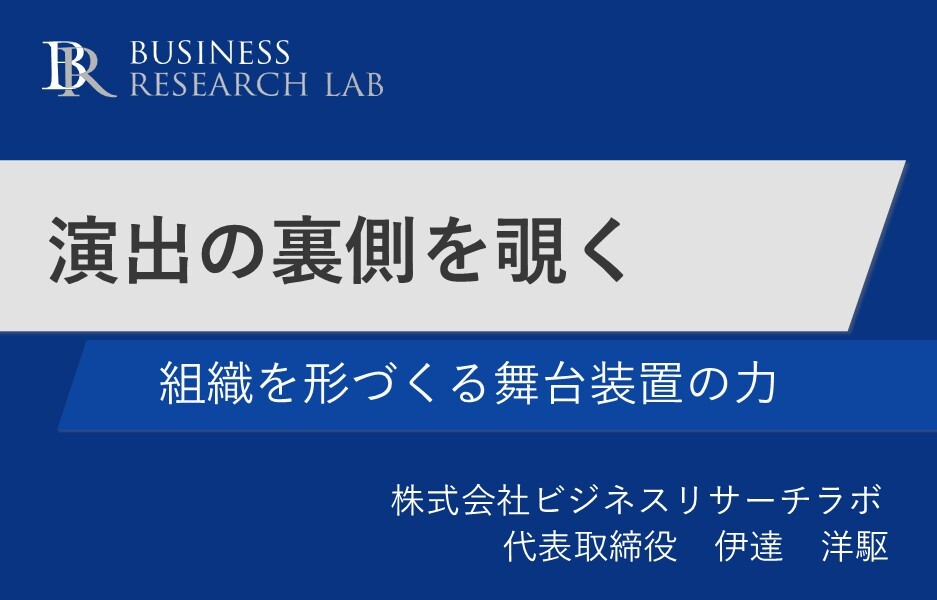2026年1月27日
演出の裏側を覗く:組織を形づくる舞台装置の力
政治家の力強い演説や、企業の華々しい新事業発表。私たちは日々、様々な組織からのメッセージに触れています。その言葉を額面通りに受け取ることもあれば、「本当のところはどうなのだろう」と、その裏側にある意図や駆け引きに思いを馳せることもあるでしょう。
私たちが「現実」として認識している社会の出来事は、もしかすると、誰かによって巧みに作り上げられた「舞台」の一場面なのかもしれません。そこには脚本があり、役者がいて、観客の反応を計算した演出が施されているとしたら、私たちは世界をどう見れば良いのでしょうか。
本コラムでは、政治や組織変革といった社会的な営みを、一つの「演劇」として捉え直す視点から読み解いていきます。組織が自らの正当性を主張し、周囲を納得させようとするとき、そこでは何が問題で、どうあるべきかという「現実の定義」をめぐる綱引きが繰り広げられます。それはまさに、どちらの「演出」が観客の心を掴むかを競い合う闘争のようです。
これから紹介するのは、そうした「演出闘争」の具体的な姿を描き出す研究です。政治の世界から、身近な組織の内部対立、病院の改革、巨大企業の崩壊劇まで。それぞれの舞台で役者たちがどのような仮面をつけ、いかなる台詞を語り、現実を形作っていったのかを追体験することで、私たちの社会を見る目が少しだけ変わるかもしれません。
政治は仮面と即興で現実を形づくる上演である
政治の世界を一つの劇場とみなし、政治家を舞台上の役者にたとえる見方は古くから存在します。そのたとえを深く掘り下げ、政治活動の本質に迫ろうとする試みがあります。スウェーデンの行政組織におけるふるまいを分析したある研究は、その鍵として、イタリアの古典的な即興喜劇「コンメディア・デッラルテ」というユニークな視点を用いています[1]。
コンメディア・デッラルテの際立った特徴は「仮面」と「即興」です。登場人物は職業などを象徴する仮面をつけ、役者はその類型的なキャラクターと自身の個性の間で緊張感を保ちながら演じます。決まった台本はなく、大筋だけを頼りにその場で台詞や動きを創り出しますが、その出来栄えは長年の訓練に裏打ちされた周到な準備に支えられています。
この二つの特徴が、政治家の姿に重なります。政治家もまた、大臣や議員といった公的な「仮面」をつけ、その役割にふさわしい言動を求められます。人々は、政治家がその役割を一貫して説得力をもって演じきることを期待します。国会答弁や記者会見での発言は、「即興」に見えますが、その裏では官僚たちによる入念な準備や稽古が繰り返されています。政治の世界では、言葉を発すること自体が、約束や宣言といった具体的な結果を生み出す「行為」となります。
この研究は、理論的な説明に留まらず、実際の政策交渉をコンメディア・デッラルテの形式に当てはめた三幕構成の戯曲として描き出しました。そこには、産業エネルギー大臣、敏腕官僚、大企業の最高経営責任者といった、おなじみの仮面をつけた登場人物たちが現れます。
第一幕、大企業のCEOが補助金を求めて官庁を訪れます。官僚は「環境改善という大義名分を加えれば大臣は説得しやすい」と助言します。舞台上では「市場原理の尊重」といった公式の原則が語られますが、水面下では互いの利益を図る駆け引きが展開されます。大臣は原則論と国益という例外を使い分け、補助金の支出へと道筋をつけます。
続く第二幕、大臣は自治体や環境派グループといった他の利害関係者と交渉します。それぞれに「環境のため」「手続きの正当性」といった異なる脚本を使い分け、自身の決定の正当性を演出します。そこへ競合企業のCEOが登場すると、大臣は「特定の企業だけを優遇できない」と原則を盾に、形式的な公平性を保ちます。
第三幕、舞台はテレビ討論会へ移ります。専門家は一般論を、業界団体は特殊性を訴えます。大臣はあくまで原則に則ったと主張し、官僚は関係者全員に配慮を見せます。「誠実さは少しずつ与えよ」という皮肉な言葉で幕が下ります。
この戯曲が描き出すのは、政治家がいかに相矛盾する要求の板挟みになりながら、一つの上演を成立させているかという現実です。公の利益と個別の取引、公開性と水面下での調整、原則の遵守と例外の運用。これらの両極にあるものを同時に満たすことが、優れた政治的上演の条件となります。
政治家とは、公的な役割と一個人の人格が分かちがたく結びついた存在であり、私的な場でもその役割から完全に自由にはなれません。この「役割と人格の溶着」が、政治という職業の厳しさです。現代社会ではメディアの発達により、政治はスペクタクルとして消費されやすくなりましたが、この劇化は社会の価値観形成に大きな力を持ちます。
組織変革の成否は状況定義を巡る演出闘争に左右される
政治という大きな舞台で繰り広げられる演出の力学は、国家レベルの出来事に留まりません。私たちの身近な組織の中にも、現実の定義をめぐる駆け引きは存在します。とりわけ、組織が大きく変わろうとするとき、その方向性をめぐって、異なる立場の人々がそれぞれの「正義」を主張し、演劇のような闘争が始まることがあります。
この現象を解明するため、社会的な相互行為を演劇のメタファーで分析する「ドラマツルギー」という考え方を、組織全体のレベルへと広げた研究があります[2]。この視点によれば、組織にも公演を行う「チーム」がいて、公開される「表舞台」とその準備が行われる「舞台裏」が存在します。組織変革をめぐる対立とは、何が公式の「状況定義(ライン)」として認められるかをめぐる、演出の主導権争いとして理解できます。
この分析枠組みが適用されたのは、ある連邦系の研究機関で実際に起きた出来事です。発端は、一人の女性職員が上司からの嫌がらせを訴えたことでした。この訴えを支援するため、所内の活動家チームが結成され、ニュースレターの発行などを通じて問題の存在を広く知らせ始めました。これは、組織の管理者たちが維持しようとしていた「公正で問題のない職場」という表舞台の裏側を、白日の下に晒す行為でした。
これに対して、管理側チームは事態の収拾に乗り出しますが、協議は難航します。やがて管理側は、この問題に関する内部研究の名称を、当初の「嫌がらせと脅迫」から、より一般的な「従業員の対立に関する研究」へと変更しました。これは、深刻な問題をありふれた人間関係の摩擦へと矮小化し、公式の状況定義を書き換えようとする一種の演出でした。
外部の専門的な研究チームに調査が委託されます。このとき、外部の研究者は特殊な立場に置かれました。活動家チームと管理側チームの双方が、この調査によって「自分たちの主張が客観的な事実である」とお墨付きを得られることを期待したのです。研究者は、対立する二つのチームから、いわば状況定義の最終的な審判役を委ねられました。
調査の結果、活動家チームの主張を裏付けるような実態が明らかになりました。マイノリティの女性職員の間で対立経験が多く、昇進の機会が乏しいこと、多くの職員がハラスメントを経験・目撃していること、報復を恐れて声を上げられないでいることなどが、データによって示されました。問題を解決するはずの公式な苦情処理手続きが、利用者からは「かえって対立を悪化させた」と認識されていたことも判明しました。管理側が用意した「正規の舞台装置」が、意図とは逆の結末を演出していたのです。
この調査結果は、当初問題を過小評価していた管理職たちの認識を一部改めさせました。しかし、最終的に組織全体の変革は実現しませんでした。各部門がそれぞれの立場から提言を行い、意見の集約が困難になる中、新しいトップが就任したことで、改革に向けた動きが立ち消えになってしまいました。
この一連の過程は、組織の公式ラインをめぐる演出闘争として描き出すことができます。管理側は名称の変更などを通じて、自分たちが望む「理想化されたライン」を維持しようとします。対して活動家チームは、ニュースレターの発行やメディアへの情報提供といった、現状のラインを破壊する「シーン」を意図的に作り出そうとします。それは、組織が隠したい舞台裏を暴露し、不正義を可視化することで、自分たちの主張が正当であるという代替ラインを提示する試みでした。
ドラマツルギーの視点は、日々の何気ない言葉の言い換えや会議の名称といった細部が、変革の成否を左右する「演出」の一部であることを教えてくれます。
病院は構造革新を環境要因で正当化し防御した
組織における演出闘争は、内部の対立といった熱い形で現れるだけではありません。組織が自ら行おうとする大きな変革に対して、外部から疑問や批判が向けられることをあらかじめ想定し、それを未然に防ぐための「予防的な演出」も存在します。社会から強い規範的な期待を寄せられている組織の場合、常識を覆す変革をいかに正当化するかは、繊細な課題となります。
この予防的な演出の巧みな実例を、1980年代のアメリカの病院に見ることができます。当時の非営利病院は、一つの法人が慈善目的のもとに全てのサービスを運営するという形が「当たり前」でした。しかし、一部の先進的な病院はその常識を破り、非営利の親会社のもとに、病院本体や様々な営利・非営利の子会社を置く、多角的な企業グループのような組織構造へと転換を始めました。これは、医療が持つべき公共性や地域への奉仕といった、社会の期待と衝突しかねない革新でした。
ある研究は、こうした構造革新を先駆けて導入した病院が、そのラディカルな変化を外部の利害関係者に対し、どのように説明し納得させようとしたのかを分析しました[3]。分析対象は、病院が年に一度発行する「年次報告書」、まさに演出そのものと言えるメディアです。
報告書の語りを分析した結果、これらの病院が、一貫した「防御的」な説明戦略をとっていたことが判明しました。その戦略は、主に四つの技法から成り立っていました。
第一に、「弁解」です。病院は、自らが進んでこの新しい構造を選んだという能動性を隠し、「複雑化する医療環境」「政府による厳しい規制」といった外部環境の圧力を強調しました。逸脱の責任を、自らの意思決定ではなく、抗いがたい外部の力に転嫁していました。
第二に、「正当化」です。構造を変える責任は認めつつ、その否定的なイメージを打ち消そうとします。再編は「病院の存続のため」「地域医療や研究といった本来の使命を継続するため」であると説明し、新しい構造を既に社会的に正統と認められている価値に結びつけました。
第三に、「断り書き」です。この変革がいかに慎重な準備の末に決定されたかを詳述し、決定の合理性をアピールします。同時に、「患者さんや職員の皆さんの日常は、これまでと何も変わりません」といった言葉で、関係者の不安を先回りして取り除こうとしました。
第四に、「秘匿」です。自分たちがこの革新的な構造を「初めて」導入したという事実には触れず、「これは全国的な趨勢です」とほのめかすことで、自らの逸脱性を薄めようとしました。
興味深いことに、同じ年次報告書の中でも、医療サービスや最新技術について語る段になると、口調は一変します。そこでは、「地域で唯一の最先端設備」といった、他との差別化や先進性を誇る「攻めの自己呈示」が全面的に展開されていました。この対比は、組織が語る対象によって、見事に仮面を使い分けていることを明らかにします。
制度的に確立された「当たり前」を最初に壊す組織は、単に正しいと信じることを実行するだけでは不十分です。その行動を、社会が受け入れ可能な「正しい語り方」でパッケージ化し、事前に説明責任を果たしておく必要があります。ここで見られた四つの防御的な技法は、同質性を求める社会的な圧力の中で、革新という逸脱を成し遂げつつ、組織の正統性を守り抜くための、計算され尽くしたレトリックだったのです。
エンロンは壮大な演出で正当性を装い崩壊した
これまで見てきたのは、政治の駆け引きや、組織変革をめぐる攻防、正統性を守るための防御的な演出でした。しかし、この「演出」という営みは、時に組織全体を巻き込み、社会を欺くほどの「見世物(スペクタクル)」と化し、悲劇的な結末を迎えることがあります。21世紀初頭に世界を震撼させたエンロンの崩壊は、その劇的な事例と言えるでしょう。
エンロンの興亡を分析したある研究は、従来の演劇のメタファーをさらに一歩進め、「クリティカル・ドラマツルギー」という視点を提示しました[4]。これは、企業の演出活動を、ただの印象操作ではなく、投資家や社会全体を受動的な観客へと変えてしまう権力装置として、批判的に読み解こうとするものです。この視点から見ると、エンロンという企業は、自らの正当性と先進性を誇示するための壮大な劇場であり、その成功と失敗は、一つのスペクタクルの上演と閉幕として理解できます。
この研究は、エンロンが崩壊に至るまでの様々な出来事を、物語として完成する前の「アンテナラティブ(前物語)」、すなわち伏線となる断片的な語りの連なりとして捉えます。そこから浮かび上がってきたのは、エンロンが実に多層的な演出を駆使していたという事実です。
その演出の一つは、組織内部に向けられたものでした。社内では「ランク&ヤンク」と呼ばれる過酷な評価制度が敷かれ、上位の者は英雄として莫大な報酬を手にし、下位の者は容赦なく解雇されるという、恐怖と栄光のドラマが日々演じられていました。これは、従業員をエンロンという神話の熱狂的な信者へと変えていくための、内向きに凝縮されたスペクタクルでした。
同時に、エンロンはグローバル市場という外部の観客に向けても、演出を行いました。世界各国で大規模な事業を展開し、規制緩和の旗手として「新経済」の象徴であるかのように振る舞い、環境保護や慈善活動にも熱心な姿を見せることで、そのビジネスモデルの裏にあるリスクを覆い隠しました。これら内外の演出は統合され、エンロンが「宇宙の支配者」であるという自己神話を強化していきました。
しかし、これらの華やかなスペクタクルの舞台裏では、不正な会計処理によって損失を隠蔽し、利益を水増しするという、もう一つの劇が進行していました。巨額の負債を帳簿から隠すための舞台装置が組み立てられていたのです。実は、その後の崩壊劇の原型となるような不正の兆候は、会社の歴史の早い段階から何度も現れていましたが、より大きな成功のスペクタクルによって、その都度覆い隠されてきました。
最終的に、内部告発と調査報道によって舞台裏が暴露されると、エンロンという壮大なスペクタクルは一気に崩壊します。その崩壊の過程が、今度はメディアによって連日報道され、公聴会での幹部たちの証言や関係者の逮捕といった一連の出来事が、ギリシア悲劇のような展開で消費されていく「メガスペクタクル」へと転化しました。
エンロンの事例が示すのは、企業の演出がいかに現実を構築し、多くの人々をその物語の中に巻き込んでいくかという力です。観客であったはずの投資家やメディアもまた、エンロンが演出する成長神話に魅了され、そのスペクタクルを維持するための共犯者となっていた側面は否定できません。この視点は、私たちが企業の語る物語を受け取る際に、その舞台裏に隠された矛盾や、周縁化された声に耳を澄ますことの必要性を教えてくれます。
脚注
[1] Czarniawska-Joerges, B., and Jacobsson, B. (1995). Political organizations and commedia dell’arte. Organization Studies, 16(3), 375-394.
[2] McCormick, D. W. (2007). Dramaturgical analysis of organizational change and conflict. Journal of Organizational Change Management, 20(5), 685-699.
[3] Arndt, M., and Bigelow, B. (2000). Presenting structural innovation in an institutional environment: Hospitals’ use of impression management. Administrative Science Quarterly, 45(3), 494-522.
[4] Boje, D. M., Rosile, G. A., Durant, R. A., and Luhman, J. T. (2004). Enron spectacles: A critical dramaturgical analysis. Organization Studies, 25(5), 751-774.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。