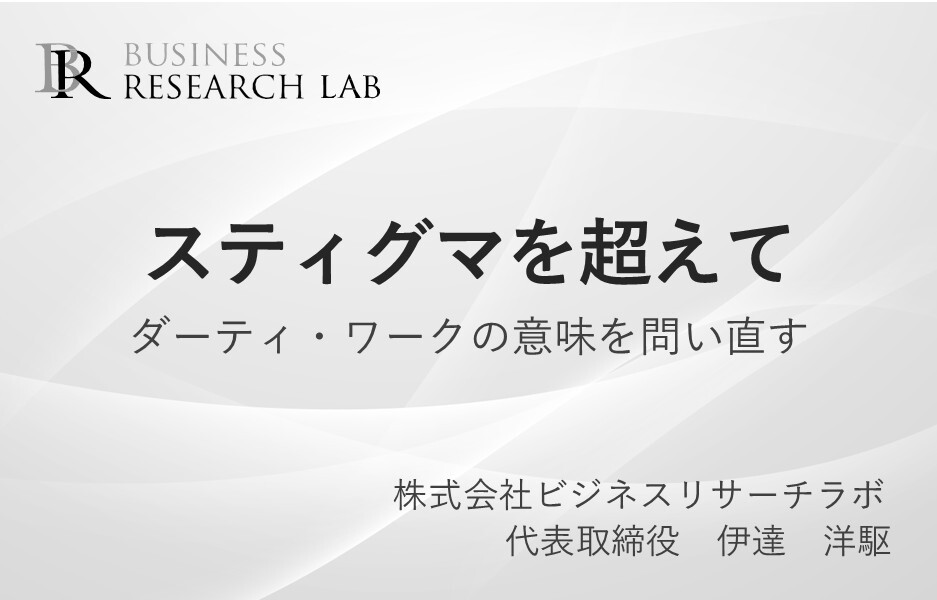2026年1月27日
スティグマを超えて:ダーティ・ワークの意味を問い直す
私たちの社会には、物理的に汚れていたり、社会的に低い評価を受けたり、道徳的に割り切れないとされたりする仕事も存在します。こうした仕事は「ダーティ・ワーク」と呼ばれ、私たちの生活を陰で支えています。普段、私たちはその存在を意識することは少ないかもしれません。ですが、ひとたび社会が大きな危機に見舞われたとき、そうした仕事の担い手たちが、突如として社会の前面に姿を現すことがあります。
本コラムでは、この「ダーティ・ワーク」という現象を掘り下げていきます。社会は、この種の仕事がもたらす精神的な負担や社会的なスティグマ(負の烙印)に、どのように向き合っているのでしょうか。また、現場の管理者は、従業員が誇りを失わずに働き続けられるよう、日々どのような工夫を凝らしているのでしょうか。そこには、仕事の意味を再構築したり、あえて仕事の厳しい現実を逆手にとったりする、知られざる実践があります。
ダーティ・ワークへの対処は社会の側にもある
ダーティ・ワークがもたらすスティグマへの対処は、仕事の担い手である当事者だけの課題なのでしょうか。近年のパンデミックは、この問いに新たな光を当てました。ある研究では、パンデミック初期のアメリカにおけるニュース記事を分析し、社会が「エッセンシャル・サービス労働者」をどのように描き、その仕事の意味づけをどう変化させていったかを検証しています[1]。分析の対象となったのは、例えば食料品店の店員、配送ドライバー、飲食店員といった、医療従事者を除いた第一線のサービス労働者に関する報道です。
分析の結果、二つの大きなテーマが浮かび上がりました。一つは「危険な仕事」というテーマです。
報道では、ウイルス感染の危険に常に晒される労働環境が強調されていました。レストランの従業員が「消毒液に浸かるようだ」と語ったり、トラックの運転手が「自分たちが止まれば物流も止まる」と自らの仕事の根幹的な性質を述べたりする様子が報じられました。パンデミックという未曾有の事態は、これらの仕事に「社会に不可欠である」という中心性を与えた半面、その仕事が持つ汚れや危険性を、これまでにないほど強く社会に認識させることになったのです。
もう一つの大きなテーマは「対処メカニズム」です。これまで仕事の当事者に見られるとされてきた心理的な対処法が、社会の側、すなわち外集団(当事者以外の一般の人々)の言説の中にも見出されました。例えば、当事者である内集団が、自らの集団の価値を称え合うことで誇りを保とうとする「社会的加重」という対処を好むのに対し、外集団は、SNSなどで支援のメッセージを広め、他の人々の認識や行動を変えようとする「対抗・反駁」という方法を多用する様子がうかがえました。
両者に共通していたのは、マスクをしない人や安全対策を怠る雇用主などを非難し、問題の責任を他に転嫁しようとする「防衛的戦術」でした。また、外集団の言説には、危険手当の支給を求める議論などを通じて、仕事の価値を社会的に再評価しようとする「再フレーミング」も見られました。
分析で大きな部分を占めたのが、「みんなで自分の役割を果たそう」という呼びかけでした。マスク着用や手洗い、外出自粛といった具体的な行動の推奨から、ウイルスの知識に関する「教育」、「希望」を語る言説まで、これは社会全体の行動変容を促す物語となっていました。
このことは、ダーティ・ワークの意味づけが、仕事の内容だけでなく、それを取り巻く社会全体の価値観や行動規範によっても左右されることを物語っています。社会もまた、ダーティ・ワークという現象に対して、無関心な傍観者ではなく、意味づけに関与し、対処しようとする主体であることがわかります。
管理者は、汚れを「当たり前」に調律する
ダーティ・ワークに従事する人々が、仕事への誇りを持ち、日々の業務を円滑に進めるためには、管理者の存在が欠かせません。管理者は、仕事に伴うスティグマをどのように和らげ、従業員がそれらを「当たり前のこと」として受け入れられるようにしているのでしょうか。ある質的研究が、18の異なるダーティ・ワークの管理者54名へのインタビューを通じて、そのための手法を明らかにしました[2]。
対象となった職業は、例えば害虫駆除や葬儀に関わる仕事、一部の娯楽施設の管理職など、身体的、社会的、道徳的な汚れを伴うとされる、多岐にわたるものでした。
この研究によれば、管理者は二つの特有の課題に直面しています。一つは「役割の複雑化」です。通常の管理業務に加えて、仕事の汚れから生じる人間関係や制度上の問題に対処しなくてはなりません。例えば、法執行機関の内部監察を担う者は同僚を厳しく追及する必要があり、救急医療の現場をまとめる管理者は部下の感情を鼓舞し続けなければなりません。複数の利害関係者がそれぞれ異なる価値観で仕事の「汚れ」を評価するため、その間で巧みな調整が求められます。
もう一つの課題は「スティグマ意識」です。多くの管理者は、自分の仕事が社会からどう見られているかを敏感に察知しています。同僚から避けられたり、敵意のこもった言葉を投げかけられたりすることも少なくありません。管理者という立場は、必ずしもスティグマからの盾にはならないのです。
管理者はこれらの課題に対し、どのように仕事の汚れを「正規化」し、日常業務に溶け込ませているのでしょうか。研究からは、四つの実践群が浮かび上がりました。
一つ目は「職業イデオロギー」の活用です。これは、仕事の意味づけを組み替える語りの技術です。例えば、ある種の法律専門家は自らの仕事を「企業の安全性を高める社会貢献」と捉え直し、また害虫駆除の専門家は昆虫に関する知識を強調することでプロ意識を育みます。これによって、従業員は自分の仕事に内在的な価値を見出し、心理的な支えを得ることができます。
二つ目は「ソーシャル・バッファ」の形成です。これは、同業者や家族など、理解し合える人々との間に支持的なコミュニティを作り、外部からの否定的な視線を和らげる緩衝地帯を設けることです。葬儀業の専門大会などで同業者と交流し、互いの苦労を分かち合うことがこれにあたります。
三つ目は「顧客・公衆への対峙」です。受け身の姿勢に留まらず、外部の認識に働きかける実践です。矯正施設の職員が「収容者の処遇は公共の安全に貢献する」と仕事の価値を説明したり、ユーモアを交えて緊張を和らげたりします。
四つ目は「防御的タクティクス」です。これは、自分たちの身を守るための行動的・認知的な技法です。私生活で職業を明言しない「パッシング」や、不謹慎に見える冗談で緊張を緩和する「ガロウズ・ユーモア」、あるいは批判してくる相手の正当性を問うことで心理的な優位に立とうとすることなどが含まれます。
これらの四つの実践は、単独で用いられるのではなく、互いに補い合いながら機能します。管理者は、これらの手法を組み合わせることで、仕事の汚れが過度に意識されることを防ぎ、従業員が日々の業務に集中できる環境を整えているのです。この「正規化」のプロセスは、いわば汚れの深刻さを現場が扱える水準にまで「調律」する営みと言えますでしょう。
管理者は汚れを逆用し人材を適合させる
ダーティ・ワークの管理者は、仕事の汚れを覆い隠したり、その意味を和らげたりするだけではありません。その汚れの性質を深く理解し、それを利用して従業員と仕事環境の「かみ合わせ」を高めていくという、より踏み込んだ実践を行っています。この一連の取り組みは「コングルエンス・ワーク(適合をもたらすための働き)」と名付けられています。これもまた、複数の職種の管理者へのインタビュー調査から導き出された知見です[3]。このアプローチは、採用から日々のマネジメントに至るまで、長期的な視点で展開されます。
第一段階は「採用・選抜」です。ここでは、仕事の汚れに対して親和性を持つ人材を見極めることが基本となります。例えば、過去の個人的な体験からその仕事に強い使命感を感じている人や、仕事が持つ独特の側面に魅力を感じる人などが選ばれます。管理者は、社会的なスティグマを乗り越えるほどの内的な動機を持つ候補者を探します。
同時に、管理者は「リアリスティック・スティグマ・プレビュー」と呼ばれる手法を用います。これは、仕事の厳しい現実を、ありのままに、事前に候補者に見せることです。例えば、ある医療施設では処置に関する映像を見せ、動物管理施設では安楽死の現場に立ち会わせます。これは、候補者をふるいにかけるだけでなく、入職後のショックを和らげ、覚悟を固めてもらうためのプロセスでもあります。
第二段階は「社会化」です。新入職員が抱いてきた社会的な偏見や先入観を、ここで意図的に「はぎ取る」作業が行われます。例えば、サービスや支援の対象となる人々に対するステレオタイプ的な見方を正し、共感的な視点を養うための訓練が施されます。家庭訪問などを通じて、対象者が置かれた複雑な文脈を理解させ、「判断よりも理解」を優先する姿勢を教え込みます。また、家族や友人、メディアなど、外部からの否定的な反応にどう対処するか、その作法も指導されます。
第三段階は「日常的マネジメント」です。ここでは、築き上げてきた適合感を維持し、定着させることが目的となります。失敗談や恥ずかしい体験をチーム内で共有し、笑い話に変えることで心理的な負担を軽減したり、仕事の社会的価値を物語として語り継いだりします。また、物理的な危険から従業員を守るための安全対策を徹底することも、自分が組織から守られているという感覚、すなわち適合感を強固にする上で欠かせません。
外部向けの「表舞台(フロントステージ)」での振る舞いと、内部向けの「舞台裏(バックステージ)」での感情表出を区別する規範を運用し、従業員が安心して本音を吐露できる場を確保します。
このように、管理者は採用から日常業務に至るまで、一貫したプロセスを通じて、従業員とダーティ・ワークとの適合を能動的に作り上げていきます。汚れを隠すのではなく、それを前提とした上で、人と仕事の最適な関係性をデザインしていく。これが、ダーティ・ワークにおける管理のもう一つの姿です。
満足度は低いが仕事への関与は高める
ダーティ・ワークは、従事する人々の心に複雑な状態を生み出すことがあります。特に、仕事への満足感と、仕事への熱意や没頭の度合いを示す「仕事関与」との間に、一見すると矛盾した関係が見られることがあります。ある研究は、アメリカの動物保護施設で働く499名の職員を対象とした調査を通じて、この現象を定量的に明らかにしました[4]。この職場では、動物の安楽死が、身体的・道徳的な汚れを伴う中核的なダーティ・タスクとされています。
研究の仮説では、安楽死の業務に直接関与している職員は、そうでない職員に比べて、精神的な消耗や身体的な不調、仕事と家庭の間の葛藤といった「ストレイン」が高いと予測されました。仕事のネガティブな側面について、家族以外の外部の人に話すことを避けるようになること、仕事に対する満足度が低くなることも想定されました。一方で、これらとは反対に、仕事への関与はむしろ高まるのではないかという仮説も立てられました。
分析の結果、これらの予測の多くが裏付けられました。安楽死に関与している職員は、関与していない職員と比較して、ストレインの指標が高く、外部との会話を避ける傾向があり、仕事満足度が低いという結果でした。同じ職場、同じ職種であっても、中核的なダーティ・タスクを担うかどうかが、働く人の心身の健康や仕事への態度に差を生じさせていたのです。
しかし、同時に、予測通り、仕事への関与は有意に高まっていました。仕事への満足度は低いにもかかわらず、その仕事に対する心理的な結びつきや没頭の度合いは強いというパラドックスが生じていたのです。これは、仕事が持つスティグマに対抗するために、職員たちが仲間との連帯感を強めたり、仕事の意義を再確認したりする中で、仕事への同一化が深まるためだと解釈できます。
この研究は安楽死に関わる職員の中でも、その「頻度」と「心理的顕在性」の違いによって、心身へのあらわれ方が異なることを明らかにしました。安楽死を執行する頻度が高い職員ほど、燃え尽き感や外部との会話回避、仕事への関与が高まり、仕事満足度は低下しました。他方、「この仕事で最も否定的な側面は何か」という問いに対して「安楽死」と答えた、心理的にこのタスクを重く受け止めている職員は、身体的な不調や仕事と家庭の葛藤が特に強いことがわかりました。
この結果は、ダーティ・タスクへの「物理的な近さ」と「心理的な近さ」が、それぞれ異なる経路をたどって、働く人に負担をもたらすことを示唆しています。満足と関与の間に見られる複雑な関係は、ダーティ・ワークが人の心に単純ではないかたちで作用することを示しています。
ダーティ・ワークと呼ぶことで、組織の理想を守る
ある仕事が「ダーティ・ワーク」と呼ばれるとき、それは単にその仕事が嫌なものであるという事実を述べているだけなのでしょうか。そうではありません。その呼称自体が、組織の中で特定の機能を持っている場合があります。ある古典的な研究は、精神科の救急チーム(PET)が、一部の業務を「shit work(汚れ仕事)」と呼ぶ実践を参与観察し、その言葉が持つ意味を分析しました[5]。
このPETの専門家たちは、本来、危機的な状況にある人々に対して、短期的な介入を通じて治療的な援助を行うこと(doing for)を理想としていました。しかし、現場で遭遇するケースの多くは、支援を拒否したり、長年にわたる問題を抱えていたりするため、理想的な援助が困難な状況でした。
援助の見通しが立たず、かといってその場を立ち去ることもできない場合、チームは本人の同意なしに緊急入院を命じるという、強制力を伴う手段(doing to)を取らざるを得なくなります。これは、治療というよりは社会的な「統制」に近い行為であり、専門家としての理想とは相容れません。この「理想的な援助(doing for)が不可能になり、強制的な処置(doing to)が避けられなくなった」ときに、「これはshit workだ」という言葉が発せられるのです。
この呼称は、いくつかの組織的な機能を果たします。第一に、それは「業績規準の再確認」です。新人や外部の研究者など、観察者の前でこの言葉を使うことは、「私たちPETが本来目指しているのは、このような統制的な仕事ではない。私たちの理想はあくまで治療的な援助にある」というメッセージを伝え、組織が掲げる理想への忠誠を再表明する儀式となります。これによって、日常業務の多くが統制的なものであっても、組織の自己理解は「治療的援助機関」として維持されます。
第二に、それは「道徳的距離の表示」です。この言葉を発することで、行為者はその強制的な実践から自分自身の道徳的な自己を切り離し、心理的な距離を確保することができます。これは、個人の精神的な安定だけでなく、チームの評判を守ることにもつながります。
第三に、それは「望ましい解釈への手ほどき」の機能を持ちます。この言葉は、新人などに対して、「PETの仕事の本質は統制ではなく、これはあくまで例外的な、やむを得ない措置なのだ」という、組織として望ましい解釈の枠組みを教えるチュートリアルとして作用します。
「ダーティ・ワーク」という呼称は、仕事の不快な性質を描写する以上に、組織の理想を守り、そのアイデンティティを維持するための言説的な装置として機能しているのです。汚れを「汚れ」と名指すことによって、組織は自らの「清らかさ」を逆説的に証明し、その存続を図っていると言えます。
脚注
[1] Mejia, C., Pittman, R., Beltramo, J. M. D., Horan, K., Grinley, A., and Shoss, M. K. (2021). Stigma & dirty work: In-group and out-group perceptions of essential service workers during COVID-19. International Journal of Hospitality Management, 93, 102772.
[2] Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Clark, M. A., and Fugate, M. (2007). Normalizing dirty work: Managerial tactics for countering occupational taint. Academy of Management Journal, 50(1), 149-174.
[3] Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Clark, M. A., and Fugate, M. (2017). Congruence work in stigmatized occupations: A managerial lens on employee fit with dirty work. Journal of Organizational Behavior, 38(8), 1260-1279.
[4] Baran, B. E., Rogelberg, S. G., Lopina, E. C., Allen, J. A., Spitzmuller, C., and Bergman, M. (2012). Shouldering a silent burden: The toll of dirty tasks. Human Relations, 65(5), 597-626.
[5] Emerson, R. M., and Pollner, M. (1976). Dirty work designations: Their features and consequences in a psychiatric setting. Social Problems, 23(3), 243-254.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。