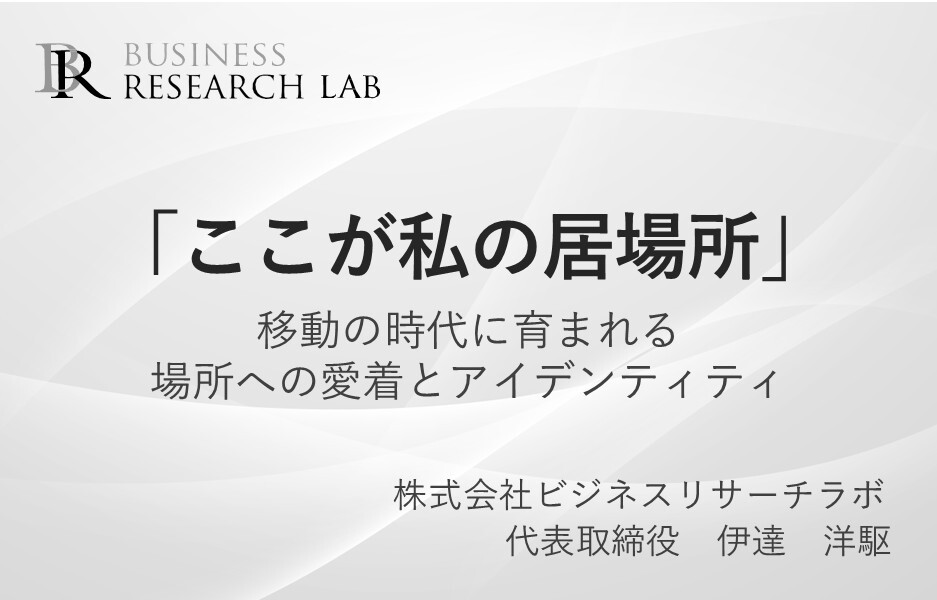2026年1月26日
「ここが私の居場所」:移動の時代に育まれる場所への愛着とアイデンティティ
私たちは、人生の中で幾度となく「移動」を経験します。進学や就職、転勤、結婚、あるいは心機一転のための移住。生まれた場所で生涯を終える生き方が当たり前ではなくなった現代において、移動は特別な出来事ではなく、私たちの生活の一部となりました。「ふるさと」という言葉に温かい響きを感じながらも、多くの人が複数の土地に暮らし、それぞれの場所で異なる思い出を紡いでいます。
こうした移動の多い時代に、私たちが特定の場所に対して抱く「愛着」や「ここが自分の居場所だ」という感覚は、どのように育まれ、変化していくのでしょうか。新しい土地に降り立ったとき、私たちの心と場所との関係は、ゼロから始まります。その場所を「好き」だと感じる気持ちと、「自分はこの場所の一員だ」と感じる意識は、同じものなのでしょうか。それとも、異なるプロセスを経て、別々のタイミングで心の中に芽生えるものなのでしょうか。
本コラムでは、人が場所とどのように心理的な結びつきを築いていくのか、その心の動きを探求していきます。移住者の心の中で起こる変化、急速な開発が進む地域で生じる住民の思いとのズレ、複数の拠点を持つ働き方が自己認識に及ぼす作用、一つの場所に長く住み続けることがもたらす心の充足。これらのテーマを、調査研究の知見を紐解きながら検討していきます。
移住者は新しい場所で、愛着がアイデンティティ形成より先に育つ
新しい環境に身を置いたとき、私たちの心はどのようにその場所と結びついていくのでしょうか。その場所を心地よいと感じる感情的なつながり、いわば「愛着」と、自分はその場所の一部であると認識する自己同一化、すなわち「アイデンティティ」は、しばしばひとくくりに語られます。しかし、この二つは、特に新しい土地へ移り住んだ人々にとっては、異なる道のりをたどって育っていくのかもしれません。この問いを明らかにするため、スペインのテネリフェ島で、そこに住む人々の出身地に着目した二つの調査が行われました[1]。
最初の調査は、島の大学に通う学生たちを対象にしたものです。彼ら彼女らを三つのグループに分けて比較しました。一つ目は、調査が行われた街で生まれ育った「地元出身者」。二つ目は、島の他の地域から引っ越してきた「島内からの移動者」。三つ目は、他の島やスペイン本土からやってきた「島外からの移動者」です。
調査では、彼ら彼女らが今住んでいる「近隣」「都市」「島」という三つの異なる広さの範囲それぞれに対して、愛着とアイデンティティの度合いを尋ねました。愛着は「この場所が好きだ」「離れたくない」といった感情的な項目で、アイデンティティは「自分はこの場所の一員だと感じる」といった自己認識に関する項目で測定されました。
結果は、グループごとにはっきりとした違いを映し出しました。地元出身者のグループでは、最も身近な生活圏である「近隣」においてのみ、愛着がアイデンティティを上回りました。より広い範囲である「都市」や「島」に対しては、愛着とアイデンティティの強さはほぼ同じでした。生まれたときからその場所の文化や物語の中で育ってきた彼ら彼女らにとっては、場所を好きだと感じることと、場所と自己とを同一視することが、分かちがたく結びついている様子がうかがえます。
一方で、島内、島外を問わず、故郷を離れてきた移動者のグループでは、様相が異なりました。彼ら彼女らは、近隣、都市、島外からの移動者においては島のレベルに至るまで、一貫して愛着の度合いがアイデンティティの度合いを上回っていたのです。このことから、新しい土地にやってきた人々は、その場所の雰囲気や居心地の良さといった点に心惹かれ、感情的な結びつきを先に形成するという心の動きが見えてきます。「ここが自分の居場所だ」という自己認識は、感情的な愛着が育った後、少し時間をかけて追いついてくるようです。
この発見をより確かなものにするため、二つ目の調査が行われました。今度は、テネリフェ島で生まれ育った人々と、主にラテンアメリカ諸国から移り住んできた「移民」の人々を直接比較しました。結果は、一つ目の調査で得られた見方を裏付けるものでした。移民のグループは、近隣、都市、島というすべての範囲において、愛着がアイデンティティよりも有意に高い値を示したのです。対照的に、地元出身者のグループでは、最初の調査と同様に、近隣でのみ愛着がアイデンティティを上回り、都市と島では両者に差は見られませんでした。
これら二つの調査から導き出されるのは、場所との心理的な結びつきにおける発達の順序です。私たちは新しい環境に適応していく過程で、その場所の快適さや魅力を感じ取り、情緒的な「愛着」を育みます。そして、その場所での日々の生活、人々との交流、経験の積み重ねを通じて、その土地の歴史や文化を自らの物語の一部として取り込み、やがて「自分はこのコミュニティの一員である」という「アイデンティティ」を形成していくのです。
開発が進む場所では、住民の愛着と外部が作るイメージが乖離する
個人が場所との間に育む心の結びつきは、その場所自体が静的であるとは限りません。とりわけ、観光地化や都市開発によって街の風景が急速に塗り替えられていくとき、そこに住む人々の思いと、外部から持ち込まれるイメージとの間には、溝が生まれることがあります。個人の内側から湧き上がる場所への「愛着」と、開発などを推進する側が作り出す場所の「アイデンティティ」は、必ずしも同じ方向を向いているわけではないのです。
この現象を浮き彫りにしたのが、オーストラリア有数の急成長地域であるサンシャイン・コーストで行われた調査です[2]。
この調査では、住民が日々の暮らしの中で育んできた、いわば「ボトムアップ」の気持ちとしての「場所への愛着」と、観光業者や不動産開発業者が宣伝などを通じて発信する、いわば「トップダウン」の表象としての「場所のアイデンティティ」とを区別して考えます。調査チームは、この地域の5000世帯にアンケートを配布し、住民が抱く場所への愛着の強さや、進行する観光開発に対する意見などを尋ねました。
分析の結果、いくつかの点が明らかになりました。都市部から離れた農村地域に住んでいる人ほど、そして、その土地での居住年数が長い人ほど、「ここが自分の居場所だ」と感じる愛着が強いことが分かりました。安定した暮らしと土地への根付きが、愛着を深く育むようです。こうした愛着の強い住民層は、地域の観光開発に対して批判的な姿勢をとっていました。彼ら彼女らにとって、自分たちの生活様式は観光客向けの余暇とは異なり、日々の労働と結びついたものであり、外部から押し付けられる変化に抵抗感を抱いていたのです。
この調査における際立った発見は、「場所への愛着」と、外部から提示される「場所のアイデンティティ」との間に、統計的な関連性が見いだせなかったことです。それどころか、場所への愛着が強い住民ほど、地域を宣伝文句で飾り立てるようなアイデンティティに対して、否定的な感情を持っていることが判明しました。これは、農村部の長期居住者たちが、外部向けに都合よく「パッケージ化」されたレッテル貼りを拒絶していることの表れと解釈できます。
調査チームは、地域の看板や広告といった視覚的なイメージの分析も行っています。かつてこの地域の農業を象徴し、住民の誇りでもあった巨大なパイナップルのオブジェ「ビッグ・パイナップル」は、今や存続が危ぶまれ、その輝きを失いつつあります。その一方で、新しい宅地開発の広告は、ビーチで優雅に過ごす人々のイメージを前面に押し出し、都市部からの中流階級の移住を促す物語を盛んに消費しています。また、かつては地域のワニを売りにしていた動物園が、今ではトラやゾウといった世界的に人気のある動物を宣伝の中心に据えています。
これらの分析が物語るのは、現在のサンシャイン・コーストの「場所のアイデンティティ」が、そこに住む多様な人々の経験や歴史を反映したものではなく、大規模な商業的論理によって一方的に構築されているという現実です。住民が抱く愛着は、労働の記憶やコミュニティでの日々の営み、土地の自然と共に生きてきた実感に根差しています。しかし、トップダウンで押し進められるアイデンティティは、そうした複雑で多層的な現実を覆い隠し、消費されやすい表層的な魅力だけを切り取って見せるのです。
住民の内なる声と、外から与えられるイメージとの乖離は、開発の波に洗われる多くの地域が直面する課題であると言えるでしょう。
複数の場所をまたぐ働き方は、どこにも属さない自己を形作る
これまでは、人々が特定の場所に根を下ろす過程や、その場所の変化にどう向き合うかを見てきました。しかし現代社会では、仕事や生活のために、一つの場所にとどまらず、複数の国や都市を行き来する人々も少なくありません。このような移動し続ける「トランスローカル」な生き方は、私たちの自己認識、すなわち「自分とは何者か」という感覚に、どのような変化をもたらすのでしょうか。この問いを探るため、三人の研究者が自らの経験を物語として描き出し、それを分析するという独創的な試みが行われました[3]。
この研究を理解する上で鍵となるのが、「リミナリティ」という概念です。これは文化人類学の用語で、ある状態から次の状態へと移行する途中の「どちらでもない」「狭間にある」中間的な状態を指します。通過儀礼の最中のように、古い自分を脱ぎ捨てたものの、まだ新しい自分にはなりきれていない、曖昧で不安定な期間のことです。この研究では、複数の場所をまたぐ生活が、一時的なものではなく、恒常的なリミナリティの感覚を生み出すのではないかと考えられています。
三つの自伝的な物語は、このリミナルな感覚を描き出します。一人目は、カナダのケベック州で生まれ、後にイギリスへ移住した研究者の物語です。英語圏とフランス語圏、カナダ文化とイギリス文化という二つの世界の狭間で、常に自分が「他者」であると感じ、アイデンティティが引き裂かれるような感覚が綴られます。「私はカナダ人なのか、イギリス人なのか」という問いが、答えの出ないまま心の中を巡り、どこにも完全には属すことができないという感覚が表現されています。
二人目は、セルビア出身で長年イギリスに住む研究者の物語です。たまに故郷のセルビアに帰っても、そこはもはや心安らぐ「我が家」とは感じられません。かといって、長く暮らすイギリスも完全な故郷とは言い切れない。どこにも根を下ろすことができない「根無し草(uprooted)」になったという感覚と、もう戻ることのできない故郷への静かな喪失感が語られます。アイデンティティの変容は、自分でも気づかないうちに、後戻りできないところまで進んでしまっていたのです。
三人目は、二つの国を頻繁に行き来する生活を送る研究者の物語です。この物語では、移動のたびに自己が断片化されていくような感覚が描かれます。「あちらの国にいる私」と「こちらの国にいる私」は、まるで別人のようです。物理的な移動が、自己の連続性の感覚を揺るがし、人生が結末を迎えることなく、常に次の目的地へと旅立ち続ける映画のように感じられると表現されています。
これらの物語の分析から、トランスローカルな経験を特徴づけるいくつかのテーマが浮かび上がります。「家」や「故郷」といった安定した「場所」の感覚が揺らぎ、かつての故郷ですら、よそよそしい「非場所」のように感じられることがあります。そして、他者との関係の中で、あるいは現地の文化に馴染めない瞬間瞬間に、自分が「他者」であることを絶えず意識させられ、自己認識が揺さぶられます。アイデンティティはどこかに固定されたものではなく、常に「動き」の中にあるプロセスなのだと実感させられるのです。
複数の場所をまたぐ生き方は、確かに豊かで刺激的な経験をもたらすでしょう。しかしその一方で、どこにも完全に帰属することのできない、宙吊りのような、あるいは断片化された自己の感覚を形作ることがあるのかもしれません。それは、現代的な働き方が私たちにもたらす、一つの心の肖像と言えます。
長く住むことで育つ場所への一体感は、社会的な満足感を高める
移動し続ける生活が自己認識を揺るがす側面を描いた一方で、一つの場所に長く住み続けることは、私たちの心にどのような安定と充足をもたらすのでしょうか。時間をかけて育まれる場所との結びつきは、日々の生活の満足度にどのように関わっているのでしょうか。これまで見てきた場所への愛着やアイデンティティといった感覚が、私たちの幸福感にどう作用するのか、そのメカニズムを探ったフランスでの調査があります[4]。
この調査は、「居住期間が長くなればなるほど、その場所への一体感が強まり、その強まった一体感が、居住満足度を高める」という一連の流れを検証することを目的としました。調査はフランスの三つの主要都市に住む女性たちを対象に行われました。
参加者には、現在の居住期間に加えて、住んでいる近隣地域への「一体感」の度合いと、「居住満足度」を尋ねるアンケートに回答してもらいました。ここで言う一体感とは、その場所が自分自身を定義する一部になっていると感じる度合いを指します。満足度については、建物の快適さや公共サービスの便利さといった物理的・機能的な側面だけでなく、住民同士の関係や地域の雰囲気といった社会的な側面についても尋ねています。
データの分析から、いくつかの関係性が見えてきました。居住満足度を構成する要素を分析したところ、それは大きく四つに分けられることが分かりました。「近隣の社会的イメージ」「サービス」「緑地」「社会的関係」の四つです。
それぞれの変数間の関係を見ていくと、予想された通り、居住期間が長い人ほど、その場所への一体感が強いという結果が得られました。長く住むことで、場所が自己の一部となっていくプロセスが確認されたのです。しかし、意外なことに、居住期間の長さは、総合的な居住満足度や、四つの個別要素の満足度とは直接的には結びついていませんでした。長く住んでいるからといって、必ずしも満足度が高くなるわけではなかったのです。
何が満足度を高めるのでしょうか。ここで重要になるのが「一体感」です。場所への一体感が強い人ほど、総合的な居住満足度が高いことが分かりました。ここからがこの調査の核心部分です。一体感が高める満足度を見てみると、それは「近隣の社会的イメージ」や「社会的関係」といった、二つの社会的な側面に関する満足度だけだったのです。公共サービスの利便性や公園の質といった機能的な側面への満足度とは、一体感の強さは関係ありませんでした。
これらの結果を総合して統計的に検証したところ、「居住期間が長い→場所への一体感が強まる→社会的な側面での居住満足度が高まる」という一連の流れが裏付けられました。
この結果は、私たちに何を教えてくれるのでしょうか。それは、一つの場所に長く住むことの価値が、慣れや利便性の享受にあるのではないということです。
時間をかけて育まれるのは、その場所と自分とを分かちがたく感じる「一体感」です。この心理的な結びつきが、その地域の雰囲気や人々との関係に対する肯定的な評価、要するに社会的な満足感を高めるのです。研究者たちは、この背景に「自分と一体化しているこの場所や、ここに住む人々が悪いはずがない」という、自己の肯定感を保とうとする心理的な働きがあるのではないかと考えています。場所との深い結びつきは、物理的な快適さを超えて、私たちの社会的な幸福感を静かに支えているのです。
脚注
[1] Hernandez, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., and Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of Environmental Psychology, 27(4), 310-319.
[2] Carter, J., Dyer, P., and Sharma, B. (2007). Dis-placed voices: sense of place and place-identity on the Sunshine Coast. Social & Cultural Geography, 8(5), 755-773.
[3] Daskalaki, M., Butler, C., and Petrovic, J. (2015). Somewhere in-between: Narratives of place, identity and translocal work. Journal of Management Inquiry, 25(2), 184-198.
[4] Fleury-Bahi, G., Felonneau, M.-L., & Marchand, D. (2008). Processes of place identification and residential satisfaction. Environment and Behavior, 40(5), 669-682.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。